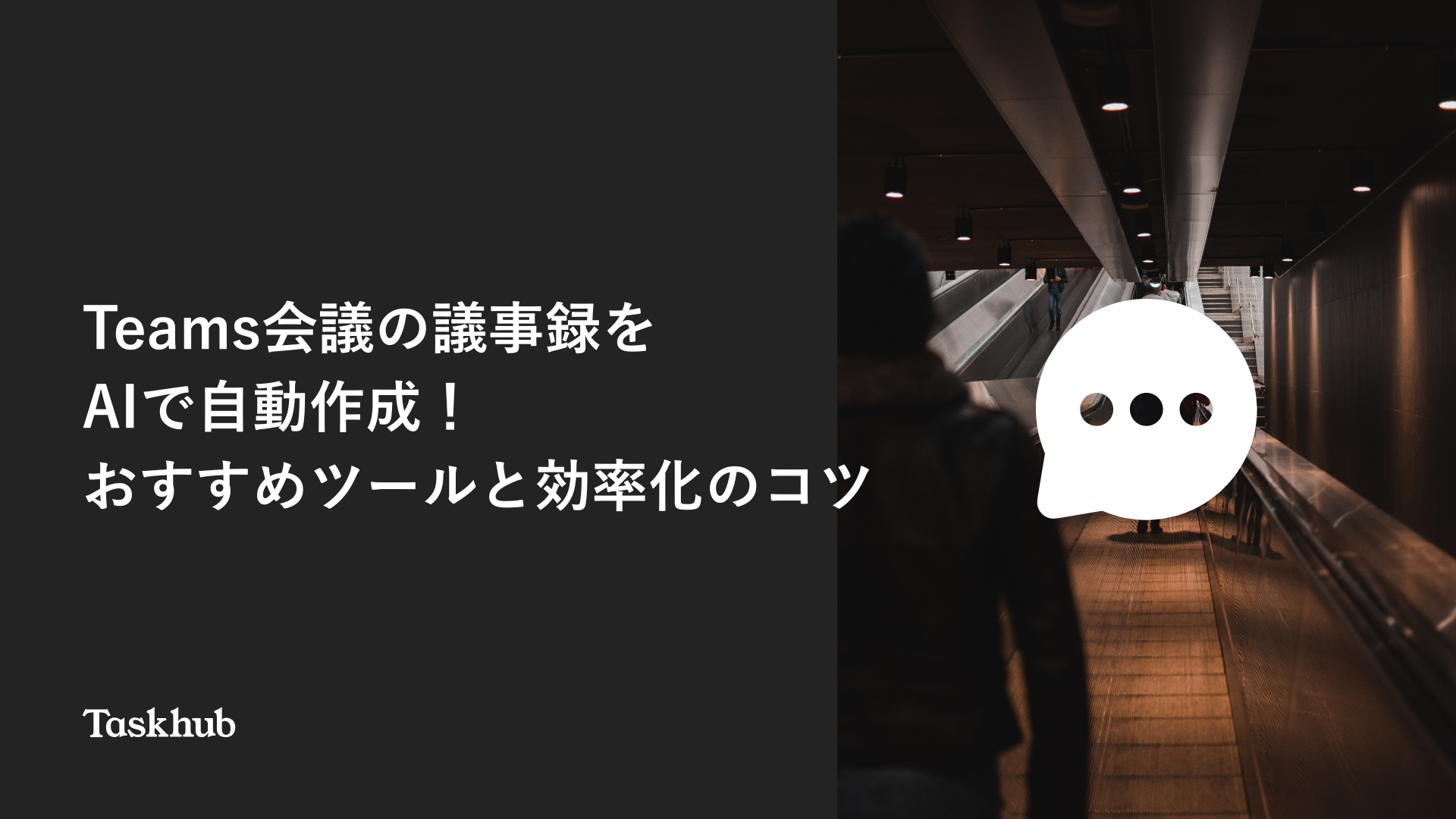「Teamsでの会議が増えたけれど、議事録作成に時間がかかりすぎている」
「会議の内容を聞き漏らしてしまい、正確な記録が残せているか不安だ」
このように、日々の議事録作成業務に負担を感じている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、Teams会議の議事録を自動化する具体的な3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら解説します。
実際に多くの企業で導入支援を行ってきた弊社の知見をもとに、初心者でもすぐに実践できる手順をまとめました。
業務効率を劇的に向上させるためのヒントが詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
Teams会議の議事録を自動作成する方法3選(比較表あり)
ここからは、Microsoft Teamsで行われる会議の議事録を自動で作成するための主要な3つの方法をご紹介します。
- Teams標準の文字起こし機能とChatGPTを組み合わせる
- Microsoft Copilot for Microsoft 365を活用する
- Teams連携が可能なAI議事録ツール(Taskhubなど)を導入する
それぞれの方法にはコストや手軽さ、精度の面で違いがあります。
まずは以下の比較表をご覧いただき、自社の状況に最も適した方法の当たりをつけてみてください。
| 項目 | ①文字起こし×ChatGPT | ②Copilot活用 | ③AI議事録ツール |
|---|---|---|---|
| コスト | 低(既存ライセンスで可) | 高(追加ライセンス必要) | 中(ツールによる) |
| 手軽さ | 中(コピペの手間あり) | 高(Teams内で完結) | 高(自動化・多機能) |
| 精度・機能 | 中(プロンプト次第) | 高(要約機能が優秀) | 高(特化型で高精度) |
| こんな人にオススメ | コストをかけずに工夫で乗り切りたい人 | Microsoft 365環境で全て完結させたい人 | 議事録以外の業務も効率化したい人 |
それでは、各方法の具体的な手順と特徴を詳しく解説していきます。
文字起こし機能×ChatGPTで議事録作成する3ステップ
コストを抑えて議事録を自動化したい場合、Teams標準のトランスクリプト(文字起こし)機能と生成AIであるChatGPTを組み合わせる方法が最も手軽です。
この方法は、特別な追加ツールを契約することなく、既存の環境だけですぐに始められる点が最大のメリットです。
ただし、文字起こしデータを手動でAIに渡す作業が発生するため、完全自動化とは言えない部分があります。
具体的な手順は以下の3ステップです。
まず、Teams会議を開始したら「レコーディングと文字起こし」から「文字起こしの開始」をクリックします。
会議中は自動的に発言内容がテキスト化されていきます。
次に、会議終了後に生成されたトランスクリプトデータをダウンロード、または全文をコピーします。
この際、Speakerの表記などが含まれるため、テキストエディタ等で整理しておくとAIの精度が上がります。
最後に、コピーしたテキストをChatGPTに貼り付け、「以下の会議内容を要約し、決定事項とネクストアクションを抽出して」というプロンプトと共に指示を出します。
これにより、長文の会話ログがきれいに構造化された議事録として出力されます。
手間は少しかかりますが、プロンプトを工夫することで、自社のフォーマットに合わせた議事録が作成可能です。
会議中にCopilotで議事録作成する3ステップ
Microsoft Copilot for Microsoft 365のライセンスを保有している場合、Teams内に統合されたAIアシスタント機能を使うことで、最もシームレスに議事録を作成できます。
Copilotを利用するメリットは、別のツールを開くことなく、Teamsの画面上だけで完結する利便性の高さにあります。
リアルタイムで会議の内容を把握し、途中参加した場合でも「ここまでの経緯を教えて」と質問できるなど、単なる記録以上の価値を提供します。
手順は非常にシンプルです。
まず、会議画面の上部にある「Copilot」アイコンをクリックし、サイドパネルを表示させます。
前提として、文字起こし機能が有効になっている必要があります。
次に、会議が進行する中でCopilotに対して指示を出します。
例えば「これまでの議論のポイントを箇条書きでまとめて」や「懸念点として挙がった項目をリストアップして」と入力すると、即座に回答が得られます。
最後に、会議終了後に「会議の議事録を作成して」と指示を出すだけで、全体の要約、決定事項、タスクの割り当てを含んだドラフトが完成します。
セキュリティ面でもMicrosoft 365のコンプライアンス基準に準拠しているため、機密性の高い会議でも安心して利用できるのが強みです。
Teams対応のAI議事録ツールで議事録作成する2ステップ
より高度な管理機能や、議事録作成以外の業務効率化も同時に図りたい場合は、Teamsと連携可能な外部のAI議事録ツールや、多機能な生成AIプラットフォームの導入がおすすめです。
特におすすめなのが、様々なAI機能をアプリ感覚で使える「Taskhub」のようなツールを活用することです。
これらは議事録作成に特化した調整がなされているため、汎用的なAIよりも直感的に操作でき、質の高いアウトプットが期待できます。
手順は以下の2ステップで完了します。
まず、TaskhubなどのツールにTeamsの会議録画データ(動画または音声ファイル)、あるいは文字起こしテキストをアップロードします。
ツールによっては、会議URLを入力するだけでBotが同席し、自動録音してくれるものもあります。
次に、ツール内の「議事録作成アプリ」や機能を実行します。
Taskhubの場合、単なる要約だけでなく、議題ごとの整理や、関係者への共有メール作成までワンストップで行うことが可能です。
Azure OpenAI Serviceを基盤としているケースが多く、企業利用に必須となるデータセキュリティも万全です。
専門的なプロンプト知識がなくても、ボタン一つで高品質な議事録が手に入るため、全社的な業務標準化を目指す企業に最適な選択肢と言えます。
Teams以外のAI議事録作成サービス3選
Teamsを利用していない会議や、対面での会議を含めて一元管理したい場合には、独立したAI議事録作成サービスを検討する必要があります。
ここでは、Teams以外のプラットフォームでも利用しやすく、日本国内で特に人気の高いサービスを3つ厳選しました。
- Taskhub
- Notta
- tl;dv
それぞれのサービスには得意分野があります。
汎用的な業務効率化を重視するのか、リアルタイム性を重視するのかなど、自社のニーズに合わせて選定することが重要です。
以下で各サービスの特徴を解説します。
Taskhub
Taskhubは、議事録作成にとどまらず、200種類以上のAIタスクをアプリのように利用できる総合型生成AIプラットフォームです。
Teams会議の録画データや音声ファイルをアップロードするだけで、高精度な議事録が自動生成される機能を持っています。
最大の特徴は、議事録作成で終わらず、その内容をもとに「報告メールの作成」や「ToDoリストの抽出」、「企画書のドラフト作成」など、次の業務へシームレスに繋げられる点です。
一般的な議事録ツールは「記録」に特化していますが、Taskhubは「業務全体の効率化」を目指して設計されています。
そのため、営業部門だけでなく、人事、総務、企画など全社的な導入に適しています。
セキュリティ面でもAzure OpenAI Serviceを採用しており、入力データがAIの学習に使われない仕様となっているため、機密情報を扱う会議でも安心して利用できます。
「議事録ツールを入れたけれど、結局あまり使われていない」という事態を避け、日常業務にAIを浸透させたい企業に最適です。
公式HP:https://taskhub.jp/

Notta
Nottaは、高精度な音声認識技術を搭載し、リアルタイムでの文字起こしと翻訳に強みを持つAI議事録作成ツールです。
Web会議だけでなく、対面会議の録音データや、スマートフォンアプリ経由での音声入力にも対応しているため、場所を選ばずに利用できる汎用性の高さが魅力です。
特に日本語の認識精度が高く評価されており、誤字脱字の修正にかかる時間を大幅に削減できます。
また、AI要約機能が充実しており、長時間の会議でも「重要ポイント」「行動項目」などを自動的に抽出してくれます。
Teams、Zoom、Google Meetなど主要なWeb会議ツールすべてに対応しており、カレンダー連携をしておけば、自動でBotが会議に参加して記録を開始する機能も備えています。
営業先での商談記録から社内の定例会議まで、幅広いシーンで議事録作成を効率化したい企業に適しています。

tl;dv
tl;dvは、ZoomやGoogle Meet、Teamsでの会議動画を録画し、重要な瞬間にタイムスタンプを押して共有することに特化したツールです。
完全な文字起こしテキストを読むよりも、実際の動画の該当箇所を見直した方が早いというニーズに応える設計になっています。
AIが会議中のハイライトシーンを自動で検出し、クリップとして切り出してくれる機能が非常に便利です。
多言語対応が進んでおり、海外拠点との会議が多い企業でも重宝されています。
基本的な機能の多くを無料プランから利用できるため、まずはコストをかけずにAI議事録ツールを試してみたいというスタートアップや中小企業にも人気があります。
「会議の空気感」や「微妙なニュアンス」を動画で振り返りつつ、必要な部分だけをテキストで確認したいというハイブリッドな利用スタイルに最適です。
公式HP:https://tldv.io/ja/

Teams以外のAI議事録作成サービスの3つの選び方
数多くのAI議事録サービスが存在する中で、自社に最適なツールを選ぶには明確な基準が必要です。
単に機能が多いものを選ぶのではなく、現場の運用に耐えうるかどうかを見極める必要があります。
- Teamsで連携しやすい
- セキュリティに強い
- カスタマイズしやすさ
これら3つのポイントを押さえて選定することで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。
それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
Teamsで連携しやすい
「Teams以外」のサービスを導入する場合でも、Teamsとの連携のしやすさは非常に重要な選定ポイントです。
なぜなら、多くの企業においてメインのコミュニケーションツールとしてTeamsが使われているため、そこから断絶されたツールは定着しにくいからです。
具体的には、Teamsのカレンダーと同期して自動で録音を開始できるか、あるいは作成された議事録をTeamsのチャットやチャネルに直接共有できるかを確認しましょう。
連携がスムーズであれば、会議が終わった直後にTeamsのグループチャットに議事録のリンクが投稿され、参加者全員がすぐに内容を確認できるというフローが構築できます。
Botを招待するタイプなのか、録画データを後からアップロードするタイプなのかによっても運用が変わります。
自社のTeams利用ポリシー(外部アプリの許可設定など)と照らし合わせ、ストレスなく連携できるツールを選ぶことが、継続的な利用への第一歩です。
セキュリティに強い
議事録には、企業の機密情報や個人情報、未発表のプロジェクト内容が含まれることが多いため、セキュリティ対策は最も慎重に確認すべき項目です。
特に外部のAIサービスを利用する場合、「入力したデータがAIの学習に利用されるかどうか」は必ずチェックする必要があります。
安価なツールや無料プランでは、データがサービス改善のために利用される規約になっていることがあるため注意が必要です。
企業で導入する場合は、SOC2 Type2認証やISO27001などの国際的なセキュリティ基準を満たしているか、データが暗号化されて保存されているかを確認しましょう。
また、ユーザーごとのアクセス権限管理(閲覧・編集の制限)が細かく設定できるかどうかも重要です。
Taskhubのように、エンタープライズレベルのセキュリティ基盤(Azure OpenAI Serviceなど)を採用しているサービスを選ぶことで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。
カスタマイズしやすさ
AIが作成する議事録の品質を自社に合わせるためには、出力形式やプロンプトのカスタマイズのしやすさが重要です。
一般的な「要約」だけでは、業界特有の用語や、社内独自の会議フォーマット(例:結論、理由、ネクストアクションの順で書くなど)に対応しきれない場合があります。
そのため、単語登録機能や、要約のテンプレートを自由に編集できる機能があるツールを選ぶと良いでしょう。
さらに進んで、プロンプト自体を調整できるツールであれば、「もっと詳細に書いてほしい」「課題点だけを箇条書きにしてほしい」といった細かい要望に応えることができます。
カスタマイズ性が高いツールを導入すれば、会議の種類(定例会、商談、ブレインストーミング)に応じて最適なアウトプット設定を使い分けることができ、修正の手間を極限まで減らすことが可能になります。
導入当初はデフォルト機能で十分でも、使い込むうちに必ず「ここをこうしたい」という要望が出てくるため、柔軟性は長く使う上で欠かせない要素です。
Teams会議での議事録作成に関するよくある質問
最後に、Teams会議の議事録作成に関して、導入検討時によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
機能の制限やデータの保存場所など、実務運用で気になるポイントを解消しておきましょう。
- Teamsの無料版でも自動文字起こしは使える?
- 多言語の会議でも自動で翻訳・議事録作成できる?
- 文字起こしデータや録画データはどこに保存される?
これらの疑問をクリアにしておくことで、スムーズな導入が可能になります。
それぞれの質問に回答します。
Teamsの無料版でも自動文字起こしは使える?
残念ながら、Teamsの無料版(Microsoft Teams Essentialsなど一部プランを除く)では、会議のレコーディング機能やライブトランスクリプション(文字起こし)機能は制限されており、利用できないケースがほとんどです。
自動文字起こし機能を利用するためには、基本的にはMicrosoft 365 Business StandardやOffice 365 E3などの有料ライセンスが必要になります。
もし無料版を使用している状況で議事録を自動化したい場合は、Teams自体の機能に頼るのではなく、PCのシステム音声を直接拾って文字起こしをする外部のAIツールを併用する必要があります。
あるいは、Windows 11などに標準搭載されている機能や、スマートフォンの録音アプリを活用するなどの工夫が必要ですが、有料ライセンスを導入した方が業務効率は圧倒的に高くなります。
多言語の会議でも自動で翻訳・議事録作成できる?
はい、Teamsの標準機能および多くのAI議事録ツールは多言語に対応しています。
Teamsのライブトランスクリプション機能は、会議の言語設定を変更することで、英語、中国語、フランス語など多数の言語を認識し、文字起こしを行うことが可能です。
さらに、Copilotや翻訳機能を併用すれば、英語で行われた会議の内容を日本語で要約して議事録化することも容易です。
ただし、一つの会議の中で複数の言語が飛び交うような複雑な状況(コードスイッチング)では、認識精度が落ちる可能性があります。
そのような場合は、話者設定を明確にするか、多言語対応に特化した外部ツール(Nottaやtl;dvなど)を組み合わせることで、より正確な記録を残すことができます。
グローバルチームでの会議では、リアルタイム翻訳字幕を表示させることで、議事録だけでなく会議自体の円滑化も図れます。
文字起こしデータや録画データはどこに保存される?
Teamsで記録された会議の録画データやトランスクリプト(文字起こしデータ)は、基本的にはSharePoint OnlineまたはOneDrive for Businessに保存されます。
以前はMicrosoft Stream(クラシック)に保存されていましたが、仕様変更により現在はファイルとして扱われるようになりました。
具体的には、チャネル会議の場合はそのチームのSharePointサイトに、チャネル以外の会議(予定表から作成した会議など)の場合は、録画を開始したユーザーのOneDriveの「レコーディング」フォルダに保存されます。
保存容量は各ユーザーや組織の契約プランに依存します。
動画データは容量を圧迫しやすいため、一定期間(デフォルトでは60日など)で自動削除される設定になっている場合もあります。
重要な議事録データについては、保存期限の設定を確認するか、Taskhubのような外部ストレージと連携できるツールを用いて、永続的なアーカイブ環境を整えておくことをお勧めします。
まとめ
本記事では、Teams会議の議事録を自動作成する3つの方法や、ツールの選び方について解説しました。
議事録作成は重要ですが、そこに多くの時間を奪われてしまっては本末転倒です。
Teams標準機能やCopilot、そして外部ツールを上手く活用することで、業務効率は劇的に改善します。
しかし、「どのツールも設定が難しそう」「もっと手軽に、色々な業務を一括でAI化したい」と感じる担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは、日本初のアプリ型インターフェースを採用した生成AI活用プラットフォームです。
議事録作成はもちろん、メール作成や資料の要約、画像生成など、200種類以上の実用的なAIタスクが「アプリ」としてパッケージ化されています。
Teams会議の録音データをアップロードするだけで、即座に整理された議事録が手に入るだけでなく、その内容を元にした報告書作成までワンクリックで完結します。
Azure OpenAI Serviceを基盤としているため、企業が最も気にするデータセキュリティも万全。
情報漏えいのリスクを心配することなく、全社的なAI導入を実現できます。
さらに、AI導入のプロによる手厚いサポート体制も整っており、社内に専門知識を持つ人材がいなくても安心してスタートできるのが大きな強みです。
「まずは何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひTaskhubの活用事例や詳細機能をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速・簡単・安全”な生成AI活用を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。