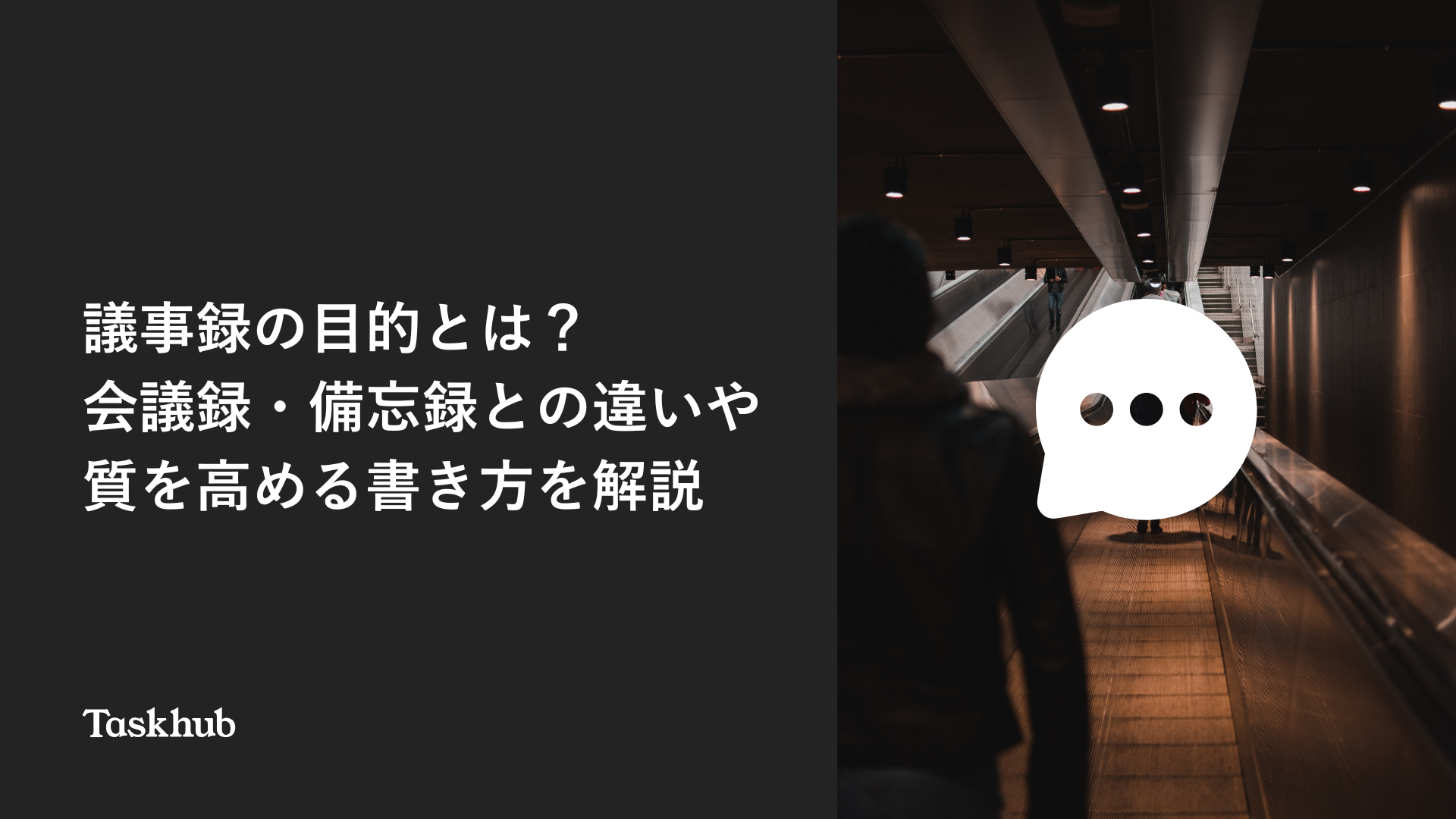「上司に議事録の作成を頼まれたけれど、何のために書くのかよくわからない」
「頑張ってメモを取ったのに、ただの発言録だと言われてしまった」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
議事録は単なる会議の記録ではなく、プロジェクトを円滑に進めるための重要なビジネス文書です。目的を正しく理解していないと、時間をかけて作成しても誰にも読まれない、役に立たない資料になってしまいます。
こちらは会議の非効率性が経済に与える損失について解説した記事です。 合わせてご覧ください。https://fellow.ai/blog/unproductive-meeting-statistics/
本記事では、議事録・会議録・備忘録の明確な違いや、議事録を作成する5つの本来の目的、そして質の高い議事録を書くための具体的なコツについて解説しました。
企業のDX支援や業務効率化コンサルティングを行っている知見を活かし、実務で即座に使えるノウハウをご紹介します。
明日からの会議ですぐに役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
業務効率化の全体像について知りたい方は、DXによる業務効率化の成功事例と進め方について解説したこちらの記事を合わせてご覧ください。
議事録・会議録・備忘録の違いとは?それぞれの定義と役割
会議の記録を残す文書には、主に「議事録」「会議録」「備忘録」の3種類があります。これらは似ているようでいて、作成する目的や対象となる読者、重視すべきポイントが全く異なります。
それぞれの違いを曖昧にしたまま作成してしまうと、読み手にとって必要な情報が見つからなかったり、逆に不要な情報が多すぎて要点がぼやけてしまったりする原因になります。まずは、これら3つの文書の定義と役割について、詳しく見ていきましょう。
こちらは記録管理の国際標準における記録の定義について解説した用語集です。 合わせてご覧ください。https://recordsmanagement.uoregon.edu/glossary
議事録:決定事項と「誰が・いつまでに・何をするか」を記録する公的な資料
議事録とは、会議において何が決まったのか、そして今後誰がどのように動くのかを記録し、関係者間で共有するための公的な文書です。最も重視されるのは「決定事項」と「ネクストアクション(タスク)」の2点です。
会議の中で誰がどのような発言をしたかという詳細なプロセスよりも、最終的な結論として何に合意したのかという「結果」が求められます。そのため、発言を一言一句書き残す必要はありません。むしろ、議論の要点を整理し、結論に至ったロジックを簡潔にまとめる編集能力が問われます。
また、議事録は会議に参加しなかった関係者や、将来的にプロジェクトに参加するメンバーが見たときに、その会議でプロジェクトがどう進んだかを把握できる状態にしておく必要があります。つまり、主観を含まず、客観的な事実に基づいて記載され、組織としての合意形成を証明する役割を担っています。上司やクライアントへの報告資料としても機能するため、正確性とわかりやすさが不可欠です。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
会議録:発言内容を漏らさず記録する詳細なログ(書き起こし)
会議録とは、会議中の発言内容を可能な限り詳細に、時系列順に記録した文書のことを指します。議事録が「結論」を重視するのに対し、会議録は「プロセス」や「発言そのもの」を保存することに重きを置いています。
一般的には「書き起こし」や「ログ」とも呼ばれ、誰がどのようなニュアンスで発言したか、議論がどのように紛糾し、どう収束していったかという文脈を正確に残すことが目的です。裁判の記録や国会の答弁記録、あるいは学術的なインタビュー調査などがこれに該当します。また、企業においても、コンプライアンス上の重要な会議や、人事面談など、後から「言った・言わない」の事実確認が極めて重要になる場面で作成されます。
会議録を作成する際は、編集者の意図で要約したりカットしたりすることは基本的に許されず、正確性が最優先されます。そのため、作成には膨大な時間と労力がかかりますが、近年ではAIによる音声認識技術の発達により、自動化が進んでいる領域でもあります。あくまで事実の保存が目的であり、タスク管理の機能は弱いため、通常のビジネス会議でそのまま議事録として使うには不向きな場合があります。
備忘録:個人の記憶を補助するための私的なメモ
備忘録とは、その名の通り「忘れることに備える記録」、つまり個人の記憶を補助するために作成する私的なメモのことです。議事録や会議録が他者への共有を前提とした公的な文書であるのに対し、備忘録は基本的に自分自身が後で見返すために書かれます。
そのため、形式や書き方に決まったルールはありません。自分が理解できれば、箇条書きでも、図やイラスト交じりでも、あるいはキーワードの羅列だけでも問題ありません。内容も、決定事項だけでなく、会議中にふと思いついたアイデアや、個人的に調べたいこと、抱いた感想など、主観的な情報を含めて自由に記述することができます。
ビジネスシーンにおいては、正式な議事録が発行されるまでのつなぎとして活用したり、自分のタスクを整理するために手帳に書き留めたりするものがこれに当たります。ただし、備忘録はあくまで自分用のメモであるため、これをそのままチームへの共有資料として提出してしまうと、他人には文脈が伝わらなかったり、重要な決定事項が抜けていたりして、トラブルの原因になることがあります。公的な議事録とは明確に区別して扱う必要があります。
【比較表】3つの違いを一覧で確認
これまでに解説した議事録、会議録、備忘録の違いを整理するために、比較表を作成しました。それぞれの特徴を一覧で確認し、目的に応じて適切な形式を選択できるようにしましょう。
| 項目 | 議事録 | 会議録 | 備忘録 |
| 主な目的 | 決定事項とタスクの共有・管理 | 発言内容とプロセスの正確な保存 | 個人の記憶補助・アイデアの記録 |
| 重視する点 | 結論、ネクストアクション、要点 | 正確性、網羅性、発言のニュアンス | 自分にとっての分かりやすさ |
| 対象読者 | 会議参加者、関係者、上司 | 監査担当、法務、詳細を知りたい人 | 自分自身 |
| 形式 | 結論優先の構成(結論→経緯) | 時系列順(発言順) | 自由(箇条書き、メモなど) |
| 主観の有無 | なし(客観的事実のみ) | なし(事実のみ) | あり(感想やアイデアも可) |
| 作成難易度 | 中~高(要約・整理スキルが必要) | 低~中(書き起こす労力が必要) | 低(自由に書ける) |
このように、ビジネスの現場で一般的に求められるのは、情報を整理してアクションにつなげる「議事録」です。会議録のように全てを記録する必要はなく、備忘録のように自分だけが分かれば良いものでもありません。
この違いを意識するだけで、作成にかかる時間を大幅に短縮でき、かつ読み手にとって価値のある資料を作成できるようになります。
なぜ議事録を作成する必要があるのか?5つの主要な目的
議事録を作成する作業は、手間がかかる面倒な業務だと思われがちです。しかし、「議事録 目的」を正しく理解すれば、それが単なる事務作業ではなく、プロジェクトを成功させるための強力な武器になることがわかります。
議事録を作成する目的は、大きく分けて5つあります。これらの目的を意識しながら作成することで、記載すべき内容や強調すべきポイントが自然と明確になり、質の高いアウトプットにつながります。
決定事項を関係者全員で正確に共有するため
議事録の最大の目的は、会議で決まったことを関係者全員が「同じ解像度」で理解し、共有することです。会議の場では、参加者それぞれが自分の関心のある分野や立場から話を聞いているため、同じ話を聞いていても、受け取り方や解釈にズレが生じることが珍しくありません。
例えば、「なるべく早く対応する」という決定があった場合、ある人は「今日中」と捉え、別の人は「今週中」と捉えているかもしれません。このような認識のズレを放置したままプロジェクトが進むと、後になって手戻りが発生したり、期待していた成果物が上がってこなかったりする事態を招きます。
議事録として文字情報に残し、それを全員で確認することで、曖昧だった部分が明確になります。「A案で進めることになった」「予算は〇〇万円で確定した」といった決定事項を客観的なテキストとして固定することで、参加者全員の認識を統一し、チームとしての一体感と方向性を揃えることができます。これは組織として成果を出すための第一歩と言えるでしょう。
「言った・言わない」のトラブルを防ぐ証拠として残すため
ビジネスにおいて、口約束ほど危険なものはありません。「あの時、部長は良いと言ったはずだ」「いや、条件付きで許可したつもりだった」といった「言った・言わない」の水掛け論は、社内だけでなく、クライアントとの間でも頻繁に起こりうるトラブルです。こうした不毛な争いを防ぐために、議事録は強力な証拠資料として機能します。
議事録に会議の内容を記録し、会議終了後に関係者の合意を得ておくことで、その内容が「事実」として確定します。万が一、後からトラブルが発生したとしても、議事録を提示することで「〇月〇日の会議で、このように合意しています」と冷静に事実を伝えることができます。これにより、責任の所在が明確になり、不要な対立を避けることができます。
こちらは口頭での合意に関するトラブルの実態について解説した記事です。 合わせてご覧ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000016795.html
特に、外部のパートナー企業や顧客との会議においては、契約内容や仕様変更に関する重要なやり取りが行われることが多いため、議事録の証拠能力は非常に重要です。自分自身や自社を守るための防衛策としても、正確な議事録を残しておくことは必須のリスクマネジメントと言えます。
ネクストアクション(タスク・担当者・期限)を明確にするため
会議が終わった後、最も避けなければならないのは「で、結局誰が何をするんだっけ?」と誰も動かない状態になることです。良い会議とは、次のアクションが明確になり、プロジェクトが一歩前進する会議のことです。議事録には、この「次の一歩」を確実に実行させるためのタスク管理ツールとしての役割があります。
具体的には、決定事項に基づいて発生したタスクについて、「誰が(担当者)」「いつまでに(期限)」「何をするのか(内容)」の3点をセットで明記します。これを曖昧にしておくと、タスクが宙に浮いてしまい、期限直前になって「誰もやっていなかった」という事態になりかねません。
議事録にタスク一覧としてまとめておけば、担当者は自分の責任範囲を自覚でき、マネージャーは進捗管理がしやすくなります。また、次回の会議の冒頭で前回の議事録を確認すれば、宿題が完了しているかどうかをスムーズにチェックすることも可能です。つまり、議事録は会議と会議の間をつなぎ、実行を促すためのドライバーとなるのです。
こちらは目標を書き留めることによる達成率への影響について解説した研究結果です。 合わせてご覧ください。https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=psychology-faculty-conference-presentations
会議に参加していない人へ情報を共有・報告するため
会議には、必ずしも全ての関係者が参加できるわけではありません。他の業務で忙しいメンバーや、決裁権を持つ上司、あるいは将来的にプロジェクトに参加する可能性のある人がいます。議事録は、そうした会議に参加していない人々に対して、効率的に情報を共有・報告するためのメディアとしての役割も果たします。
欠席者が議事録を読めば、1時間の会議の内容をわずか5分程度で把握できるようにまとめることが理想です。そのためには、ダラダラとした会話の記録ではなく、結論と経緯が構造化された、読みやすい文章が求められます。
上司への報告資料としても、口頭で説明するより議事録を提出する方が正確で、時間の節約にもなります。また、適切に情報共有がなされていれば、欠席者から後で「そんな話は聞いていない」と苦情が来ることも防げます。組織全体で情報の透明性を高め、スムーズな連携を可能にするためにも、第三者が読むことを前提としたわかりやすい議事録作成が重要です。
次回の会議をスムーズに進めるための資産にするため
議事録は、過去の記録であると同時に、未来の会議のための資産でもあります。人間の記憶は時間の経過とともに薄れていくものです。1週間前、1ヶ月前の会議でどのような議論を経て結論に至ったのか、詳細を正確に覚えている人は稀でしょう。
次回の会議を開催する際、前回の議事録があれば、前回の決定事項や積み残した課題(宿題)をすぐに振り返ることができます。これにより、「前回どこまで話したっけ?」という確認作業に時間を取られることなく、すぐに本題に入ることができます。継続的な会議体においては、議事録が議論の土台となり、積み上げ式に検討を深めていくことが可能になります。
また、長期的なプロジェクトでは、途中でメンバーが入れ替わることもあります。その際、過去の議事録がきちんと整理されていれば、新メンバーはそれを読み返すことでプロジェクトの経緯や背景を素早くキャッチアップできます。議事録は、組織のナレッジとして蓄積され、業務の効率化や属人化の解消にも寄与する重要な資産なのです。
目的を果たせない「ダメな議事録」になってしまう原因
議事録を書く目的は理解していても、実際に作成してみると「何だか分かりにくい」「役に立たない」と言われてしまうことがあります。目的を果たせない議事録には、共通するいくつかの悪いパターンが存在します。
ここでは、多くの人が陥りがちな「ダメな議事録」の原因を3つ挙げます。これらを反面教師とすることで、質の高い議事録作成への近道となります。
構成が決まっておらず、ただの発言録になっている
最もよくある失敗例が、発言を発言順に羅列しただけの「発言録」になってしまっているケースです。「Aさんが〇〇と言った。次にBさんが××と返した。それに対してCさんが…」というように、会話の流れをそのまま追体験させるような書き方は、議事録としては不適切です。
読み手が知りたいのは「どんな会話があったか」ではなく「何が決まったのか」です。時系列に沿って書かれた長文の中から、重要な決定事項を探し出すのは、読み手にとって大きなストレスであり、時間の無駄です。また、話題があちこちに飛ぶ実際の会議をそのまま記録すると、構成が支離滅裂になりがちです。
これを防ぐためには、時系列ではなく「議題(トピック)」ごとに情報を再構成する必要があります。たとえ会議の冒頭と最後で同じテーマについて話していたとしても、議事録上では一つの項目にまとめて記載します。情報を構造化し、読み手が知りたい結論へ最短距離でアクセスできるように整理することが、議事録作成者の腕の見せ所です。
事実(決定事項)と個人の感想(意見)が混ざっている
議事録は客観的な事実を記録する文書ですが、そこに作成者の主観や感想が混ざり込んでしまうと、信頼性が大きく損なわれます。例えば、「A部長は不満そうだった」「B案の方が優れていると感じた」「議論は盛り上がった」といった記述は、作成者の解釈に過ぎず、事実とは限りません。
また、会議中の発言者の「意見」と、会議としての「決定事項」が明確に区別されていないケースも問題です。誰かの強い意見があたかも決定事項のように書かれていたり、逆に決定事項が単なる一意見のように埋もれていたりすると、読んだ人が誤った認識を持ってしまう危険性があります。
議事録を書く際は、「事実(Fact)」と「意見(Opinion)」を厳密に切り分ける意識が必要です。「決定事項:〇〇とする」と「意見:〇〇という懸念点が出た」は明確に書き分けましょう。もし補足として自分の所感を残したい場合は、「作成者コメント」や「備考」として欄を分け、本文とは別枠で記載するなどの工夫が必要です。
結論が曖昧で、結局何が決まったのか分からない
最後まで読んでも「で、結局どうなったの?」という疑問が残る議事録は、目的を果たせているとは言えません。これは、会議自体の結論が曖昧だった場合に起こりやすい現象ですが、議事録作成者がその曖昧さをそのまま書き写してしまうことが原因です。
例えば、「検討する」「調整する」「善処する」といった言葉で締めくくられている場合、具体的に誰がいつまでに何をするのかが全く見えません。また、「A案とB案が出た」という記述だけで、どちら採用されたのか、あるいは継続審議になったのかが書かれていないケースもあります。
もし会議中に結論が出なかった場合は、「結論:保留」とするだけでなく、「次回会議までにAさんが追加データを調査し、その結果をもとに再検討する」というように、次のアクションまで具体的に落とし込んで記載する必要があります。曖昧な部分を残さず、白黒はっきりさせること、あるいは「今は白黒つけられない状態であること」を明確に定義することが、良い議事録の条件です。
議事録の目的を達成するための必須項目と構成フォーマット
読みやすく、役に立つ議事録を作成するためには、一定のフォーマット(型)に沿って書くことが推奨されます。毎回ゼロから構成を考えるのではなく、必要な項目を網羅したテンプレートを用意しておけば、抜け漏れを防ぎ、作成スピードも向上します。
ここでは、議事録として最低限押さえておくべき必須項目と、情報を整理するための基本構成について解説します。
基本情報(日時・場所・出席者)は正確に記載する
議事録の冒頭には、必ず会議の基本情報を記載します。これは、その文書が「いつ、どこで、誰が行った会議の記録なのか」を特定するために不可欠なインデックス情報です。
具体的には以下の項目を含めます。
- 会議名:何の会議かがひと目でわかる名称
- 日時:開始時間だけでなく終了時間も記載(会議の長さを記録するため)
- 場所:会議室名や、オンライン(Zoom/Teams等)の区分
- 出席者:社内・社外を分け、役職順に記載。欠席者がいる場合はその旨も記載
- 作成者:問い合わせ先として自分の名前を記載
これらの情報は、後から過去の議事録を検索する際に非常に重要になります。また、出席者の記録は、誰がその意思決定に関与したかを示す証拠にもなります。特に重要な会議では、出席者の氏名に間違いがないか、漢字や役職も含めて細心の注意を払って確認しましょう。
議題(アジェンダ)ごとに結論を記載する
本文の構成において最も重要なのが、議題(アジェンダ)ごとの整理です。会議の進行順ではなく、テーマごとに項目を立て、それぞれの項目の直下に「結論」をまず記載します。
ビジネス文書では「結論ファースト」が鉄則です。忙しい役員や関係者は、詳細な経緯よりも、まずは結果を知りたがっています。
例:
- 議題1:新商品のパッケージデザインについて
- 結論:B案(青色ベース)に決定
- 理由:ターゲット層である20代男性の支持率が最も高かったため
このように、見出しを見ただけで何について話したかが分かり、その直下を見れば結果がわかる構成にします。もしアジェンダが事前に配布されている場合は、その項目に沿って書くと、参加者にとっても振り返りやすくなります。
決定事項に至った経緯や理由を簡潔に添える
結論の次には、なぜその結論に至ったのかという「経緯」や「理由」を補足します。結論だけでは、後から読み返したときに「なぜこっちの案になったんだっけ?」という疑問が湧いたり、事情を知らない人が読んだときに納得感が得られなかったりするからです。
ここでは、詳細な発言録を書く必要はありません。
- どのような選択肢があったのか
- それぞれのメリット・デメリットとして何が挙がったか
- 最終的な決め手となった要因は何か
- 反対意見に対してはどう対処したか
これらを要約して記載します。決定のロジックを残しておくことで、後になって「やっぱりA案の方が良かったのではないか」という蒸し返しが起きた際にも、「当時はこういう理由でB案を選んだ」と説明することができ、手戻りを防ぐことができます。箇条書きを活用して簡潔にまとめるのがポイントです。
次回までの宿題(タスク・期限・担当者)を明記する
議事録の最後、あるいは各議題の締めくくりとして、決定事項から派生した「宿題(ToDo/タスク)」を必ず明記します。これがプロジェクトを前に進めるためのエンジンとなります。
タスクを記載する際は、5W1Hの中でも特に以下の3要素を欠かさないようにしましょう。
- Who(誰が):具体的な個人名を指定する(「営業部」などの部署名ではなく個人名が望ましい)
- When(いつまでに):具体的な日付や時間を設定する(「なる早」はNG)
- What(何を):完了条件がわかる具体的な行動内容
これらを「タスク一覧」として別枠でまとめておくと、視認性が高まり、担当者が自分のタスクを見落とすリスクを減らせます。また、次回の会議予定が決まっている場合は、その日時と場所も合わせて記載し、ネクストステップを明確にして文書を締めくくります。
読みやすく価値のある議事録を書くための5つのコツ
必須項目を埋めるだけでは、まだ「普通の議事録」です。そこから一歩進んで、「さすが!」と言われるような読みやすく価値のある議事録にするためには、書き方にいくつかのテクニックが必要です。
読み手の負担を減らし、情報を正確かつ迅速に伝えるための5つの実践的なコツを紹介します。これらを意識するだけで、議事録の品質は劇的に向上します。
5W2H(誰が・いつ・何をなど)を意識して具体的に書く
曖昧な表現はビジネス文書の敵です。誰が読んでも同じ解釈ができるように、5W2H(Who, When, Where, What, Why, How, How much)を意識して、具体的に記述しましょう。
特に数字や固有名詞は重要です。「コストを削減する」ではなく「製造原価を10%(約50円)削減する」、「A社と協議する」ではなく「A社の佐藤氏と電話で協議する」といった具合です。
会議中は文脈が共有されているため、「あれ」「それ」「例の件」などの指示代名詞で会話が成立してしまいますが、議事録にする際はこれらを全て具体的な名詞に置き換える必要があります。文章を書いた後に、「これって具体的にどういうこと?」とツッコミが入る余地がないか、自問自答してみると良いでしょう。5W2Hが揃っている文章は、誤解を生む隙がありません。
敬語は省き「だ・である」調で簡潔に言い切る
議事録は社内文書としての性質が強いため、過度な敬語は不要です。「~とおっしゃいました」「~とのことです」といった丁寧語や尊敬語を使うと、文章が冗長になり、要点が掴みにくくなります。また、文字数が増えることで読むスピードも落ちてしまいます。
基本的には「だ・である」調(常体)で統一し、事実を簡潔に言い切るスタイルが適しています。
- 悪い例:部長は、予算については問題ないとおっしゃっていました。
- 良い例:予算については承認済み。(部長確認)
このように短く言い切ることで、リズム良く読める文章になります。箇条書きも積極的に活用しましょう。ただし、クライアント提出用の議事録など、相手との関係性によっては「です・ます」調(敬体)の方が適切な場合もあるため、提出先に応じて使い分ける柔軟性も必要です。
こちらは箇条書きが情報の処理効率に与える影響について解説した記事です。 合わせてご覧ください。https://medium.com/@ameritor/how-bullet-points-can-make-you-smarter-and-more-efficient-4be673c9a058
会議中はメモ書きに集中し、終了直後に清書する
人間の記憶力には限界があります。どれだけ集中して聞いていても、1時間後の会議終了時には詳細を忘れてしまっているものです。そのため、会議中はきれいな文章を書こうとせず、メモを取ることだけに全集中してください。キーワードの羅列や、自分だけの略語を使っても構いません。とにかく情報を漏らさないことが最優先です。
そして重要なのが、会議が終わったら「すぐに」清書することです。記憶が鮮明なうちにメモを見返し、整った文章に書き直します。時間が経てば経つほど記憶は曖昧になり、メモの意図を思い出すのにも時間がかかってしまいます。
理想は会議終了後30分以内、遅くとも当日中に初稿を書き上げることです。「鉄は熱いうちに打て」と同様に、「議事録は熱いうちに書け」が鉄則です。このスピード感が、議事録作成の効率と質を大きく左右します。
主観を入れず、客観的な事実のみを記載する
先述の「ダメな議事録」の原因でも触れましたが、主観の排除は議事録の信頼性を担保するために極めて重要です。議事録作成者は、あくまで透明な記録係(レコーダー)であり、解説者(コメンテーター)になってはいけません。
自分の感情や推測が入らないように、事実ベースの記述を徹底します。もし会議の雰囲気を伝えたい場合でも、「激しい議論になった」と書くのではなく、「A案とB案について、30分間にわたり質疑応答が行われた」と事実として記述します。
また、自分にとって都合の悪い情報をカットしたり、特定の発言を強調しすぎたりする「バイアス」にも注意が必要です。常に中立的な視点を持ち、第三者が見ても公平な記録であると判断される内容を心がけましょう。客観性が高い議事録ほど、資料としての価値も高まります。
完成したらすぐに共有し、認識のズレがないか確認してもらう
議事録は書き上げて終わりではありません。関係者に共有し、内容に間違いがないか確認してもらい、承認を得て初めて「完成」となります。
作成後は速やかに関係者へメールやチャットで送付しましょう。その際、「内容に相違がある場合は、〇月〇日までにご連絡ください」と確認期限を設けるとスムーズです。早期に共有することで、もし認識のズレや記載ミスがあっても、記憶が新しいうちならすぐに修正可能です。
時間が経ってから「実はあの時の決定は違っていた」となると、すでに作業が進んでしまっており、大きなトラブルになりかねません。スピード共有とフィードバックの受付は、リスク管理の一環でもあります。「素早く出して、周りにチェックしてもらう」というプロセス自体を、議事録作成のルーティンに組み込みましょう。
議事録作成の負担を減らし効率化する方法
質の高い議事録を作成することは重要ですが、それに時間をかけすぎて他の業務が圧迫されてしまっては本末転倒です。議事録作成は、工夫次第で大幅に時間を短縮できる業務でもあります。
最後に、クオリティを落とさずに作成時間を短縮し、効率的に議事録を作成するための3つの方法を紹介します。
事前にフォーマット(テンプレート)を用意しておく
会議が始まってから白紙のドキュメントを開くのではなく、事前に決まったフォーマット(テンプレート)を用意しておきましょう。日時、場所、出席者、議題、決定事項、タスクといった枠があらかじめ作られていれば、会議中はそこに内容を埋めていくだけで済みます。
さらに一歩進んで、会議のアジェンダ(進行表)自体を議事録のテンプレートとして活用するのがおすすめです。会議前にアジェンダを共有し、会議中はそこに決定事項を追記していく形にすれば、会議終了と同時に議事録の骨子が完成している状態になります。
また、定例会議であれば、前回の議事録をコピーしてフォーマットとして使い回すのも効率的です。書くべき項目が決まっているだけで、思考の整理にかかる負担が減り、書くスピードも格段に上がります。
録音・文字起こしツールやAIを活用して自動化する
近年、議事録作成の効率化において最も注目されているのが、AIツールの活用です。全て手動でメモを取るのではなく、録音と文字起こしをツールに任せることで、作成者は議論の整理や要約に集中できます。
こちらはAIによる会議の要約がもたらす時間短縮効果について解説したレポートです。 合わせてご覧ください。https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index
ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールには標準で録音・文字起こし機能がついているものも多くあります。また、2025年8月7日にOpenAIがリリースした最新言語モデル「GPT-5」などの高度な生成AIを活用すれば、単なる文字起こしだけでなく、文章の要約、決定事項の抽出、タスクの整理までを自動で行うことが可能です。
こちらは最新言語モデルGPT-5の機能、リリース日、GPT-4との違いについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。
GPT-5のような最新AIは、簡単な質問には即座に答え、複雑な文脈理解が必要な場合にはじっくりと推論してから回答する「思考時間の自動切替」機能を備えています。これにより、会議の複雑な議論の流れを正確に理解し、精度の高い議事録案を短時間で生成してくれます。もちろん最終的なチェックは人間が行う必要がありますが、ゼロから書く労力と比較すれば、圧倒的な時短になります。
共同編集ツール(Googleドキュメント等)で会議中に完成させる
議事録を「持ち帰って書く宿題」にしない究極の方法は、会議中に全員で書き上げてしまうことです。GoogleドキュメントやNotionなどの共同編集ツールを画面共有し、リアルタイムで議事録を打ち込みながら会議を進行します。
この方法のメリットは、その場で全員の認識を確認できることです。「決定事項はこれで合っていますか?」と画面を見せながら確認すれば、後から「ニュアンスが違う」と言われるリスクをゼロにできます。
書記担当者が打ち込んでいる内容を全員が見ているため、誤字脱字や抜け漏れがあればその場で他の参加者が指摘・修正してくれます。会議が終わった瞬間には、全員が合意した議事録が完成しており、あとは共有ボタンを押すだけ。これにより、議事録作成時間そのものを「ゼロ」に近づけることができます。
【脳科学】人間の記憶は1時間で半分消える?「記録」がビジネスの勝敗を分ける科学的理由
会議で完璧に理解したつもりでも、翌日には「あれ、何だっけ?」となってしまった経験はありませんか。それはあなたの能力不足ではなく、人間の脳の正常な仕組みです。ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスの研究によれば、人間は新しい情報を得てからわずか20分後にはその42%を忘れ、1時間後には56%を忘れてしまうことが分かっています。つまり、会議が終わった直後から、私たちの脳内では猛烈な勢いで情報の消失が始まっているのです。
こちらはエビングハウスの忘却曲線の再現実験について解説した文献です。 合わせてご覧ください。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492928/
この記事では議事録の重要性を解説しましたが、脳科学の視点からも「記録」は極めて合理的です。文字として書き出す(アウトプットする)行為は、脳の「網様体賦活系(RAS)」を刺激し、情報の重要度を高めて記憶の定着を促す効果があると言われています。逆に言えば、議事録を残さない会議は、その内容の半分以上を最初から捨てているのと同じことなのです。「記憶」という不確かなものではなく、「記録」という確実な資産を残すことこそが、生産性を最大化する鍵となります。
引用元:
ヘルマン・エビングハウス著『記憶について』(Über das Gedächtnis)、および認知心理学における忘却曲線の検証データより
まとめ
企業において会議の生産性向上や議事録作成の効率化は、避けて通れない重要課題です。記事内でも触れた通り、AIツールの活用は非常に有効な解決策となります。
しかし、「どのAIツールを選べばいいかわからない」「セキュリティ面が不安で導入が進まない」といった悩みを抱える担当者様も多いのではないでしょうか。
生成AIを企業で導入する際に懸念されるリスクとその対策について詳細に解説した記事です。 合わせてご覧ください。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは、議事録の自動作成や要約はもちろん、メール作成や資料のたたき台作成など、200種類以上のAIタスクを直感的に使えるプラットフォームです。
議事録作成においては、録音データの文字起こしから要点の抽出、ネクストアクションの整理までをスムーズに行い、作成時間を大幅に短縮します。
また、Azure OpenAI Serviceを基盤としているため、会議内容という機密情報も高度なセキュリティ環境下で安全に扱えます。
さらに、導入後の活用サポートも充実しており、AIに不慣れな方でもすぐに業務に定着させることが可能です。
議事録作成というノンコア業務をAIに任せ、人間はより創造的な議論に集中するために。
まずは、Taskhubの機能詳細や導入事例がわかる【サービス概要資料】を無料でダウンロードして、その実力をお確かめください。