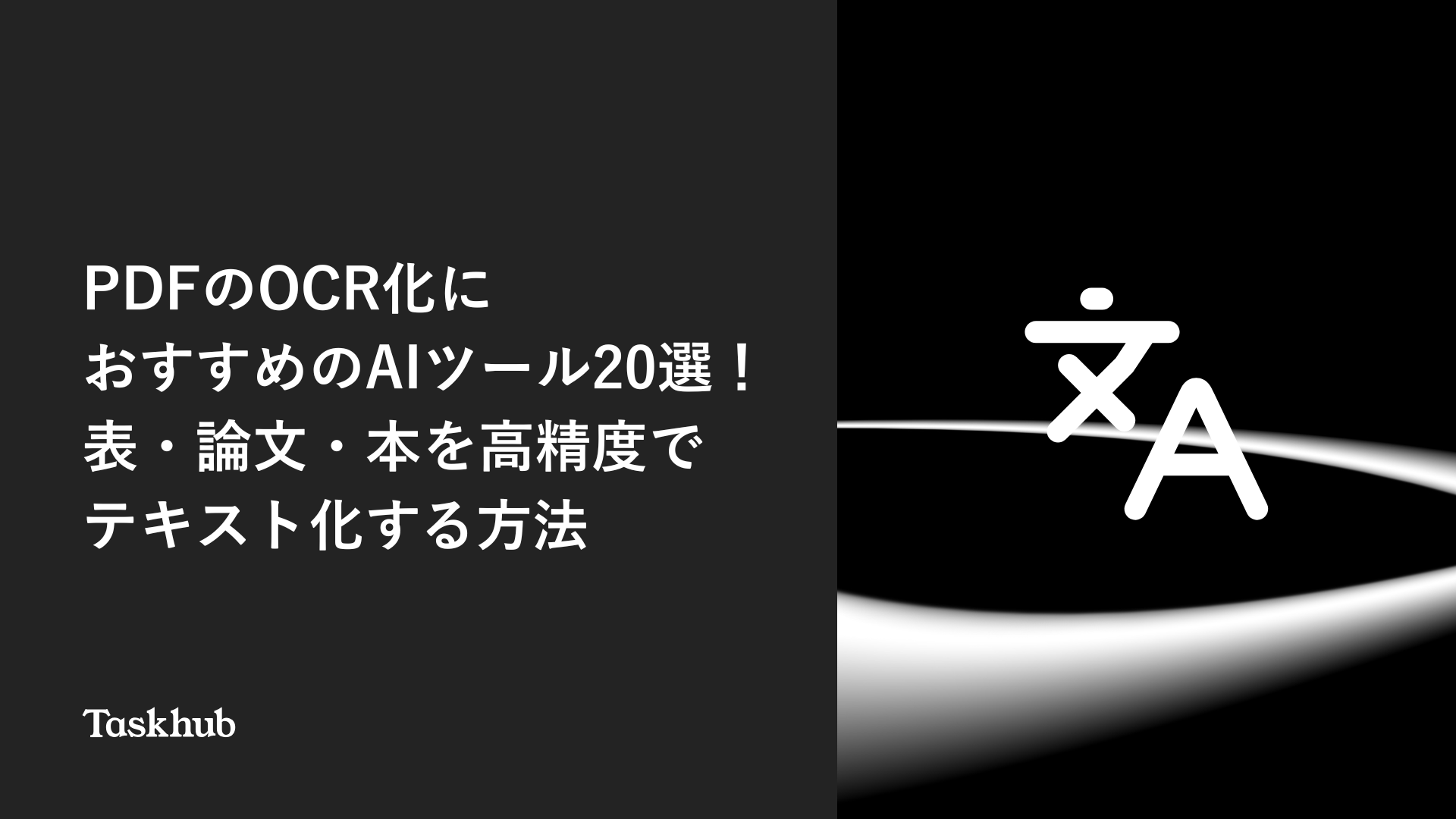「PDFの資料をテキスト化したいけれど、手入力するのは時間がかかりすぎる……」
「無料のOCRツールを使ってみたけれど、文字化けばかりで使い物にならなかった」
このように、日々の業務や研究でPDFのデータ化に頭を抱えている方は多いのではないでしょうか?
実は、近年のAI技術の進化により、これまで困難だった「崩れた文字」や「複雑なレイアウト」の認識精度が劇的に向上しています。
本記事では、PDFのOCR化に最適なAIツールを目的別に厳選してご紹介します。
さらに、AIを活用して精度を高めるための具体的な手順や、導入前に知っておくべき注意点についても詳しく解説しました。
最新のAI技術動向を熟知し、業務効率化のコンサルティングを行っている視点から、本当に使えるツールとノウハウだけをお届けします。
企業でのChatGPT導入の具体的な手順、料金、セキュリティについては、こちらの完全ガイドをご覧ください。
この記事を読めば、あなたの用途にぴったりのAI-OCRツールが見つかり、面倒な入力作業から解放されるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
PDFのOCR処理になぜAIが必要なのか?従来型との決定的な違い
従来のOCR技術と、最新のAIを搭載したOCRには、文字認識の仕組みそのものに大きな違いがあります。
- AI-OCRの特徴
- 学習能力による精度の向上
- 非定型フォーマットへの対応力
- 文脈理解による誤認識の補正
単に文字を形として読み取るだけでなく、AIが文脈やパターンを理解することで、これまでは認識不可能だったドキュメントも高精度にデータ化できるようになりました。
それでは、AI-OCRの革新的なメリットについて、具体的に3つのポイントで解説します。
AI-OCRと従来のOCRにおける文字認識精度の差
従来のOCR(光学文字認識)は、あらかじめ登録されたフォントや文字のパターンと、スキャンした画像を照らし合わせることで文字を特定していました。
そのため、鮮明な活字であれば問題なく認識できましたが、スキャン時のノイズが入ったり、文字がかすれていたりすると、途端に認識率が下がるという課題がありました。
また、異なるフォントが混在している場合や、文字の間隔が不均一な場合も、誤変換が頻発する原因となっていました。
一方で、AIを活用したOCR(AI-OCR)は、ディープラーニング(深層学習)技術を用いています。
膨大な量の文字データをAIが学習しているため、文字の特徴をより深く理解し、多少のかすれやノイズがあっても、「この文字は『あ』である確率が高い」といったように推論することが可能です。
これにより、従来型では認識率が60〜70%程度だった帳票でも、AI-OCRでは95%以上の精度を叩き出すケースも珍しくありません。
特に、画数の多い漢字や、類似した形状の文字(「シ」と「ツ」、「ソ」と「ン」など)の判別において、その差は歴然としています。
こちらは、TesseractやGoogle Visionなど、主要なOCRエンジンの認識精度を比較分析した研究論文です。エンジンの違いによる特性を知りたい方は参考にしてください。 https://arxiv.org/pdf/2506.11156
AIなら手書き文字や崩れたレイアウトも認識可能
AI-OCRの最大の強みの一つが、手書き文字の認識能力です。
人の手書き文字は、書き手によってクセが強く、大きさや傾きもバラバラであるため、従来のパターンマッチング型のOCRでは読み取りがほぼ不可能でした。
しかし、AIは数百万、数千万といった手書き文字のサンプルを学習することで、個人の筆跡のクセを吸収し、高い精度でテキスト化することができます。
乱雑に書かれたメモや、枠からはみ出した文字であっても、AIが文脈から判断して正しく読み取ってくれるのです。
また、レイアウト解析能力も飛躍的に向上しています。
雑誌やパンフレットのように、写真やイラストが複雑に入り組んだデザインや、表と文章が混在しているドキュメントでも、AIが「ここは見出し」「ここは本文」「ここは画像」といった領域を自動的に判別します。
これにより、文章の順番がバラバラになったり、画像内の文字が無視されたりすることなく、見た目通りの構造を維持したままテキストデータを抽出することが可能になりました。
この柔軟性は、定型的な書類だけでなく、非定型の資料を扱う際に大きな威力を発揮します。
画像化されたPDFを検索可能にするメリット
スキャナーで取り込んだPDFファイルは、そのままでは単なる「画像の塊」であり、パソコン上で文字を検索することができません。
必要な情報を探すためには、ファイルを開いて目で見て確認する必要があり、ページ数が多い資料では膨大な時間がかかってしまいます。
AI-OCRを使ってPDFをテキスト化(透明テキスト付きPDF化)することで、ファイル内の全文検索が可能になり、情報の活用価値が一気に高まります。
AIを用いるメリットは、ここでも発揮されます。
単に文字を埋め込むだけでなく、AIがドキュメントの内容を解析し、適切なキーワードやタグを自動で付与してくれるツールも登場しています。
例えば、請求書のPDFであれば、日付、会社名、金額といった重要項目をAIが自動抽出し、ファイル名に付与したり、データベースに登録したりすることができます。
これにより、「〇〇株式会社の請求書」や「2025年1月の資料」といった条件で瞬時にファイルを検索できるようになります。
過去の資料がデジタル資産として活用できるようになることは、ナレッジマネジメントの観点からも非常に大きな意味を持ちます。
紙で保管していた情報をAI-OCRでデジタル化することは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の第一歩と言えるでしょう。DX導入の全体像について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご確認ください。
【目的別】PDFのOCR化に強いAIツールの選び方
AI-OCRツールと一口に言っても、その得意分野はツールによって大きく異なります。
導入に失敗しないためには、自社の課題や目的に合わせて最適なツールを選定することが重要です。
- ツール選びの視点
- 表形式のデータ化が得意か
- 専門用語や多言語に対応しているか
- 書籍などの歪み補正機能があるか
- 手書き文字の認識率は高いか
ここでは、よくある4つの利用シーンに合わせて、どのような基準でAIツールを選ぶべきかを解説します。
【表・Excel】崩れやすい罫線や数値を正確にデータ化したい場合
請求書、見積書、納品書、あるいは決算資料など、ビジネス文書の多くには「表」が含まれています。
これらの表組みを含んだPDFをOCR化する際、最も多いトラブルが、罫線が認識されずに列がずれてしまったり、セル内の数値が隣のセルと結合してしまったりすることです。
Excelにコピー&ペーストした瞬間にレイアウトが崩壊し、修正に何時間もかかってしまった経験がある方もいるでしょう。
表データを正確に抽出したい場合は、表計算ソフトとの連携機能や、表構造の解析に特化したAIモデルを搭載しているツールを選ぶ必要があります。
具体的には、罫線のない表(空白で区切られた表)でも列を認識できるか、セル内の改行を正しく処理できるかといった点がチェックポイントになります。
また、出力形式としてExcel(.xlsx)やCSVをサポートしていることは必須条件です。
高度なAIツールの中には、読み取った表データを自動的にデータベース化し、構造化データとして出力してくれるものもあります。
数値データとしての正確性が求められる経理業務やデータ分析業務においては、単なる文字認識だけでなく、この「構造解析能力」の高さがツール選びの決定的な要因となります。
ディープラーニングを用いた表検出や構造認識の技術動向については、こちらの調査論文で詳しく解説されています。 https://arxiv.org/abs/2211.08469
【論文・文献】段組みや専門用語、英語交じりの文章を読み取りたい場合
学術論文や技術仕様書、古い文献などをテキスト化したい場合、一般的なOCRツールでは対応しきれない課題がいくつかあります。
まず、論文特有の「段組み(マルチカラム)」レイアウトです。
2段組みや3段組みの記事を上から下へそのまま読み取ってしまうと、左右の文章が混ざってしまい、意味の通らないテキストになってしまいます。
AI-OCRを選ぶ際は、段組みを正しく認識し、人間が読む順序通りにテキストを繋ぎ合わせる機能(読み順の最適化)が備わっているかが重要です。
こちらは科学論文の複雑なレイアウトを解析するディープラーニングモデル(PubLayNet)について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/1908.07836
次に、専門用語や多言語対応です。
論文には専門的な技術用語や数式、さらには英語と日本語が混在する文章が頻繁に登場します。
一般的な辞書しか持たないOCRでは、専門用語を誤変換してしまうリスクが高いため、特定の分野(医療、法律、工学など)に特化した学習モデルを持っているか、あるいはユーザー辞書機能があるツールが望ましいです。
また、数式に関しては、LaTeX形式で出力できるツールを選ぶと、後の編集作業が非常にスムーズになります。
英語などの外国語認識精度に関しては、海外製のAIエンジン(Google Cloud Vision APIやMicrosoft Azureなど)を採用しているツールが比較的高性能である傾向があります。
【本・書籍】ページの湾曲やノド(綴じ代)の影を補正したい場合
書籍や冊子を開いた状態でスキャンや撮影を行うと、どうしてもページの中央部分(ノド)が湾曲してしまい、文字が歪んでしまいます。
また、照明の影響で影ができたり、指が写り込んだりすることもよくあります。
このような条件下で撮影された画像の文字を正確に読み取るためには、高度な画像補正機能を備えたAIツールが必要です。
書籍の電子化(自炊)やアーカイブ化を目的とする場合は、「湾曲補正(Curve Correction)」や「指消し機能」が搭載されているかを必ず確認しましょう。
AIがページの曲がり具合を3次元的に解析し、あたかも平面の紙をスキャンしたかのように画像を真っ直ぐに補正してからOCR処理を行うことで、認識精度は劇的に向上します。
さらに、裏写り(裏ページの文字が透けて見える現象)を除去する機能や、古い紙の黄ばみを白く補正する機能があると、よりクリアなテキストデータが得られます。
最近では、スマートフォンのカメラで撮影するだけで、これらの補正をリアルタイムで行ってくれるアプリも登場しており、専用のスキャナーがなくても手軽に書籍のテキスト化が可能になっています。
文書画像の湾曲補正(Dewarping)技術に関する比較研究は、こちらで確認できます。技術的な仕組みに興味がある方はご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/346491873_Dewarping_Document_Image_Techniques_Survey_and_Comparative_Study
【手書き】アンケートや申込書などの手書き文字を認識させたい場合
手書きのアンケート用紙、申込書、問診票などのデータ入力は、これまで人間が目視で行うしかなく、膨大な工数がかかる業務の一つでした。
手書き文字のOCR化は、最も難易度が高い分野ですが、近年のAI技術の進歩により、実用レベルに達したツールが増えています。
手書き文字認識に強いツールを選ぶ際は、日本語の手書き文字(漢字、ひらがな、カタカナ)の学習データ量が豊富な国産のAI-OCRエンジンを採用しているサービスが有利です。
海外製のツールはアルファベットの認識には強いものの、崩した漢字や続け字の認識には弱い傾向があるからです。
また、チェックボックスや丸囲みなどの記号を認識できるかどうかも重要なポイントです。
アンケート集計などでは、文字だけでなく「どの項目が選択されたか」をデータ化する必要があるためです。
さらに、認識精度が100%になることは稀であるため、人間が確認・修正するためのインターフェース(補正画面)が使いやすいかどうかも、業務効率を左右します。
AIが自信がない文字をハイライト表示してくれたり、元の画像と並べて比較しながら修正できたりする機能があると、入力作業の負担を大幅に軽減できます。
GPT-4oと従来のOCR(Textractなど)の手書き認識精度を比較したベンチマーク結果が公開されています。 https://research.aimultiple.com/handwriting-recognition/
無料で手軽に使えるPDF対応AI-OCRツール・サービス
予算をかけずに、まずは手元のPDFをテキスト化したいという方のために、無料で利用できるAI-OCRツールを厳選しました。
無料とはいえ、GoogleやMicrosoftなどの大手IT企業が提供するAIエンジンを搭載しているものが多く、日常的な用途であれば十分な精度を発揮します。
- 無料ツールの特徴
- Webブラウザ上で完結するものが多い
- インストール不要ですぐに使える
- クラウドストレージとの連携が便利
- 枚数制限やファイルサイズ制限がある場合も
ここでは、特に使い勝手が良く、精度の高い9つのツール・サービスをご紹介します。
Googleドライブ(Googleドキュメント)
Googleドライブは、単なるクラウドストレージではなく、実は非常に強力なOCR機能を内蔵しています。
使い方は非常にシンプルで、GoogleドライブにアップロードしたPDFファイルや画像ファイルを右クリックし、「アプリで開く」>「Googleドキュメント」を選択するだけです。
これだけの操作で、GoogleのAIが画像内の文字を解析し、テキストデータに変換してドキュメントとして開いてくれます。
この機能の最大のメリットは、Googleアカウントさえあれば誰でも完全無料で利用できる点と、多言語対応の強さです。
世界中のWebページをインデックスしているGoogleの膨大なデータセットを基にしているため、英語はもちろん、マイナーな言語でも高い精度で認識します。
ただし、元々のレイアウトを維持する機能は弱く、表組みや段組みは崩れてプレーンテキストに近い形で出力されることが多いです。
また、ファイルサイズには上限(通常は2MB程度)があり、あまりにページ数が多いPDFは一度に処理できない場合があります。
レイアウトよりも、とにかく「文字情報だけを抽出したい」という場合に最適なツールです。
Microsoft 365 (Office) アプリ / Word / Azure Computer Vision
Microsoftが提供するモバイルアプリ「Microsoft 365(Office)」は、ホワイトボードや書類をスマホで撮影し、瞬時にPDFやWordファイルに変換できる統合アプリです(旧Office Lens機能を内蔵)。
このアプリには強力なOCR機能が搭載されており、撮影した画像内の文字を認識して、WordやPowerPoint形式で保存することが可能です。
特に「インク」機能を使えば、手書きの文字や図形もデジタルデータとして取り込むことができます。
外出先で書類をデータ化したいビジネスパーソンにとっては必須級のアプリと言えるでしょう。
また、PC版のMicrosoft Wordでも、PDFファイルを開くだけで自動的にWord文書に変換(OCR処理)する機能があります。
PDFのレイアウトを可能な限りWord上で再現しようとするため、編集作業がしやすいのが特徴です。
さらに開発者向けにはなりますが、Microsoft Azureの「Computer Vision API」を利用すれば、より高度で大量のOCR処理を自動化することも可能です。
Microsoftのエコシステムを利用しているユーザーにとっては、追加コストなしで利用できる最も身近な選択肢となります。
LINE WORKS OCR(CLOVA OCR)
LINE WORKS OCRは、LINEが開発したAI技術「CLOVA OCR」を基盤としたサービスです。
このエンジンの最大の特徴は、日本語の手書き文字認識において世界最高レベルの精度を誇る点です。
縦書き、横書きが混在する書類や、丸印で囲まれた文字、さらには歪んだ文字であっても、高い確率で正しく読み取ることができます。
LINE WORKSのチャットボット機能を活用して、トーク画面に画像を送信するだけでOCR結果を返してくれるような使い方も可能です。
無料版(フリープラン)でも一定回数までOCR機能を利用できる場合がありますが、本格的な業務利用には有料プランが必要になるケースが多いです。
しかし、その精度の高さから、「まずは無料で試してみたい」というニーズには十分応えてくれます。
特に、日本のビジネスシーン特有の帳票や手書きメモをデータ化したい場合には、海外製のツールよりも圧倒的に有利です。
身近なLINEのインターフェースで利用できるため、ITツールに不慣れな現場でも導入しやすいというメリットもあります。
Google Gemini / ChatGPT / Claude(画像認識機能の活用)
対話型AIであるGoogle Gemini、ChatGPT、そしてAnthropic社のClaude(クロード)も、強力なOCRツールとして活用できます。
2025年8月にリリースされた「GPT-5」や最新のClaudeモデルをはじめ、マルチモーダルAIは画像を「見る」能力が飛躍的に向上しています。
使い方は、チャット画面にPDFのスクリーンショットや画像ファイルをアップロードし、「この画像に書かれている文字をすべて書き起こしてください」や「この表をCSV形式に変換してください」と指示するだけです。
従来のOCRソフトとの違いは、単に文字を読み取るだけでなく、内容を理解して整形してくれる点です。
例えば、「このレシートから商品名と金額だけを抽出して表にまとめて」といった指示や、「手書きで読みにくい部分を文脈から推測して補完して」といった高度なリクエストにも応えてくれます。
特にGPT-5は、推論能力が強化されているため、崩れた文字や欠損している情報の補完において、人間並みかそれ以上のパフォーマンスを発揮することがあります。
枚数が少ない場合や、読み取り後に要約や翻訳を行いたい場合には、最も手軽で多機能なツールと言えます。
Gemini 1.5などのマルチモーダルAIが、どのように膨大なトークンから情報を理解しているかについては、こちらの論文が参考になります。 https://arxiv.org/html/2403.05530v2
FreeOCR.AI
FreeOCR.AIは、その名の通り無料で利用できるWebベースのOCRサービスです。
登録不要で、ブラウザ上にPDFや画像をドラッグ&ドロップするだけで、すぐにテキスト抽出が行われます。
TesseractというオープンソースのOCRエンジンを採用しており、シンプルながらも実用的な精度を持っています。
このツールの特徴は、余計な機能がなく、とにかくシンプルであることです。
複雑なレイアウト解析や手書き文字認識には向きませんが、標準的な活字文書であれば十分な結果が得られます。
出力結果はテキストとしてコピーできるほか、WordやExcel形式でのダウンロードも可能です。
ただし、無料のWebサービスであるため、機密性の高い文書をアップロードすることにはセキュリティ上のリスクが伴います。
個人情報の含まれない、公開情報のPDFをサクッとテキスト化したい場合などに適しています。
また、一度に処理できるファイルサイズやページ数に制限があるため、大量のドキュメント処理には向きません。
i2OCR
i2OCRも、登録不要で使えるオンラインの無料OCRツールです。
このサービスの特徴は、対応言語が非常に豊富であることです。
日本語や英語だけでなく、中国語、アラビア語、ヒンディー語など、100以上の言語に対応しており、多言語のドキュメントを扱う際に重宝します。
また、PDFだけでなく、JPG、PNG、TIFFなど多様な画像フォーマットに対応している点も便利です。
使い方は、言語を選択し、ファイルをアップロードして「Extract Text」ボタンを押すだけです。
抽出されたテキストは、Googleドキュメントに直接転送したり、翻訳ツールにかけたりすることができます。
i2OCRは、カラム(段組み)の認識にはあまり強くありませんが、プレーンテキストとしての抽出能力は安定しています。
海外の文献や、マイナーな言語で書かれた説明書などを翻訳するためにテキスト化したいといったシーンで活躍するツールです。
こちらもクラウド上のサービスであるため、プライバシーに関わる文書の取り扱いには注意が必要です。
Free Online OCR
Free Online OCRは、Webブラウザで完結するOCRコンバーターの中で、比較的古くからある定番のサービスです。
PDFをWord(.doc)、Excel(.xls)、テキスト(.txt)に変換することに特化しており、元のレイアウトをある程度維持したまま変換してくれるのが特徴です。
特に、シンプルな表組みであれば、Excelへの変換精度もそこそこ期待できます。
会員登録なしで利用できる「ゲストモード」では、1時間あたりに変換できるファイル数に制限(例えば15ファイルまでなど)がありますが、一般的な利用頻度であれば十分でしょう。
サイトのインターフェースは英語ですが、操作は直感的で迷うことはありません。
日本語の認識精度に関しては、Googleドライブや有料ソフトに比べるとやや劣る場合がありますが、インストール不要で手早くOfficeファイルに変換したいというニーズにはマッチします。
「PDFでもらった資料をWordで編集したいけれど、手元に有料ソフトがない」という緊急時の避難先としてブックマークしておくと便利です。
User Local 手書きOCR
User Local(ユーザーローカル)が提供する「手書きOCR」は、ブラウザ上で無料で試せるAI-OCRのデモサービスです。
ディープラーニングを活用したAIが、手書きの文字を高精度でテキスト化します。
ユーザー登録なども不要で、画像をアップロードするだけですぐに認識結果が表示されます。
このツールの面白い点は、認識結果に対してAIがどれくらい自信を持っているか(確信度)が表示されることや、認識した文字の位置が画像上で矩形表示されることです。
これにより、AIがどこをどう読み取ったのかを視覚的に確認できます。
あくまでデモツール的な位置づけであるため、大量のファイルを一括処理したり、業務システムに組み込んだりすることはできませんが、国産AIの手書き認識精度を体験するには最適です。
手書きのメモやホワイトボードの文字を、とりあえずテキストとして取り出したい時にサッと使える便利なツールです。
その他Webブラウザで完結する無料ツール
上記以外にも、Webブラウザ上で無料で使えるOCRツールは数多く存在します。
例えば、「Smallpdf」や「iLovePDF」といったPDF編集サイトにも、OCR機能が含まれています。
これらのサイトは、PDFの結合・分割・圧縮などの機能と合わせてOCRを利用できるため、PDF編集作業の一環としてテキスト化を行いたい場合に非常に便利です。
また、「OnlineOCR.net」なども有名で、こちらは出力フォーマットの多様性が売りです。
これらの無料Webツールの多くは、無料プランでは「1日〇ファイルまで」といった制限や、「OCR処理は有料プランのみ」といった制限を設けている場合があります。
しかし、たまにしか使わないユーザーにとっては、ソフトをインストールする手間が省けるというメリットが勝ります。
選ぶ際の基準としては、日本語の対応有無、広告の多さ、そしてプライバシーポリシー(アップロードしたデータが一定時間後に削除されるかなど)を確認するとよいでしょう。
複数のツールを試してみて、自分の持っているPDFと相性の良いものを見つけるのがコツです。
業務効率化に特化した高精度な有料AI-OCRソフト・ツール
企業の経理部門や自治体、教育機関など、大量の紙書類を日常的に処理する必要がある場合は、無料ツールではなく、業務用の有料AI-OCRツールの導入が推奨されます。
有料ツールは、単に文字認識精度が高いだけでなく、RPA(ロボットによる業務自動化)との連携や、強固なセキュリティ、使いやすい補正画面など、業務プロセス全体を効率化するための機能が充実しています。
- 有料ツールのメリット
- 手書き文字の認識率が圧倒的に高い
- 帳票の仕分けやデータ入力を自動化できる
- 学習機能により使えば使うほど賢くなる
- サポート体制やセキュリティが万全
ここでは、日本国内で多くの導入実績を持つ、信頼できる有料AI-OCRソフト・ツールを11選ご紹介します。
Adobe Acrobat Pro
PDFの本家本元であるAdobeが提供する「Acrobat Pro」は、世界で最も標準的なPDF編集・作成ソフトであり、強力なOCR機能を備えています。
スキャンされたPDFを開くと自動的にテキスト認識が走り、透明テキスト付きPDFとして保存したり、テキストや画像を直接編集したりすることが可能です。
また、Word、Excel、PowerPointへの書き出し精度も非常に高く、元のレイアウトを崩さずに再利用可能な形式に変換します。
Acrobat Proの強みは、その安定性と信頼性です。
AIを活用した文字認識技術(Adobe Senseiなど)により、フォントの認識や画像の補正も自動で行われます。
特定の業務に特化したAI-OCRではありませんが、汎用的なビジネスツールとして、どのPCにも入れておくべき基本ソフトと言えます。
Adobe Creative Cloudのプランに含まれていることも多いため、すでに契約している場合は追加コストなしで利用できる点も魅力です。
DX Suite(ディーエックス スイート)
AI inside株式会社が提供する「DX Suite」は、日本国内のAI-OCR市場でトップクラスのシェアを誇るサービスです。
最大の特徴は、手書き文字認識の圧倒的な精度です。
「Intelligent OCR」というエンジンを搭載しており、乱筆や訂正印、はみ出した文字なども、人間が読めるレベルであればほぼ正確に認識します。
また、帳票のフォーマットが異なっていても、AIが自動で読み取り箇所を特定する「Elastic Sorter」という機能があり、種類の異なる書類をまとめてスキャンしても、自動で仕分け・データ化を行ってくれます。
RPAとの連携実績も豊富で、紙のデータ化からシステムへの入力までを完全自動化する「ハイパーオートメーション」を実現するための基盤ツールとして、多くの金融機関や自治体で採用されています。
直感的なUI(ユーザーインターフェース)で、専門知識がなくても設定・運用ができる点も高く評価されています。
DX Suiteのクラウドセキュリティ認証(ISO/IEC 27017)取得に関する情報はこちらです。セキュリティ要件を確認したい場合に役立ちます。 https://inside.ai/news/2021/03/10/cloud-security-certification
SmartRead(スマートリード)
株式会社Cogent Labs(コージェントラボ)が提供する「SmartRead」は、独自開発のAIエンジン「Tegaki」をベースにした次世代のIDP(Intelligent Document Processing)サービスです。
2025年リリースの「SmartRead PLUS+」など、人の目による補正まで含めたトータルサービスも展開しており、文書の種類の自動分類や、必要な情報の抽出設定が非常に簡単であることも強みです。
定型帳票だけでなく、請求書や領収書などの「非定型帳票」や、図面、専門文書など、あらゆるドキュメントに対応可能です。
特に、事前定義なしで項目を抽出する機能が優れており、レイアウトがバラバラな請求書からでも、「日付」「金額」「取引先」などをピンポイントで抜き出すことができます。
確認・修正作業を行う画面も見やすく設計されており、確信度が低い文字だけを効率的にチェックできるため、担当者の作業負担を最小限に抑えられます。
AI JIMY Paperbot
「AI JIMY Paperbot(AIジミー ペーパーボット)」は、シー・システム株式会社が提供する、中小企業でも導入しやすい価格帯と使いやすさを重視したAI-OCRソリューションです。
AI-OCR機能とRPA機能がセットになっているようなイメージで、スキャンしたデータを読み取り、CSV化し、さらに業務システムへ転送するところまでをワンストップで支援します。
このツールの特徴は、FAX受注業務などの効率化に特化している点です。
手書きのFAX注文書をAIが読み取り、販売管理システムへの入力用データを作成する、といったフローを簡単に構築できます。
導入コストが比較的高額になりがちなAI-OCR製品の中で、月額固定のリーズナブルなプランや、従量課金のプランなど、利用規模に合わせた柔軟な料金体系が用意されているのも魅力です。
RECERQA Scan
「RECERQA Scan(リサーカスキャン)」は、株式会社三菱総合研究所やアイ・エス・ビーなどが関わる、高精度なAI文字認識サービスです。
特に、金融業界などで求められる高いセキュリティ基準と、正確なデータ化能力を兼ね備えています。
日本語の難読漢字や、住所・氏名などの手書き情報の読み取りにおいて高いパフォーマンスを発揮します。
特徴的なのは、AIによる自動認識だけでなく、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)と組み合わせたサービス展開も視野に入れている点です。
AIで読み取れない部分や、100%の精度が必要な重要書類については、オペレーターによる補正入力を組み合わせることで、完全なデータ化を実現するソリューションとしても利用されます。
ReiWorQ AI-OCR
「ReiWorQ(レイワーク)AI-OCR」は、スターティアレイズ株式会社が提供するRPAツール「ReiWorQ」と連携するAI-OCRです。
手書き、活字、FAX、写真など、あらゆる紙帳票をデジタルデータ化します。
「誰でも簡単に使える」ことをコンセプトにしており、複雑な設定なしで、ドラッグ&ドロップで読み取り箇所を指定するだけで利用開始できます。
また、親和性の高いRPAツールが同シリーズで提供されているため、OCRで読み取ったデータをExcelに転記したり、会計ソフトに入力したりする自動化ロボットを、ノンプログラミングで作成できるのが強みです。
「AI-OCRを入れたいけれど、その後のデータ活用まで手が回らない」という企業にとって、トータルでの業務効率化を実現しやすいツールです。
スマートOCR
株式会社アイリックコーポレーションが提供する「スマートOCR」は、特に「非定型帳票」の読み取りに強みを持つAI-OCRです。
請求書やレシートのように、発行元によってレイアウトが全く異なる書類でも、AIが項目(日付、金額など)の意味を理解してデータを抽出します。
座標指定(どの位置を読み取るか)をする必要がないため、フォーマットが増えるたびに設定を行う手間が省けます。
また、スマートフォンのカメラで撮影した画像の補正機能も強力で、歪み補正や照明ムラの除去を行った上で文字認識を行います。
経費精算システムと連携し、スマホで領収書を撮るだけで申請が完了する仕組みなどを構築する際に威力を発揮します。
クラウド型だけでなく、セキュリティ要件の厳しい企業向けにオンプレミス(自社サーバー)型や閉域網での提供も行っています。
AIRead
アライズイノベーション株式会社の「AIRead(エーアイリード)」は、手書き・活字の読み取りに対応したAI-OCRです。
最大の特徴は、オンプレミス環境やLGWAN(総合行政ネットワーク)環境でも利用できるという点です。
クラウドサービスを利用できない自治体や金融機関、医療機関などにおいて、外部にデータを出さずにAI-OCRを利用したいというニーズに応えます。
もちろんクラウド版も提供されており、利用形態を用途に合わせて選べます。
また、読み取り定義(テンプレート)の作成支援機能や、手書き文字の学習機能など、運用をサポートする機能も充実しています。
コストパフォーマンスにも優れており、スモールスタートから大規模運用まで幅広く対応できる柔軟性があります。
DEEPREAD
株式会社EduLab(エデュラボ)が提供する「DEEPREAD」は、教育現場やテスト採点業務などで培われた技術をベースにしたAI-OCRです。
手書き文字の認識に定評があり、特に枠に収まっていない文字や、行からはみ出した記述などの認識に強みを持っています。
金融業界や医療業界での導入実績も多く、独自の深層学習モデルにより、業界特有の専門用語やフォーマットに合わせたチューニングが可能です。
APIでの提供も行っているため、自社の既存システムやアプリに高精度な手書き認識機能を組み込みたいという開発者・企業にとっても有力な選択肢となります。
CaptureBrain
キヤノンITソリューションズの「CaptureBrain(キャプチャーブレイン)」は、キヤノン独自の画像処理技術とAI技術を融合させたクラウド型OCRソリューションです。
スキャナーメーカーとしての知見が活かされており、読み取り前の画像補正処理(ノイズ除去、傾き補正など)が非常に高品質です。
これにより、OCRエンジンの認識率を最大限に引き出します。
また、クラウド型のサービスでありながら、学習済みAIモデルを利用するため、ユーザー側での事前学習の手間が不要です。
非定型帳票への対応や、確認・修正作業を効率化するWebインターフェースなど、実務担当者の使い勝手を考慮した設計になっています。
キヤノン製の複合機との連携もスムーズで、紙のスキャンからデータ保存までをシームレスに行えます。
Autoジョブ名人
ユーザックシステム株式会社の「Autoジョブ名人」は、正確にはRPAツールですが、オプションや連携機能として強力なOCR機能を活用できます。
PC上のあらゆる操作を自動化するツールであり、AI-OCRで読み取ったデータを基幹システムへ入力する作業を自動化するのを得意としています。
特に、OCR変換後のデータチェックや加工(例えば、全角・半角の統一や、日付フォーマットの変換など)をRPA側のシナリオで柔軟に処理できるため、実務で使えるきれいなデータを作成することができます。
「AI-OCRを導入したけれど、結局データ修正に時間がかかっている」という課題を持つ現場において、その後のプロセスまで面倒を見てくれる頼もしいツールです。
AIを活用してPDFをテキスト化する具体的な手順とコツ
ツールを選んだら、実際にPDFをテキスト化してみましょう。
ここでは、代表的な3つのパターンにおける具体的な操作手順と、精度を高めるためのちょっとしたコツを紹介します。
Googleドライブを使って無料でテキスト抽出する手順
最も手軽でお金のかからない方法です。
- GoogleドライブにアップロードPDFファイル(または画像ファイル)をGoogleドライブのマイドライブにドラッグ&ドロップします。
- Googleドキュメントで開くアップロードしたファイルを右クリックし、「アプリで開く」>「Google ドキュメント」を選択します。
- 変換完了しばらく待つと、画像の下にテキスト化された文章が表示されます。
コツ: 元の画像が粗い場合は、スマホのスキャンアプリなどでコントラストを上げてからアップロードすると認識率が上がります。また、縦書きの文章は認識精度が落ちる傾向にあるため、横書きの文書に最適です。
Adobe Acrobatで透明テキスト付きPDFを作成する手順
PDFの見た目はそのままに、検索可能なテキスト情報を埋め込む方法です。
- PDFを開くAdobe Acrobat Proで対象のPDFファイルを開きます。
- スキャンとOCRツールを選択「ツール」タブから「スキャンとOCR」をクリックします。
- テキスト認識を実行「テキスト認識」>「このファイル内」を選択し、言語(日本語など)を設定して「テキスト認識」ボタンをクリックします。
- 保存処理が終わったらファイルを保存します。これで、Ctrl+Fなどで文字検索ができるようになります。
コツ: 「設定」から「画像のダウンサンプリング」をオフ(最低画質にしない)にすることで、文字の輪郭が保たれ、認識精度が維持されます。また、認識後に「認識されたテキストを修正」機能を使うと、疑わしい箇所をハイライト表示してくれ、手動で修正できます。
ChatGPTやGeminiに画像を読み込ませて文字起こしさせる方法
部分的な抽出や、内容の要約も同時に行いたい場合に便利な最新の方法です。
- チャット画面を開くChatGPT(GPT-4o/GPT-5等)やGoogle Geminiのチャット画面を開きます。
- 画像を添付クリップマークからPDFや画像をアップロードします。
- プロンプトを入力「この画像に書かれている文章をすべてテキストにしてください」や「この表をマークダウン形式で出力して」と指示を送ります。
- 結果をコピーAIが出力したテキストをコピーして利用します。
コツ: * 役割を与える: 「あなたはプロのタイピストです。一字一句間違わずに書き起こしてください」と指示すると精度が上がることがあります。
- 補正を依頼する: 「誤字脱字がある場合は、文脈から判断して修正してください」と付け加えると、AIが自動でクリーニングしてくれます。ただし、原文ママが必要な場合はその旨を伝えましょう。
AI-OCR導入前に知っておくべき注意点と精度の限界
AI-OCRは魔法の杖のように便利ですが、万能ではありません。
導入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、事前に理解しておくべきリスクと限界があります。
100%の精度ではないため目視チェックは必須
最新のGPT-5や高性能な有料ツールであっても、文字認識精度が100%になることはありません。
99%の精度だとしても、1,000文字あれば10文字は間違っている計算になります。
特に、数字の「1」と「7」、「3」と「8」の間違いや、金額の桁間違いは、ビジネスにおいて致命的なミスにつながります。
したがって、AI-OCRの結果をそのまま鵜呑みにせず、必ず人間による目視チェック(ベリリファイ)の工程を業務フローに組み込む必要があります。
AIはあくまで「入力補助」であり、最終責任は人間にあるという意識を持つことが大切です。
OCRにおけるハルシネーション(幻覚)を低減させるための不確実性認識に関する研究も進められています。AIのリスク管理に関心がある方は合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/html/2506.20168v2
機密情報を含むPDFを無料クラウドツールに上げるリスク
無料のWebサービスや、パブリックなAIチャットボットを利用する場合、アップロードしたデータがAIの学習データとして利用されたり、サーバー上に一時的に保存されたりする可能性があります。
個人情報(マイナンバー、氏名、住所)や、企業の機密情報(未発表の決算データ、契約書など)が含まれるPDFを、安易に無料ツールに通すことは情報漏洩のリスクがあります。
業務で利用する場合は、セキュリティポリシーを確認し、「学習データに利用しない」と明記されている有料プラン(ChatGPT EnterpriseやAPI利用など)や、オンプレミス型のツールを選ぶようにしましょう。
生成AIの企業利用リスクと具体的な対策については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
複雑なレイアウトや網掛けがある場合の認識エラー対策
AIは文字を読むのは得意ですが、デザイン的な要素にはまだ弱い部分があります。
例えば、文字の上に網掛け(ハーフトーン)がかかっている箇所、透かし文字が入っている背景、極端に装飾されたフォントなどは、認識エラーの温床となります。
また、複雑に入り組んだ表や、セル結合が多用されたExcel帳票などは、構造を正しく理解できず、データがずれてしまうことがあります。
対策としては、スキャン時に「文字くっきりモード」などで撮影する、またはOCRにかける前に画像編集ソフトでコントラストを調整し、文字を二値化(白黒はっきりさせる)するなどの前処理を行うことが有効です。
PDFのAI-OCR化に関するよくある質問
最後に、PDFのOCR化に関してよく寄せられる質問にお答えします。
スマホで撮影した書類もOCRできますか?
はい、可能です。
むしろ最近のAI-OCRは、スキャナー画像よりもスマホ画像の方が多いことを前提に開発されています。 Microsoft 365アプリやGoogleドライブアプリ、またはスマートOCRのようなツールを使えば、斜めに撮影された書類でも自動で台形補正を行い、正面から見たような画像に変換してから文字認識を行ってくれます。
ただし、手ブレやピンボケはAIでも修正しきれないため、撮影時は明るい場所で、カメラを固定して撮影するのがコツです。
日本語と英語が混ざった文章でも認識されますか?
はい、主要なAI-OCRツールのほとんどが多言語認識に対応しています。
特にGoogle系のツールやDeepLなどが搭載しているエンジン、そしてGPT-5などのLLMは、文脈から言語を自動判定して切り替える能力に長けています。
「AI」や「OCR」といった英単語が日本語の文章の中に混ざっていても、問題なく認識します。
ただし、ツールによっては「主な言語」を設定する必要がある場合があるので、設定画面で「日本語+英語」などを選択しておくと安心です。
縦書きの書籍や古い文献の読み取り精度はどうですか?
縦書きや古文書(くずし字など)は、海外製のツールでは苦手とする分野です。
Googleドライブなどは縦書きを横書きとして認識してしまうことがよくあります。
縦書きの書籍を読み取りたい場合は、CLOVA OCR(LINE WORKS)や、読書バリアフリー法に対応した国産のOCRソフト、または国立国会図書館などが開発に関わっているような専門的なツール(「みらいOCR」や古文書解読AIなど)を利用することをおすすめします。
これらのツールは、縦書き特有の読み順や、旧字体・異体字の学習データを豊富に持っているため、高い精度でテキスト化が可能です。
「データ入力」が企業の成長を止める?非構造化データがもたらす隠れた損失
企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)が進まない最大の要因をご存知でしょうか。それは、システムで扱いにくい「非構造化データ」の存在です。実は、企業内に存在するデータの80%以上は、PDF、画像、メール、ドキュメントなどの非構造化データであると言われています。これらのデータを活用できずに放置することは、単なる機会損失にとどまらず、企業の成長そのものを阻害する深刻な要因となり得ます。
国際的な市場調査会社であるIDCの調査によると、ナレッジワーカーは業務時間の約30%を情報の検索や取得に費やしており、その多くの時間が、整理されていない非構造化データの中から必要な情報を探し出すことに充てられています。PDF化された資料の中身が検索できない状態であるということは、実質的にその情報が存在しないも同然の状態を作り出しているのです。
また、手作業によるデータ入力(パンチ入力)は、従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。単純作業の反復は、創造的な思考を妨げ、従業員エンゲージメント(仕事への熱意)を低下させる要因の一つとして指摘されています。マッキンゼー・グローバル・インスティテュートの研究では、現在の技術で業務の約50%が自動化可能であり、特にデータ収集や処理業務はその割合が高いと報告されています。
つまり、PDFのOCR化やデータ抽出をAIに任せることは、単なる「作業時間の短縮」ではありません。埋もれていた8割のデータ資産を掘り起こし、従業員を単純作業から解放して、より付加価値の高い業務にシフトさせるための経営戦略なのです。AIによる非構造化データの処理は、これからの企業が競争力を維持するために避けては通れない道と言えるでしょう。
引用元:
IDC “The Untapped Value of Unstructured Data”
McKinsey Global Institute “A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity” (2017)
まとめ
本記事では、PDFのデータ化におけるAI-OCRツールの有用性や具体的な選び方について解説してきました。
業務効率化のためにAIツールの導入が急務であることは間違いありませんが、いざ導入しようとすると「どのツールが自社に合っているかわからない」「複数のツールを使い分けるのが面倒」「セキュリティが心配」といった新たな課題に直面することも事実です。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは、AI-OCR機能を含む200種類以上の実用的なAIタスクを、アプリ形式で直感的に利用できる生成AI活用プラットフォームです。
今回の記事で紹介したようなPDFからのテキスト抽出はもちろん、抽出したデータを使ったレポートの自動生成、要約、翻訳、メール作成など、業務に必要なあらゆるAI機能がこれ一つで完結します。
特定のOCRソフトを単体で契約するよりも、業務フロー全体をカバーできるTaskhubの方が、結果的にコストパフォーマンスが高くなるケースも多くあります。
また、企業利用で最も懸念されるセキュリティ面においても、Azure OpenAI Serviceを基盤とした堅牢な環境を提供しており、入力したデータがAIの学習に利用されることはありません。
さらに、導入時には専任のAIコンサルタントが業務課題のヒアリングからサポートするため、AIに詳しくない企業でも最短で成果を出すことが可能です。
「PDFのデータ化」という目の前の課題を解決するだけでなく、その先の業務自動化まで見据えたTaskhubで、御社の生産性を劇的に向上させませんか。
まずは、Taskhubの豊富な機能と具体的な活用事例をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードして、その実力をお確かめください。