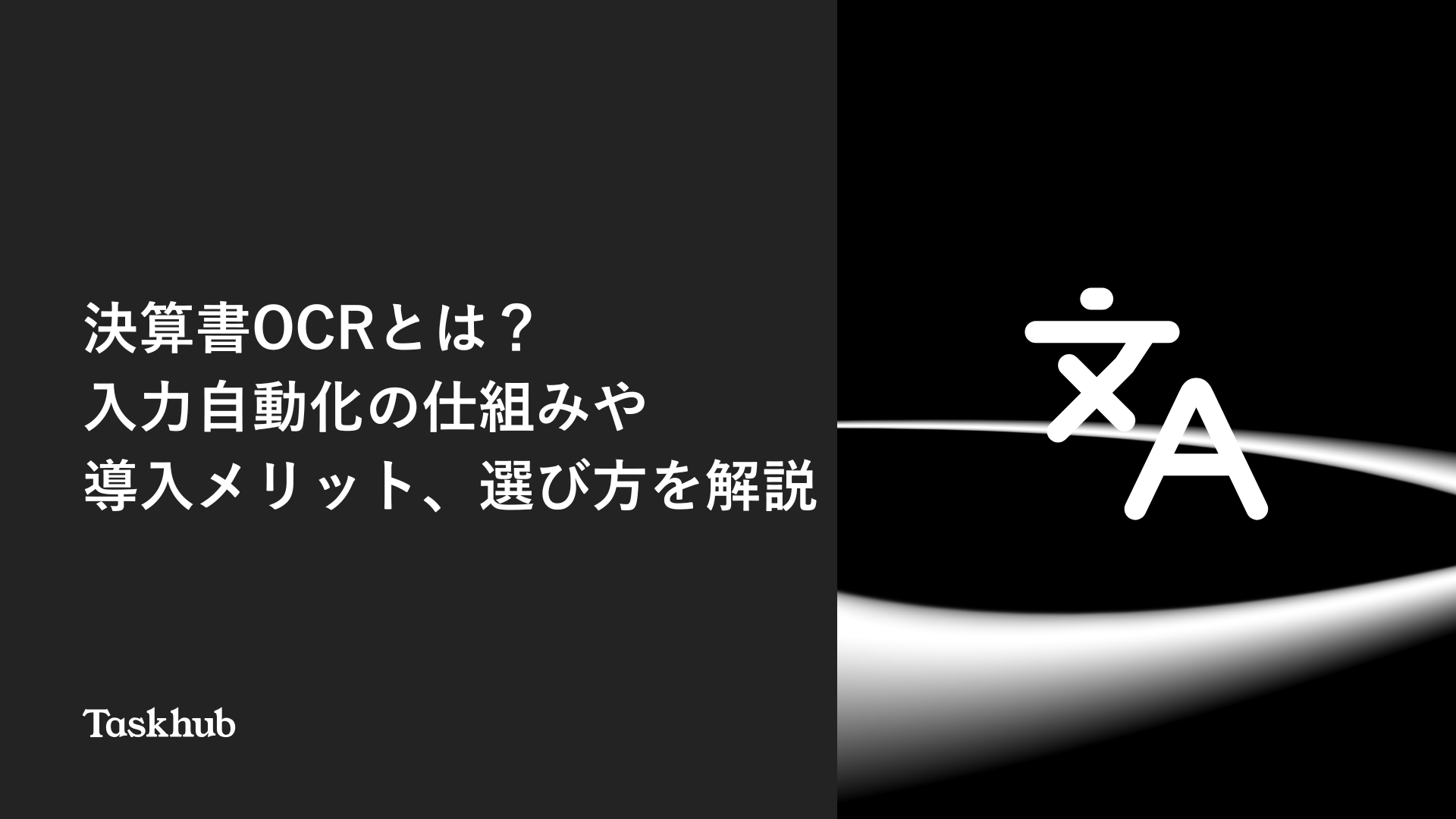「大量の決算書を手入力する作業に、毎月多くの時間を奪われている」
「入力ミスが許されないプレッシャーで、精神的にも疲弊してしまう…」
経理担当者や会計事務所、金融機関にお勤めの方で、このような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか?
決算書は企業ごとにフォーマットが異なり、独特の勘定科目が使われることも多いため、従来のOCR技術では読み取りが難しい領域でした。
しかし、生成AI(LLM)をはじめとするAI技術の進化により、現在では高精度に決算書をデータ化できる「決算書OCR」が登場し、業務効率を劇的に改善しています。
こちらは国内のAIシステム市場規模の予測についてまとめたデータです。AI技術の浸透度合いを知る参考になります。 https://aismiley.co.jp/ai_news/idc-survay-aimarketsize-japan/
本記事では、決算書OCRの仕組みや導入する具体的なメリット、失敗しないための選び方のポイントについて解説しました。
企業のDX支援を行ってきた弊社が、現場で本当に役立つ視点だけを厳選してご紹介します。
こちらはDX導入の手順やメリット、成功事例について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
業務負担を減らし、より付加価値の高い業務に時間を割くためのヒントが見つかるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。
決算書OCRとは?一般的なOCRとの違い
決算書OCRとは、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表をスキャンし、AIを活用してデジタルデータ(CSVやExcelなど)に変換する技術のことです。
一般的なOCR(光学文字認識)が「書かれている文字をそのままテキストにする」のに対し、決算書OCRは「その文字が何を意味する数字なのか」までを理解します。
ここでは、なぜ従来のOCRでは難しかった決算書の読み取りが可能になったのか、その仕組みについて3つのポイントで解説します。
こちらはLLM(大規模言語モデル)の概要やChatGPTとの違いについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。
AI技術(特に生成AI)を活用した構造解析、勘定科目の意味理解、そして推論・学習機能による精度向上について詳しく見ていきましょう。
財務データ特有の「非定型フォーマット」に対応できる仕組み
決算書OCRが従来のOCRと最も異なる点は、定まった位置に情報がない「非定型フォーマット」に対応できることです。
従来のOCRは、あらかじめ「この座標に日付がある」「この座標に金額がある」と定義する「帳票定義型」が主流でした。
しかし、決算書は作成する会計ソフトや税理士によってレイアウトが千差万別です。
行数も異なれば、列の幅も違い、注記が入る場所もバラバラであるため、座標を指定する方法では対応しきれませんでした。
決算書OCRでは、AIが人間のように文書全体の構造を視覚的に把握します。
表の罫線だけでなく、文字の配置やインデント、空行の意味などを解析することで、どこからどこまでが「資産の部」なのか、どの数字が「合計」なのかを自動で判断します。
こちらは表構造認識(TSR)に関する最新の研究技術について解説された論文情報です。AIがどのように複雑な表を認識するか、技術的な背景に関心がある方はご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/385447022_TSRDet_A_Table_Structure_Recognition_Method_Based_on_Row-Column_Detection
これにより、事前にフォーマットごとの設定を行うことなく、スキャンするだけで即座に表構造を認識し、適切な項目に値を割り当てることが可能になりました。
この「座標に依存しない読み取り」こそが、多様な決算書を扱う現場で実用化された最大の理由です。
ただ読み取るだけでなく「勘定科目」を識別・データ化する
決算書OCRのもう一つの大きな特徴は、読み取った文字列が「勘定科目」であることを認識し、必要に応じて正規化してデータ化する機能です。
一般的なOCRであれば、「現金」という文字と「1,000」という数字をただ読み取るだけですが、決算書OCRはこれらがセットであることを理解します。
決算書では、同じ意味を持つ項目でも企業によって表記が異なるケースが多々あります。
例えば、「現預金」「現金及び預金」「現金・預金」はすべて同じ勘定科目として扱われるべきですが、単純な文字認識では別の項目として出力されてしまいます。
決算書OCRには、あらかじめ膨大な財務データの辞書やパターンが学習されています。
こちらは金融分野に特化した自然言語処理モデル「FinBERT」に関する論文です。AIがどのように金融用語を理解しているかの参考になります。 https://arxiv.org/pdf/2211.08842
そのため、表記のゆらぎがあっても、システム側で「これは『現金及び預金』のことである」と自動的に判断し、会計システムに取り込みやすい統一された名称に変換して出力することが可能です。
さらに、貸借がバランスしているかどうかの検算機能を持っているものも多く、読み取った数字の合計が合わない場合にアラートを出すなど、財務データ特有のロジックに基づいた処理が行われます。
このように、単なる文字データではなく「意味のある財務データ」として出力できる点が、決算書OCRの強みです。
生成AI(LLM)の推論・学習機能で読み取り精度が向上する理由
決算書OCRの精度を支えているのは、ディープラーニングや大規模言語モデル(LLM)の高度な推論機能です。
最新のAIは大量の決算書パターンを学習済みであり、前後の文脈から人間のように意味を理解して補正を行います。
初期のOCRでは、数字の「0」と「6」や「8」の誤読、あるいは背景の網掛けや印鑑とかぶった文字の認識ミスが頻発していました。
しかし、最新のAIモデルを搭載した決算書OCRは、前後の文脈や桁数の整合性などから推論を行うことで、画質の悪いデータでも高い精度で数値を復元します。
こちらはGPT-4を用いた金融予測の研究事例です。LLMが数値データの文脈をどう処理するかについての知見が深まります。 https://www.adventuresincre.com/gpt-4-financial-prediction-study/
特筆すべきは、ユーザーが修正したデータを再学習することで、使えば使うほど精度が向上していく点です。
例えば、ある特定の業界でよく使われる特殊な勘定科目や、独特なフォントを使用している決算書であっても、一度修正を行えばAIがそのパターンを記憶します。
次回以降は、学習した内容に基づいて正しく読み取ることができるようになるため、人間側での確認や修正の手間は徐々に減少していきます。
このように、導入後も成長し続けるシステムであることが、長期的な業務効率化を実現する上で重要な要素となっています。
決算書OCRを導入する具体的なメリット
決算書OCRを導入することで、現場の業務フローはどのように変わるのでしょうか。
単に「入力が楽になる」というだけでなく、組織全体としての生産性向上やリスク管理の観点からも大きな効果が期待できます。
こちらは生成AIの企業活用について、メリットから導入の注意点まで解説した記事です。 合わせてご覧ください。
ここでは、決算書OCRの導入によって得られる具体的なメリットを3つの側面に分けて解説します。
作業時間の短縮、品質の向上、そしてシステム連携によるスムーズなデータ活用について、それぞれの効果を見ていきましょう。
膨大な手入力作業の削減と業務スピードの向上
決算書OCR導入の最も分かりやすいメリットは、手入力にかかる工数の劇的な削減です。
1社の決算書を入力するのに、熟練した担当者でも数十分、場合によっては1時間以上かかることは珍しくありません。
特に繁忙期には、数百社分の決算書入力が集中することもあり、残業や休日出勤で対応せざるを得ない現場も多いでしょう。
OCRを活用すれば、スキャンからデータ化まで数分、確認作業を含めても大幅な時間短縮が可能になります。
例えば、数十ページに及ぶ勘定科目内訳書であっても、AIは瞬時にすべての行をテキスト化します。
人間が行うタイピングとは比較にならないスピードで処理が進むため、入力業務そのものがボトルネックになることを防げます。
こちらはAI-OCR導入による業務削減効果について統計的にまとめた記事です。具体的な削減時間の目安として参考にしてください。 https://www.keihi.com/column/57980/
これにより、決算書を受け取ってから審査や分析を開始するまでのリードタイムが大幅に短縮されます。
金融機関であれば融資審査の回答スピード向上、会計事務所であれば月次監査の早期化など、顧客へのサービス品質向上に直結する成果が得られるでしょう。
単純作業をAIに任せることで、人間はより高度な判断や分析業務に集中できるようになります。
転記ミスの防止と目視チェック工数の大幅削減
手入力による業務には、どうしてもヒューマンエラーのリスクがつきまといます。
数字の打ち間違い、桁数のズレ、行の読み飛ばしなどは、どんなに注意していても完全にゼロにすることは難しいものです。
特に決算書のような重要書類においては、たった一つの入力ミスが誤った経営判断や審査結果につながる可能性があるため、入力後のダブルチェックやトリプルチェックが欠かせません。
この「確認作業」にかかる精神的負担と時間コストは計り知れないものがあります。
決算書OCRは、画像データから直接数値を抽出するため、タイピングミスという概念が存在しません。
もちろん、文字認識の誤りが発生する可能性はありますが、多くのツールには貸借一致の自動検算機能や、元画像との対比表示機能が備わっています。
「画像上の数字」と「認識した数字」を並べて表示し、疑わしい箇所だけをハイライトしてくれるため、人間はすべての数字を目視で追う必要がなくなります。
確認作業は「間違いがないか一から探す作業」から「AIの指摘を確認する作業」へと変わり、チェックにかかる時間は大幅に削減されるとともに、心理的な負担も軽減されるでしょう。
紙・PDFデータのCSV変換による会計システム連携
決算書は紙で受領することもあれば、PDFファイルで送られてくることもあります。
これらを自社の会計システムや分析ツールに取り込むためには、従来であれば一度Excelなどに手入力し、CSV形式に加工してインポートするという手間が必要でした。
この過程で、勘定科目の名称を自社システムのマスターデータに合わせて書き換えるなどの「変換作業」も発生します。
このデータ加工の手間が、システム連携の大きな障壁となっていました。
決算書OCRの多くは、読み取ったデータを主要な会計ソフトや税務申告ソフト、または汎用的なCSV形式で出力する機能を標準で備えています。
読み取りと同時に勘定科目のコード変換を行ったり、借方・貸方のフォーマットを整えたりすることが可能です。
これにより、紙の決算書を複合機でスキャンするだけで、そのまま会計システムへインポートできる状態のデータが生成されます。
データ入力からシステム登録までのプロセスがシームレスに繋がることで、情報の鮮度を保ったまま活用できるようになり、経営分析や予実管理のサイクルを高速化することができます。
失敗しない決算書OCRの選び方・比較ポイント
市場には多くのAI-OCR製品が存在しますが、その全てが決算書の読み取りに適しているわけではありません。
汎用的なOCRでは専門用語に対応できなかったり、複雑な表組みを認識できなかったりすることがあるため、選定には慎重さが求められます。
自社の業務にフィットするツールを選ぶためには、いくつかの重要な比較ポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、導入後に後悔しないための5つの選定基準について詳しく解説します。
【認識精度】罫線なし・印字ズレ・低画質でも読み取れるか
決算書OCRを選ぶ上で最も基本的かつ重要なのが、文字認識の精度です。
特に決算書は、綺麗に印字されたものばかりではありません。
FAXで送られてきて文字が潰れているもの、コピーを繰り返して斜めに傾いているもの、さらには手書きの修正が入っているものなど、悪条件のデータも多く存在します。
また、罫線が省略されている表や、勘定科目と金額の間が極端に離れているレイアウトなど、読み取り難易度が高いフォーマットも珍しくありません。
選定時には、デモや無料トライアルを活用して、自社で実際に扱っている「状態の悪い決算書」を読み込ませてみることが不可欠です。
カタログスペック上の「認識率99%」という数字だけで判断するのではなく、実務レベルでどの程度使えるかを確認しましょう。
特に、マイナスの数字(▲や△、マイナス記号)や、桁区切りのカンマなどを正確に認識できるかは、財務データを扱う上で致命的な差となるため、重点的にチェックする必要があります。
【補正機能】表記のゆらぎや独自の勘定科目を自動で統一できるか
単に文字を正しく読み取れるだけでなく、それを「使えるデータ」に変換できるかどうかも重要なポイントです。
先述した通り、勘定科目の表記は企業によって千差万別です。
「売掛金」を「売掛」と書く企業もあれば、「工事未収入金」とする企業もあります。
優れた決算書OCRであれば、こうした表記のゆらぎを吸収し、自社で規定している勘定科目コードや名称に自動変換する機能を持っています。
この「データクレンジング」の精度が低いと、OCRで読み取った後に人間が手動で科目を修正する作業が発生し、導入効果が半減してしまいます。
辞書機能の充実度や、ユーザー側で変換ルールをカスタマイズできる機能があるかを確認しましょう。
また、読み取ったデータに対して、貸借バランスのチェックや、前年同期比での異常値検知など、会計的なロジックでの補正機能があるかどうかも、業務効率を大きく左右します。
【操作性】ITに詳しくない担当者でも直感的に修正・確認ができるか
どんなに高機能なツールであっても、現場の担当者が使いこなせなければ意味がありません。
決算書OCRは経理担当者や営業担当者が日常的に使用するものであるため、直感的な操作性(UI/UX)が求められます。
特に重要なのが、読み取り結果の確認と修正画面の使いやすさです。
AIが認識に自信がない箇所をアラートで知らせてくれるか、元の画像とテキストを見比べやすい配置になっているか、キーボード操作だけで修正が完結するか(マウスへの持ち替えが不要か)などは、作業効率に直結します。
ITリテラシーが高くないスタッフでも、マニュアルを読み込まずに操作できるようなシンプルな設計になっているかを確認しましょう。
導入時の教育コストを下げるためにも、実際の画面を触って「これなら使えそう」という感触を得ておくことが大切です。
【連携】自社で使用している会計ソフトやシステムに取り込めるか
決算書OCRの最終的なゴールは、読み取ったデータを基幹システムや会計ソフトに連携させることです。
そのため、導入を検討しているOCRが、自社で利用しているシステムとスムーズに連携できるかを確認する必要があります。
主要な会計ソフト(弥生会計、マネーフォワード、freee、勘定奉行など)であれば、API連携や専用のCSVフォーマット出力に対応している製品が多くあります。
API連携ができれば、ボタン一つでデータの転送が完了するため、ファイルを取り込んでインポートするという手間すら不要になります。
もし独自の基幹システムを使用している場合は、出力されるCSVファイルのレイアウトを自由にカスタマイズできる機能があるかが重要になります。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールと組み合わせて自動化をさらに進めたい場合は、RPAとの親和性についても確認しておくと良いでしょう。
【セキュリティ】機密性の高い財務データを安全に扱えるか
決算書には、企業の売上、利益、借入状況、取引先情報など、極めて機密性の高い情報が含まれています。
そのため、クラウド型の決算書OCRを利用する場合は、セキュリティ対策が万全であるかどうかが選定の絶対条件となります。
通信経路や保存データの暗号化はもちろんのこと、アクセスログの管理機能、IPアドレス制限、二要素認証などのセキュリティ機能が備わっているかを確認しましょう。
また、サービス提供事業者がISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やPマークなどの第三者認証を取得しているかも判断材料になります。
こちらは電子帳簿保存法に対応したJIIMA認証に関する解説記事です。ツールの法的適合性を確認する際の指標としてご覧ください。 https://www.smartocr.jp/ocr-lab/?p=1150
金融機関など、特に厳しいセキュリティ基準が求められる組織の場合は、生成AIモデル等の学習に自社データが利用されない設定(オプトアウト)が確実に行えるかも重要な確認事項です。
情報漏洩リスクを最小限に抑えつつ、便利に活用できる環境が整っているかを慎重に見極める必要があります。
決算書OCRの活用事例と導入効果
ここでは、実際に決算書OCRを導入した企業や組織が、どのような課題を抱え、どう解決したのかという事例をご紹介します。
金融機関と会計事務所という、決算書を大量に扱う2つの業種における導入効果を見ることで、自社での活用イメージをより具体的にしていただけるはずです。
金融機関:融資審査における決算書入力の自動化・ペーパーレス化
地方銀行や信用金庫などの金融機関では、融資先企業の決算書を財務分析システムに入力する業務が大きな負担となっていました。
1社あたり数十ページに及ぶ決算書を手作業で入力するため、審査開始までに数日を要することも珍しくありませんでした。
ある金融機関では、決算書OCRを導入し、スキャナで読み取ったデータを自動で財務システムに連携するフローを構築しました。
その結果、従来は1件あたり60分かかっていた入力作業が、確認作業を含めても15分程度に短縮され、約75%の工数削減を実現しました。
また、紙の決算書を保管する必要がなくなり、ペーパーレス化も進行しました。
支店から本部への書類郵送コストや紛失リスクも解消され、審査スピードが向上したことで、顧客への融資実行までの期間短縮にもつながっています。
こちらは建設設備業のユアテック社における請求書関連業務のデジタル化事例です。アナログな書類業務をどう効率化したかの実例として参考になります。 https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0806.html
営業担当者が事務作業から解放され、顧客との対話や提案活動に多くの時間を割けるようになったことも大きな成果です。
会計事務所・経理部門:入力業務の工数削減とコア業務への集中
多くの顧問先を持つ会計事務所では、確定申告時期などの繁忙期になると、預かった領収書や決算書の入力作業で事務所内が殺気立つのが常態化していました。
こちらはChatGPTの会計業務での活用事例や注意点について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
パートスタッフを大量に雇用して入力作業にあたらせていましたが、採用難や教育コストの問題も抱えていました。
決算書OCRと通帳OCRなどを組み合わせて導入した結果、記帳代行業務の自動化が一気に進みました。
AIが勘定科目を推論してくれるため、経験の浅いスタッフでも確認作業を行うだけで済むようになり、属人化の解消にも成功しています。
これにより、職員は単純入力作業から解放され、顧問先への経営アドバイスや税務相談といった、より付加価値の高い「コア業務」に集中できるようになりました。
結果として、同じ人員数でより多くの顧問先を担当できるようになり、事務所全体の収益性向上にも寄与しています。
また、残業時間が大幅に減ったことで、職員の定着率向上という副次的な効果も生まれています。
決算書OCR導入時のよくある質問(FAQ)
最後に、決算書OCRの導入を検討されている方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
導入前の不安解消にお役立てください。
手書きの文字やFAXで届いた決算書は読み取れますか?
はい、読み取り可能です。
近年のAI-OCR技術は飛躍的に向上しており、手書き文字であっても高い精度で認識できます。
特に数字に関しては、崩れた文字でも前後の文脈から高い確率で正解を導き出します。
FAXで届いたかすれた文字や、解像度の低い画像についても、ノイズ除去機能や画像補正機能を持つOCRエンジンであれば対応可能です。
ただし、人間が読んでも判読不能なレベルの汚れや潰れがある場合は、AIでも読み取れないことがあります。
トライアルなどで実際のFAX帳票を使ってテストしてみることをお勧めします。
導入にかかる初期費用やランニングコストの目安は?
費用体系はサービスによって異なりますが、一般的には「初期費用」+「月額基本料」+「読み取り枚数に応じた従量課金」という構成が多いです。
クラウド型(SaaS)の場合、初期費用は10万円〜30万円程度、月額費用は数万円〜という価格帯が一般的です。
読み取り枚数が少ない小規模向けプランであれば、月額数千円から始められるサービスもあります。
一方で、オンプレミス型や大規模なカスタマイズが必要な場合は、数百万円規模の投資になることもあります。
自社の処理枚数や必要な機能に合わせて、費用対効果の合うプランを選定しましょう。
どの程度の期間で運用を開始できますか?
クラウド型のサービスであれば、契約からアカウント発行まで数日〜1週間程度で利用を開始できます。
特別なサーバー構築などが不要なため、スキャナとインターネット環境があればすぐに始められるのがメリットです。
ただし、実際に業務フローに組み込むためには、勘定科目の変換設定や、現場スタッフへの操作トレーニングなどの準備期間が必要です。
スムーズな運用開始を目指すなら、設定やテスト運用の期間として2週間〜1ヶ月程度を見ておくと安心です。
ベンダーによっては導入支援サポートを提供している場合もあるので、それらを活用することで立ち上げ期間を短縮することも可能です。
【警告】「手入力」への固執が組織の意思決定を遅らせる
「正確に打ち込むことが経理の仕事だ」——。もし現場がそう考えているとしたら、それは企業の成長を阻害する危険なサインかもしれません。経済産業省のDXレポートでも指摘されている通り、日本企業の多くは「2025年の崖」と呼ばれるレガシーシステムやアナログ業務の弊害に直面しています。特に決算書のような重要データのデータ化に時間をかけすぎることは、経営判断に必要な「情報の鮮度」を著しく低下させる要因となります。
ある研究によると、単純なデータ入力作業は人間の認知リソースを大きく消費し、その後の分析や判断業務におけるパフォーマンスを低下させることが示唆されています。手入力にリソースを割くことは、単なる時間の浪費だけでなく、組織全体の「思考の瞬発力」を奪う行為になりかねないのです。
引用元:
経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格展開~」(2018年)および、認知心理学における「自我消耗(Ego Depletion)」に関する一般研究を参照。
【実践】経理業務を「守り」から「攻め」に変えるAI活用術
では、DX先進企業はどのように経理業務を変革しているのでしょうか。彼らはAI-OCRを単なる「入力代行ツール」としてではなく、経営のPDCAサイクルを高速化する「加速装置」として位置づけています。
入力業務がボトルネックにならなければ、月次決算の早期化が可能になり、リアルタイムに近い数字で経営戦略を練り直すことができます。AIに「正確なデータ化」を任せ、人間はそのデータから「何が起きているか」を読み解く。この役割分担こそが、これからの経理部門に求められる「攻め」の姿勢です。最新のAI技術を活用することで、これまで数日かかっていたデータ化のリードタイムを数分に短縮し、余った時間をより付加価値の高い財務分析や予測業務に充てることが可能になります。
【本質】人間が担うべきは「データ作成」ではなく「データ活用」
AI技術が進化しても、最終的な経営判断を下すのは人間です。しかし、その判断の質は「材料となるデータの精度と鮮度」に依存します。ゼロから「間違いのないように入力する」ことに神経を使うのは、AI時代においては非効率なリソース配分と言わざるを得ません。
既存のデータをAIに読み込ませ、人間はAIが提示した結果の「妥当性」を検証し、そこからインサイト(洞察)を導き出す。このプロセスへの転換が、企業の競争力を左右します。AI-OCRの導入は、単なる業務効率化のツール導入ではなく、社員の意識を「作業者」から「分析者」へと変革させるための重要なステップなのです。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、今回ご紹介したようなOCRによる文字起こしやデータ化はもちろん、メール作成や議事録作成、レポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、決算書のような機密性の高い情報も安心して扱えます。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。