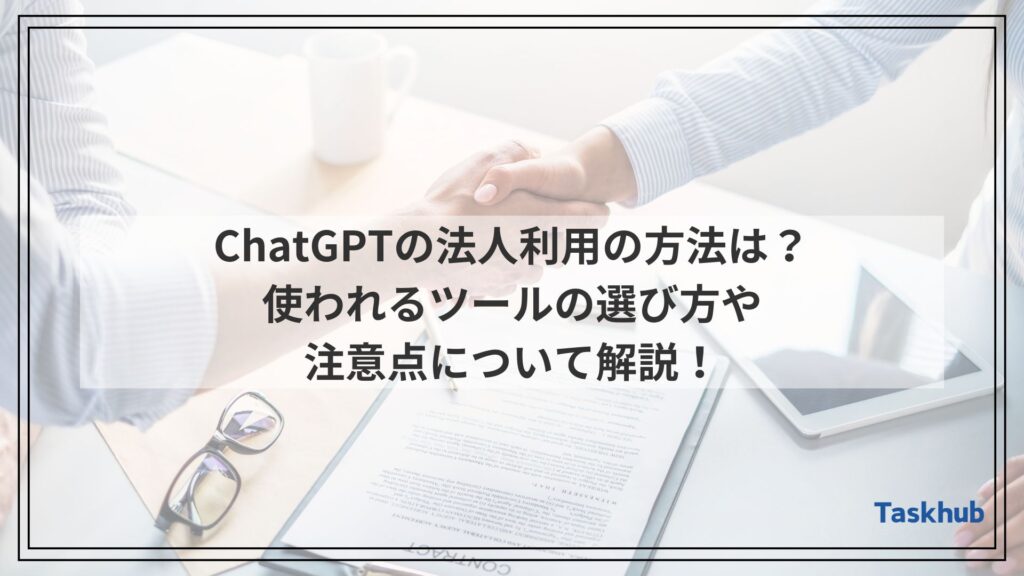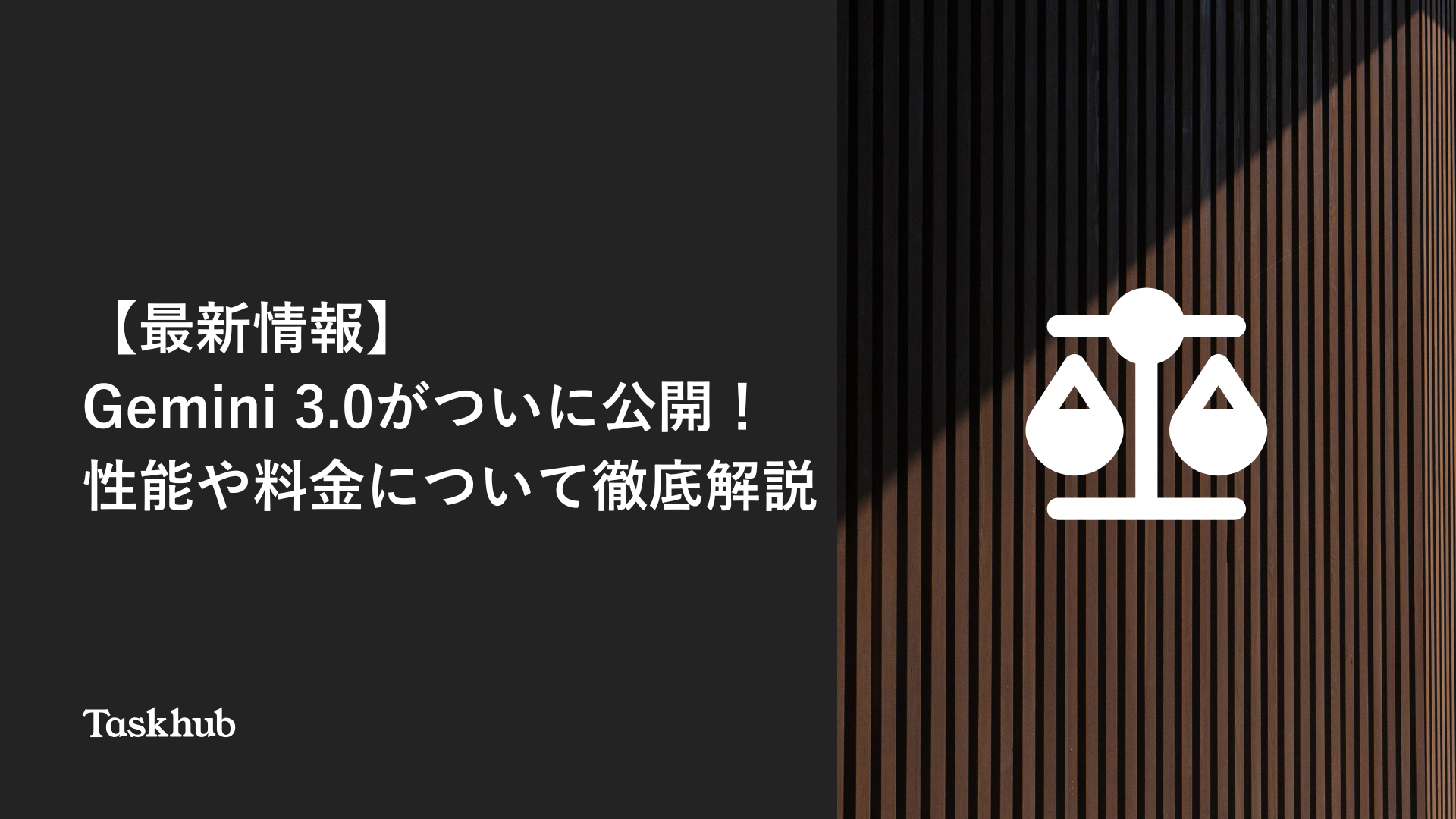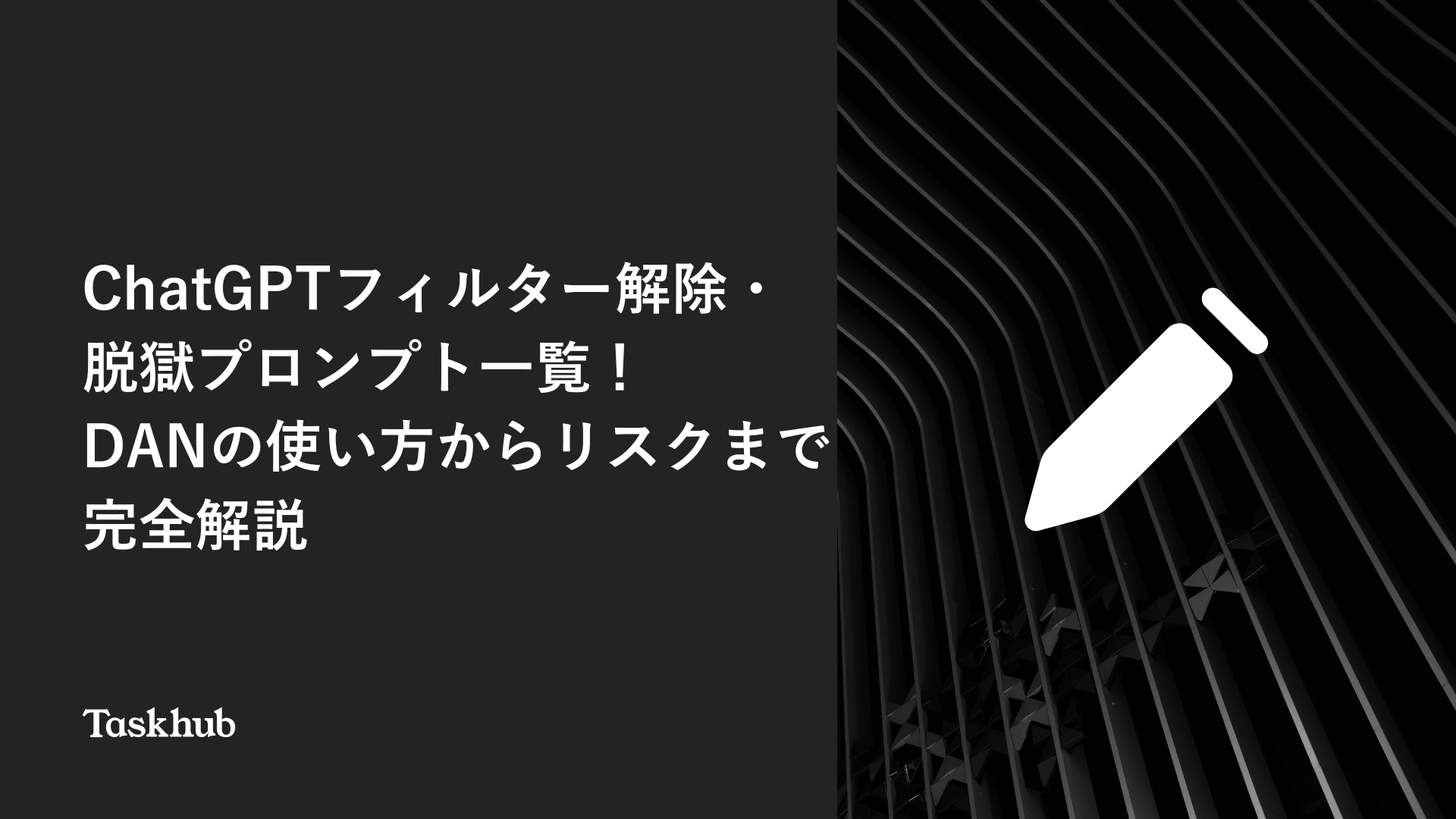「ChatGPTを自社に導入したいが、どうすればいいか分からない」
「ChatGPTの法人活用における要点が知りたい!」という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ChatGPTの法人活用では、いくつかのポイントを抑えることで、社員が積極的にChatGPTを活用する組織を実現できます。
今回は、ChatGPT法人導入のポイントを徹底解説します。
ChatGPTとは
ChatGPTは、OpenAIが開発したAIチャットボットです。
「GPT」と呼ばれる大規模言語モデル(LLM)を対話向けにチューニングしたサービスであり、人間の言葉に非常に近い自然な文章を生成することができます。
ChatGPTはビジネスの現場でも活用することができ、メール文作成のような単純業務から、アイデア出し・戦略立案のような複雑な業務にも利用できます。
生成AIについては以下の記事で詳しく説明しています。
ChatGPTを法人利用する3つのメリット
ChatGPTの法人活用では、3つのメリットが存在します。
この3つのメリットについて詳しく解説します。
①生産性の向上が実現できる
ChatGPTは幅広い業務で活用でき、「簡単だが、自分でやると時間がかかる仕事」を効率化していくことができます。
ボストンコンサルティンググループが行った調査では、生成AIを活用している従業員の58%が「生成AI活用による週5時間以上の工数削減」を実現しています。
引用:BCG
②クリエイティブ系業務の補助ができる
生成AIの強みは、学習した膨大なデータセットを基に「新たなコンテンツ」を作成できる所にあります。
画像生成AIや音楽生成AIは特にクリエイティビティの要素が強く見えますが、ChatGPTもクリエイティブ業務に活用することができます。
人間の定性的な感覚を理解した、コピーライトや文章作成に強みを持っています。
③24時間365日稼働できる
ChatGPTは365日休まず稼働させることができます。
社内向けであれば、各社員が何でも質問できるアシスタントAIとして展開することで、コミュニケーションロスやコストを削減できます。
社外向けであれば、お客様対応のチャットボットとして展開することで、質の高いカスタマーサポートを常時提供することが可能です。
ChatGPTの追加学習の方法として現在注目されているのが「RAG」という方法です。
こちらの記事でRAGについて詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。
法人向けChatGPTの使い方4選
ChatGPTの法人での活用方法には、以下の4つがあります。

この4つについて詳しく解説します。
①個人単位でChatGPTを契約する
ChatGPTの法人活用で、最も簡単な方法は個人単位でChatGPTを使用することです。
ChatGPTの使用自体は無料ですが、業務利用する場合は「ChatGPT-o1」を使用できた方がいいので、有料プランの登録がおすすめです。
| 料金 | 20ドル(約3,100円)※2025年2月3日現在 |
| 使用できるモデル | ・GPT-o1・GPT-o1 pro・Sora(動画生成AI)の一部利用・カスタムGPTの作成 |
② ChatGPTの法人プランを契約する
企業全体での導入を考えるなら、ChatGPT Enterpriseを契約するのが最適です。
「有料モデルの無制限利用」「入力可能トークン数の増加」など、企業向けにカスタマイズされた機能を使用することができます。
| 料金 | 非公表(OpenAIに要問い合わせ) |
| 使用できるモデル | ・GPT-o1・GPT-o1 pro・Sora(動画生成AI)の一部利用・カスタムGPTの作成・管理者向けダッシュボードの使用 |
③ChatGPTのAPIを使って社内向けGPTを開発する
ChatGPTのAPIを利用し、独自の社内システムやチャットボットを開発するケースがあります。
自社データを活用したカスタムモデルのトレーニングや、社内ポータルとの連携など、業務効率を最大化するための機能を自由にカスタマイズできるのが強みです。
しかし、自社開発の体制とコストがかかるため、社内向けGPTの社内開発が可能であるかどうかの判断は必要となります。
④ChatGPT基盤の生成AIツールを活用する
上記三点の実施が難しい場合、外部の生成AIツールを導入する方法があります。
ChatGPTや類似の生成AIを基盤とし、それをさらに使いやすい形にしたビジネスツールが各社から提供されています。
専用のUIやセキュリティ機能を備え、非エンジニアでも簡単に導入・運用できるようになっているケースが多いです。
法人向けChatGPTツールの選び方
法人向けの生成AIツールを選ぶ際の注意点は以下の3点です。
- 「生成AIでできることが」直感的に分かるツールを選ぶ
- セキュリティの安全性を担保したツールを選ぶ
- 生成AI導入効果を可視化できるツールを選ぶ
この3点について詳しく解説します。
①生成AIでできることが直感的に分かるツールを選ぶ
生成AIは多岐に渡る業務に活用できるため、特に初心者の方だと「生成AIで何ができるのか分からない」と感じるという課題があります。
UIや使い方がシンプルで、「これなら自分でも使えそう!」と思ってもらえるようなツールを選ぶことが重要です。
UIやサンプルワークフローが分かりやすいツールは、ユーザーの学習コストを抑えるのに有効です。
UIやサンプルワークフローが分かりやすいツールを導入することで、ユーザーの学習コストを抑えることができます。
②セキュリティの安全性を担保したツールを選ぶ
法人がChaGPTを導入する際、最も重視すべきポイントの一つがセキュリティです。
機密情報や個人情報をやり取りすることもあるため、データ暗号化、アクセス制限、ログ監査などの機能がどの程度充実しているかを確認しましょう。
特に確認すべき点は以下の2点です。
- 入力情報をサービス提供者が「二次利用しないこと」を明言しているか
- 入力情報が自動的に学習されないか
外部サービスの場合、「Azure OpenAI service」を使用しているかどうかを基準の1つにするのがおすすめです。
③生成AI導入効果を可視化できるツールを選ぶ
AI導入に際しては、投資対効果(ROI)の検証が欠かせません。
レポート機能や分析機能が備わっているツールを選ぶと、工数削減や売上向上など具体的な数値で効果を可視化しやすくなり、導入後の運用改善や追加投資の判断にも役立ちます。
具体的には、「誰がどの業務を何回使用し、合計で何分の工数削減ができたのか」を管理できるツールである必要があります。
ChatGPT法人利用の2つの注意点
ChatGPTの法人活用では、特に出力データの取り扱いに関して注意しなければいけません。

ここでは、「著作権」と「ハルシネーション」の2つのリスクを解説します。
①著作権リスク
生成AIで作成した文章や画像は、元データに含まれる著作物に由来する場合があります。
また著作権侵害のリスク有無を判断する際は「類似性と依拠性」の観点から判断することが重要です。
参考:文化庁『AIと著作権』
著作権を侵害しないように注意が必要してください。
特に外部公開のコンテンツを生成する際には、作成物におけるライセンス確認や利用規約の遵守が必須となります。
②ハルシネーションリスク
生成AIは、時に存在しない情報や誤情報をあたかも事実かのように回答してしまう「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象が発生する場合があります。
重要な意思決定や顧客対応では、必ず人間が内容をチェックし、誤情報の拡散を防ぐ仕組みを整えましょう。
ChatGPTの法人利用ならTaskhub
Taskhubは、法人生成AI活用の障壁を突破する、誰でも簡単に利用できる生成AIツールです。
1. 生成AIでできることが直感的にわかる
Taskhubでは、「生成AIでできること」が直感的にわかる、タスク型UIを採用しています。
また、タイル形式でタスクが表示されるため、開いてすぐ、生成AIを活用することができます。
・Taskhubのホーム画面イメージ
プロンプトは事前にセットされており、プロンプトを入力する必要がないため、プロンプト教育コストを軽減しつつChatGPTを導入していくことができます。
・Taskhubの実際の使用画面
2. ノーコードでAIワークフローの構築ができる
ChatGPTの課題でもある「一回のプロンプト入力では局所的タスクにしか活用できない」という点を解決しているのがAIワークフローです。
Taskhubでは、ノーコードでAIを活用したワークフローの構築が可能であり、日本語だけで、手軽に高度なAIアプリを構築できます。
まとめ
今回はChatGPTの法人活用について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
本記事の簡単なまとめは以下の通りです。
・ChatGPT導入により高い業務効率化とコスト削減が期待できる
テキスト生成や問い合わせ対応などの繰り返し業務を自動化し、社員が高付加価値業務に専念できる。
・導入・運用時のリスク管理(ハルシネーション・著作権・機密情報保護)が必須
誤情報の拡散防止や第三者の著作権侵害、社外への機密情報流出などを防ぐ仕組みづくりが重要。
・生成AI活用はツールの選択が鍵
セキュリティが担保され、簡単にAIを使えるツールを選ぶことにより、スムーズかつ安全なAI導入が実現できる。
ChatGPTを活用することで、企業は大幅な業務効率化とコスト削減を見込めます。一方でハルシネーションや著作権侵害、機密情報の流出などのリスクを考慮した運用設計が不可欠です。こうした課題に対応できるプラットフォームを選ぶことで、ノーコード実装やセキュリティ対策を強化しつつ、導入による効果を最大化できます。