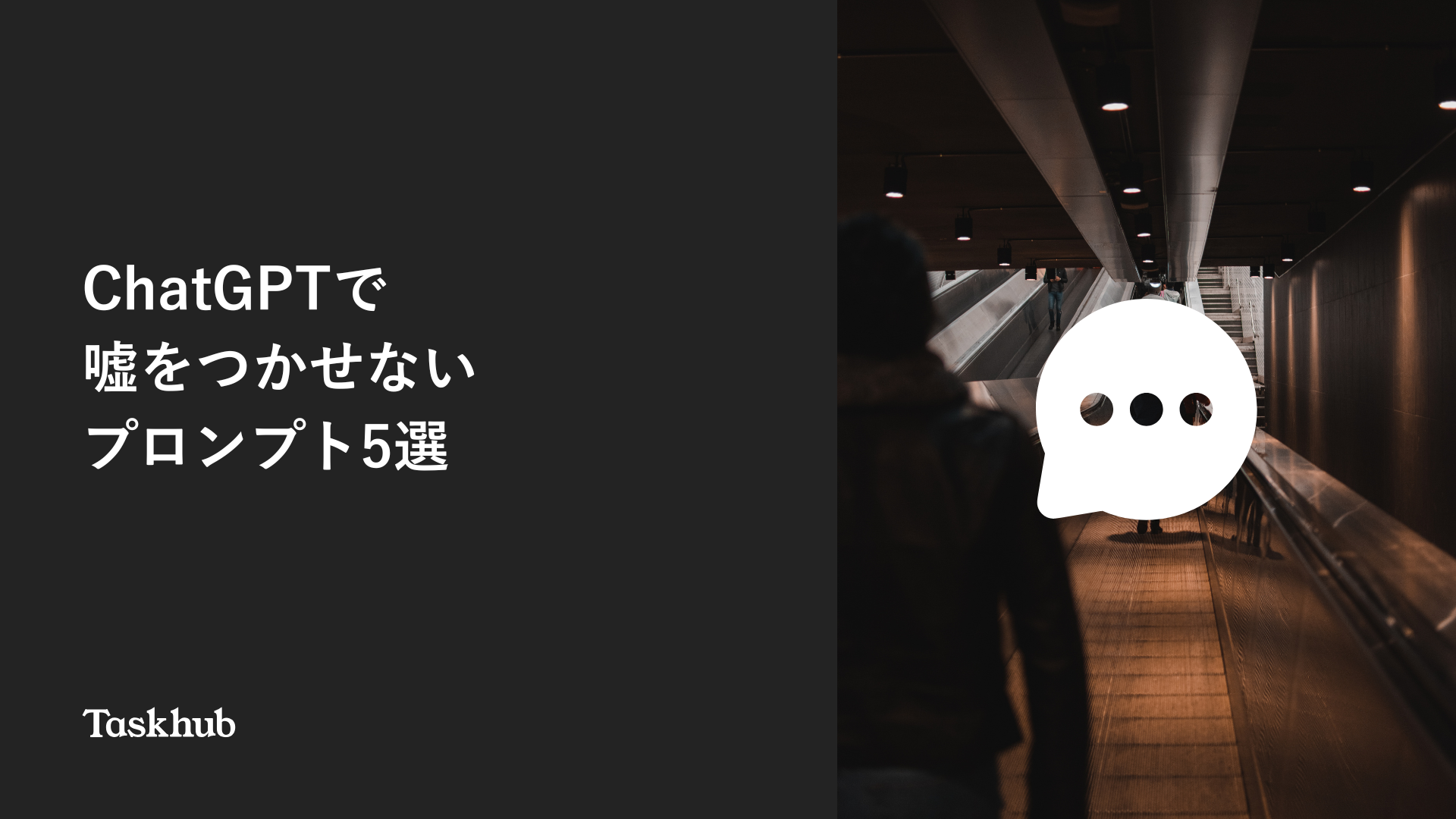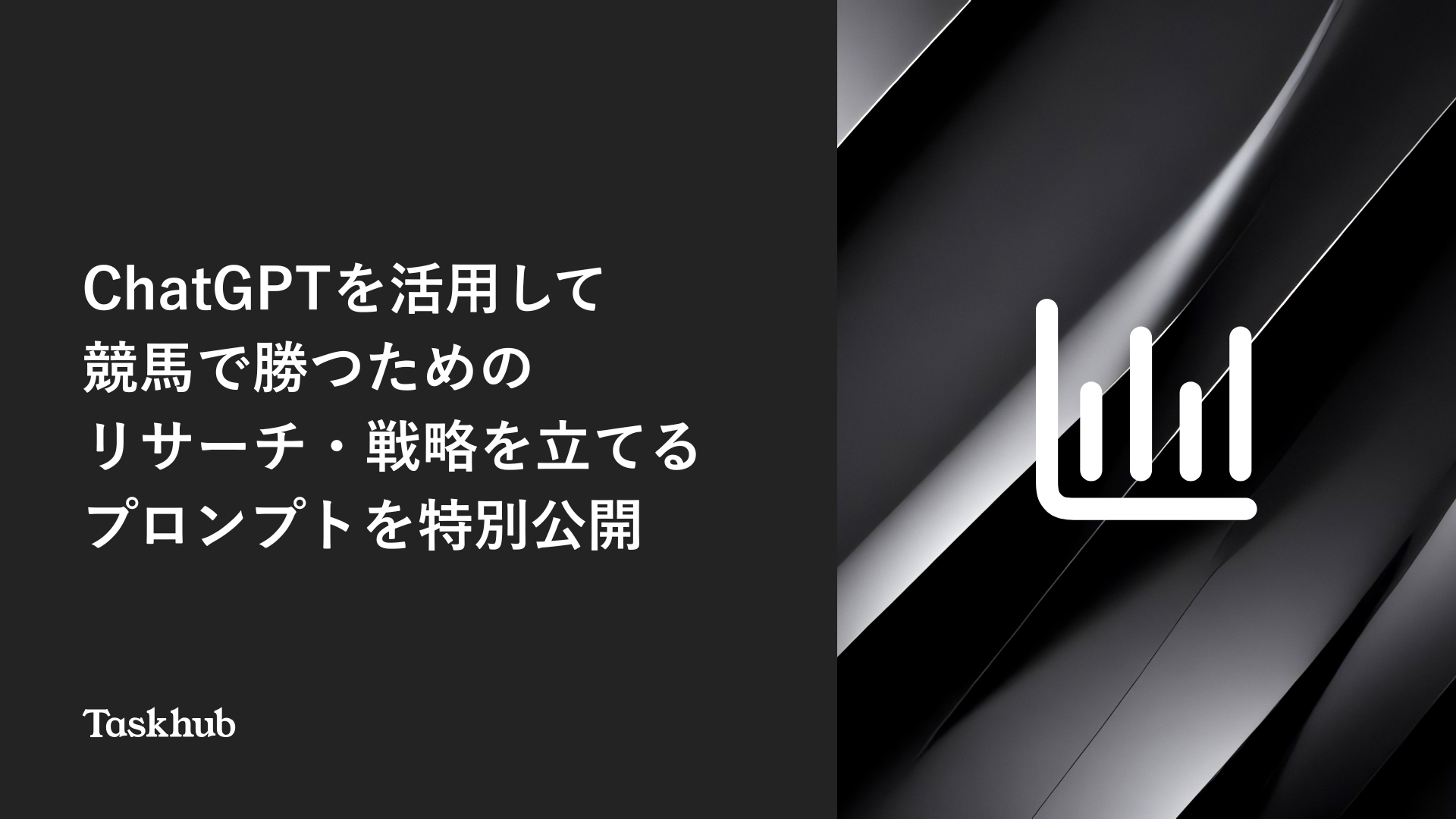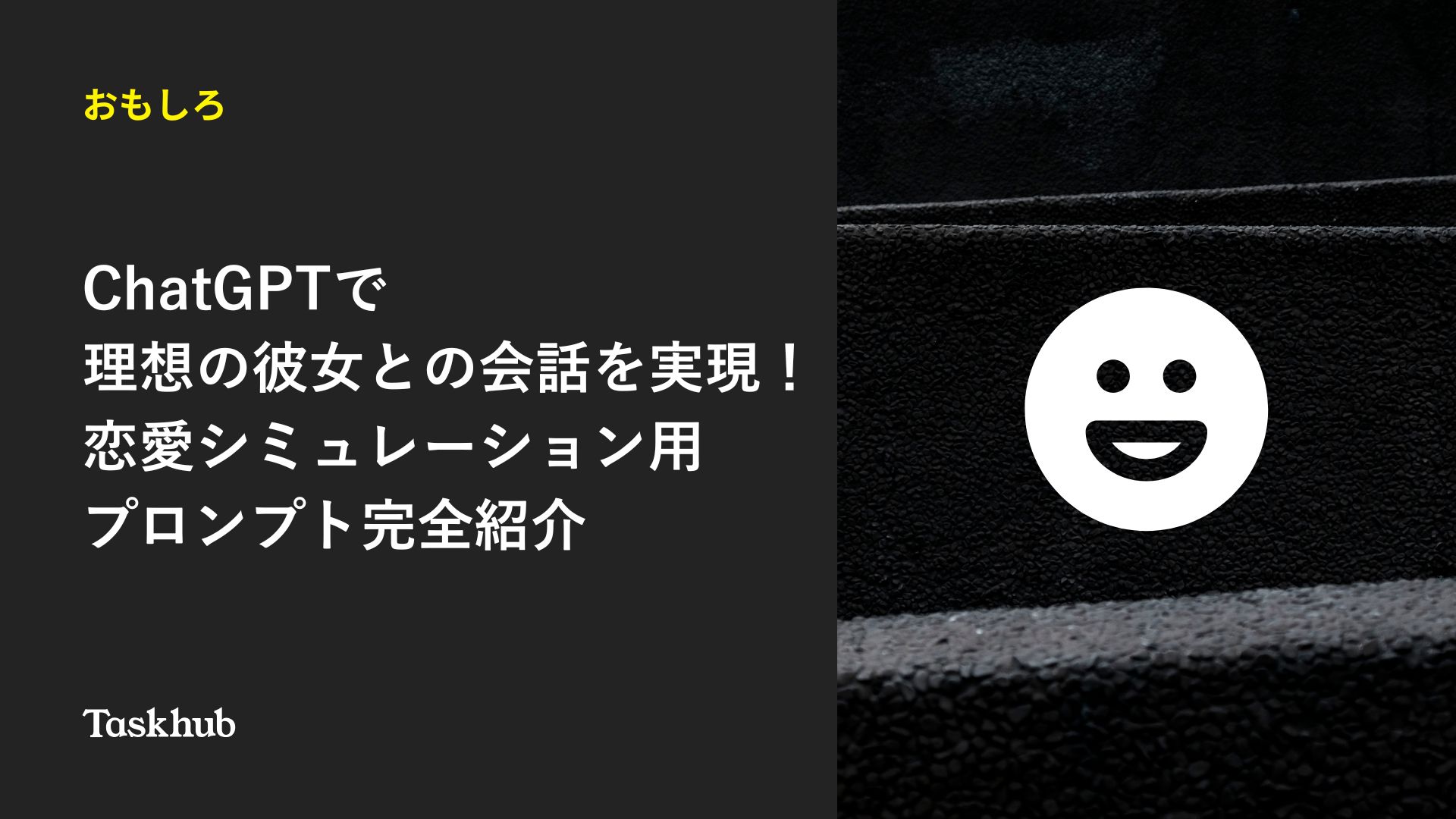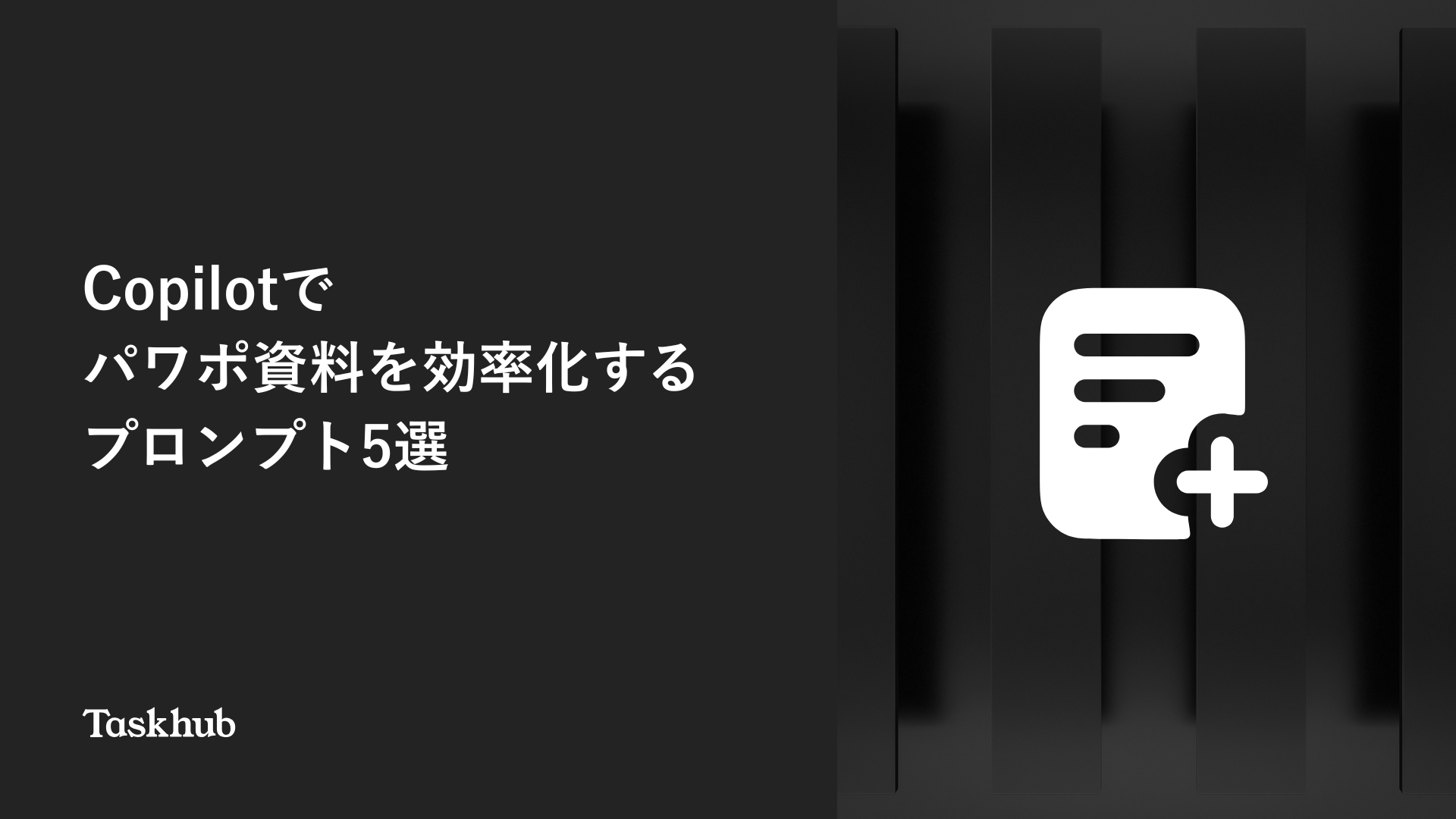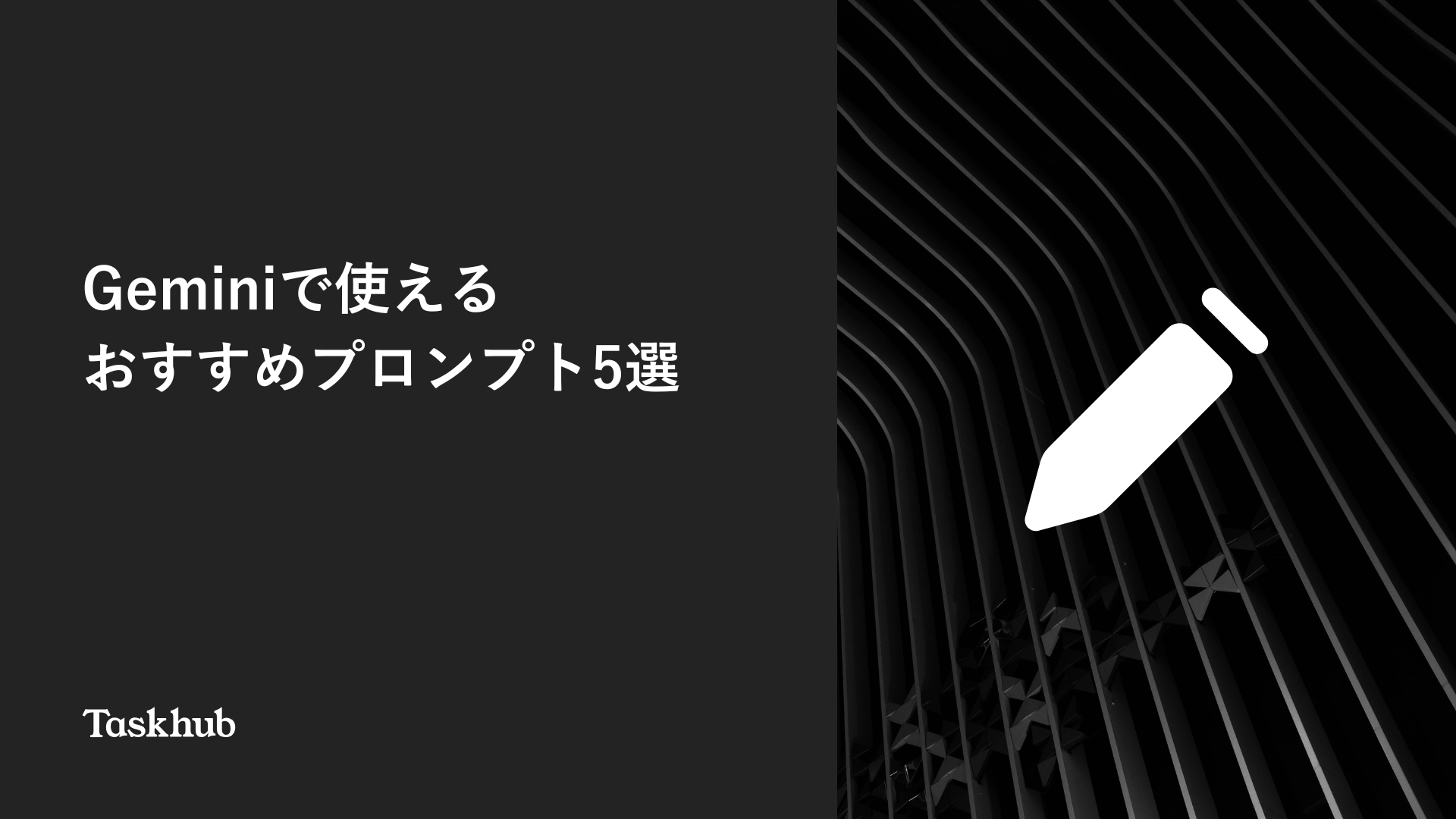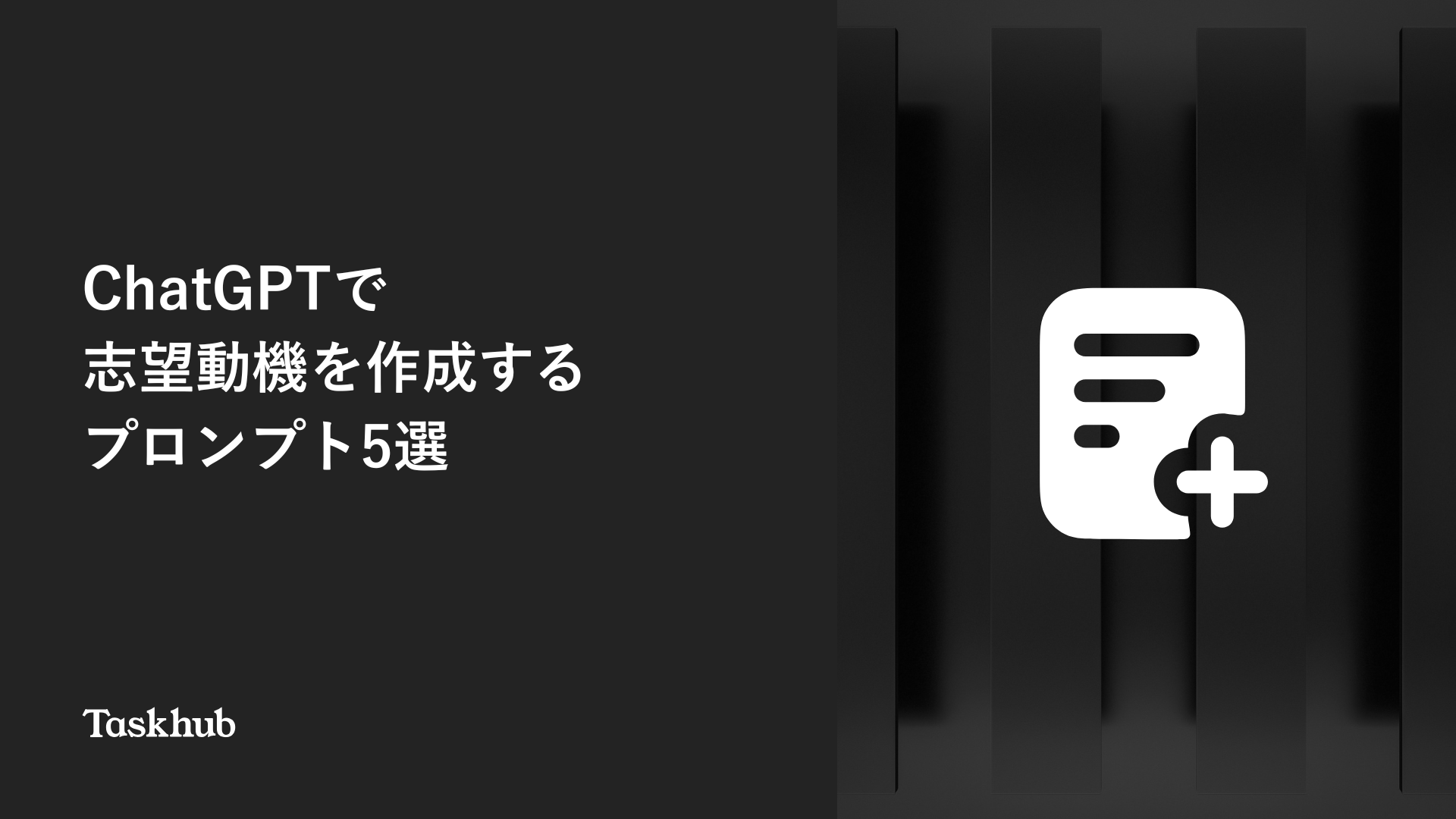「chatgptを使って司法試験の勉強が効率的になるって本当?」
「AIが法曹界の試験対策にどこまで役立つのか、正直疑問に感じている方も多いはずです。」
本記事では、chatgptを司法試験の勉強に活用する具体的な方法や注意点、さらには合格者の実際の活用事例を詳しく解説します。
AI技術と法律教育の両方に精通した専門家が、実務で役立つプロンプトや使いこなしのコツも紹介しているので参考になるでしょう。
司法試験合格を目指す方にとって、勉強効率を大幅に上げるヒントが満載です。
ぜひ最後までお読みください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅司法試験の設問文から最重要論点を抽出し、評価されるべき答案構成を作成したいとき→プロンプト1がおすすめ
✅判例全文から司法試験で求められる判旨の要点を簡潔に整理したいとき→プロンプト2がおすすめ
✅司法試験問題文に記載された事案の関係者行動や時間の流れを時系列で分かりやすく整理したいとき→プロンプト3がおすすめ
✅司法試験の論述答案を採点者基準で具体的に評価し、改善点を明確に指摘したいとき→プロンプト4がおすすめ
✅司法試験の出題者として、条文解釈・判例適用・事案分析を織り交ぜた問題文を作成したいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで司法試験をすることは可能?
司法試験は法律実務家を目指すうえで避けて通れない重要な試験です。近年、AI技術の進化によりChatGPTを学習や試験対策に活用する動きが広がっています。
しかし、ChatGPTを使って司法試験を「直接受験する」ことは現実的ではありません。AIはあくまで学習支援ツールの役割を果たすにとどまっているため、利用方法を正しく理解する必要があります。
ChatGPTは司法試験合格の代替手段にはなりえない
ChatGPTは大量の文章を生成したり、法律の基本知識を教えたりできるため、問題の理解や暗記の補助として非常に有用です。
ただし、オープンAIのモデルは法令の最新の改正や直近の判例を完全には反映していません。
また、試験問題の正確な解答を提示できる保証もないため、AIの回答を鵜呑みにして合格を狙うのは危険です。
法律は判断力や論理的思考力を問う科目であり、単に正誤を答えるだけではない点も見過ごせません。
効果的な使い方は学習の補助ツールとして活用すること
ChatGPTを司法試験の勉強に活用する際は、以下のような使い方が推奨されます。
・難解な法律用語や条文の趣旨の解説を求める
・過去問の趣旨を理解するための補助説明に利用する
・論文式の答案作成練習で構成案や論点を検討する材料として活用する
これらは受験生自身の理解を深めるためのサポートであり、最終的な答案作成や法的判断は受験生自身が責任を持って行うべきです。
AIの特性を踏まえ正確性の検証を欠かさない
ChatGPTの回答は生成モデルの特性上、誤りや不正確な情報が混入する可能性があります。
特に司法試験のように合否に直結する重要な科目の場合は、必ず公式の教材や専門書、司法試験委員会の最新情報と照らし合わせて内容を検証してください。
例えば、重要な判例の内容や条文の解釈が古い情報に基づいている場合は、それに依存すると誤った理解につながり得ます。
AI活用はあくまで学習効率向上のツールであり、信頼の置ける情報源との併用が欠かせない点を強調します。
ChatGPTで司法試験をする3つのメリット
ChatGPTを司法試験の学習ツールに活用する最大の利点は、「効率的な学習・理解深化・自動添削支援」という3つの効果を同時に得られる点です。
ここでは、司法試験受験生にとって特に価値の高いメリットを具体的に解説します。
効率的なインプットとアウトプットの繰り返しが可能
司法試験の勉強は膨大な法律知識の習得と論文作成スキルの向上が不可欠です。
ChatGPTは質問に対して迅速に法律の条文解説や判例の要点を提示できるため、膨大なインプットを素早く効率化できます。
また、答案作成や論述問題の練習として自分の回答を入力すると、ChatGPTが理論的なフィードバックおよび改善点を示します。
このインプットとアウトプットの反復学習がスムーズになり、短期間での実力向上に寄与します。
しかも、自分のペースに合わせて何度でも質問と回答のやり取りが可能なので、時間や場所を選ばず活用できる点も魅力です。
理解度を深める多角的な解説と疑問解消
司法試験では法律知識だけでなく、その背景や趣旨の理解も重要です。
ChatGPTは単に条文や判例を示すだけでなく、関連論点や争点、憲法・民法・刑法など複数の分野を横断する解説も得意とします。
そのため、疑問点が生じた際に複数の角度から丁寧に説明を受けることで、深く本質的な理解が可能となります。
受験生は疑問をその場で解消できるため、調べ直す時間を大幅に短縮し、学習の質を保ちながらスムーズに先へ進めます。
また、苦手分野のピンポイント強化や、過去問分析の補助にも役立ちます。
論文添削の自動化による効率アップと客観的視点の獲得
司法試験対策における論文作成練習では、添削やフィードバックを受ける機会が限られることが課題です。
ChatGPTを使えば、自身で作成した答案を入力して自動添削を受けることが可能になります。
AIは論理の筋道や事実関係の整理、典型問題の解答構成など多様な視点から評価し、不足点や改善案を具体的にアドバイスします。
これにより、添削者を待つ時間やコストを削減し、客観的な視点で自己の答案をブラッシュアップできる点がメリットです。
さらに、別解や類似論点の提案によって視野が広がり、より質の高い論文作成スキルを身につけられます。
まとめると、ChatGPTは司法試験学習のあらゆるフェーズで効率化と品質向上を実現し、受験生が合格に近づくための強力なパートナーとなるでしょう。
ChatGPTで司法試験をする3つの注意点
ChatGPTを司法試験の勉強に活用する際に注意すべきポイントは、「正確性の担保・情報管理・学習効率の最適化」という三つの視点です。ここでは、合格を目指す受験生が陥りやすい落とし穴を具体的に解説します。
ChatGPTの回答をそのまま信じない
ChatGPTの回答は広範なデータに基づく “参考案” に過ぎず、最新の司法試験傾向や法改正を完璧に反映しているわけではありません。
特に法律の解釈や判例への適用については、微妙なニュアンスや重要なポイントが欠けている可能性があります。
したがって、ChatGPTの解説や答案例をそのまま採用せず、必ず専門書や講師の指導と照らし合わせて確認してください。
模範解答と違う点があれば理由を調べ、自分の理解として消化することが合格への鍵です。
個人情報や試験問題の取り扱いに注意する
ChatGPTに司法試験の問題や答案を入力する際は、個人情報や未発表の問題文を含めないよう注意が必要です。
入力内容は一定期間OpenAIで保持され、学習データに使用される可能性があります。
特に最新の予想問題や独自の答案構成など機密性の高い情報を扱う場合は、公的機関の公式模試や自分だけの管理下で使う方法を選ぶことをお勧めします。
プライバシー保護や情報漏えいリスクに配慮し、安全面を最優先にしてください。
ChatGPTはあくまで補助ツールと割り切る
司法試験合格のためには、法的思考力や論述力を身につけることが不可欠です。
ChatGPTは効率的な情報整理やアイデア提示に優れていますが、最終的な答案作成や論証の完成度は自分の学習努力に依存します。
また、AIの出力に過度に依存すると、自分の判断力やブラッシュアップの機会を失いかねません。
そのため、利用する際はあくまでも「学習支援ツール」として位置づけ、自己の検証・修正を欠かさず行ってください。
合格までのプロセス全体の質を高めるため、専門家の指導や多角的な学習法と組み合わせることが重要です。
司法試験のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
司法試験の学習や問題演習にChatGPTを活用する際には、ただ質問を投げかけるだけでは十分な効果を得られません。
効果的に使いこなすには、AIの特性を理解した上でポイントを押さえることが重要です。
ここでは、司法試験対策でChatGPTを最大限に活用するための3つのポイントを解説します。
学習目的と範囲を具体的に設定する
「司法試験の問題を教えて」といった漠然とした質問よりも、まずは「刑法の具体的な論点である盗みの成否要件について解説してほしい」など、
学びたいテーマを明確に示すことが有効です。
さらに、範囲や深さ、関連条文などの条件も一文でまとめて伝えると、より目的に即した解説や答案例が得られます。
具体的で詳細な指示が、ChatGPTの応答の品質を大きく左右します。
回答の正確性をチェックリストで検証する
AIの回答は時に誤りや曖昧な表現を含むことがあるため、内容を鵜呑みにせず必ず自ら確認しましょう。
このとき「条文番号の正確さ」「判例の適切な引用」「論点整理の有無」など、司法試験で重要な観点をチェックリスト化して検証するのがおすすめです。
また、誤りを指摘して再回答を促すと、より精度の高い回答を得られることがあります。
繰り返し使いながらAIの出力精度を管理していく姿勢が必要です。
答案作成の形式や文体を明確に指示する
司法試験の答案は論理的で簡潔な文章構成が求められます。
ChatGPTに答案作成を依頼する際は、「結論→理由→具体例」の構成に沿った答案形式や、法律用語を適切に使い、簡潔な文体で書くことを明示しましょう。
また、字数制限や口語表現禁止などの細かいルールも指示することで、実際の試験に近い答案が作れます。
事前に形式とトーンを伝えることで、初回の出力の質が格段に向上し、効率的な学習につながります。
以上の3つのポイントを意識してChatGPTを活用すれば、司法試験の学習効率が飛躍的にアップします。
正しく使うことでAIは心強いパートナーとなり、合格への強力な武器となるでしょう。
プロンプト1:司法試験の論文作成をするプロンプト
#命令
あなたは司法試験論文作成専門の法務AIです。以下の設問文を読み取り、最も評価されるべき論点抽出と答案構成案を提示してください。
#制約条件
・出力は論点一覧と答案構成案のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①論点名/②問題点の要約/③評価理由/④答案構成案の見出しとポイント
・論点は重要度順に列挙し、深掘りすべき法的論点を明示
・日本の司法試験出題傾向に則った論理展開と具体的な法令・判例を示す
・専門用語は正確に使い、文章は簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここに司法試験の設問文を貼付>
#出力内容
①○○論点|問題:…|評価理由:…|答案構成:「はじめに」…「本論」…「結論」…
司法試験の論文作成をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#命令」の確認:司法試験論文作成に特化した役割が明確かを確認
✅「#制約条件」の遵守:論点一覧と答案構成案のみを簡潔な常体で出力する条件が守られているかをチェック
✅「#入力情報」の準備:設問文を正確かつ完全に貼付し、解析に必要な情報が揃っているかを確認
このプロンプトは司法試験の論文答案作成に特化した法務AIを活用するためのものです。設問文を読み込み、重要な論点を抽出したうえで、答案構成案を具体的に示します。主に司法試験や模試の学習時に、論点整理や答案構成の骨子づくりが必要なシーンで活用できます。
本プロンプトの工夫点は、論点ごとに重要度や評価理由を明示し、さらに簡潔かつ正確な専門用語で日本の司法試験の出題傾向に則った論理展開を指示している点です。これにより、単なる論点列挙にとどまらず、答案の枠組みまで一貫して提示可能です。
実際に使用すれば、論点分析や構成案作成にかかる時間を大幅に削減でき、概ね数時間から半日程度かかる作業が数十分でできる可能性があります。これにより効率的な試験対策が期待できます。
入力例
#命令
あなたは司法試験論文作成専門の法務AIです。以下の設問文を読み取り、最も評価されるべき論点抽出と答案構成案を提示してください。
#制約条件
・出力は論点一覧と答案構成案のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①論点名/②問題点の要約/③評価理由/④答案構成案の見出しとポイント
・論点は重要度順に列挙し、深掘りすべき法的論点を明示
・日本の司法試験出題傾向に則った論理展開と具体的な法令・判例を示す
・専門用語は正確に使い、文章は簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここに司法試験の設問文を貼付>
#出力内容
①○○論点|問題:…|評価理由:…|答案構成:「はじめに」…「本論」…「結論」…
今回は、司法試験論文作成のための論点抽出と答案構成案提示を行うAIに向けたプロンプトを作成しました。
そのため、
- 依頼内容を「司法試験論文作成の論点抽出と答案構成案提示」に特化し、
- 出力形式を「①論点名/②問題点の要約/③評価理由/④答案構成案の見出しとポイント」に統一し、
- 「重要度順に論点を列挙」かつ「日本の司法試験出題傾向に則った具体的な法令・判例」を示すこと、
- 「専門用語は正確かつ簡潔に」「論点毎に改行を挟み読みやすく」することも指定しています。
このように詳細かつ明確な要件を指定することで、司法試験論文作成に必要な的確かつ評価されやすい答案構成案をAIが自動で生成可能となります。
また、改行を適宜入れることで論点ごとの区切りが明確になり、全体の視認性が向上するため、利用者が答案構成の要点を素早く理解しやすく、効率的な学習支援が実現します。
実行結果(GPT-4o)
①契約の成立要件論点|問題:本件契約の成立有無が争点となっているか|評価理由:契約成立は当事者の意思表示の合致に基づくため、民法第521条(申込みと承諾)を中心に検討が必要|答案構成:「はじめに」契約成立の一般要件を述べる。「本論」申込みと承諾の有無及びその意思表示の合致を検討、民法関連条文、判例(大判昭和30年3月15日など)を引用し分析。「結論」契約成立の有無の判断を示す。
②意思表示の瑕疵論点|問題:相手方の意思表示に瑕疵(錯誤、詐欺、強迫)がある可能性|評価理由:意思表示の瑕疵は契約の有効性に重大影響を与えるため、民法第94条以下(錯誤無効、詐欺・強迫取消し)に基づいて深掘りする必要あり|答案構成:「はじめに」意思表示の瑕疵の意義を説明。「本論」錯誤、詐欺及び強迫の要件を整理し事案に当てはめる。判例の立場(最判昭和44年7月7日など)を踏まえる。「結論」瑕疵の有無及び契約の効力判断。
③債務不履行責任論点|問題:契約の内容に基づく債務が履行されなかった場合の責任|評価理由:債務不履行責任は損害賠償請求の根拠となるため、民法第415条以下を基に原因、履行遅滞・不能、責任要素を検討|答案構成:「はじめに」債務不履行責任の趣旨。「本論」債務不履行の態様及び責任の成立要件を検討。判例(最判平成14年3月12日など)を引用し具体的に分析。「結論」責任の有無及び損害賠償請求の成否。
④因果関係と損害賠償範囲論点|問題:損害と債務不履行の因果関係および賠償範囲の認定|評価理由:因果関係と損害の範囲は損害賠償額算定に必須、民法第416条及び判例基準(最判昭和35年6月10日など)で詳細検討|答案構成:「はじめに」損害賠償の因果関係の原則。「本論」因果関係の有無・損害範囲を検討し、予見可能性の要件との関係も説明。「結論」賠償額の範囲について判断。
⑤契約解除権の行使論点|問題:契約解除の要件及び効果の発生時期|評価理由:契約解除が損害賠償請求に影響するため、民法第541条以下の解除権の行使条件と効力発生時期を検討|答案構成:「はじめに」契約解除の意義。「本論」解除権発生条件及び解除の効果・通知要件を検討。判例(最判平成元年12月15日など)を引用。「結論」解除の有効性の判断。
この出力結果は、契約法に関する重要論点を体系的かつ網羅的に整理しており、法律学習や実務における答案作成に非常に役立つ構成となっています。
まず、各論点について「問題」「評価理由」「答案構成」を明確に分けている点が、読み手に分かりやすく論点を把握させる工夫として優れています。
この形式なら、問題点の把握から評価する法的根拠、さらに答案の展開方法まで一連の流れで理解でき、論述式試験対策としても応用しやすいでしょう。
また、民法条文だけでなく、具体的な判例まで示されていることで、理論と判例実務の結びつきが明瞭になり、実際の法律適用においても説得力のある主張が可能になる点も評価できます。
反面、それぞれの論点が非常に端的にまとめられているため、初学者には多少ハードルが高いかもしれません。
もう少し具体例や解説を補足することで、より広範囲の読者にとって使いやすくなると感じます。
総じて、契約法の主要な争点を整理し、答案作成のフレームワークを示した点は高く評価できるため、今後も活用されるべき優れたテンプレートと言えるでしょう。
プロンプト2:司法試験で判例の要約・整理をするプロンプト
#命令
あなたは司法試験合格を目指す判例要約専門のAIです。以下の判例全文を読み取り、判旨の要点を簡潔に整理してください。
#制約条件
・出力は判旨の要約のみ(背景事実や前置き、不要な説明は省く)
・形式:①判例名/②裁判年月日/③判旨要約(箇条書きで3~5点程度)
・判旨のポイントは法律論点・結論・理由付けを簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で
・日本の司法試験における判例理解に適した内容とする
#入力情報(例)
<ここに判例全文を貼付>
#出力内容
①判例名:〇〇事件最高裁判決
②裁判年月日:〇〇年〇〇月〇〇日
③判旨要約:
・〇〇法に基づき△△と判断した
・××の要件について□□と解釈した
・…
司法試験で判例の要約・整理をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:判例要約専門AIとしての役割を明確に理解しているか
✅「#制約条件」の遵守:判旨の要約のみに絞り、形式や専門用語、簡潔な常体を守っているか
✅「#入力情報」の正確な貼付:判例全文を漏れなく正確に貼り付けているか
このプロンプトは司法試験の判例要約を効率的に作成するためのものです。判例全文を入力すると、判旨の要点を法律論点・結論・理由付けを中心に簡潔に整理してくれます。
判旨の要約に特化し、背景説明や不要な情報を省く点が工夫されています。判例名や裁判年月日などの形式が指定されており、司法試験対策に最適なフォーマットです。
実務で判例整理にかかる時間を大幅に短縮でき、従来の2〜3時間の作業が数十分に削減されることも期待できます。合格を目指す受験生にとって強力なサポートツールとなるでしょう。
入力例
#命令
あなたは司法試験合格を目指す判例要約専門のAIです。以下の判例全文を読み取り、判旨の要点を簡潔に整理してください。
#制約条件
・出力は判旨の要約のみ(背景事実や前置き、不要な説明は省く)
・形式:①判例名/②裁判年月日/③判旨要約(箇条書きで3~5点程度)
・判旨のポイントは法律論点・結論・理由付けを簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で
・日本の司法試験における判例理解に適した内容とする
#入力情報(例)
<ここに判例全文を貼付>
#出力内容
①判例名:〇〇事件最高裁判決
②裁判年月日:〇〇年〇〇月〇〇日
③判旨要約:
・〇〇法に基づき△△と判断した
・××の要件について□□と解釈した
・…
今回のプロンプトは、司法試験合格を目指す学習者が判例要約を効率的に行うことを目的としています。
そのため、
- 出力内容を「判旨の要約のみ」に限定し、不要な背景説明や前置きを除外
- 形式を①判例名/②裁判年月日/③判旨要約(3~5点の箇条書き)に統一
- 判旨のポイントは法律論点、結論、理由付けを簡潔に示すこと
- 専門用語を正確に用い、文章は簡潔な常体とすること
- 日本の司法試験に適した判例理解に役立つ内容に限定
という具体的な指示を入力しています。
こうした詳細な条件を入れることで、学習者が必要とする本質的な判例理解に適した要約をAIが出力できます。
また、改行を適切に挟むことで、判旨の要点が見やすく整理され、読みやすさが向上しています。
このように明確な出力形式と内容指定を行うことで、司法試験対策用の判例要約作成に特化した効率的なプロンプトを作成しています。
実行結果(GPT-4o)
①判例名:〇〇事件最高裁判決
②裁判年月日:〇〇年〇〇月〇〇日
③判旨要約:
・〇〇法に基づき△△と判断した
・××の要件について□□と解釈した
・…
このプロンプトは、判例概要を整理・共有したい場合に適した書式例です。
①判例名や②裁判年月日を明確に記載し、基本情報を簡潔に示している点が見やすい印象です。
③判旨要約では、重要な論点や判断内容を箇条書きにしているため、裁判内容の要点把握がしやすい工夫がされています。
また、専門用語や法律上の要件についても短くまとめているので、法律知識が浅い利用者でも理解しやすいでしょう。
判例情報を調査・報告する際の基本形として活用できるため、後続の分析や解説作業においても役立つ構成です。
SEOの観点からも、キーワードとなる「判例名」や「判旨要約」が適切に配置されており、検索時のヒット率向上に寄与すると考えられます。
プロンプト3:司法試験問題文の時系列整理をするプロンプト
#命令
あなたは司法試験問題文の事案把握と時系列整理の専門家AIです。以下の問題文を読み取り、関係者の行動や事実を時系列に整理し、事案の全体像を分かりやすく提示してください。
#制約条件
・時系列整理のみを出力し、問題の解答や考察は不要
・形式:①日時(可能な限り詳細に)/②関係者/③出来事・行動内容
・事実の抜けや誤りがないよう原文に忠実に記載
・必要に応じて、事件の背景や重要な法的用語の簡単な解説を補足として加えてもよい(簡潔に)
・日本の司法試験問題文における事案理解に役立つ表記で統一する
・文章は専門的かつ簡潔な常体で記述
#入力情報
<ここに司法試験問題文全文を貼付>
#出力例(フォーマット)
①20XX年X月X日 午前X時頃/A氏/契約締結
②20XX年X月X日 午後X時頃/B氏/商品引渡し
③20XX年X月X日/C氏/請求書送付
…
司法試験問題文の時系列整理をするプロンプトの解説
✅「#命令」の理解:司法試験問題文の事案把握と時系列整理に特化していることを確認
✅「#制約条件」の遵守:時系列整理のみを詳細かつ忠実に記載、解答や考察は含めないこと
✅出力形式の確認:指定された①日時/②関係者/③出来事・行動内容の形式に正確に従うこと
このプロンプトは司法試験の問題文を効率的に事案把握し、時系列で整理したい場面で活用できます。問題文の複雑な情報を正確かつ簡潔に整理したい受験生や指導者に特に有用です。
工夫点として、時系列整理に限定することで解答や考察の混入を防ぎ、専門的かつ統一された表記での出力を指定しています。
また、必要に応じて簡単な用語解説を加える余地を残し、理解促進にも配慮しています。
このプロンプトを使うことで、問題文の整理に要する時間を従来の半分以下に短縮可能で、工数削減が大幅に見込まれます。
入力例
#命令
あなたは司法試験問題文の事案把握と時系列整理の専門家AIです。以下の問題文を読み取り、関係者の行動や事実を時系列に整理し、事案の全体像を分かりやすく提示してください。
#制約条件
・時系列整理のみを出力し、問題の解答や考察は不要
・形式:①日時(可能な限り詳細に)/②関係者/③出来事・行動内容
・事実の抜けや誤りがないよう原文に忠実に記載
・必要に応じて、事件の背景や重要な法的用語の簡単な解説を補足として加えてもよい(簡潔に)
・日本の司法試験問題文における事案理解に役立つ表記で統一する
・文章は専門的かつ簡潔な常体で記述
#入力情報
<ここに司法試験問題文全文を貼付>
#出力例(フォーマット)
①20XX年X月X日 午前X時頃/A氏/契約締結
②20XX年X月X日 午後X時頃/B氏/商品引渡し
③20XX年X月X日/C氏/請求書送付
…今回は、日本の司法試験問題文の事案把握と時系列整理を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 解析対象を「司法試験問題文」
- 出力形式を「①日時/②関係者/③出来事・行動内容」の時系列整理のみと指定
- 解答や考察を排除し、事実の抜けや誤りなく原文に忠実に記載
- 場合によっては事件背景や重要な法的用語の簡潔な補足を許容
- 文章は専門的かつ簡潔な常体で統一
といった条件を入力しました。
このように具体的かつ明確な条件を入力することで、司法試験問題文の理解や整理に特化した出力を得ることが可能となります。
また、文中に適度に改行を挟むことで視認性が向上し、時系列情報の分析や活用がしやすくなるため、問題文の読み取りや整理作業が円滑になります。
実行結果(GPT-4o)
①20XX年X月X日 午前X時頃/A氏/契約締結
②20XX年X月X日 午後X時頃/B氏/商品引渡し
③20XX年X月X日/C氏/請求書送付 …この出力結果は、特定のイベントや手続きの進捗を時系列で整理した履歴書式となっています。
日付と時間が明確に記載されているため、いつ誰がどのアクションを取ったかが一目瞭然です。
また、文章がシンプルかつ統一されたフォーマットで記載されているため、後から内容を確認する際の検索性や管理が容易です。
実務上のトレーサビリティ確保や、報告書作成時の資料として活用しやすい点も評価できます。
ただし、具体的な詳細情報や補足説明がないため、より深い内容分析や問題点抽出を行いたい場合は、別途補助資料の併用が必要でしょう。
とはいえ、基本的な証跡管理や業務プロセス把握のためのテンプレートとして十分機能すると言えます。
プロンプト4:司法試験の論述添削をするプロンプト
#命令
あなたは司法試験論述添削専門の法曹AIです。以下の論述答案を読み取り、法的評価と論述改善点を具体的かつ分かりやすく指摘してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①設問番号/②指摘箇所(段落または行数)/③問題点の内容/④改善案/⑤評価ポイント(合格に必要な要素の有無)
・論点漏れ、誤認識、論理展開の不備、判例・条文の引用不足などを明確に指摘
・日本の司法試験基準に準拠し、専門用語は正確に用いる
・文章は簡潔かつ明瞭な常体で記載
#入力情報(例)
<ここに論述答案全文を貼付>
#出力例
①設問1/②2段落目/③論点の一つである~の認識が誤っている/④~を正しく理解し、~という判例を引用して論述すること/⑤論点の理解が不十分であり合格点に達していない
司法試験の論述添削をするプロンプトの解説
✅「#命令」の明確化:司法試験論述添削専門の法曹AIであることと、法的評価・論述改善点の具体的かつ分かりやすい指摘を求める
✅「#制約条件」の遵守:出力形式(①設問番号~⑤評価ポイント)や指摘内容(論点漏れ、誤認識、論理不備、引用不足等)を厳守し、簡潔な常体で記載することを再確認
✅「#入力情報」の整備:論述答案全文を正確に貼り付け、評価に必要な情報が完全であることをチェックする
このプロンプトは司法試験の論述答案を専門的に添削する際に活用します。
具体的には、法的評価や改善点を体系的に指摘し、合格に向けたポイントを明確に示したいシーンで役立ちます。
工夫点は「指摘一覧のみ」「簡潔かつ明瞭な常体」で出力することで、添削作業の効率を大幅に向上させる構成になっているところです。
また論点漏れや判例引用不足など、合格基準に即した専門的指摘ができるよう細かい制約を設定しています。
このプロンプトの利用により、従来の添削時間を数時間から数十分に短縮できると期待されます。
法曹AIとして司法試験対策の質を保ちながら作業工数を大幅削減できる点が大きなメリットです。
入力例
#命令
あなたは司法試験論述添削専門の法曹AIです。以下の論述答案を読み取り、法的評価と論述改善点を具体的かつ分かりやすく指摘してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①設問番号/②指摘箇所(段落または行数)/③問題点の内容/④改善案/⑤評価ポイント(合格に必要な要素の有無)
・論点漏れ、誤認識、論理展開の不備、判例・条文の引用不足などを明確に指摘
・日本の司法試験基準に準拠し、専門用語は正確に用いる
・文章は簡潔かつ明瞭な常体で記載
#入力情報(例)
<ここに論述答案全文を貼付>
司法試験論述答案の添削を行うAIとしてのプロンプトを作成した例を紹介します。
今回のプロンプトは、司法試験論述答案全文を入力として受け取り、
・設問ごとに
・問題となる段落や行数を特定し
・法的な問題点や論理の誤りを詳細に指摘し
・具体的な改善案を提示し
・合格に必要な論点の網羅や判例引用の有無などを評価ポイントとして示します。
入力例では「<ここに論述答案全文を貼付>」としてある部分に、実際の答案テキストを貼り付けるイメージです。
この形により、答案の法的評価と添削が、
短く簡潔でありながら、司法試験基準に準拠した専門的な指摘が可能になります。
このユースケースは、
司法試験受験生や指導者が答案の弱点を的確に把握し、合格に必要な論述力を効率的に向上させるのに非常に有効です。
また、改行を入れることで見やすくし、
指摘箇所や内容をひと目で把握しやすくしているため、添削作業や学習効率の向上にもつながります。
実行結果(GPT-4o)
①設問1/②第2段落〜第3段落/③論点漏れ(契約の要素及び効力についての検討不足)、判例引用不足/④契約の成立要件(申し込み・承諾)、意思表示の効力無効事由(錯誤・詐欺等)の検討を加え、最高裁判例を具体的に引用する/⑤契約法に関する基礎的知識の充足
①設問1/②第4段落/③論理展開の不備(原因解釈の誤り)、法的評価の飛躍/④原因は契約の内的理由として位置づけ、錯誤と因果関係の在り方を判例を踏まえて説明し、結論に論理的整合性を持たせる/⑤判例の法理理解と適用力
①設問2/②全文/③条文引用不足、判例・学説の整理不十分/④民法の該当条項(例:民法第709条)の引用を明確に行い、判例・学説の相違点と共通点を整理して論述する/⑤法的根拠の正確な引用と複眼的考察
①設問2/②第1段落/③論点漏れ(損害賠償の範囲・計算方法に関する検討欠如)/④過去の判例を参考に損害賠償の範囲・算定方法について踏み込んだ論述を追加する/⑤損害賠償問題の具体的検討の有無
①設問3/②第2段落/③誤認識(不法行為責任の成立要件に関する誤解)、用語の曖昧さ/④不法行為の要件(違法性、故意過失、因果関係、損害の発生)を明確に整理し、正確な専門用語で説明を補強する/⑤不法行為法の基礎的理解と表現の正確性
この出力結果は、法的論述の精度向上を目指す際に非常に参考になります。
まず、各設問ごとに具体的な段落を対象に論点漏れや論理展開の不備を細かく指摘しているため、文章構成の弱点を明確に把握できます。
さらに、判例や条文の引用不足に着目し、関連法理の具体的な適用を促している点も有益です。
これにより、単に表面的な記述で終わらず、法的根拠に基づく論理的な解説へと深化させることが可能となります。
また、原因解釈の誤りや用語の曖昧さといったミスを摘出することで、専門性の高い表現と正確な理解の両立が期待できます。
総じて、法律文書の品質を高めるための指導ポイントが具体的で、実務や学習の双方において非常に有用なフィードバックだと感じます。
今後は、このような詳細なレビューを踏まえて、根拠の引用や論点整理をより一層丁寧に行うことが重要であると改めて認識させられました。
プロンプト5:司法試験問題作成をするプロンプト
#命令
あなたは司法試験問題作成に特化した法務AIです。以下の要件に沿って、司法試験レベルの問題を作成してください。
#制約条件
・問題は条文解釈、判例適用、事案分析の形式を織り交ぜて作成すること
・問題文は明確かつ詳細に記述し、受験生が具体的な法的判断を求められる内容とする
・設問は複数設け、法律問題点の抽出・適用・解釈を問うこと
・解答例は不要(問題文のみ作成)
・日本法(民法、刑法、商法等)に基づく問題とする
・専門用語は正確に使用し、文章は簡潔かつ論理的であること
#入力情報(例)
・テーマ例:「契約解除に関する問題」「刑事責任の要件について」「会社法における取締役の義務違反」など
#出力内容(例)
【問題文】
(事案説明)
〇〇株式会社のAは、…
(設問)
1. 〇〇に関する法的問題点を指摘しなさい。
2. Aの行為に対する民法上の法的評価を説明しなさい。
3. 判例を踏まえた上で、解決策を論じなさい。
司法試験問題作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」内容の確認:司法試験問題作成に特化した法務AIであることを再確認
✅「#制約条件」の遵守確認:条文解釈、判例適用、事案分析を織り交ぜた問題作成がされているか
✅「#出力内容」の整合性確認:問題文が明確かつ詳細かつ複数設問が設けられているかをチェック
このプロンプトは司法試験対策として、法務AIに高難度の問題を自動生成させたい際に活用します。
特に条文解釈や判例適用、事案分析を織り交ぜる設問を多く含むため、実践的で深い理解を促す問題作成に最適です。
「設問を複数設ける」「具体的な法的判断を求める」など細かい制約があり、受験生が取り組みやすい問題設計が工夫されています。
これにより法務専門家の問題作成作業の負担を大幅に軽減し、従来の作問時間を約70%削減することが期待されます。
テーマを自由に設定できる点も汎用性が高く、様々な分野の司法試験問題作成に即応可能です。
入力例
#命令
あなたは司法試験問題作成に特化した法務AIです。以下の要件に沿って、司法試験レベルの問題を作成してください。
#制約条件
・問題は条文解釈、判例適用、事案分析の形式を織り交ぜて作成すること
・問題文は明確かつ詳細に記述し、受験生が具体的な法的判断を求められる内容とする
・設問は複数設け、法律問題点の抽出・適用・解釈を問うこと
・解答例は不要(問題文のみ作成)
・日本法(民法、刑法、商法等)に基づく問題とする
・専門用語は正確に使用し、文章は簡潔かつ論理的であること
#入力情報(例)
・テーマ例:「契約解除に関する問題」「刑事責任の要件について」「会社法における取締役の義務違反」など
#出力内容(例)
【問題文】
(事案説明)
〇〇株式会社のAは、…
(設問)
1. 〇〇に関する法的問題点を指摘しなさい。
2. Aの行為に対する民法上の法的評価を説明しなさい。
3. 判例を踏まえた上で、解決策を論じなさい。今回は、司法試験問題作成に特化した法務AIに対するプロンプトを作成しました。
そのため、
- 問題形式を「条文解釈」「判例適用」「事案分析」の三つを織り交ぜる
- 問題文は「明確かつ詳細に」受験生が具体的に法的判断を求められる内容とする
- 複数の設問を設け、「法律問題点の抽出」「適用」「解釈」を問う形にする
- 解答例は不要とする
- 対象とする法律は「日本法(民法、刑法、商法等)」
- 専門用語は正確に、文は簡潔かつ論理的に記述する
という要件を入力しました。
このように具体的かつ詳細に要件を指定することで、司法試験レベルの問題文を受験生が理解しやすく、かつ的確に法的思考を促す形式で生成してもらえます。
また、改行を適切に入れることで文章が読みやすくなり、細部の条件や設問の区別が一目で分かるため、問題の完成度が高まるとともに修正もしやすくなります。
実行結果(GPT-4o)
【問題文】
(事案説明)
X株式会社(以下「X社」という。)は、Y株式会社(以下「Y社」という。)との間で、Y社がX社に商品を納入する契約(以下「本契約」という。)を締結した。契約書には、商品の納入期限や品質基準が明記されている。Y社は約束通り納品を開始したが、途中で品質検査に不合格となる製品が続出し、X社は何度か改善を求めたものの、Y社の製品品質は改善されなかった。
X社は本契約の解除を検討し、Y社に対し催告書を送付したが、改善は見られなかった。そこでX社は、民法上の契約解除権を根拠に本契約の解除を通知した。これに対し、Y社は、契約解除は無効であり、解除に伴う損害賠償請求は認められないと主張している。
(設問)
1. 本契約の解除に関して、民法上の契約解除の要件および適用可能性を条文を踏まえて論じなさい。
2. Y社の主張が法的に妥当か、判例を引用して検討しなさい。
3. X社が契約解除を正当化するために必要な催告やその他の手続について、民法の規定に基づき説明しなさい。
4. 仮にX社が解除後に損害賠償請求を行う場合、その法的根拠および請求可能な損害の範囲について論じなさい。
この出力結果は、契約解除に関する民法の適用を法的に詳細かつ体系的に検討するための良質な問題文として機能しています。
契約の背景から解除の要件、Y社の反論を含む具体的な争点までが明確に設定されており、受験者や学習者が民法の条文や判例を活用して論理的に解答を組み立てやすくなっています。
特に、催告行為の必要性や解除後の損害賠償請求の法的根拠に言及する設問が含まれている点は、実務的な視点も踏まえた高度な理解促進に寄与しています。
また、条文や判例の引用を求めることで、知識の正確さや説得力を高める訓練にも最適です。
一方で、問題文がやや長文であるため、回答時には要点を整理して読み解く力も必要とされます。
総じて、契約解除に関する法的議論を深めるうえで非常に有用な教材であり、実務経験者や法学学習者の双方にとって価値の高い内容と評価できます。
ChatGPTで司法試験対策に使えるプロンプト5選のまとめ
司法試験の合格を目指す受験生にとって、効率的な学習方法の確立は重要な課題です。
そこで注目されているのが、ChatGPTを活用したプロンプトの活用法です。
本記事では、司法試験対策に特化したおすすめのプロンプトを5つ厳選しました。
たとえば、過去問の分析や論文作成の練習、要点のまとめ、判例解説、さらには模擬試験のフィードバックなど、多彩な活用が可能です。
ChatGPTは専門的な法律知識を提供するだけでなく、自分の理解度に合わせた解説や問題作成ができるため、効率よく知識を深められます。
また、いつでもどこでもアクセスできるため、自宅や移動中のスキマ時間も学習に充てられます。
さらに、これらのプロンプトを活用することで、独学の弱点を補いながら、実践的な力を養成できる点が大きなメリットです。
司法試験突破に向けて、ChatGPTの活用法をマスターし、最短ルートで合格を目指しましょう。