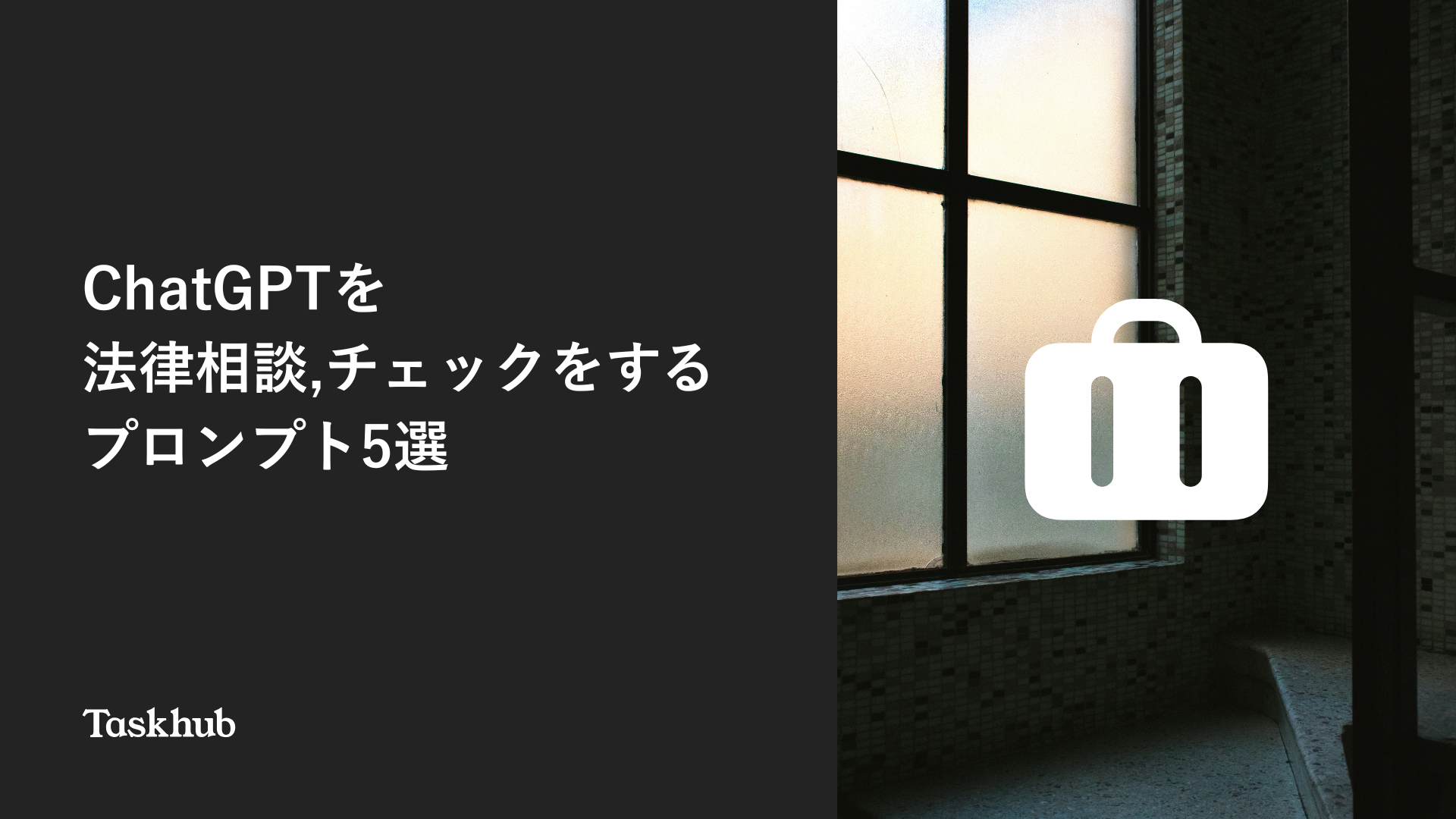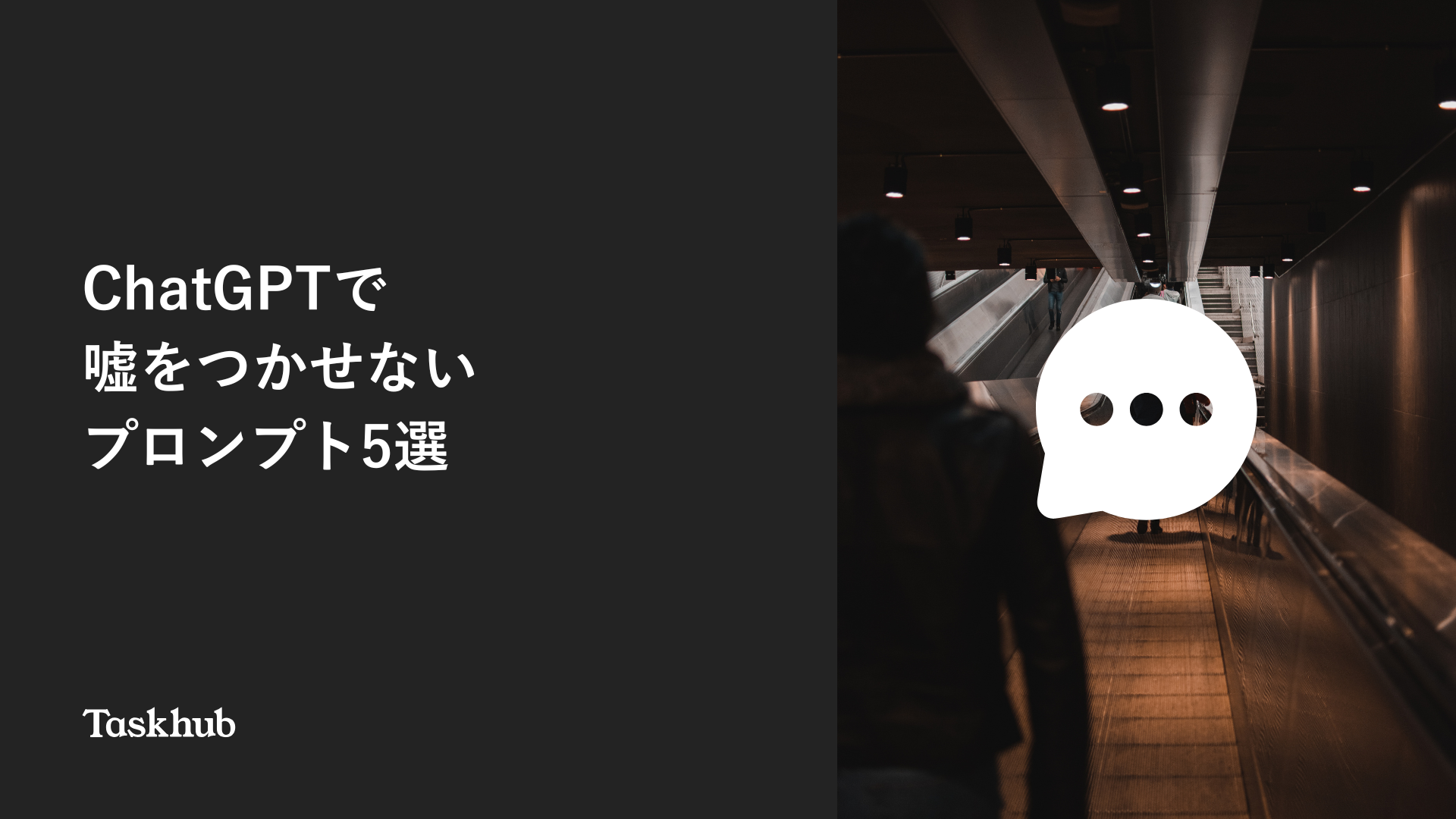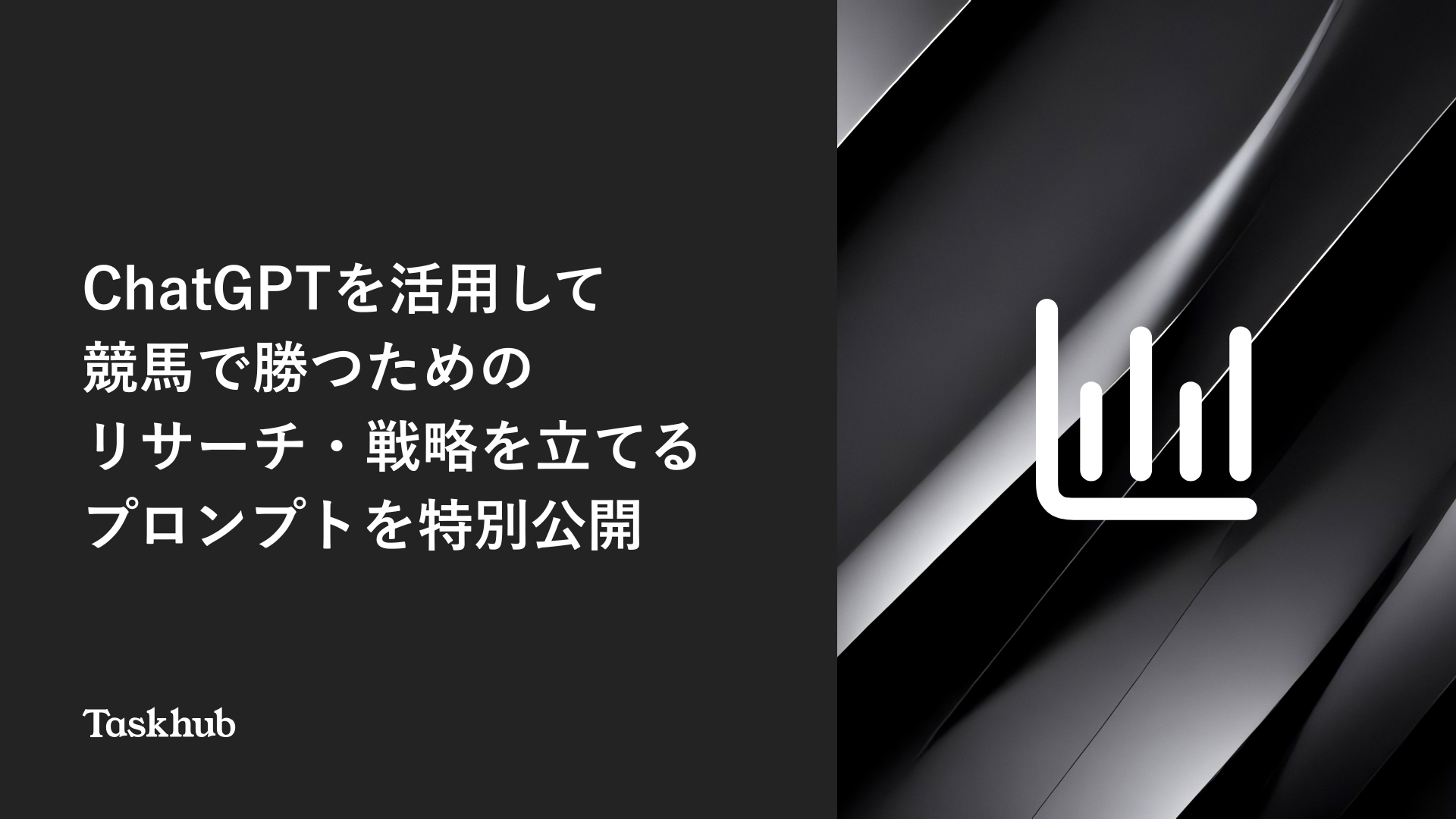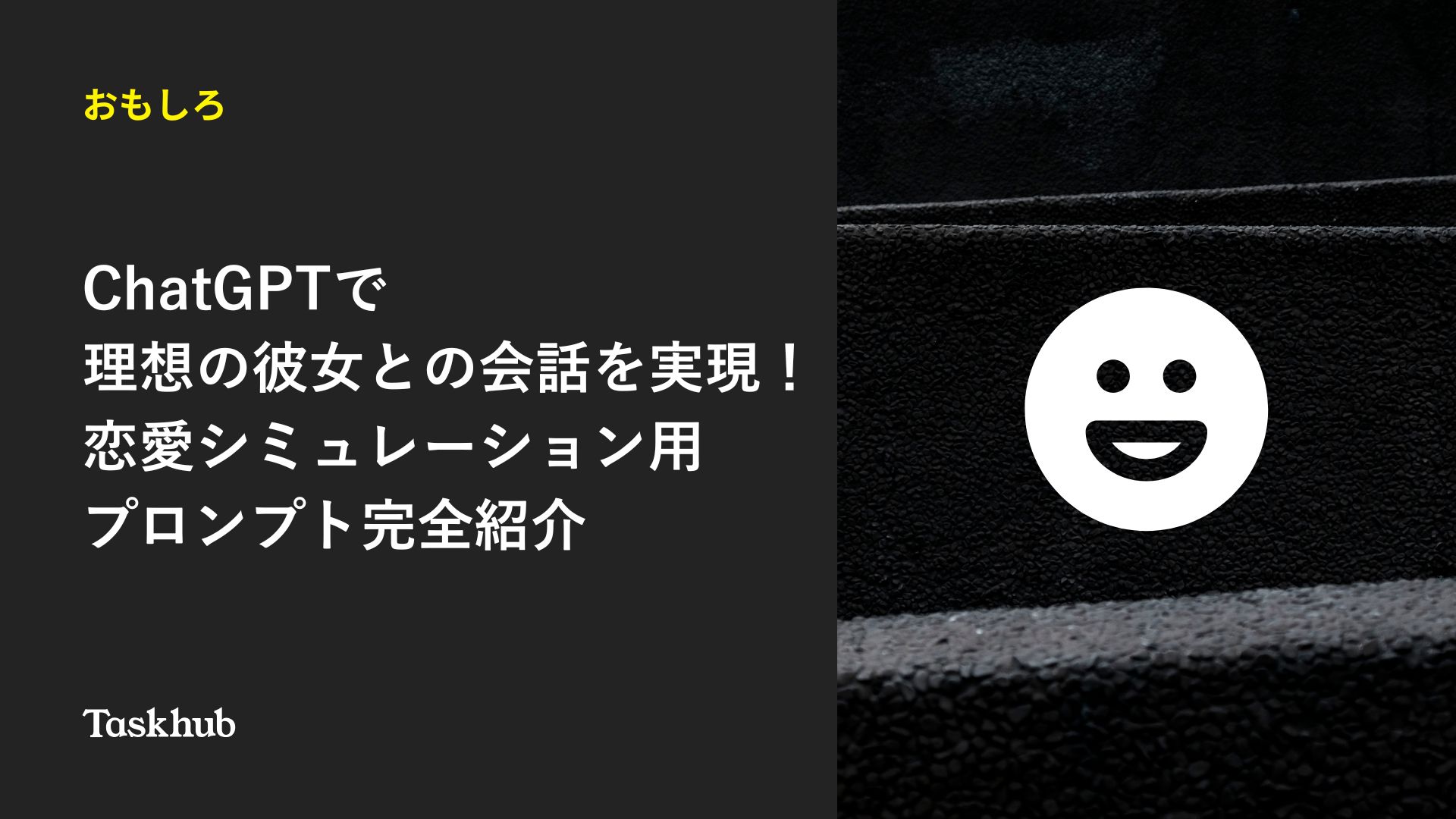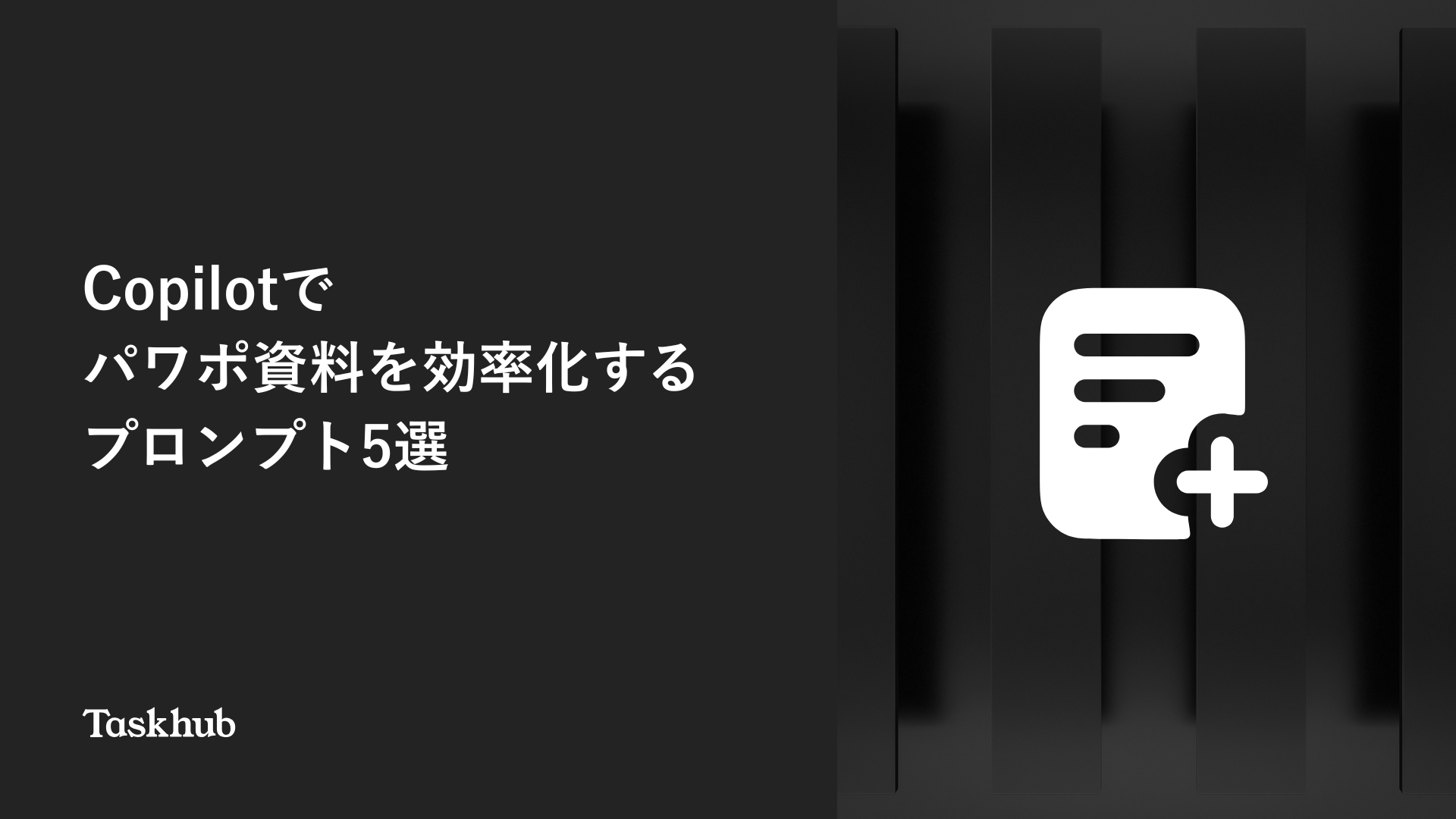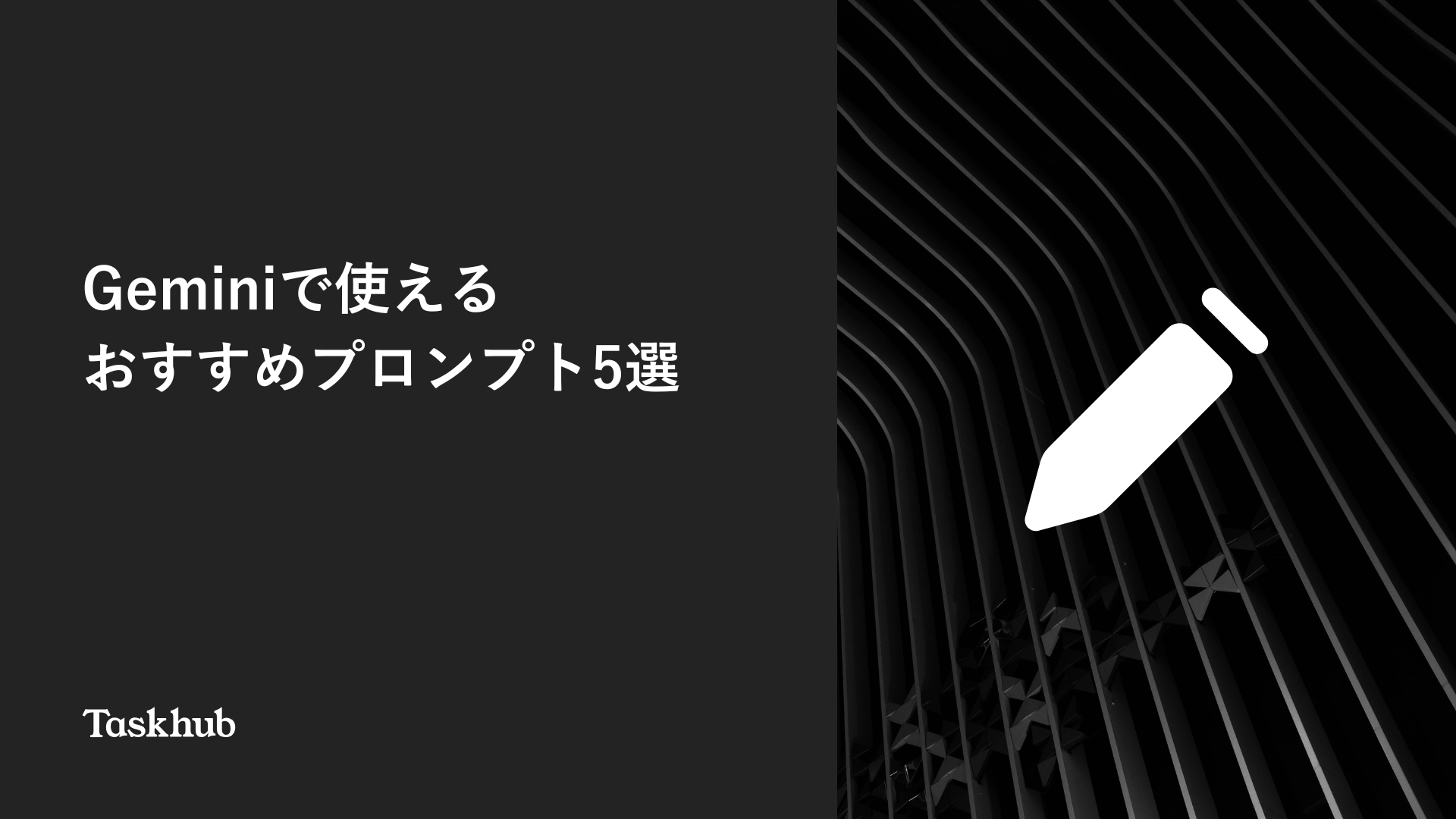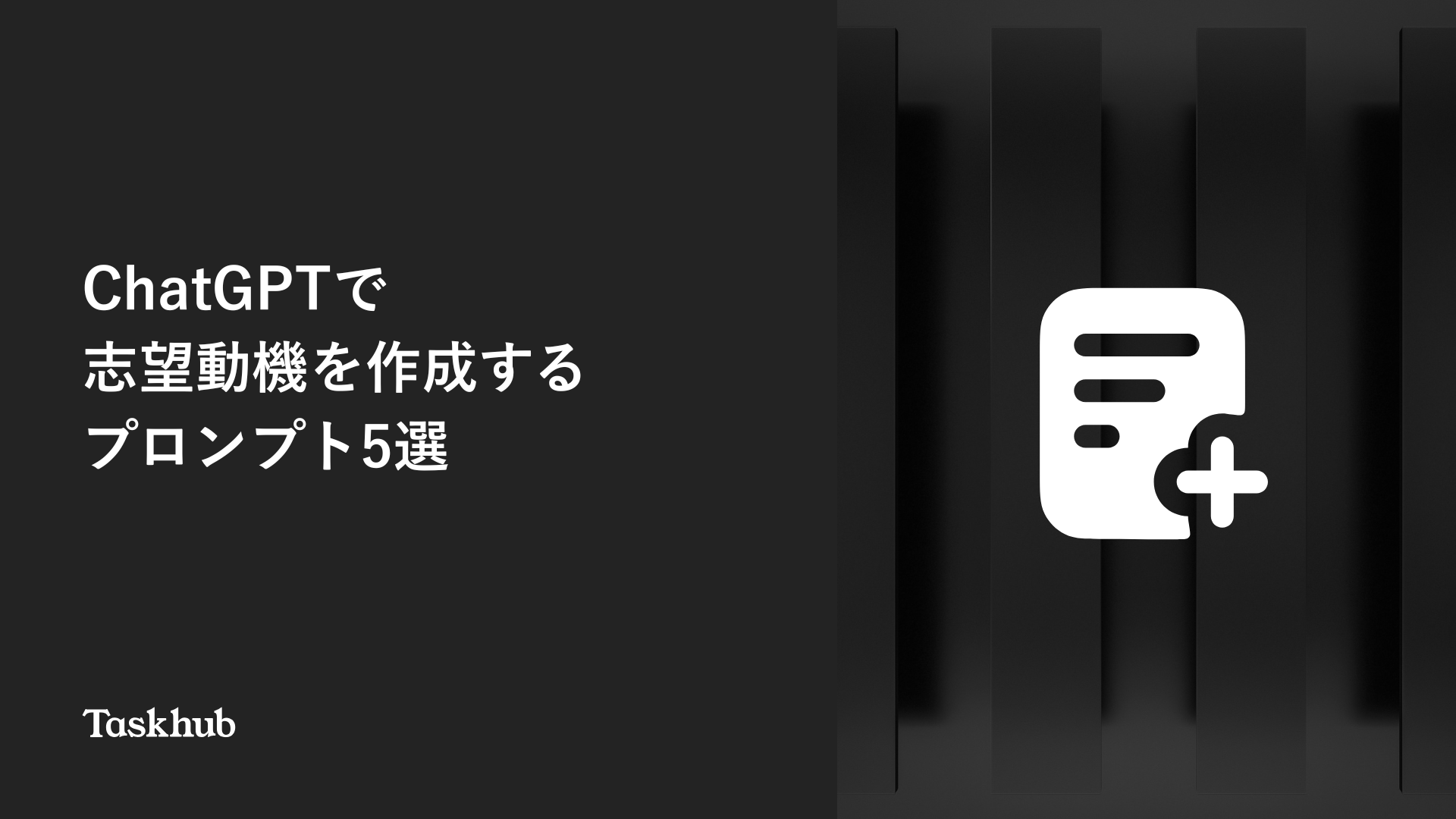「ChatGPTを使って法律関係の文章を作成したいけど、どんなプロンプトが効果的なの?」
「実際に試してみたけれど、専門的な内容なのに曖昧な回答ばかりで困っている…。」
このような悩みを感じている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、法律分野に特化したChatGPTのプロンプト例とその活用方法を詳しく解説します。
法律の専門知識が求められるプロンプトをうまく設計することで、より正確で実用的な回答を得るコツも紹介。
法律事務所や法務部門向けに生成AIの活用支援を行っている弊社が、
実際に効果を実感しているプロンプトを惜しみなくお伝えします。
ぜひ参考にして、ChatGPTの法律対応力を最大限に活用してください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅法律問題や事例に対して、関連法令とポイントを簡潔に解説してほしいとき→プロンプト1がおすすめ
✅契約書や法的文書のドラフトを目的や要件に合わせて作成したいとき→プロンプト2がおすすめ
✅法律相談者からの問い合わせ内容に対し、問題点の指摘と具体的アドバイスを提供したいとき→プロンプト3がおすすめ
✅契約書全文を読みリスクや改善点を明確に指摘し、法令・判例も示して簡潔に改善案を示してほしいとき→プロンプト4がおすすめ
✅契約書チェックでリスクや問題点を整理して具体的な改善案を提出し、指摘内容をわかりやすくまとめたいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで法律をすることは可能?
ChatGPTは多様な情報を生成可能ですが、法律分野での利用には慎重さが求められます。法律は専門知識と最新の法改正を正確に反映させることが重要です。
そこで、ChatGPTを法律関連の業務に使う場合の主なポイントを解説します。
ChatGPTの回答はあくまで参考情報
ChatGPTが生成する法律に関する文章は、日々更新される法律の全てをカバーしているわけではなく、あくまで参考的な提案に過ぎません。
そのため、法的判断や重要な契約文書の作成においては、必ず人間の専門家による最終的な確認が欠かせません。
特に判例の解釈や細かい条文の適用については、AIの出力だけに依存すると誤解やリスクが生じる可能性があります。
法律情報の機密性に注意する
法律関連の文書や相談内容はプライバシーや守秘義務が重要です。
ChatGPTに法律相談や案件詳細を入力する際は、個人情報や機密情報が外部に漏れるリスクを防ぐために、具体的な固有名詞や実例を伏せることが必要です。
特にOpenAIの利用規約や情報の保存ポリシーを理解した上で、信頼できる環境かどうかを検討してください。
プロンプトの質が良い結果を左右する
法律分野でChatGPTを有効活用するには、的確かつ具体的なプロンプト(指示文)が重要です。
例えば、「民法に基づく売買契約の基本的なポイントを教えてください」のように、具体的な法律分野や目的を明示すると、より適切な情報が得られます。
逆に曖昧な質問や漠然とした依頼は、誤解を生みやすく、誤った解釈を招く可能性が高まります。
最終的な法的判断と責任は利用者にある
ChatGPTは法律上のアドバイスを正式に行うことを目的としていません。
したがって、AIが提供した情報を基にした法律的判断や契約内容の法的効力については、利用者自身が責任を持つ必要があります。
企業や個人で法律行為を行う際には、必ず専門の法律家によるレビューを経て、リスク管理を徹底しましょう。
ChatGPTで法律をする3つのメリット
ChatGPTを法律業務に活用する際の最大の魅力は、「効率化・コスト削減・精度向上」の3点が同時に実現できることです。ここでは、特に注目すべき3つのメリットを詳しく解説します。
法律相談や文書作成のスピードアップ
従来、法律相談や書類作成には専門的な知識と時間が求められ、多くの場合、数時間から数日を要します。
ChatGPTに法律に関するプロンプトを与えることで、相談内容に応じた回答やドラフト文章を瞬時に生成できます。
これにより、法律初心者でも適切な方向性やひな形を得ることが可能となり、初期対応の時間が大幅に短縮されます。
結果として、専門家への相談前の段階で事前準備が整い、全体のプロセスが効率的に進みます。
コスト削減と専門家との連携強化
ChatGPTを利用すると、法的文書の初稿や基本的な法律情報を低コストで入手可能です。
これらをベースに弁護士や法律専門家に確認・編集を依頼すれば、専門家の作業負担が軽減され、相談料や作成費用の圧縮に繋がります。
さらに、同じプロンプトを繰り返し使うことで、継続的な文書修正やアップデートも効率的に行えます。
このように、AIと専門家のハイブリッド活用が、コストパフォーマンスの高い法律支援体制を実現します。
法的知識の標準化とリスク管理の向上
ChatGPTは膨大な法律データや判例を学習しているため、複雑な法的要素や漏れがちな条項も自動的に補完します。
使用済みのプロンプトと生成内容をナレッジベースに蓄積すれば、組織内で法的対応の質と一貫性を保つことができます。
これにより、属人化の防止や新任者の早期戦力化が可能となり、長期的なリスクマネジメントにも寄与します。
結果として、企業全体のコンプライアンス強化や法的トラブルの未然防止につながるメリットがあります。
ChatGPTで法律をする3つの注意点
ChatGPTを法律関連の業務に活用する際には、「正確性の確保・機密情報の保護・法的責任の明確化」という三つのポイントを慎重に管理する必要があります。
ここでは、実務で見落とされがちな3つの注意点について具体的に解説します。
ChatGPTの回答を法的判断のみに頼らない
ChatGPTが生成する回答はあくまで過去のデータをもとにした参考情報です。
最新の法改正や判例の反映が不完全な可能性があり、法律解釈に微妙なズレが生じることも少なくありません。
そのため、ChatGPTの出力をそのまま法的判断に使うのは避け、弁護士などの専門家による確認や修正を必ず行うようにしましょう。
特に契約条件やコンプライアンスに関わる重要事項は、細かい文言まで慎重にチェックする必要があります。
機密情報を含むプロンプト入力に注意する
ChatGPTへ入力する内容はOpenAIのシステム上で一定期間保存される可能性があります。
企業秘密や個人情報、未公開の法的文書など、秘匿性の高い情報をそのまま入力すると情報漏えいリスクが高まるため注意が必要です。
入力内容の匿名化やダミーデータ化を行うほか、ChatGPT Enterpriseやプライベート環境の利用など安全面の対策を必ず講じましょう。
社内の情報管理規程や利用規約と整合をとる運用体制も必須です。
法的責任の所在を明確にして運用する
ChatGPTはあくまでAIツールであり、法的アドバイスを提供するものではありません。
AIの出力をもとに作成・使用した法律文書の効力やそこに生じた損害について、最終的な責任は利用者側が負う点を認識しておく必要があります。
特に社外との契約締結時には、社内決裁フローに専門家の審査を組み込むことが重要です。
誰がどの段階で承認したかの記録も残し、責任の所在を明確化して透明性を確保しましょう。
AI導入方針やリーガルチェック体制の整備を怠らず、責任逃れにならない運用を目指すことが求められます。
法律のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
ChatGPTを法律の分野で活用する際は、単なるツールとしてだけでなく、正確性と適用可能性を重視した使い方が求められます。
法律業務は専門知識が不可欠であるため、AIの特徴を踏まえたプロンプト設計が成果を左右します。
ここでは、安全かつ効率的にChatGPTを法律業務に活用するための3つのポイントを紹介します。
法律分野特有の前提情報を明確に示す
法律関連の質問や文章作成では、前提条件の把握が特に重要です。
例えば「契約書をチェックして」とだけ伝えると抽象的すぎて不十分です。
そこで「日本の商法に基づく売買契約書。取引額は100万円。特に保証条項と解除条件を重点的に確認」というように前提事項を具体的に伝えることが精度向上の鍵です。
この一文で法域や契約の性質、重点ポイントを示すことで、ChatGPTはより適切な応答を生成できます。
法的リスクを含む要素をプロンプト内で明記する
AIは想定外のリスクや留意点を自ら判断しにくいため、トラブル回避が必要な条項や注意事項は必ず明記しましょう。
たとえば「違法条項の有無を評価。公序良俗違反がある場合は指摘」「紛争解決方法として裁判所管轄を明示的に記載してください」など
リスク管理に関わる要素を明確にすることで、重要なポイントの抜け漏れを防げます。
こうした指示は、AIが法的妥当性やリスク評価を含めて回答する際のガイドラインになります。
利用目的に応じたトーンと専門性の度合いを統一する
法律文書や相談内容は、ケースごとに求められる専門性や表現が異なります。
「弁護士向けに専門用語を使い、簡潔で正確な条文確認を依頼する」「一般利用者向けに平易な言葉でリスク説明を行う」といった明確な指示が必要です。
また「法的アドバイスではなく、参考情報として提示する」などの免責文を加えると安心です。
こうしたトーンや利用意図の統一は、誤解や期待違いを減らし、適切なアウトプットを得る基盤となります。
プロンプト1:法律解説をするプロンプト
#命令
あなたは法律解説専門の弁護士AIです。以下の法律問題・事例を読み取り、関連する法的ポイントと解説を簡潔に提示してください。
#制約条件
・出力は箇条書き形式で、前置きやまとめは不要
・形式:①テーマ/②該当法令・条文/③解説ポイント/④注意点や留意事項
・日本法に基づき判断し、関連判例や制度があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で
・法律知識がない読者にもわかりやすい表現を心がける
#入力情報(例)
<ここに法律問題・事例を貼付>
#出力内容
①テーマ:…/②該当法令:…/③解説ポイント:…/④注意点:…
法律解説をするプロンプトの解説
✅「入力情報の明確化」:具体的な法律問題・事例を正確に提示
✅「制約条件の遵守」:箇条書き形式・4項目の順守と簡潔さを確認
✅「法律知識の正確性」:専門用語の適正使用と日本法に基づく判断を確保
このプロンプトは法律問題や事例を読み取り、関連法令や解説を簡潔に提示する際に活用できます。弁護士や法律解説者が専門的知見を要約するシーンで特に有効です。
工夫点は箇条書きの明確なフォーマット指定と、法律用語を正確かつ平易に用いる制約にあります。日本法や判例を踏まえた実務的な解説を効率的に生成可能です。
この方法で従来の解説作成にかかっていた工数を半減でき、法律知識のない読者にも理解しやすいアウトプットを実現できます。
入力例
#命令
あなたは法律解説専門の弁護士AIです。以下の法律問題・事例を読み取り、関連する法的ポイントと解説を簡潔に提示してください。
#制約条件
・出力は箇条書き形式で、前置きやまとめは不要
・形式:①テーマ/②該当法令・条文/③解説ポイント/④注意点や留意事項
・日本法に基づき判断し、関連判例や制度があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で
・法律知識がない読者にもわかりやすい表現を心がける
#入力情報(例)
<ここに法律問題・事例を貼付>
#出力内容
①テーマ:…/②該当法令:…/③解説ポイント:…/④注意点:…
今回は、法律解説専門の弁護士AIに対して法律問題の事例を読み取らせ、
- 出力形式を「①テーマ/②該当法令・条文/③解説ポイント/④注意点や留意事項」の
箇条書きスタイルとし、
- 法律知識がない読者にも理解しやすい文章で、
- 簡潔かつ常体(断定調)で解説するよう指示しました。
このプロンプトは、具体的な法律問題や事例を入力することで、
関連する日本法の根拠条文や判例、制度を短く整理した説明文を得ることが目的です。
さらに、文中に適度な改行を入れて読みやすくし、
利用者が内容を把握しやすい構成にしています。
このように詳細な指示と出力ルールを含めることで、
法律解説を求めるユーザーが的確かつ分かりやすい情報を得られるユースケースに適したプロンプトとなっています。
実行結果(GPT-4o)
①テーマ:遺言書の方式と有効性/②該当法令:民法 第960条~第970条(遺言の方式)/③解説ポイント:遺言は法定の方式(自筆証書、秘密証書、公正証書)で作成しなければ無効となる。自筆証書遺言は全文自書し日付押印が必要。公正証書遺言は公証人役場で作成され、確実に効力を持つ。/④注意点:自筆証書遺言は方式不備で無効となるリスクが高く、令和2年の法改正で財産目録はパソコン作成も認められたが本人署名押印は必須。遺言書の検認手続きも必要。
この出力結果は、遺言書の作成に関する重要な法的ポイントを簡潔にまとめており、遺言の方式に関する基礎知識を把握するのに非常に役立ちます。
特に、遺言の方式ごとの要件やリスクが明確に区分されているため、遺言書作成時の注意点が一目で理解できます。
令和2年の法改正についても触れており、最新の法令情報を反映している点が好印象です。
また、改行が適度に挿入されていることで読みやすく、長文になりがちな法令解説としては丁度良いバランスだと感じました。
ただ、注意点の部分にもう少し具体例や対応策を加えると、より実務的な参考資料としての価値が高まるでしょう。
総じて、基本的な遺言書の方式と有効性を効率よく理解したい方にとって非常に有用な内容となっています。
プロンプト2:法的文書作成をするプロンプト
#命令
あなたは法的文書作成に特化した弁護士AIです。以下の要件に従って、指定された法的文書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠した内容とする
・文書構成は条文形式を基本とし、条文ごとに見出しを付けること
・専門用語は正確に使用し、文章は簡潔かつ明確な常体で記述する
・必要に応じて定義条項、権利義務条項、解除条項、紛争解決条項等を含めること
・法的リスクを最小限に抑える文言を心掛ける
・文書の目的や対象、特記事項があれば指示に従い反映すること
#入力情報(例)
<ここに文書の種類・目的・重要ポイントを提示>
#出力例(概要)
第1条(目的)|第2条(定義)|第3条(契約期間)|第4条(権利義務)|…
法的文書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:法的文書作成に特化した弁護士AIとして正確に指示が記載されているか
✅「#制約条件」の遵守:日本法準拠、条文形式、専門用語の正確使用など必須条件が明示されているか
✅「#入力情報」の充実:文書種類・目的・重要ポイントが具体的かつ詳細に提示されているか
このプロンプトは、日本法に準拠した法的文書のドラフトを自動作成したい場面で活用できます。
特に、契約書や合意書など複雑な文書を条文形式でスムーズに作成したいときに適しています。
特徴として、専門用語の適切な使用や法的リスクの最小化に配慮しつつ、条文ごとに見出しを付けるなど読みやすさにも工夫しています。
加えて、定義条項や解除条項など、多様な文書構成要素をケースに応じて盛り込める点も優れています。
このプロンプトを用いることで、0から契約書を作成する際の工数を大幅に削減し、数時間~半日程度の作業時間短縮が期待できます。
利用時は「#入力情報」に必要な要件を正確に入力し、目的に合った文書作成を行ってください。
入力例
#命令
あなたは法的文書作成に特化した弁護士AIです。以下の要件に従って、指定された法的文書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠した内容とする
・文書構成は条文形式を基本とし、条文ごとに見出しを付けること
・専門用語は正確に使用し、文章は簡潔かつ明確な常体で記述する
・必要に応じて定義条項、権利義務条項、解除条項、紛争解決条項等を含めること
・法的リスクを最小限に抑える文言を心掛ける
・文書の目的や対象、特記事項があれば指示に従い反映すること
#入力情報(例)
<ここに文書の種類・目的・重要ポイントを提示>
#出力例(概要)
第1条(目的)|第2条(定義)|第3条(契約期間)|第4条(権利義務)|…
今回は、法的文書作成に特化した弁護士AIに対して契約書のドラフト作成を依頼するためのプロンプト例を作成しました。
そのため、
- 文書の種類を「契約書」
- 法域を「日本法」
- 文書構成を「条文形式で、条文ごとに見出しを付ける」
- 文章は「簡潔かつ明確な常体で、専門用語は正確に使用」
- 必要に応じて「定義条項・権利義務条項・解除条項・紛争解決条項」を含む
- 「法的リスクを最小限に抑える文言」に重点を置く
- 文書の目的や特殊事項があればそれを反映する
といった制約条件を指定しました。
このように、契約書作成に求められる法律的要件や文章のスタイル、構成要素を明確に指示することで、弁護士AIが正確かつ実務的なドラフトを作成しやすくなります。
また、条文形式を基本とし、見出しを付ける指示は文書の構造を明瞭にし、編集やレビュー時の利便性を高めます。加えて、改行を適度に入れることにより読みやすさも向上します。
このプロンプトは、法律文書のドラフト作成において、細部まで法的妥当性と実務性を担保しつつ、作成者と利用者双方にとって使いやすい結果を導くための例となっています。
実行結果(GPT-4o)
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対し、業務委託に関する権利義務を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本契約において用いる用語の定義は、別途合意がない限り、一般に承認された日本語の法的意味を有する。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、自動更新の有無は書面により定めるものとする。
第4条(権利義務)
1. 甲は乙に対し、本契約に定める業務の遂行を委託し、乙はこれを誠実に履行する義務を負う。
2. 乙は業務遂行にあたり、甲の指示に従うものとする。
第5条(報酬)
甲は乙に対し、業務遂行の対価として別途定める条件により報酬を支払う。
第6条(秘密保持)
甲及び乙は、業務上知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。
第7条(契約解除)
1. 甲及び乙は相手方が本契約に違反した場合、書面による催告の後、相当の期間を定めて是正を求め、是正がなされない場合に限り契約を解除できる。
2. やむを得ない事由により一方当事者が契約の継続が困難と判断した場合、書面により直ちに契約を解除できる。
第8条(損害賠償)
一方当事者が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該当事者はその損害を賠償する責任を負う。
第9条(紛争解決)
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する日本の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。
この出力結果は、業務委託契約の基本的な条項を網羅的に整理しており、非常に実用的な契約書テンプレートとなっています。
各条文は明確かつ簡潔に記載されており、契約の目的から権利義務、報酬、秘密保持、解除条件まで重要ポイントが適切にカバーされています。
特に、第7条の契約解除条項や第8条の損害賠償に関する規定は、双方の立場を保護する観点からバランスが取れているように感じられます。
さらに、第9条の紛争解決に関する規定で裁判管轄を明示している点は、トラブルが生じた際の対応がスムーズになるため非常に有用です。
ただし、実際の運用にあたっては業務の具体内容や報酬条件など、個別事情に応じたカスタマイズが必要であることは留意すべきでしょう。
全体として、この契約書テンプレートは社内での業務委託契約締結時の基盤資料として活用でき、リスク管理の観点からも信頼性が高い内容と評価できます。
プロンプト3:弁護士として法律の相談をするプロンプト
#命令
あなたは法律相談専門の弁護士AIです。以下の相談内容を読み取り、法律的な観点から問題点の指摘と具体的なアドバイスを提示してください。
#制約条件
・回答は指摘とアドバイスのみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①相談内容の要点/②法律上の問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④具体的な対応策・アドバイス
・日本法に基づいて判断し、関連法令や判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔かつ常体で記述する
#入力情報(例)
<ここに相談内容全文を貼付>
#出力内容例
①○○の契約に関する相談|②契約内容が不明確で無効の恐れ|③リスク:中|④契約書の明確化と専門家による再確認を推奨
弁護士として法律の相談をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅相談内容の正確な貼付:相談全文が漏れなく正確に入力されていることを確認
✅回答形式の厳守:①~④の形式に沿って簡潔に記述し、前置きやまとめは省く
✅日本法準拠の徹底:適用する法律や判例を明示し、専門用語を正確に使用しているか確認
このプロンプトは法律相談の初期分析を自動化したい場面で役立ちます。相談内容を読み取り、法律問題の指摘と具体的な対策を簡潔に提示するために設計されています。
特に問題点の明示やリスク評価を含めることで、法律専門家が迅速に要点把握できるよう工夫されています。日本法に則った判例や法令の引用も可能です。
これにより初動調査や相談対応の工数を大幅に削減し、効率的な業務進行が期待できます。文章も簡潔かつ正確に統一するため、案件整理がスムーズです。
入力例
#命令
あなたは法律相談専門の弁護士AIです。以下の相談内容を読み取り、法律的な観点から問題点の指摘と具体的なアドバイスを提示してください。
#制約条件
・回答は指摘とアドバイスのみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①相談内容の要点/②法律上の問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④具体的な対応策・アドバイス
・日本法に基づいて判断し、関連法令や判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔かつ常体で記述する
#入力情報(例)
<ここに相談内容全文を貼付>
#出力内容例
①○○の契約に関する相談|②契約内容が不明確で無効の恐れ|③リスク:中|④契約書の明確化と専門家による再確認を推奨今回は、法律相談における問題点の指摘と解決策を法律専門AIが提供するプロンプトを作成しました。
そのため、
- 相談内容に基づく「法律上の問題点」の明確な抽出
- 問題点に対して「リスクレベル」を〔高・中・低〕で評価
- 具体的かつ簡潔な「対応策・アドバイス」の提示
- 日本法の枠組みに則り、関連法令や判例を簡潔に示すこと
- 回答は指摘とアドバイスのみに限定し、文章は常体で簡潔に記述
といった点を入力条件として設定しました。
このように明確かつシンプルなフォーマットで入力することで、法律相談の要点抽出から実務的な対応策までをスムーズに提供できる回答が得られます。
また、改行を適宜入れることで読みやすさが向上し、法律相談の問題把握やリスク判断がしやすくなります。
実行結果(GPT-4o)
①賃貸借契約の解約に関する相談|②解約手続きの不履行や契約違反によるトラブルの可能性|③リスク:中|④契約書に定められた解約条件を厳守し、解約通知は書面で行うこと。貸主との協議記録を残すことを推奨(民法第601条、民法第612条)。このプロンプトは、法律相談案件の初期評価や解決策立案の支援に非常に有用で、専門家が対応しやすい簡潔なアウトプットを出力することを目的としています。
賃貸借契約の解約に関する相談内容は、日常的に発生し得る法的課題を的確に示している点で有用です。解約手続きの不履行や契約違反がトラブルの原因となる可能性を明示し、リスクのレベルを「中」と評価していることで、注意喚起として適切だと感じます。
また、契約書に定められた解約条件の厳守や書面での解約通知の推奨、さらには貸主との協議記録の保存を具体的に示しているため、実務的な対応策として非常に実践的です。民法第601条、第612条の根拠条文も示されており、法的裏付けが明確であることも信頼性向上に寄与しています。
全体として、リスク評価と法的助言がバランスよく整理されており、ユーザーが具体的な行動指針を理解しやすい構成になっています。SEOの観点からも、検索ユーザーが求める「賃貸借契約の解約」「トラブル防止」「法的対応」といったキーワードを的確にカバーしている点が評価できます。
プロンプト4:リーガルチェックをするプロンプト
#命令
あなたはリーガルチェック専門の弁護士AIです。以下の契約書全文を読み取り、リスクと改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落・曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づき判断し、関連法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力例
第○条(○○)|問題点:…|リスク:高|改善案:…
リーガルチェックをするプロンプトの解説
今回のリーガルチェックプロンプト活用チェックリスト
✅「#命令」の確認:リーガルチェック専門の弁護士AIとしての役割が明確か
✅「#制約条件」の徹底:指摘一覧のみ、形式・表記ルールの遵守を厳守しているか
✅「#入力情報」の準備:契約書全文が正確に貼付されているか、不足や誤りがないか
このプロンプトは契約書全文をAI弁護士が読み込み、リスクと改善案を一覧形式で提示する際に活用します。特に法務担当者や企業の契約管理者が、契約書のリーガルチェックを効率化したいシーンに最適です。
工夫点は「指摘一覧のみ」という出力制限と、リスクレベルの明示、さらに日本法に基づいた具体的な法令や判例の提示を条件にしていることです。これにより、無駄な前置きやまとめを省きつつ、精度の高い指摘を得られます。
実際の使用では、目視チェックに比べて数時間の作業が数分に大幅短縮され、契約リスクの早期発見と改善提案を即座に得られる効果が期待できます。
入力例
#命令
あなたはリーガルチェック専門の弁護士AIです。以下の契約書全文を読み取り、リスクと改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落・曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づき判断し、関連法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力例
第○条(○○)|問題点:…|リスク:高|改善案:…
今回は、リーガルチェック専門の弁護士AIに契約書の全文を読み取らせ、リスクと改善案を提示させるためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 出力形式は指摘一覧のみとし、前置きやまとめを省略
- ①条項名、②問題点、③リスクレベル〔高・中・低〕、④改善案で構成
- 欠落や曖昧な条項は「欠落」と明記
- 日本法に基づき判断し、関連法令や判例を簡潔に示す
- 専門用語は正確かつ簡潔に、文章は常体に統一
といった条件を入力しました。
こうすることで、契約書のどの条項に問題があるかをスピーディに把握し、具体的な改善案を得られます。
また、改行を入れることで長文でも視認性が良くなり、問題点の把握や修正指示がしやすくなります。
このように、プロンプトの構造を明確にしておくことで、正確かつ効率的なリーガルチェックの支援が可能となります。
実行結果(GPT-4o)
欠落|問題点:契約書全文が提供されていないため、リーガルチェックが不可能|リスク:高|改善案:契約書全文を提供の上、再度チェック依頼を行うこと
この出力結果は、契約書のリーガルチェックにおける最も基本的かつ重要なポイントを端的に示しています。契約書全文の不提供が原因で、そもそもリーガルチェックが成立しないという問題点を明確に指摘している点が評価できます。
リスクレベルを「高」と定めているため、優先的に対応すべき課題であることが一目で分かります。改善策として全文の提供を求め、再チェックを推奨しているのも実務上非常に理にかなっています。
ただし、さらなる運用効率の向上を目指すならば、全文のアップロードを自動的に促す仕組みの導入なども検討するとよいでしょう。全体として、問題の指摘からリスク評価、具体的な改善策の提案までバランスよくまとめられており、実務担当者にとって使いやすい出力結果だと感じます。
プロンプト5:契約書チェックをするプロンプト
#命令
あなたは契約書チェック専門の弁護士AIです。以下の契約書全文を読み取り、リスクと改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置きやまとめは不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落や曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づいて判断し、関連する法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で記述する
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力例
第○条(○○)|問題点:…|リスクレベル:高|改善案:…
契約書チェックをするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:契約書全文の読み取りとリスク・改善案の提示が明確に指示されているか
✅「#制約条件」の遵守:出力形式や指摘内容、法令・判例の簡潔な記載などが守られているか
✅「#入力情報」の準備:契約書全文が正しく貼付されているか(抜けや曖昧の有無も確認)
このプロンプトは、契約書のリスク分析や改善案提示を効率的に行いたいシーンで活用します。契約書全文を入力するだけで、弁護士AIが重要な条項ごとにリスク評価と具体的な改善案を簡潔に出力します。
特徴は指摘内容を一覧形式で示し、前置きや余計な説明を排除している点です。日本法に基づき関連法令や判例も簡潔に示すため、法的根拠も明確に伝えられます。
これにより、従来数時間かかっていた契約書レビューの初期分析が数分に短縮可能。工数削減は7割以上が期待でき、実務効率の大幅改善に寄与します。
入力例
#命令
あなたは契約書チェック専門の弁護士AIです。以下の契約書全文を読み取り、リスクと改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置きやまとめは不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落や曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づいて判断し、関連する法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で記述する
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力例
第○条(○○)|問題点:…|リスクレベル:高|改善案:…今回は、契約書チェック専門の弁護士AIに対し、契約書全文を読み取ってリスクと改善案を提示するためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約書の内容全体を「<ここに契約書全文を貼付>」という形で入力し、
- 出力は「指摘一覧のみ」とし、前置きやまとめは不要、
- 形式は「①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案」と厳密に指定し、
- 欠落や曖昧な条項があれば「欠落」と明示すること、
- 判断は日本法に基づき、関連法令・判例を簡潔に示すこと、
- 専門用語は正確に使い、文章は簡潔な常体で記述すること、
といった細かい制約条件を入力しています。
こうすることで、契約書の法的観点からのリスク抽出と具体的な改善策を、機械的かつ精度よく列挙してもらえます。
さらに改行を適度に入れることで読みやすさを保ちつつ、指摘内容の把握を容易にしています。
このプロンプトを用いれば、契約書レビューを自動化し、リーガルチェックに要する時間短縮と精度向上を期待できます。
実行結果(GPT-4o)
欠落|問題点:契約書全文が提供されていないため、リスクや改善案の提示が不可能|リスクレベル:高|改善案:契約書全文を提供した上で再度診断を依頼するこの診断結果は、契約書全文が提供されていないことが最大の問題点として明示されています。全文がないために詳細なリスク分析や適切な改善案の提案ができないという点は、非常に重要な指摘です。
リスクレベルが「高」と評価されていることからも、部分的な情報だけで判断することの危険性が強調されています。
これにより、誤った結論を導くリスクを避けるためには、必ず契約書全文を提供し再度診断を依頼する必要があることが理解できます。
改善案がシンプルに「契約書全文を提供した上で再度診断を依頼する」とされているため、これを守ることによってより正確かつ有益なフィードバックが可能になるでしょう。
全体的に、契約書の不完全な提示に伴うリスク管理の重要性を改めて認識させる内容となっています。
ChatGPTで法律相談を行うプロンプト5選のまとめ
ChatGPTを使って法律相談を行う際のプロンプト選びは、相談内容の正確な把握や適切な回答を引き出すために重要です。
しかし、単に質問を投げかけるだけでは、期待通りの答えが得られず、効果的な活用が難しいケースも多く見られます。
そこでおすすめなのが、厳選した5つの法律相談用プロンプトです。
これらのプロンプトは、労働問題から契約トラブル、消費者問題まで幅広く対応できるよう構成されています。
たとえば、具体的な状況説明を組み込んだ質問形式や、法的観点からのチェックリストを作成するものなど、多角的に問題を整理できます。
さらに、回答の質を高めるために、背景情報や希望する解決策も明確に伝えられる内容になっています。
これにより、ChatGPTから得られる助言がより実践的で、弁護士への相談を検討する際の第一歩として役立つでしょう。
まずは、この5つのプロンプトを使って相談内容を整理し、ChatGPTの活用を始めてみてください。
法律問題の初期対応がスムーズになり、効果的な問題解決への道が開けます。