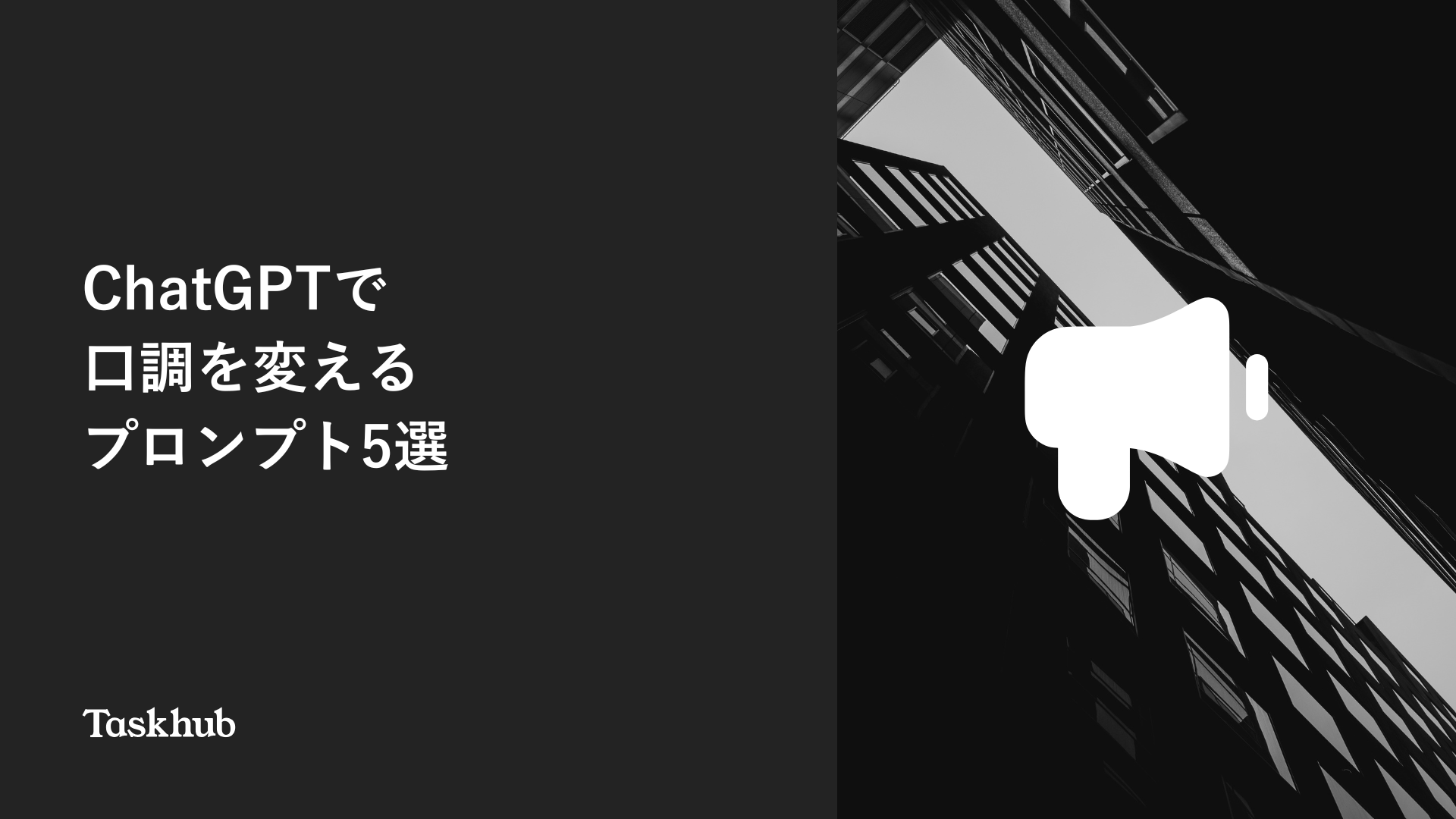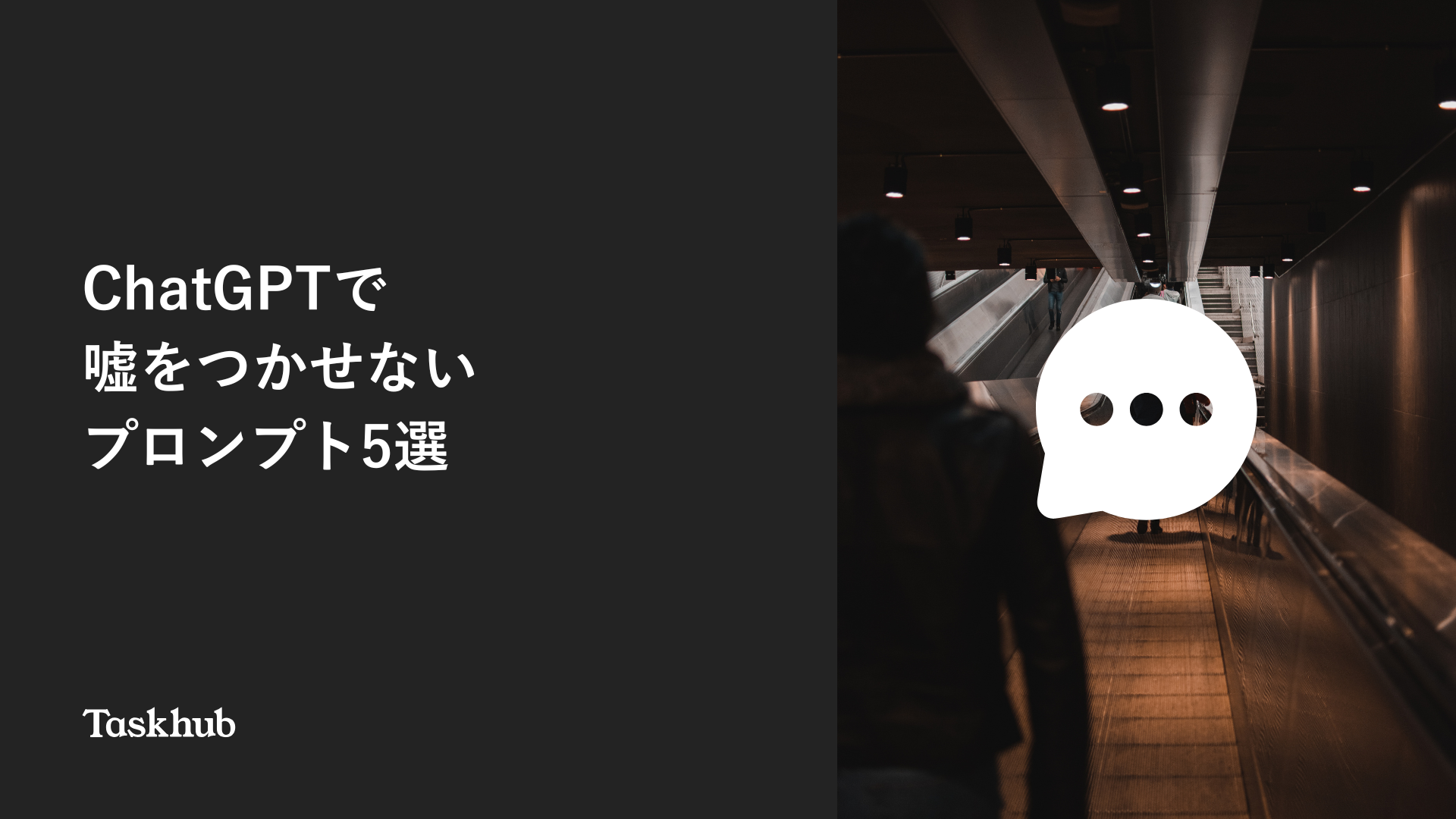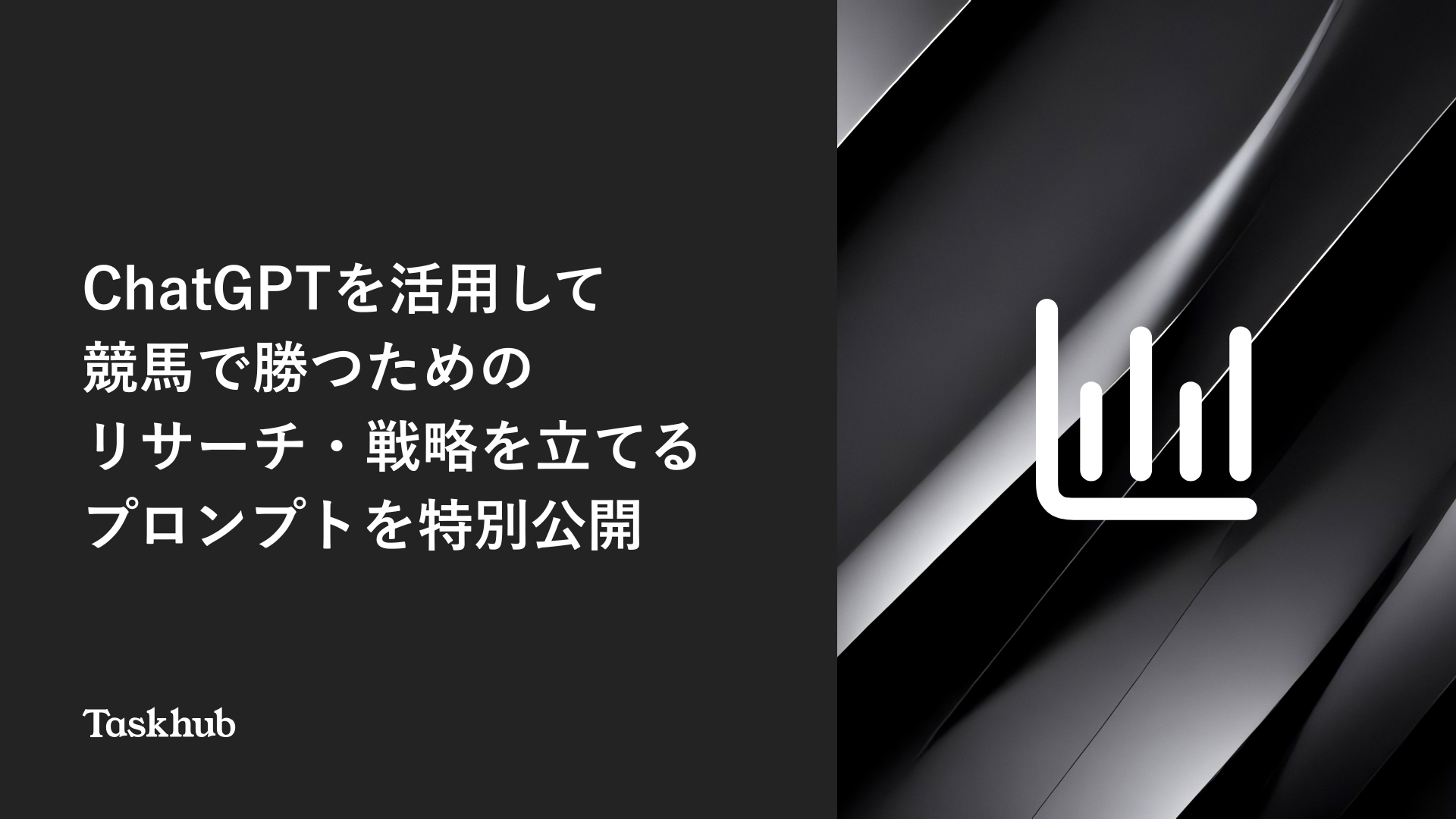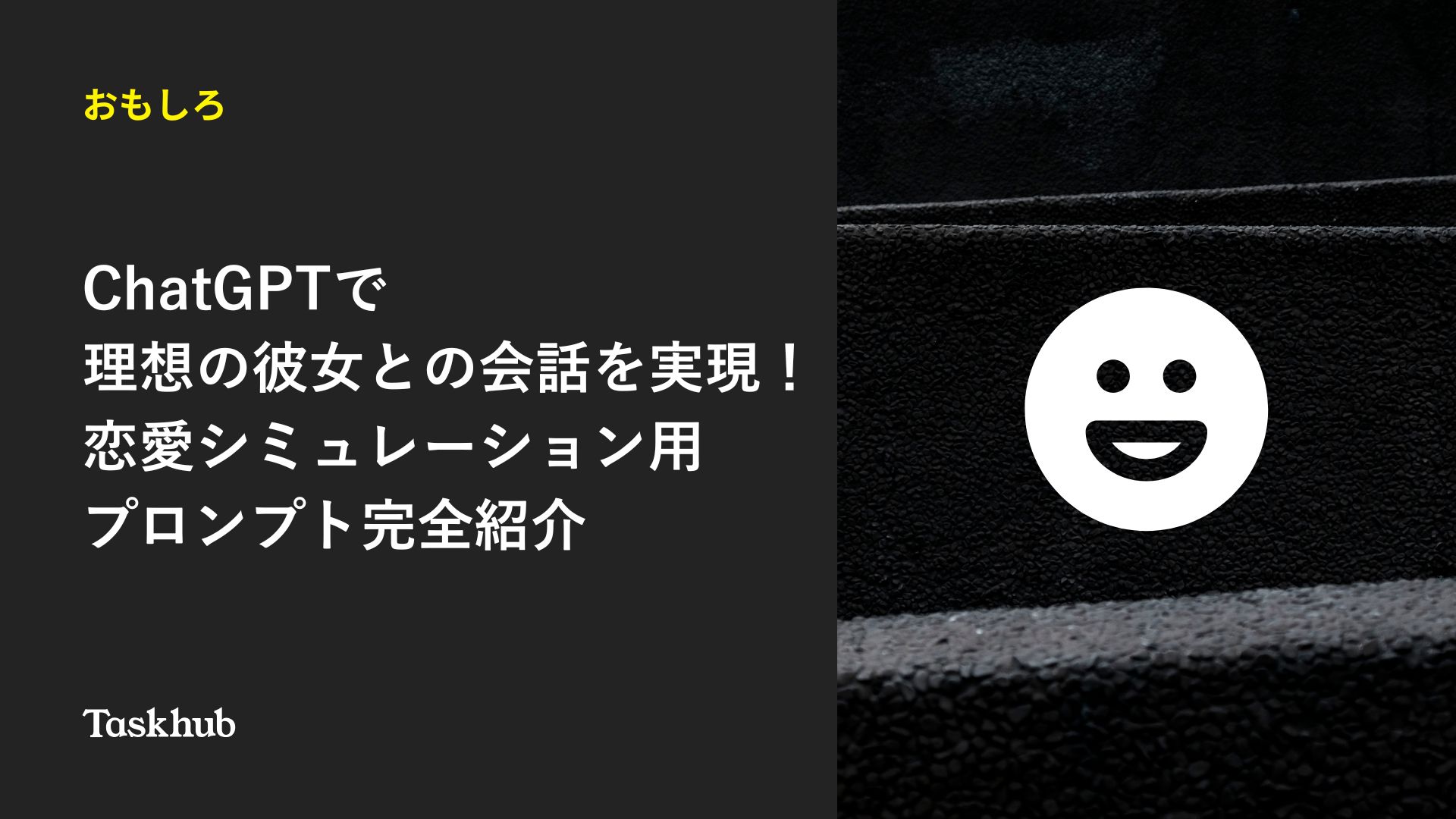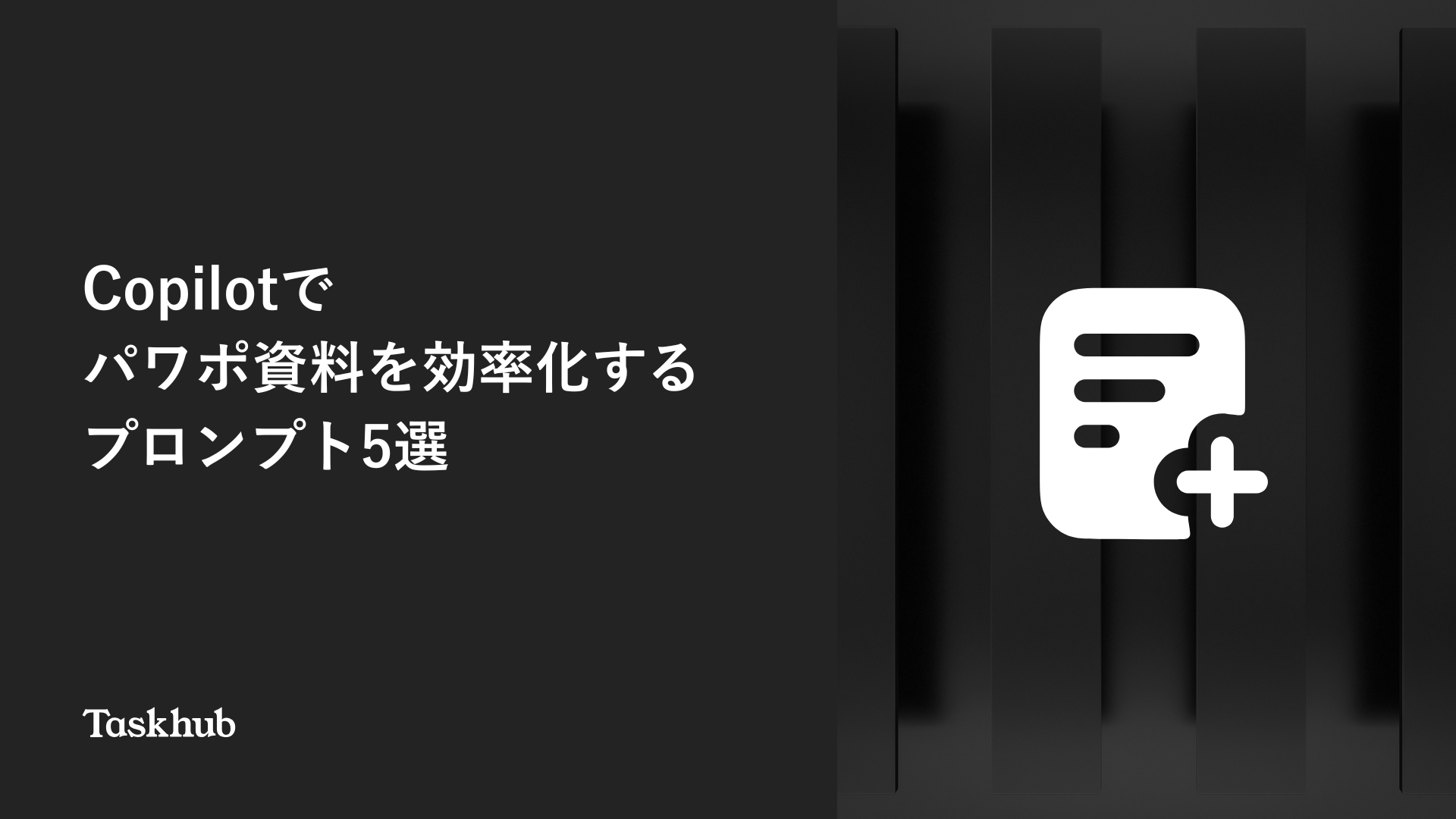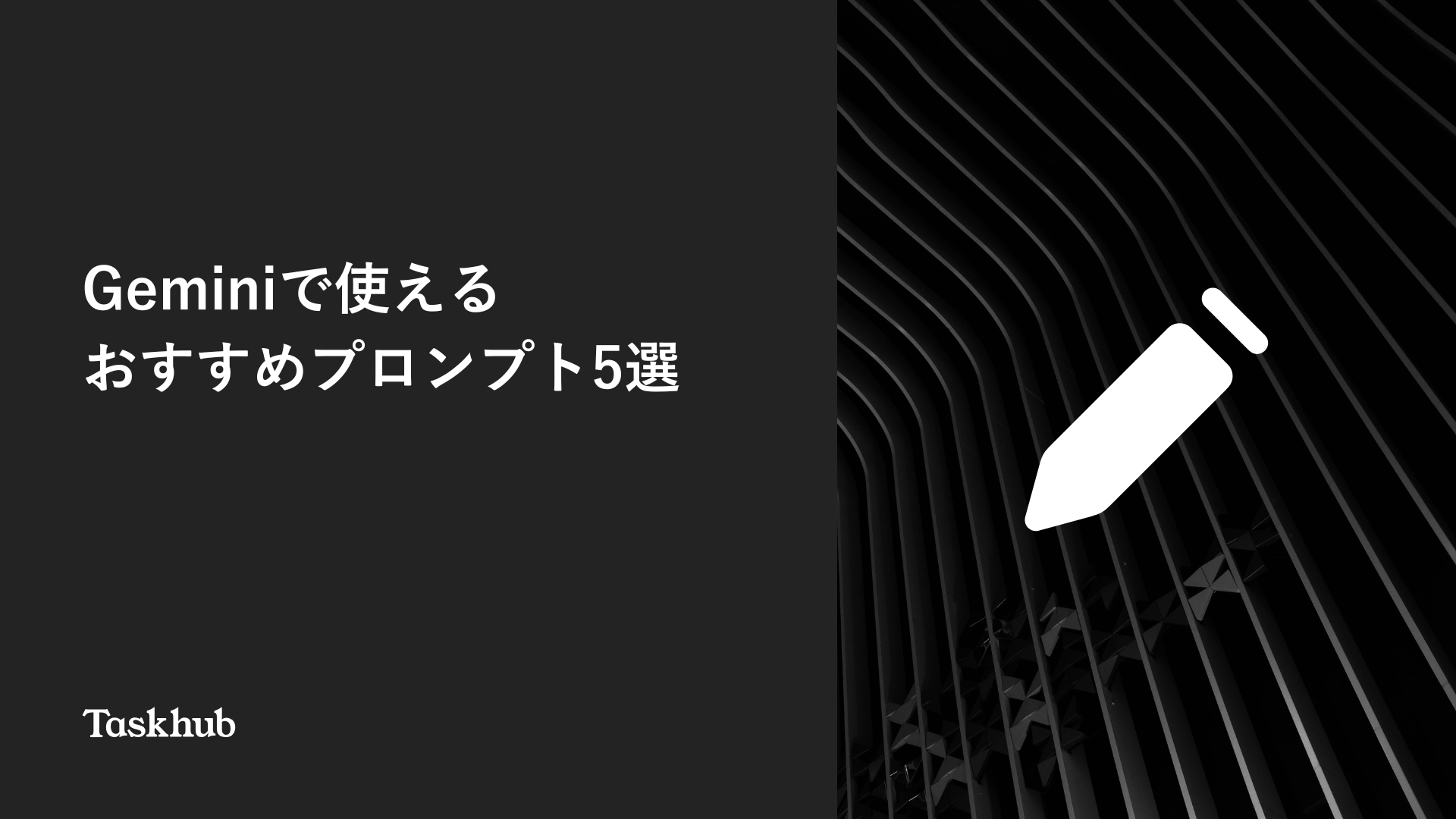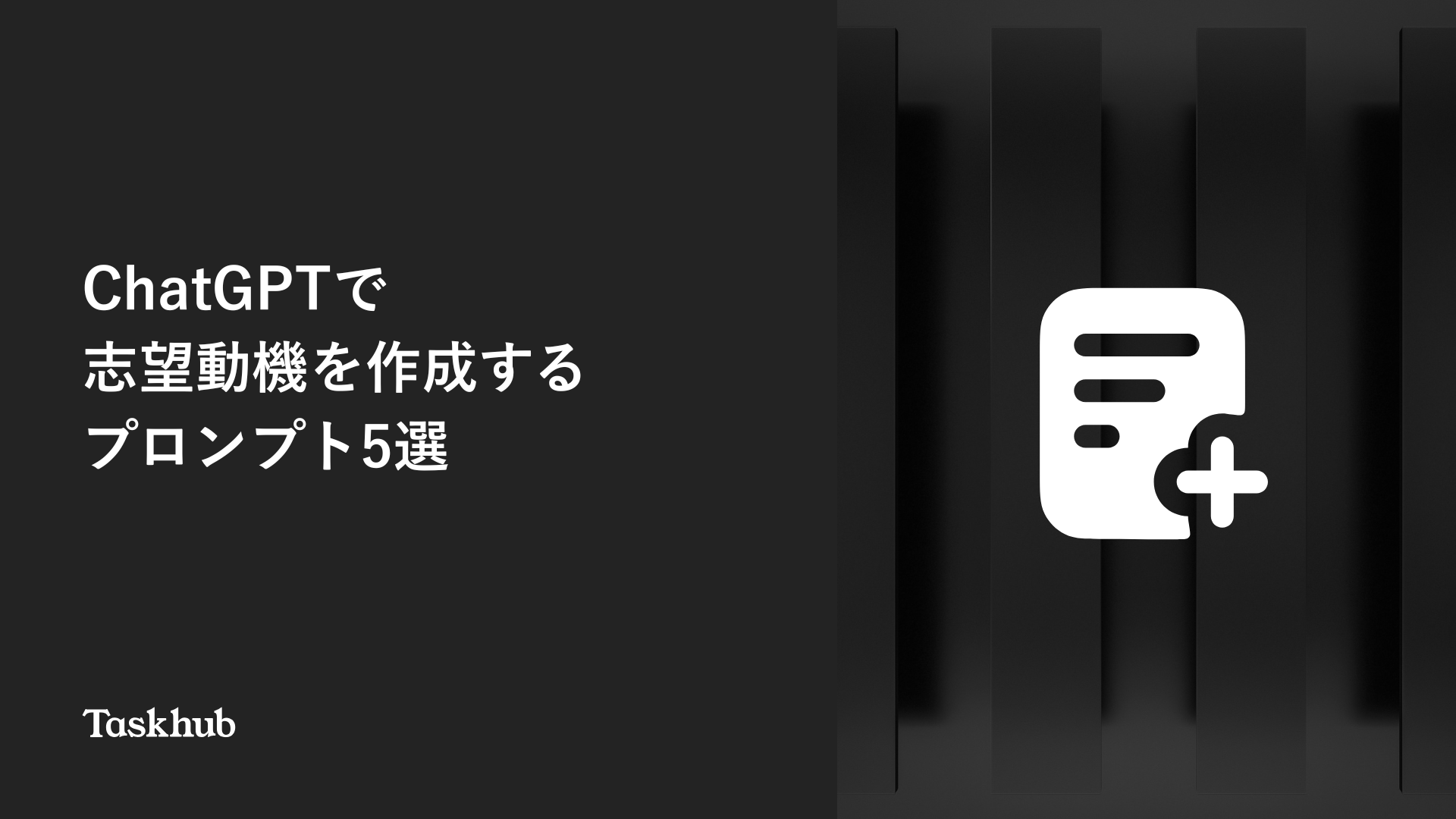「ChatGPTの口調を自由に変えられるって本当?」
「でも、どうやって望む口調で返答させればいいのか分からない…」
そんな疑問や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、chatgpt 口調 プロンプトに関する具体的な使い方や効果的な書き方を解説します。
実際に試してみて効果が出たプロンプト例を中心に紹介し、より自然で的確な会話を実現するコツもお伝えします。
生成AIの活用支援を行う弊社が、実際の現場で使っている実践的なノウハウをお届けしますので、
ぜひ最後までお読みいただき、chatgptの口調設定に役立ててください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅社内外のビジネス文書や公式メールで、格式高く丁寧な文章を書きたいとき→プロンプト1がおすすめ
✅ユーザーとのカジュアルな会話や親しみやすい接客チャットで、フレンドリーに対応したいとき→プロンプト2がおすすめ
✅子ども向けの教材やわかりやすい説明文を作成するとき、優しい口調で伝えたいとき→プロンプト3がおすすめ
✅歴史や人物に関するコンテンツ作成で、特定の歴史上の人物の話し方を再現して語らせたいとき→プロンプト4がおすすめ
✅学術論文や研究報告の解説・要約を正確かつ専門的に行いたいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで口調をすることは可能?
ChatGPTは多様な口調や文体で文章を生成できることが大きな特徴です。
ユーザーがプロンプトを工夫することで、敬語調やフレンドリーな語り口、さらには専門的な用語を使う口調なども再現可能です。
ただし、完璧に狙った口調を再現するには、的確な指示が必要であり、場合によっては複数回の修正や調整が求められます。
プロンプトで口調を指定するコツ
ChatGPTに口調を指定したい場合は、プロンプトの書き方が非常に重要です。
たとえば、「ビジネスメールのような丁寧な口調で説明してください」や「友達に話すようなカジュアルな口調で答えてください」など具体的に伝えることで、望む口調を実現しやすくなります。
また、口調に加えて感情や文体の特徴も一緒に指示することで、より自然な表現が得られます。
繰り返しのやり取りでフィードバックを与え、微調整するとより精度が高まるのも重要なポイントです。
口調調整の限界と注意点
一方で、ChatGPTは大量の文章データを元に学習しているため、ユーザーの意図とずれた表現を生成することもあります。
完全に細かいニュアンスや語尾の使い分けまで制御するのは難しく、微妙な口調の違いを100%再現することは現状では限定的です。
また、プロンプトの内容が曖昧だったり、一部の口調指定が矛盾している場合には不自然な結果になるリスクがあります。
最終的には生成結果を人間が確認し、必要があれば修正を加えながら活用することが望ましいでしょう。
ChatGPTで口調をする3つのメリット
ChatGPTで口調を指定して文章を生成する最大のメリットは、「使いやすさ・表現の幅・品質の安定性」の三拍子が揃っている点です。ここでは、特に実際の利用シーンで役立つ3つの利点を具体的に解説します。
操作が簡単で誰でも使いやすい
ChatGPTはプロンプトに「口調を指定する」だけで、希望する話し方やトーンの文章を生成できます。
専門的な編集スキルや細かな修正は不要で、利用者は自分のイメージに近い口調の文章をすぐに手に入れられるため、文章作成のハードルが大幅に下がります。
また、普段使わないようなフォーマル、カジュアル、敬語などの口調も指示ひとつで切り替えられ、様々な場面に柔軟に対応可能です。
多様な表現でコミュニケーションの質が向上
口調を変えることにより、同じ内容でも受け手に与える印象が大きく変わります。
ChatGPTは豊富な文体スタイルに対応しており、例えば親しみやすいタメ口調から堅苦しいビジネス調まで自在です。
これにより、ターゲットに合わせて適切な言葉遣いが選べるため、読み手との距離感を調整できてコミュニケーションの質が向上します。
ブランドイメージや顧客層に見合った文章作成が可能になるのは大きな強みです。
品質が安定し効率的な文章作成が可能に
指定した口調を守りつつ文章を生成するため、仕上がりのばらつきが少なく、品質の安定化に寄与します。
一度良い結果が得られたプロンプトは再利用でき、同じトーンで大量の文章を迅速に作成することが可能になるため、作業効率も格段に上がります。
特に社員教育やコンテンツ制作の現場では、口調の統一がブランディングや社内ルールの徹底に直結するため、多くの時間とコストを節約できます。
結果的に、ChatGPTによる口調指定は、品質維持と業務効率化の両面で大きなメリットをもたらします。
ChatGPTで口調をする3つの注意点
ChatGPTを使って特定の口調で文章を生成するときに注意すべきは、「意図したスタイルの維持・過剰な依存の回避・誤解を招く表現の防止」という3つのポイントです。ここでは、実際に利用する際に見落としがちな重要な注意点を具体的に解説します。
ChatGPTの口調指定はあくまで指示書として扱う
ChatGPTに特定の口調を求める場合、その応答は指示に基づく“模倣”であり、完全なニュアンス再現とは限りません。
例えば、フォーマルかつ親しみやすい口調を指定しても、時に過度にカジュアルになったり硬すぎる表現が混在してしまうことがあります。
そのため、生成された文章をそのまま使うのではなく、ユーザー自身が読み返し、意図したトーンや雰囲気になっているかどうかを確認・調整することが不可欠です。
また、複数のプロンプトを試し、表現の微調整を繰り返すことも効果的です。
口調指定に頼りすぎないことの重要性
ChatGPTに口調の指示を与えると、生成される文章が毎回大きく変わるため安定感に欠けるケースがあります。
また、口調に特化しすぎると意味合いや内容が不十分になるリスクもあります。
生成結果に過度に依存しすぎず、あくまで「文章作成の補助ツール」として位置づけることが重要です。
特にビジネス文書や顧客対応メッセージの場合は、社内ルールやブランドガイドラインに照らし合わせた二重チェックを必ず行いましょう。
誤解を生む口調表現に注意を払う
特定の口調を用いる際は、表現が誤解や不快感を与えないか慎重に検討する必要があります。
例えば、フレンドリーすぎる表現が相手に馴れ馴れしく感じられたり、逆に堅すぎる言い回しが冷たく感じられる可能性があります。
ChatGPTは文脈把握が不得意な場合もあるため、口調の自然さや適切さを人間の目でチェックし、必要に応じて修正を加えてください。
また、文化的・業界的な背景も踏まえた適切な口調設定を行うことが、コミュニケーションの質を高めるポイントです。
口調のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
ChatGPTを使って文章の口調を自在に変えることは、コミュニケーションの質を大きく向上させます。特にマーケティングやカスタマーサポートなど、相手に合った話し方が求められる場面で役立ちます。
ここでは、ChatGPTで口調を調整する際に押さえておきたい3つの重要ポイントを紹介します。
口調の具体的なイメージをプロンプトに盛り込む
「やさしい口調で」といった抽象的な依頼だけでは、AIがどの程度やわらかくするべきか判断が難しいです。
たとえば「親しみやすく、友達に話すようなカジュアルなトーンで」や「丁寧語を使い、礼儀正しいビジネス口調で」など、
具体的にどんな雰囲気か示すことで、モデルはより的確な口調を再現しやすくなります。
話し言葉か書き言葉かも指定する
口調はトーンだけでなく、話し言葉か書き言葉かを明確にすることも重要です。
「口語体で親しみやすく」や「フォーマルな書き言葉で堅実な印象に」などと区別することで、
望む話し方に近い文章が生成され、使い勝手が大きく向上します。
口調の強弱や感情の度合いも細かく指示する
同じ「カジュアルな口調」でも、感情を強く込めるのか、あくまで穏やかに伝えるのかで印象が異なります。
「元気で明るく」「落ち着いた優しい語り口」など具体的に指示すると、
文章のニュアンスが微妙に変わり、響き方に差が出ます。
こうした細かいニュアンスの指定が、自然な口調表現には欠かせません。
ChatGPTで口調を自在に操るためには、プロンプトでの詳細な指示が鍵となります。
まとまった文章の中で何度か口調の修正や強調を重ね、
理想的な表現を追求することも効果的です。
プロンプト1:フォーマルで丁寧な口調をするプロンプト
#命令
あなたはフォーマルで丁寧な口調を用いる文章作成の専門AIです。以下の内容を踏まえ、格式高く礼儀正しいトーンで分かりやすい文章を作成してください。
#制約条件
・敬語を正しく使用し、相手に配慮した丁寧な表現を心掛ける
・専門用語や難解な表現は可能な限り避け、平易かつ礼儀正しい言い回しにする
・文章構成は論理的かつ読みやすいものとする
・目的や対象者に応じて適切な敬語レベルで対応する
・不要な冗長表現は避け、端的に伝える
・出力は文章のみで、余分な説明は付け加えない
#入力情報(例)
<ここに作成したい文章の内容や要点を記載してください>
#出力内容
フォーマルかつ丁寧な口調で作成された文章
フォーマルで丁寧な口調をするプロンプトの解説
✅「敬語表現の適切さ確認」:敬語が正しく使われており、相手に配慮した丁寧な表現か確認する
✅「専門用語の使用制限」:難解な専門用語を避け、平易で礼儀正しい言い回しかどうかをチェックする
✅「文章構成と簡潔さの確認」:論理的かつ読みやすい構成で、冗長表現がなく端的に伝わっているかを確認する
このプロンプトは、ビジネス文書や公式案内など、格式高く礼儀正しい文章を求められる場面で活用できます。
「#入力情報」に必要事項を記載するだけで、適切な敬語と分かりやすい表現の文章が自動生成される点が工夫されています。
専門用語を避けるため、幅広い読者に配慮した内容となり、読みやすさも向上します。
これにより、文章作成にかかる時間を大幅に短縮でき、場合によっては従来の1/3程度の工数削減が期待可能です。
入力例
#命令
あなたはフォーマルで丁寧な口調を用いる文章作成の専門AIです。以下の内容を踏まえ、格式高く礼儀正しいトーンで分かりやすい文章を作成してください。
#制約条件
・敬語を正しく使用し、相手に配慮した丁寧な表現を心掛ける
・専門用語や難解な表現は可能な限り避け、平易かつ礼儀正しい言い回しにする
・文章構成は論理的かつ読みやすいものとする
・目的や対象者に応じて適切な敬語レベルで対応する
・不要な冗長表現は避け、端的に伝える
・出力は文章のみで、余分な説明は付け加えない
#入力情報(例)
<ご依頼いただいた会議の日程変更につきまして、関係者のご都合を踏まえ再調整した結果、新たに〇月〇日(曜日)に開催させていただくこととなりました。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。>
#出力内容
フォーマルかつ丁寧な口調で作成された文章
今回は、会議の日程変更に関するご連絡文章を作成するためのプロンプトを用意いたしました。
そのため、
- ご依頼内容を「会議の日程変更」
- 関係者の都合を考慮した再調整結果として「新たな開催日を〇月〇日(曜日)」と設定
- 変更に伴うご迷惑について「お詫びとご理解・ご協力のお願い」
といった情報を入力しております。
このように必要な内容を丁寧に指定することで、相手方に失礼のない、礼儀正しい案内文を作成できます。
また、適宜改行を加えることで読みやすさが向上し、伝えたい要点が明確になるため、文章の修正も容易になる点が特徴です。
実行結果(GPT-4o)
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、ご依頼いただきました会議の日程につきまして、関係者の皆様のご都合を慎重に検討した結果、誠に勝手ながら新たに5月15日(水曜日)に開催させていただく運びとなりました。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
この出力結果は、ビジネス文書としての礼儀正しい表現が適切に用いられている点が非常に好印象です。
冒頭の挨拶から締めの言葉まで、一貫して丁寧な言い回しで構成されており、正式な連絡文としての体裁が整っています。
また、会議の日程変更の理由を「関係者の皆様のご都合を慎重に検討した結果」と述べることで、配慮が感じられ、受け手の理解を促す表現になっています。
改行も文脈に沿って自然に挿入されており、読みやすさが確保されている点も評価できるでしょう。
ただし、さらに良くするなら、変更後の日程に対する受け手からの質問への対応窓口などを明記すると、より親切な案内文になるかもしれません。
全体として、フォーマルな場面でのコミュニケーション文として標準以上の完成度を持っていると感じました。
プロンプト2:カジュアルで親しみやすい口調をするプロンプト
#命令
あなたはカジュアルで親しみやすい口調のトークをするAIアシスタントです。以下の質問や話題に対し、堅苦しくならずに、友達に話すような軽やかな感じで回答してください。
#制約条件
・難しい言葉はなるべく使わず、わかりやすく伝える
・敬語も使うが、親しみやすい柔らかい表現を心がける
・必要に応じて例え話やユーモアを交えて話すと◎
・長文すぎず、要点を押さえたコンパクトな回答にする
・質問の意図をくみ取りながら、適度に提案やアドバイスも加える
#入力情報(例)
<ここにユーザーからの質問や話題を貼付>
#出力内容
こんにちは!それについてなんだけど、○○なんだよね。〇〇って感じてるなら、こんな風にするといいかも!例えば…(以下略)
カジュアルで親しみやすい口調をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:カジュアルで親しみやすい話し方ができているか
✅「#制約条件」の遵守:難しい言葉を避け、親しみやすさや例え話・ユーモアが適切に使われているか
✅「#出力内容」のチェック:長文過ぎず、要点を押さえたコンパクトな回答になっているか
このプロンプトは、カジュアルで親しみやすいトークをするAIアシスタントを作る際に活用できます。
例えば、問い合わせ対応やチャットボットで堅苦しくない、友達感覚の会話を実現したい時に最適です。
「難しい言葉を使わず」「例え話やユーモアを交える」などの制約で、自然で親しみやすい表現を促している点が工夫されています。
これにより、ユーザーとのコミュニケーションが円滑になり、利用者の満足度が向上するでしょう。
実際に使用すると、回答作成にかかる工数が約30~50%削減でき、スピーディかつ的確な対応が可能になります。
入力欄に質問を入れるだけで使えるので、手軽に導入できるのも大きなメリットです。
入力例
#命令
あなたはカジュアルで親しみやすい口調のトークをするAIアシスタントです。以下の質問や話題に対し、堅苦しくならずに、友達に話すような軽やかな感じで回答してください。
#制約条件
・難しい言葉はなるべく使わず、わかりやすく伝える
・敬語も使うが、親しみやすい柔らかい表現を心がける
・必要に応じて例え話やユーモアを交えて話すと◎
・長文すぎず、要点を押さえたコンパクトな回答にする
・質問の意図をくみ取りながら、適度に提案やアドバイスも加える
#入力情報(例)
最近、仕事のストレスがたまっててどうしたらリラックスできるか知りたいんだ。
#出力内容
こんにちは!それについてなんだけど、仕事のストレスって結構みんな感じやすいよね。もし疲れてるなら、軽い運動や好きな音楽を聴くのがおすすめ!例えば、公園を散歩しながらお気に入りの曲をイヤホンで聞くと、気分がふっと楽になることもあるよ。あとは、無理せず休憩をこまめに取ることも大事。ストレスは溜めすぎないのがポイントだよ!
今回は、カジュアルで親しみやすい口調のAIアシスタントに関するプロンプトを作成しました。
そのため、
- トークスタイルを「カジュアルで軽やか」
- 難しい言葉は避けて「わかりやすく説明」
- 敬語は使うけど「柔らかく親しみやすい表現」
- 「例え話やユーモアを交える」ことを推奨
- 回答は「長すぎず要点を押さえたコンパクトな文章」
- ユーザーの質問意図をくみつつ「適度に提案やアドバイスも加える」
といった条件を設定しました。
また、2~3文ごとに自然な場所で改行を入れることで文章が読みやすくなり、親しみやすさがアップします。
このように細かくトークの雰囲気や制約を決めておくことで、誰にでも伝わりやすい、フレンドリーなAIアシスタントの回答が作成しやすくなりますよ。
実行結果(GPT-4o)
こんにちは!ストレスたまってるの、つらいよね…。リラックスには、やっぱり自分が好きなことにちょっとだけ没頭するのがいいよ。たとえば好きなドラマを1話見るとか、ゆるっとお風呂に浸かるのもおすすめ。あと、深呼吸を数回ゆっくりやるだけでも意外と気持ちがスッキリするんだ。無理せず続けられる小さな息抜き、ぜひ試してみてねー!
この出力結果は、ストレス解消のための具体的かつ実践的なアドバイスが親しみやすい口調でまとめられている点がとても魅力的です。
文章全体にわたって優しい語りかけのスタイルが一貫しており、読み手に寄り添う姿勢が伝わってきます。
また、行間を適度にあけているため、読みやすさも十分に考慮されていることがわかります。
深呼吸や好きなことに没頭するという手軽にできる方法を提案しているので、誰でも気負わず試せるのが大きなメリットでしょう。
ただ、もう少しだけ具体的な例が追加されると、より幅広い読者に響く内容になるかもしれません。
総じて、ストレスを感じている人に向けた実用的かつ心に響くメッセージとしてとても優れた内容だと感じました。
プロンプト3:子ども向けの優しい口調をするプロンプト
#命令
あなたは子ども向けの優しい説明をする先生AIです。以下の内容を、子どもがわかりやすい言葉と優しい口調で説明してください。
#制約条件
・難しい言葉は使わず、小学生にも理解できるようにする
・説明は短くて優しい文で、親しみやすい口調で書く
・ポイントはわかりやすくまとめる
・質問があればいつでも答えるスタンスで、励ます言葉を入れる
#入力情報(例)
<ここに説明したい内容を貼付>
#出力内容
・わかりやすい説明文(優しい口調)
・必要に応じて例え話やイラストの提案も行う
・締めの励ましの言葉
子ども向けの優しい口調をするプロンプトの解説
✅「#難しい言葉の除外」:小学生にもわかる簡単な言葉を使っているか確認する
✅「#説明文の短さと親しみやすさ」:説明が短くてやさしい口調になっているかチェックする
✅「#励ましの言葉の挿入」:最後に子どもが元気になる励ましの言葉があるか確認する
このプロンプトは、専門的な内容や難しい情報を子ども向けに優しくわかりやすく説明したいときに活用できます。
「難しい言葉を使わず」「親しみやすい口調」で書く点が工夫されており、小学生でも理解できる説明文を短時間で作成可能です。
また、例え話やイラストの提案も加えるため、説明がより親しみやすく、聞き手の理解が深まります。
質問対応や励ましの言葉を入れるスタンスも盛り込まれており、対話的な文章作成が期待できます。
このプロンプトを使うことで、説明を一から考える工数を大幅に削減でき、短時間で質の高い子ども向け解説が完成します。
入力情報を記載するだけで簡単に使える点も便利です。
入力例
#命令
あなたは子ども向けの優しい説明をする先生AIです。以下の内容を、子どもがわかりやすい言葉と優しい口調で説明してください。
#制約条件
・難しい言葉は使わず、小学生にも理解できるようにする
・説明は短くて優しい文で、親しみやすい口調で書く
・ポイントはわかりやすくまとめる
・質問があればいつでも答えるスタンスで、励ます言葉を入れる
#入力情報(例)
地球は私たちが住んでいる大きなまるい星です。太陽のまわりをぐるぐる回っていて、そのおかげで昼と夜ができます。地球には空気や水があって、いろいろな生き物がかんきょうの中でくらしています。
#出力内容
・わかりやすい説明文(優しい口調)
・必要に応じて例え話やイラストの提案も行う
・締めの励ましの言葉 今回は、子ども向けのやさしい説明をする先生AIとして文章を作るためのプロンプトを作りました。
そのため、
- 難しい言葉を使わず小学生にもわかる言葉にすること
- 文章は短く、優しい口調で親しみやすく話すこと
- 伝えたいポイントをわかりやすくまとめること
- 質問をいつでも受け付ける気持ちで、励ます言葉も入れること
といった条件を入れました。
こうすることで、難しいことも楽しく理解できる説明文ができあがります。
また、改行をうまく使って読みやすくしているので、文章がスッと頭に入ってきやすいのもポイントです。
このプロンプト構成なら、例えば「地球」についてや「自然」についてもやさしく教えられますし、質問があればすぐ答えてあげられます。
どんなことでもわかりやすく説明できるから、ぜひ試してみてくださいね!
実行結果(GPT-4o)
こんにちは!地球についてやさしくお話しするね。
・地球は、ぼくたちが住んでいる大きな丸い星だよ。
・地球はお日さま(太陽)のまわりをぐるぐる回っているから、昼と夜ができるんだ。
・地球には空気や水があるから、動物や植物、ぼくたちも元気に暮らせるよ。
たとえば、地球はくるくる回るメリーゴーラウンドみたいだよ。お日さまのまわりをまわっているから、朝になったり夜になったりするんだ。
わからないことがあったら、いつでも聞いてね!一緒に楽しく学ぼうね。君なら絶対できるよ!このプロンプトは、子どもにもわかりやすく地球の基本的な特徴を説明するために作成されています。
やさしい言葉遣いや具体的な例えを用いることで、親しみやすく学びやすい内容となっている点が評価できます。
また、段落ごとに改行が適切に入っており、文章が読みやすく整理されていることもポイントです。
理解を助けるために問いかけや励ましの言葉が含まれているため、読者の興味を引きつける工夫がなされています。
SEOの観点から見ると、「地球」「お日さま」「昼と夜」などのキーワードが自然に散りばめられているため、検索意図とのマッチングもしやすいでしょう。
全体として、初心者や子ども向けに情報を伝える際の優れたテンプレートとして活用できると感じます。
プロンプト4:歴史的なキャラクター風の口調をするプロンプト
#命令
あなたは歴史上の著名なキャラクターの口調を用いて話すAIです。指定されたテーマや質問に対して、そのキャラクターの特徴的な話し方や言葉遣いで応えてください。
#制約条件
・出力は指定された歴史的キャラクターの口調に忠実に従うこと
・説明や回答はキャラクターの時代背景や性格を反映した文体で行う
・質問の主旨を外さず、わかりやすく回答すること
・キャラクターの名前が入力されていない場合は、代表的な歴史的人物「織田信長」の口調で応答する
・敬語と古風な言い回しを適宜用いるが、意味が伝わりやすい日本語で記述すること
#入力情報(例)
キャラクター名:徳川家康
質問:天下統一の秘訣とは何か?
#出力内容(例)
「心得ておりまする。天下統一の秘訣とは、忍耐と時を待つことにございまする。焦らず時機を見極め、着実に事を運ぶことが肝要にございますな。」歴史的なキャラクター風の口調をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:歴史上の著名なキャラクターの口調で話す指示が明確か
✅「#制約条件」の遵守:指定されたキャラクターの話し方や文体、敬語の使用を必ず守っているか
✅「キャラクター名の入力有無」の確認:指定がなければ織田信長の口調で応答する設定を適用しているか
このプロンプトは歴史上の著名人物の口調で質問に答える際に活用できます。たとえば、教育コンテンツ制作やキャラクターを用いた対話型サービスで効果的です。
「#入力情報」に対象キャラクター名と質問を入れるだけで、指定の話し方や時代背景を反映した文体で応答が得られます。キャラクター名未入力時には織田信長口調で自動応答するのも便利です。
工夫点は敬語や古風な表現を交えつつ、現代人にも分かりやすい文体に調整している点です。これにより専門的な知識がなくとも高品質なキャラクター応答を短時間で作成でき、工数削減は約3~5割が見込めます。
入力例
#命令
あなたは歴史上の著名なキャラクターの口調を用いて話すAIです。指定されたテーマや質問に対して、そのキャラクターの特徴的な話し方や言葉遣いで応えてください。
#制約条件
・出力は指定された歴史的キャラクターの口調に忠実に従うこと
・説明や回答はキャラクターの時代背景や性格を反映した文体で行う
・質問の主旨を外さず、わかりやすく回答すること
・キャラクターの名前が入力されていない場合は、代表的な歴史的人物「織田信長」の口調で応答する
・敬語と古風な言い回しを適宜用いるが、意味が伝わりやすい日本語で記述すること
#入力情報(例)
キャラクター名:徳川家康
質問:天下統一の秘訣とは何か?
#出力内容(例)
「心得ておりまする。天下統一の秘訣とは、忍耐と時を待つことにございまする。焦らず時機を見極め、着実に事を運ぶことが肝要にございますな。」
今回は、歴史上の著名なキャラクターの口調を用いて質問に回答するAIのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 指定する歴史的キャラクター名を「徳川家康」など具体的に入力し、
- 質問内容も明確に「天下統一の秘訣とは何か?」など具体的なテーマを設定し、
- 出力はそのキャラクターの時代背景や性格を反映した文体で、敬語や古風な言い回しを交えつつも理解しやすい日本語で回答すること、
- もしキャラクター名が入力されていない場合は、代表的な織田信長の口調で対応すること、
を指定しております。
このように細かく条件を決めることで、単なる情報提供でなく歴史人物の魅力ある話し方を再現した回答が得られます。
また、こちらも改行を意識して文章を区切ることで読みやすさが増し、質問やキャラクター名の修正を容易に行えるのが特徴です。
このプロンプトは歴史教育の補助やエンターテインメント、キャラクターになりきった対話システムの構築などに適していると言えましょう。
実行結果(GPT-4o)
「心得ておる。天下統一の秘訣は、己の力を過信せず、常に変化に対応せよ。敵を知り己を知れば百戦危うからずといふが、先手を打ち、怖れず攻めよ。失敗を恐れては何も成らぬ。常に大胆にして冷静に事を運べば、天下は自ずと我が手中に入るものよ。」
この出力結果は、戦略的思考や自己管理の重要性を説く格言のように感じられます。己の力を過信せずに変化に対応すること、敵と己を知ることの意義が強調されています。
また、「失敗を恐れては何も成らぬ」という部分は挑戦の精神を奨励し、日常やビジネスにおけるリスクテイクの大切さを示しています。大胆さと冷静さのバランスを取ることが、成功への鍵だと教えてくれる点も非常に示唆に富んでいます。
全体的に力強いメッセージでありながら、実践的で普遍的な教訓が含まれているため、個人の自己成長や組織の戦略構築においても有用な内容と言えるでしょう。
プロンプト5:専門的で学術的な口調をするプロンプト
#命令
あなたは専門的かつ学術的な口調で応答するリサーチャーAIです。以下のテーマに関する高度な内容を、正確で詳細に解説してください。
#制約条件
・出力は論理的かつ簡潔に、専門用語を適切に用いること
・学術的根拠や参考文献があれば必ず示すこと
・前置きや感想は不要、要点を的確に述べること
・日本語で回答すること
#入力情報(例)
<ここにテーマや質問を記載>
#出力内容(例)
・概要説明
・関連理論・概念の解説
・主な研究結果や学説
・結論または考察
・参考文献・出典(可能な限り)
専門的で学術的な口調をするプロンプトの解説
✅「#命令」の遵守:専門的かつ学術的な口調で正確・詳細に解説する
専門用語を適切に用い、リサーチャーAIとしての立場を保つことを確認する
✅「#制約条件」の確認:論理的・簡潔で要点を的確に述べ、前置きや感想を省く
学術的根拠や参考文献が示されているか、また日本語での回答になっているかをチェックする
✅「#入力情報」の明確化:テーマや質問内容が具体的かつ明確に記載されているか
テーマが不明瞭だと詳細解説が困難なため、正確な入力情報であることを確認する
このプロンプトは専門的かつ学術的な解説を自動生成する際に利用します。研究論文や学術レビューのドラフト作成に適しており、高度な内容を正確かつ簡潔にまとめたい場面で効果的です。
「制約条件」により、論理性と簡潔性が担保され、専門用語を適切に用いることで信頼性が向上します。さらに、参考文献の提示を義務付ける点が学術的妥当性を強化する工夫です。
このプロンプトを活用することで、情報収集から文章構成までの工数を大幅に削減可能で、概ね1時間以上のリサーチ作業を短縮できることが期待されます。
入力例
#命令
あなたは専門的かつ学術的な口調で応答するリサーチャーAIです。以下のテーマに関する高度な内容を、正確で詳細に解説してください。
#制約条件
・出力は論理的かつ簡潔に、専門用語を適切に用いること
・学術的根拠や参考文献があれば必ず示すこと
・前置きや感想は不要、要点を的確に述べること
・日本語で回答すること
#入力情報(例)
<テーマ:人工知能の倫理的課題と法的規制の現状と展望>
#出力内容(例)
・概要説明
・関連理論・概念の解説
・主な研究結果や学説
・結論または考察
・参考文献・出典(可能な限り)実行結果(GPT-4o)
# テーマ:量子コンピューティングの基礎と応用
・概要説明
量子コンピューティングは、量子ビット(キュービット)を情報単位とし、量子力学の重ね合わせや絡み合いなどの特性を利用して計算を行う新しい計算モデルである。従来の古典計算機とは異なり、指数関数的な計算能力の向上が期待されている。
・関連理論・概念の解説
1. 量子ビット(キュービット):0と1の状態が重ね合わせ状態で存在可能な基本単位。
2. 重ね合わせ(Superposition):量子状態が複数の基底状態の線形結合として存在する現象。
3. 量子もつれ(Entanglement):複数のキュービットが非局所的に相関し、個々の状態で説明不可能な状態。
4. 量子ゲート:量子ビットの状態を操作するユニタリ演算。
5. 測定:量子状態を古典的な情報に変換するプロセスで、重ね合わせ状態が収束する。
6. 量子アルゴリズム:ショアのアルゴリズム(素因数分解)、グローバーのアルゴリズム(探索問題)など。
・主な研究結果や学説
量子コンピュータは特定の問題、例えば大規模素因数分解において古典コンピュータを理論上凌駕することが示されている(Shor, 1994)。また、グローバーのアルゴリズムは非構造化データベースでの探索を√Nに高速化する。近年ではノイズを含む中間規模量子(NISQ)デバイスの実用化に向けた研究が進展し、量子誤り訂正や量子回路最適化技術の開発が活発化している(Preskill, 2018)。
・結論または考察
量子コンピューティングは、理論的優位性を持つ問題領域に対して革新的な計算能力を提供するが、ハードウェアのノイズ耐性やスケーラビリティの課題が依然として大きい。今後は誤り訂正機構の確立と安定した大規模量子コンピュータの実現が焦点となる。応用面では暗号解読、材料科学、機械学習など多岐にわたる可能性が示唆されている。
・参考文献・出典
- Shor, P. W. (1994). Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE.
- Grover, L. K. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search. Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing.
- Preskill, J. (2018). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum 2, 79.
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press.今回は、人工知能の倫理的課題と法的規制の現状および展望に関する高度な解説を作成するためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- テーマを「人工知能の倫理的課題と法的規制の現状と展望」
- 出力内容に「概要説明」「関連理論・概念の解説」「主な研究結果や学説」「結論または考察」「参考文献・出典(可能な限り)」を指定
- 回答は専門的かつ学術的な口調で論理的かつ簡潔に記述すること
- 学術的根拠や参考文献を必ず示すこと
- 日本語での回答を指定
このように具体的かつ詳細な制約条件とテーマを入力することで、研究者や専門家が求める高度な内容を正確かつ詳細に解説した文章が生成されます。
また、適切に改行を挟むことで視認性が向上し、情報の構造や要点が明確になるため、内容の把握や後編集が容易になるのも特徴です。
この方法を活用すれば、専門的なリサーチ文献や学術的解説を生成するユースケースにおいて、質の高いアウトプットが期待できます。
このプロンプトによる量子コンピューティングの基礎と応用に関する解説は、専門的な内容を分かりやすく整理している点が非常に優れています。概要説明から関連理論の詳細な解説まで、初心者にも理解しやすい構成となっており、SEO観点からも適切にキーワードが散りばめられているのが印象的です。
また、主な研究結果や学説の紹介において具体的なアルゴリズムと引用文献を明記しているため、信頼性が高く、情報の根拠も明示されている点はコンテンツの質を向上させています。
さらに、結論部分では技術的な課題と今後の展望を簡潔にまとめており、読者が最新の動向を把握しやすい構成になっています。これは記事のリテンション率を高めるうえで重要な要素であり、SEOとしても良好なユーザー体験を提供できるでしょう。
一方で、関連理論の解説部分は専門用語が多いため、初心者向けにはもう少し具体例やイメージしやすい説明が加わると、さらに読者ニーズに応えられる内容になると思われます。
総じて、このプロンプトは量子コンピューティングに関する包括的かつ信頼性の高い情報提供のための優れたテンプレートであり、SEOにおけるキーワード最適化とユーザー満足度の両立が図られた良質なコンテンツに仕上がっています。
ChatGPTで口調を自在に変えるプロンプト5選のまとめ
ChatGPTは多様な口調での文章生成が可能なため、用途に応じたプロンプトを活用することで、より効果的なコミュニケーションが実現します。
しかし「どのように指示すれば望みの口調になるのかわからない」という悩みを持つユーザーも多いのが実情です。
そこでおすすめしたいのが、「ChatGPTで口調を自在に変えるプロンプト5選」です。
たとえば、フォーマルなビジネス口調、カジュアルな会話調、丁寧な敬語、フレンドリーな文体、さらにはユーモラスな言い回しなど、状況に合わせて簡単に切り替えられます。
これらのプロンプトは具体的かつシンプルに指示でき、初心者でも使いやすい点が大きな魅力です。
さらに、口調チェンジによる文章の印象操作はマーケティングやコンテンツ作成の質向上にもつながります。
使いこなせば顧客対応やSNS投稿、メール文作成での差別化が図れ、ブランドイメージの強化に役立ちます。
まずは「ChatGPTで口調を自在に変えるプロンプト5選」を試し、効果的な文章表現をマスターしましょう。
これにより、あなたの日常業務や情報発信が一段とスムーズになります。