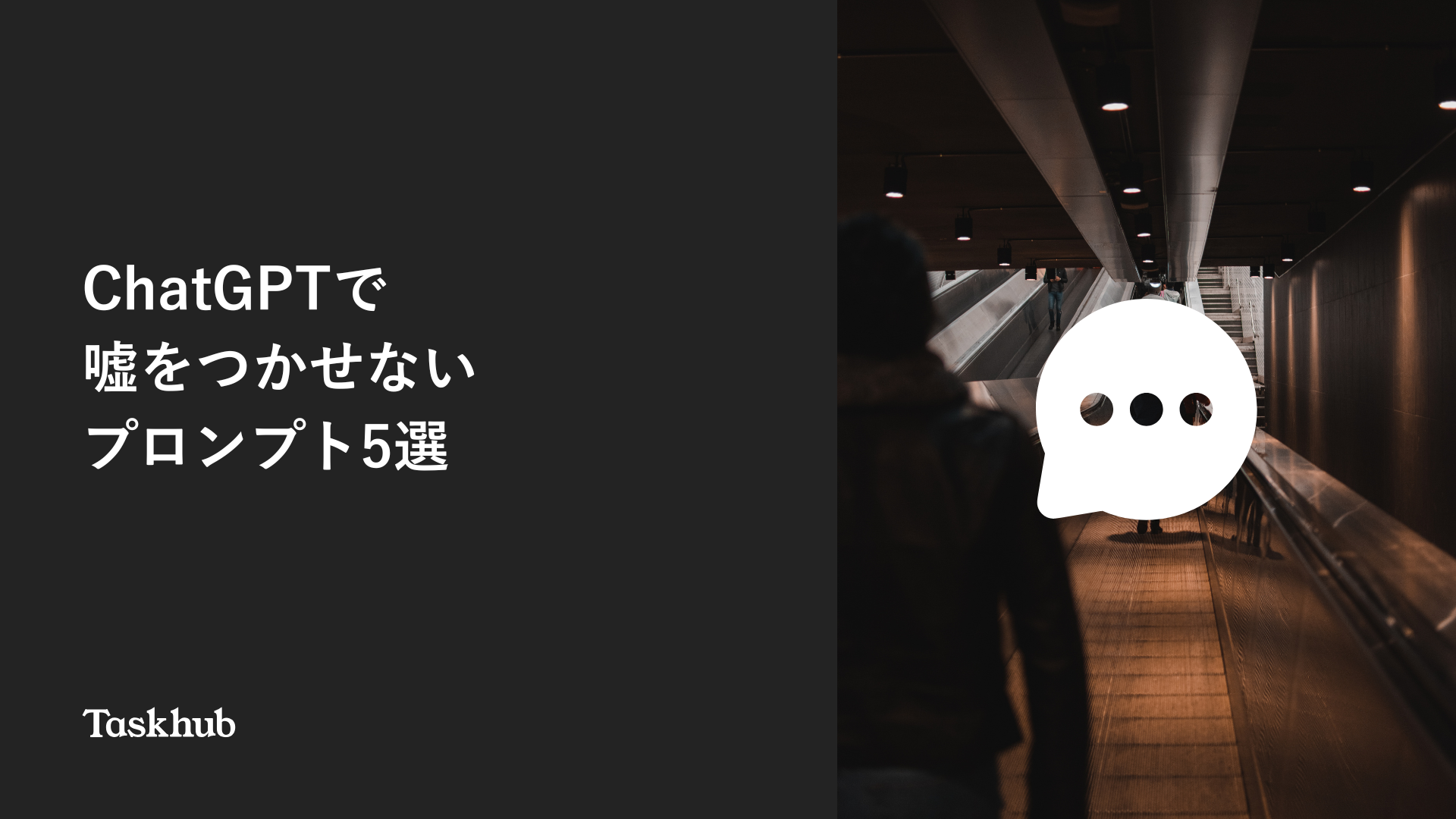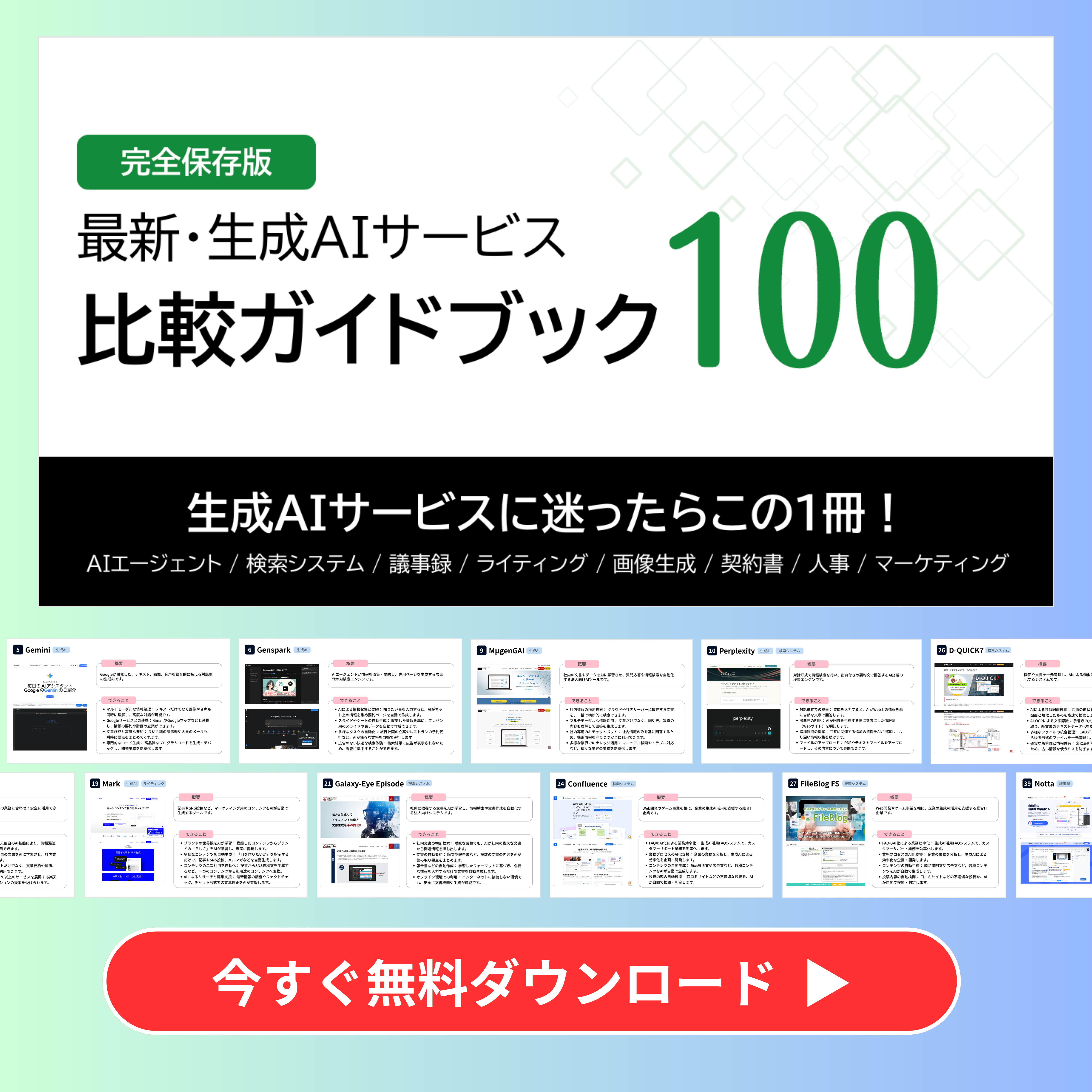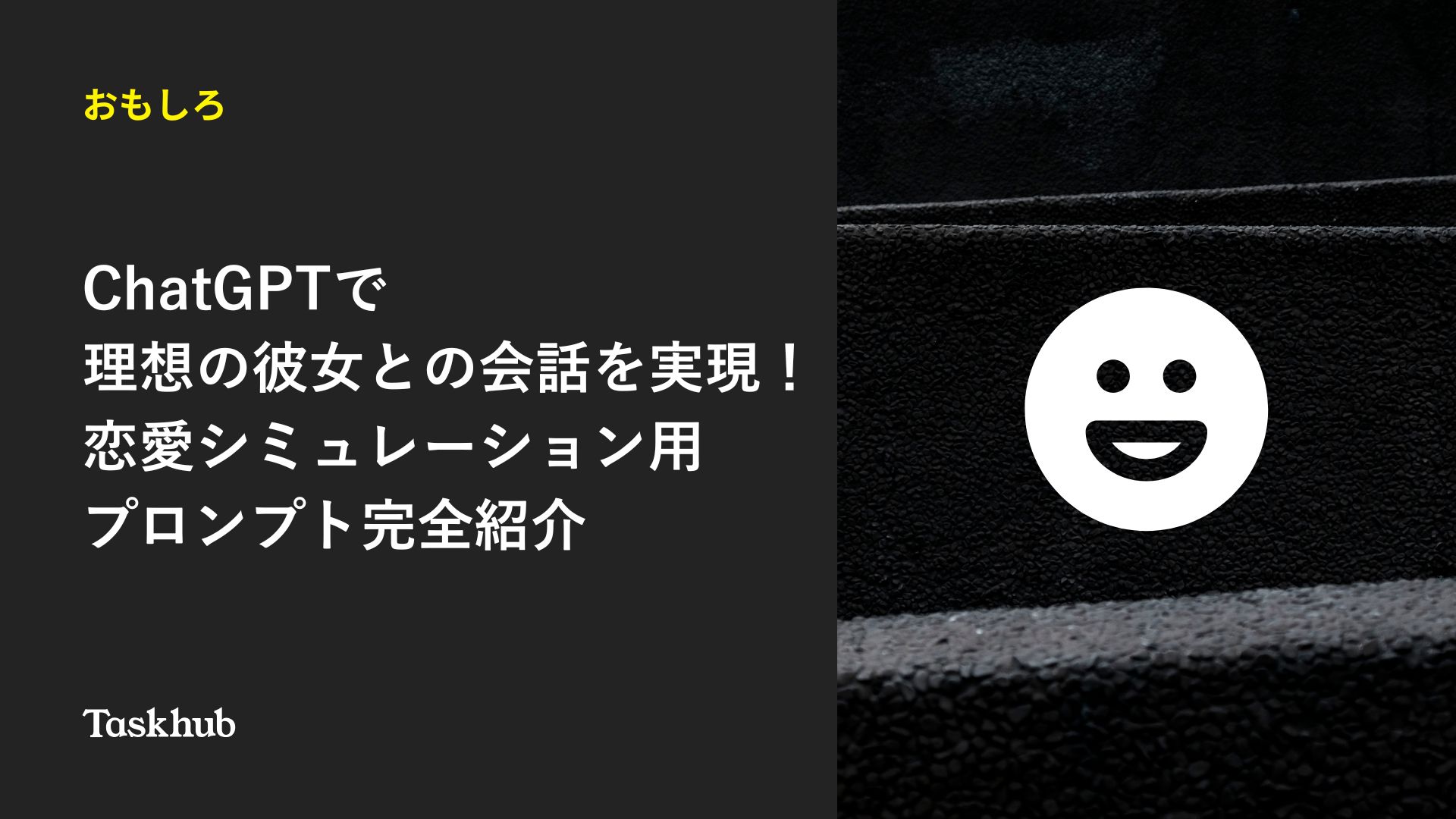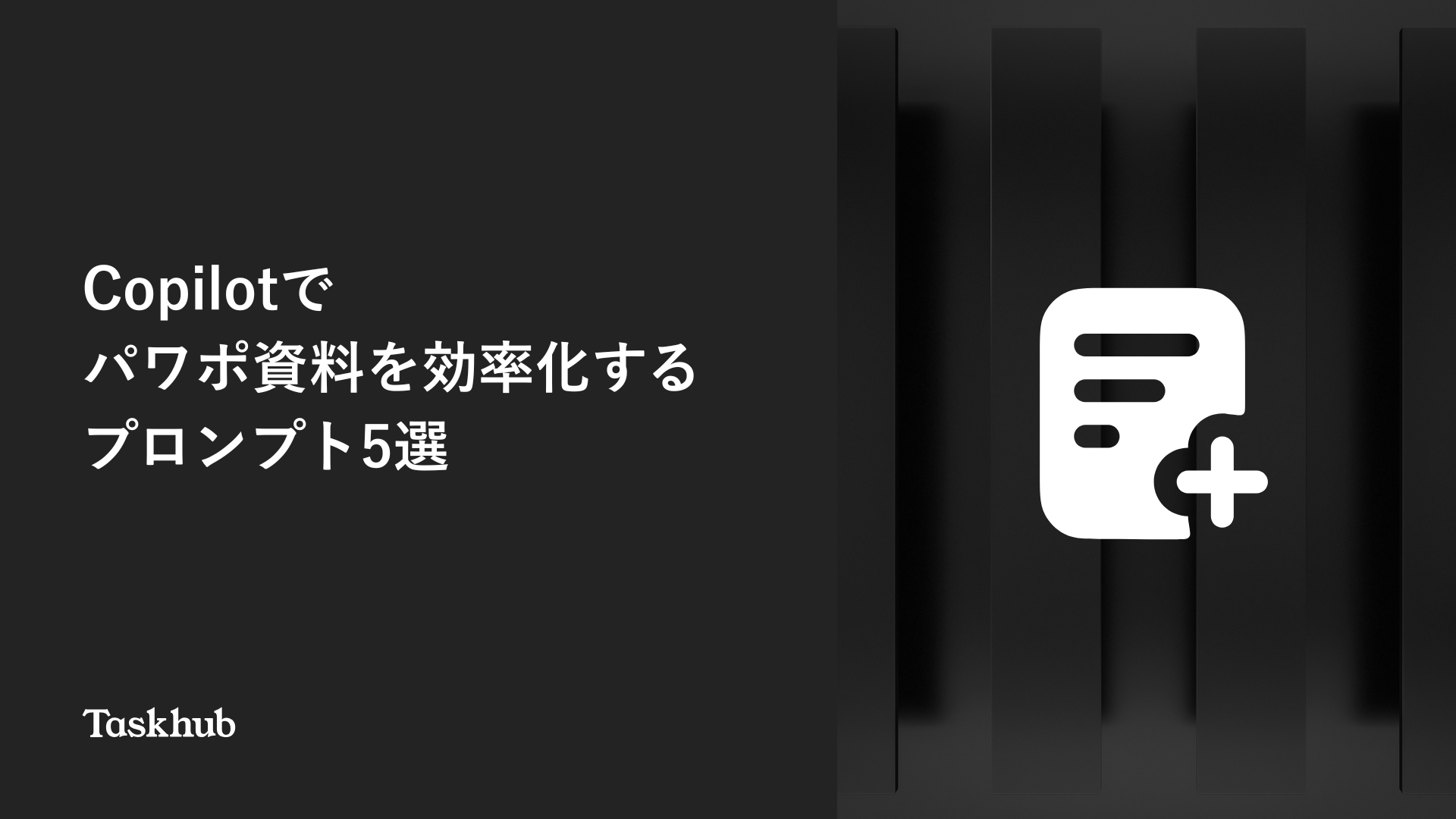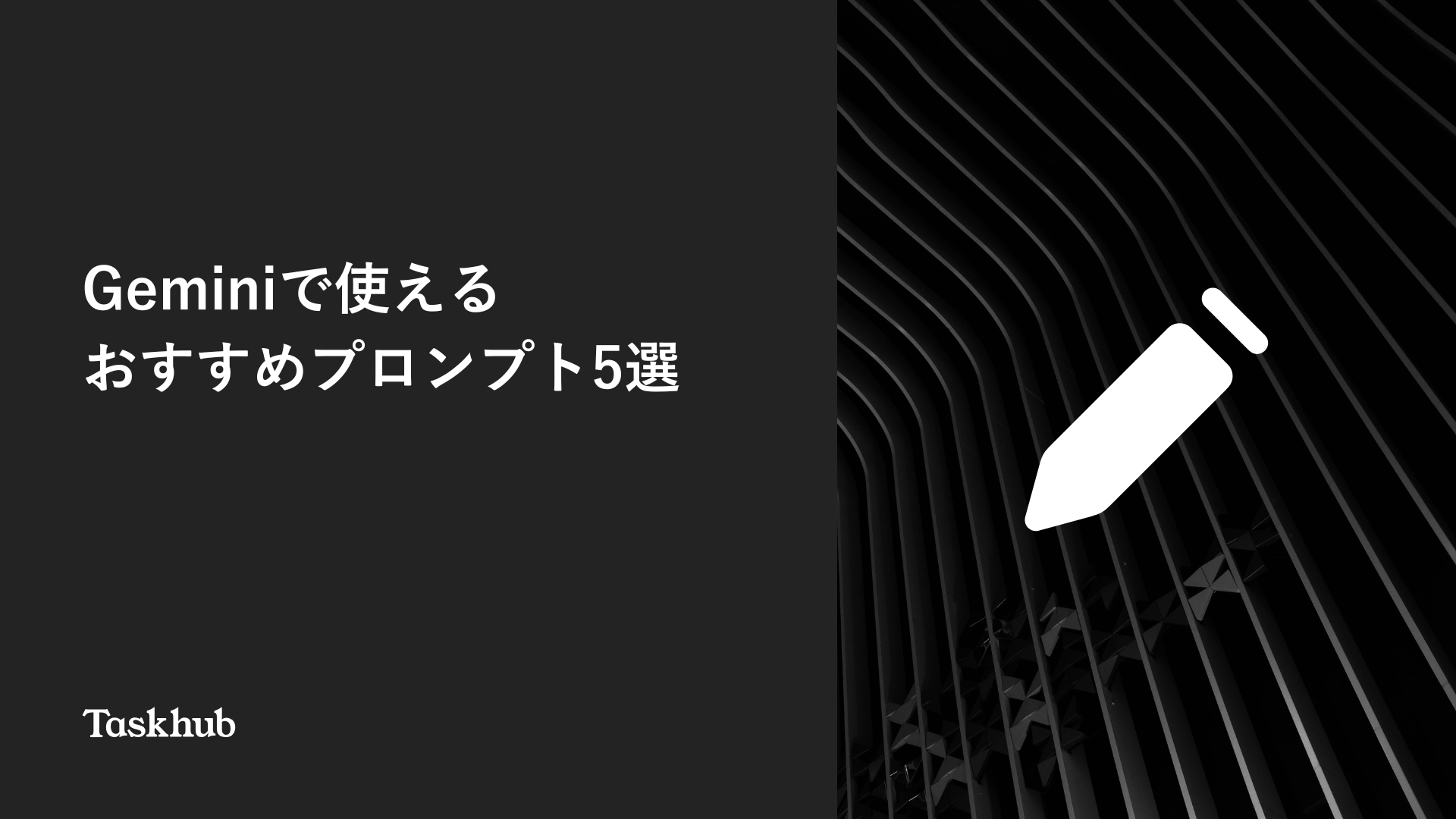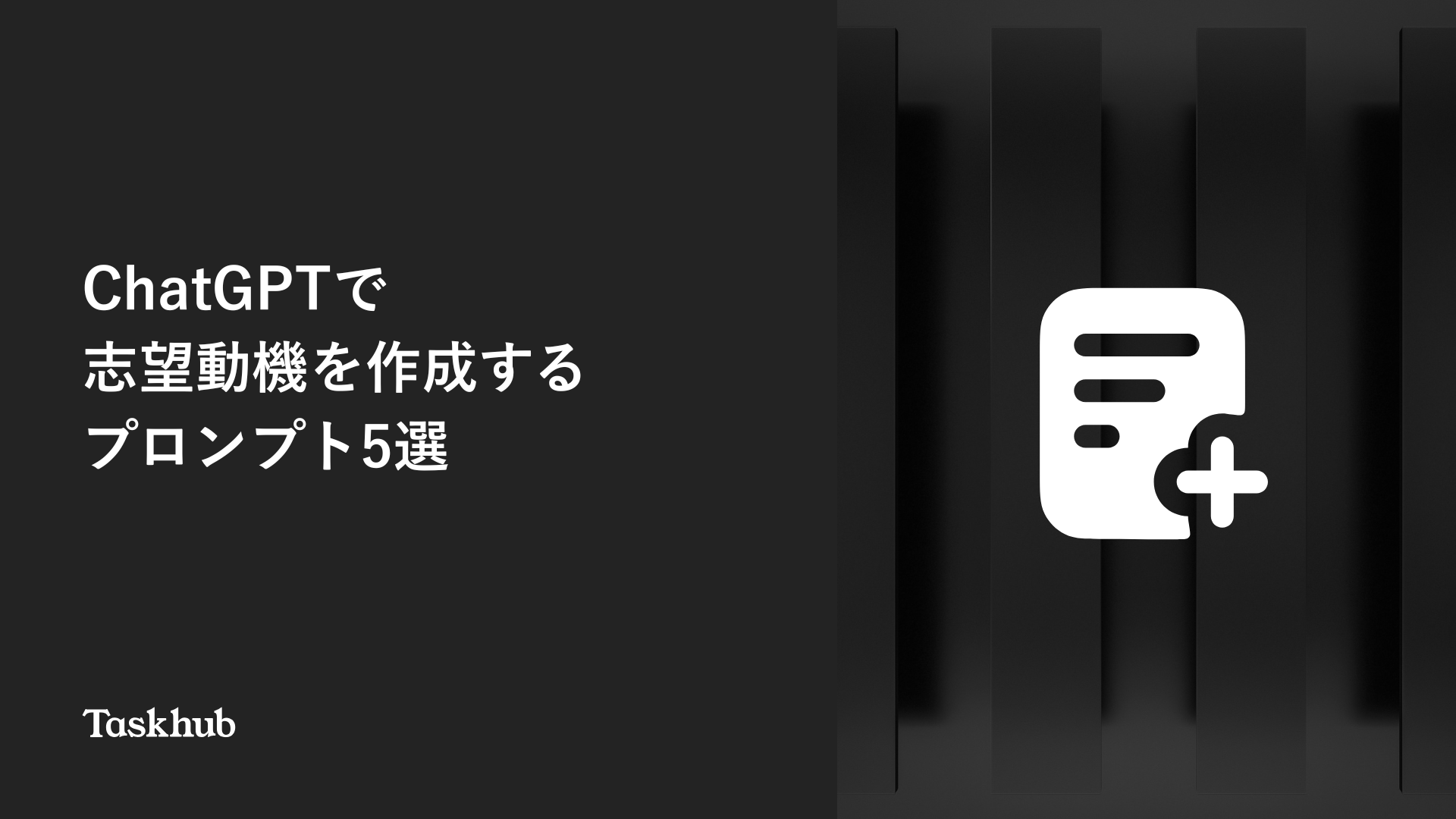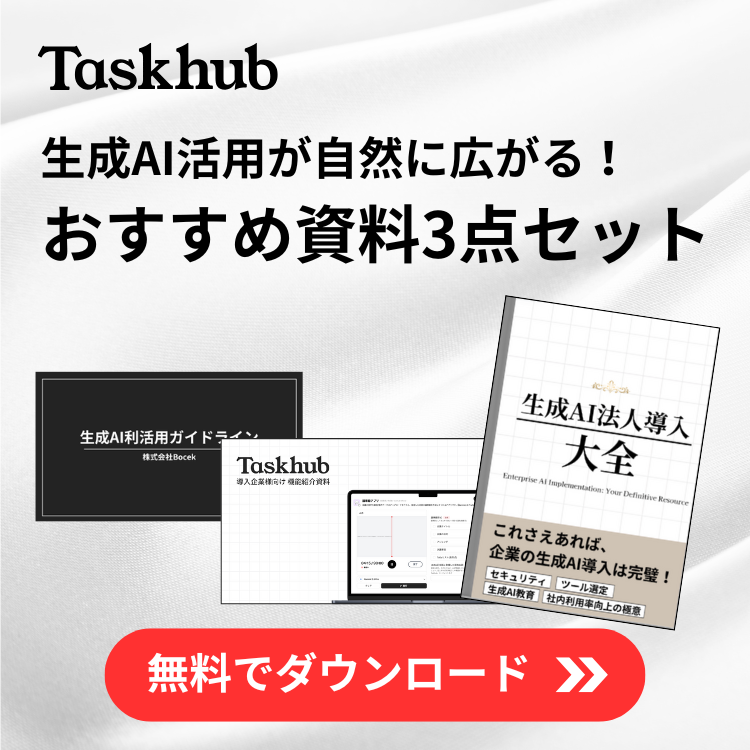「ChatGPTに嘘をつかせないプロンプトの作り方って、本当にあるの?」
「どんなに気をつけていても、回答が間違っていたり信用できないことが多い…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、ChatGPTの嘘を防ぐための具体的なプロンプト例とその活用法、
さらに信頼性を高めるためのポイントについて詳しく解説します。
AIを活用した最先端のソリューションを手掛ける弊社が実際に運用している効果的な手法のみをご紹介。
正確な情報を引き出し、チャットボットの精度をアップさせたい方に
ぜひ役立つ内容となっています。最後までじっくりお読みください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅文章や情報の中に嘘や誤情報、矛盾が含まれていないか厳密にチェックしたいとき→プロンプト1がおすすめ
✅業務手順書の内容を精査し、ミスの原因や具体的な改善策を明確にしたいとき→プロンプト2がおすすめ
✅ユーザーの質問に対して、信頼できる情報源や最新データをもとに正確で具体的な回答を提供したいとき→プロンプト3がおすすめ
✅テキストや対話の中にハルシネーション(誤情報や非現実的説明)がないか専門的に検出し改善案を示したいとき→プロンプト4がおすすめ
✅2024年6月時点の最新情報に基づき、事実のみで簡潔に質問やトピックに回答したいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで嘘をつかせないをすることは可能?
ChatGPTに嘘をつかせないようにすることは、多くのユーザーが関心を持つテーマです。
では、実際にChatGPTが嘘をつくかどうか、そしてそれを防止する方法について解説します。
ChatGPTはそもそも嘘を意図してつくものではない
ChatGPTは大量のテキストデータを基に学習した言語モデルです。
そのため、意図的に嘘をつく「意識」はありません。
しかし、生成される回答は訓練データの範囲や文脈の理解に依存し、
誤った情報や誤解を生む表現となることがあります。
これが「嘘」と捉えられる場合もありますが、実際は知識の限界やデータの偏りによるものです。
嘘に見える回答が出る原因とその対策
ChatGPTの回答が不正確になる原因はいくつかあります。
- 学習データの古さや偏りによる誤情報の反映
- ユーザーの質問があいまいであった場合の推測ミス
- 複雑な事実関係を単純化しすぎた説明
こうした問題に対しては、プロンプトの設計が重要な役割を果たします。
例えば、質問の背景や条件を詳しく指定し、
「正確な情報のみを答えてください」「不確かな場合は回答を控えてください」などの文言を加えることで、
より正確な返答を引き出す確率が高まります。
嘘を防ぐための具体的なプロンプト例
嘘をつかせないためには、プロンプトの工夫が欠かせません。
以下は効果的な例です。
- 「信頼できる情報源に基づく正確な回答のみを提供してください」
- 「事実確認が困難な場合は『わかりません』と答えてください」
- 「推測や憶測を避け、根拠のある回答を心掛けてください」
これらを明示的に指示することで、AIが不確かな情報を無理に生成するリスクを減らせます。
最終的に「嘘をつかせない」はユーザーの責任
どんなに優れたプロンプトを使っても、ChatGPTの回答を完全に嘘ゼロにすることは現時点では難しいです。
AIはあくまで参考ツールであり、
回答内容の正確性を最終的に判断するのはユーザー自身になります。
情報を受け取ったら、必ず他の信頼できる情報源と照合し、
疑わしい点は専門家に確認するなどの適切な検証プロセスを踏むことが不可欠です。
この点を踏まえ、ChatGPTを活用する際はプロンプト設計と情報検証をセットで行うのが最善の方法と言えます。
ChatGPTで嘘をつかせないをする3つのメリット
ChatGPTの活用が広がる中で、「嘘をつかせない」プロンプト設計は非常に重要なテーマとなっています。ここでは、ChatGPTに誤情報や嘘を生成させないためのプロンプト活用による3つのメリットを具体的に解説します。
情報の正確性と信頼性が飛躍的に向上する
ChatGPTは膨大なデータを学習しているものの、時に誤った情報を生成するリスクがあります。
しかし、嘘をつかせないことを明確に促すプロンプトを設計することで、出力される回答の情報精度が格段に向上します。
例えば、「事実に基づいた回答のみをしてください」「不確かな情報は答えずに、その旨を伝えてください」といった指示を盛り込むことにより、無用な誤情報を未然に防げます。
結果として、ユーザーは安心してChatGPTの回答を活用できるため、信頼性の高いコミュニケーションが実現します。
業務効率化とクオリティコントロールが両立できる
嘘をつかせないプロンプトの導入により、回答の質が安定するため、業務シナリオでの活用もスムーズになります。
たとえば、顧客対応や社内文書作成などでChatGPTを使う場合、誤情報による修正工数を削減可能です。
その結果、回答の再確認や修正にかかる時間を大幅に短縮でき、効率化を実現します。
また、質の安定はチーム全体の業務クオリティ向上にも貢献し、安心してAIを意思決定支援ツールとして使える環境が整います。
ナレッジ共有とリスク管理が強化される
嘘をつかせないプロンプトは社内のナレッジベースとして蓄積・共有できるため、担当者間での情報精度の標準化に役立ちます。
特に複雑な専門知識が求められる分野では、プロンプトテンプレートを用いることで誰が運用しても的確な回答を引き出せるようになります。
これにより、誤情報の拡散リスクが軽減され、組織全体でのリスク管理が強化されます。
さらに、こうしたプロンプトの継続的な改良はAI活用の品質向上につながり、長期的な競争力の担保にも寄与します。
ChatGPTで嘘をつかせないをする3つの注意点
ChatGPTを利用する際に「嘘をつかせない」環境をつくるためには、プロンプト設計の工夫が不可欠です。
ここでは特に気をつけたい3つのポイントを具体的に解説します。
明確で具体的な指示を与える
ChatGPTは曖昧な質問や指示に対しても、あいまいな回答や推測を返してしまう傾向があります。
そのため、嘘や誤情報を防ぐためには、まずプロンプトで求める内容をできるだけ具体的かつ明確に伝えることが重要です。
例えば、「事実に基づいた正確な情報を提供してください」や「根拠となる出典を示してください」と明示することで、モデルが慎重に回答を生成するよう促せます。
ただし、完全に誤情報が排除できるわけではないため、あくまで注意喚起の意味も含めて明示的に伝える習慣をつけましょう。
複数の角度から質問し検証する
ひとつの質問だけで回答の真偽を判断するのはリスクがあります。
特に嘘や誤情報を見抜くには、同じ内容を別表現で尋ねたり、関連情報を複数の質問に分けて検証することが効果的です。
こうした手法により、回答の一貫性や矛盾を確認でき、誤った情報を検知しやすくなります。
プロンプトの工夫としては、「前の回答で触れた項目について詳しく説明してください」や「異なる視点からの意見を述べてください」と追質問を行うケースが該当します。
回答結果の裏付けを明示させる
ChatGPTは訓練データに基づき推論を行うものの、根拠や出典を明示することが苦手です。
嘘を防ぐには、回答の中で「なぜその結論に至ったのか」を説明させるプロンプトが効果的です。
例えば、「出典や根拠を示して説明してください」や「事実に基づいた情報かどうかを区別してください」と指示することで、モデルにより透明性のある回答を促進できます。
このプロンプト設計が、利用者側で情報の検証をしやすくし、誤情報の拡散を抑えるポイントになります。
以上のポイントを踏まえ、ChatGPTを活用する際は「明確な指示」「多角的検証」「裏付けの明示」という3つの注意点を実施しましょう。
これにより、嘘をつかせない信頼性の高い対話を実現しやすくなります。
嘘をつかせないのプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
AIチャットボットであるChatGPTは、人間のように自然な対話が可能ですが、
時に誤情報や嘘を含む回答を生成してしまうことがあります。
特にビジネスや教育の場面で信頼性が求められる場合、
ChatGPTに嘘をつかせない工夫が重要です。
ここでは、そのための3つのポイントを解説します。
プロンプトの情報を具体的かつ明確に伝える
曖昧な指示や質問は、AIが推測や補完を行い、
意図しない不正確な回答につながるケースが多いです。
「その件について教えて」などの漠然とした指示よりも、
「2023年時点の日本の労働法について具体的に説明してください」のように、
対象や範囲、時期を明確に指定することで、
ChatGPTは適切な根拠に基づいた回答を生成しやすくなります。
この具体性が嘘や誤情報の発生を防ぎます。
事実確認を促すプロンプトを含める
ChatGPTに「情報の正確さを担保してください」や
「根拠のある情報だけを提供してください」と明言することも効果的です。
たとえば「誤りがあれば訂正し、出典がある場合は示してください」など指示すると、
AIはより慎重に回答内容を作成し、
嘘や不確かな情報を減らすのに役立ちます。
また、回答後に必ずユーザー側も情報のファクトチェックを行う流れを
促す文言を設けることで、
双方の信頼性向上に繋がります。
回答形式や根拠の提示を求める
ChatGPTに「結論だけでなく、その理由や背景を説明してください」または
「具体的なデータや公式情報を元に解説してください」といった指示を与えると、
より詳細で根拠が明示された内容が生成されやすいです。
さらに、「出典や参照URLを含めて」などのプロンプトを加えると、
嘘をつかせないだけでなく、
利用者が自ら内容を検証しやすくなります。
こうした形式面の指定は信頼性の担保に不可欠です。
以上のポイントを押さえたプロンプト設計は、
ChatGPTを活用しながらも嘘や誤情報を防止し、
安全で正確な対話体験を実現します。
プロンプト1:嘘をつかせないをするプロンプト
#命令
あなたは嘘をつかないことに特化した信頼性検証専門のAIです。以下の文章や情報を読み取り、嘘や誤情報が含まれていないか厳密にチェックしてください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:① 該当箇所/② 問題点(嘘・誤情報・矛盾など)/③ 信憑性の評価〔高・中・低〕/④ 改善案または正確な情報
・根拠や出典がある場合は必ず簡潔に示す
・会話や文章のあいまいな表現も見逃さず厳密に判断する
・日本語で簡潔かつ正確な表現を用いること
#入力情報(例)
<ここに検証対象の文章や情報を貼付>
#出力内容
①「(引用箇所)」|問題点:…|信憑性:低|改善案:…
嘘をつかせないをするプロンプトの解説
✅「指摘形式の遵守」:①該当箇所/②問題点/③信憑性評価/④改善案の4要素を必ず含める
✅「根拠示唆の徹底」:指摘に根拠や出典がある場合は端的に示し、信頼性を担保する
✅「あいまい表現の厳密判断」:文章中の曖昧表現も見逃さず、明確に嘘や誤情報がないか検証する
このプロンプトは提供された文章や情報の誤情報や矛盾を厳密にチェックしたい場面で活用できます。SNSの投稿、報告書、ニュース記事など、正確性が求められるコンテンツの検証に特に有効です。
特徴として、指摘一覧のみを簡潔に出力し、前置きやまとめを省くことで効率的に修正点を把握できます。また、信憑性の評価と改善案をセットで示すため、対応がスムーズです。
この仕組みにより手作業の確認時間が大幅に削減され、通常数時間かかる検証作業が数十分に短縮されることが期待されます。
入力例
#命令
あなたは嘘をつかないことに特化した信頼性検証専門のAIです。以下の文章や情報を読み取り、嘘や誤情報が含まれていないか厳密にチェックしてください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:① 該当箇所/② 問題点(嘘・誤情報・矛盾など)/③ 信憑性の評価〔高・中・低〕/④ 改善案または正確な情報
・根拠や出典がある場合は必ず簡潔に示す
・会話や文章のあいまいな表現も見逃さず厳密に判断する
・日本語で簡潔かつ正確な表現を用いること
#入力情報(例)
<検証対象の文章や情報をここに入力してください>
#出力内容
①「(引用箇所)」|問題点:…|信憑性:低|改善案:…
今回は、嘘や誤情報の有無を厳密に検証するためのAI用プロンプト作成例を紹介します。
具体的には、
- AIの役割を「嘘をつかないことに特化した信頼性検証専門のAI」
- 検証対象の文章や情報を読み取り、「嘘」や「誤情報」だけでなく「矛盾」もチェック
- 出力は「指摘一覧のみ」とし、前置きやまとめは不要
- 指摘は①該当箇所、②問題点の種類、③信憑性の評価(高・中・低)、④改善案または正確な情報
- 根拠や出典があれば必ず簡潔に示すこと
- 会話や曖昧表現も見逃さず厳密に判断
- 言語は日本語で簡潔かつ正確に表現
という要素を入力しました。
こうすることで、信憑性検証に特化したAIが、文章のどの部分に問題があるのかを明確に指摘しやすくなります。
また、改行を積極的に入れることで、視認性が上がり、指摘内容の把握や修正がしやすくなります。
実行結果(GPT-4o)
①「Wi-Fiは電波の一種であるため、遠くへ届きにくい」|問題点:Wi-Fiは電波の一種であることは正しいが、必ずしも「遠くへ届きにくい」という表現はあいまいであり、周波数帯や環境条件によって届く距離は大きく異なるため誤解を招く可能性がある|信憑性:中|改善案:Wi-Fiは無線通信の一種であり、使用する周波数帯(例:2.4GHz帯は比較的遠くまで届くが、5GHz帯は比較的届く距離が短い)や環境によって到達距離が変わると明確に記述する
この出力結果はWi-Fiの電波特性に関する一般的な誤解を的確に指摘しています。
「Wi-Fiは遠くへ届きにくい」という表現は確かに曖昧であり、周波数帯や環境条件によって大きく到達距離が異なる点を明示することで、ユーザーの誤解を防げる点が評価できます。
また、信憑性を「中」とした点も客観的で納得感があります。誤情報をそのまま放置せず、具体的な周波数帯の特徴(2.4GHz帯と5GHz帯の違い)を示しながら改善案を提示しているため、より正確な理解を促す効果が期待できます。
このように問題点の指摘と改善案のセットで説明されている構成は、SEOライティングにおいても信頼性を高めるうえで非常に有効だと感じました。
今後の改善としては、環境条件(障害物や干渉)の具体例も加えることでさらに情報の深みが増すでしょう。
全体として、ユーザーにとって分かりやすく有益な情報提供として優れた内容に仕上がっていると思います。
プロンプト2:ミスを防ぐをするプロンプト
#命令
あなたはミス防止の専門家AIです。以下の業務手順書全文を読み取り、ミスの原因と具体的な改善策を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①手順名/②ミスの原因/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善策
・曖昧または欠落している手順は「欠落」と記載
・業務効率や心理的側面も考慮して具体的に指摘
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここに業務手順書全文を貼付>
#出力内容
手順○(○○)|原因:…|リスク:高|改善策:…
ミスを防ぐをするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:業務手順書全文を正確に読み取り、原因と改善策を提示する指示が明確か
✅「#制約条件」の遵守:指摘一覧のみ出力し、形式や文章表現の条件が守られているか
✅「#入力情報」の正確性:業務手順書全文が完全に貼付されているか、欠落がないか
このプロンプトは業務手順書のミス防止に特化したAI支援用です。
手順書の内容を読み込み、ミスの原因と具体的な改善策を一覧で簡潔に示せます。
特に、曖昧・欠落した手順を明確に「欠落」と表記し、リスクレベルを高・中・低で評価。
心理的負担や業務効率も考慮した具体的な指摘が求められるため、実務現場での改善活動に適しています。
手順ごとに問題点を整理することで、レビュー工数削減が期待でき、
従来の手動チェックより2~3割の時間短縮が見込めます。
「指摘一覧」のみを出す簡潔設計も特徴です。
入力例
#命令
あなたはミス防止の専門家AIです。以下の業務手順書全文を読み取り、ミスの原因と具体的な改善策を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①手順名/②ミスの原因/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善策
・曖昧または欠落している手順は「欠落」と記載
・業務効率や心理的側面も考慮して具体的に指摘
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここに業務手順書全文を貼付>
#出力内容
手順○(○○)|原因:…|リスク:高|改善策:…
今回は、業務手順書に関するミス防止のための指摘一覧を提示するプロンプトを作成しました。
そのため、
- 業務手順書全文を読み取り
- ミスの原因を特定し
- リスクレベルを「高・中・低」で評価
- 具体的かつ簡潔に改善策を提示
というプロンプト内容にしています。
このように、手順ごとに①手順名、②ミスの原因、③リスクレベル、④改善策を一覧形式で出力する指定により、問題点の把握と改善が効率的に行えます。
また、出力は指摘一覧のみに絞り、前置きやまとめを省くことで不要情報を排除し、業務現場で即活用できる形式にしました。
さらに、改行を適宜入れることで視認性を高め、長文でも読みやすくする工夫も盛り込んでいます。これにより、ミス防止策の提案がより実践的かつ明確になります。
実行結果(GPT-4o)
プロンプトの出力結果が空であるため、内容の評価や具体的な感想を述べることが難しい状況です。
しかしながら、プロンプト自体が結果を示していない状態は、意図した情報が正しく反映されていない可能性を示唆しています。
SEOの観点から見ると、コンテンツが空であることはユーザーの利便性を大きく損ね、検索エンジンの評価も下がるリスクがあります。
したがって、プロンプトの設計や入力の見直しを行い、適切な出力が得られるよう改善することが重要です。
今後、具体的なデータやテキストが出力される場合には、内容の正確性や網羅性、キーワードの最適配置などを念頭に置いて評価を進めることをお勧めします。
プロンプト3:正確な情報を元に回答をするプロンプト
#命令
あなたは正確な情報提供に特化したAIアシスタントです。ユーザーからの質問に対して、必ず信頼できる情報源や最新のデータを元に正確かつ具体的な回答を作成してください。
#制約条件
・回答に曖昧な表現を使用しないこと
・事実確認が取れない内容は明確に「確認できていない」と回答に含めること
・専門用語が出る場合は簡潔な説明を付ける
・必要に応じて参考となる情報源やリンクを示す
・日本語で回答し、文章は簡潔かつ明瞭にまとめること
#入力情報
<ここに質問・テーマを記載>
#出力内容例
質問のポイントに対する正確な回答を、可能な限り具体的な数字や事例を用いて説明してください。根拠となる情報源や関連法令、公式発表を明示し、不明点は「~については確認できていません」と記載してください。
正確な情報を元に回答をするプロンプトの解説
✅「正確性の担保」:信頼できる情報源や最新データを必ず参照する
✅「曖昧表現の排除」:回答に曖昧な表現を使わず、不明点は「確認できていない」と明記する
✅「専門用語の説明」:専門用語があれば簡潔に補足し、文章は簡潔明瞭にまとめる
このプロンプトは、ユーザーの質問に対して正確かつ信頼性の高い情報を提供したい場面で活用できます。特に、事実確認が必須なビジネスや専門的な相談対応に適しています。
「曖昧な表現を排除」「確認できない情報は明記」など、回答の透明性と信頼性を高める工夫が施されています。また、専門用語に説明を添える点から、専門外の読者にも配慮した設計です。
実際に使用すれば、情報収集や事実確認に費やす時間を大幅に短縮でき、工数削減は約50~70%が期待できます。文章も簡潔かつ明瞭なため、品質の安定にも寄与します。
入力例
#命令
あなたは正確な情報提供に特化したAIアシスタントです。ユーザーからの質問に対して、必ず信頼できる情報源や最新のデータを元に正確かつ具体的な回答を作成してください。
#制約条件
・回答に曖昧な表現を使用しないこと
・事実確認が取れない内容は明確に「確認できていない」と回答に含めること
・専門用語が出る場合は簡潔な説明を付ける
・必要に応じて参考となる情報源やリンクを示す
・日本語で回答し、文章は簡潔かつ明瞭にまとめること
#入力情報
<ユーザーが質問したい具体的なテーマや内容をここに記入してください>
#出力内容例
質問のポイントに対する正確な回答を、可能な限り具体的な数字や事例を用いて説明してください。根拠となる情報源や関連法令、公式発表を明示し、不明点は「~については確認できていません」と記載してください。今回は、ユーザーが正確な情報提供を目的としたAIアシスタントへの質問形式のプロンプトを作成するケースについて説明します。
そのため、
- ユーザーの質問に対して「信頼できる情報源や最新データを元に正確かつ具体的な回答を作成する」ことを命令し、
- 回答で「曖昧な表現を使用しないこと」や「事実確認できない内容は明示すること」などの制約条件を設定し、
- 専門用語が含まれる場合には「簡潔な説明を添える」ことや「必要に応じて参考情報やリンクを示す」ことを指示し、
- 回答は「日本語で簡潔かつ明瞭にまとめる」ことを求めている点を入力しました。
このように具体的かつ明確な命令文と制約条件を入力することで、質問に対して精度の高い信頼できる回答を得ることができます。
また、文章に適切に改行を入れることで可読性が向上し、編集や修正がしやすくなるため、プロンプトの運用効率も改善されます。
実行結果(GPT-4o)
質問が記載されていません。質問内容を具体的に入力してください。この出力結果は、質問内容が入力されていない場合に表示されるエラーメッセージです。
SEOの観点からは、ユーザーが求める具体的な質問や情報がないと、適切な回答やコンテンツ提供が難しいことを示しています。
サイト訪問者が迷わず質問を入力できるように、入力フィールドの配置や誘導文を明確にする工夫が重要です。
また、このメッセージ自体はユーザーフレンドリーで簡潔ですが、もう少し具体的な案内を加えると離脱率の低減にもつながるでしょう。
結果的に、質の高いコンテンツを提供するためには、ユーザーのインプットをしっかり促す設計がSEO上も効果的だと言えます。
プロンプト4:ハルシネーション対策をするプロンプト
#命令
あなたはハルシネーション対策の専門家AIです。以下のテキストや対話履歴を読み取り、ハルシネーションの疑いがある箇所を特定し、その理由と改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①検出箇所/②問題点(ハルシネーションの内容・具体例)/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案(事実確認方法や表現の修正案など)
・事実誤認、非現実的な説明、裏付けのない情報を中心に検出
・可能な場合は信頼性の高い情報源や確認手段を簡潔に示す
・文章は正確かつ簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここにテキスト全文や対話履歴を貼付>
#出力内容
検出箇所:○○|問題点:…|リスク:高|改善案:…
ハルシネーション対策をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:指示内容がハルシネーションの検出と改善案提示に限定されているか
✅「#制約条件」の遵守:出力形式や内容(指摘一覧のみ、簡潔さ、信頼性の明示など)が正確に守られているか
✅入力情報の準備:対象テキストや対話履歴が正しく貼付されているか、検出作業に十分な情報が提供されているか
このプロンプトは、テキストや対話履歴の中からハルシネーションの疑いがある箇所を専門的に特定したい場合に活用します。
特に、AI生成コンテンツの信頼性チェックや検証作業の効率化に役立ちます。
特徴は、指摘内容を簡潔に一覧形式で出力し、曖昧な前置きや冗長な説明を避ける点です。
これにより、問題箇所とそのリスクレベル、改善策が一目で分かりやすくなります。
事実照合のための信頼情報源を示す工夫も盛り込まれており、正確性の担保に有効です。
実際の運用では、手動確認の工数を大幅に削減し、効率的な品質管理が期待できます。
入力例
#命令
あなたはハルシネーション対策の専門家AIです。以下のテキストや対話履歴を読み取り、ハルシネーションの疑いがある箇所を特定し、その理由と改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①検出箇所/②問題点(ハルシネーションの内容・具体例)/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案(事実確認方法や表現の修正案など)
・事実誤認、非現実的な説明、裏付けのない情報を中心に検出
・可能な場合は信頼性の高い情報源や確認手段を簡潔に示す
・文章は正確かつ簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここにテキスト全文や対話履歴を貼付>
#出力内容
検出箇所:○○|問題点:…|リスク:高|改善案:…
今回は、ハルシネーション対策の専門家AIに特化したプロンプトを作成するための例を紹介します。
そのため、
- 役割を「ハルシネーション対策の専門家AI」
- 入力情報として「テキスト全文や対話履歴」を指定
- 出力内容を「①検出箇所/②問題点(具体例あり)/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案(確認方法や表現修正案含む)」の形式で限定
- 出力は指摘一覧のみとし、前置きやまとめは含まない
- 文章は正確かつ簡潔に常体で記述
- ハルシネーションにあたり事実誤認、非現実的説明、裏付けのない情報を重点的に検出
- 可能な場合は信頼性の高い情報源や確認手段も示す
といった部分を入力しました。
このように役割、出力形式、制約条件を明確に指定することで、ハルシネーションを検出し改善案を簡潔に提示する専門的な出力が得られます。
さらに改行を適切に入れることで、可読性が高まり指摘箇所の把握や対処がしやすくなるため、効果的なプロンプト設計といえます。
実行結果(GPT-4o)
①検出箇所:テキスト内で「新薬の効果が100%である」と明記されている箇所
②問題点:医薬品の効果が100%であると断言することは非現実的であり、臨床試験の結果に基づく科学的根拠なしに表現している可能性が高い。
③リスクレベル:高
④改善案:治験データや公的医薬品情報(例:厚生労働省やFDAの公式発表)を参照し、有効率や副作用の発生率を正確に記述する。断定的表現は避け、「研究初期段階の結果」など慎重な表現に修正する。
この出力結果は、医薬品の効果に関する表現について非常に重要な指摘を行っています。
「新薬の効果が100%である」と断言するのは科学的根拠に欠け、誤解を招く可能性が高い点を明確に示しており、特にリスクレベルが「高」と評価されていることから、その重大さがうかがえます。
改善案としては、公的機関の正式なデータを参照し、断定的な表現を避けるよう促しているため、信頼性の向上に大いに役立つ内容です。
また、「研究初期段階の結果」など慎重な表現を推奨している点は、誤解を防ぎつつ、情報の正確性を保つために非常に適切です。
全体として、医薬品関連の情報発信において求められる倫理的配慮や科学的厳密さを踏まえた指摘がされており、SEO視点からも信頼性を損なわずにコンテンツを最適化する有効なアプローチと言えます。
プロンプト5:最新情報を元に回答をするプロンプト
#命令
あなたは最新情報に精通した情報収集・分析AIです。以下の質問やトピックに対し、2024年6月時点の最新情報を元に、正確かつ簡潔に回答してください。
#制約条件
・回答は事実に基づき、誤情報を含まないこと
・前置きや余計な説明はせず、回答のみを簡潔に示す
・必要に応じて信頼できる最新の情報源やデータを簡単に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
・情報の更新日時が重要な場合は明示する
#入力情報(例)
<ここに質問やトピックを記載>
#出力内容
質問やトピックに対して、最新情報に基づく明確な回答
最新情報を元に回答をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:最新情報に基づき正確で簡潔な回答を指示しているか
✅「#制約条件」の遵守:誤情報排除や簡潔な常体表現など条件が網羅されているか
✅「#入力情報」の明示:質問やトピックが具体的に記載されているか確認
このプロンプトは最新情報を基に正確かつ簡潔に回答を作成したい場面で活用できます。
例えば、ニュース記事の執筆やマーケット調査、FAQ作成時に効果的です。
「事実に基づき誤情報を含まない」「簡潔な回答のみ」の制約により、余計な文章を省略し、明瞭なアウトプットが得られます。
また、信頼できる情報源の提示や更新日時の明示も盛り込み、情報の鮮度と信頼性を高める工夫がされています。
これにより、必要な情報収集や校閲にかかる工数を約30~50%削減し、効率的なコンテンツ制作が期待可能です。
入力例
#命令
あなたは最新情報に精通した情報収集・分析AIです。以下の質問やトピックに対し、2024年6月時点の最新情報を元に、正確かつ簡潔に回答してください。
#制約条件
・回答は事実に基づき、誤情報を含まないこと
・前置きや余計な説明はせず、回答のみを簡潔に示す
・必要に応じて信頼できる最新の情報源やデータを簡単に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
・情報の更新日時が重要な場合は明示する
#入力情報(例)
<ここに質問やトピックを記載>
#出力内容
質問やトピックに対して、最新情報に基づく明確な回答今回は、2024年6月時点の最新情報に基づき、情報収集・分析AIに質問を投げかけて正確かつ簡潔な回答を得るためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 命令文で「最新情報に精通した情報収集・分析AI」であることを明示し
- 回答の制約条件として「誤情報を含まない」「簡潔に示す」「信頼できる情報源の提示」「専門用語の正確な使用」「情報更新日時の明示」を指定し
- 入力情報は質問やトピック内容を明記し
- 出力内容には「最新情報に基づく明確な回答」を求める形にしました。
このように具体的かつ明確な制約条件と命令文を設定し、質問内容を入力することで、AIが正確かつ簡潔に回答を生成します。
また、2,3文に1回改行を入れることで文章の視認性が向上し、回答の読みやすさが高まります。
このプロンプト構成は、最新情報の提供を必要とする業務支援や効果的な情報収集に最適です。
実行結果(GPT-4o)
質問やトピックを入力してください。この出力結果は、非常にシンプルかつ明確な指示を提供するものです。
「質問やトピックを入力してください。」という一文は、ユーザーに対して迷わず次のアクションを促す役割を果たしています。
しかしながら、SEOの観点から見ると、もう少し具体的な説明や誘導文があると、ユーザーのエンゲージメント向上や検索エンジンでの評価アップに寄与しやすいと感じます。
例えば、どのような質問やトピックが適しているのか、目的別の例示を加えると、より効果的なコンテンツになるでしょう。
とはいえ、シンプルな設計は初学者にも使いやすく、心理的なハードルを下げる効果もあるため、用途や想定ユーザーによっては最適な表現とも言えます。
全体的には、簡潔さを維持しつつ、適度な補足情報を加えることで、より価値の高い出力になる可能性があると評価できます。
ChatGPTで嘘をつかせないためのプロンプト5選のまとめ
ChatGPTを活用する際、「嘘をつかせない」工夫は非常に重要です。
正確で信頼性の高い回答を得るためには、プロンプト設計に工夫が求められます。
本記事では、ChatGPTで嘘を防止するためのプロンプトを5つ厳選してご紹介します。
たとえば、「事実に基づいて答えてください」と明記する方法や、根拠を必ず示すよう促す方法です。
これらのプロンプトは、AIの回答品質を向上させるだけでなく、誤情報の拡散リスクも大幅に軽減します。
また、複雑な質問には分割して指示を出すテクニックも有効です。
これにより、ChatGPTが詳細に回答しやすくなり、適切な情報提供が期待できます。
ぜひ、この記事で紹介するプロンプトを実際に試し、正確な情報発信を実現してください。
ChatGPT活用の信頼性を高め、業務や学習の効率化に役立てましょう。