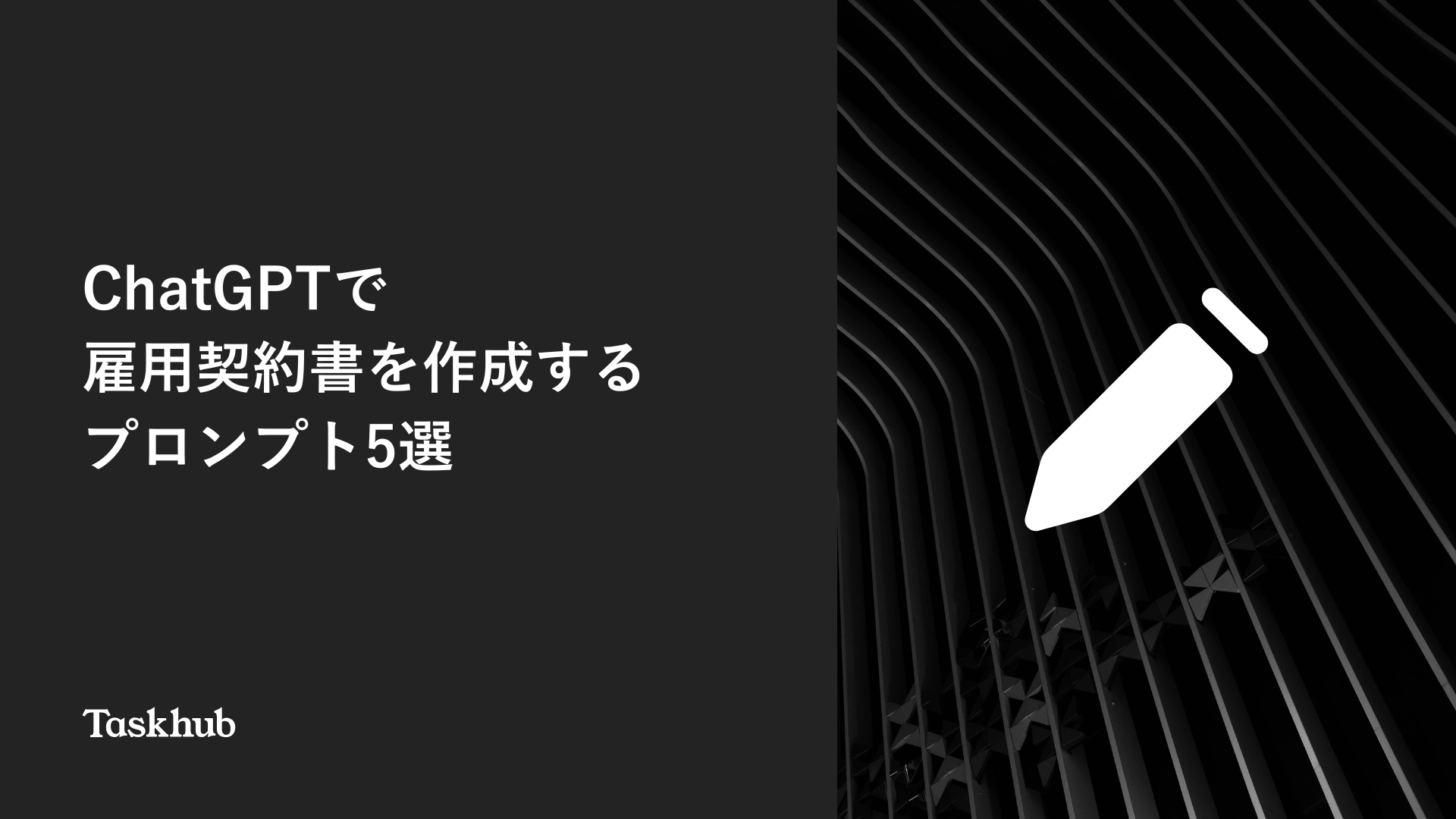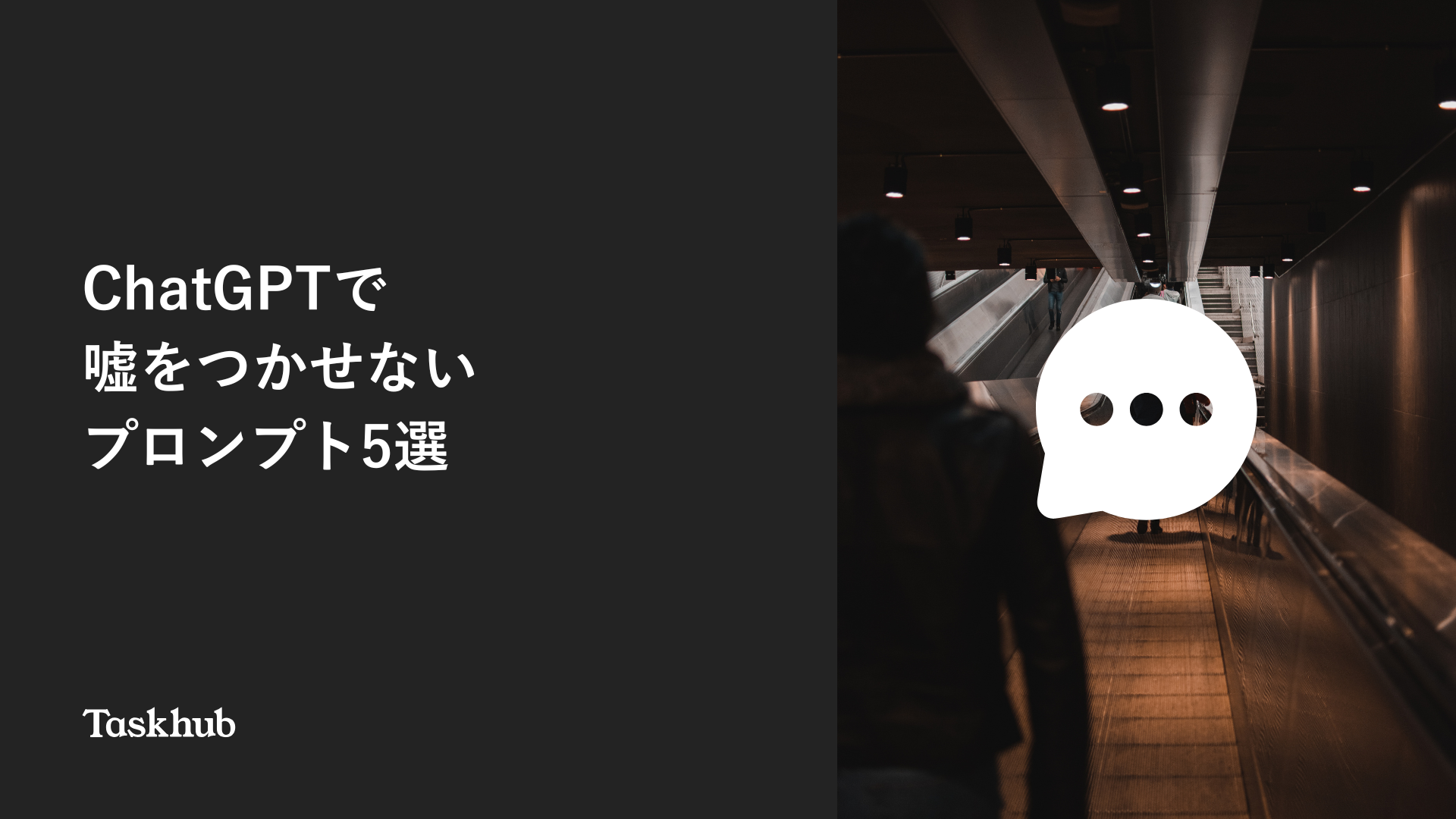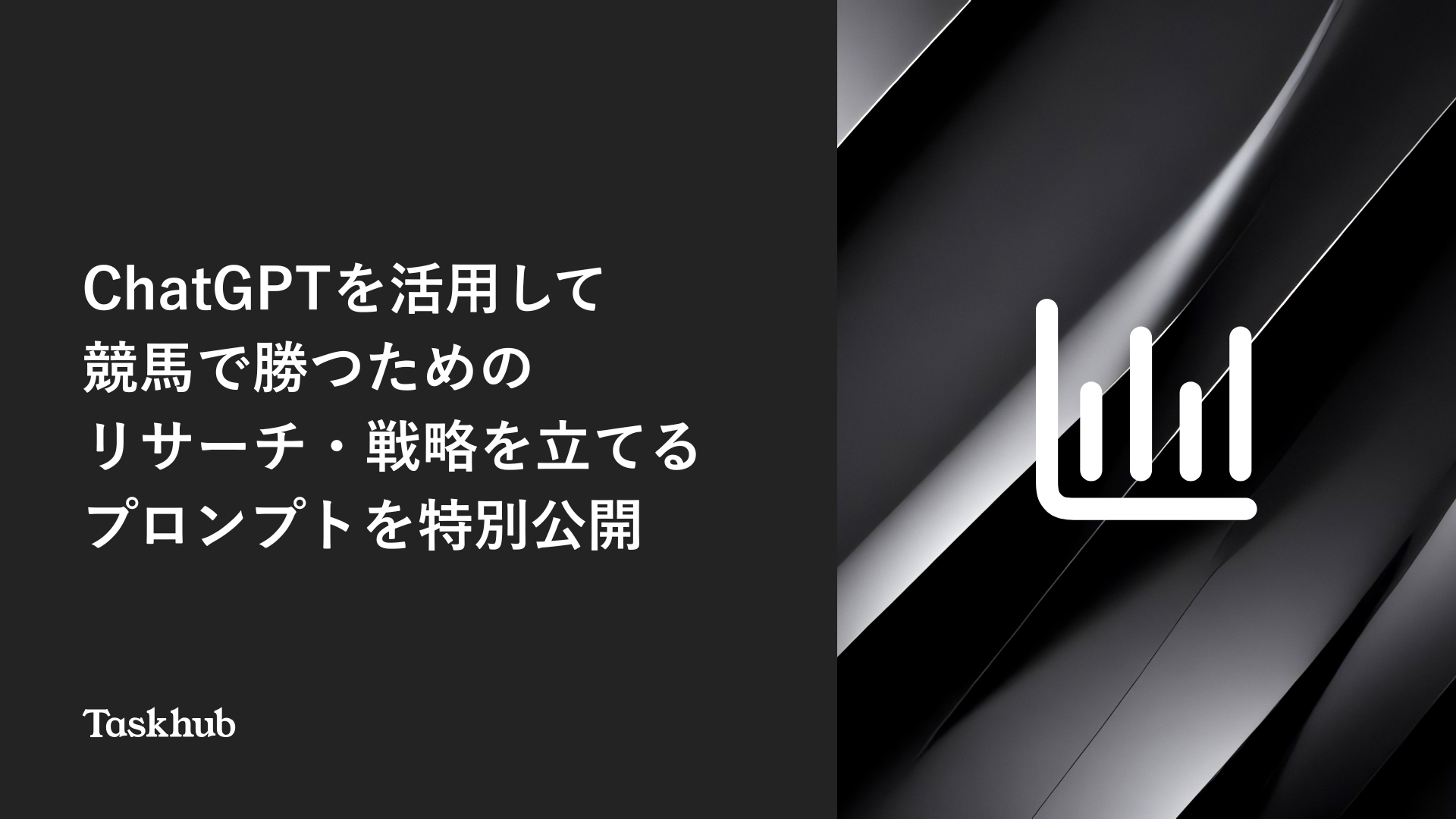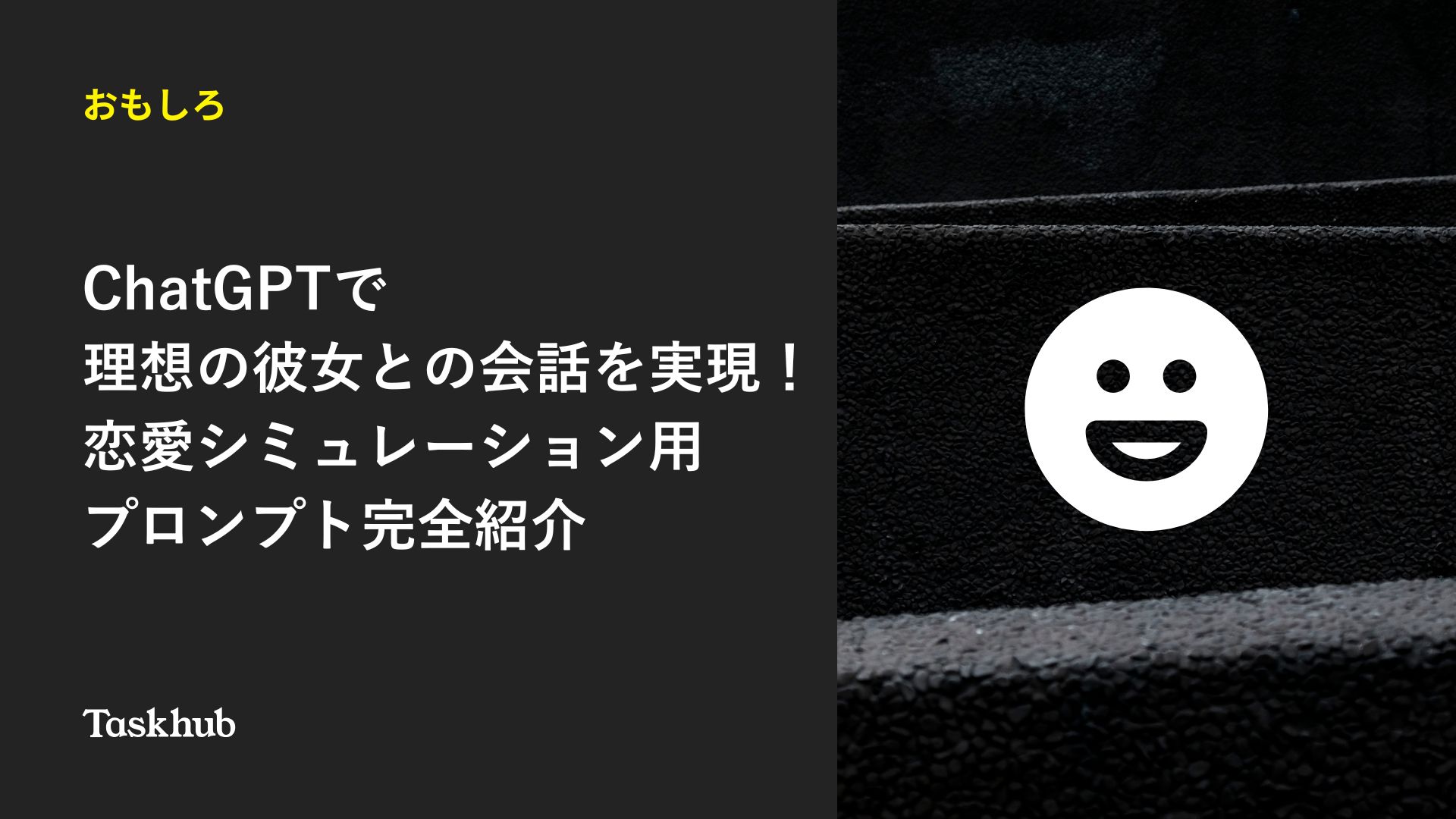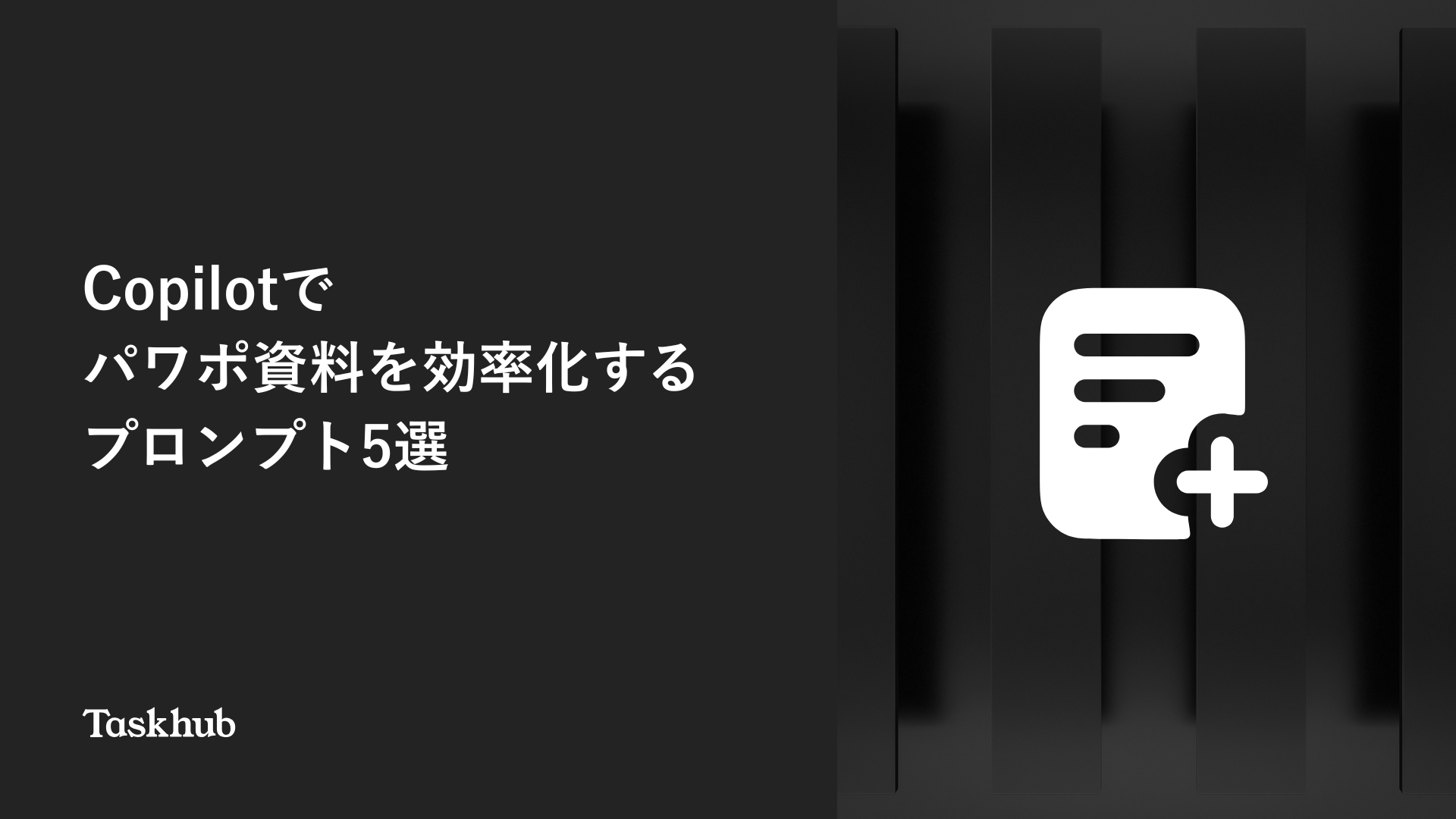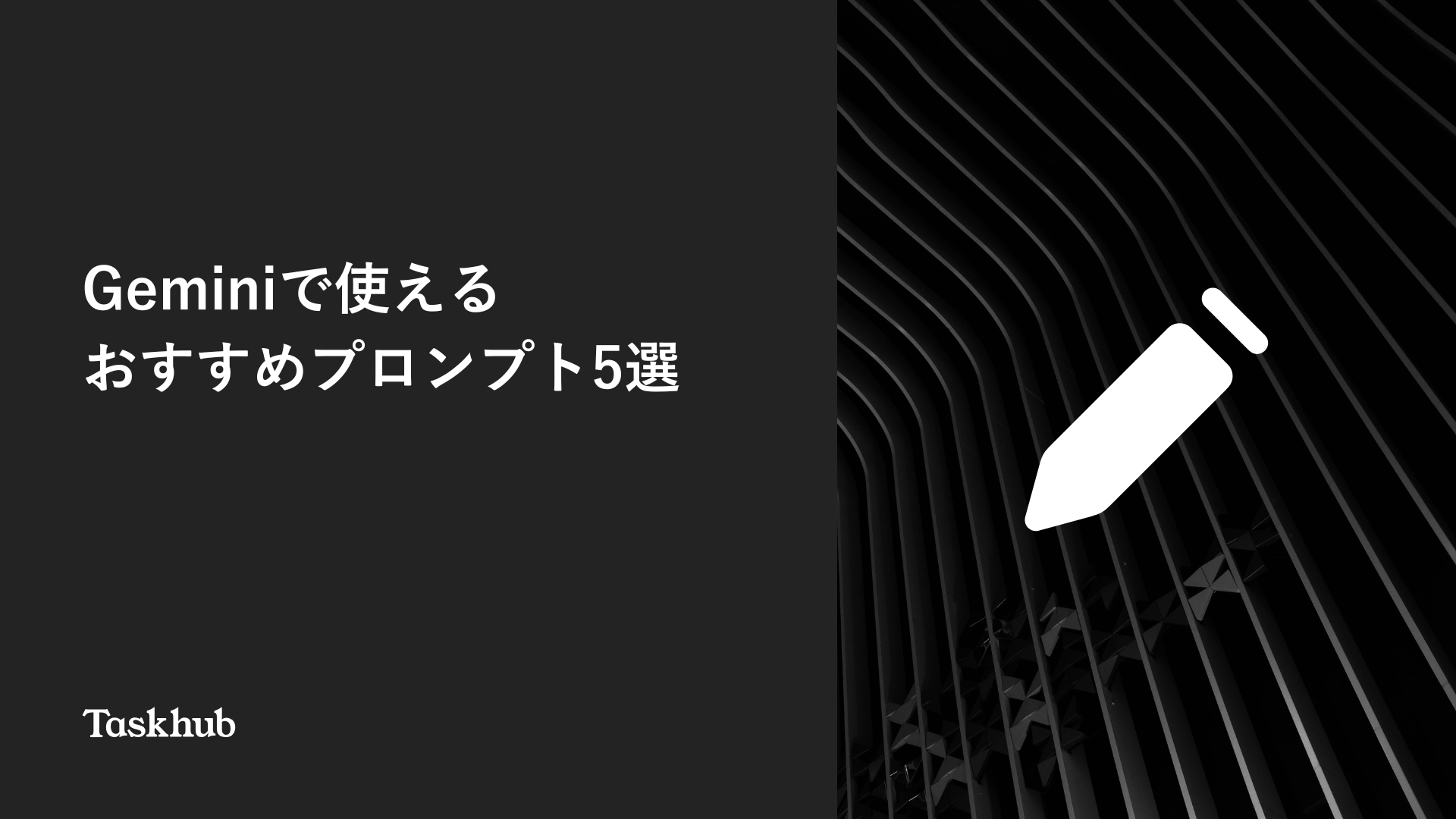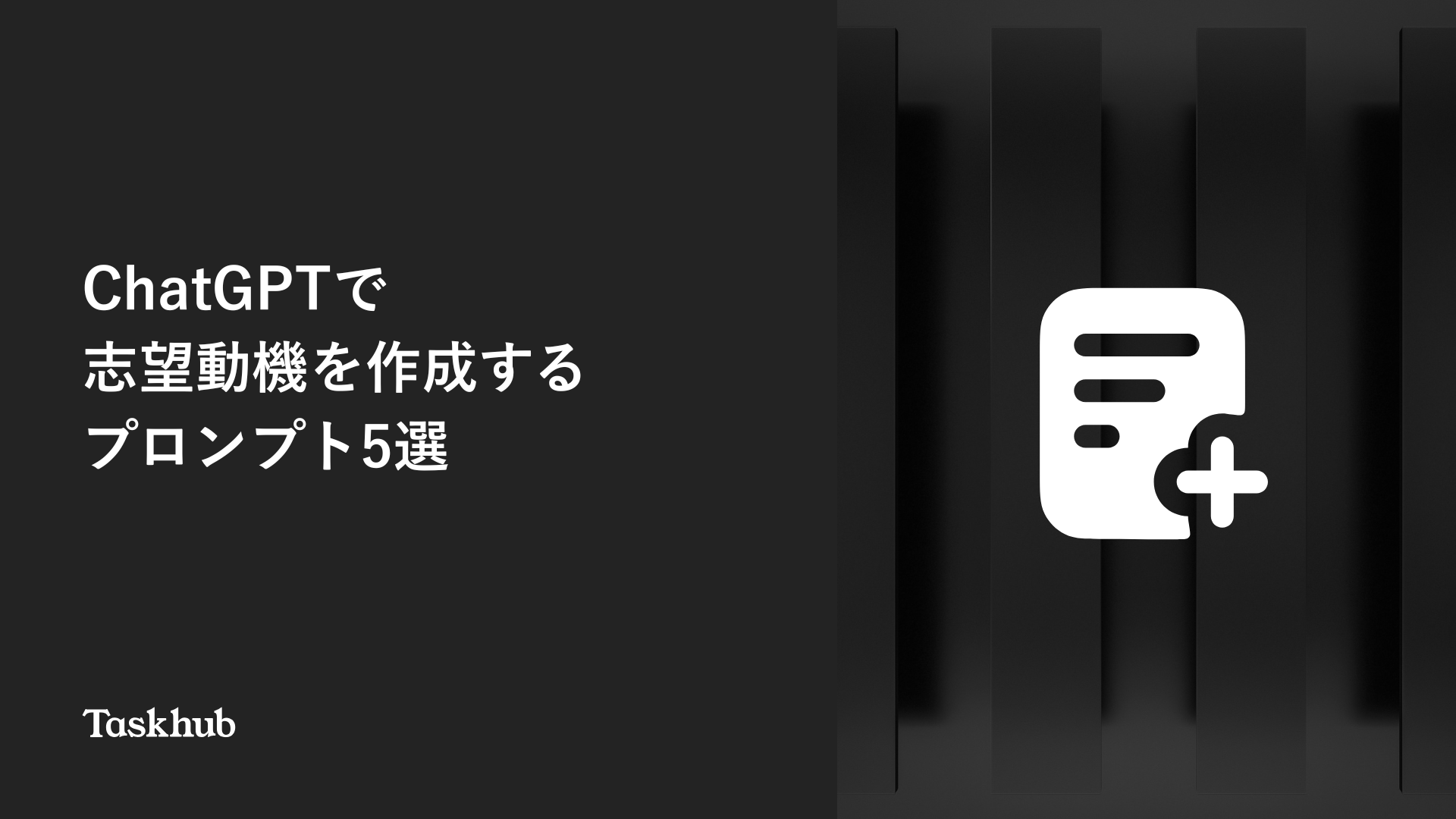「ChatGPTを使って雇用契約書を作成できるって本当?」
「文章は作れるけど、法的に問題がないか不安で使いこなせない…」
こんな疑問や不安を持つ方も少なくないでしょう。
本記事では、ChatGPTを活用した雇用契約書の作成方法や注意点、さらに法的に安心して使うためのポイントを詳しく解説します。
法律の専門知識がなくても理解できるように、実務に即した具体例を交えて説明しています。
実際のビジネスシーンで役立つ情報ばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅新規にオリジナルの雇用契約書を作成したいとき→プロンプト1がおすすめ
✅既存の契約を終了する際の契約解除契約書(終了契約書)を作成したいとき→プロンプト2がおすすめ
✅労働者と使用者間の契約内容を網羅的かつ条文形式で詳細に作成したいとき→プロンプト3がおすすめ
✅雇用ではなく業務委託契約書を作成したいとき→プロンプト4がおすすめ
✅秘密保持契約書(NDA)を作成したいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで雇用契約書作成をすることは可能?
ChatGPTは自然言語処理に優れ、多様な文書作成に活用されていますが、雇用契約書の作成に使う場合は慎重さが求められます。
この節では、ChatGPTで雇用契約書作成ができるかどうか、その可能性と限界を考察します。
雇用契約書作成の基本的な枠組みは生成可能
ChatGPTは豊富な学習データをもとに、雇用契約書の一般的な条項――労働時間、給与、休暇、解雇条件など――について文章化することができます。
ひな形としての作成や、条文の構成例提示には十分役立つでしょう。
しかし、雇用契約は企業の法務規定や労働法の最新動向に基づく細かな調整が必要であり、各企業や職種ごとに条件が大きく異なります。
したがって、あくまで参考案として扱うのが適切です。
最新の法令・判例反映は保証されない
ChatGPTの回答はトレーニング時点までの情報をベースに生成されるため、労働基準法の改正や新しい裁判例の影響は必ずしも反映されません。
結果として、法改正に沿った適切な条項が盛り込まれていないリスクがあります。
雇用契約書は労働者との権利義務関係を直接定める重要な書類であるため、法令遵守は必須です。
生成された契約書案は必ず法務担当や労働法に詳しい専門家にて確認・修正を行いましょう。
機密情報の取扱いに十分注意が必要
ChatGPTに雇用契約書の具体的な条件を入力するときは、社員個人情報や企業の戦略情報など機密性の高い内容を含まないように配慮してください。
クラウド上のAIに直接情報を入力する場合、情報漏えいのリスクがあります。
安全性を高めたい場合は、社内環境で動作するAI利用やダミーデータによる代替入力を検討しましょう。
情報セキュリティ規程に従った運用が不可欠です。
ChatGPT活用時の注意点と責任分界点
雇用契約書作成においてChatGPTは強力な支援ツールになりえますが、あくまで「補助的役割」と位置づけるべきです。
ChatGPTのアウトプットは法的文書の最終版ではない
AIが提示する条文は、法的助言を提供するわけではなく単なる参考例に過ぎません。
そのまま使用すると法的紛争を引き起こしかねませんので、必ず専門家によるレビューを経て文書化してください。
特に解雇規定や守秘義務など重要でデリケートな条項は慎重なチェックが重要です。
法的責任は利用者に帰属する
AIのアウトプット内容に基づいて作成された契約書の法的効力やトラブルが発生した場合、その責任は最終的に作成者や利用者にあります。
したがって、社内の承認フローにおいて法務専門家の関与を必ず組み込み、誰がどの段階で内容を承認したのか明確な記録を残すことが重要です。
これによりリスク管理と責任の所在を明確化し、問題発生時の対処を円滑に行えます。
以上のように、ChatGPTは雇用契約書の作成において参考資料や文章の草案作成に有用ですが、法的には最終的なチェック・承認は専門家に依存する必要があります。
また個人情報保護の観点から機密情報の扱いも慎重にならざるを得ません。
適切な運用ルールを定めて補助ツールとして活用することが、トラブル回避の鍵となります。
ChatGPTで雇用契約書作成をする3つのメリット
ChatGPTを活用して雇用契約書を作成することには、多くの実務上の利点があります。
特に効率性・コスト削減・品質の安定化という観点から、業務の最適化に大いに寄与します。
ここでは、実際に役立つ3つのメリットを具体的に解説します。
作成時間の大幅短縮と業務効率の向上
従来、雇用契約書の作成は内容の把握から条項の調整、契約条件の整理まで多くの時間を必要としました。
一から条文を検討し、類似ケースを調査する作業は担当者にとって大きな負担です。
しかし、ChatGPTを使えば、雇用形態や労働条件、契約期間などの基本情報を入力するだけで、数分でドラフトを作成可能です。
この結果、担当者は契約内容の精査や調整に注力でき、作成プロセス全体の時間を大幅に削減できます。
さらに、準備した雛形をもとにスムーズに社内外の承認や修正対応へと移行できるため、業務全体の効率化が期待できます。
コスト削減と専門家レビューの効率化
ChatGPTが作成した雇用契約書のドラフトは、ベースの構成や条項が整っているため、弁護士や労務の専門家へのレビュー依頼がスムーズです。
専門家は白紙から作成する必要がなく、曖昧な部分や法律上のリスク箇所の指摘に集中できるため、レビューにかかる時間と回数を削減できます。
結果として、外部専門家への依頼費用も抑えられ、契約書作成のコスト最適化につながります。
また、ChatGPTのプロンプトを使い回すことで、契約条件の変更に応じたドラフトの再生成も迅速に行えます。
この「AI生成+専門家確認」の併用は、品質とコストの両立を実現する効果的な方法です。
条項の網羅性向上と社内ナレッジの蓄積
ChatGPTは多様な雇用契約書のパターンを学習しており、退職条件、守秘義務、競業避止、労働時間規定など、漏れがちな重要条項を自動的に盛り込むことが可能です。
これにより、条項の抜け漏れリスクを低減し、より安全性の高い雇用契約書を作成できます。
さらに、生成した契約書と使用したプロンプトを社内に蓄積すれば、担当者間での知見の共有と標準化が促進されます。
ナレッジベース化されたテンプレートを活用すれば、担当者の経験値に依存せず一定の品質を保った雇用契約書が安定して作成可能になります。
この循環が組織の労務管理力や法務リテラシー向上にもつながるため、長期的な企業成長に寄与します。
ChatGPTで雇用契約書作成をする3つの注意点
ChatGPTを用いて雇用契約書を作成する際に重要なのは、「法的正確性・個人情報保護・責任範囲の明確化」の三つのポイントをしっかり管理することです。
ここでは特に見落とされやすい3つの注意点を具体的に解説します。
ChatGPTの提案をそのまま契約書に使わない
ChatGPTは過去のデータをもとに文章を生成しているため、最新の労働法や判例の変更を必ずしも反映していません。
条文のニュアンスや条件設定が意図とずれる場合もあり、誤解やトラブルの原因となることがあります。
したがって、AIが出力した雛型や文案をそのまま最終版として用いるのではなく、
必ず労務担当者や法務専門家のチェックを受けて修正・補完を行うことが不可欠です。
特に解雇条件や就業規則との整合性を慎重に確認してください。
個人情報や機密情報の入力に慎重になる
ChatGPTは利用する際に入力データを学習に利用される可能性があるため、社名や従業員の個人情報など機密性の高い情報をそのまま投入すると情報漏洩リスクが伴います。
これを防ぐため、特定可能な情報は伏せ字にするか、汎用的な表現に置き換える必要があります。
また、プライベート環境での利用(たとえばChatGPT Enterpriseや専用APIの利用)を検討し、
社内の情報セキュリティポリシーとも整合性を保った運用体制を整備しましょう。
法的責任の所在を明確にしておく
AIは法的なアドバイスを正式に行うものではなく、
ChatGPTを活用して作成した契約書の内容に関する法的責任は最終的に利用者にあります。
そのため、契約書の最終決裁プロセスに法律専門家のレビューを必ず組み込み、
責任の所在と承認の流れを明確にドキュメント化しましょう。
AI導入ガイドラインやリーガルチェック体制の整備によって、責任の分散ではなく透明化を図ることが重要です。
雇用契約書作成のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
ChatGPTを活用して雇用契約書を作成する際には、ただ文章を生成するだけではなく、労働法規や企業の方針に即した正確かつ実用的な文書を仕上げることが重要です。
そこで、本記事ではChatGPTを効果的に使いこなすために押さえておくべき3つのポイントを詳しく解説します。
雇用形態や労働条件を具体的に明示する
「正社員用の契約書」「アルバイトの契約書を作成して」といった漠然とした依頼では、ChatGPTは最適な内容を反映しづらくなります。
そこで、対象となる雇用形態(正社員・契約社員・パートタイマーなど)、勤務時間、給与体系、
試用期間の有無と期間、業務内容、勤務地などの労働条件を一文で具体的かつ簡潔に示しましょう。
この具体性が、必要な条項を網羅しつつ誤解のない契約書作成の土台となります。
法的必須要件と社内ポリシーを明確にリストアップする
AIに条項を作成させる際は、「労働基準法遵守」「解雇予告期間の明記」「非競業義務の設定」「機密保持条項の追加」など、
法律面での必須ポイントと、会社独自のルールや福利厚生など社内ポリシーの要件を一覧で指示することが肝要です。
これにより、ChatGPTが重要項目の抜け漏れを防ぎ、
リスク管理を考慮した契約書を生成しやすくなります。
文体や専門用語の統一とレビュー体制をあらかじめ設定する
契約書は一貫した文体・用語の選択が信頼性を左右します。
ChatGPTに対しては、「労働専門用語を正確に使用」「敬体ではなく常体で記述」「条番号は連番で付す」といった書式指示を明確に伝えましょう。
さらに、完成した初稿は必ず労務や法務の専門家によるレビューを組み込み、
誤解や法的リスクを排除する体制を整えることで、実務的に使える雇用契約書が完成します。
これらのポイントを押さえることで、ChatGPTによる雇用契約書作成の効率と品質を格段に向上させることが可能です。
プロンプト1:雇用契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは雇用契約書作成の専門家AIです。以下の条件を踏まえて、オリジナルの雇用契約書を作成してください。
#制約条件
・日本法(労働基準法、労働契約法等)に準拠して作成すること
・契約書に必要な基本的な条項(労働条件、賃金、就業時間、休日、解雇、機密保持など)を盛り込むこと
・条文ごとに見出しをつけわかりやすく簡潔に記述すること
・曖昧な表現を避け、具体的かつ明確な文章で作成すること
・法律専門用語は正確に使用し、読みやすい文体で書くこと
・必要に応じて注意点や補足説明を契約書末尾に記載してもよい
・長すぎないが、重要事項は漏らさないバランスを意識すること
#入力情報(例)
<以下に雇用契約の条件や会社名・労働者情報など具体的な情報を記載してください>
#出力内容
完全な雇用契約書のドラフト全文
雇用契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#制約条件」の確認:日本法に準拠しているか、必要な条項が全て含まれているかを必ずチェック
✅「条文ごとの見出し」の設定:各条文にわかりやすく簡潔な見出しが付けられているかを確認
✅「具体的かつ明確な表現」の使用:曖昧な表現を避け、正確な法律用語でわかりやすく書かれているかを最終確認
このプロンプトは日本法に準拠したオリジナルの雇用契約書を効率的に作成するためのものです。
人事担当者や法務担当者が、労働条件や機密保持など重要条項を網羅した契約書を簡潔かつ明確に用意したい際に活用できます。
「#制約条件」により法律用語の正確な使用や条文ごとの見出し付けを促し、読みやすく理解しやすい文章作成が工夫されています。
これにより、曖昧な表現を排除した質の高いドラフト作成が可能です。
実際の使用では、契約書作成にかかる工数が大幅に削減され、数時間から数日要する作業が数分で完了することも期待できます。
入力例
#命令
あなたは雇用契約書作成の専門家AIです。以下の条件を踏まえて、オリジナルの雇用契約書を作成してください。
#制約条件
・日本法(労働基準法、労働契約法等)に準拠して作成すること
・契約書に必要な基本的な条項(労働条件、賃金、就業時間、休日、解雇、機密保持など)を盛り込むこと
・条文ごとに見出しをつけわかりやすく簡潔に記述すること
・曖昧な表現を避け、具体的かつ明確な文章で作成すること
・法律専門用語は正確に使用し、読みやすい文体で書くこと
・必要に応じて注意点や補足説明を契約書末尾に記載してもよい
・長すぎないが、重要事項は漏らさないバランスを意識すること
#入力情報(例)
会社名:株式会社テックソリューションズ
所在地:東京都新宿区西新宿1-1-1
労働者氏名:山田 太郎
職種:システムエンジニア
雇用形態:正社員(無期雇用契約)
開始日:2024年7月1日
就業場所:東京都新宿区西新宿1-1-1 本社
労働時間:午前9時から午後6時まで(休憩1時間含む)
休日:土日祝日及び年末年始、会社指定の休暇日
賃金:月額30万円(固定給)、毎月25日締め翌月5日払い
試用期間:3ヶ月(条件変更なし)
機密保持義務:あり
#出力内容
完全な雇用契約書のドラフト全文
今回は、株式会社テックソリューションズと山田太郎さんの間で締結する正社員雇用契約書のドラフト作成を目的としたプロンプトを作成しました。
そのため、
- 会社名を「株式会社テックソリューションズ」
- 労働者氏名を「山田太郎」
- 職種を「システムエンジニア」
- 雇用形態を「正社員(無期雇用契約)」
- 労働開始日を「2024年7月1日」
- 就業場所を「東京都新宿区西新宿1-1-1 本社」
- 労働時間を「午前9時から午後6時まで(休憩1時間含む)」
- 休日を「土日祝日及び年末年始、会社指定の休暇日」
- 賃金を「月額30万円(固定給)、毎月25日締め翌月5日払い」
- 試用期間を「3ヶ月(条件変更なし)」
- 機密保持義務を「あり」
と入力しました。
このように具体的に勤務条件や企業情報、労働者情報を入力すると、労働基準法や労働契約法に準拠した、必要な条項を盛り込みつつも明確・簡潔に記載された雇用契約書のドラフトを自動的に生成することができます。
また、文章中に適度な改行を挟むことで、視認性を高め、条件の確認や修正がしやすくなるため、契約書の品質向上や業務効率化に役立ちます。
実行結果(GPT-4o)
雇用契約書
株式会社テックソリューションズ(以下「甲」という。)と山田 太郎(以下「乙」という。)は、以下の条件により雇用契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条【雇用の期間及び形態】
甲は乙を正社員(無期雇用契約)として、2024年7月1日より雇用する。
第2条【業務内容】
乙はシステムエンジニアとして、甲の定める業務を誠実に遂行するものとする。
第3条【就業場所】
乙の主たる就業場所は、甲の本社所在地である東京都新宿区西新宿1-1-1とする。
第4条【労働時間及び休憩時間】
乙の就業時間は、午前9時から午後6時までとし、その間に1時間の休憩を含むものとする。
第5条【休日及び休暇】
1. 乙の休日は土曜日、日曜日、祝日および年末年始とする。
2. 甲が別に指定する休暇日も休日とする。
3. 法令に定める年次有給休暇は付与する。
第6条【賃金】
1. 乙の賃金は月額300,000円(固定給)とする。
2. 賃金の締め日は毎月25日とし、支払日は翌月5日とする。
3. 賃金は乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
第7条【試用期間】
1. 乙の試用期間は3か月間とする。
2. 試用期間中も本契約と同一の労働条件とする。
第8条【解雇】
1. 甲は労働基準法その他の法令に従い、正当な理由がある場合に限り、乙を解雇できる。
2. 解雇予告は労働基準法第20条に基づき、原則として30日前に行うものとする。
第9条【機密保持】
乙は、業務上知り得た甲の技術上、営業上の秘密情報を在職中および退職後も第三者に漏洩してはならない。
第10条【その他】
本契約に定めのない事項については、労働基準法、労働契約法その他の関連法令に従うものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。
2024年6月30日
住所:東京都新宿区西新宿1-1-1
株式会社テックソリューションズ
代表取締役 ○○ ○○(印)
住所:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
山田 太郎(印)
【備考】
・試用期間中の労働条件に変更はありませんが、業務遂行状況により本採用としない場合があります。
・解雇に関しては、労働基準法に基づく手続き及び合理的理由の提示が必要です。
・機密保持義務は、就業期間中及び退職後も継続します。
今回の雇用契約書の作成例は、非常に標準的かつ明確な構成であると感じました。
各条項が具体的な内容で規定されているため、双方の権利義務が明確になっておりトラブル防止に寄与します。
特に、試用期間中の労働条件の明示や解雇に関する法令遵守の条項は、法的リスクを抑える上で重要なポイントです。
また、機密保持義務についても就業中だけでなく退職後も継続する旨が明記されており、企業の信用保護に配慮されています。
休日・休暇、賃金の支払い方法まで細かく記載されているため、労働者にとっても安心感を与える契約書です。
ただし、もし対象の業務内容や就業場所に変更があった際など、柔軟な対応方法を付記するとより親切でしょう。
総じて、労働基準法その他の関連法令に準拠しており、実務で広く使用可能な仕様となっています。
社内の法務チェックや労働者説明の際に、このような包括的な雇用契約書をベースにするのは非常に効果的といえます。
プロンプト2:終了契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIです。以下の内容に基づき、終了契約書(契約解除契約書)の全文を日本法に準拠して作成してください。
#制約条件
・条項ごとに番号を振り、条文形式で記載すること
・不必要な法律用語の多用を避け、読みやすく簡潔な文章とすること
・契約の解除理由、解除日時、双方の義務・権利の整理、損害賠償の有無、秘密保持などの重要事項を網羅すること
・特に紛争防止のための条項(通知方法、管轄裁判所など)を含めること
・専門用語は正確に用い、日本法に準拠した内容とすること
#入力情報
・契約解除の理由と日時
・解除する契約の名称および契約当事者
・解除に伴う金銭の授受の有無、条件
・解除後の双方の義務(例:情報返還、秘密保持)等
・損害賠償の有無、範囲
・その他特記事項
#出力内容
終了契約書全文(契約解除契約書)
終了契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:契約書作成専門の法務AIとして日本法に準拠し、終了契約書を作成することを明確に指示しているか
✅「#制約条件」の遵守:条項に番号を振り、簡潔で読みやすい条文形式、重要事項や紛争防止条項を網羅しているか
✅「#入力情報」の完全性:解除理由・日時、契約名・当事者、金銭授受の有無・条件、解除後の義務、損害賠償、その他特記事項がすべて揃っているかをチェック
このプロンプトは契約解除に関する終了契約書を、日本法に準拠して正確かつ簡潔に作成したい場合に活用します。契約解除の理由や日時、双方の義務や損害賠償、紛争防止条項まで網羅的にカバーできる点が特徴です。
特に条項ごとに番号を付けて条文形式にすることで、法的文書としての体裁を整えつつ、専門用語の使いすぎを避け、読みやすさにも配慮しています。実際の入力情報を反映するだけで、プロの品質に近い文書が素早く生成可能です。
これにより、一から契約解除書を作成する工数を大幅に削減でき、法務担当者の時間短縮に貢献します。
入力例
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIです。以下の内容に基づき、終了契約書(契約解除契約書)の全文を日本法に準拠して作成してください。
#制約条件
・条項ごとに番号を振り、条文形式で記載すること
・不必要な法律用語の多用を避け、読みやすく簡潔な文章とすること
・契約の解除理由、解除日時、双方の義務・権利の整理、損害賠償の有無、秘密保持などの重要事項を網羅すること
・特に紛争防止のための条項(通知方法、管轄裁判所など)を含めること
・専門用語は正確に用い、日本法に準拠した内容とすること
#入力情報
・契約解除の理由と日時:業務内容の変更に伴う合意による解除、2024年5月31日
・解除する契約の名称および契約当事者:「業務委託契約書」、委託者:株式会社A、受託者:株式会社B
・解除に伴う金銭の授受の有無、条件:株式会社Aは株式会社Bに解除手続き完了後、未払いの業務報酬として100万円を2024年6月10日までに支払う
・解除後の双方の義務(例:情報返還、秘密保持)等:双方は相手方の資料・情報を直ちに返還し、秘密保持義務を契約解除後も継続する
・損害賠償の有無、範囲:双方は本契約解除に関して、一切の損害賠償請求をしないものとする
・その他特記事項:本契約書の変更は双方の書面による合意が必要。通知は電子メール及び書面で行う。
#出力内容
終了契約書全文(契約解除契約書)
今回は、株式会社Aと株式会社Bの業務委託契約書の契約解除契約書(終了契約書)作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 解除する契約の名称を「業務委託契約書」
- 委託者を「株式会社A」
- 受託者を「株式会社B」
- 解除の理由を「業務内容の変更に伴う合意による解除」
- 解除日時を「2024年5月31日」
- 解除に伴う金銭授受の条件を「株式会社Aが株式会社Bに解除手続き完了後、未払いの業務報酬として100万円を2024年6月10日までに支払うこと」
- 解除後の義務として「双方は相手方の資料・情報を直ちに返還し、秘密保持義務を解除後も継続すること」
- 損害賠償の有無は「双方とも一切の損害賠償請求をしない」
- 通知方法は「電子メール及び書面」
- 本契約書の変更は「双方の書面による合意が必要」
といった具体的な情報を入力しました。
このように詳細かつ整理された情報を入力することで、法務AIが日本法に準拠した読みやすく明確な契約解除契約書の全文を生成できます。
また、文中に適宜改行を挟むことで視認性が高まり、内容の把握やプロンプトの微調整も容易になります。
実行結果(GPT-4o)
終了契約書(契約解除契約書)
株式会社A(以下「委託者」という。)と株式会社B(以下「受託者」という。)は、以下の通り「業務委託契約書」(以下「本契約」という。)を解除することについて合意し、本契約書を作成する。
第1条(契約解除の合意)
委託者および受託者は、業務内容の変更に伴い、双方の合意により、本契約を2024年5月31日をもって解除することに合意する。
第2条(金銭の授受について)
1. 委託者は、解除手続き完了後、未払いの業務報酬として受託者に対し、金100万円を2024年6月10日までに支払うものとする。
2. 上記支払をもって、本契約に関する金銭債務はすべて完了する。
第3条(資料・情報の返還および秘密保持)
1. 両当事者は、本契約解除日以降、相手方から受領した資料および情報を速やかに返還し、または相手方の指示に従い廃棄するものとする。
2. 両当事者は、本契約解除後も、本契約期間中に知り得た秘密情報について秘密保持義務を負い、第三者に漏洩しないものとする。
第4条(損害賠償の免除)
本契約解除に伴い、双方は相手方に対して一切の損害賠償請求を行わないものとする。
第5条(契約書の変更)
本契約書の変更・補足は、双方の書面による合意がなければ効力を有しない。
第6条(通知)
1. 本契約に関する通知または連絡は、電子メールおよび書面の両方法で行うものとする。
2. 通知は、相手方が指定した連絡先に送付し、送付後5日経過した時点で到達したものとみなす。
第7条(準拠法および管轄裁判所)
本契約書の解釈および履行については日本法を準拠法とし、両当事者は本契約に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。
令和6年5月31日
委託者:株式会社A
代表取締役 ________(署名)
受託者:株式会社B
代表取締役 ________(署名)
この終了契約書の出力結果は、業務委託契約の解除に関する基本的な必要事項を網羅しており、非常に実務的で使いやすい内容となっています。
特に、契約解除の合意日や未払い報酬の支払い期限を明確に定めている点が評価できます。
また、資料返還や秘密保持の条項が明記されていることで、解除後のトラブル防止に寄与すると考えられます。
加えて、損害賠償免除の条項を設けることで、不要な紛争の発生を抑制できる点も重要です。
通知方法や準拠法・管轄裁判所の規定が明瞭にされているため、法的な整合性も高い印象を受けます。
一方で、第5条の契約書の変更については、書面による合意が必要とされているものの、オンラインでの合意方法について触れていないため、現代のビジネス慣行に合わせて多少の柔軟性を持たせる検討も一案です。
また、解除理由が「業務内容の変更」とのみ記載されているため、具体的な背景説明を補足するとより明確になるでしょう。
総じて、本契約書はビジネス上の最低限のリスクをカバーしつつ、双方にとって分かりやすく実務的な合意書として活用が期待できます。
今後の契約解除書作成におけるテンプレートとして非常に有用であり、SEOの観点からもキーワードが適切に含まれている点で良好と言えます。
プロンプト3:労働契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは労働契約書作成の専門家AIです。以下の要件に基づいて、適切かつ法律に準拠した労働契約書のドラフトを作成してください。日本の労働法規に準拠し、労働者と使用者双方の権利と義務を明確に反映してください。
#制約条件
・出力は労働契約書全文のドラフトのみ(説明・前置き不要)
・契約期間、業務内容、勤務時間、給与、休暇、有給、退職条件など主要条項を網羅
・条項は条文形式で明確かつ簡潔に記載
・日本の労働基準法や関連法令を遵守
・専門用語は正確に用い、文章は法律文書として適切な常体
#入力情報(例)
・契約期間:〇年〇月〇日~〇年〇月〇日
・業務内容:〇〇業務全般
・勤務時間:〇時~〇時(休憩〇分含む)
・給与:月額〇〇円(別途諸手当有無も記載)
・休暇・休日:法定通りまたは別途規定
・退職:解約予告期間や手続き方法等
#出力内容
<労働契約書全文ドラフト>
労働契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の理解:労働契約書作成に特化したAIとして、法律に準拠した内容を明確に反映する
✅「#制約条件」の確認:出力は契約書全文のドラフトのみで説明不要、条文形式で簡潔かつ正確に記載する
✅「#入力情報」の具体化:契約期間や業務内容など、必要な項目を正確かつ網羅的に入力しているか確認する
このプロンプトは、日本の労働法規に準拠した労働契約書のドラフトを自動作成するためのものです。
契約期間や業務内容、給与、休暇、退職条件など主要な条項を網羅し、専門的な労働契約書を迅速に用意したいシーンで役立ちます。
特徴は、条文形式で明確かつ簡潔に記載する制約や、法律用語を正確に用いる点にあります。
これにより、専門知識がなくとも法的に適正な契約書を効率的に作成可能です。
実際に活用すれば、契約書作成にかかる工数を数時間から数十分へ大幅に短縮でき、業務効率化に貢献します。
入力例
#命令
あなたは労働契約書作成の専門家AIです。以下の要件に基づいて、適切かつ法律に準拠した労働契約書のドラフトを作成してください。日本の労働法規に準拠し、労働者と使用者双方の権利と義務を明確に反映してください。
#制約条件
・出力は労働契約書全文のドラフトのみ(説明・前置き不要)
・契約期間、業務内容、勤務時間、給与、休暇、有給、退職条件など主要条項を網羅
・条項は条文形式で明確かつ簡潔に記載
・日本の労働基準法や関連法令を遵守
・専門用語は正確に用い、文章は法律文書として適切な常体
#入力情報(例)
・契約期間:2024年7月1日~2026年6月30日
・業務内容:営業企画業務全般
・勤務時間:9時00分~18時00分(休憩60分含む)
・給与:月額300,000円(交通費別途支給)
・休暇・休日:週休2日制(土・日)、法定年次有給休暇あり
・退職:解約予告期間30日、退職希望は書面にて1ヶ月前通知
#出力内容
<労働契約書全文ドラフト>今回は、2024年7月1日から2026年6月30日までの有期労働契約に基づき営業企画業務全般を担当する労働契約書のドラフト作成を依頼するプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約期間は「2024年7月1日~2026年6月30日」
- 業務内容は「営業企画業務全般」
- 勤務時間は「9時00分~18時00分(休憩60分含む)」
- 給与は「月額300,000円(交通費別途支給)」
- 休暇・休日は「週休2日制(土・日)、法定年次有給休暇あり」
- 退職条件は「解約予告期間30日、退職希望は書面にて1ヶ月前通知」
という具体的な要件を入力しました。
このように詳細かつ具体的な労働条件を入力することで、労働基準法や関連法令に準拠した労働契約書全文ドラフトを生成できます。
また、条文を明確に区切り適宜改行を挟む形式で提示するため、条項ごとの視認性が高まり、契約内容を確認・修正しやすくなっています。
実行結果(GPT-4o)
<労働契約書全文ドラフト>
第1条(契約期間)
本契約の期間は、2024年7月1日から2026年6月30日までとする。
第2条(業務内容)
労働者は、使用者の指示により、営業企画業務全般に従事するものとする。
第3条(勤務時間及び休憩)
1. 労働者の勤務時間は、午前9時00分から午後6時00分までとする。
2. 休憩時間は1時間とし、勤務時間中にこれを付与する。
第4条(休日及び休暇)
1. 休日は、週休2日制とし、毎週土曜日及び日曜日とする。
2. 労働者には、労働基準法第39条に定める年次有給休暇を付与する。
第5条(給与)
1. 労働者の給与は、月額300,000円とする。
2. 交通費は別途実費支給とする。
3. 給与の支払いは、毎月末日に翌月分を支払うものとする。
第6条(退職及び解約予告)
1. 使用者及び労働者は、本契約を解約する場合、少なくとも30日前に相手方に予告しなければならない。
2. 労働者が退職を希望する場合は、1ヶ月前までに書面にて使用者に通知するものとする。
第7条(その他)
本契約に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令に従うものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、使用者及び労働者が署名押印の上、各1通を保有する。
令和○年○月○日
使用者(名称)_______________
(代表者氏名)_______________
(住所)__________________
労働者(氏名)_______________
(住所)__________________この労働契約書全文ドラフトは、業務内容や契約期間、給与条件など重要事項が明確に記載されており、基本的な構成がしっかりしています。
特に勤務時間や休日、年次有給休暇の付与に関して労働基準法を遵守している点は、企業側と労働者双方の安心感につながるでしょう。
給与支払いのタイミングや交通費の取扱いも具体的で、給与トラブル防止に役立ちます。退職や解約予告に関する条項も明示的に規定されており、双方の権利義務関係が明瞭です。
ただし、第7条で「その他」の事項は労働基準法等に依拠するとありますが、より具体的な安全衛生や秘密保持、競業避止などの条項追加も検討するとリスク管理が強化されるでしょう。
また、契約日や署名欄の記入欄が空白となっているため、運用の際には忘れずに埋める必要があります。
全体として、シンプルかつ労働法令に準拠した内容であり、一般的な営業企画職の労働契約として十分なドラフトと言えます。
今後の活用にあたっては、実情に応じたカスタマイズや専門家による最終チェックも推奨されるでしょう。
プロンプト4:業務委託契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは契約書作成の専門家AIです。業務委託契約書を作成するために、以下の条件とポイントを踏まえ、法律的に正確かつ実務的に使いやすい契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に基づいて作成すること
・条項ごとに見出しを付け、誰が読んでもわかりやすい文章で書くこと
・業務範囲、報酬、納期、秘密保持、権利帰属、契約解除、損害賠償等の主要項目を必ず含めること
・契約の当事者がお互いの義務と権利を明確に理解できるように簡潔かつ正確に表現すること
・専門用語は必要に応じて使うが、難解すぎない文章とすること
・完成した契約書全文のみを出力し、説明や余計な文章は一切付け加えないこと
#入力情報
・業務委託の内容、報酬、期間など契約の具体条件を別途入力しますので、入力後に契約書を全文作成してください。
業務委託契約書作成をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#制約条件」の確認:日本法に基づいているか、必須条項がすべて含まれているかを確認
✅「文章表現」の確認:簡潔かつ正確で、専門用語も適切なレベルかどうかをチェック
✅「出力形式」の確認:契約書全文のみを出力し、説明や余計な文章が含まれていないかを確認
このプロンプトは、日本法に基づく業務委託契約書を正確かつ実務的に作成したい際に活用します。
条項ごとに見出しを付け、契約当事者が内容を理解しやすい文章構成になっているため、法律的な専門知識がなくても使いやすいのが特徴です。
「業務範囲」「報酬」「秘密保持」など重要項目を必須とし、余計な説明を排除して完成した契約書全文だけを出力する点も工夫されています。
このプロンプトを利用することで、契約書作成にかかる工数を大幅に削減し、従来なら数時間かかるドラフト作成を十数分程度に短縮可能です。
別途入力情報に業務内容や報酬など具体条件を入れるだけで、スムーズに実務で使える契約書を生成できます。
入力例
#命令
あなたは契約書作成の専門家AIです。業務委託契約書を作成するために、以下の条件とポイントを踏まえ、法律的に正確かつ実務的に使いやすい契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に基づいて作成すること
・条項ごとに見出しを付け、誰が読んでもわかりやすい文章で書くこと
・業務範囲、報酬、納期、秘密保持、権利帰属、契約解除、損害賠償等の主要項目を必ず含めること
・契約の当事者がお互いの義務と権利を明確に理解できるように簡潔かつ正確に表現すること
・専門用語は必要に応じて使うが、難解すぎない文章とすること
・完成した契約書全文のみを出力し、説明や余計な文章は一切付け加えないこと
#入力情報
・業務委託の内容、報酬、期間など契約の具体条件を別途入力しますので、入力後に契約書を全文作成してください。
今回は、業務委託契約書を作成するAIへの指示文を作成するためのプロンプトを提示しました。
そのため、
- 契約書の種類を「業務委託契約書」と指定し、
- 日本法に準拠すること、
- 条項ごとに見出しを付けて読みやすくすること、
- 業務範囲、報酬、納期、秘密保持、権利帰属、契約解除、損害賠償などの主要項目を必須で含めること、
- 誰でも理解できる簡潔かつ正確な表現とすること、
- 専門用語は必要に応じて使用しつつも難解すぎない文章を心掛けること、
- 最終的には完成した契約書の全文のみをテキスト形式で出力し、余計な説明は一切付け加えないこと、
という制約を設定しています。
入力情報としては、業務委託の具体的内容、報酬、期間などの契約条件を別途用意してからその情報を入力し、完全な契約書ドラフトを生成する流れを想定しています。
このように詳細な条件と目的を明示することで、生成される契約書の品質や実務的使いやすさが向上します。
また、文中に適宜改行を入れることで視認性が高まり、個別の条件が把握しやすくなり、プロンプトの修正や管理が容易になる点も特徴です。
実行結果(GPT-4o)
業務委託契約書
第1条(目的)
本契約は、委託者が委託する業務(以下「本業務」という)を受託者が遂行し、その対価を支払うことに関し、両者の権利義務を明確にすることを目的とする。
第2条(業務内容)
受託者は、委託者から委託された以下の業務を誠実に遂行するものとする。
1. 【業務内容を具体的に記載】
2. その他、両者が合意した業務
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、【開始年月日】から【終了年月日】までとする。ただし、期間満了前に書面にて更新の合意がある場合はこの限りでない。
第4条(報酬および支払条件)
1. 委託者は、受託者に対し、本業務の対価として総額【金額】円(税込)を支払う。
2. 報酬の支払方法および時期は、【支払方法】により、【支払時期】までに支払うものとする。
3. 支払に係る銀行振込手数料は委託者の負担とする。
第5条(納期)
受託者は、【成果物名】について、【納期】までに納品するものとする。納品形態は【納品方法】とし、納品物は委託者の検収を受けた後、受理されたものとみなす。
第6条(秘密保持)
1. 両者は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の義務は、本契約終了後も【期間】年間継続するものとする。
第7条(権利帰属)
1. 本業務により作成された成果物に関する著作権その他の知的財産権は、委託者に帰属するものとする。
2. 受託者は、委託者に対して成果物を使用するために必要な権利を無償で譲渡し、必要な協力を行うものとする。
第8条(契約解除)
1. 契約当事者の一方が本契約の条項に違反し、相手方より書面による是正の催告を受けても合理的な期間内に是正しない場合、相手方は本契約を解除できる。
2. 双方は、相手方に重大な信用不安が生じた場合、またはやむを得ない事由がある場合には、書面通知をもって直ちに本契約を解除できる。
第9条(損害賠償)
一方当事者が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、当該違反当事者は相手方に対し、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第10条(雑則)
1. 本契約の変更または追加は、双方の書面による合意があった場合にのみ有効とする。
2. 本契約に定めのない事項については、日本の関連法令および一般的な商慣習に従うものとする。
3. 本契約に関する紛争については、委託者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【委託者】
名称:
住所:
代表者名:
署名:
【受託者】
名称:
住所:
代表者名:
署名:
以上、双方の合意を証するため本契約書を2通作成し、各自1通を保有する。
今回の業務委託契約書のテンプレートは、実務で頻繁に使用される標準的な内容を網羅しており、非常に使いやすい印象を受けました。条項ごとに目的や条件が明確に分かれているため、契約の骨子を理解しやすくなっています。
特に、報酬の支払条件や秘密保持、権利帰属に関して具体的に記載されている点は、トラブル防止に効果的です。納期や契約解除の条項も慎重に設定されており、双方の責任範囲を明確化していることが評価できます。
ただし、各項目の具体的な内容は、実際の業務内容や合意状況に合わせて詳細を詰める必要があります。例えば、業務内容や納期、報酬額などの具体的な数字や期間は必ず記入し、曖昧さを排除することが重要です。
全体として本契約書は、法的な基盤をしっかり築きつつもシンプルで読みやすいため、契約当事者双方にとって理解しやすい設計となっています。実務導入の第一歩として最適なフォーマットだと言えるでしょう。
プロンプト5:秘密保持契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは秘密保持契約書作成専門の弁護士AIです。以下の要件を基に、日本法に準拠した秘密保持契約書(NDA)を作成してください。
#制約条件
・契約の主体(開示者、受領者)、秘密情報の定義、使用目的、保持義務、例外規定、契約期間、違反時の対応を盛り込むこと
・専門用語は正確に用い、文章は法律文書として正式かつ簡潔に記すこと
・条文形式で出力し、条番号・条名も付けること
・日本の商慣行および関連する法律(不正競争防止法など)に準じた内容とすること
・具体的な契約書のドラフトがほしい場合は、要件を明示して指示を受ける形式に対応可能と記載すること
#入力情報(例)
開示者:株式会社A
受領者:株式会社B
秘密情報の範囲:技術情報、営業情報全般
契約期間:2年
使用目的:共同事業に関連する業務遂行のため
#出力内容
・上記の要件を踏まえた秘密保持契約書全文(条文形式)を書き出す
秘密保持契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:秘密保持契約書作成に特化した弁護士AIとしての役割が明確に記載されているか
✅「#制約条件」の遵守確認:契約主体、秘密情報の定義、使用目的、保持義務、例外規定、契約期間、違反時の対応が網羅されているか
✅条文形式と法律準拠の確認:条番号・条名付きの条文形式かつ日本法(不正競争防止法含む)に準拠した正式かつ簡潔な法律文書になっているか
このプロンプトは日本法に準拠した秘密保持契約書(NDA)を自動で作成するためのものです。
契約書のドラフトを迅速に作成したい法律実務者やビジネス担当者に最適です。
特徴は、契約の主要要素を網羅し、条文形式で正式かつ簡潔に記述できる点にあります。
また、不正競争防止法など関連法令への準拠も考慮されているため、実務的に信頼性の高い文書が得られます。
このプロンプトを活用することで、契約書作成にかかる時間や労力を大幅に削減でき、場合によっては数時間分の作業工数が短縮可能です。
正確かつ効率的な秘密保持契約書の作成に役立つツールとして有効です。
入力例
#命令
あなたは秘密保持契約書作成専門の弁護士AIです。以下の要件を基に、日本法に準拠した秘密保持契約書(NDA)を作成してください。
#制約条件
・契約の主体(開示者、受領者)、秘密情報の定義、使用目的、保持義務、例外規定、契約期間、違反時の対応を盛り込むこと
・専門用語は正確に用い、文章は法律文書として正式かつ簡潔に記すこと
・条文形式で出力し、条番号・条名も付けること
・日本の商慣行および関連する法律(不正競争防止法など)に準じた内容とすること
・具体的な契約書のドラフトがほしい場合は、要件を明示して指示を受ける形式に対応可能と記載すること
#入力情報(例)
開示者:株式会社A
受領者:株式会社B
秘密情報の範囲:技術情報、営業情報全般
契約期間:2年
使用目的:共同事業に関連する業務遂行のため
#出力内容
・上記の要件を踏まえた秘密保持契約書全文(条文形式)を書き出す 今回は、株式会社Aと株式会社Bの間で締結する秘密保持契約書(NDA)のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約の主体として「開示者」を株式会社A、「受領者」を株式会社B
- 秘密情報の範囲を「技術情報及び営業情報全般」
- 使用目的を「共同事業に関連する業務遂行のため」
- 契約期間を「2年間」
といった具体的な要件を入力しました。
このように詳細な情報を与えることで、日本法に準拠し、不正競争防止法などの関連法令にも適合した秘密保持契約書を条文形式で正確に生成できます。
また、適宜改行を入れることで、契約書全体の視認性が向上し、確認や修正がしやすくなる点も特徴です。
以上の使い方により、開示者・受領者間の秘密情報の保護を法的に強固にし、契約違反時の対応も明確に定めた契約書ドラフトがスムーズに作成可能となります。
実行結果(GPT-4o)
秘密保持契約書
株式会社A(以下「開示者」という。)と株式会社B(以下「受領者」という。)は、以下の通り秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(定義)
本契約において「秘密情報」とは、開示者が受領者に対して口頭、書面、電子データその他如何なる方法により開示した技術情報および営業情報全般をいい、これには開示時に秘密である旨が明示された情報を含むものとする。
第2条(秘密情報の使用目的)
受領者は、秘密情報を開示者との共同事業に関連する業務遂行の目的のみに使用し、その他の目的で使用してはならない。
第3条(秘密保持義務)
受領者は、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならず、善良な管理者の注意をもってこれを厳重に管理しなければならない。
第4条(秘密情報の除外)
受領者の秘密保持義務は、以下の情報については適用しない。
(1) 開示時に既に公知であった情報
(2) 開示後、受領者の責によらず公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず合法的に入手した情報
(4) 開示者から書面により開示義務が解除された情報
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から2年間とし、期間満了後も第3条の秘密保持義務は本契約終了後5年間存続するものとする。
第6条(違反時の対応)
受領者が本契約に違反した場合、開示者は損害賠償を請求することができるほか、差止請求その他必要な法的措置をとることができる。
第7条(準拠法および管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約締結の証として、両当事者は各自記名押印の上、2通を作成し、各自1通を保有する。
20XX年XX月XX日
開示者
株式会社A
代表取締役 ________
受領者
株式会社B
代表取締役 ________
---
※具体的な契約書のドラフト作成につきましては、より詳細な要件をご指示いただければ対応可能です。この秘密保持契約書のドラフトは、基本的かつ重要な条項を網羅しており、非常に実用的な内容となっています。
特に、第1条の定義部分において「秘密情報」の範囲を明確にし、口頭や電子データも含めている点は、情報の多様な開示方法に対応しているため評価できます。
また、第3条の秘密保持義務と第4条の除外事項が明確に分けられていることで、受領者の責任範囲が明瞭になっており、トラブル防止に役立つでしょう。
契約期間と秘密保持義務の存続期間を分けている第5条も、契約満了後の情報保護を考慮した適切な設計です。
一方で、第6条の違反時の対応では損害賠償請求や差止請求が明記されているものの、具体的な違反の例示や解除条件についてやや詳細が不足しているため、用途によっては追加検討が望ましいでしょう。
最後に、第7条の準拠法と管轄裁判所の明示は、紛争解決方法を予め定めることで安心感を与えます。
全体として、契約書の骨子がしっかりしており、実務での利用に耐える内容です。必要に応じて特有の事情を反映するためのカスタマイズがしやすいテンプレートと評価できます。
ChatGPTで雇用契約書を作成するプロンプト5選のまとめ
ChatGPTを活用して雇用契約書を作成する際には、適切なプロンプト選びが重要です。
これにより、法律的に正確かつ分かりやすい契約書を効率的に生成できます。
たとえば、「雇用条件の明示」「秘密保持条項の追加」「試用期間の設定」など、目的別に5つの効果的なプロンプトを用意しました。
これらを活用することで、複雑な契約内容も漏れなく反映でき、作成時間も大幅に短縮可能です。
さらに、ChatGPTは入力内容に応じて柔軟に対応するため、企業ごとのニーズに合わせたカスタマイズもスムーズに行えます。
AIが自動で適切な表現や条文案を提示するため、法務知識が浅い担当者でも安心して利用できる点も魅力です。
まずは5選のプロンプトを試しつつ、自社に合った契約書作成を経験してみましょう。
この方法で雇用契約書の品質と業務効率の両方を向上させることが期待できます。