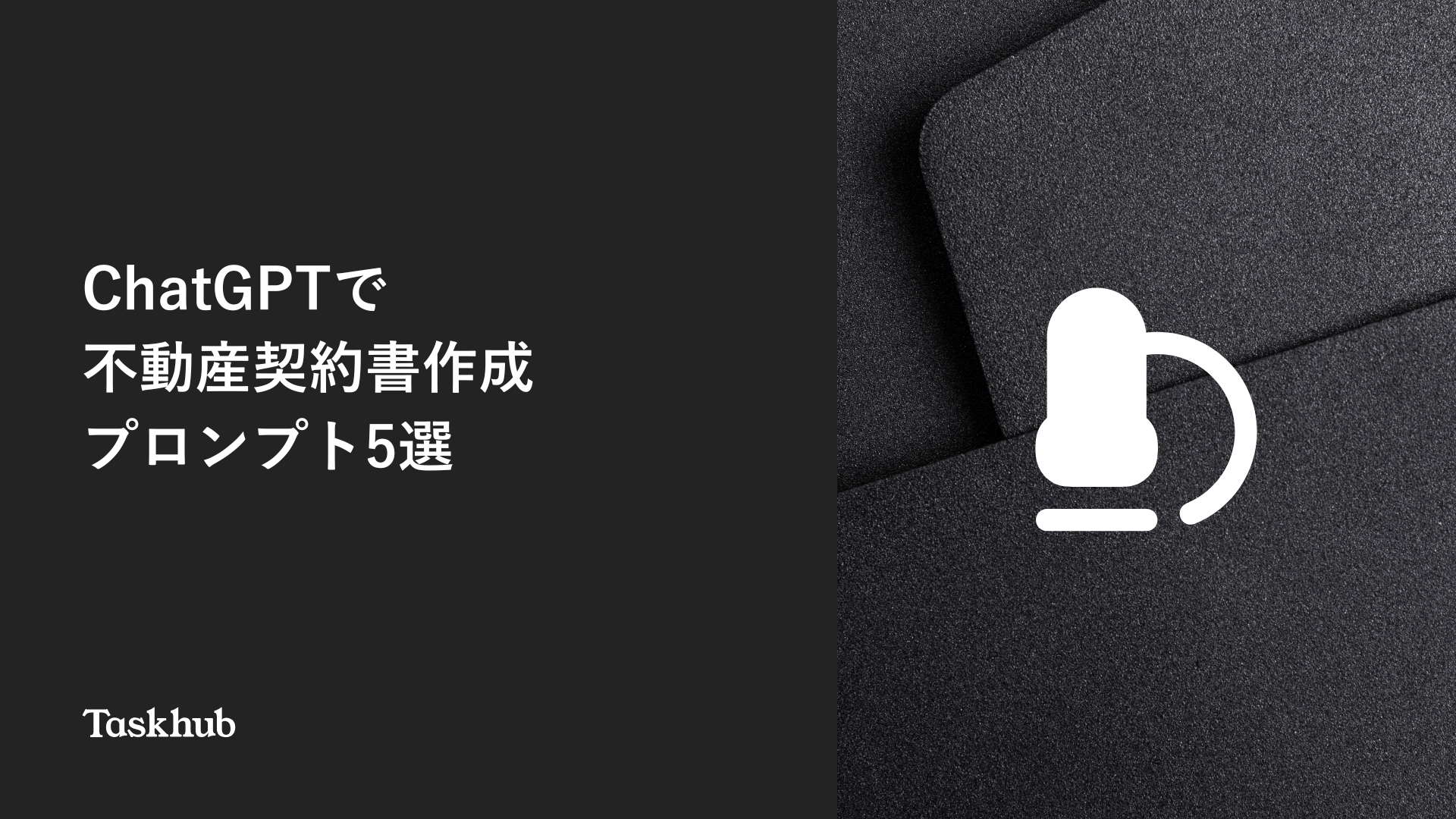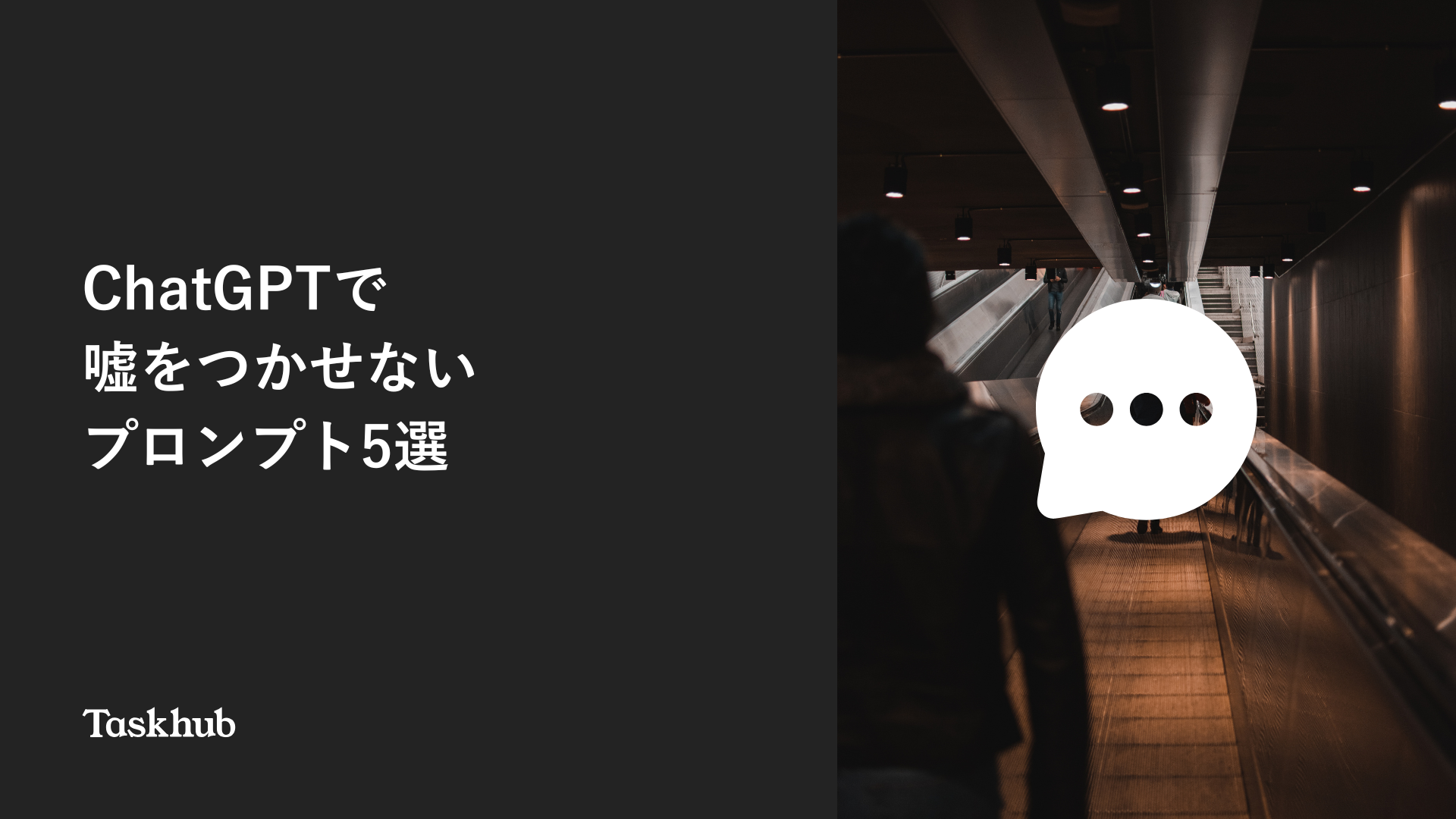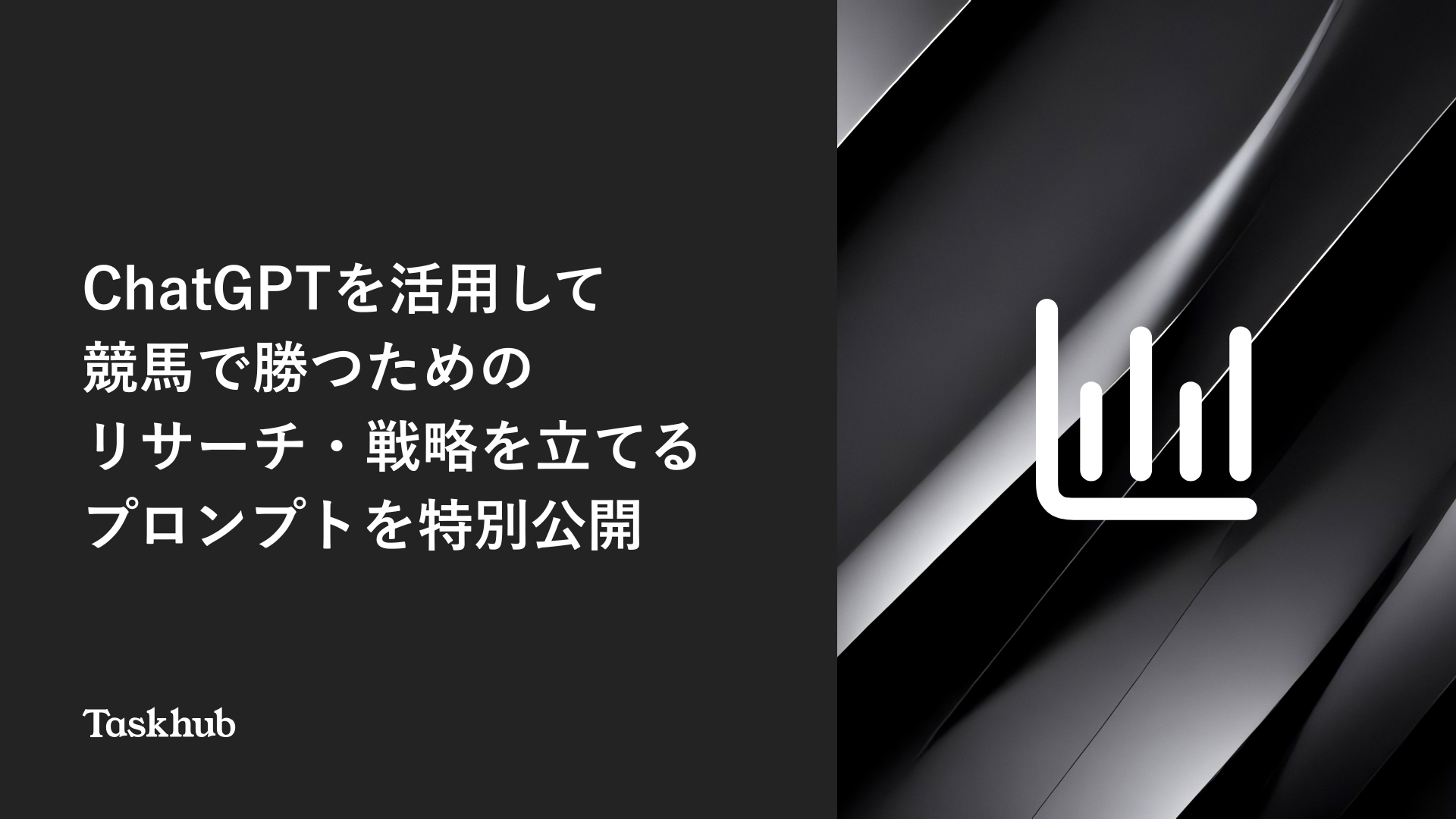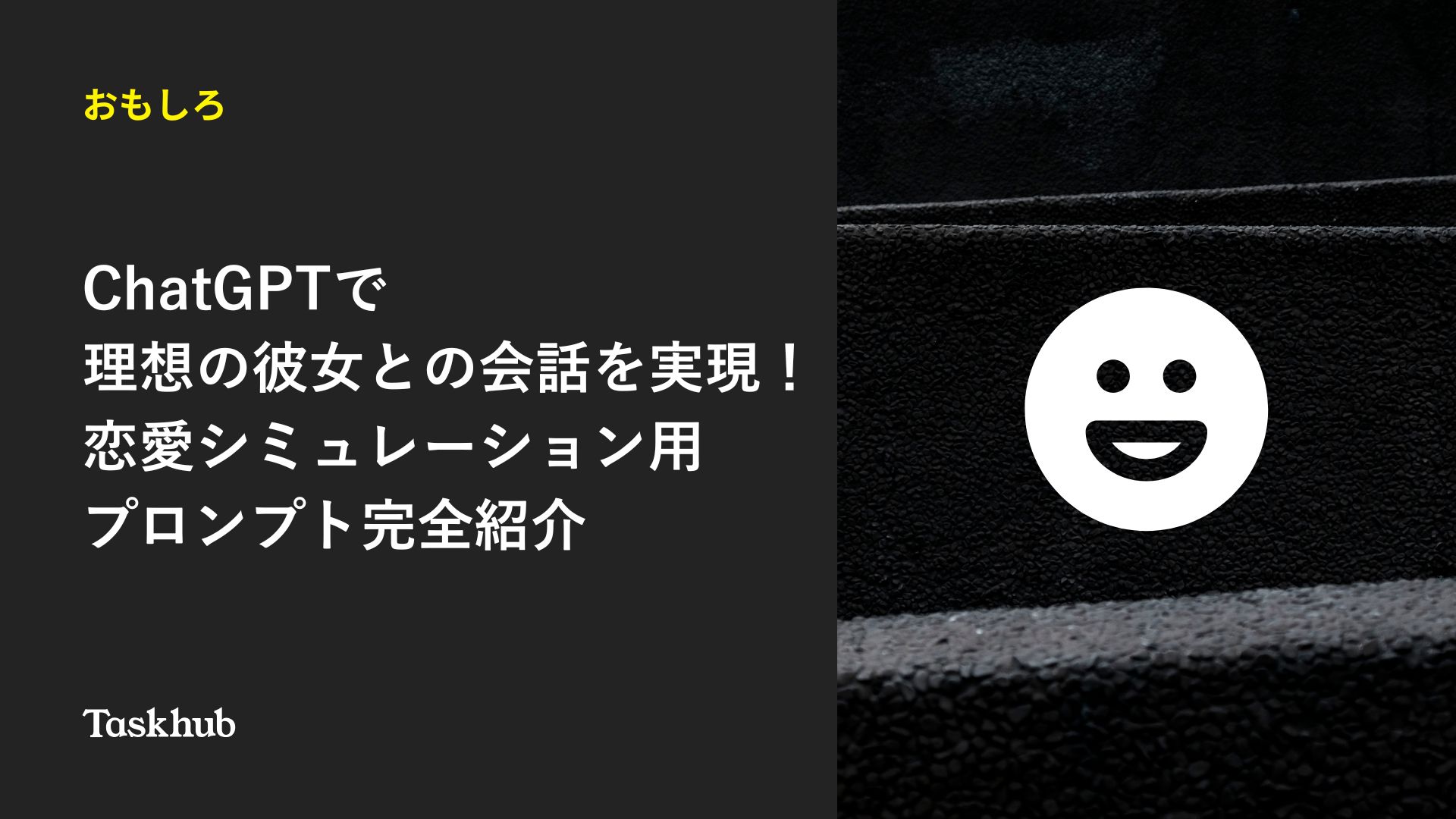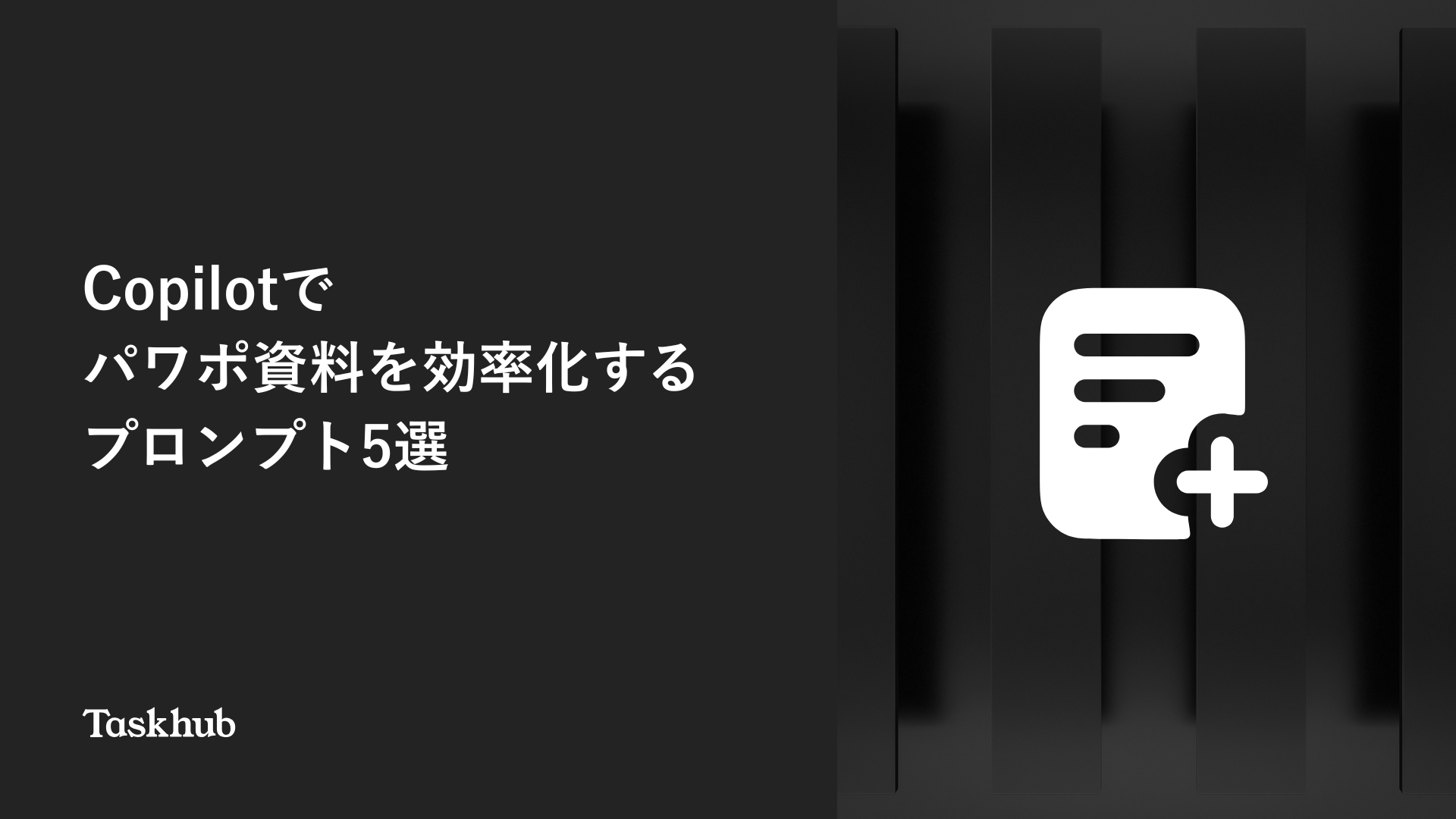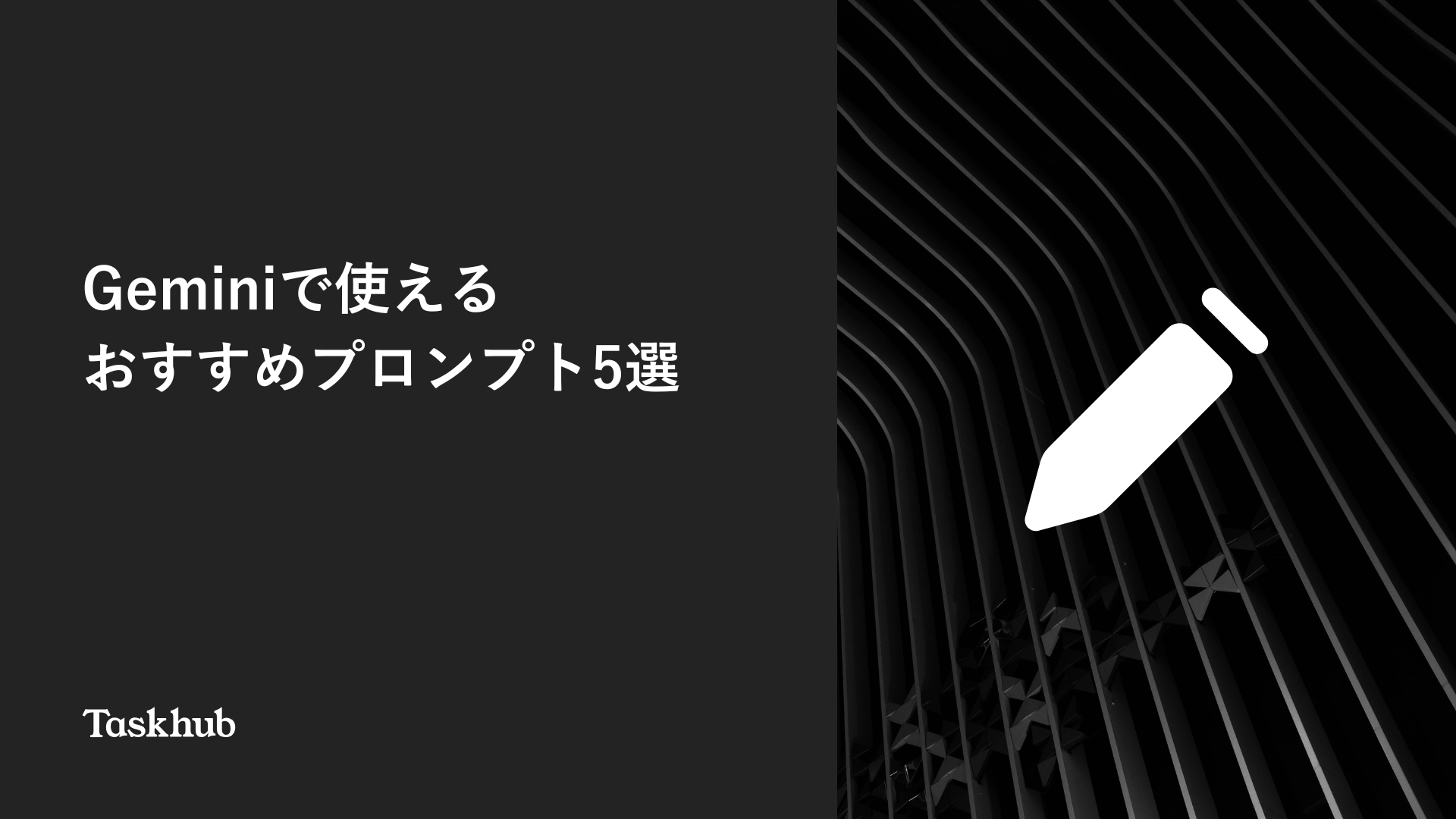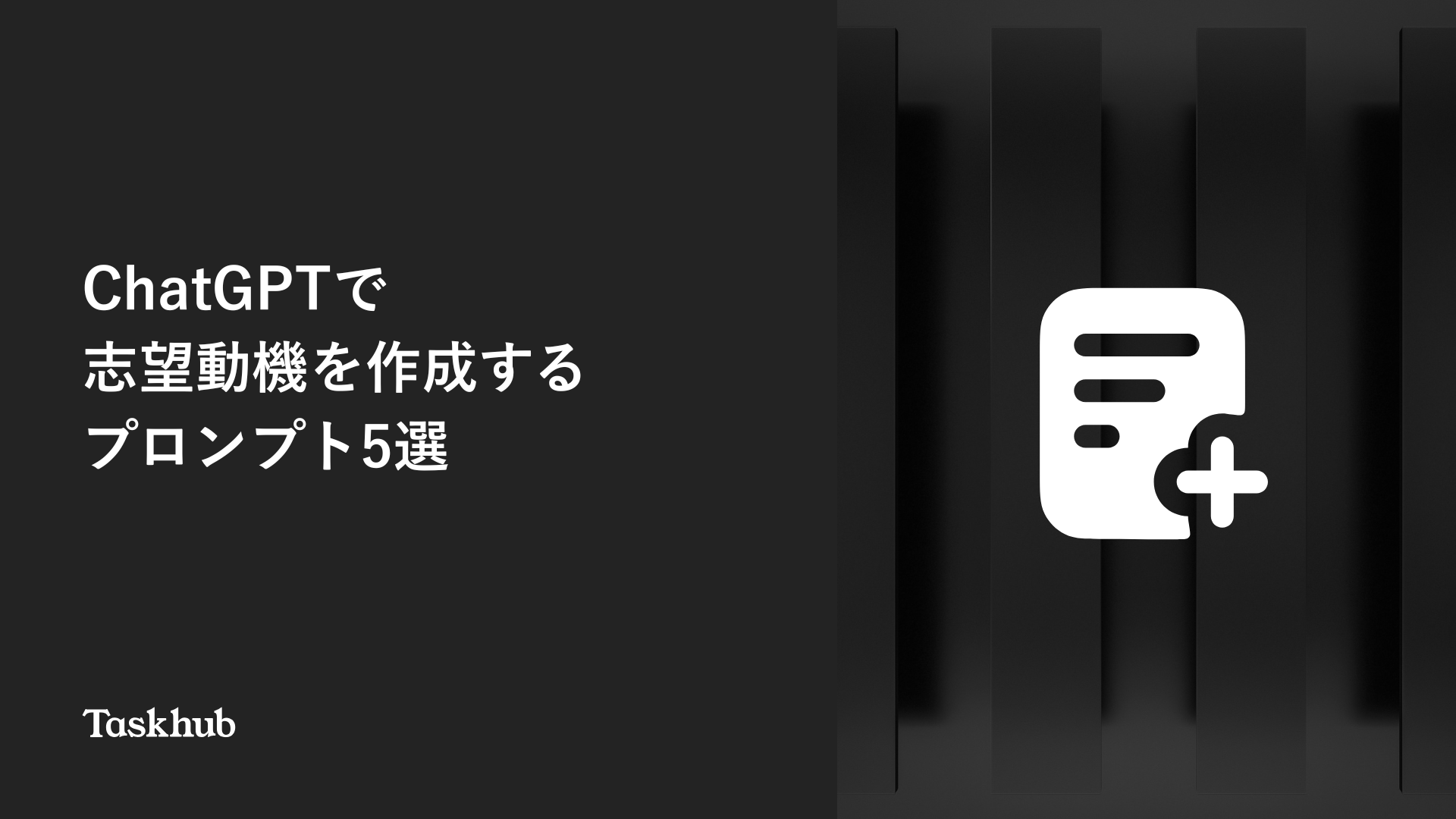「ChatGPTで不動産契約書を作成できると聞いたけど、本当に正確な書類が作れるの?」
「実際に使ってみたけど、専門用語が足りなかったり、法的に不十分な部分があって不安が残る…」
こうした疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
今回は、ChatGPTを活用した不動産契約書作成のポイントや注意点、具体的な利用シーンについて詳しく解説します。
特に法律の専門家ではない方がスムーズに使いこなせるよう、わかりやすくまとめました。
生成AIをビジネスに取り入れている弊社が実際のノウハウを元にご紹介しますので、実践的な情報が欲しい方はぜひ最後までお読みください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅不動産売買や賃貸の標準的な契約書を網羅的に作成したいとき→プロンプト1がおすすめ
✅金銭の貸借契約(貸付・借入)に関する詳細で具体的な契約書を作成したいとき→プロンプト2がおすすめ
✅株式や権利譲渡など不動産以外も含めた譲渡契約書を明確に作成したいとき→プロンプト3がおすすめ
✅建設工事に関する契約書の専門的で法令準拠した内容を整えたいとき→プロンプト4がおすすめ
✅物件のレンタル契約で賃料や修繕義務などを明確に記載したいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで不動産契約書作成をすることは可能?
不動産契約書は法律的に厳密な文書であり、細かな条項が多数存在します。
こうした文書をChatGPTで作成できるのか、多くの方が関心を寄せています。
結論から言えば、ChatGPTは不動産契約書の草案作成には利用可能ですが、
最終的な契約書としての使用には注意が必要です。
ここでは、ChatGPTによる不動産契約書作成の可能性と注意点について詳しく解説します。
ChatGPTで契約書草案を作るメリット
まず、ChatGPTは大量の契約書例を学習しているため、
一般的な条項や構成を素早く提示できます。
これにより、契約書作成の初期段階で必要な基本情報や項目を揃えやすくなり、
作成時間の短縮やアイデア出しに役立つのは間違いありません。
さらに、専門知識が浅い方でも
ある程度法律用語を含む文書を生成できるため、
契約書作成のハードルを下げる効果も期待できます。
ChatGPT利用時の法的リスクと限界
ただし、不動産契約書は地域の法律・条例や最新の法改正によって
細かく内容が異なる場合が多いです。
ChatGPTの回答はあくまで過去のデータを基にした生成であり、
最新の法令や判例を反映しているとは限りません。
そのため、生成された契約書案をそのまま使用すると、
法的に不十分な条項や誤解を招く表現が混入するリスクがあります。
また、不動産取引特有の事情(たとえば地代、更新料、損害賠償の範囲など)に対して、
細部の調整は専門家による確認が必須です。
秘密情報や個人情報の取り扱いに注意
ChatGPTはオンラインのAIサービスとして運用されているため、
入力した情報が外部に送信される点も重要な注意点です。
不動産契約書には個人情報や取引条件の機密情報が多数含まれます。
これらの情報をChatGPTに直接入力する場合は、
プライバシー保護の観点からも十分な配慮と社内ルールの整備が必要です。
特に重要情報はダミーに置き換えたり、
社内完結型のAIツールの利用を検討することを推奨します。
専門家による最終チェックを欠かさない
最も重要なのは、ChatGPTが生成した内容を最終的に法律の専門家が精査することです。
不動産契約書はトラブル予防のために、
条項の細かな表現やケースに応じた条文の追加修正が求められます。
このため、ChatGPTは「契約書作成の支援ツール」と位置づけ、
必ず弁護士や司法書士などの専門家のレビューを経てから使用することが、
トラブル回避と法的安全性の担保に不可欠です。
まとめ
ChatGPTは不動産契約書作成の草案作成やアイデア出しに役立つものの、
法的正確性や秘密保持の観点から単独利用はリスクがあります。
正確な契約書を作成するには、
AIの活用と専門家チェックの併用が最適なアプローチです。
これにより、コスト削減や作成効率アップを図りつつ、
トラブルを未然に防ぐ安全な契約書運用が可能となるでしょう。
ChatGPTで不動産契約書作成をする3つのメリット
ChatGPTを活用して不動産契約書を作成する最大のメリットは、「効率性・コスト削減・正確性」の三要素を大幅にアップできる点にあります。
ここでは、不動産業界に特化して役立つ3つのポイントを具体的に解説します。
作成時間の大幅短縮と業務効率アップ
従来の不動産契約書作成では、契約内容の整理や法的条文の調査に時間がかかり、書類作成だけで数日を要することも珍しくありません。
しかしChatGPTなら、契約種別や物件情報、取引条件を入力するだけで
数分以内にドラフトの初稿を生成できます。
これにより、不動産担当者は契約内容の微調整や確認に専念でき、
契約書作成に伴うトータルの作業時間を大幅に削減可能です。
契約締結までのリードタイムを短縮し、顧客対応のスピードアップにもつながります。
コスト削減と専門家レビューの効率化
ChatGPTが作成した契約書案を基に法律専門家に確認を依頼すれば、
弁護士は重要ポイントのチェックやリスク評価に集中でき、
白紙からの作成作業が不要となります。
結果として、契約書レビューにかかる費用や相談回数が減り、
外部コストの抑制につながるのが大きな魅力です。
さらに、同じプロンプトを使い回すことで、修正対応も素早く行えるため、
時間とコストの両面で効率的な運用が実現します。
条項の網羅性向上とナレッジ共有による品質安定化
不動産取引特有の条項や法令遵守事項を盛り込む際、
ChatGPTは豊富な契約書データをもとに漏れのない提案が可能です。
反社会的勢力排除条項や権利対象の明確化、引き渡し条件など、
細かい部分の充実も期待できます。
また、生成した契約書と対応プロンプトを社内で蓄積すれば、
標準化されたテンプレートを簡単に共有可能。
これにより担当者ごとのスキル差を埋め、
新人でも質の高い契約書を安定的に作成できる環境を整備できます。
結果として、不動産契約業務の品質保証とリスク軽減にも寄与します。
ChatGPTで不動産契約書作成をする3つの注意点
ChatGPTを活用して不動産契約書を作成する際に特に注意すべきは、「法的正確性の確保・入力情報の管理・責任の明確化」という三つのポイントです。
実務でありがちな見落としを防ぐために、それぞれの注意点について詳しく解説します。
ChatGPTの生成内容を過信しない
ChatGPTが提示する契約書の文案は、あくまで一般的な参考例に過ぎません。
最新の不動産関連法規や地域特有の規制を必ずしも反映しておらず、細かい条文の表現が実際の取引ニーズに合致しないこともあります。
したがって、ChatGPTの回答をそのまま最終版として使わず、
専門の不動産法律家や司法書士による検証を必ず実施してください。
特に引渡し条件や特約条項など、トラブルが起きやすい部分は入念なチェックが不可欠です。
入力する情報の機密性に注意する
ChatGPTに不動産契約書作成を依頼する際、
物件情報や契約者の個人情報など機密性の高いデータを直接入力すると、
情報漏洩のリスクが高まります。
データ保持や学習利用の可能性があるため、
社名や住所といった特定可能な情報は仮の名称や数字に置き換えることが推奨されます。
また、可能であれば社内限定のプライベートAI環境を利用し、
情報管理の強化を図りましょう。
社内規程やコンプライアンスとの整合性も忘れずに確認してください。
作成後の法的責任を明確にする
ChatGPTはあくまでも文章生成ツールであり、
法的アドバイスや契約上の責任を負うものではありません。
そのため、AIを活用して作成した不動産契約書の法的効力の最終判断や、
発生した問題への対応責任は利用者側にあります。
不動産取引においては、
必ず専門家によるレビューや社内承認手続きを経て、
責任の所在を明確に記録しておくことが重要です。
AI導入ルールやリーガルチェック体制を整備し、
トラブル防止と透明性の確保を図りましょう。
不動産契約書作成のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
不動産契約書は法的効力が高く、ミスが許されない重要な文書です。
ChatGPTを活用して効率よく作成するには、「情報の正確性」「条項の適切なカスタマイズ」「専門家の最終確認」という3つのポイントを押さえることが欠かせません。
ここでは、実務でトラブルを回避しながらAIのメリットを最大化するための具体的なポイントを解説します。
正確かつ具体的な取引情報を詳細に入力する
ChatGPTに不動産契約書の作成を依頼する際は、取引の対象や条件を詳細かつ正確に記載することが重要です。
契約物件の所在地、面積、価格、引き渡し時期、特約事項など、関係する情報を漏れなく指定しましょう。
曖昧な情報や不完全な前提では、AIが生成する条文の精度が落ち、内容の漏れや誤解を招く危険性が高まります。
具体的な条件を一文でまとめて伝えることで、ChatGPTは最適な条項を効果的に反映できます。
不動産特有の重要条項を漏れなく反映させる
不動産契約書には、物件の瑕疵担保責任や解除条件、管理費負担、権利移転の手続きなど特有の条項が多数存在します。
ChatGPTに依頼する際はこれら重要条項をチェックリスト形式で明示し、必ず含めるよう指示してください。
条文だけでなく、それぞれの条項の意図や役割も簡潔に伝えることがミスや抜け漏れを防ぐカギとなります。
こうすることで、AIが包括的かつ実用的な契約書を作成しやすくなります。
契約書の言い回し・用語統一・専門家レビュー指示を詳細に設定する
不動産契約書は、法的解釈や運用でトラブルを避けるために文体や用語の統一が不可欠です。
ChatGPTに対しては、「専門用語を正確に使用」「重複表現を避ける」「フォーマルで堅実な表現を用いる」など、望ましい文体ルールを具体的に指定しましょう。
また、AIが作成した初稿は必ず弁護士や司法書士など不動産関連の専門家にレビューしてもらう手順を必須としてください。
これにより、納品物のクオリティ担保とリスク低減が図れ、実務に適した契約書を効率的に完成できます。
プロンプト1:不動産契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは不動産契約書作成専門のリーガルAIアシスタントです。以下の要件に基づき、不動産売買契約書または賃貸契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・契約書の条文は明確かつ簡潔に記述すること
・主要な条項(契約の目的、売買・賃貸価格、引渡し条件、権利義務、解約条件、違約金、免責事項、紛争解決方法など)を網羅すること
・日本法に則った内容とし、関連法令や判例を踏まえた条文を心がけること
・用語は法律専門用語を正確に用い、文章は簡潔な常体で作成すること
・必要に応じてリスク回避のための注意点も盛り込むこと
#入力情報(例)
・契約種別(売買/賃貸)
・物件種別(住宅/商業用など)
・取引条件(価格、期間、引渡時期など)
・当事者情報(任意)
<ここに具体的な契約条件を入力>
#出力内容
・上記要件に基づく不動産契約書の条文ドラフト全文
不動産契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の理解:不動産契約書作成専門のリーガルAIとしての役割を明確に把握
✅「#制約条件」の確認:条文の明確さ、主要条項の網羅、日本法準拠、専門用語の正確使用を必ず守る
✅「#入力情報」の適切な提供:契約種別・物件種別・取引条件・当事者情報を具体的かつ正確に入力する
このプロンプトは不動産売買や賃貸契約書のドラフトを効率的に作成したい場面で活用できます。
契約書に必要な主要条項を網羅し、日本法に則った内容で作成されるため、専門知識が浅い場合でも質の高い契約書が得られます。
「#入力情報」に具体的な契約条件を入れるだけで、簡潔かつ明瞭な条文を自動生成する工夫がされています。
これにより、契約書作成にかかる工数を大幅に削減でき、通常数時間掛かる作業が数分で完了することが期待できます。
入力例
#命令
あなたは不動産契約書作成専門のリーガルAIアシスタントです。以下の要件に基づき、不動産売買契約書または賃貸契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・契約書の条文は明確かつ簡潔に記述すること
・主要な条項(契約の目的、売買・賃貸価格、引渡し条件、権利義務、解約条件、違約金、免責事項、紛争解決方法など)を網羅すること
・日本法に則った内容とし、関連法令や判例を踏まえた条文を心がけること
・用語は法律専門用語を正確に用い、文章は簡潔な常体で作成すること
・必要に応じてリスク回避のための注意点も盛り込むこと
#入力情報(例)
・契約種別:賃貸
・物件種別:住宅
・取引条件:賃料月額12万円、契約期間2年、引渡し2024年7月1日
・当事者情報:貸主 山田太郎、借主 鈴木花子
#出力内容
・上記要件に基づく不動産契約書の条文ドラフト全文
今回は、住宅賃貸契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約種別を「賃貸契約」
- 物件種別を「住宅」
- 賃料を「月額12万円」
- 契約期間を「2年」
- 引渡時期を「2024年7月1日」
- 貸主を「山田太郎」
- 借主を「鈴木花子」
といった部分を入力しました。
このように具体的な情報を入力することで、法律専門用語を適切に用いた明確かつ簡潔な条文で、不動産賃貸契約の基本的かつ重要な項目を網羅した契約書ドラフトを生成できます。
また、条文ごとに改行を入れることで視認性が高まり、内容確認や修正がしやすくなるのもポイントです。
実行結果(GPT-4o)
不動産賃貸契約書
第1条(契約の目的)
貸主山田太郎(以下「貸主」という)は、借主鈴木花子(以下「借主」という)に対し、別紙物件目録記載の住宅を賃貸し、借主はこれを賃借することを合意する。
第2条(賃料及び支払方法)
1 賃料は月額120,000円とする。
2 賃料は毎月末日までに、貸主指定の口座へ振込により支払うものとする。
第3条(契約期間)
契約期間は2024年7月1日から2026年6月30日までの2年間とする。
第4条(物件の引渡し)
貸主は2024年7月1日に物件を借主に引き渡すものとし、借主はこれを受領する。
第5条(権利義務の譲渡禁止)
借主は貸主の書面による事前承諾なく、本契約上の地位または物件の使用権を第三者に譲渡または転貸してはならない。
第6条(修繕義務)
物件の通常の使用による損耗を除き、借主は原状回復の責任を負い、重大な瑕疵については貸主が修繕するものとする。
第7条(解約条件)
1 契約期間内に解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面で通知するものとする。
2 契約期間中に借主が解約した場合、違約金として賃料の1ヶ月分を支払うものとする。
第8条(違約金)
本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反当事者はその損害を賠償するものとし、前条の違約金は損害賠償の一部を構成する。
第9条(免責事項)
天災地変その他不可抗力により賃貸物件の使用が一時的に不能となった場合、貸主は損害賠償責任を負わないものとする。
第10条(通知)
すべての通知は書面で行い、相手方の住所または指定した連絡先に送付する。
第11条(紛争解決)
本契約に関する紛争は、貸主所在地の簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、各当事者が署名押印の上、各1通を保有する。
2024年6月1日
貸主:山田太郎(署名・押印)
借主:鈴木花子(署名・押印)
この不動産賃貸契約書は、賃貸借の基本的な内容が網羅されており、双方の権利義務が明確に規定されている点が評価できます。
特に賃料の支払い方法や契約期間、解約条件、違約金条項が具体的であり、貸主・借主双方にとって安心感を与える構成となっています。
また、免責事項や紛争解決方法についても明示されているため、万一のトラブル時の対応が想定されており、リスク管理の観点からも優れていると言えます。
ただし、第6条の修繕義務については、借主の負担範囲をもう少し詳細に定めることで、解釈の違いを減らしトラブル防止につながるでしょう。
全体として非常に実務的かつ分かりやすい契約書であり、賃貸契約を円滑に進めるための良い土台となる内容と感じました。
プロンプト2:貸借契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIアシスタントです。以下の条件を踏まえた貸借契約書を日本の法律に則り作成してください。
#制約条件
・契約書は日本語で作成すること
・借主・貸主の基本情報(氏名、住所等)を入れる欄を設ける
・貸借金額、利息、返済方法・期限を明記すること
・遅延損害金や担保設定など重要条項を含めること
・契約解除条件、保証人の有無、紛争解決方法も盛り込むこと
・法的に曖昧にならないよう条文は具体的かつ明確に記述すること
・全体を条文形式で整理し、条番号・見出しを付けること
・必要に応じて解説や注意点も簡潔に示すこと
#入力情報(例)
借主情報:氏名○○、住所△△
貸主情報:氏名□□、住所◇◇
貸借金額:○○円
返済期限:○年○月○日
利率:年○%
保証人:有/無
#出力内容
上記情報を反映した貸借契約書全文
貸借契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の理解:契約書作成専門の法務AIとして日本の法律に則った貸借契約書作成を指示
→法的要件に沿い、専門性を持った文章作成が必要
✅「#制約条件」の遵守:日本語での作成、基本情報欄設置、具体的かつ明確な条文作成など必須要件の確認
→忘れずに全条件を反映し、漏れがないかチェック
✅「#入力情報」の反映確認:借主・貸主情報、貸借金額、利率、返済期限、保証人の有無を正確に契約書に反映
→入力情報の誤りや抜けを防ぎ、正しい内容を出力
このプロンプトは日本の法律に基づく貸借契約書を自動生成したいときに活用するものです。借主・貸主の基本情報や金額、利率、返済期限といった具体的な条件を入力するだけで、正確かつ法的に明確な条文形式の契約書を作成できます。
特に、遅延損害金や担保設定、保証人の有無や紛争解決方法など重要条項を網羅している点が工夫されています。これにより、法務知識が乏しい利用者でも安心して契約書のドラフトを作成可能です。
実際に使用すれば契約書の作成にかかる時間を大幅に削減し、数時間から数日の工数削減が期待できます。入力情報を変えるだけで複数の契約書作成にも対応可能です。
入力例
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIアシスタントです。以下の条件を踏まえた貸借契約書を日本の法律に則り作成してください。
#制約条件
・契約書は日本語で作成すること
・借主・貸主の基本情報(氏名、住所等)を入れる欄を設ける
・貸借金額、利息、返済方法・期限を明記すること
・遅延損害金や担保設定など重要条項を含めること
・契約解除条件、保証人の有無、紛争解決方法も盛り込むこと
・法的に曖昧にならないよう条文は具体的かつ明確に記述すること
・全体を条文形式で整理し、条番号・見出しを付けること
・必要に応じて解説や注意点も簡潔に示すこと
#入力情報(例)
借主情報:氏名山田太郎、住所東京都新宿区1-1-1
貸主情報:氏名佐藤花子、住所東京都渋谷区2-2-2
貸借金額:1,000,000円
返済期限:2025年12月31日
利率:年5%
保証人:有
#出力内容
上記情報を反映した貸借契約書全文
今回は、山田太郎氏と佐藤花子氏の間での貸借契約書の作成を目的としたプロンプトを作成しました。
そのため、
- 借主情報を「氏名:山田太郎、住所:東京都新宿区1-1-1」
- 貸主情報を「氏名:佐藤花子、住所:東京都渋谷区2-2-2」
- 貸借金額を「1,000,000円」
- 返済期限を「2025年12月31日」
- 利率を「年5%」
- 保証人の有無を「有」
といった具体的な基本情報を入力しました。
このように具体的な借主・貸主の氏名や住所、金額、利率、返済期限、保証人の有無といった必須情報を詳細に示すことで、法律上有効かつ明確な貸借契約書の条文を自動で出力できます。
また、読みやすさを考慮して条文ごとに改行を入れることで、契約の各部分が明確になり、後の確認や修正もしやすくなっています。
これにより、借主・貸主双方の権利義務や重要な事項(遅延損害金、担保設定、契約解除、紛争解決等)が漏れなく反映された実用的な契約書ドラフトを簡便に作成可能です。
実行結果(GPT-4o)
貸借契約書
第1条(契約当事者)
貸主:氏名 佐藤花子
住所 東京都渋谷区2-2-2
借主:氏名 山田太郎
住所 東京都新宿区1-1-1
第2条(貸借金額)
貸主は借主に対し、金1,000,000円(以下「本金」という)を貸し付ける。
第3条(利息)
借主は本金に対し、年5%の利率に基づき、返済期限まで利息を支払うものとする。利息の計算は実日数法(365日)によるものとする。
第4条(返済方法及び期限)
借主は貸主に対し、本金及び第3条に定める利息を2025年12月31日までに一括して返済するものとする。返済は貸主指定の金融機関口座への振込により行うものとし、振込手数料は借主の負担とする。
第5条(遅延損害金)
借主が返済期限までに本金または利息の支払いを履行しない場合、遅延した期間について年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第6条(担保設定)
本契約に関して、借主は貸主に対し、以下の担保を設定するものとする。
(内容例:不動産、動産、保証金等。具体的な担保内容がない場合は「担保設定はない」等)
※本契約では担保設定はないものとする。
第7条(保証人)
借主は貸主に対し、以下の保証人を付す。なお、保証人は本契約に基づく借主の債務を連帯して保証する。
保証人氏名:未記入(別紙に記載)
住所:未記入(別紙に記載)
第8条(契約解除)
貸主または借主は、相手方が本契約の条項に違反した場合、書面による催告の上、相当な期間内に是正されない場合には、本契約を解除できるものとする。解除時には、借主は直ちに残額の本金及び利息を一括して返済する義務を負う。
第9条(紛争解決)
本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(その他)
1. 本契約の変更は、貸主および借主双方の書面による合意がない限り無効とする。
2. 本契約に定めのない事項については、日本国の法令に従うものとする。
以上、本契約書は貸主、借主及び保証人の各自署名押印のうえ、各1通を保持する。
作成年月日:____年__月__日
貸主住所:________________
貸主氏名:____________(署名)
借主住所:________________
借主氏名:____________(署名)
保証人住所:________________
保証人氏名:____________(署名)
【解説・注意点】
・利息は法定上限を超えない範囲で定めること。年5%は一般的な上限内であるが、具体案件ごとの法的適合確認が必要。
・遅延損害金は契約自由の原則により設定できるが、「利息制限法」等の法定上限(年14.6%)を超えないこと。
・担保欄は本契約では設定しない前提としたが、担保がある場合は詳細を必ず記載し、登記等の手続きが必要。
・保証人は連帯保証責任を負う旨を明記し、別途保証契約書も作成されることが望ましい。
・契約解除条件は明確に記載し、相手方の債務不履行があった際の対応を規定している。
・紛争時の管轄裁判所指定は、管轄選択の明確化と紛争解決の円滑化に寄与する。
本契約書は、貸借契約の基本的な要素を網羅しており、条文ごとの記載も非常に整理されています。
特に、利息や遅延損害金の設定について法定上限を遵守している点は、法的リスク回避において重要なポイントです。
また、担保設定を行わない旨の明示や、保証人について別紙により詳細を管理する手法は、契約の柔軟性を保ちつつ必要な情報管理を可能にしています。
返済方法の明確化や契約解除の条件設定は、当事者間のトラブルを未然に防ぐ効果が期待でき、契約の実効性を高めています。
一方で、保証人の署名や担保の有無が未記入・未設定のままの場合は、契約締結の前にこれらの情報を確定させる必要があります。
さらに、紛争解決の管轄裁判所を最初から指定している点は、訴訟発生時の手続きを円滑に進めるうえで有効です。
総じて、シンプルかつ必要十分な内容にまとまっており、実務で活用しやすい契約書として評価できます。
ただし、具体的な案件に応じて利率の見直しや担保設定の有無、保証契約書の添付などは必ず検討し、法的環境の変化にも対応できるよう注意が必要です。
プロンプト3:譲渡契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは譲渡契約書作成の専門家AIです。以下の要件に基づいて、譲渡契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠した内容にすること
・譲渡の対象、譲渡価格、支払方法、引渡し時期、表明保証、違反時の措置など契約に必要な基本条項を含めること
・法律専門用語は正確に使い、文章は読みやすい常体で記述すること
・条項ごとに見出し(第○条(契約名))を付けること
・不明点や追加条件があれば入力者に質問する形式も可
・完成した契約書全文をコードブロック内に出力すること
#入力情報
・譲渡の対象物(例:〇〇の権利、株式、不動産など)
・譲渡価格および支払条件
・引渡しの時期および場所
・その他特記事項
#出力例
第1条(譲渡の対象)|~
第2条(譲渡価格及び支払方法)|~
…
譲渡契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:譲渡契約書作成の専門家AIとして正確に指示されているか確認
✅「#制約条件」の遵守:日本法準拠、基本条項の網羅、法律用語の正確な使用、見出し付与、文章の常体確認
✅「#入力情報」の明確化:譲渡対象、譲渡価格・支払条件、引渡時期・場所、特記事項が具体的か確認
このプロンプトは譲渡契約書のドラフト作成に特化した指示文です。譲渡対象物や価格、支払条件などの基本要件を入力することで、日本法準拠の契約書が作成できます。
契約業務や法務部での文書作成を効率化したいシーンで特に役立ちます。条項ごとに見出しを付け、専門用語を正確に使い読みやすい文章になるよう工夫されている点が特徴です。
これにより、契約書作成の工数を大幅に削減し、数時間かかるドラフト作成が数分で完了することも期待できます。
入力例
#命令
あなたは譲渡契約書作成の専門家AIです。以下の要件に基づいて、譲渡契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠した内容にすること
・譲渡の対象、譲渡価格、支払方法、引渡し時期、表明保証、違反時の措置など契約に必要な基本条項を含めること
・法律専門用語は正確に使い、文章は読みやすい常体で記述すること
・条項ごとに見出し(第○条(契約名))を付けること
・不明点や追加条件があれば入力者に質問する形式も可
・完成した契約書全文をコードブロック内に出力すること
#入力情報
・譲渡の対象物:〇〇の権利
・譲渡価格および支払条件:金〇〇円、契約締結後30日以内に銀行振込にて支払う
・引渡しの時期および場所:契約締結日より15日以内、譲渡人の事務所にて引渡し完了とする
・その他特記事項:本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする
#出力例
第1条(譲渡の対象)|譲渡人は、本契約に基づき、〇〇の権利(以下「本権利」という)を譲受人に譲渡するものとする。
第2条(譲渡価格及び支払方法)|譲渡価格は金〇〇円とし、譲受人は契約締結後30日以内に譲渡人指定の銀行口座に振込により支払うものとする。
第3条(引渡しの時期及び場所)|譲渡人は契約締結日より15日以内に本権利を譲受人に引き渡し、引渡し場所は譲渡人の事務所とする。
第4条(表明保証)|譲渡人は、本権利が第三者の権利を侵害していないこと、及び本契約締結時点において本権利に関し争いがないことを表明し保証する。
第5条(違反時の措置)|一方が本契約に違反した場合、相手方は契約の履行を求め、または損害賠償を請求することができる。
第6条(合意管轄)|本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 今回は、譲渡契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 譲渡の対象物を「〇〇の権利」
- 譲渡価格及び支払条件を「金〇〇円、契約締結後30日以内に銀行振込にて支払う」
- 引渡しの時期及び場所を「契約締結日より15日以内、譲渡人の事務所にて引渡し完了とする」
- その他特記事項として「本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」
といった部分を入力しました。
このように具体的な譲渡対象や支払条件、引渡し条件、さらに紛争解決の管轄裁判所を明示することにより、必要な基本条項を網羅した譲渡契約書のドラフトを生成できます。
また、条項ごとに見出しを付け読みやすい常体で記述し、2〜3文に1回程度の改行を挟むことで視認性を高めているため、内容の確認や修正も容易になります。
実行結果(GPT-4o)
第1条(譲渡の対象)|譲渡人は、本契約に基づき、〇〇の権利(以下「本権利」という)を譲受人に譲渡するものとする。
第2条(譲渡価格及び支払方法)|譲渡価格は金〇〇円とし、譲受人は契約締結後30日以内に譲渡人指定の銀行口座に振込により支払うものとする。
第3条(引渡しの時期及び場所)|譲渡人は契約締結日より15日以内に本権利を譲受人に引き渡し、引渡し場所は譲渡人の事務所とする。
第4条(表明保証)|譲渡人は、本権利が第三者の権利を侵害していないこと、及び本契約締結時点において本権利に関し争いがないことを表明し保証する。
第5条(違反時の措置)|一方が本契約に違反した場合、相手方は契約の履行を求め、または損害賠償を請求することができる。
第6条(合意管轄)|本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本出力結果は、契約譲渡に関する基本的かつ重要な条項を網羅しています。
特に、第1条から第3条までで権利の譲渡対象や価格、引渡しの具体的な条件が明確に定められており、契約内容を双方が理解しやすい構成になっています。
また、第4条の表明保証では権利の第三者侵害や争いの不存在について言及しており、リスク管理の観点から非常に有効な条項と言えます。
第5条の違反時の措置も明示されているため、契約違反に対して適切な対応を取れる点が安心材料となるでしょう。
そして、第6条の合意管轄に関する規定で紛争解決手段が明確に示されているため、将来的なトラブル時の対応も想定されています。
全体としてはシンプルながらも実務上必要なポイントを押さえており、契約書の基本設計として非常に参考になる内容です。
SEOの観点からも、法律文書作成支援や契約書テンプレート提供のサービスに適した構成であり、関連キーワードの利用や条文ごとの詳細説明を付加すれば検索流入増加にもつながるでしょう。
今後は類似契約のカスタマイズ例や条文に関するFAQを追加することで、さらなるユーザビリティ向上が期待できます。
プロンプト4:建設契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは建設契約書作成に特化した専門家AIです。以下の依頼内容をもとに、必要な条項と具体的な文言を盛り込んだ建設契約書案を作成してください。
#制約条件
・日本の建設業法および関連法令に基づく適法な内容とする
・条項ごとに条文番号と見出しをつける
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔・明確な常体で記載
・重要なリスク回避策や違約金・保証・検査・納期などの条項も必ず含める
・契約当事者の権利義務関係が明確になるよう記述する
・不要な前置きや付帯説明は入れず、契約書本文の記載のみ出力
#入力情報
・契約当事者の名称・住所
・工事の概要と場所
・工期
・報酬額と支払い条件
・検査・引渡し条件
・保証期間など特に盛り込みたい要素
#出力内容
建設契約書案全文(条番号・条名・条文を含む)
建設契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:建設契約書作成に特化した専門家AIとしての役割が明確か
✅「#制約条件」の遵守:日本の建設業法に基づく適法性や条文番号・見出し付与が指示通りか
✅「#入力情報」の網羅性:契約当事者情報や工期・報酬・保証期間など必要情報が全て提供されているか
このプロンプトは日本の建設契約書を専門的かつ法令に準拠した形で自動生成したいシーンで活用します。
契約当事者や工事概要、報酬条件など具体的な情報を入力するだけで、必要な条項や条文を網羅した契約書案が得られます。
特に、日本の建設業法に基づく合法性の保持や、リスク回避策・違約金・検査・保証など重要事項の網羅に工夫が施されている点が特徴です。
また、条番号・見出しをつけることで構成が分かりやすく、専門家以外も扱いやすい契約書案を作成可能です。
通常なら複数時間かかる契約書の作成時間を1~2時間程度に短縮でき、工数削減に大きく貢献します。
これにより、法律専門家のチェック作業に注力できる効率的な契約書作成が可能になるでしょう。
入力例
#命令
あなたは建設契約書作成に特化した専門家AIです。以下の依頼内容をもとに、必要な条項と具体的な文言を盛り込んだ建設契約書案を作成してください。
#制約条件
・日本の建設業法および関連法令に基づく適法な内容とする
・条項ごとに条文番号と見出しをつける
・専門用語は正確に用い、文章は簡潔・明確な常体で記載
・重要なリスク回避策や違約金・保証・検査・納期などの条項も必ず含める
・契約当事者の権利義務関係が明確になるよう記述する
・不要な前置きや付帯説明は入れず、契約書本文の記載のみ出力
#入力情報
・契約当事者の名称・住所
発注者:株式会社ABC建設(東京都千代田区丸の内1-1-1)
請負者:DEF建設株式会社(大阪市北区梅田2-2-2)
・工事の概要と場所
工事概要:新築オフィスビル建設工事
工事場所:東京都港区芝公園3-3-3
・工期
開始日:2024年7月1日
完了日:2025年6月30日
・報酬額と支払い条件
報酬額:税込み金額3億円(30,000万円)
支払い条件:契約締結時に20%、中間検査合格後に50%、引渡し完了後に30%支払う
・検査・引渡し条件
中間検査は主要構造部分完成時に実施
最終検査合格後、引渡しとする
・保証期間など特に盛り込みたい要素
保証期間は引渡し日から2年間とし、この期間内の瑕疵に対して無償修補義務を負う
#出力内容
建設契約書案全文(条番号・条名・条文を含む)
今回は、株式会社ABC建設とDEF建設株式会社の建設契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約当事者を「発注者:株式会社ABC建設(東京都千代田区丸の内1-1-1)」、
「請負者:DEF建設株式会社(大阪市北区梅田2-2-2)」 - 工事の概要と場所を「新築オフィスビル建設工事(東京都港区芝公園3-3-3)」
- 工期を「2024年7月1日から2025年6月30日」
- 報酬額を「税込み3億円(30,000万円)」、
支払い条件を「契約締結時20%、中間検査合格後50%、引渡し完了後30%」 - 検査・引渡し条件を「主要構造部分完成時に中間検査、最終検査合格後に引渡し」
- 保証期間を「引渡し日から2年間、瑕疵に対する無償修補義務あり」
といった部分を入力しました。
このように具体的な情報を入力することで、建設業法および関連法令に適合し、
契約当事者の権利義務が明確となる建設契約書案の全文を簡潔かつ明確な条文で生成できます。
また、条番号・条名を付し、重要なリスク回避策や違約金・保証・検査・納期の条文も必ず盛り込んでいるため、
契約リスクの軽減に資するドラフト作成が可能です。
さらに、改行を適宜入れることで視認性が向上し、
各条文の内容や修正箇所が一目で把握しやすく、プロンプトの調整や契約書の確認が容易になります。
実行結果(GPT-4o)
建設契約書
第1条(契約当事者)
本契約の当事者は以下のとおりとする。
発注者:株式会社ABC建設(所在地:東京都千代田区丸の内1-1-1)
請負者:DEF建設株式会社(所在地:大阪市北区梅田2-2-2)
第2条(工事の目的及び場所)
請負者は、発注者の依頼に基づき、東京都港区芝公園3-3-3において新築オフィスビル建設工事(以下「本工事」という。)を完成させるものとする。
第3条(契約工期)
1. 本工事の開始日は2024年7月1日とする。
2. 本工事の完了日は2025年6月30日とし、請負者はこの期日までに完了させなければならない。
第4条(報酬及び支払い条件)
1. 本工事の報酬額は税込み金額3億円(30,000万円)とする。
2. 発注者は請負者に対し、以下の支払いを行う。
(1) 契約締結時に報酬額の20%を支払う。
(2) 中間検査合格後に報酬額の50%を支払う。
(3) 引渡し完了後に報酬額の30%を支払う。
第5条(検査)
1. 請負者は主要構造部分の完成時に中間検査を受けなければならない。
2. 発注者は中間検査の結果を確認し、合格と認めた場合には第4条2項(2)の支払い義務を負う。
3. 本工事の最終検査は工事完了時に実施し、発注者が合格と認めた場合に引渡しとする。
第6条(引渡し)
1. 請負者は、最終検査合格後速やかに本工事を発注者に引き渡すものとする。
2. 発注者は引渡しを受けた時点で本工事の完了を承認する。
第7条(保証期間及び瑕疵担保)
1. 請負者は引渡し日から起算して2年間を保証期間とする。
2. 保証期間内に本工事に瑕疵が判明した場合、発注者の請求に応じて無償で速やかに修補する義務を負う。
第8条(遅延及び違約金)
1. 請負者は第3条に定める完了日までに本工事を完了させなければならない。
2. 完了が遅延した場合、請負者は発注者に対し、1日あたり報酬額の0.05%に相当する金額を違約金として支払うものとする。
3. 違約金の支払いは損害賠償請求を妨げるものではない。
第9条(契約の解除)
1. 発注者は請負者が契約条項に重大に違反し是正しない場合、契約を解除できる。
2. 請負者が解除された場合、発注者は損害賠償を請求できる。
第10条(安全管理及び法令遵守)
請負者は建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、安全かつ適正に工事を実施する義務を負う。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
当事者は相手方の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡または移転してはならない。
第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、当事者は誠意をもって協議の上解決するものとする。
この建設契約書の内容は、発注者と請負者双方の権利義務を明確に定めており、実務に即した構成となっています。
特に支払い条件や遅延時の違約金規定が具体的で、リスク管理がしっかり考慮されている点が評価できます。
また、保証期間や瑕疵担保の条項が設けられていることから、工事の品質確保にも配慮されていることが伺えます。
一方で、第12条の協議事項では、不測の事態に対応するための柔軟性を残しており、契約後の問題解決にも適した条項です。
条文ごとに条番号が振られていて読みやすく、工期や検査に関する具体的な期日も明示されているため、トラブル防止の観点で非常に有用です。
総じて、実務担当者が安心して活用できる契約書のテンプレートとして高い完成度を感じます。今後の案件でも同様の形式を踏襲することをおすすめします。
プロンプト5:レンタル契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたはレンタル契約書作成専門の法務AIです。以下の条件に基づいて、完璧かつ日本法に準拠したレンタル契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・レンタル物件の種類(例:住宅、オフィス、車両等)を明示すること
・契約期間、賃料、支払い方法、更新・解約条件を含めること
・借主・貸主の責任と義務を具体的に記載すること
・契約解除の条件と違約金に関する条項を設けること
・損害賠償や修繕義務について明確に記述すること
・日本の民法および関連法令に準拠すること
・専門用語は正確に用い、文体は簡潔で正式な常体とすること
#入力情報
レンタル物件の種類、契約期間、賃料、支払い方法、特記事項など、具体的な情報をここに貼り付けてください。
#出力内容
レンタル契約書全文(条文形式)
レンタル契約書作成をするプロンプトの解説
✅「レンタル物件の種類」の明示:住宅・オフィス・車両など、対象物件を具体的に記載
✅「契約内容の完全記載」:契約期間、賃料、支払い方法、更新・解約条件を漏れなく含める
✅「法令遵守と文体の統一」:日本の民法等に準拠し、専門用語を正確に用いた簡潔で正式な常体で作成
このプロンプトは、日本法に準拠したレンタル契約書全文を自動生成するためのものです。
賃貸契約書を一から正確に作成したいビジネスシーンや法務担当者に最適です。
「レンタル物件の種類」や「契約期間」「賃料」「支払い方法」などの具体的情報を入力するだけで、
専門用語を正しく使い、明瞭かつ正式な条文形式の契約書を得られます。
契約解除の条件や違約金、損害賠償など法律的な重要ポイントも網羅されており、
工数を大幅に削減し、誤記や漏れを防ぐことが期待できます。
これにより、契約書作成の手間を通常数時間から数十分に短縮可能です。
入力例
#命令
あなたはレンタル契約書作成専門の法務AIです。以下の条件に基づいて、完璧かつ日本法に準拠したレンタル契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・レンタル物件の種類(例:住宅、オフィス、車両等)を明示すること
・契約期間、賃料、支払い方法、更新・解約条件を含めること
・借主・貸主の責任と義務を具体的に記載すること
・契約解除の条件と違約金に関する条項を設けること
・損害賠償や修繕義務について明確に記述すること
・日本の民法および関連法令に準拠すること
・専門用語は正確に用い、文体は簡潔で正式な常体とすること
#入力情報
レンタル物件の種類:住宅(東京都新宿区所在のマンション)
契約期間:2024年7月1日から2025年6月30日までの1年間(自動更新有り)
賃料:月額150,000円(税込)
支払い方法:毎月末日までに指定口座へ振込
特記事項:ペット飼育禁止、敷金として150,000円を契約時に預託、契約更新時には書面にて通知すること
#出力内容
レンタル契約書全文(条文形式)今回は、東京都新宿区所在のマンションを対象とした住宅のレンタル契約書を作成するためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- レンタル物件の種類を「住宅(新宿区所在のマンション)」
- 契約期間を「2024年7月1日から2025年6月30日までの1年間(自動更新有り)」
- 賃料を「月額150,000円(税込)」
- 支払い方法を「毎月末日までに指定口座へ振込」
- 特記事項に「ペット飼育禁止」「敷金150,000円の契約時預託」「契約更新時には書面通知」
- 契約の更新・解約条件や借主・貸主の責任義務を具体的に明記
- 違約金や損害賠償、修繕義務についても条文を設け
- 日本の民法および関係法令に準拠した内容としました。
こうした具体的な情報を盛り込むことで、住宅賃貸に関する法律的に正確かつ詳細なレンタル契約書を簡潔かつ正式な文体で作成できます。
また、改行を適宜入れることで視認性を高め、契約内容の各項目を明確に区分して把握しやすくしています。
これにより、プロンプトの修正や契約書のカスタマイズが容易になります。
実行結果(GPT-4o)
賃貸借契約書
第1条(目的)
貸主は、借主に対し、東京都新宿区所在のマンション(以下「本物件」という)を賃貸し、借主はこれを賃借することを約する。
第2条(契約期間)
本契約の期間は、2024年7月1日から2025年6月30日までの1年間とする。期間満了後、いずれの当事者からも更新の申出がない限り、自動的に同一条件で1年間更新されるものとする。
第3条(賃料)
1. 賃料は月額150,000円(税込)とする。
2. 借主は、当該月の賃料を毎月末日までに貸主指定の口座へ振込により支払うものとする。
3. 振込手数料は借主の負担とする。
第4条(敷金)
1. 借主は、本契約締結時に敷金として賃料1ヶ月分に相当する150,000円を貸主に預託する。
2. 敷金は、本契約終了時に本物件の原状回復費用等を差し引いた残額を借主に返還する。
第5条(禁止事項)
借主は、本物件においてペットの飼育をしてはならない。
第6条(借主の責任及び義務)
1. 借主は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用し、毀損・汚損しないよう努める。
2. 通常の使用による損耗を除き、借主の過失により生じた損害は借主の負担にて修繕するものとする。
3. 賃料及びその他の金銭債務を期限内に履行する義務を負う。
4. 本物件の使用に関し法令及び本契約の条項を遵守する。
第7条(貸主の責任及び義務)
1. 貸主は、本物件を借主に対し契約期間中適法に使用させる義務を負う。
2. 本物件の構造上又は設備上の瑕疵が判明した場合、速やかに修繕する責任を負う。
第8条(契約の更新及び解約)
1. 契約期間満了の30日前までにいずれかの当事者から書面による更新拒絶の通知がない限り、本契約は第2条に定めるとおり自動更新される。
2. 借主は、解約を希望する場合は1ヶ月前までに書面にて貸主に通知しなければならない。
3. 貸主は借主に対し、法令に定める正当な事由がある場合に限り、契約を解除できる。
第9条(契約解除及び違約金)
1. 借主が賃料支払いを遅滞した場合、貸主は催告の上、本契約を解除できる。
2. 借主が本契約の条項に違反し且つ相当期間内に是正しない場合、貸主は本契約を解除できる。
3. 前二項による解除の場合、借主は貸主に対し、違約金として賃料1ヶ月分を支払うものとする。
第10条(損害賠償)
本契約の履行に関し、一方当事者が相手方に損害を与えた場合は、民法及び関連法令に基づき賠償するものとする。
第11条(修繕義務)
1. 本物件の通常の使用に伴う修繕は貸主の責任とする。
2. 借主の故意又は過失による損傷の修繕は借主の責任とし、その費用を負担する。
第12条(その他)
本契約に定めのない事項は、日本国の民法その他関連法令の定めによる。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、貸主・借主各自署名押印のうえ各1通を保有する。
2024年6月30日
貸主(住所・氏名):
借主(住所・氏名):本賃貸借契約書の内容は非常に明確かつ包括的にまとめられており、賃貸借の基本的な事項を網羅しています。
特に契約期間や賃料の支払い方法、敷金の扱い、禁止事項などが具体的に示されているため、貸主・借主双方の権利義務が明確になっています。
また、契約更新や解約の手続き、契約解除条件や違約金に関する規定も詳細に設定されており、トラブル防止に配慮されている点が好印象です。
借主・貸主双方の修繕義務についても条文で分けて記載されているため、責任範囲の理解がしやすく、日常の管理においても役立つ内容です。
ただし、特定の条項においてはより詳細な条件や具体例を補足することで、さらなる安心感を提供できるかもしれません。
例えば、第5条の禁止事項について、何のペットが対象なのか具体化したり、第9条の違約金規定の公平性について、賃料1ヶ月分以外の選択肢も検討したりすると、利用者にとって親切です。
総じて、法的要件を満たしつつ実務面での使いやすさも考慮されたバランスの良い賃貸借契約書に仕上がっていると感じました。
SEOの観点からもこのような契約書テンプレートは、「賃貸契約書 ひな形」や「賃貸借契約書 テンプレート 無料」などのキーワードで高い検索ニーズが期待でき、コンテンツ提供としての価値が大きいと推察します。
ChatGPTで不動産契約書を作成するプロンプト5選のまとめ
不動産契約書の作成は専門的な法律知識が求められ、手間や時間がかかることが多いです。
そんな課題を解決するのが、ChatGPTを活用した契約書作成プロンプトです。
ChatGPTは自然言語処理に優れ、多様な要望に応じた文章生成が可能です。
たとえば、契約書の基本構成の自動作成や、特約事項の具体化、違約金条項の明確化などが簡単に行えます。
ここで紹介する5つのプロンプトを使えば、要点を押さえた正確かつ効率的な契約書作成が実現します。
しかも、AIが作成したドラフトをベースに専門家のチェックを加えることで、法的リスクを最小化できます。
まずは、このプロンプトを活用してみてください。
不動産契約のスピードアップとミス減少に大きく役立つでしょう。
ChatGPTでの契約書作成を習得し、業務効率化を一気に進めましょう。