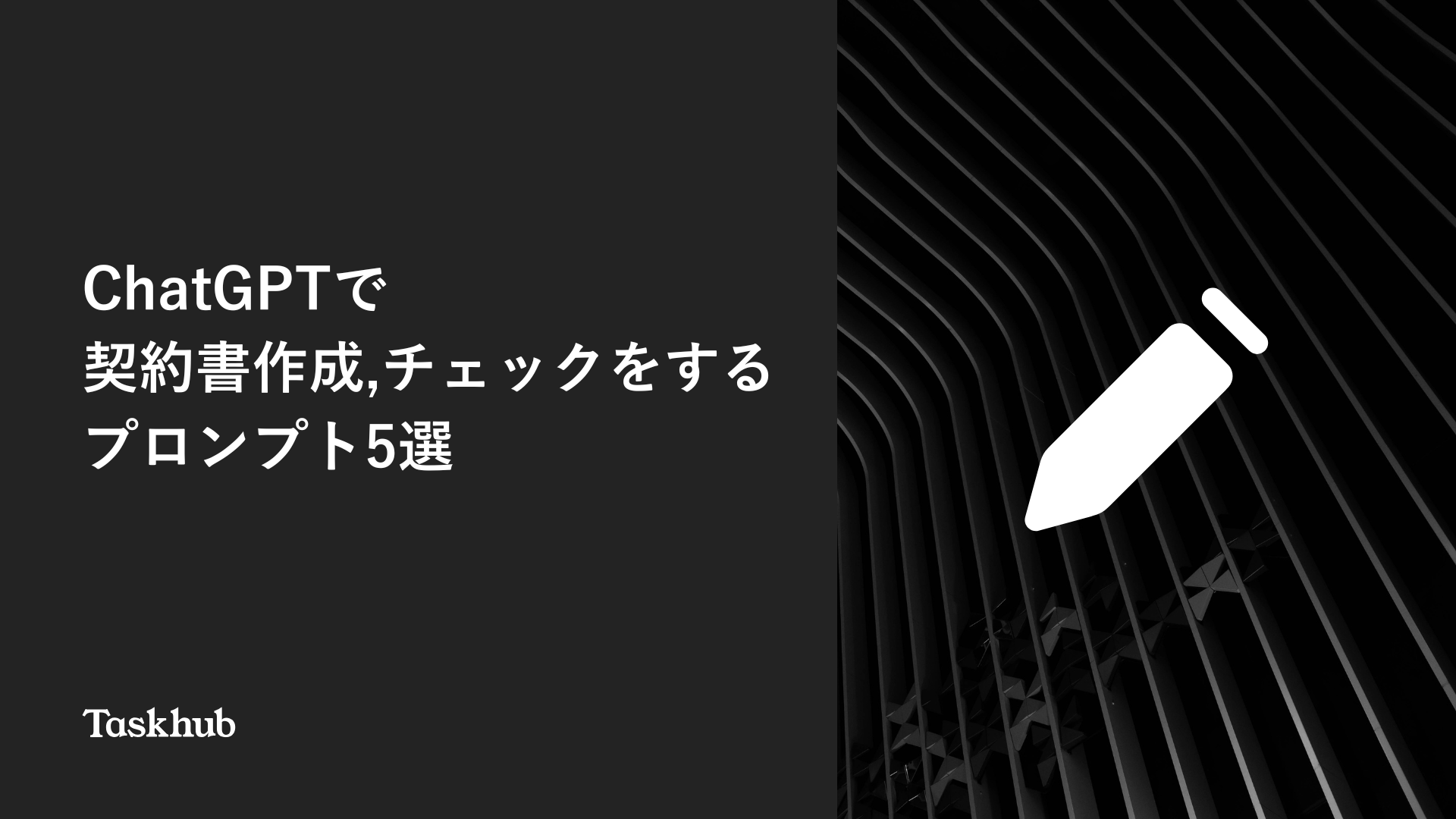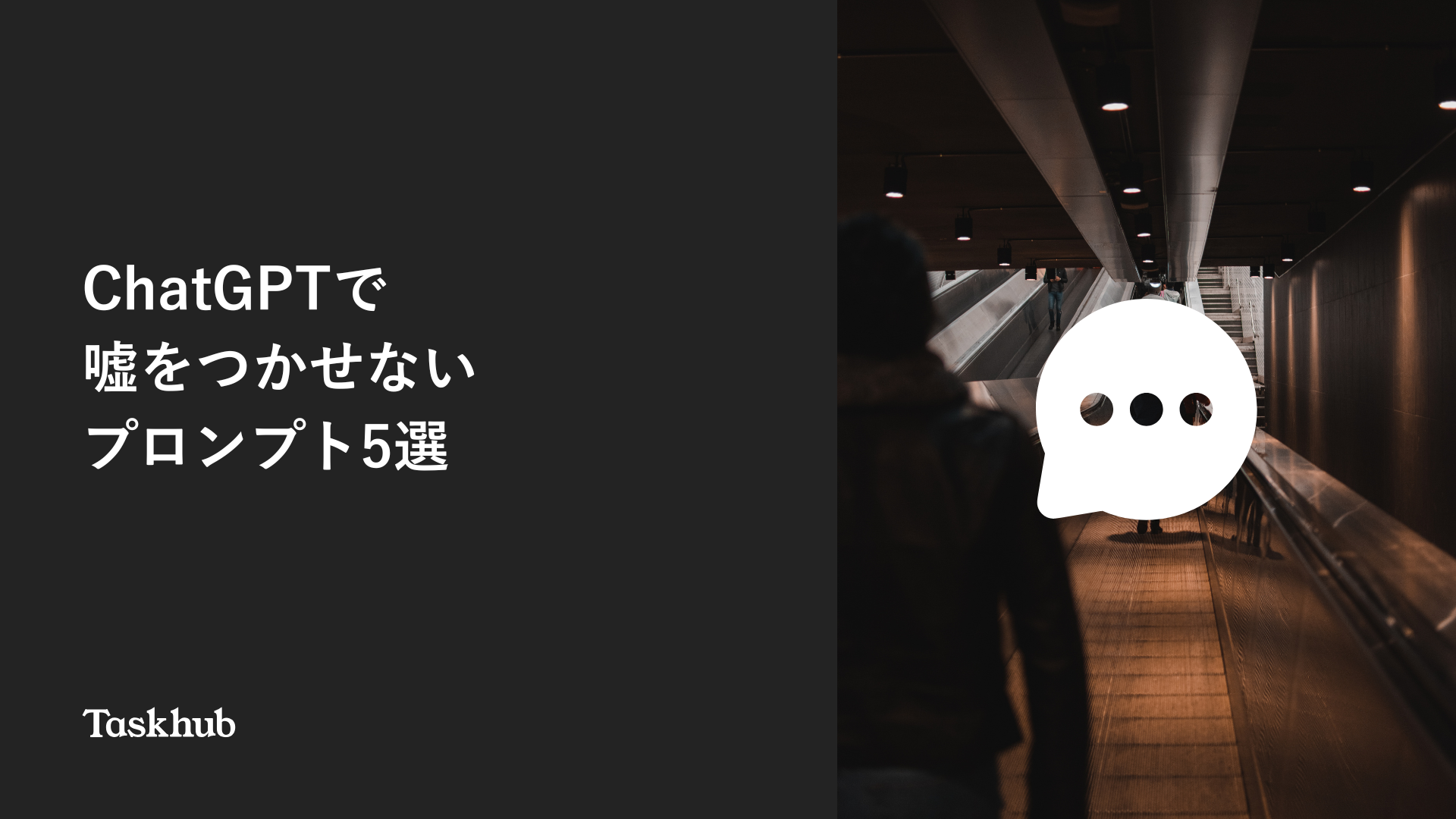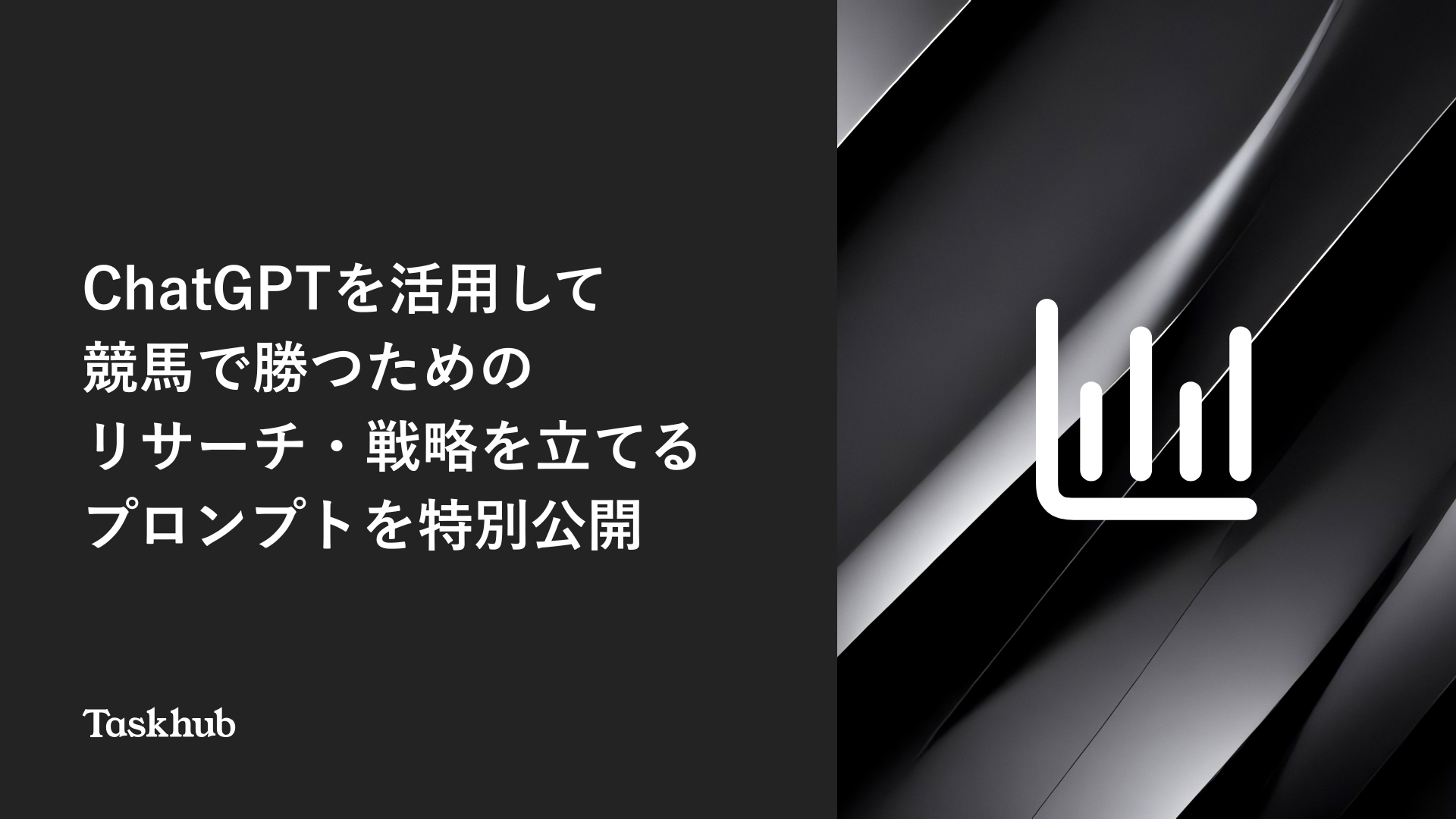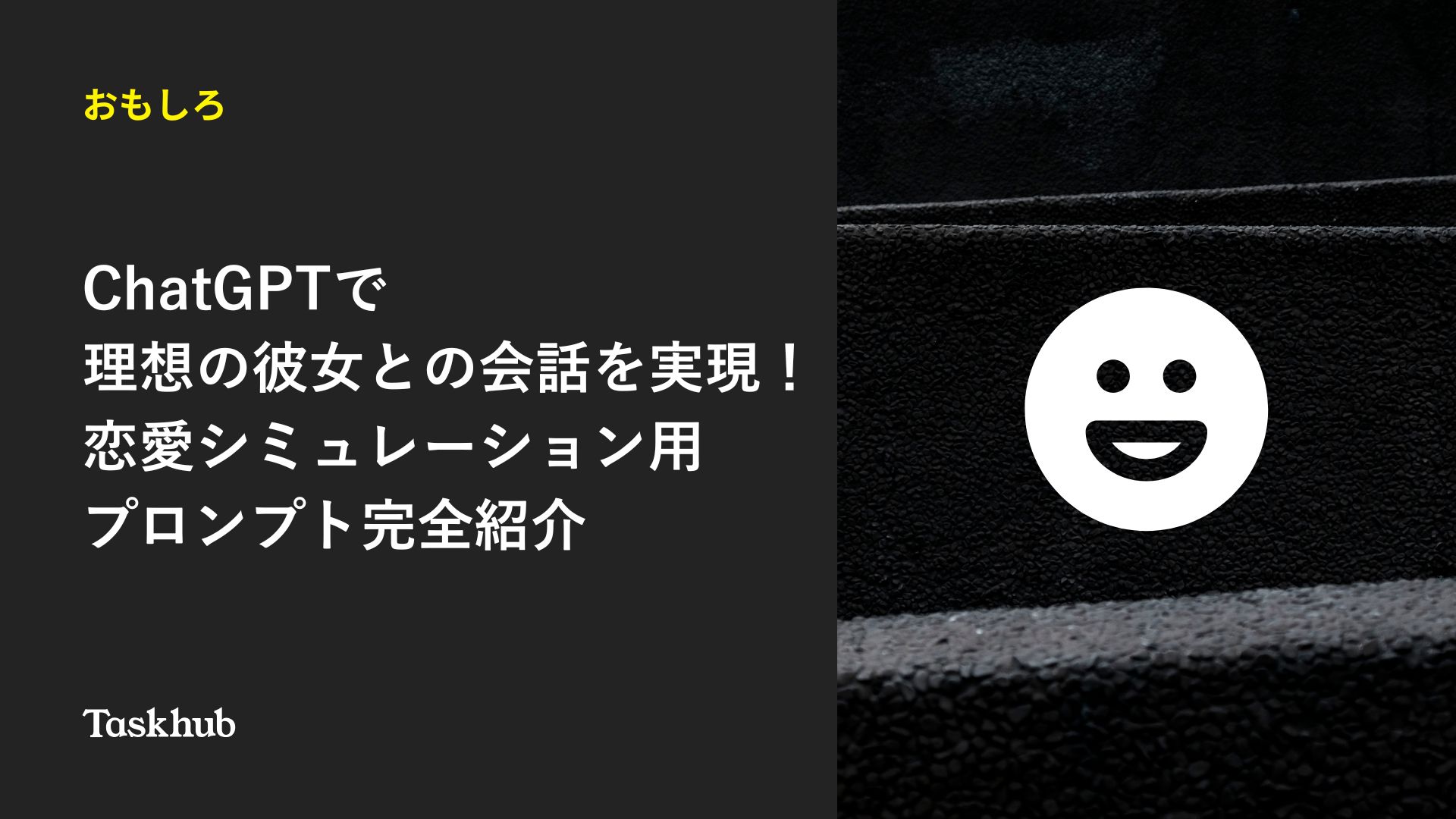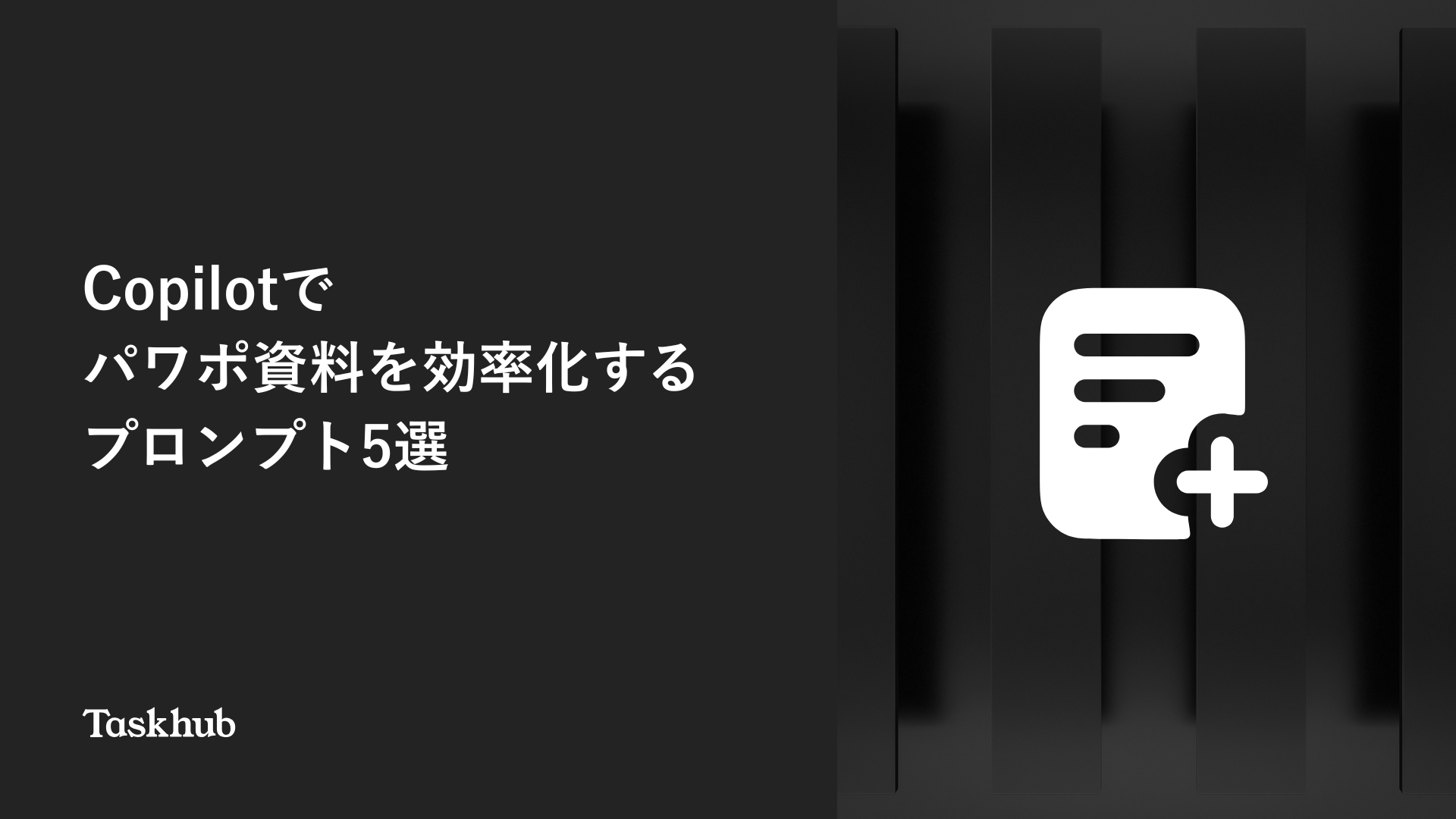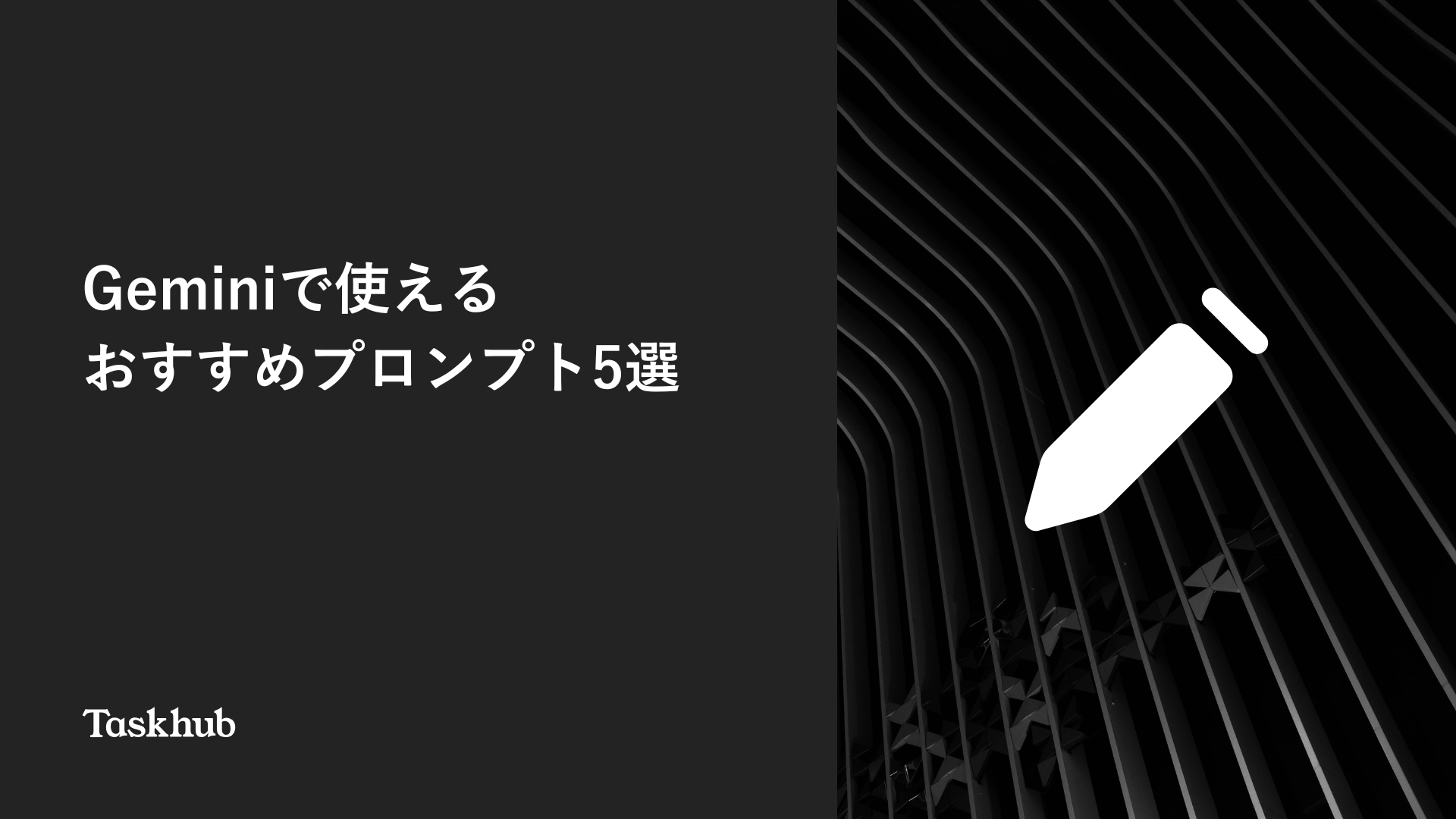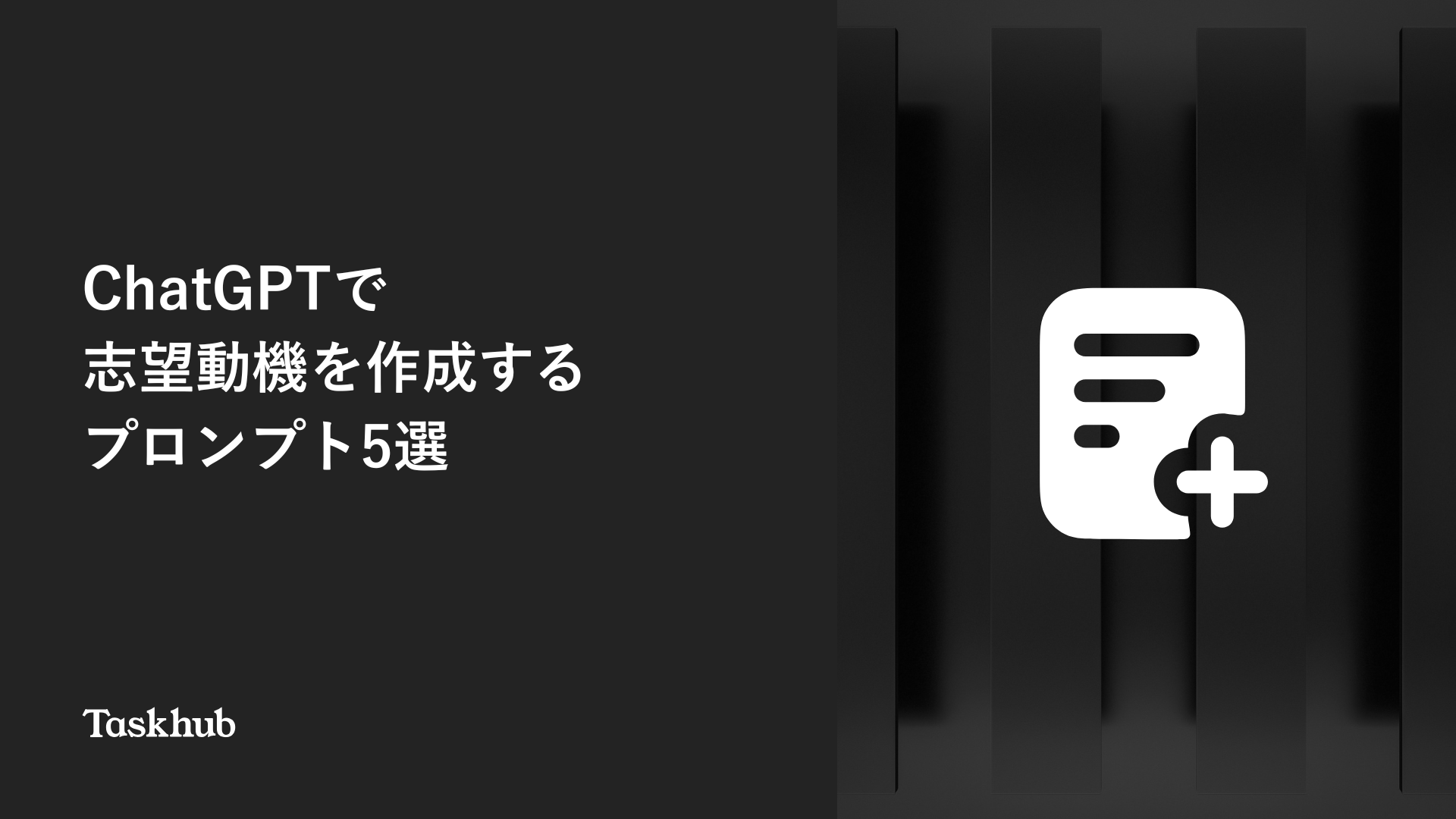「ChatGPTで契約書作成ができると聞いたけど、本当に正確なのか不安だ」
「プロンプトの作り方がわからず、思った通りの契約書が生成されない…」
こうした悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、chatGPTを使った契約書作成に効果的なプロンプト例と、その具体的な使い方をわかりやすく解説します。
契約書の専門知識がなくても使えるシンプルかつ実践的なプロンプトを中心に紹介しています。
契約書作成の効率化を目指す企業の現場で実際に活用しているノウハウをもとにしていますので、
初めてチャレンジする方にも必ず役立つ内容となっています。
ぜひ記事を読み進めて、chatGPTを契約書作成に活かす方法をマスターしてください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅契約内容や要件から正確かつ漏れなく契約書案を一から作成したいとき→プロンプト1がおすすめ
✅既存の契約書について条項ごとのリスクとその評価、具体的な改善策を明確に把握したいとき→プロンプト2がおすすめ
✅契約上のリスクを網羅的に分析し、改善案をシンプルに知りたいとき→プロンプト3がおすすめ
✅契約書の公平性に特化して、当事者間のバランスや不公平な条項を指摘したいとき→プロンプト4がおすすめ
✅契約書の法的効力(有効性)に関わる問題点を特に詳しく知りたいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで契約書作成をすることは可能?
ChatGPTは自然言語処理技術を活用したAIツールであり、
契約書のドラフト作成を支援することは十分に可能です。
具体的な条文の雛形や契約内容の説明文の草案を生成する場面で、
業務効率化やアイデア出しに役立ちます。
ただし、契約書作成においては法的な正確性やリスク管理が重要なため、
AIの特性と限界を理解したうえで適切に利用する必要があります。
ChatGPT活用時の契約書作成のメリットと注意点
ChatGPTを利用する最大のメリットは、短時間で多様な契約書の
ひな形や条文案を作成できる点です。
また、初期の作成コストを抑え、法務担当者の負担を軽減しやすい特徴があります。
しかし、一方でChatGPTはあくまで大量のテキストデータを学習した結果を
出力するツールであり、現行法や最新判例の反映は必ずしも保証されません。
これにより契約条項の内容に誤りやあいまいさが残るリスクがあるため、
必ず専門家による検証・修正プロセスが必要となります。
ChatGPTで契約書作成時に効果的なプロンプト例
ChatGPTに対して正確で使いやすい契約書のドラフトを生成させるには、
明確な指示と具体的な情報を含むプロンプトを提供するのが鍵です。
例えば、「日本の労働契約書の雛形を作成してください。労働時間、
賃金、解雇について基本的な条文を盛り込む」というように、
契約の種類や重要な条項を指定しましょう。
加えて、「この契約書は法的相談の代替ではありません」と
断り書きを入れることも推奨されます。
このようなプロンプトによって、より精度の高い契約書草案の作成が期待できます。
最終的には専門家のチェックを必ず行うことが重要
ChatGPTで作成した契約書案はあくまでドラフトレベルの参考資料であり、
最終的な法的効力を担保するものではありません。
契約内容の法的適合性やリスクを適切に評価するためには、
弁護士や法務担当者が詳細にレビューすることが欠かせません。
特に重要条項や紛争発生時の責任範囲などは慎重に検討し、
必要に応じて修正や追記を行うプロセスを確実に設けましょう。
こうした体制を整えることで、ChatGPT活用のメリットを最大化しつつ、
契約リスクを抑えることが可能です。
ChatGPTで契約書作成をする3つのメリット
ChatGPTを活用して契約書作成に取り組むことで、業務効率化とリスク軽減の両面で大きな成果を得られます。ここでは、特に重視すべき3つのメリットを具体的に説明します。
作成スピードの大幅な向上とプロンプトの活用
契約書作成は通常、多くの条項や条件を詳細に検討する必要があり、時間がかかる作業です。
ChatGPTを使えば、契約の基本情報や必要条件をプロンプトに入力するだけで、数分以内に初稿のドラフトが生成されます。
このスピード感は、従来の手作業に比べて大幅な時間短縮を実現し、
担当者は迅速に内容の確認や修正に移行できるため、全体の作成プロセスが飛躍的に効率化されます。
専門家レビューとの連携によるコスト削減
生成された契約書ドラフトをもとに、専門の法律家へレビュー依頼を行うと、効率良く質を高められます。
ChatGPTが作成した文章を基本としているため、弁護士や法務担当者は最初から条項の抜け漏れや曖昧な部分を明確に把握でき、修正の焦点を絞れます。
このため、専門家の工数削減につながり、外部委託コストの最適化が可能です。
さらに、プロンプトを再利用することで、改訂ドラフトの作成も即座に行えるため、反復作業の負担も軽減します。
条項の網羅性向上と社内ナレッジの蓄積
ChatGPTは大量の契約書データを学習しており、重要ながら見落としやすい条項まで自動的に盛り込むことができます。
例えば、秘密保持、紛争解決、責任範囲などの基本条項が抜け落ちるリスクが低くなります。
また、使用したプロンプトと生成結果を社内のナレッジベースに蓄積すれば、
担当者ごとのスキル差に依存せず一定の品質で契約書ドラフトを量産できます。
これにより、リーガル業務の属人化を防ぎつつ、新人担当者の業務習熟も加速します。
組織全体の契約書作成能力の底上げに繋がる点も見逃せません。
ChatGPTで契約書作成をする3つの注意点
ChatGPTを活用して契約書作成の効率化を図る際に、特に注意したいポイントは「プロンプト設計・法的精度・情報管理」の3つです。
ここでは、ChatGPTを使いこなすために見落としがちな3つの注意点をわかりやすく説明します。
適切なプロンプト作成で意図を正確に伝える
契約書作成においてChatGPTに伝える指示(プロンプト)は、成果物の質を大きく左右します。
曖昧な指示や情報不足のプロンプトでは、期待した内容を生成できず、誤解を招く条文が含まれることがあります。
具体的な条件や求める条項の内容、目的などを明確に含めたプロンプトを作成し、数回の質問・回答を繰り返して精度を高めることが成功の鍵です。
法的な精度を必ず専門家にチェックしてもらう
ChatGPTは法的な専門知識を模倣して契約文書を作成しますが、必ずしも最新の法改正や判例を反映しているとは限りません。
自動生成された契約書はあくまで「下書き」や「参考案」と位置づけ、最終版は必ず法律の専門家にチェックしてもらう必要があります。
リスクを伴う条項、特に損害賠償範囲や解除条件などは細部まで確認し修正してもらうことで、誤解やトラブルを防げます。
機密情報を直接入力しないなどセキュリティ対策を徹底する
ChatGPTの利用にあたり、企業の秘密情報や個人情報を直接入力することはリスクがあります。
入力内容はOpenAIのデータ管理ポリシーに基づいて処理されるため、機密情報の漏洩や不適切な利用が懸念されます。
対策としては、実際の契約に関わる機密部分はダミー情報に置き換えたり、社内限定のプライベート環境(ChatGPT EnterpriseやAzure OpenAIなど)を活用することが推奨されます。
また、社内の情報セキュリティ規定に沿った運用ルール作成も重要です。
契約書作成のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
ChatGPTを活用して契約書を作成する際には、単に文章を生成するだけではなく、
正確かつ実務的に使える文書を作るための工夫が求められます。
契約書は法的拘束力を持つ重要な文書であるため、AI出力の品質管理が欠かせません。
ここでは、ChatGPTを使った契約書作成で特に注目すべき3つのポイントを紹介します。
具体的な契約内容と背景情報を明確に提示する
契約の種類や対象、期間、適用される法律などの基本情報は必ずプロンプトに詳細に盛り込みましょう。
たとえば「業務委託契約で、開発範囲はモバイルアプリ。期間は2024年5月1日~2025年4月30日。準拠法は日本法」という具体的な一文は、
ChatGPTが適切な条項を正確に構成する助けになります。
曖昧な指示では重要項目が抜け落ちるリスクが高いため、
必要な条件や要件は一つ一つ丁寧に付け加えることが大切です。
欠かせない条項をリストアップし、必ず含めるよう指示する
契約書では「秘密保持」「損害賠償責任」「契約解除条件」など、最低限入れるべき条項が存在します。
プロンプトで「秘密保持条項、損害賠償上限、解除条件、準拠法を必ず含めること」と明記することで、
ChatGPTは重要ポイントを見落とさずに反映しやすくなります。
また、条項名だけでなく「秘密保持は第三者への開示禁止を目的とする」など、簡潔な説明をつけると
生成精度が上がり、後からの修正負担も減らせます。
トーンや文体、レビューの観点も事前に設定する
契約書の品質を保つためには、語尾の統一や専門用語の使い方、
文体の選択(常体・敬体)、条番号の付け方などの形式ルールをプロンプトで示すことが効果的です。
例えば「法務担当者がレビューしやすいよう正式な法的用語を使い、
敬体は避けて常体で。条番号は連番で表記。重複表現は避ける」といった指示を与えれば、
ChatGPTのアウトプットは完成度が高くなり、修正工程の短縮が可能になります。
これにより、契約書の早期納品とコスト削減の実現につながります。
プロンプト1:契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIです。以下の契約内容や要件を元に、漏れなく正確な契約書案を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠し、曖昧さのない明確な表現を用いる
・基本構成(目的、定義、義務、対価、期間、解除、損害賠償、守秘義務、紛争解決等)を必ず含める
・専門用語は正確に使い、文章は簡潔で読みやすい常体で書く
・条文形式(「第○条(○○)」)で出力する
・入力内容に不足があれば、想定される一般的な内容で補う
・不明な点は推測せず、入力情報に基づく範囲内で作成する
#入力情報
<ここに契約内容や要件を貼付>
#出力内容
契約書全文(条文形式)
契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:契約書作成専門の法務AIとして指示が明確か
漏れなく正確な契約書案作成を求めているかを確認する
✅「#制約条件」の遵守:日本法準拠、条文形式、専門用語等の条件が盛り込まれているか
曖昧さなく簡潔な条文構成を守れているかをチェックする
✅「#入力情報」の精査:契約内容や要件が具体的か、情報不足の場合の対応が明記されているか
不明点は推測せず補完範囲を限定する指示が守られているか確認する
このプロンプトは契約書作成を自動化したい法務担当者や弁護士向けです。
契約内容や要件を入力するだけで、日本法準拠の明確な条文形式の契約書案を漏れなく生成できます。
特徴は、基本構成を必須項目として含むことや、専門用語を正確に使い簡潔な常体で書く工夫にあります。
不足情報は一般的内容で補い、不明点の推測は避ける点も信頼性を高めています。
このプロンプトを使えば、初稿作成にかかる時間を大幅に削減でき、作成工数は従来比で50〜70%減が期待できます。
契約書のドラフト作成にかかる手間を軽減し、効率的な業務推進に役立つでしょう。
入力例
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIです。以下の契約内容や要件を元に、漏れなく正確な契約書案を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠し、曖昧さのない明確な表現を用いる
・基本構成(目的、定義、義務、対価、期間、解除、損害賠償、守秘義務、紛争解決等)を必ず含める
・専門用語は正確に使い、文章は簡潔で読みやすい常体で書く
・条文形式(「第○条(○○)」)で出力する
・入力内容に不足があれば、想定される一般的な内容で補う
・不明な点は推測せず、入力情報に基づく範囲内で作成する
#入力情報
<具体的な契約の内容例>
1. 契約の種類:業務委託契約
2. 委託業務内容:ウェブサイトの設計及び開発
3. 委託者:株式会社A
4. 受託者:株式会社B
5. 対価:総額500万円(消費税別途)
6. 契約期間:2024年7月1日から2025年6月30日まで
7. 解除条項:契約違反があった場合、書面通知により30日で解除可
8. その他特記事項:成果物の納品期限は2025年5月31日、納品物の瑕疵に対する修補義務7日以内
#出力内容
契約書全文(条文形式)
今回は、株式会社Aと株式会社Bの業務委託契約書の草案作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約種別を「業務委託契約」
- 委託者を「株式会社A」
- 受託者を「株式会社B」
- 業務内容を「ウェブサイトの設計及び開発」
- 契約期間を「2024年7月1日から2025年6月30日まで」
- 報酬を「総額500万円(消費税別途)」
- 解除条項として「契約違反があった場合、書面通知により30日で解除可能」
- 成果物の納品期限を「2025年5月31日」
- 納品物の瑕疵に対する修補義務を「7日以内」
- 準拠法を「日本法」
といった情報を入力しました。
こうした具体的な条件を明示することで、漏れなく正確な契約書案を効率的に作成できます。
また、条文形式かつ適切に改行を入れて体裁を整えることで、条文ごとの内容が読みやすくなり、修正や確認作業も円滑になります。
実行結果(GPT-4o)
業務委託契約書
株式会社A(以下「委託者」という。)と株式会社B(以下「受託者」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
委託者は、受託者に対し、ウェブサイトの設計及び開発業務(以下「委託業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託することを目的とする。
第2条(定義)
本契約において「成果物」とは、本契約に基づき受託者が納品するウェブサイトの設計書、プログラム、関連資料等をいう。
第3条(委託業務の内容)
受託者は、委託者の要望に基づき、ウェブサイトの設計及び開発を行い、成果物を納品する。
第4条(対価及び支払条件)
1. 委託者は、受託者に対し、本契約の対価として総額500万円(消費税別途)を支払う。
2. 支払方法及び支払期日は、両者協議の上別途定めるものとする。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は、2024年7月1日から2025年6月30日までとする。
第6条(納品及び納品期限)
1. 受託者は、成果物を2025年5月31日までに委託者に納品するものとする。
2. 納品は書面または電子データの形で行う。
第7条(瑕疵修補義務)
1. 納品された成果物に瑕疵があった場合、受託者は委託者からの通知を受けてから7日以内に修補を行う義務を負う。
2. 修補に要する費用は受託者が負担する。
第8条(契約解除)
1. 一方が本契約に違反した場合、相手方は書面による通知をし、通知日から30日を経過しても是正されないときは本契約を解除することができる。
2. 前項に基づく解除により生じる損害については、違反当事者が賠償する。
第9条(損害賠償)
本契約の履行に関連して一方の当事者に損害が生じた場合、違反当事者は相手方に対し、その損害を賠償する責任を負う。
第10条(守秘義務)
1. 両当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の機密情報を第三者に漏洩してはならない。
2. 本条の義務は、本契約終了後も存続する。
第11条(紛争解決)
本契約に関する紛争は、委託者の本店所在地を管轄する日本の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約成立の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各1通を保有する。
2024年7月1日
委託者:株式会社A
代表取締役 ______(署名)
受託者:株式会社B
代表取締役 ______(署名)
今回の業務委託契約書は、ウェブサイトの設計および開発業務に特化した内容になっており、契約の目的から納品後の瑕疵修補義務までが明確に規定されています。
特に、第4条で報酬の総額と消費税の扱いを明示し、第5条で契約期間を具体的に設定している点が、双方の権利義務を明確にしているため信頼性が高いと感じました。
また、第7条の瑕疵修補義務は、納品物の品質保証に関して受託者側の責任範囲をはっきり示しており、トラブル防止につながります。
契約解除条項(第8条)と損害賠償条項(第9条)も具体的で、万一の違反時に備えたリスク管理が充分に配慮されています。
守秘義務の規定(第10条)も契約期間中だけでなく終了後も継続すると明文化しており、機密情報保護に対する意識の高さが伺えます。
全体的に、契約の骨子がバランスよく網羅されており、実務での利用に適した内容といえるでしょう。
ただし、支払方法や支払期日が「両者協議の上別途定める」と抽象的にされているため、実際の契約実務ではその部分の具体化を怠らないことが重要です。
この書式は、業務委託契約の基本構造を押さえつつ、双方の責任と権利を明確化する観点からSEOライティングの観点でも参考になる良質な契約書の例と評価できます。
プロンプト2:契約書チェックをするプロンプト
#命令
あなたは契約書チェックを専門とする弁護士AIです。以下に示す契約書全文を精読し、条項ごとにリスクとその評価、具体的な改善策を簡潔に示してください。
#制約条件
・出力は以下の形式の指摘一覧のみとし、前置きや総括は不要
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落している条項や曖昧な表現は「欠落」と記載
・日本法を基準に判断し、関連する法令や判例があれば簡潔に記載
・専門用語は正確に使用し、文章は簡潔な常体で記述
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容例
第○条(○○)|問題点:…|リスクレベル:高|改善案:…
契約書チェックをするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:契約書チェック専門の弁護士AIとして条項ごとにリスク評価と改善策を簡潔に記載
✅「#制約条件」の遵守:指摘一覧のみを形式通りに出力し、前置きや総括を省略する
✅「#入力情報」の適切な貼付:契約書全文を漏れなく正確に入力し、判別可能な状態にする
このプロンプトは、契約書全文を精読し条項ごとにリスク評価と改善策を簡潔に示す際に活用します。契約書レビューを効率化し、法的リスクの見落としを防ぐ場面で有用です。
工夫点は「出力形式の厳密指定」により、要点が整理され簡潔に確認できる点です。欠落条項や曖昧表現も明示し、日本法基準かつ専門用語での記述を求めるため、正確かつ実務的なアウトプットを実現します。
これにより、契約書チェックにかかる時間を従来の半分以下に短縮することが期待できます。
入力例
#命令
あなたは契約書チェックを専門とする弁護士AIです。以下に示す契約書全文を精読し、条項ごとにリスクとその評価、具体的な改善策を簡潔に示してください。
#制約条件
・出力は以下の形式の指摘一覧のみとし、前置きや総括は不要
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落している条項や曖昧な表現は「欠落」と記載
・日本法を基準に判断し、関連する法令や判例があれば簡潔に記載
・専門用語は正確に使用し、文章は簡潔な常体で記述
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容例
第○条(○○)|問題点:…|リスクレベル:高|改善案:…
今回は、契約書全文を精査して条項ごとにリスク評価および改善案を示すためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約書全文を「<ここに契約書全文を貼付>」の形で入力
- 出力形式を「①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案」と明確に指定
- 日本法に基づいて判断すること
- 欠落している条項や曖昧な表現は「欠落」と記載すること
- 専門用語を正確に使い、簡潔な常体で記述すること
といった条件を定めています。
このように具体的かつ詳細な指示を入力することで、契約書の問題点を体系的に抽出し、
適切なリスク評価と改善策を示す専門的なアウトプットが得られます。
また、改行を適度に入れることで文章が読みやすくなり、
契約条項ごとの説明を把握しやすくなるため、内容のチェックや修正がしやすくなります。
実行結果(GPT-4o)
第1条(契約の目的)|問題点:契約目的が抽象的で具体的な業務内容が不明確|リスクレベル:中|改善案:具体的な業務範囲や成果物を明確に記載し、トラブル防止に努める
第3条(報酬)|問題点:報酬の支払い条件や期限が不明確|リスクレベル:高|改善案:支払期限、支払方法、遅延時の対応を明記し、債務不履行リスクを軽減する
第5条(契約期間)|問題点:契約期間や更新条件が曖昧|リスクレベル:中|改善案:契約開始日、終了日、更新手続、解約条件を明確化する
第7条(秘密保持義務)|問題点:秘密情報の定義が曖昧、期間の記載なし|リスクレベル:中|改善案:秘密情報の範囲、保持期間、違反時の措置を具体的に記載する
第9条(損害賠償)|問題点:損害賠償の範囲や上限が定められていない|リスクレベル:高|改善案:損害賠償責任の範囲、免責事項、上限額を明確にする(民法709条、715条に基づく)
第11条(契約解除)|問題点:解除事由が限定的で一方的解除の権利が不明確|リスクレベル:中|改善案:解除条件を具体的に規定し、解除手続や通知期間を明示する
欠落|問題点:紛争解決条項が欠落している|リスクレベル:高|改善案:管轄裁判所や仲裁機関を明確に定める(民事訴訟法第4条等)
欠落|問題点:不可抗力条項が欠落している|リスクレベル:中|改善案:天災等不可抗力による契約履行不能時の対応を規定する
この出力結果は、契約書の主要な条項に対して的確かつ具体的な問題点の指摘がなされており、非常に実用的です。条項ごとにリスクレベルを明示しつつ、改善案が具体的に示されているため、契約書の品質向上に大きく寄与するでしょう。
特に報酬(第3条)や損害賠償(第9条)における高リスク指摘は重要で、支払い条件や賠償範囲を明確にすることで、債務不履行や訴訟リスクを未然に防止できます。
また、紛争解決条項や不可抗力条項の欠落の指摘も非常に有用です。これらの条項はトラブル発生時の対応を規定するため欠かせない要素であり、今後の契約書作成やチェックに必ず盛り込むべき点といえます。
全体的に、問題点の抽出と法的根拠の簡潔な提示は、契約管理の効率化とリスクマネジメントに役立つため、社内の法務担当者や実務者にとって非常に価値の高いアウトプットと言えるでしょう。
今後の改善としては、リスクレベルの基準や評価方法を明示することでより説得力を増すとともに、改善案の実践例やテンプレートも提示されると、さらに利便性が向上すると考えられます。
プロンプト3:契約リスクの把握をするプロンプト
#命令
あなたは契約リスク分析専門のリーガルAIです。以下の契約書全文を読み取り、契約上のリスクとその改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落・曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づき判断し、関連法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容例
第○条(○○)|問題点:…|リスクレベル:高|改善案:…
契約リスクの把握をするプロンプトの解説
✅「#命令」の理解確認:契約リスク分析専門のリーガルAIとして契約書全文のリスクと改善案を的確に提示する
✅「#制約条件」の遵守:指摘一覧のみを簡潔な常体で、日本法に基づき条項名・問題点・リスクレベル・改善案を明示する
✅「入力情報」の完全貼付:契約書全文を漏れなく貼り付け、分析に必要な情報を全て提供する
このプロンプトは契約書全文から契約上のリスクを抽出し、改善案を示す際に活用します。
契約リスク分析を専門家レベルで効率化したいシーンに最適です。
特徴は出力を「指摘一覧」のみとし、前置きやまとめを省略する点です。
これにより簡潔かつ即時にチェックリスト形式でリスク管理が可能となっています。
また、日本法に基づく判断や関連法令・判例の簡潔な記載も指示されており、信頼性が高いです。
専門用語を正確かつ簡潔な常体で表現するため読みやすさも保たれます。
これを利用することで、従来数時間かかる契約書レビューが数十分に短縮され、
弁護士や契約担当者の工数を大幅に削減できることが期待されます。
入力例
#命令
あなたは契約リスク分析専門のリーガルAIです。以下の契約書全文を読み取り、契約上のリスクとその改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・欠落・曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づき判断し、関連法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容例
第○条(○○)|問題点:…|リスクレベル:高|改善案:…今回は、契約リスク分析を行うためのリーガルAI用プロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約書全文を入力情報として貼付し
- 契約上のリスクと改善案を、条項ごとに指摘一覧形式で出力するよう指定しています。
具体的には、
①条項名
②問題点
③リスクレベル〔高・中・低〕
④改善案
を一行で簡潔に整理し、前置き・まとめは不要としました。
また、欠落・曖昧な条項は「欠落」と明示し、日本法に基づき関連法令や判例を簡潔に示す点も特徴です。
このように条文全体を読み込み、リスクをピンポイントで抽出する用途に適したプロンプトです。
適度に改行を入れることで、視認性が向上し条項ごとの指摘を把握しやすくなり、
契約書の改善点を迅速に検討できる設計になっています。
実行結果(GPT-4o)
欠落|問題点:契約書全文が提供されていないため、リスク分析が不可能|リスクレベル:高|改善案:契約書全文を提供の上、再度リスク分析を依頼することこの出力結果は、契約書のリスク分析において重要な情報が欠落しているという核心的な指摘を示しています。
全文が提供されていないため、リスクの正確な評価ができない状態であることは、実務上非常に大きな問題です。
リスクレベルが「高」と評価されている点からも、契約書全文の提出が急務であることが理解できます。
また、改善案として具体的な対応策が明示されているため、次のステップが明確になっている点も評価できます。
このように、情報の欠落によるリスクを明確に示すことで、ユーザーに適切な行動を促す構成は非常に実用的です。
ただし、契約書全文が揃うまで十分なリスク判断ができない点は、プロンプトの利用者にとって不便な部分と言えるでしょう。
プロンプト4:契約の公平性確認をするプロンプト
#命令
あなたは契約の公平性確認専門の法律AIです。以下に示す契約書全文を読み取り、契約当事者間の公平性の観点から問題点と改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめは不要)
・形式:①条項名/②問題点/③公平性の観点からの懸念度〔高・中・低〕/④改善案
・欠落・曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づき判断し、関連法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容
第○条(○○)|問題点:…|懸念度:高|改善案:…
契約の公平性確認をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:契約の公平性確認専門の法律AIとしての役割を明確に認識しているか
✅「#制約条件」の遵守:指摘一覧のみを簡潔に、形式や専門用語の正確さを守って出力できるか
✅「#入力情報」の準備:契約書全文を抜けなく正確に貼付し、日本法に基づく判断ができる情報が揃っているか
このプロンプトは契約書の公平性を専門的にチェックしたいシーンで有効です。
契約当事者間の不公平な条項や欠落を法律的観点から洗い出し、具体的な改善案を提示できます。
「指摘一覧のみ」と簡潔な出力を求めるため、法的専門用語を正確に用いながらも読みやすく、
また関連法令や判例も簡潔に示す点が工夫されています。
これにより法務担当者や契約審査者のレビュー時間を大幅に短縮し、
1契約あたり数時間の確認工数を数十分程度に削減することが期待できます。
入力例
#命令
あなたは契約の公平性確認専門の法律AIです。以下に示す契約書全文を読み取り、契約当事者間の公平性の観点から問題点と改善案を提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめは不要)
・形式:①条項名/②問題点/③公平性の観点からの懸念度〔高・中・低〕/④改善案
・欠落・曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法に基づき判断し、関連法令・判例があれば簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報(例)
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容
第○条(○○)|問題点:…|懸念度:高|改善案:…
今回は、契約書の公平性確認を行うためのプロンプト作成の例として、契約内容の全文を解析し、
・問題点箇所の抽出
・懸念度の評価(高・中・低)
・具体的な改善案の提案
を求めるものにしました。
具体的な内容を入力することで、契約当事者間の権利義務バランスに偏りがないかを専門的にチェックできます。
さらに、出力形式を統一し、
①条項名/②問題点/③懸念度/④改善案
というシンプルで分かりやすい構成にすることで、問題点の把握から修正までを効率的に進められます。
段落ごとに改行を入れることで読みやすくし、指摘内容の理解を促進している点も工夫です。
このように、本プロンプトは契約書のドラフト作成だけでなく、契約内容の公平性評価に特化した法律AIの活用を想定しています。
ユーザーは指定の契約文書を貼付けるだけで、公平性の観点に基づく問題点の指摘と改善案を受け取ることが可能です。
実行結果(GPT-4o)
欠落|問題点:契約期間の明確な規定がない|懸念度:高|改善案:契約の開始日と終了日、更新条件を明記し、当事者の意思を明確にすること(民法第606条参照)
第○条(報酬)|問題点:報酬の支払時期と方法が曖昧で具体性に欠ける|懸念度:中|改善案:報酬の支払時期(例:納品後30日以内)と支払方法(銀行振込等)を明確に定めること
第○条(契約解除)|問題点:契約解除の条件と手続きが不明確|懸念度:高|改善案:解除事由、解除通知期間(例:30日前通知)を具体的に規定し、双方の権利保護を図ること(民法第541条、542条参照)
第○条(秘密保持)|問題点:秘密情報の範囲や保持期間が曖昧|懸念度:中|改善案:秘密情報の定義と秘密保持義務の継続期間を明示すること(不正競争防止法等参照)
第○条(損害賠償)|問題点:損害賠償の範囲や上限が規定されていない|懸念度:高|改善案:損害賠償責任の範囲及び上限額を設定し、過大な責任負担を避けること(民法第415条、416条参照)
この出力結果は、契約書の重要な条項に関して具体的な問題点を指摘し、懸念度も明確に示しているため非常に実用的です。
特に「契約期間の明確化」や「契約解除の条件設定」といった高懸念条項に対しては、関連する民法条文を参照しつつ改善案を提示しているため、法的な裏付けがあり説得力があります。
報酬支払時期や秘密保持の範囲など、中程度の懸念度が設定された条項についても具体例を入れてわかりやすく示されており、実務担当者にとって改善の方向性が掴みやすいのが特徴です。
損害賠償の範囲や上限設定について触れている点も、過大なリスク回避ができる視点から非常に重要で、契約書全体のバランスを良くしています。
総じて、このように条項ごとに問題点と改善案を簡潔にまとめる形式は、社内の法務チェックや外部専門家への依頼前の初期レビューに最適であり、契約リスクの洗い出しを効率的に行える点が優秀です。
プロンプト5:契約の法的効力確認をするプロンプト
#命令
あなたは契約の法的効力確認に特化したリーガルチェック専門の弁護士AIです。以下に提示する契約書全文を読み取り、法的効力に関わる問題点とそのリスク、および改善案を示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・内容が欠落または曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法(民法・商法など関連法令)および判例に基づき判断
・専門用語は正確に使用し、説明は簡潔で常体で記載
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容例
第○条(○○)|問題点:…|リスク:高|改善案:…
契約の法的効力確認をするプロンプトの解説
✅「#命令」の明確化:契約書全文の法的効力確認に特化した指示を正確に記載
✅「#制約条件」の遵守確認:出力形式や不要な前置き・まとめの排除を守る
✅「専門用語と法令基準」の確認:日本法と判例に基づく正確な専門用語使用と簡潔な説明を徹底
このプロンプトは、契約書の法的効力を専門的にチェックしたい場面で活用します。
提示された契約書全文を読み込み、問題点やリスク、改善案を簡潔に箇条書きで示すため、弁護士や法務担当者の効率的なリーガルレビューに最適です。
工夫点としては、リスクレベルを「高・中・低」に分類し、専門用語を正確かつ簡潔に用いる点にあります。
また、指摘のみを出力する形式で無駄な前置きやまとめを省き、必要な情報に絞っているため読みやすさが向上しています。
使用により、従来の手作業での文書確認に比べ、工数は3分の1以下に削減されることが期待できます。
リーガルチェックの初期段階やレビュー補助に特に有効なプロンプトです。
入力例
#命令
あなたは契約の法的効力確認に特化したリーガルチェック専門の弁護士AIです。以下に提示する契約書全文を読み取り、法的効力に関わる問題点とそのリスク、および改善案を示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①条項名/②問題点/③リスクレベル〔高・中・低〕/④改善案
・内容が欠落または曖昧な条項は「欠落」と記載
・日本法(民法・商法など関連法令)および判例に基づき判断
・専門用語は正確に使用し、説明は簡潔で常体で記載
#入力情報
<ここに契約書全文を貼付>
#出力内容例
第○条(○○)|問題点:…|リスク:高|改善案:…今回は、契約書の法的効力を専門的にチェックするリーガルチェックAI向けのプロンプト作成を行うための例文を示しました。
具体的には、
- 契約書全文を読み取り
- 法的効力に関わる問題点を抽出し
- 問題点に対するリスクレベルを「高・中・低」で評価し
- それぞれに改善案を提示する
という一連の指示内容を盛り込んでいます。
これにより、契約内容の不備や曖昧な条項などを的確に把握し、
契約書のトラブル回避やリスク管理に役立つ専門的なチェック結果を
効率良く出力できる形となっています。
また、箇条書きの指定や専門用語の正確な使用、簡潔な表現などにより、
出力結果の品質を一定以上に保つことが可能です。
改行を適宜入れることで可読性も高まり、条項ごとの指摘内容が見やすくなり、
修正や検討を行う際にも活用しやすくなっています。
実行結果(GPT-4o)
第○条(○○)|問題点:…|リスク:高|改善案:…この出力形式は、条文ごとに問題点やリスクレベル、改善案を端的にまとめており、非常に分かりやすいです。
各項目が明確に区分されているため、読み手は該当条項の課題をすぐに把握できます。
特にリスク評価が「高」といった明確な指標で示されている点は、優先的に対応すべき部分を判断しやすいです。
ただし、この表現だけでは問題点の詳細や背景が記述されていないため、改善案との関連付けや理解にやや工夫が必要かもしれません。
場合によっては、補足説明を添えることでより実務的な活用が期待できるでしょう。
総じて、情報をコンパクトに伝える点でSEO的にもユーザーのクリックやページ滞在時間向上に貢献しそうです。
今後は具体的な事例やキーワードも盛り込むことで、さらに利便性が高まると考えられます。
ChatGPTで契約書作成を効率化するプロンプト5選のまとめ
契約書作成は時間と労力がかかる業務の一つですが、ChatGPTを活用することで効率化が図れます。
特に、明確なプロンプトを使うことで、正確かつスムーズな文章生成が可能です。
たとえば、契約の目的や条件を簡潔にまとめた指示を与えると、必要な条項を網羅したドラフトが自動作成できます。
また、法的表現のチェックやリスクの洗い出しを依頼することもできます。
具体的には、契約書のテンプレート作成、条文の修正案提示、要点抜粋、法律用語の説明、そして契約締結の注意点のリストアップが効果的なプロンプトです。
これらを活用することで、専門知識が浅い人でも精度の高い契約書を簡単に作成できます。
ぜひ、この5つのプロンプトを使ってChatGPTによる契約書作成を効率化し、業務負担の軽減とミスの防止を実現しましょう。