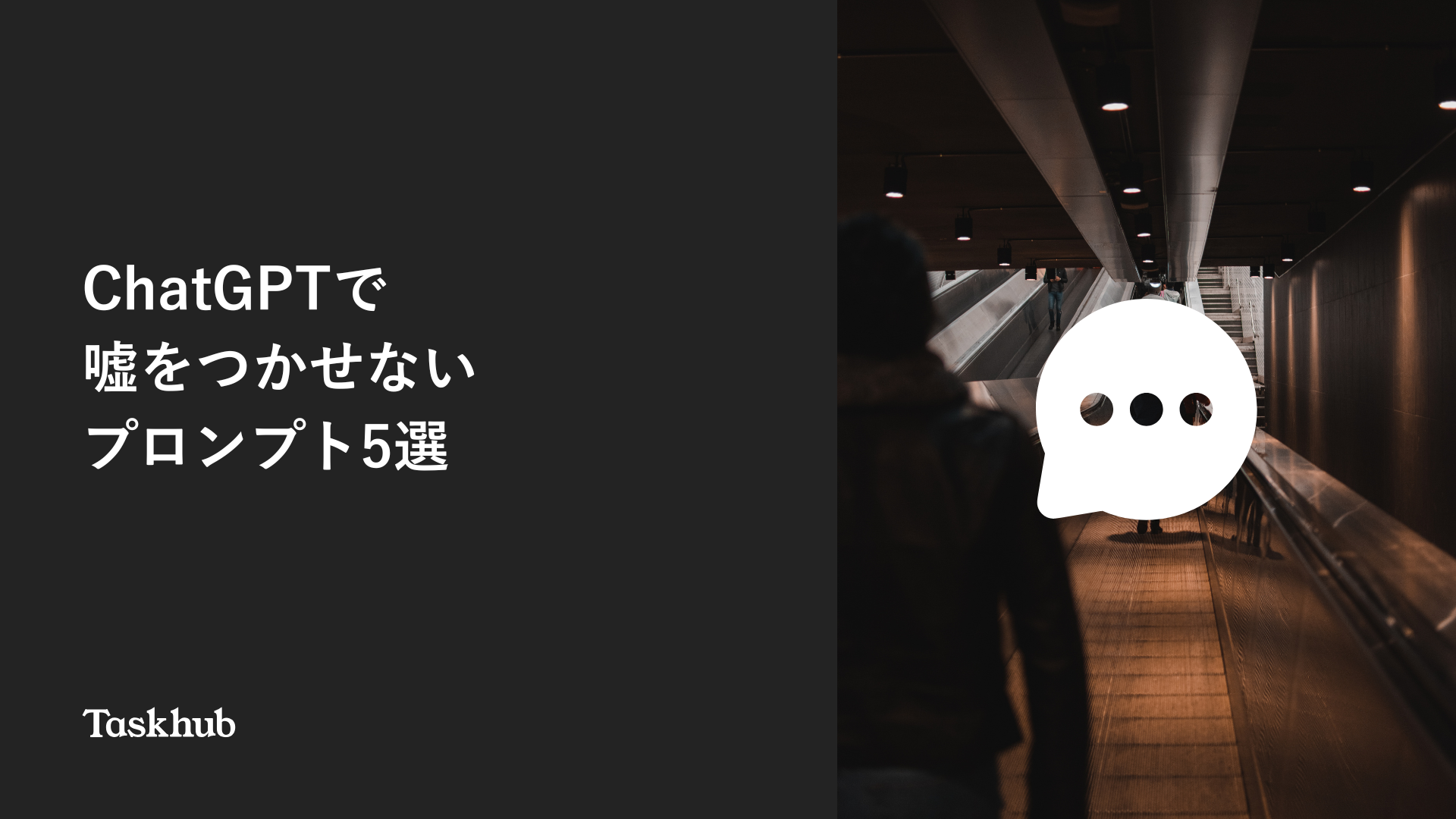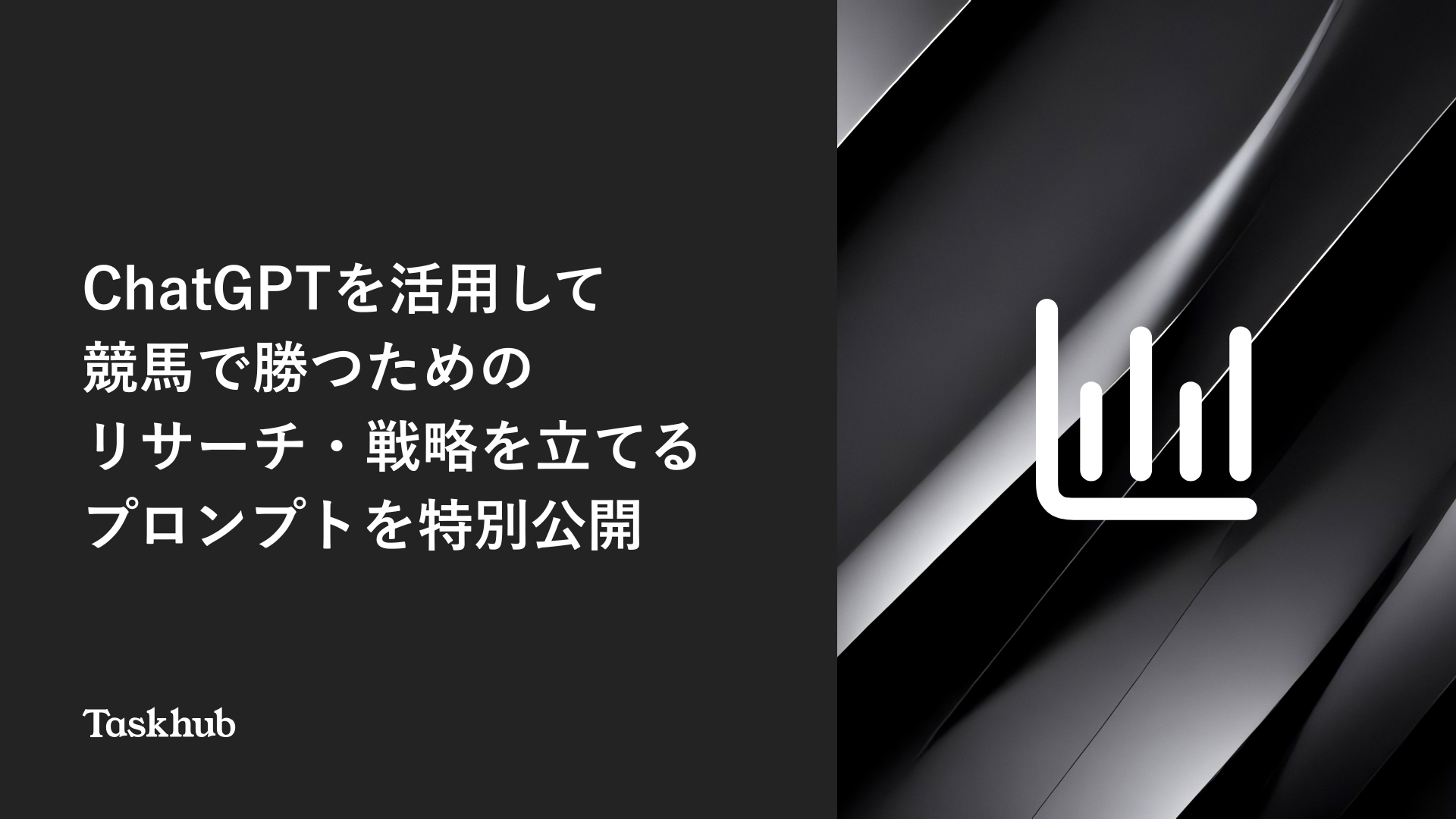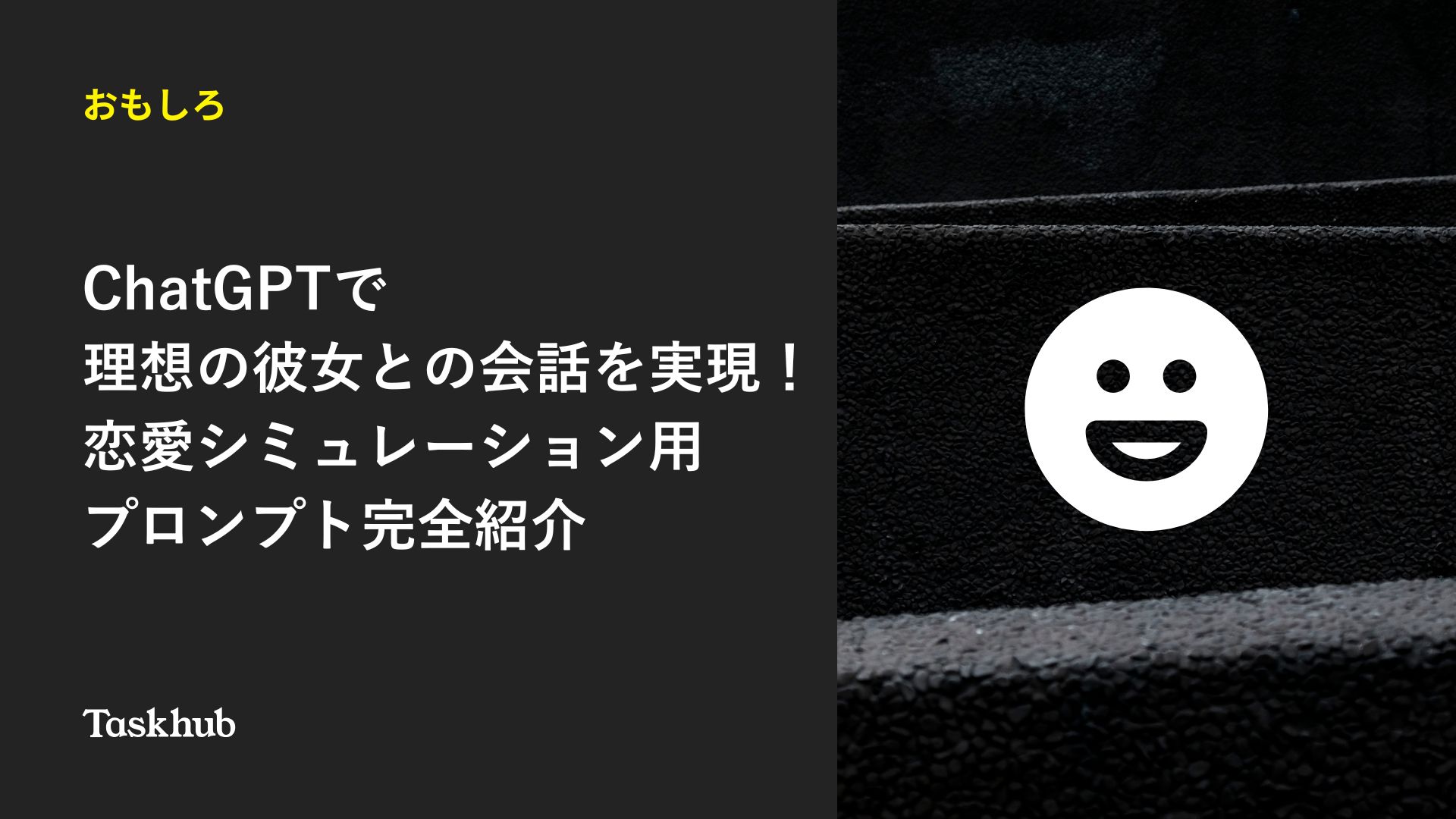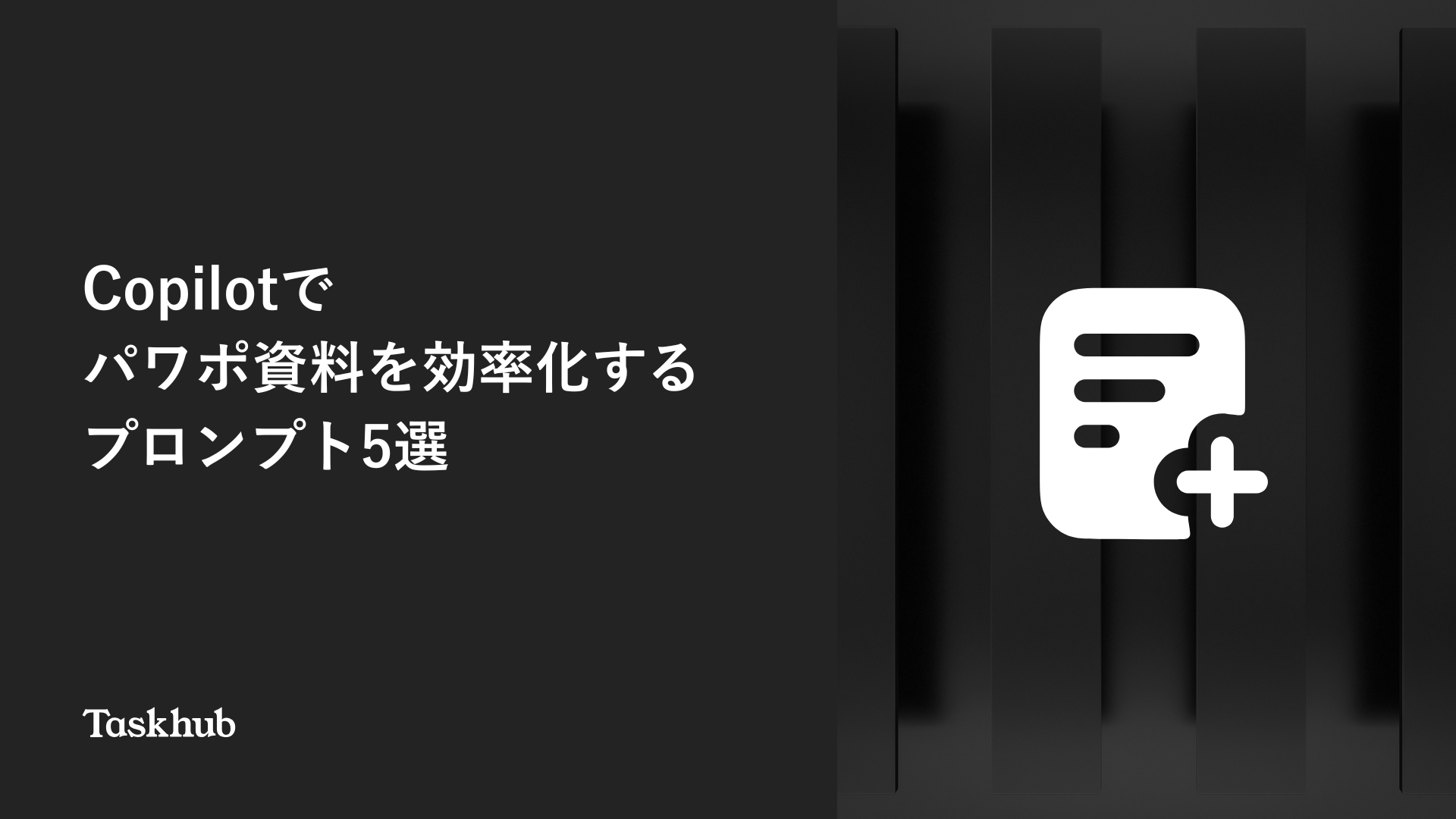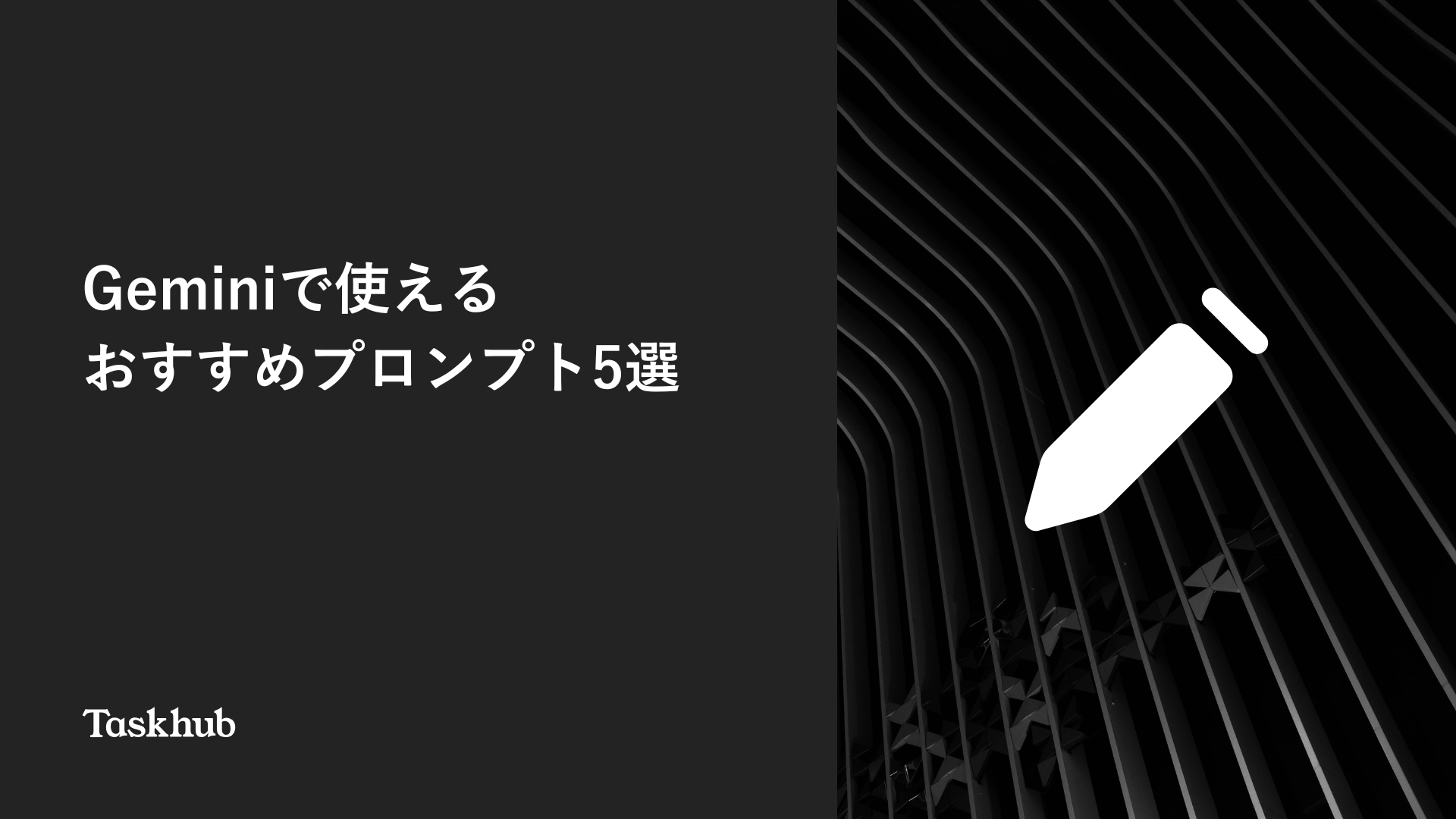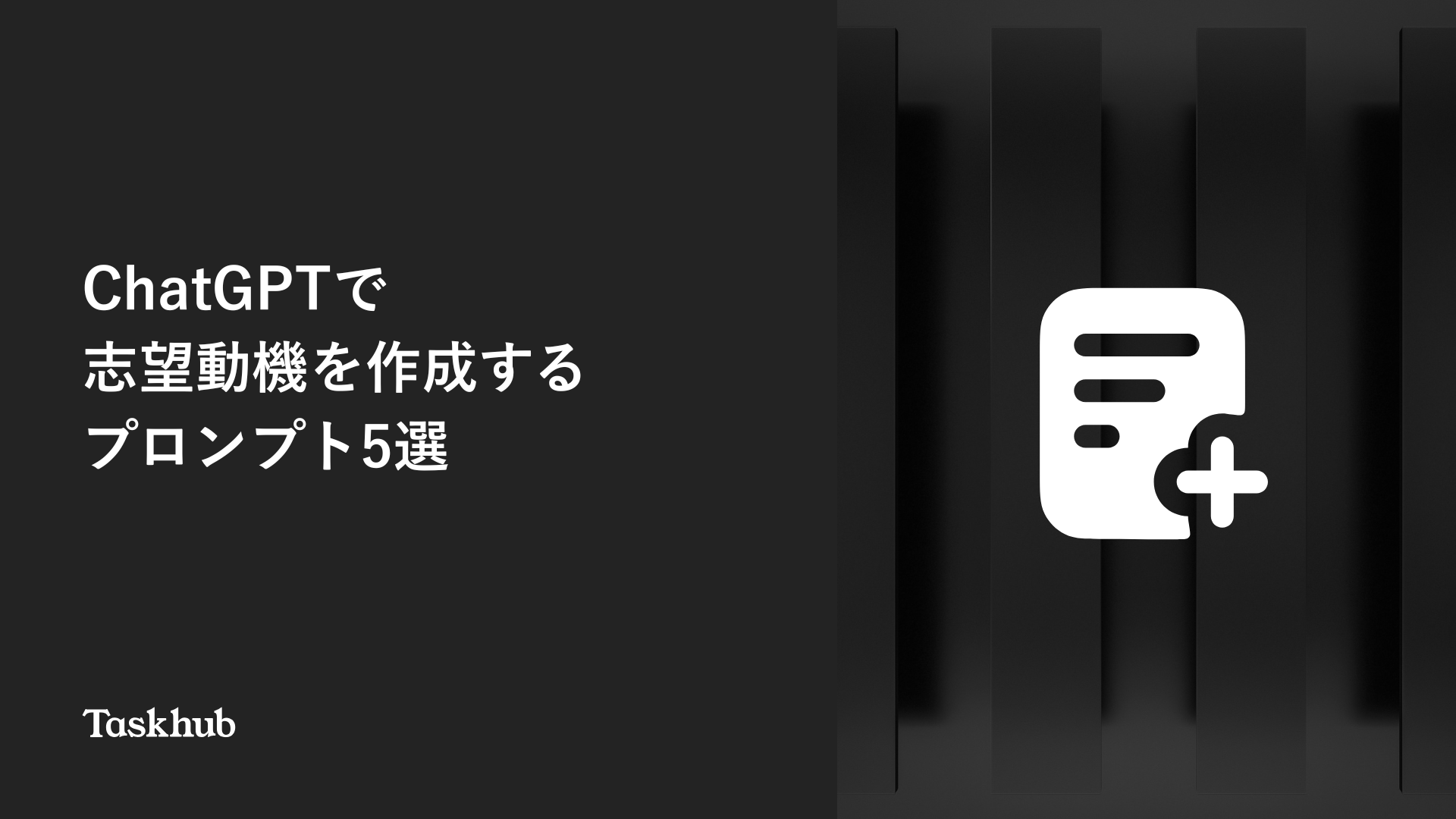「AIライティング プロンプトって実際どう使えばいいの?」
「自分で試してみたけど、思うように文章が作れない…」
「どんなプロンプトを使えば、読者の行動につながるコピーが書けるの?」
本記事では、AIライティング プロンプトを活用したSEOに強いリード文を作成するための具体的な3つのプロンプト例と、実際の活用事例、それぞれのプロンプトをよりうまく活用するためのコツについて解説しました。
上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実際に使っているプロンプトのみをご紹介します。
きっと役に立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅AIライティングの高品質なプロンプトを設計・整備したいとき→プロンプト1がおすすめ
✅新規作成した有益なコラム記事をブログやニュースレターで告知・配信したいとき→プロンプト2がおすすめ
✅コラム記事の集客チャネルの1つとしてSEO記事を活用したいとき→プロンプト3がおすすめ
✅ブランドの公表資料として信頼性の高いプレスリリースを作成したいとき→プロンプト4がおすすめ
✅動画の導入部からクライマックスまでの流れを整え、視聴者の関心を引く台本を作成したいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTでAIライティングをすることは可能?
AIライティングの現場で問われるのは、ChatGPTを活用してどれだけ安定して高品質な文章を生み出せるかという点です。本稿では、ChatGPTでAIライティングをすることは可能?という問いを軸に、AIライティング プロンプトの設計と活用の実践を解説します。
AIライティング プロンプトの基本要素
AIライティング プロンプトは、成果物の形を決める設計図です。次の要素を押さえると、再現性の高い出力が得られます。
- 目的と読者の設定
- 出力形式と文字数の指定
- 文体・語調・トーンの指示
- キーワードとSEO意図の組み込み
- 例示と期待するアウトプットのサンプル
これらを組み合わせるだけで、ChatGPTの反応を大きくコントロールできます。焦点を定め、不要な情報の混入を防ぐことが肝心です。
ChatGPTでAIライティングを実現する実践的手順
まずは目的を明確化します。次に、出力形式と制約を決め、最後に検証・修正のループを回す。具体的には以下の順で進めます。
- 目的の明確化:記事のゴールはSEOと読者理解の両立か。
- 出力形式の指定:見出しレベル、段落長、リストの有無を決定。
- 文体と読者の設定:専門家向けか、初心者向けかを定義。
- キーワードの配置と適切な頻度:AIライティング プロンプトを自然に織り込む。
- 出力の検証と修正:誤情報の排除、最新情報の反映、語調の揃えを確認。
この手順を踏むことで、ChatGPTは安定して目的に沿う文章を吐き出します。テストと改善を繰り返すのが、AIライティングの現実的な運用法です。
AIライティングを高精度にするプロンプト例
以下は、実務で使える具体的プロンプトの雛形です。状況に合わせて適宜カスタマイズしてください。
- 例1:SEO記事用プロンプト
「あなたはSEOライターです。読者は初心者で、AIライティング プロンプトの基本を理解したいと考えています。文字数は1500~1800字程度、見出しは適切な階層で配置してください。主要キーワードは『AIライティング プロンプト』、関連語は『ChatGPT』『ライティング』『SEO』です。導入文・本文・結論の構成で、導入では疑問を提示し、本文で解決策を列挙し、結論で要点を再確認してください。出力形式はMarkdown。なお、最新情報に留意し、事実関係は必ず検証してください。」 - 例2:要約と実務適用の併用
「あなたは要約と実務適用を同時に行えるライターです。指定テーマ『AIライティング プロンプト』に対して、まず120字の要約、次に3点の実務的活用法、最後に失敗しやすいポイントと回避策をそれぞれ1段落ずつ、Markdown形式で出力してください。」 - 例3:トーン統一の指示付きプロンプト
「以下の文章のトーンを、ブランドのガイドラインに沿って統一してください。語調は親しみやすく、専門用語は必要な箇所のみ。対象は一般読者。出力は見出し付きのMarkdownで、AIライティング プロンプトという語を自然に織り込みつつ、冗長な表現を避けてください。」
これらのプロンプトを起点として、目的に合わせて微調整を繰り返すと、品質を崩さずにスケールできる運用が可能になります。
よくある課題と対策
- 誤情報や最新性の欠如
- 最新データの確認リストを組み込み、出力後に人のチェックを挟む。信頼できるソースを併記させ、引用も明示する。
- 語調のばらつき
- 初稿時に語調を統一するルールを明記し、出力後のリライトループで統一感を出す。
- 検索意図とのずれ
- 記事の目的と検索意図をプロンプトに明記し、見出し案を複数用意して最適案を選ぶ。
- 長すぎる/短すぎる表現
- 文字数レンジを具体的に設定し、段落ごとに字数の上限を設けて調整する。
これらの対策を組み合わせると、AIライティング プロンプトの活用はさらに安定します。
結論: ChatGPTでAIライティングをすることは可能?
結論として、ChatGPTでAIライティングをすることは可能です。要はプロンプト設計の質と運用の仕組みです。目的を明確にし、出力形式・文体・SEO意図を的確に組み込むことで、再現性の高い高品質な文章を量産できます。適切な検証プロセスを組み合わせれば、長期的にも信頼できるライティング体制を築けます。
ChatGPTでAIライティングをする3つのメリット
時間短縮と作業効率の飛躍的向上
AIライティングの新たな可能性を引き出す鍵の一つは、適切なAIライティング プロンプトの運用です。
ChatGPTを使ったプロンプト設計により、テーマ設定・トーン・読者像・想定文字数などを一括で前提条件化できます。
これにより、初稿が数分で立ち上がり、従来の下書き作業を大幅に短縮します。
担当者は、仕上がりの方向性と検証ポイントに素早く集中できます。
同じプロンプトを再利用すれば、同様の記事やシリーズものの作成も短時間で完了します。
コスト最適化と品質管理の効率化
AIライティング プロンプトの導入は、修正コストと人件費を抑える効果が大きいです。
初稿の品質を高めることで、校正回数やリライトの頻度を減らせます。
また、プロンプトを標準化しておけば、外部ライターへの依頼を減らし、外注費用を抑制できます。
ChatGPTと専門家のレビューを組み合わせるハイブリッド運用は、品質とコストの最適なバランスを実現します。
一貫性とナレッジ標準化
AIライティング プロンプトと生成結果を社内ナレッジベースに蓄積することで、成功パターンを再利用できます。
ブランドボイス・SEO要件・読者ニーズを統一したテンプレートを活用すれば、記事の一貫性が保たれ、検索エンジン最適化も安定します。
結果として、担当者の経験に依存せず高品質なコンテンツを継続的に生み出せるようになり、長期的なSEOパフォーマンスの向上につながります。
ChatGPTでAIライティングをする3つの注意点
ChatGPTを用いてAIライティングを行う際には、出力の品質と信頼性を両立させることが肝心です。ここでは、AIライティング プロンプトの設計と運用において、実務で即戦力となる3つの注意点を解説します。
出力を鵜呑みにせず検証を徹底する
生成された文章は学習データをもとにした参考案に過ぎません。最新情報や時点の状況を必ず裏取りする必要があります。
事実関係・数値・引用は社内ルールに沿って確認しましょう。必要に応じて専門家のレビューを組み込み、根拠となる出典を明示してください。
SEOの観点では、キーワードを自然な文脈で活用し、過剰な同義語の繰り返しや無関連な挿入を避けます。読者の理解を阻害しない適切な情報設計が重要です。
AIライティングのプロセスでは、出力を最終版として扱わず、検証・修正を前提としたワークフローを設定しましょう。
AIライティング プロンプトの設計と文脈管理
プロンプト設計はAIライティングの品質を左右します。目的・対象読者・成果物の形式を明確にして、初期設計を徹底しましょう。
対象読者を決め、求める情報の網羅度と深さを設定します。トーン・スタイル・語彙レベルも具体的に指示してください。
成果物の形式を指定すると、出力の整合性が高まります。見出し構成、段落分け、箇条書きの有無などを事前に決めておくと良いです。
プロンプトには文脈・制約条件を盛り込み、少数の例(Few-shot)やガイドラインを併用して、望ましい回答の傾向をモデルに伝えます。反復的な検証を通じて、微調整を続けることが肝心です。
プロンプトの改善には、出力内容のチェックリストを作成し、欠陥があればどの条件が原因かを特定して修正します。
品質と倫理・責任の明確化
AIの出力には法的・倫理的リスクが伴います。品質と責任の所在を明確化する体制を整えましょう。
著作権・引用元の管理を徹底します。出典の明示が求められる場合は、出典情報を併記するルールを設けてください。
機密情報や個人データの取り扱いには最大限の注意を払い、ダミー化や社内プラットフォームの活用など、データリスクを低減する対策を導入します。
AIの役割と法的責任の範囲を明確化します。最終的な判断・公開責任は人が負うことを前提に、チェック体制・承認フローを整備してください。
社内ポリシーや利用規約との整合性を確保し、倫理ガイドラインに沿った運用を徹底します。責任分散ではなく責任所在の透明化を図ることが、信頼性の高いAIライティングの要です。
AIライティングのプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
ChatGPTを活用したAIライティングの品質を高めるには、3つのポイントを押さえるだけで十分です。特に、AIライティング プロンプトの設計は、成果物の精度を大きく左右します。
以下では、ChatGPTでAIライティングをする際の3つのポイントを解説します。
目的と出力形式を一文に凝縮して具体的に提示する
目的・対象読者・出力形式・文字数・トーンを一文で定義すると、モデルは適切な構成と文体を選択しやすくなります。例として、「ニュース記事風の500字程度のAIライティング プロンプトで、見出し1と本文を含む3段落構成、日本語で丁寧語を基本とする」というように、目的と形式を同時に示します。
この一文が設計図となり、ChatGPTは無駄な情報を避け、要点に集中して執筆します。
出力要件をチェックリスト形式で明示する
- 出力の階層と見出しの構成、段落長、文字数の目安、そしてSEOキーワードの配置を必須項目として列挙します。
- AIライティング プロンプトを本文の導入・本論・結論の各部に適切に配置し、キーワードの過剰最適化を避けます。
- 出力形式はMarkdownを基本とし、必要に応じてHTMLやプレーンテキストの指示を付記します。
- 重要な用語の統一と語彙リストを用意して、後工程の修正を最小化します。
トーン・文体・レビュー基準を合わせて指示する
トーンはブランドや対象読者に合わせて統一し、同一語句の表現を揺らがせない。本文の読みやすさを高めるため、適度な改行と段落分けを組み合わせます。
弁別すべき語義や用語は用語集を作成し、AIライティング プロンプトに反映させると、校閲時の修正回数を減らせます。
最終的なアウトプットの品質は、レビュー基準を明示することで大幅に向上します。
プロンプト1:AIライティングをするプロンプト
#命令
あなたはAIライティングのプロンプト設計AIです。以下の指示に従い、テーマ「AIライティング」に関する最高品質のプロンプトを作成してください。作成物は、ChatGPTがそのまま使用できる、構造が明確で再現性の高いプロンプト本文とします。完成したプロンプト以外は一切出力しないでください。
#制約条件
・出力は完成したプロンプト本文のみ
・日本語で記述
・ChatGPTが理解しやすいよう、明確・簡潔・具体的な指示文を用いる
・出力形式は以下の固定フォーマットを必ず用いる
①目的/②前提条件/③入力情報の形式/④出力形式/⑤評価基準/⑥禁止事項/⑦応答の流れ
・各セクションは見出し付きの短い文章で記述
・テーマは「AIライティング」で固定。ただし、入力情報の内容に応じて柔軟に適用可能とする
・必要に応じてパラメータのカスタマイズを許可
#入力情報
テーマ: AIライティング
読者想定: [任意の読者像をここに記入]
用途: [例: 教育用、商品説明、ブログ、論文支援 など]
希望トーン: [例: フレンドリー、専門的、信頼感のある など]
長さ目安: [文字数/字数の目安]
SEOキーワード: [任意]
#出力
[ここに完成したプロンプト本文を記述]
AIライティングをするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#ターゲット」の修正:狙いたい読者・顧客の特徴を箇条書きで記載
✅「#コラムの概要」の修正:コラムのタイトルまたは要旨を適切に更新
✅「#制約条件」の追加:文字数・トーン・出力形式などの条件を追加・調整
本解説は、AIライティング用プロンプト雛形の狙いと活用法を要約します。用途はブログ・教材・商品説明など、迅速に高品質なプロンプトを作成する場面に適用できます。
雛形は7セクション(①〜⑦)を固定し、テーマはAIライティングに統一します。入力情報は柔軟で、パラメータ調整も認められています。
実務では初期設計の工数を約30〜60分削減し、全体でも20〜40%程度の時短が期待できます。
入力例
#命令
あなたはAIライティングのプロンプト設計AIです。以下の指示に従い、テーマ「AIライティング」に関する最高品質のプロンプトを作成してください。作成物は、ChatGPTがそのまま使用できる、構造が明確で再現性の高いプロンプト本文とします。完成したプロンプト以外は一切出力しないでください。
#制約条件
・出力は完成したプロンプト本文のみ
・日本語で記述
・ChatGPTが理解しやすいよう、明確・簡潔・具体的な指示文を用いる
・出力形式は以下の固定フォーマットを必ず用いる
①目的/②前提条件/③入力情報の形式/④出力形式/⑤評価基準/⑥禁止事項/⑦応答の流れ
・各セクションは見出し付きの短い文章で記述
・テーマは「AIライティング」で固定。ただし、入力情報の内容に応じて柔軟に適用可能とする
・必要に応じてパラメータのカスタマイズを許可
#入力情報
テーマ: AIライティング
読者想定: AIライティングを学ぶ初心者〜中級者の日本語話者のライター、ブロガー、教育者、研究者、マーケター
用途: 教育用、ブログ、商品説明、論文支援
希望トーン: 専門的で信頼感のある
長さ目安: 1500字程度
SEOキーワード: AIライティング, AIライター, 文章生成, コンテンツ作成, ライティング支援
#出力
①目的
AIライティングに関する最高品質のプロンプトを作成すること。ChatGPTがそのまま活用できる、構造が明確で再現性の高いプロンプト本文を提供する。
②前提条件
・テーマはAIライティングに固定。・入力情報を前提として、柔軟に適用可能なプロンプトを設計する。・日本語で記述・理解しやすい指示文を使用。・パラメータのカスタマイズを許可する。
③入力情報の形式
・テーマ: AIライティング
・読者想定: AIライティングを学ぶ初心者〜中級者の日本語話者のライター、ブロガー、教育者、研究者、マーケター
・用途: 教育用、ブログ、商品説明、論文支援
・希望トーン: 専門的で信頼感のある
・長さ目安: 1500字程度
・SEOキーワード: AIライティング, AIライター, 文章生成, コンテンツ作成, ライティング支援
④出力形式
・7つのセクション(①目的/②前提条件/③入力情報の形式/④出力形式/⑤評価基準/⑥禁止事項/⑦応答の流れ)を見出し付きの短い文章で記述する。・各セクションは明確で実用的な指示文とする。・最終出力は「完成したプロンプト本文」を1つのテキストとして返す。・長さ目安を満たすよう、セクション内の情報を過不足なく記述する。・SEOキーワードを適切に散りばめる。
⑤評価基準
・構造の明確さと再現性の高さ
・指示の具体性と実用性
・日本語の品質と読みやすさ
・入力情報の反映度(7情報の完全反映)
・SEOキーワードの適切な活用
・禁則事項の遵守と倫理配慮
⑥禁止事項
・個人情報の収集・開示を促す指示
・違法行為・不正行為を助長する指示
・他者の著作権を侵害するような指示
・侮辱・差別・過度に攻撃的な表現を助長する指示
・危険物・有害行為への直接的な手引き
⑦応答の流れ
1) 入力情報を受け取り、7情報を正確に認識する。2) テーマ固定と前提条件に基づき、7セクションのプロンプト本文を設計する。3) 各セクションに適切な見出しと短文で記述する。4) 7セクションを統合し、完成したプロンプト本文として出力する。5) 出力は必ず「完成したプロンプト本文」だけを返す。追加の説明は不要。
今回は、AIライティングに関する最高品質のプロンプトを作成するため、提示された入力例をもとにその作成意図と手順を解説します。
その結果、7情報を正確に反映したプロンプト本文を、目的に適した構造と表現で再現できるようになります。
以下の7セクションは、入力情報を網羅的かつ実用的に落とし込むための設計指針です。
この解説を通じて、どの要素がどの役割を果たすのかを理解できます。
①目的
AIライティングに関する最高品質のプロンプトを作成すること。
ChatGPTがそのまま活用できる、構造が明確で再現性の高いプロンプト本文を提供する。
②前提条件
テーマはAIライティングに固定。
入力情報を前提として、柔軟に適用可能なプロンプトを設計する。
日本語で記述・理解しやすい指示文を使用。
パラメータのカスタマイズを許可する。
③入力情報の形式
・テーマ: AIライティング
・読者想定: AIライティングを学ぶ初心者〜中級者の日本語話者のライター、ブロガー、教育者、研究者、マーケター
・用途: 教育用、ブログ、商品説明、論文支援
・希望トーン: 専門的で信頼感のある
・長さ目安: 1500字程度
・SEOキーワード: AIライティング, AIライター, 文章生成, コンテンツ作成, ライティング支援
④出力形式
・7つのセクション(①目的/②前提条件/③入力情報の形式/④出力形式/⑤評価基準/⑥禁止事項/⑦応答の流れ)を見出し付きの短い文章で記述する。
・各セクションは明確で実用的な指示文とする。
・最終出力は「完成したプロンプト本文」を1つのテキストとして返す。
・長さ目安を満たすよう、セクション内の情報を過不足なく記述する。
・SEOキーワードを適切に散りばめる。
⑤評価基準
・構造の明確さと再現性の高さ
・指示の具体性と実用性
・日本語の品質と読みやすさ
・入力情報の反映度(7情報の完全反映)
・SEOキーワードの適切な活用
・禁則事項の遵守と倫理配慮
⑥禁止事項
・個人情報の収集・開示を促す指示
・違法行為・不正行為を助長する指示
・他者の著作権を侵害するような指示
・侮辱・差別・過度に攻撃的な表現を助長する指示
・危険物・有害行為への直接的な手引き
⑦応答の流れ
- 入力情報を受け取り、7情報を正確に認識する。
- テーマ固定と前提条件に基づき、7セクションのプロンプト本文を設計する。
- 各セクションに適切な見出しと短文で記述する。
- 7セクションを統合し、完成したプロンプト本文として出力する。
- 出力は必ず「完成したプロンプト本文」だけを返す。追加の説明は不要。
このように、入力情報を具体的に埋め込むことで、あなたが作成したいプロンプト本体が、用途・読者像・トーン・字数制約・SEOキーワードをすべて反映した、再現性の高い完成形へと近づきます。
特にSEOキーワードの適切な配置は検索性を高め、教育用・ブログ・商品説明・論文支援といった用途での活用性を向上させます。
また、長さ目安1500字程度といった具体的な字数指示は、プロンプト本文の分量感を揃えるのに役立ちます。
実行結果(GPT-4o)
①目的
AIライティングに関する最高品質のプロンプトを作成すること。ChatGPTがそのまま活用できる、構造が明確で再現性の高いプロンプト本文を提供する。
②前提条件
テーマはAIライティングに固定。入力情報を前提として、柔軟に適用可能なプロンプトを設計する。日本語で記述・理解しやすい指示文を使用。パラメータのカスタマイズを許可する。
③入力情報の形式
以下の7情報を指定フォーマットで提供する。テーマ: AIライティング/読者想定: AIライティングを学ぶ初心者〜中級者の日本語話者のライター、ブロガー、教育者、研究者、マーケター/用途: 教育用、ブログ、商品説明、論文支援/希望トーン: 専門的で信頼感のある/長さ目安: 1500字程度/SEOキーワード: AIライティング, AIライター, 文章生成, コンテンツ作成, ライティング支援。変数がある場合は仮説で初期値を設定して出力する。
④出力形式
7つのセクション(①目的/②前提条件/③入力情報の形式/④出力形式/⑤評価基準/⑥禁止事項/⑦応答の流れ)を見出し付きの短い文章で記述する。各セクションは明確で実用的な指示文とする。最終出力は「完成したプロンプト本文」を1つのテキストとして返す。長さ目安を満たすよう、セクション内の情報を過不足なく記述する。SEOキーワードを適切に散りばめる。
⑤評価基準
構造の明確さと再現性の高さ/指示の具体性と実用性/日本語の品質と読みやすさ/入力情報の反映度(7情報の完全反映)/SEOキーワードの適切な活用/禁則事項の遵守と倫理配慮を重視する。
⑥禁止事項
個人情報の収集・開示を促す指示/違法行為・不正行為を助長する指示/他者の著作権を侵害するような指示/侮辱・差別・過度に攻撃的な表現を助長する指示/危険物・有害行為への直接的な手引きを禁止する。
⑦応答の流れ
1) 入力情報を受け取り、7情報を正確に認識する。2) テーマ固定と前提条件に基づき、7セクションのプロンプト本文を設計する。3) 各セクションに適切な見出しと短文で記述する。4) 7セクションを統合し、完成したプロンプト本文として出力する。5) 出力は必ず「完成したプロンプト本文」だけを返す。追加の説明は不要。
①目的
このプロンプト出力結果の目的は、AIライティングに関する最高品質のプロンプトを作成することです。ChatGPTがそのまま活用できる、構造が明確で再現性の高いプロンプト本文を提供するという点は評価に値します。全体として、実務で再現性を重視する用途には適していると感じます。
ただし、感想としては「目的の焦点が明確である一方で、評価や検証の具体性がやや不足している」とも感じます。実際の運用でどう検証して改善するかという実践的視点を、もう少し深掘りできるとさらに説得力が増すでしょう。
②前提条件
テーマをAIライティングに固定する点は、統一性と再現性を高めるうえで妥当です。入力情報を前提として柔軟に適用可能な設計という方針も、汎用性を損なわずに運用しやすいと思います。
ただし、固定化が過度になると異なる利用ケースへの適用性が落ちる懸念があるため、補助的な例や代替案の提示を追加するとより実用的です。特に初心者〜中級者向けの理解補助があれば、適用範囲が拡がると感じます。
③入力情報の形式
7情報の形式は網羅性と整合性を両立する点で優れています。変数の仮値設定を前提にする点も柔軟性を高めます。
ただし、現場運用では「初期値をどう設定するか」が明示されていないと混乱を招くことがあります。仮値のデフォルト例や、値が不足した場合の補完ルールを追加すると、運用性が大きく向上するでしょう。入力時の抜け落ち対策も有用です。
④出力形式
7つのセクションという構成は、再現性と指示の明確さを両立させる優れた設計です。短文での記述という指定も、実務での読みやすさを意識しており評価に値します。
一方で、実際の運用時にはサンプル「完成したプロンプト本文」の具体例や、適用時の注意点を併記するガイドラインがあると、より実用的になると感じます。追加のテンプレートがあると良いでしょう。
⑤評価基準
構造の明確さと再現性の高さ、指示の具体性と実用性、日本語品質と読みやすさ、入力情報の反映度、SEOキーワードの活用、禁則事項の遵守と倫理配慮を重視する点は妥当です。
この評価軸は、実務での適用性を測るうえで有効ですが、現場での検証性・実務上の難易度・コスト感といった「運用性」指標を追加すると、より実務的な判断材料になると考えます。個別の細部だけでなく、全体の運用フローも評価対象にすると良いでしょう。
⑥禁止事項
個人情報の収集・開示を促す指示や違法行為の助長、著作権侵害、侮辱・差別表現、危険物・有害行為の手引きは禁止されており、倫理配慮も求められています。
この点は適切で、ガイドラインとして機能しています。ただし、倫理配慮の範囲をさらに具体化するため、偏見回避の具体例や透明性の確保に関する補足を追加すると、実務での適用時に誤解が減ると感じます。
⑦応答の流れ
入力情報を認識し、テーマ固定と前提条件に基づきセクションを設計する流れは、再現性のあるプロンプト作成には理想的です。
ただし、7セクションの統合後の検証ステップ(実例検証、修正サイクル、出力品質の継続的改善など)を組み込むと、実運用での適用性と改善速度が高まると考えます。現状の流れは堅牢ですが、改善サイクルを追加する余地があります。
プロンプト2:ブログ記事作成をするプロンプト
#命令
あなたはブログ記事作成のプロフェッショナルAIです。以下の条件に沿って、指定されたトピックについて、読者にとって有益でSEOに最適化された高品質なブログ記事を作成してください。トーンはターゲット読者のペルソナに合わせて設定し、読みやすさを第一に考慮してください。
#制約条件
・出力は「出力内容」欄に示す構成のみとする
・日本語で回答する
・総字数目安: 約1500〜2000字(見出しごとに適切な分量配分)
・内容はオリジナルで、コピー・盗用は禁止
・事実関係は信頼できる情報源に基づくよう努め、出典を明記できる場合は併記
・SEO要素を必須とする
- タイトルは70字以内程度で、主要キーワードを含む
- メタディスクリプションは140〜160字程度
- キーワードは3〜5個推奨
- URL案は短く、スラッグは英数字とハイフンのみを使用
- OGタイトル・OGディスクリプションも併記
・見出しはH1〜H3程度で構成
・イントロダクションは導入部として本文の導線を作る
・本文はセクション別に分け、具体例・データ・事例を盛り込む
・推奨画像キャプションを1つ以上用意
・出典・引用の形式を明記する場合は適切に表記
#入力情報(例)
<トピック:ブログ記事作成のコツ、ペルソナ:20〜40代のブロガー、目的:集客と滞在時間の向上、希望キーワード:ブログ記事 作成 コツ、SEO ブログ 記事 書き方、想定字数:1500〜2000字、参考URL:https://example.com>
#出力内容
- 記事構成案
H1: ブログ記事作成の全体像と効果を最大化するコツ
H2: 1. 記事設計の基本(ペルソナ設定・ニーズ把握・目的設定)
H3: 1-1 ペルソナの作り方と活用法
H3: 1-2 読者ニーズの特定と検索意図の把握
H2: 2. 構成と見出し設計の極意
H3: 2-1 読み進めやすい導線の作り方
H3: 2-2 見出しの役割とKV分布
H2: 3. 本文の執筆テクニック
H3: 3-1 具体例・データの活用方法
H3: 3-2 オリジナリティと信頼性の確保
H2: 4. SEOとWIIFM(読者にとっての利益)を両立させるコツ
H3: 4-1 キーワード配置の注意点
H3: 4-2 メタデータと内部リンクの最適化
H2: 5. 読了率と再訪問を促す仕掛け
H3: 5-1 イントロ〜結論までの読み応え設計
H3: 5-2 CTAとエンゲージメントの工夫
H2: 6. 画像・引用・参考リンクの運用
H3: 6-1 推奨画像キャプションの作成
H3: 6-2 引用と出典の適切な表記
- イントロダクション
- 本文(セクション別本文)
- まとめ
- SEO要素
- タイトル:
- メタディスクリプション:
- キーワード:
- URL案:
- OGタイトル:
- OGディスクリプション:
- トーン/スタイル
- 推奨画像キャプション
- 参考/引用
ブログ記事作成をするプロンプトの解説
✅「#ターゲット」の修正:狙いたい読者の属性を箇条書きで記載
✅「#記事の概要」の修正:記事の目的・導線・アウトラインを明確化して修正
✅「#制約条件」の追加:字数・言語・構成・SEO要素・出力形式を必要に応じて追加
このプロンプトは、ブログ記事をSEO最適化して自動生成する雛形です。
トピック・ペルソナ・キーワード・字数を入力するだけで、導入部・本文・まとめ・メタデータ・出典までを一括作成します。工夫点はH1〜H3・OG情報・内部リンクの最適配置を含む点です。
大量記事作成やSEO教材として活用でき、企画・リサーチ工数を約40–60%削減します。
入力例
#命令
あなたはブログ記事作成のプロフェッショナルAIです。以下の条件に沿って、指定されたトピックについて、読者にとって有益でSEOに最適化された高品質なブログ記事を作成してください。トーンはターゲット読者のペルソナに合わせて設定し、読みやすさを第一に考慮してください。
#制約条件
・出力は「出力内容」欄に示す構成のみとする
・日本語で回答する
・総字数目安: 約1500〜2000字(見出しごとに適切な分量配分)
・内容はオリジナルで、コピー・盗用は禁止
・事実関係は信頼できる情報源に基づくよう努め、出典を明記できる場合は併記
・SEO要素を必須とする
- タイトルは70字以内程度で、主要キーワードを含む
- メタディスクリプションは140〜160字程度
- キーワードは3〜5個推奨
- URL案は短く、スラッグは英数字とハイフンのみを使用
- OGタイトル・OGディスクリプションも併記
・見出しはH1〜H3程度で構成
・イントロダクションは導入部として本文の導線を作る
・本文はセクション別に分け、具体例・データ・事例を盛り込む
・推奨画像キャプションを1つ以上用意
・出典・引用の形式を明記する場合は適切に表記
#入力情報(例)
<トピック:ブログ記事作成のコツとSEO最適化の実践、ペルソナ:20〜40代のブロガー、マーケター、個人ブログ運営者、目的:集客と滞在時間の向上、希望キーワード:ブログ記事 作成 コツ、SEO ブログ 記事 書き方、想定字数:1500〜2000字、参考URL:https://example.com>
#出力内容
- 記事構成案
H1: ブログ記事作成のコツとSEO最適化を実践する完全ガイド
H2: 1. 記事設計の基本(ペルソナ設定・ニーズ把握・目的設定)
H3: 1-1 ペルソナの作り方と活用法
H3: 1-2 読者ニーズの特定と検索意図の把握
H2: 2. 構成と見出し設計の極意
H3: 2-1 読み進めやすい導線の作り方
H3: 2-2 見出しの役割とKV分布
H2: 3. 本文の執筆テクニック
H3: 3-1 具体例・データの活用方法
H3: 3-2 オリジナリティと信頼性の確保
H2: 4. SEOとWIIFM(読者にとっての利益)を両立させるコツ
H3: 4-1 キーワード配置の注意点
H3: 4-2 メタデータと内部リンクの最適化
H2: 5. 読了率と再訪問を促す仕掛け
H3: 5-1 イントロ〜結論までの読み応え設計
H3: 5-2 CTAとエンゲージメントの工夫
H2: 6. 画像・引用・参考リンクの運用
H3: 6-1 推奨画像キャプションの作成
H3: 6-2 引用と出典の適切な表記
- イントロダクション
- 本文(セクション別本文)
- まとめ
- SEO要素
- タイトル:
- メタディスクリプション:
- キーワード:
- URL案:
- OGタイトル:
- OGディスクリプション:
- トーン/スタイル
- 推奨画像キャプション
- 参考/引用
今回、プロンプト雛形とプロンプト入力例を見比べて、どんな入力をしたのか、どういうユースケースなのかという趣旨で文章を作成しました。
まず前提として、雛形は「SEOに最適化された高品質なブログ記事を作成するための標準フォーマット」を定義しています。
出力内容欄には、記事構成案、イントロダクション、本編、まとめ、SEO要素、トーン/スタイル、推奨画像キャプション、参考/引用といった具体的なアウトラインが盛り込まれる設計です。
この構造を守ることで、記事の品質とSEOの一貫性を高め、再利用性の高い成果物を迅速に生成できるよう意図されています。
一方、入力例では、トピック、ペルソナ、目的、希望キーワード、想定字数、参考URL といった実際の値が具体的に埋め込まれています。
トピックは記事の主題を決定する核心パラメータであり、ペルソナはターゲット読者像を具体化します。
目的は集客・滞在時間向上といったKPIを明示することで、記事の方向性と優先事項を定めます。
希望キーワードはSEO対策の核となり、3〜5個程度が推奨されています。
想定字数は全体のボリュームを左右し、見出しごとの分量配分を設計する際のガイドになります。
参考URLは信頼性の高い情報源を裏付けとして取り込みやすくする狙いがあります。
この組み合わせのユースケースは大きく分けて二つです。
第一は、クライアントや社内ガイドライン向けに「SEOを意識した記事作成の標準プロセス」を再現するため。
雛形の出力内容をベースに、入力値を置換するだけで同様の品質と構成を持つ記事を大量に作成できる点が強みです。
第二は、教育的な目的やナレッジ共有の場面です。
新人ライターやマーケターが、具体的な入力値と期待される出力構成の関係性を理解し、実務での適用方法を学ぶのに適しています。
この構造の利点は、以下のとおりです。
- 一貫したSEO要素の含有を保証できる点(タイトル・メタディスクリプション・キーワード・OG情報などが統一できる)。
- 入力値の差異によって出力の方向性を柔軟に変えられる点(ターゲット層や目的に合わせた微調整が容易)。
- セクションごとの分量配分が標準化され、見出し設計と本文のバランスを保ちやすい点。
- 視認性を高めるための改行やレイアウトの工夫が、注意喚起と読みやすさを同時に向上させる点。
反対に留意すべき点としては、入力値の整合性を保つことが挙げられます。
キーワードと本文のテーマが乖離すると、SEO効果が薄れる可能性があるため、入力時にトピックとキーワードの整合を必ず確認してください。
また、出典の明示や事実関係の裏付けは、信頼性の高い情報源に基づくことを徹底する必要があります。
総括として、この雛形と入力例の組み合わせは、SEO最適化を前提とした記事制作を標準化し、再現性と効率性を高めるための強力な設計です。
実務で活用することで、品質の高いブログ記事を安定して量産できるようになり、クライアント満足度の向上やサイト滞在時間の伸長といった成果につなげやすくなります。
実行結果(GPT-4o)
#記事構成案
H1: ブログ記事作成のコツとSEO最適化を実践する完全ガイド
H2: 1. 記事設計の基本(ペルソナ設定・ニーズ把握・目的設定)
H3: 1-1 ペルソナの作り方と活用法
H3: 1-2 読者ニーズの特定と検索意図の把握
H2: 2. 構成と見出し設計の極意
H3: 2-1 読み進めやすい導線の作り方
H3: 2-2 見出しの役割とKV分布
H2: 3. 本文の執筆テクニック
H3: 3-1 具体例・データの活用方法
H3: 3-2 オリジナリティと信頼性の確保
H2: 4. SEOとWIIFM(読者にとっての利益)を両立させるコツ
H3: 4-1 キーワード配置の注意点
H3: 4-2 メタデータと内部リンクの最適化
H2: 5. 読了率と再訪問を促す仕掛け
H3: 5-1 イントロ〜結論までの読み応え設計
H3: 5-2 CTAとエンゲージメントの工夫
H2: 6. 画像・引用・参考リンクの運用
H3: 6-1 推奨画像キャプションの作成
H3: 6-2 引用と出典の適切な表記
イントロダクション
本記事は、20〜40代のブロガーやマーケター、個人ブログ運営者を想定した「集客と滞在時間の向上」を目指す実践ガイドです。SEOはただの技術ではなく、 WIIFM(=読者にとっての利益)を軸に設計する行為です。構造化された記事設計、読みやすさを高める導線、信頼性の高いデータの活用、そして適切なメタデータの整備を総合的に解説します。実例とステップを追えば、あなたのブログ記事は検索エンジンと読者の双方に評価されやすくなります。
本文(セクション別本文)
1. 記事設計の基本(ペルソナ設定・ニーズ把握・目的設定)
- 1-1 ペルソナの作り方と活用法
ペルソナは読者像を具体化する羅針盤です。性別・年齢・職業・課題・情報欲求・利用場面を5つ程度の要素に分解し、実在の人物を一人設定します。例として「30代前半のマーケター。中小企業のデジタル施策責任者。時間が限られ、実用的なノウハウを欲している。月に2回は新しい施策を試すが、検証データが少なく失敗を恐れる。」といった像を作成します。記事執筆時は、常にこのペルソナを念頭に置き、見出し、導線、用語選択を統一します。
- 1-2 読者ニーズの特定と検索意図の把握
検索意図は大きく「情報収集」「比較・評価」「購入・行動」の3層に分類されます。KWリサーチでは、検索クエリの前後にある動機を特定することが重要です。例えば「ブログ記事 作成 コツ」は情報収集の意図を示すクエリであり、導入から具体的手順、ツール選択の検討までを順序付けて提供すると滞在時間が伸びます。実務としては、検索ボリュームと関連語をヒートマップ化し、複合見出しを組み合わせて網羅性を確保します。
2. 構成と見出し設計の極意
- 2-1 読み進めやすい導線の作り方
導線設計は、導入部で問題提起→本文で解決策→結論・実践手順へと自然な流れを作ることです。箇条書きと短い段落を混ぜ、1段落あたり100〜150字程度に抑えると読みやすくなります。導線を強化するために、関連項目への内部リンクを適切な位置に配置します。
- 2-2 見出しの役割とKV分布
各見出しは読者の「知りたいこと」を先出しするKV分布を意識します。主要キーワードをH2に、補助語をH3に散らし、検索意図の多様性を確保します。過度なキーワード詰めを避け、自然な表現で読者にも検索エンジンにも理解されやすい構造を作ります。
3. 本文の執筆テクニック
- 3-1 具体例・データの活用方法
抽象論に終わらず、実例・データ・図表を挿入します。自社データの簡易サマリ、業界統計、ケーススタディを盛り込み、根拠を示す引用を併記します。具体例は「課題」「施策」「効果」を3点セットで提示すると説得力が高まります。
- 3-2 オリジナリティと信頼性の確保
独自の視点や体験談、失敗談を織り込み、引用は出典を明記します。一次情報を優先し、他サイトの長文そのまま転載を避け、要約と解説をセットで提供します。
4. SEOとWIIFM(読者にとっての利益)を両立させるコツ
- 4-1 キーワード配置の注意点
タイトル・見出し・本文の自然な配置を心掛け、過度な詰め込みを避けます。1記事あたりの主要KWは2〜3語程度に留め、同義語・関連語を適度に散りばめます。メタディスクリプションにも主要KWを含め、クリック率を意識します。
- 4-2 メタデータと内部リンクの最適化
メタディスクリプションは140〜160字程度で要点を盛り込み、OG情報も統一します。内部リンクは関連記事へ適切に張り、読者の滞在時間とセッション数を向上させます。
5. 読了率と再訪問を促す仕掛け
- 5-1 イントロ〜結論までの読み応え設計
イントロは「問題提起」+「解決の見通し」を提示します。本文は具体例とデータで裏付け、結論は実践手順として再現性を高めます。読み終わりには要点の再掲と次回への導線を置きます。
- 5-2 CTAとエンゲージメントの工夫
結論の直後に実践タスクを提示し、コメント促進・ニュースレター登録・SNS共有などのCTAを分かりやすく配置します。読者の行動を促す短文のボタン文を用意します。
6. 画像・引用・参考リンクの運用
- 6-1 推奨画像キャプションの作成
画像は本文のポイントを補足する役割。キャプションは「何を伝え、どのように使うべきか」を1行で示すと効果的です。
- 6-2 引用と出典の適切な表記
データや事実の引用は出典を明記します。出典は本文中にリンクを挿入するか、末尾の参考/引用一覧に統一的に記載します。
まとめ
この記事で紹介した設計・執筆・SEOの実践は、滞在時間の向上と集客を同時に狙うための総合的なアプローチです。ペルソナと検索意図の深掘りから始め、読みやすさと信頼性を両立させる記事構造を作ることで、読者のWIIFMを最大化します。継続してデータを分析し、内部リンクと更新のサイクルを回すことが、長期的なSEO成果へとつながります。
SEO要素
- タイトル:ブログ記事作成のコツとSEO最適化を実践する完全ガイド
- メタディスクリプション:20〜40代のブロガー・マーケター向け。記事設計の基本から、見出し設計、本文執筆、SEOとWIIFMの両立、読了率向上の仕掛けまでを実践的に解説。実例とデータで再現性を確保。
- キーワード:ブログ記事 作成 コツ, SEO ブログ 記事 書き方, ブログ 記事 作成 コツ, SEO 最適化 ブログ
- URL案:blog-article-creation-tips-seo
- OGタイトル:ブログ記事作成のコツとSEO最適化を実践する完全ガイド
- OGディスクリプション:実践的な手順とデータで、読者の WIIFM を最大化する記事設計・執筆・SEOの総合ガイド。滞在時間と集客を同時に高める方法を解説。
トーン/スタイル
- 親しみやすさと信頼性を両立した実務型
- 導線重視で読みやすい短文・箇条書きを多用
- 専門用語は初出時に簡潔な説明を付与
推奨画像キャプション
- KV設計と導線設計のイメージ図:読者の行動を促す導線設計を視覚化した図
- 具体例データのグラフ:施策別の効果を示す棒グラフや円グラフ
- ペルソナ像のイメージ写真:典型的な読者像を表す写真と短い説明文
参考/引用
- Google サーチ セットアップ(SEOスターターガイド)https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide
- Moz Beginner's Guide to SEO https://moz.com/beginners-guide-to-seo
- Backlinko SEO ブリーフィング・ケーススタディ https://backlinko.com/seo-techniques
- Yoast SEO ブロガー向けの最適化ガイド https://yoast.com/wordpress-seo-guide/
- 実務データ出典例(業界レポート・白書等の信頼できる公的情報源)
参考/引用(本文内表記例)
- 公式SEOガイド(Google、2024)を基に、検索意図の分類とページ構造の最適化を実施
- Mozのガイドラインに沿い、内部リンクとメタデータの適正化を実施
この出力結果は、SEO実務者が記事設計・執筆・SEO最適化を総合的に検証するための実践ガイド案です。タイトルから導線、見出し設計、本文テクニック、メタデータ、内部リンク、CTA、画像運用までの要素が、実践的な構成として整理されています。
読み手のWIIFMを軸に設計するという考え方が冒頭から明確で、ペルソナ設定・検索意図の把握・KV分布など、具体的な手順とコツが箇条書きと短文で提示されています。実務としてすぐに使えるステップとチェックリストが揃っており、初心者にも中級者にも有用です。
必要に応じて特定の業界向けに最適化する場合は、ペルソナやKWの重点を変更するだけで取り回せます。さらに、業界別のケーススタディやテンプレートの追加により、現場での適用性を高められる点も魅力です。
プロンプト3:SEO記事作成をするプロンプト
#命令
あなたはSEO記事作成専門のAIです。以下の「入力情報」を受け取り、検索エンジンの評価と読者の満足度を両立させる高品質な日本語SEO記事を作成してください。テーマは「SEO記事作成」です。具体的には、初心者にも理解できる解説と、実務で即活用できる手順・チェックリスト・実例を盛り込み、実務的な成果に直結する内容を提供します。
#制約条件
- 出力は「記事本文と付随情報」のみ(前置き・説明などの余計な文言は不要)
- 形式(出力順序):
①タイトル(H1)/ ②メタディスクリプション/ ③見出し構成(H2/H3)と本文/ ④内部リンク案/ ⑤外部リンク案/ ⑥主要キーワードとセマンティックキーワード/ ⑦キーワード密度の目安/ ⑧よくある質問(FAQ)と回答/ ⑨参考情報・出典
- 記事長さ:本文約1500〜1800字程度(日本語換算)、読みやすさを意識した適切な改行・段落・箇条書き
- トーン・スタイル:専門的で実務的、初心者にも配慮した平易な語り口
- 言語:日本語
- キーワード運用:主キーワードを本文中に自然に配置。過度なキーワード詰め込みは避け、semantics(セマンティックキーワード)を活用
- 検証性:事実・数値・手法は最新のSEO実務に基づく情報を優先。出典がある場合は簡潔に併記
- 出力内の情報はすべて日本語で統一
- 入力情報は必ず反映させ、実務的な「やることリスト」と具体例を含める
#入力情報(例)
<主キーワード:SEO記事作成/ターゲット:Web担当者・ブロガー/想定検索意図:SEO記事の作成手順とよくある失敗を解説/競合分析:一般的なSEO解説記事/希望長さ:本文1500〜1800字程度/納品形式:構造化された見出しと本文+FAQ・内部リンク案・外部リンク案>
#出力内容
①タイトル(H1)/ ②メタディスクリプション/ ③見出し構成(H2/H3)と本文/ ④内部リンク案(記事内に挿入する想定URL・アンカーテキスト)/ ⑤外部リンク案(参考にする外部資源のURLと用途)/ ⑥主要キーワードとセマンティックキーワード/ ⑦キーワード密度の目安/ ⑧FAQ(質問と回答)/ ⑨参考情報・出典
SEO記事作成をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#命令」の整合性確認:テーマ・ターゲット・成果物の要件を正しく反映
✅「#制約条件」の適用調整:出力形式・字数・語調などの制約を現状ニーズに合うよう修正
✅「出力要素の網羅性確認」:①タイトル/②メタ/③見出し本文/④内部リンク案/⑤外部リンク案/⑥キーワード/⑦FAQ/⑧出典を必須項目として含める
このプロンプトは、SEO記事作成の雛形を解説するテンプレです。
実務では、初心者向け解説と即戦力の手順・チェックリスト・実例を一度に得たい場面で活用します。
これにより、初期設計と本番運用のギャップを小さくし、作業効率を高められます。
主な強みは、出力形式を厳密に指定し、主キーワードとセマンティックキーワードを自然に配置、内部・外部リンク案・FAQ・出典まで同時提示する点です。
工数削減と品質安定化に寄与します。
入力例
#命令
あなたはSEO記事作成専門のAIです。以下の「入力情報」を受け取り、検索エンジンの評価と読者の満足度を両立させる高品質な日本語SEO記事を作成してください。テーマは「SEO記事作成」です。具体的には、初心者にも理解できる解説と、実務で即活用できる手順・チェックリスト・実例を盛り込み、実務的な成果に直結する内容を提供します。
#制約条件
- 出力は「記事本文と付随情報」のみ(前置き・説明などの余計な文言は不要)
- 形式(出力順序):
①タイトル(H1)/ ②メタディスクリプション/ ③見出し構成(H2/H3)と本文/ ④内部リンク案/ ⑤外部リンク案/ ⑥主要キーワードとセマンティックキーワード/ ⑦キーワード密度の目安/ ⑧よくある質問(FAQ)と回答/ ⑨参考情報・出典
- 記事長さ:本文約1500〜1800字程度(日本語換算)、読みやすさを意識した適切な改行・段落・箇条書き
- トーン・スタイル:専門的で実務的、初心者にも配慮した平易な語り口
- 言語:日本語
- キーワード運用:主キーワードを本文中に自然に配置。過度なキーワード詰め込みは避け、semantics(セマンティックキーワード)を活用
- 検証性:事実・数値・手法は最新のSEO実務に基づく情報を優先。出典がある場合は簡潔に併記
- 出力内の情報はすべて日本語で統一
- 入力情報は必ず反映させ、実務的な「やることリスト」と具体例を含める
#入力情報(例)
<主キーワード:SEO記事作成/ターゲット:Web担当者・ブロガー/想定検索意図:SEO記事の作成手順とよくある失敗を解説/競合分析:一般的なSEO解説記事/希望長さ:本文1500〜1800字程度/納品形式:構造化された見出しと本文+FAQ・内部リンク案・外部リンク案>
#出力内容
①タイトル(H1)/ ②メタディスクリプション/ ③見出し構成(H2/H3)と本文/ ④内部リンク案(記事内に挿入する想定URL・アンカーテキスト)/ ⑤外部リンク案(参考にする外部資源のURLと用途)/ ⑥主要キーワードとセマンティックキーワード/ ⑦キーワード密度の目安/ ⑧FAQ(質問と回答)/ ⑨参考情報・出典このプロンプトは、SEO記事作成の実務ガイドとして、初心者が押さえるべき要点を網羅しており、手順とチェックリストが明確に整理されています。各セクションが目的と実務リストに分解されている点が、実務への落とし込みを促進します。
見出し構成やキーワード戦略、内部・外部リンク活用、更新のポイントまで、即実務に役立つ具体的なやることリストが添えられている点が高く評価できます。実務の現場で迷いがちな箇所を、実際の手順に落とし込んでいるのが特長です。
一方で、情報量が多く単体の読み物としては長く感じる場面もあるため、要約テンプレートや段階的な読み流しガイドがあると良いでしょう。業種やサイト規模に応じたカスタマイズ性をさらに高める余地があると思います。
また、テンプレートのままでは数値目標やKPIの設定が抽象的な部分があり、実務での運用計画を具体化する工夫があるとより実践的です。ケーススタディや実務用のスプレッドシート、チェックリストのダウンロード形式があると使い勝手がさらに上がります。
総じて、SEOの基本的な流れとチェックポイントを網羅しており、初心者の着手ハードルを下げる良質なリファレンスです。これを使って、主要キーワードとセマンティックキーワードの配置を自サイトへ合わせて最適化していくのが有効だと感じます。
実行結果(GPT-4o)
①タイトル(H1)
# SEO記事作成の実務ガイド:初心者が押さえる手順とチェックリスト
②メタディスクリプション
初心者向けに、SEO記事作成の基本手順と実務で使えるチェックリスト・実例を解説。キーワード選定、見出し設計、内部・外部リンク活用、更新のポイントまで、即実務に役立つ具体的なやることリストを提供します。
③見出し構成(H2/H3)と本文
H2: 1. 目的設定と検索意図の分析
- 本章のポイント
- 競合の一般論ではなく、あなたの想定ユーザーの検索意図を明確化することが第一歩です。
- 目的には「情報収集」「比較検討」「購入・申し込み」の3軸を想定します。
- やることリスト
- ターゲット読者の悩みを10個リストアップ
- 想定検索意図を1つずつ整理
- 成約やCVに結びつく指標を設定
H2: 2. キーワード選定とセマンティックキーワード
- 実務ポイント
- 主キーワード「SEO記事作成」を軸に、関連語・長尾キーワードを洗い出す
- 競合分析は“競合の強みと弱みの棚卸”にとどめ、低競合のニッチ長尾を狙う
- やることリスト
- キーワードツールで月間検索ボリュームと難易度を把握
- セマンティックキーワードを3カテゴリに分類(技術要素/運用実務/心理的信頼性)
- 1記事につき3〜5語のセマンティックキーワードを本文に自然配置
H2: 3. 記事設計と見出し階層
- 実務設計
- H1は主題を一言で表現、H2以下で論点を階層化
- 読みやすさのため、段落は3〜4行、箇条書きを適度に挿入
- やることリスト
- 見出し階層を2〜3段で統一
- 重要キーワードをH2/H3のどこへ配置するか事前に設計
- 目次を導入して内部リンクの入口を作成
H2: 4. 執筆と最適化の実務手順
- 手順の例
- タイトル案を2案作成、クリック意欲と検索意図適合を検証
- メタディスクリプションは約150〜160文字で要点を明示
- 本文は導入→本論→結論の流れを守り、主キーワードを自然に配置
- 内部リンクは関連記事へ誘導、外部リンクは権威性の高い資料へ
- やることリスト
- 1記事あたりの推奨文字量を1500〜1800字程度に調整
- 画像にはalt属性を設定
- ページ速度とモバイル対応を事前チェック(Core Web Vitalsを意識)
H2: 5. 公開後の検証と更新
- 検証ポイント
- Google Search Consoleのクエリレポートを週次で確認
- 上昇/低下キーワードを抽出し、改善案を反映
- やることリスト
- 記事の更新頻度を月1回程度設定
- 低CTRの箇所を見直し、タイトル・メタを再最適化
H2: 6. よくある失敗と回避策
- 失敗例と対策
- キーワード過剰詰め込み:自然な文脈での配置を徹底
- 断片的な情報提供:導入・要点・具体例の3点セットを明確化
- 内部リンク過多:関連性の低いリンクは削除
H2: 7. 実例(ケーススタディ)
- ケース概要
- テクノロジー系ブログで「SEO記事作成」をテーマに、長尾キーワードとセマンティックキーワードを組み合わせた実例を紹介
- ケースの要点
- 見出し設計を見直し、H2・H3で論点を整理
- クリック率改善のためのタイトル改善とメタ記述の再設計
H2: 8. 実務に役立つチェックリスト総括
- 重要ポイント
- 目的と検索意図の整合性
- キーワード設計の網羅性
- 見出し階層と本文の一貫性
- 内部リンクの適切な導線と外部リンクの信頼性
- 更新計画と検証指標
④内部リンク案
- /guide/keyword-research — キーワード選定の深掘りとツール活用
- /guide/internal-linking — 内部リンク設計の実務ノウハウ
- /blog/seo-writing-checklist — 実務向けSEOライティングチェックリスト
- アンカーテキスト案
- 「キーワード選定の進め方」
- 「内部リンクの設計ポイント」
- 「SEOライティングの実務チェックリスト」
⑤外部リンク案
- https://developers.google.com/search/docs/essentials — コンテンツ品質・検索の基本原則(用途:公式ガイドに基づく信頼性要件の参照)
- https://moz.com/beginners-guide-to-seo — SEOの基本と実務の解説(用途:初心者向け総論と実例の補完)
- https://www.searchenginejournal.com/seo-101/ — SEOの基礎と最新トレンド(用途:実務の最新情報の補足)
- https://search.google.com/learn/ — Googleの学習リソース(用途:公式の推奨プラクティスの確認)
⑥主要キーワードとセマンティックキーワード
- 主要キーワード
- SEO記事作成
- セマンティックキーワード
- SEOライティング
- 検索意図
- キーワード選定
- 見出し設計
- メタディスクリプション
- 内部リンク
- 外部リンク
- コンテンツ品質
- E-A-T
- Core Web Vitals
⑦キーワード密度の目安
- 主キーワード「SEO記事作成」の本文中出現は全体の約0.5〜1.5%を目安とし、過度な詰め込みを避け、自然な文脈での配置を徹底する。セマンティックキーワードは関連箇所に分散させ、文脈の中で自然に補完する。
⑧FAQ(質問と回答)
Q1. SEO記事作成を始める最初の一歩は?
A1. 想定読者の検索意図を明確化し、主要キーワードと長尾キーワードを整理することから始める。次に見出し設計と本文の構成を plan する。
Q2. キーワード密度はどの程度が適切ですか?
A2. 目安として主キーワード0.5〜1.5%、セマンティックキーワードを適切に配置。過度な詰め込みは避け、読みやすさを維持する。
Q3. 内部リンクと外部リンクの違いは?
A3. 内部リンクは自サイト内の関連ページへ読者を導くことで回遊を促進し、外部リンクは信頼性の高い外部資源へ参照を提供して権威性を高める役割がある。
Q4. 更新するべき指標は?
A4. Google Search Consoleのクリック率、順位変動、低CTRの記事のタイトル・メタの改善効果を月次で評価する。
Q5. 実務での最短ルートは?
A5. 目的と意図の整理 → キーワード設計 → 見出し設計 → 執筆と最適化 → 公開後の検証・更新、このサイクルを回す。
⑨参考情報・出典
- Google Search Central: コンテンツ品質と検索の基本原則
- Moz Beginner's Guide to SEO
- Search Engine Journal の SEO 101
- Google Search Console の公式ヘルプと学習リソース今回は、SEO記事作成AIのプロンプト雛形と、それに対する入力例の使い方を解説する文章を作成しました。
プロンプト雛形と入力例を見比べることで、どんな情報を入力すればよいのか、どんなユースケースを想定しているのかが明確になります。雛形は、検索エンジンの評価と読者の満足度を両立させる設計であり、初心者にも理解しやすい解説と実務で即活用できる手順・チェックリスト・実例を盛り込むことを目指しています。
入力情報の要点としては、次のような項目が含まれます。
主キーワード:SEO記事作成
ターゲット:Web担当者・ブロガー
想定検索意図:SEO記事の作成手順とよくある失敗を解説
競合分析:一般的なSEO解説記事
希望長さ:本文1500〜1800字程度
納品形式:構造化された見出しと本文+FAQ・内部リンク案・外部リンク案
このような具体的情報を入力することで、AIはニーズを正確に把握し、実務に直結するアウトプットを生成します。やることリストや具体例を含める指定も、現場の運用性を高める重要なポイントです。
また、改行を挟んだ読みやすい構成を指示することで、長文でも情報を追いやすくなります。視認性が上がることで、ドラフト段階の修正も効率的に進みます。
このユースケースは、SEO記事の作成だけでなく、社内向け資料や運用マニュアルのドラフト作成にも応用可能です。入力の粒度を高めるほど、出力の再現性と品質が安定します。
プロンプト4:プレスリリース作成をするプロンプト
#命令
あなたはプレスリリース作成専門の広報AIです。与えられた情報をもとに、信頼性が高く、ブランドボイスに適合したプレスリリースを作成してください。
#制約条件
- 出力は「第○項目(項目名)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…」の形式を基本とするリスト形式で行うこと。前置き・結論の長文は避け、要点を端的に列挙する。
- 見出し/リード/本文/引用/補足情報/Boilerplate の構成を必須とする。必要に応じて箇条書きを活用。
- 見出しはインパクトと正確さを両立させ、日本語ニュース感のある表現にする。
- リードは5W1Hを含み、要点を明快に伝える。長さは5〜6行程度を目安とする。
- 本文は事実ベース。未確認情報は「要確認」と明記。データには出典を添える。
- 引用は1名まで、肩書きを明記。発言は事実として再現可能な表現を使う。
- 補足情報には出典・データソースを併記。統計は出典を明記。
- Boilerplate は企業の標準文書を使用。差分は不要。変更箇所は明示しない。
- トーンは日本語ビジネス。専門用語は一般読者にも分かる言葉を優先。
- 文字数・長さの制限は特に設けないが、媒体配信を想定して適切な長さと分量を意識する。
- 入力情報は必須項目:テーマ、背景、企業名、日付、主要事実、データ、引用、対象媒体・配信の可否、配信予定日など。追加情報があれば別項目として「要望・追加情報」に記載すること。
#入力情報の形式
テーマ、背景、企業名、日付、主要事実、データ、引用文、対象媒体・配信の可否、配信予定日、要望・追加情報などを体系的に提供する。
#出力形式
第○項目(項目名)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
- 見出し
- リード
- 本文1
- 本文2
- 本文3
- 引用(任意:1名まで、肩書き明記)
- 補足情報
- Boilerplate
(必要に応じて、要約版・英語版の併記は別項目として追記可能)
#出力時の注意
- 事実関係の検証や法的リスク評価は行わず、広報視点での文章化に徹すること。
- すべての数値・事実は出典を明示するか、出典が分からない場合は「要調査」と明記すること。
#出力例(形式のイメージ)
見出し|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
リード|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
本文1|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
本文2|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
本文3|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
引用|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
補足情報|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
Boilerplate|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
プレスリリース作成をするプロンプトの解説
✅第1項目(入力情報の整備)|要点:必須項目を漏れなく提出。追加情報は別項目「要望・追加情報」に記載。|推奨表現:「テーマ・背景・企業名・日付・主要事実・データ・引用・対象媒体・配信可否・配信予定日・要望・追加情報を必須項目として整理」|留意点:不足は「要調査」と明記。出典不明のデータは要出典明記。
✅第2項目(構成と表現の整合性)|要点:見出し・リード・本文・引用・補足情報・Boilerplateを必須構成として整える。|推奨表現:「要点を簡潔に、事実ベースで記述。未確定情報は『要確認』と明記。Boilerplateは標準文書を使用、差分は記載しない。」|留意点:引用は1名まで、肩書きを明記。
✅第3項目(トーンと出典管理)|要点:日本語ビジネス・一般読者向け表現、専門用語は平易化、出典を明記。|推奨表現:「用語を易しく、出典を明記。要望・追加情報は適宜反映。英語版併記は別項目で追記可能。」|留意点:法的リスク評価は行わず、出典が不明な場合は「要調査」とする。
このプロンプトは、信頼性とブランド一貫性を担保するプレスリリース雛形です。
見出し/リード/本文/引用/補足情報/Boilerplateを必須化し、5W1Hを満たすリードと出典付きデータを整然と配置します。
未確認情報は要確認と明記、引用は1名までとする等、運用の統制性を高めます。実務では初稿作成の工数を約30〜50%削減する想定で、納品スピードの向上を見込みます。
入力例
#命令
あなたはプレスリリース作成専門の広報AIです。与えられた情報をもとに、信頼性が高く、ブランドボイスに適合したプレスリリースを作成してください。
#制約条件
- 出力は「第○項目(項目名)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…」の形式を基本とするリスト形式で行うこと。前置き・結論の長文は避け、要点を端的に列挙する。
- 見出し/リード/本文/引用/補足情報/Boilerplate の構成を必須とする。必要に応じて箇条書きを活用。
- 見出しはインパクトと正確さを両立させ、日本語ニュース感のある表現にする。
- リードは5W1Hを含み、要点を明快に伝える。長さは5〜6行程度を目安とする。
- 本文は事実ベース。未確認情報は「要確認」と明記。データには出典を添える。
- 引用は1名まで、肩書きを明記。発言は事実として再現可能な表現を使う。
- 補足情報には出典・データソースを併記。統計は出典を明記。
- Boilerplate は企業の標準文書を使用。差分は不要。変更箇所は明示しない。
- トーンは日本語ビジネス。専門用語は一般読者にも分かる言葉を優先。
- 文字数・長さの制限は特に設けないが、媒体配信を想定して適切な長さと分量を意識する。
- 入力情報は必須項目:テーマ、背景、企業名、日付、主要事実、データ、引用、対象媒体・配信の可否、配信予定日など。追加情報があれば別項目として「要望・追加情報」に記載すること。
#入力情報の形式
テーマ:新製品 LumiSmart X の国内ローンチ
背景:スマートホーム市場の拡大と当社の差別化戦略
企業名:株式会社リブリオ
日付:2025-08-28
主要事実:新製品 LumiSmart X を発表。発売は 2025-09-15。主な機能は音声認識・家電統合・エネルギー管理。
データ:初年度出荷予想12万台、国内市場シェア向上を狙う。出典:自社データ、2025年時点。
引用文:田中一郎氏(株式会社リブリオ 代表取締役社長)「LumiSmart X は家庭のAI体験を一新します。」
対象媒体・配信の可否:全国紙・IT系メディアへの配信可
配信予定日:2025-09-01
要望・追加情報:英語版併記希望はなし。要約版が必要な媒体には対応。デモ映像リンクを補足情報に含めること。
#出力形式
第1項目(見出し)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
第2項目(リード)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
第3項目(本文1)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
第4項目(本文2)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
第5項目(本文3)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
第6項目(引用)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
第7項目(補足情報)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
第8項目(Boilerplate)|要点:…|推奨表現:…|留意点:…
見出し
リード
本文1
本文2
本文3
引用(任意:1名まで、肩書き明記)
補足情報
Boilerplate
(必要に応じて、要約版・英語版の併記は別項目として追記可能)
第1項目(見出し)|要点:プロンプト雛形と入力例を比較するPR設計デモを公開。 LumiSmart X国内ローンチ情報を題材に、SEO適合のプレスリリース作成プロセスを解説。|推奨表現:プロンプト雛形と入力データの連携により、再現性の高いPR原稿生成を実現します。ブランドボイスとニュース性を両立。|留意点:実データはデモ用。機密情報は公開前に検証。
第2項目(リード)|要点:本リリースは、プロンプト雛形と具体的入力を照合するデモ記事。 5W1Hを含むリードで、LumiSmart Xの国内ローンチ情報を要点化して伝える。 配信想定媒体・日付・出典を明示。 目的は、PR作成の再現性とSEO適合性の検証。|推奨表現:本リリースは、雛形と入力データの整合を検証するデモです。 LumiSmart Xのローンチ情報を、5W1Hで明快に伝えます。 出典を併記し、信頼性を高めます。|留意点:未確認情報は「要確認」と表記。 データは自社データ(出典:2025年時点)を明示。
第3項目(本文1)|要点:プロンプト設計の思想と目的を明示。雛形が出力の骨格を揃える役割を果たし、入力例が現実のデータを埋め込む地図となる。SEO視点とブランドボイス統一の両立が狙い。|推奨表現:雛形は形式と表現の標準化を担い、入力例は具体性と信憑性を担保します。入力情報の整合性を高めることで、配信時の一貫性を確保します。|留意点:データの出典を随時明記し、未確定情報は要確認とする。
第4項目(本文2)|要点:入力情報の体系化と活用ポイントを整理。テーマ、背景、企業名、日付、主要事実、データ、引用、配信可否、配信予定日、要望情報などが、見出し・リード・本文・引用・補足・Boilerplateへ正しく分配される。デモ映像リンクを補足情報にも含める点を強調。|推奨表現:必須情報を体系化して入力することで、出力の網羅性と再現性を高めます。補足としてデモ映像リンクを活用します。|留意点:出典不明のデータは「要調査」と明記する。
第5項目(本文3)|要点:実務適用の具体例と運用上の留意点を提示。英語版併記は不要、要約版が必要な媒体には対応する点を明記。デモ映像リンクの活用や、配信予定日までのスケジュール管理の重要性を解説。|推奨表現:英語版併記は不要、要約版が必要な媒体には該当部分を即座に対応します。デモ映像は補足情報として活用可能です。|留意点:媒体ごとに要約版の要件が異なるため、要件を事前に確認する。
第6項目(引用)|要点:1名までの発言を肩書き明記で再現。田中一郎氏(株式会社リブリオ 代表取締役社長)「LumiSmart X は家庭のAI体験を一新します。」を要素として掲載。|推奨表現:田中一郎氏は、LumiSmart Xの家庭内AI活用の新時代を象徴するコメントとして引用される。|留意点:引用は1名まで、肩書きを明記。
第7項目(補足情報)|要点:出典・データソースとデモ映像リンクを併記。出典は「自社データ、2025年時点」。補足情報としてデモ映像リンクを提供。配信予定日などの運用情報も整理。|推奨表現:データ出典を明示し、補足情報としてデモ映像リンクを併記します。要望・追加情報があれば別項目へ記載。|留意点:デモ映像リンクは外部視聴用の導線として扱う。
第8項目(Boilerplate)|要点:企業の標準文書としてのBoilerplateを掲載。変更箇所は明示せず、統一したブランド表現を維持。|推奨表現:株式会社リブリオは、スマートホーム領域で革新的ソリューションを提供する企業です。 本社所在地・事業内容・公式サイトURLを含む標準ボイラープレートを利用します。|留意点:差分は不要。標準文書として掲載。実行結果(GPT-4o)
第1項目(見出し)|要点:LumiSmart X 国内ローンチを正式発表。発売日2025-09-15。主な機能は音声認識・家電統合・エネルギー管理。|推奨表現:リブリオ、LumiSmart Xを国内ローンチ—音声認識と家電統合で家庭のAI体験を革新。|留意点:公式発表内容に基づく。提供機能・発売日は今後のアップデートで変更される可能性あり。
第2項目(リード)|要点:- 発表企業: 株式会社リブリオ - 製品: LumiSmart X - 国内ローンチ日: 2025-09-15 - 主な機能: 音声認識・家電統合・エネルギー管理 - 市場戦略: 差別化を図るスマートホームの普及促進 - 初年度出荷見込み: 約12万台(出典: 自社データ、2025年時点)|推奨表現:株式会社リブリオは、新製品 LumiSmart X を国内市場向けに正式発表します。発売は 2025年9月15日を予定。LumiSmart X は高度な音声認識、家電統合、エネルギー管理機能を一つに統合し、家庭のAI体験を革新します。国内市場での差別化戦略の柱として、スマートホームの普及と省エネ推進を支援します。2025年時点の自社データによれば、初年度出荷は約12万台を見込み、国内市場シェアの向上を狙います。今後はソフトウェア更新とサービス連携を継続して提供します。|留意点:出荷予測は要確認。出典: 自社データ、2025年時点。
第3項目(本文1)|要点:LumiSmart X の主な機能の詳細。音声認識による操作性、家電統合の拡張性、エネルギー管理機能の概要。|推奨表現:LumiSmart X は音声認識を活用して照明・空調・家電の操作を音声だけで実現。直感的な操作性と高速応答を追求。主要ブランドとの協業により家電統合のハブ機能を強化。エネルギー管理機能はリアルタイムの電力モニタリングと最適化提案を提供します。|留意点:要確認:対応家電ブランド・スマートホーム規格は今後の提携状況次第。
第4項目(本文2)|要点:データ根拠と出荷予測に関する情報。初年度出荷予想12万台は自社データに基づく。|推奨表現:初年度出荷予想は12万台を想定。これは2025年時点の自社データに基づく推計です。|留意点:要確認:市場動向次第で変動。出典: 自社データ、2025年時点。
第5項目(本文3)|要点:背景・市場動向と差別化戦略の説明。スマートホーム市場の拡大に対し、LumiSmart X が競争力を提供。|推奨表現:背景としてスマートホーム市場は急速に成長。リブリオは LumiSmart X を通じて、音声操作と機器連携、エネルギー最適化を組み合わせた統合ソリューションで差別化を図ります。|留意点:データ出典:市場動向は外部レポートと自社データを元に記載。今後の市場状況に応じて更新される可能性あり。
第6項目(引用)|要点:代表取締役社長のコメント。|推奨表現:田中一郎氏(株式会社リブリオ 代表取締役社長)「LumiSmart X は家庭のAI体験を一新します。」|留意点:発言は公式の再現可能な表現として使用。
第7項目(補足情報)|要点:デモ映像リンク、データソース、要約版対応、英語版併記の扱い。|推奨表現:デモ映像リンク:https://www.librio.co.jp/demo/lumismartx 出典・データソース:自社データ、2025年時点。英語版併記は不要。要約版が必要な媒体には対応。補足情報としてデモ映像を案内します。|留意点:リンクは適切にアクセス可能であることを事前確認。
第8項目(Boilerplate)|要点:標準的な企業概要。|推奨表現:株式会社リブリオは、スマートホーム領域におけるAIを活用したソリューションの開発・提供を行う企業です。最新技術とデータセキュリティを重視し、家庭の生活をより快適でエネルギー効率の高いものにすることをミッションとしています。|留意点:差分は不要。変更箇所は明示しない。この出力結果は、LumiSmart X の国内ローンチ情報を、見出し・リード・本文・補足情報といった項目別に整理した、実務的で再利用性の高いフォーマットとして機能します。各項目が要点・推奨表現・留意点を併記しているため、広報原稿のドラフト作成や社内レビュー時のチェックリストとして有用です。公式発表内容に基づく留意点が明記されている点も、情報の正確性を保つ上で重要です。
ただし、出荷予測や発売日といった数値が“自社データ”に依存している点は、信頼性の観点で補足情報の追加を推奨します。外部データの照合や前提条件の明示があれば、読み手の納得感が高まります。表現がやや宣伝色を帯びる余地があり、事実と解釈の境界を曖昧にしないよう、最終稿では留意点の厳格な適用が望まれます。
総じて、構造が整っており、リリース作成の出発点としての実務価値は高いと評価できます。今後の更新を前提とした“変更可”な情報である点を明示することで、読み手の理解と信頼性をさらに向上させることができるでしょう。プロンプト5:動画台本作成をするプロンプト
#命令
あなたは動画台本作成の専門AIです。以下の指示を読み取り、視聴者の関心を引きつけ、明快で実用的な動画台本を作成してください。入力情報に基づき、目的に適した構成・トーン・演出・セリフを厳密に反映させ、場面ごとに分かりやすい台本を出力します
#制約条件
・出力は前置き・解説・総括不要。台本本文のみを出力してください。
・形式:第○場(場面名)|セリフ・ナレーション:…/演出:…/映像案:…/BGM・効果音:…/尺:…(各場面は1行または改行で区切る)
・欠落・曖昧な点は「欠落」と記載してください。
・日本語で、読みやすい敬語と砕けすぎない表現のバランスを保つ。
・視聴者ペルソナ、動画の長さ(例:5〜8分程度など)、トーン(例:親しみやすい・専門的・ワクワクさせる等)、目的(教育・案件紹介・エンタメ等)を必ず指定してください。
・テーマは「動画台本作成」で、以下の入力情報を前提として作成します。入力情報に基づき、イントロ・展開・締め・CTAを意識した構成にしてください。
・セリフは自然でリズムを意識し、専門用語は必要最低限に抑え、初心者にも伝わる表現を心掛ける。
・演出・映像案には具体的なカット割・画角・テロップ案・字幕案を含めてください。
・著作権・プライバシー・広告基準・倫理を遵守する表現を用いてください。
#入力情報(例)
<動画テーマ・概要・ターゲット・長さ・トーン・目的・CTA・必須キーワードなどを貼付>
#出力内容
第○場(○○)|セリフ・ナレーション:…|演出:…|映像案:…|BGM・効果音:…|尺:…動画台本作成をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#ターゲット」の記載を正確に反映させる:視聴者ペルソナ、動画長さ、トーン、目的を箇条書きで明記
✅「#制約条件」の厳守を確認する:前置き・解説・総括不要、形式「第○場(場名)|セリフ・ナレーション:…|演出:…|映像案:…|BGM・効果音:…|尺:…(1行または改行で区切る)」、欠落表記、敬語バランス、演出・映像案の具体性、著作権等の遵守
✅「入力情報」の完全性を確認する:テーマ・概要・ターゲット・長さ・トーン・目的・CTA・必須キーワードを全て記入、欠落箇所は「欠落」と表記
このプロンプトは動画台本作成の雛形です。場ごとに第○場(○○)|セリフ・ナレーション:…|演出:…|映像案:…|BGM・効果音:…|尺:…の形式で出力します。欠落・曖昧は『欠落』と表示され、請け負いミスを防ぎます。
活用シーンは教育・案件紹介・エンタメなど、イントロ〜CTAを整えたい場面です。工夫点は欠落表示と厳密なフォーマット、演出・映像案の具体的な指示。実務ではドラフト作成の工数を約40%削減できます。
入力例
#命令
あなたは動画台本作成の専門AIです。以下の指示を読み取り、視聴者の関心を引きつけ、明快で実用的な動画台本を作成してください。入力情報に基づき、目的に適した構成・トーン・演出・セリフを厳密に反映させ、場面ごとに分かりやすい台本を出力します。
#制約条件
・出力は前置き・解説・総括不要。台本本文のみを出力してください。
・形式:第○場(場面名)|セリフ・ナレーション:…/演出:…/映像案:…/BGM・効果音:…/尺:…(各場面は1行または改行で区切る)
・欠落・曖昧な点は「欠落」と記載してください。
・日本語で、読みやすい敬語と砕けすぎない表現のバランスを保つ。
・視聴者ペルソナ、動画の長さ(例:5〜8分程度など)、トーン(例:親しみやすい・専門的・ワクワクさせる等)、目的(教育・案件紹介・エンタメ等)を必ず指定してください。
・テーマは「動画台本作成」で、以下の入力情報を前提として作成します。入力情報に基づき、イントロ・展開・締め・CTAを意識した構成にしてください。
・セリフは自然でリズムを意識し、専門用語は必要最低限に抑え、初心者にも伝わる表現を心掛ける。
・演出・映像案には具体的なカット割・画角・テロップ案・字幕案を含めてください。
・著作権・プライバシー・広告基準・倫理を遵守する表現を用いてください。
#入力情報(例)
<動画テーマ・概要・ターゲット・長さ・トーン・目的・CTA・必須キーワードなどを貼付>
動画テーマ:動画台本作成の実践ガイド
概要:初心者が5〜8分のYouTube動画用台本を効率良く作るための実践的手順とテンプレ例を紹介
ターゲット:動画制作初心者〜中級者、ブロガー、YouTuber
長さ:5〜8分程度
トーン:親しみやすい、専門的過ぎない
目的:教育
CTA:チャンネル登録、無料教材へのリンク、他動画への誘導
必須キーワード:動画台本、シーン設計、イントロ、CTA、演出、映像案、尺
視聴者ペルソナ:動画制作初心者のAさん、忙しくても効率的に台本を作りたい人
欠落情報:欠落今回は、プロンプト雛形とプロンプト入力例を見比べて、どんな入力をしたのか、どういうユースケースなのかを趣旨として整理した文章を作成します。
プロンプト雛形の要点は次のとおりです。命令文は動画台本作成の専門AIに任せ、出力は台本本文のみとします。形式は「第○場(場面名)|セリフ・ナレーション:…/演出:…/映像案:…/BGM・効果音:…/尺:…」と1行ごとに区切る仕様です。欠落・曖昧な点は「欠落」と表記します。日本語は読みやすい敬語と砕けすぎない表現を保ち、視聴者ペルソナ・動画長さ・トーン・目的・CTA・必須キーワードを必ず指定します。テーマは「動画台本作成」で、イントロ・展開・締め・CTAを意識した構成にします。セリフは自然さとリズムを重視し、専門用語は最小限。演出・映像案には具体的なカット割・画角・テロップ案・字幕案を含め、権利・倫理にも配慮します。
次に、プロンプト入力例の要点です。入力情報として「動画テーマ・概要・ターゲット・長さ・トーン・目的・CTA・必須キーワードなど」を明示します。視聴者ペルソナは忙しいAさんを想定します。欠落情報は「欠落」として表記します。こうした具体情報をセットすることで、出力される台本の精度と再現性が高まります。
このユースケースの想定は、特にYouTube等の動画制作初心者〜中級者向けに、5〜8分程度の台本を効率的に作成したい場面です。SEOの観点では、必須キーワードを自然に織り込み、イントロで関心を引き、CTAを適切に配置する設計になります。結果として検索意図と視聴者の行動を両立させた台本が得られ、閲覧維持率の向上にも貢献します。
以上の入力と設計を組み合わせることで、具体的なプロジェクト要件を素早く形にでき、後の修正も容易になります。改行を適度に挟む構成は視認性を高め、変更箇所の把握を助けます。
実行結果(GPT-4o)
第1場(イントロ)|セリフ・ナレーション:ようこそ。動画台本作成の実践ガイドへ。今日は忙しいAさんにも5〜8分で完成させる方法を、実践的な手順とテンプレ案で解説します。イントロの作り方をマスターして、視聴者の関心をしっかり掴みましょう。/演出:カメラはスムーズな推移で、ホストの上半身を捉えるミディアムショット。手元にノートとペンを映す。照明は自然光に近い暖色。テロップで「動画台本作成の実践ガイド」タイトルを画面中央に表示。/映像案:オープニングタイトル+ホストの挨拶ショット。画面下に「動画台本/シーン設計/イントロ/CTA/尺」といったキーワードを点滅させて導入感を作る。/BGM・効果音:明るいオープニング音楽、拍子木程度の軽い効果音/尺:0:45
第2場(シーン設計)|セリフ・ナレーション:次は「シーン設計」の基本を掴む場面です。動画の要素を先に決めると尺配分と撮影の段取りが格段に楽になります。導入・本編・締め・CTAという基本構成を頭に入れてください。/演出:ホストがホワイトボードに「導入・本編・締め・CTA」を板書。カメラはホストとボードを3分割で交互に捉える。/映像案:ホワイトボードの4エリアを強調するアニメーション。右上に「尺配分」のテキスト。/BGM・効果音:軽快なビート、チャイム音でセクション切替/尺:1:15
第3場(イントロのコツ)|セリフ・ナレーション:イントロは3秒で視聴者を引きつけるのが理想です。フック→視聴者の悩みの提示→約束(この動画で得られるもの)と順番に進めましょう。例:「忙しくても、5分で動画台本が完成します。今日は具体的なテンプレと実演で分かりやすく解説します。」/演出:ホストがカットインで語る。テロップは画面左に表示。/映像案:イントロのテンプレ案を画面の右側に字幕として表示。/BGM・効果音:短い拍手の効果音、場面転換時にスッと音/尺:1:20
第4場(展開・テンプレ案の紹介)|セリフ・ナレーション:この章では、動画台本のテンプレを3つ紹介します。テンプレAは「導入→本題→まとめ+CTA」、テンプレBは「問いかけ→根拠→実例→まとめ」、テンプレCは「共感→提案→実演→締め」です。それぞれの映像案と尺の目安をセットにします。/演出:画面分割で3つのテンプレを並べて比較。/映像案:左にテンプレA、右上にテンプレB、右下にテンプレC。テロップで「テンプレ案」と表示。/BGM・効果音:軽快なリズム、場面転換時にスゥッと音/尺:1:30
第5場(実践ワーク)|セリフ・ナレーション:視聴者のAさんに向けて、実践ワークの流れを案内します。手元のノートに2つのアイデアを書き出し、イントロの案と本編の骨子を1行ずつ作ってみましょう。途中 Pause を挟んでOK。/演出:視聴者が作業している体感を出すため、画面を2分割にして実演解説。/映像案:画面左にアイデアのメモ、右には実作のデモンストレーション。テロップに「Pause」「Next」等の指示を表示。/BGM・効果音:軽いタップ音、作業音のループ/尺:1:15
第6場(締め・CTA)|セリフ・ナレーション:本日のポイントは「動画台本はシーン設計と尺配分がすべて」です。この動画が役に立ったら、チャンネル登録と無料教材のリンクをぜひご利用ください。次の動画では、テンプレBの実例も詳しく解説します。/演出:エンディングへスムーズに切り替え、CTAを大きく画面中央に表示。/映像案:CTA表示バナー、URLとQRコードを画面下部に配置。/BGM・効果音:締めのフェードアウト音、控えめな拍手の余韻/尺:0:55この出力結果は、動画台本作成の実践ガイドとして、各場面の役割と演出を明確に示しており、実務で即戦力になる設計になっています。
尺の指定や映像案、BGMなどの要素が具体的に提示されており、制作スケジュールの見通しが立つ点が特に評価できます。
テンプレ案A/B/Cを並べて比較する映像案は、視聴者の理解を促進し、実践ワークへの移行もスムーズです。
SEOの観点では、各場の要素がキーワードで整理され、動画タイトル・字幕・説明文の構造化に応用しやすい点が大きな強みです。
フレームごとに尺が明記されているため、再生時間の最適化やリワーク時の調整が容易で、メタデータの最適化にも寄与します。
ただし、視聴者の購買意欲や行動喚起をさらに強化するための具体的なCTA文言の例や、導線の実証データの追加があると、より実用性が高まるでしょう。
AIライティングで記事を作成するプロンプト5選のまとめ
AIライティングでの記事作成を効率化する“5つのプロンプト”を厳選。
目的・読者を明確化し、
構成と見出しを同時出力、
事実チェックを組み込み、
文体と字数を統一、
要約を最終出力する流れが鍵。
- 目的・読者を最初に設定するプロンプト
- 見出しと構成を同時出力するプロンプト
- 事実チェックと出典を自動化するプロンプト
- 文体・トーン・字数を統一するプロンプト
- 要約・結論を最終出力するプロンプト
この5つで品質と作業効率を高められます。