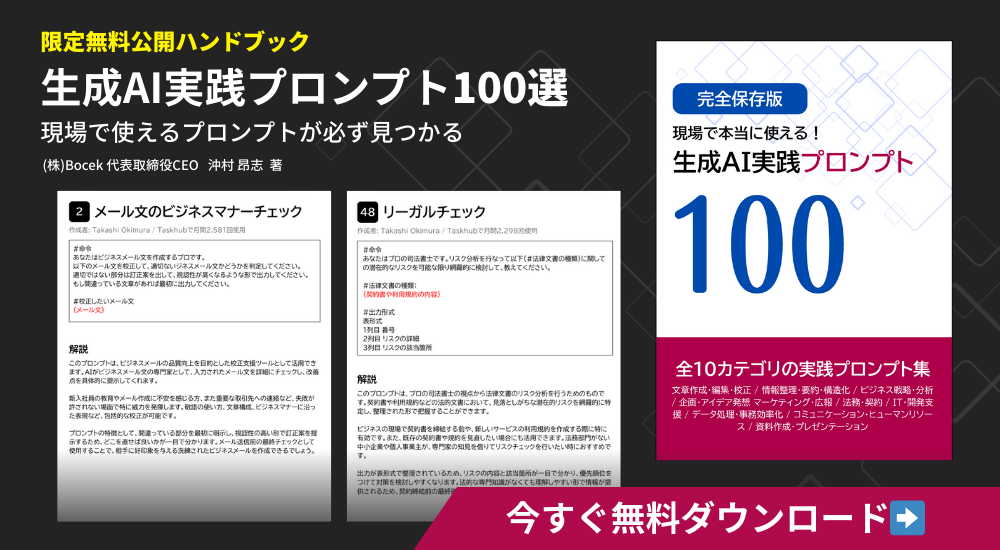ジェネリック医薬品のリーディングカンパニーである沢井製薬株式会社。同社は研究開発の革新を目指し、生成AIの活用に積極的に取り組んでいます。特に、社内に蓄積された膨大な研究データをナレッジとして継承し、業務効率を飛躍的に向上させるため、Azure OpenAI Serviceを活用したRAG(Retrieval-Augmented Generation)システムを構築しています。
今回は、プロジェクトを主導する研究開発本部 製剤研究部の西村さんと木全さんに、導入の背景から具体的な活用法、そして導入を成功に導いた秘訣まで、詳しくお話を伺いました。

属人化するノウハウの継承が急務。RAG技術との親和性がプロジェクトの起点に

Q.そもそも、なぜ研究開発の現場で生成AIの活用を検討し始めたのですか?
西村さん: 近年、社会全体で人材の流動性が高まる中で、当社が長年培ってきた独自のノウハウが失われることなく、次世代に継承され、さらに有効活用される仕組みを構築したいという強い思いがありました。その課題を解決する手段を模索する中で、社内の膨大な文書データから必要な情報を引き出して回答を生成するAIの「RAG」と呼ばれる技術が、私たちの目指す方向性と非常に親和性が高いのではないかと注目し、今回のプロジェクトを立ち上げたという背景があります。研究開発はまさに知の継承が重要であり、この技術に大きな可能性を感じました。
Q.導入はいつ頃から始まったのでしょうか?
西村さん: 具体的に動き出したのは2024年の1月頃です。ちょうどMicrosoft社とOpenAI社の提携が強化され、Azure上で安全にChatGPTが利用できるという発表が出た時期でした。その情報をいち早くキャッチした当社のシステム部が先行トライアルに申し込んでくれまして。私たち製剤研究部としても、常々AIを活用したプロジェクトを立ち上げたいと考えていたので、システム部と我々の目的と利害が一致し、連携してプロジェクトを進めていく流れになりました。
Q.様々なサービスがある中で、Azure OpenAI Serviceを選んだのはなぜですか?
西村さん: 研究開発で扱うデータは、すべてが機密情報です。そのため、セキュリティの担保はツール選定における絶対条件でした。私たちが検討していた当時、セキュリティを万全に確保し、安全な閉域環境ですべての機能を利用できると言う面は、Azure OpenAI Serviceが最も優れていたため、実質的に一択という状況でした。
引用機能と文章分割の最適化で課題を克服。過去の報告書から”ヒント”を得る

Q.現在、構築したシステムをどのような業務に活用しているのでしょうか?
木全さん: 主に、過去に蓄積された膨大な研究報告書や申請関連書類の中から、現在の業務課題を解決するための「ヒント」を得るという形で活用しています。何か困ったことがあった際に、関連する過去の事例やデータをAIに問い合わせることで、解決の糸口を迅速に見つけ出すことが主な目的です。
Q.過去の膨大なデータをAIに読み込ませる上で、何か工夫した点や課題はありましたか?
木全さん: 弊社では報告書のフォーマットが長年にわたって統一されていたため、比較的スムーズにデータの取り込みを進めることができました。しかし、報告書内に画像データとして貼り付けられた図表など、AIがテキストとして正確に読み取れない情報も存在します。この課題を乗り越えるため、AIの回答に「引用元」を明記する機能を実装しました。これにより、研究者はAIの回答がどの文書のどの部分に基づいているのかを即座に確認し、必要に応じて元のデータに立ち返って内容を精査できます。
また、RAGの回答精度は文書をどのように分割するかに大きく左右されます。この専門的な部分に関しては、構築を支援してくださった株式会社ベーシック様と共に検討を重ね、文書の内容をAIが正しく解釈できるよう、文章の分割方式を最適化しました。これにより、精度の高い情報検索が可能になっています。
数時間の業務が数分に。現場主導で進めたボトムアップ戦略が成功の鍵
Q.導入によって、具体的にどのような効果がありましたか?
木全さん: 最も大きな効果は、圧倒的な時間短縮です。これまでは、何か課題に直面すると、担当者が先輩社員と数時間にわたってディスカッションし、先輩社員もまた関連する過去のデータを膨大な資料の中から探す必要がありました。それが今では、AIに質問を投げかけることで、数回のやり取りを通じて数分で解決のヒントが得られます。この変化は非常に大きいと感じています。
定量的な効果も明確に表れており、現在では部員の約80%がこのシステムを利用しています。申請書作成業務においても同様の効率化が進んでおり、定性的な効果はもちろん、今後さらなる定量的効果が出てくることを期待しています。
| 活用業務 | 導入前の課題 | 導入後の変化 |
| 先行研究・事例検索 | ・課題解決のために先輩社員と数時間の議論が発生
・膨大な報告書から手作業で情報を探す必要があった |
・AIへの質問を通じて、数分で解決のヒントを発見可能に
・月平均40~50回の利用があり、大幅な時間削減を実現 |
| 申請フォーマットへの
落とし込み |
・過去の申請データをExcelから探し、手作業で転記
・類似案件の検索が煩雑で時間がかかっていた |
・状況を説明するだけで、AIが過去の事例に基づいた回答方針を提示
・定性的に大きな業務負荷軽減を実感 |

Q.導入を進める上で、コスト削減効果など、経営層からの厳しい指摘はありませんでしたか?
西村さん: もちろん、費用対効果に関する指摘はありました。しかし、私たちは今回のAIプロジェクトに先立ち、RPAなどを活用した地道な「コツコツDX」を2022年頃から進めていました。そこで「何時間削減できた」という具体的な経済効果を既に出していたため、信頼の土台があったのです。その実績を示した上で、「より大きな効果が見込めるAIを導入すれば、さらなるコスト削減が期待できます」と、最初に成功体験を見せる形で説明しました。
もう一つ重要だったのは、会社の経営目標との連携です。サワイグループは2030年までに「DX推進企業」になるという目標を掲げており、その中には「過去品目のナレッジ活用」による安定生産や申請の迅速化も含まれています。そこで、「私たちがやろうとしているAI活用は、まさに会社が掲げる目標そのものです」と訴えました。経営陣が掲げた目標と現場の取り組みが完全に一致していることを示すことで、投資の正当性を論理的に説明できたことが大きかったですね。
Q.現場の協力が得られずDXが難航するケースも多いですが、なぜうまくいったのでしょうか?
西村さん: それは、実務者である私たち自身が開発に深く関わっている点が非常に大きいと思います。現場の業務フローを熟知しているため、「ここのプロセスは自動化できる」「この作業はやり方を変えれば効率化できる」といった、地に足のついた議論ができます。システム部門任せにせず、現場が主体となって自分たちのためのツールを作り上げたからこそ、実用的で本当に使えるシステムになったのだと考えています。
特化型と汎用型を使い分け。丁寧な情報発信で組織全体のITリテラシーを底上げ

Q.AI活用を組織に浸透させるため、どのような教育を行いましたか?
木全さん: 前述の「コツコツDX」を通じて、部員が少しずつデジタルツールに触れる機会を増やし、組織全体のITリテラシーを底上げしてきた土壌がありました。その上で、今回のAIシステムに関しては、プロンプトの重要性を周知することに注力しました。例えば、「小学生に話しかけるように、具体的で分かりやすい言葉を使うと良いですよ」といった実践的なコツを私たちから発信したり、Microsoft社に社内講演会でプロンプトの書き方を解説していただいたりしました。こうした地道な情報発信を通じて、徐々に皆のリテラシーが向上していったと感じています。
Q.RAGシステム以外にも、一般的な生成AIツールは利用されているのですか?
木全さん: はい、明確に使い分けています。今回構築したシステムは、あくまで社内の研究開発ナレッジ検索に特化させたものです。一方、法令調査や一般的な資料作成といった汎用的な業務効率化には、全社的に導入されているGeminiを活用しています。法令のように常に情報がアップデートされる分野はネットワークに接続されたSaaSを利用し、社内の機密情報や独自ノウハウに関わる部分は自社で管理する閉域のRAGシステムを利用する。このように、業務の特性に応じて最適なツールを使い分けることが非常に重要だと考えています。
“自律実験”と”自動文書作成”へ。AIで24時間365日稼働する研究開発体制を目指す
Q.今後の活用について、どのような展望をお持ちですか?
西村さん: 大きく2つのテーマを掲げています。一つは「自律実験」の実現です。これは、AIが自ら実験計画を立案し、ロボットを動かしてデータを取得する、という次世代の研究スタイルです。自律実験の仕組みそのものは、医薬品だけでなくあらゆる分野で検討が進んでいくと考えていますが、それを自社の業務フローに落とし込むためには、何をAIに参照させるかが重要です。ここに私たちのRAGシステムを組み合わせ、AIが実験を進める中で社内の膨大なノウハウを参照できるようにすれば、人間では思いつかなかったような革新的な実験を自律的に進められるようになると期待しています。
木全さん: もう一つは、申請書類などの「自動文書作成」です。製薬企業は一つの薬を世に出すために、膨大な量の書類を作成する必要があり、これが大きな業務負荷となっています。そこで、設計書などのデータをもとに、AIが必要な書類の叩き台を自動で生成する仕組みを開発しています。人間は最終的なチェックと修正に専念することで、業務を劇的に効率化できると考えています。
Q.最後に、この記事の読者へメッセージがあればお願いします。
木全さん: デジタルを使って製剤研究をより効率化し、そこから新しい可能性が広がっていく。そんな未来を、少しずつ形にしていければと思っています。そのためには、このDXの流れをさらに加速させていく必要があり、専門知識とデジタルスキルの両方を併せ持つことが不可欠と考えます。専門分野の研究知識だけではなく、AIやプログラミングといったデジタル分野にも目を広げていくことが、よりよい製品開発につながるのではないでしょうか。