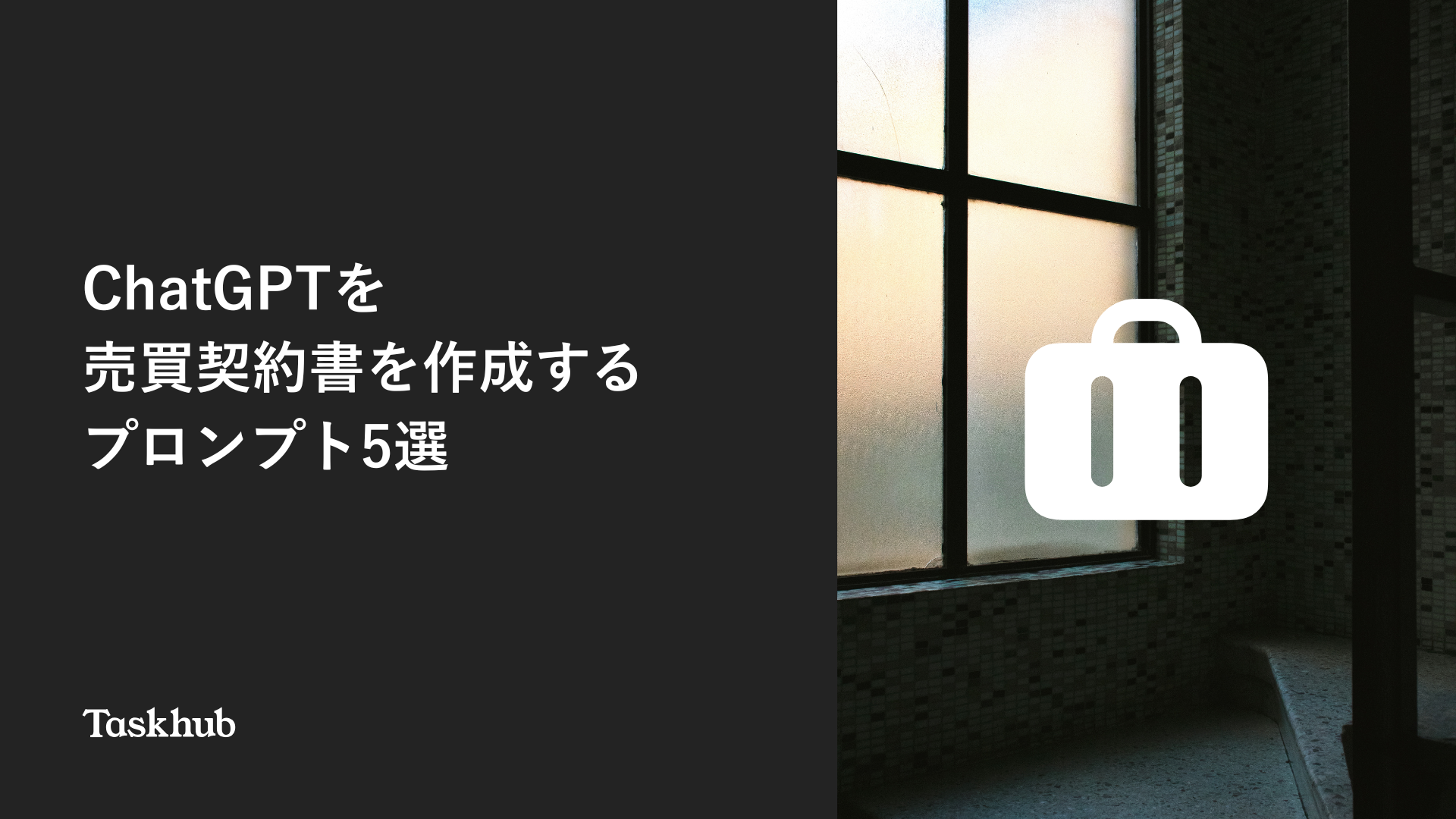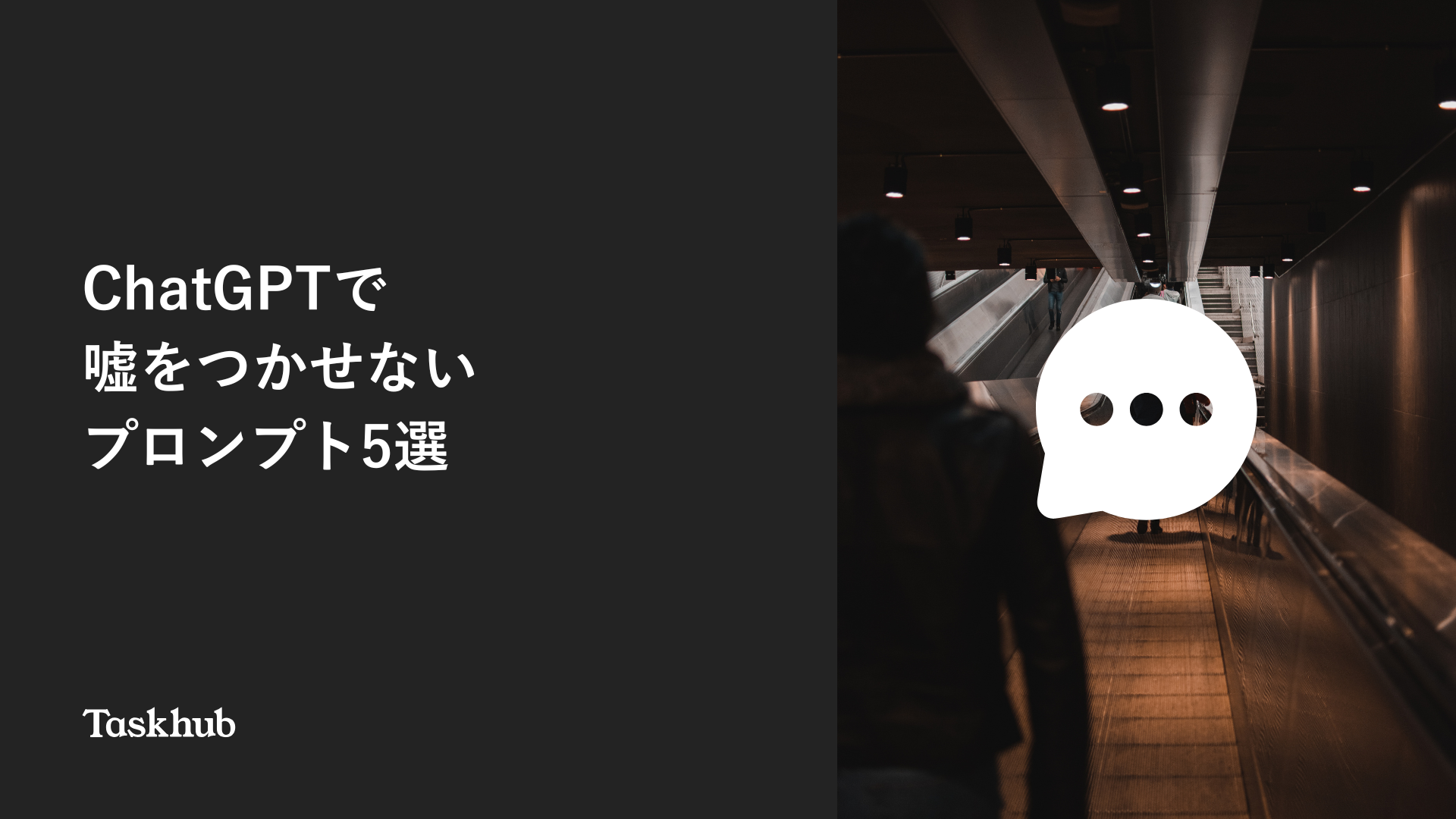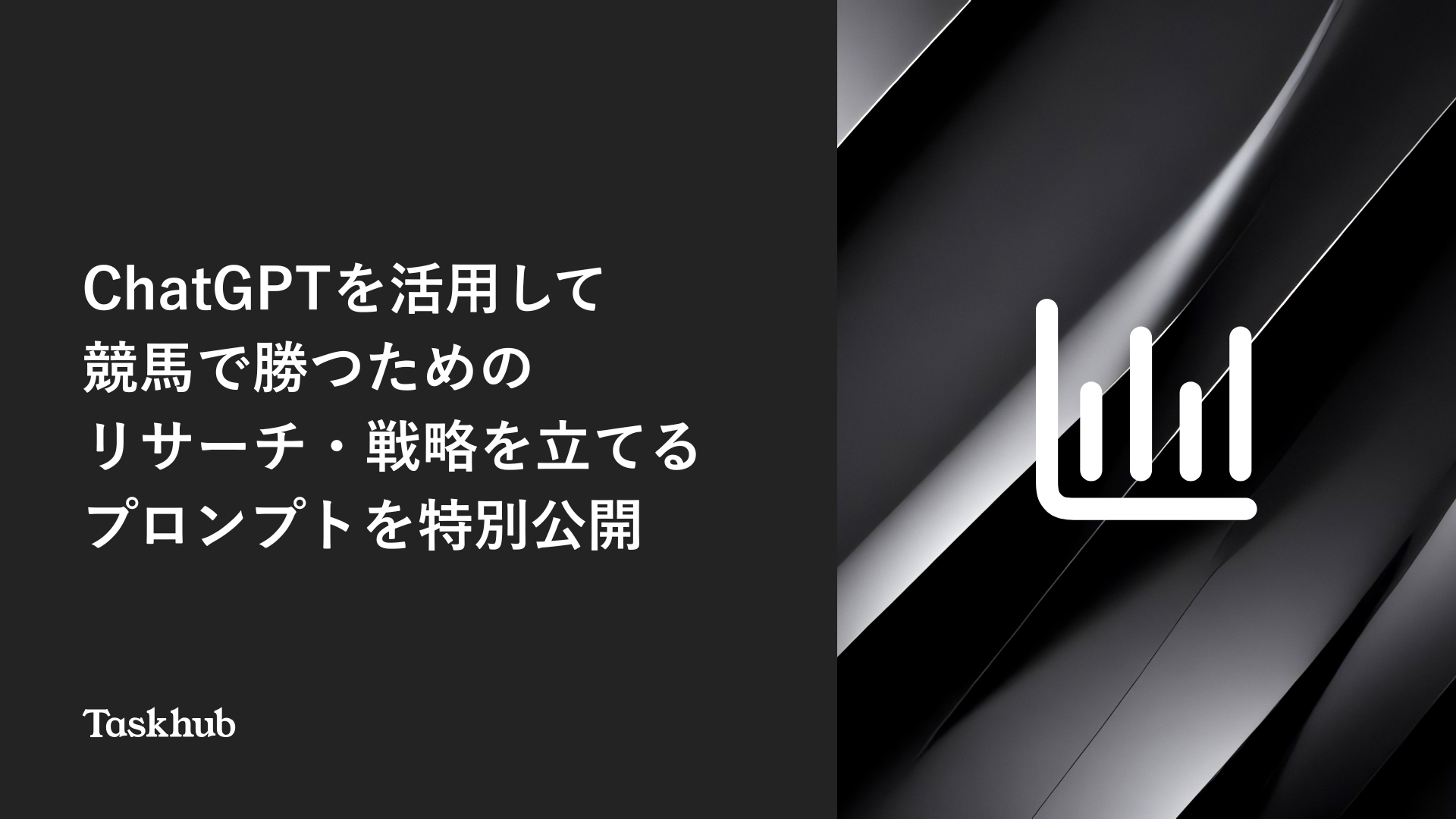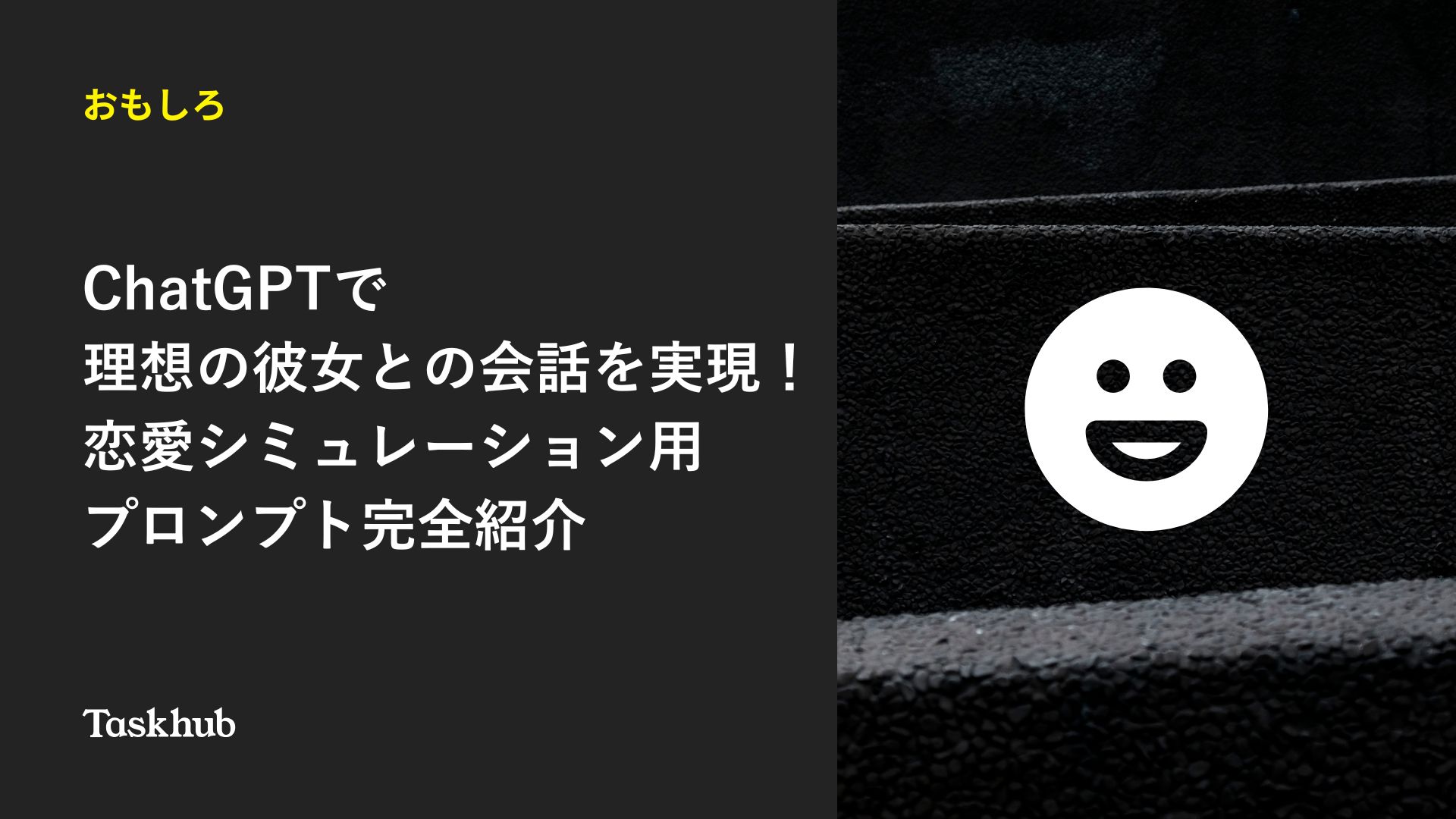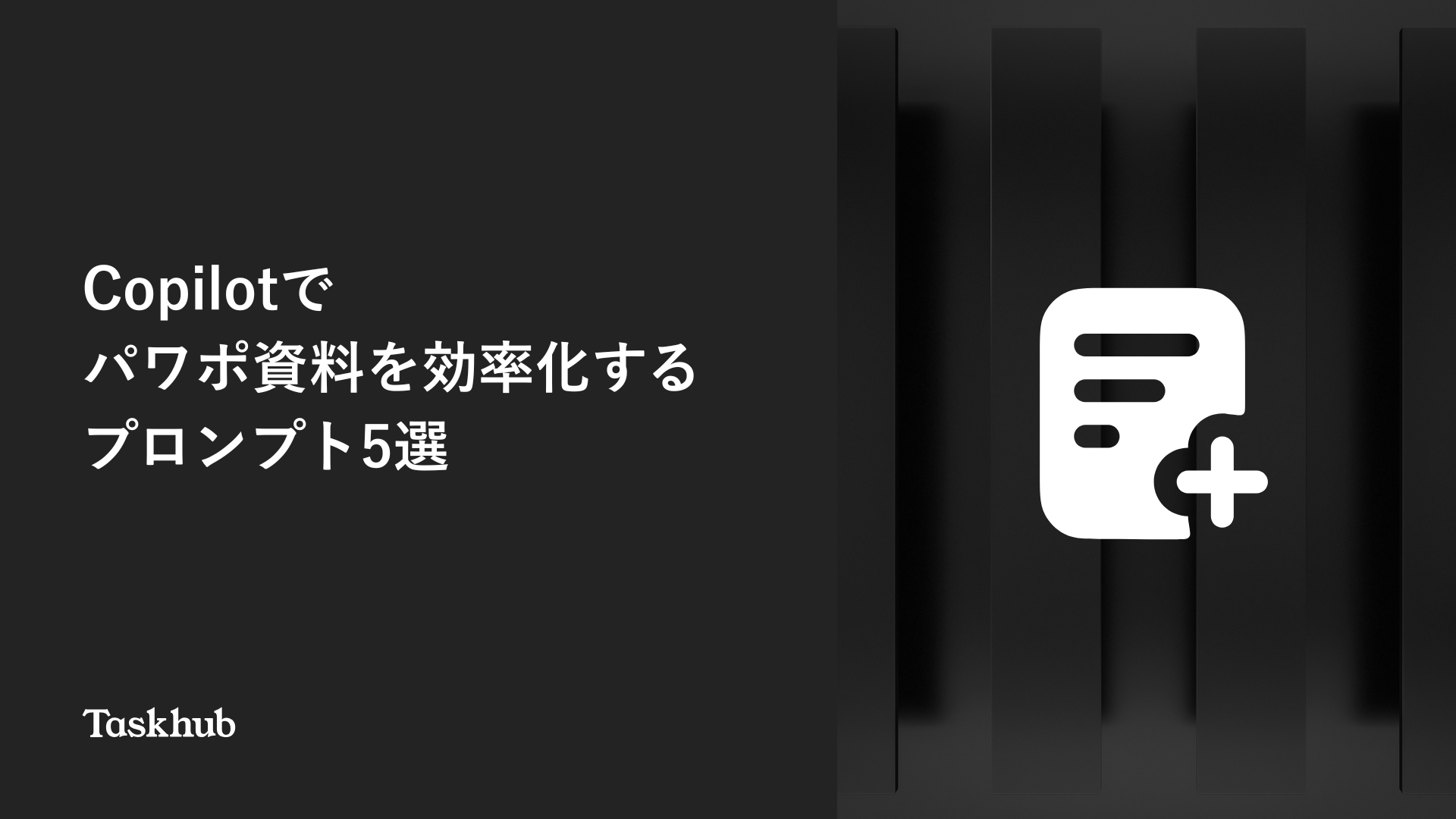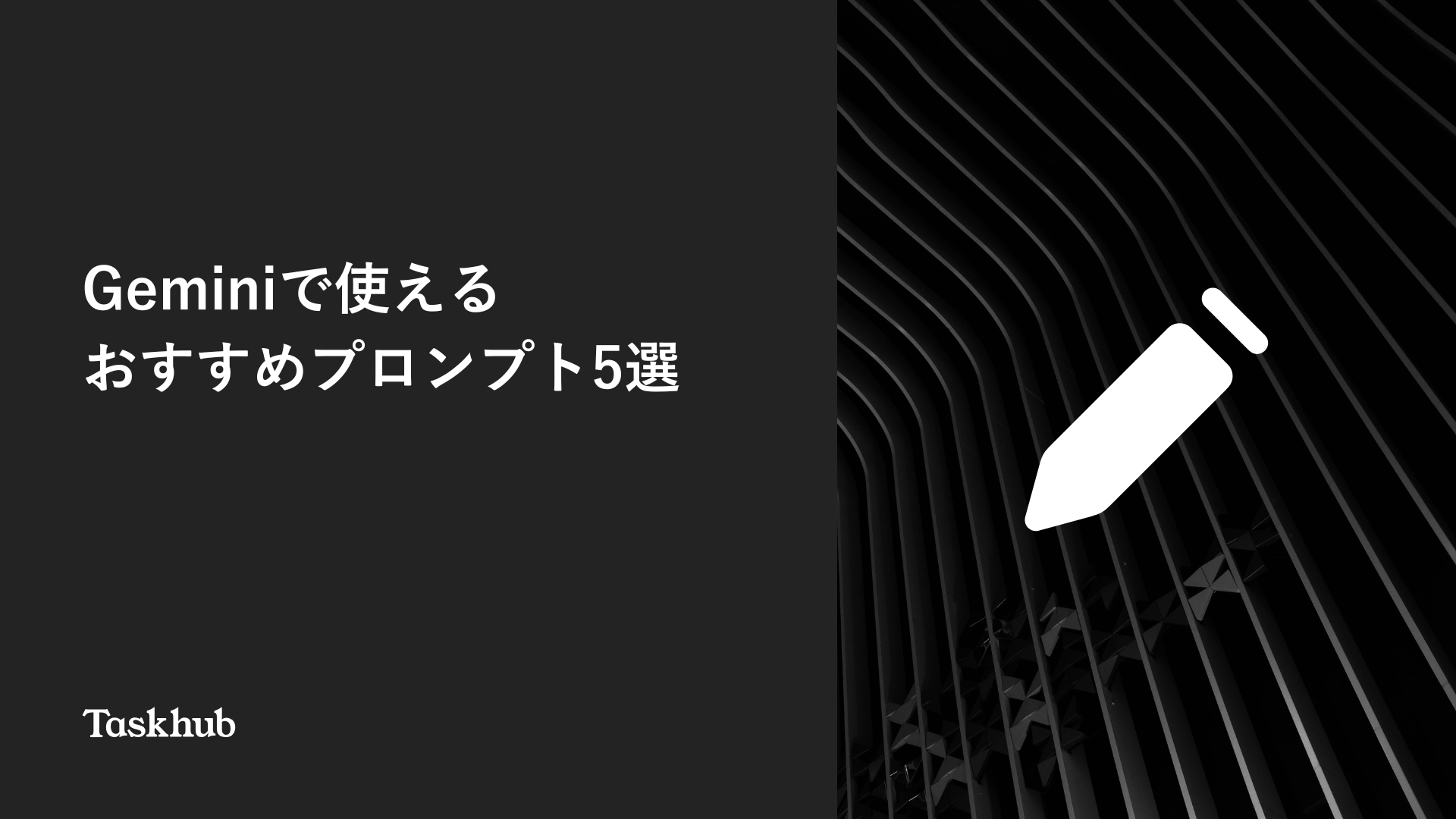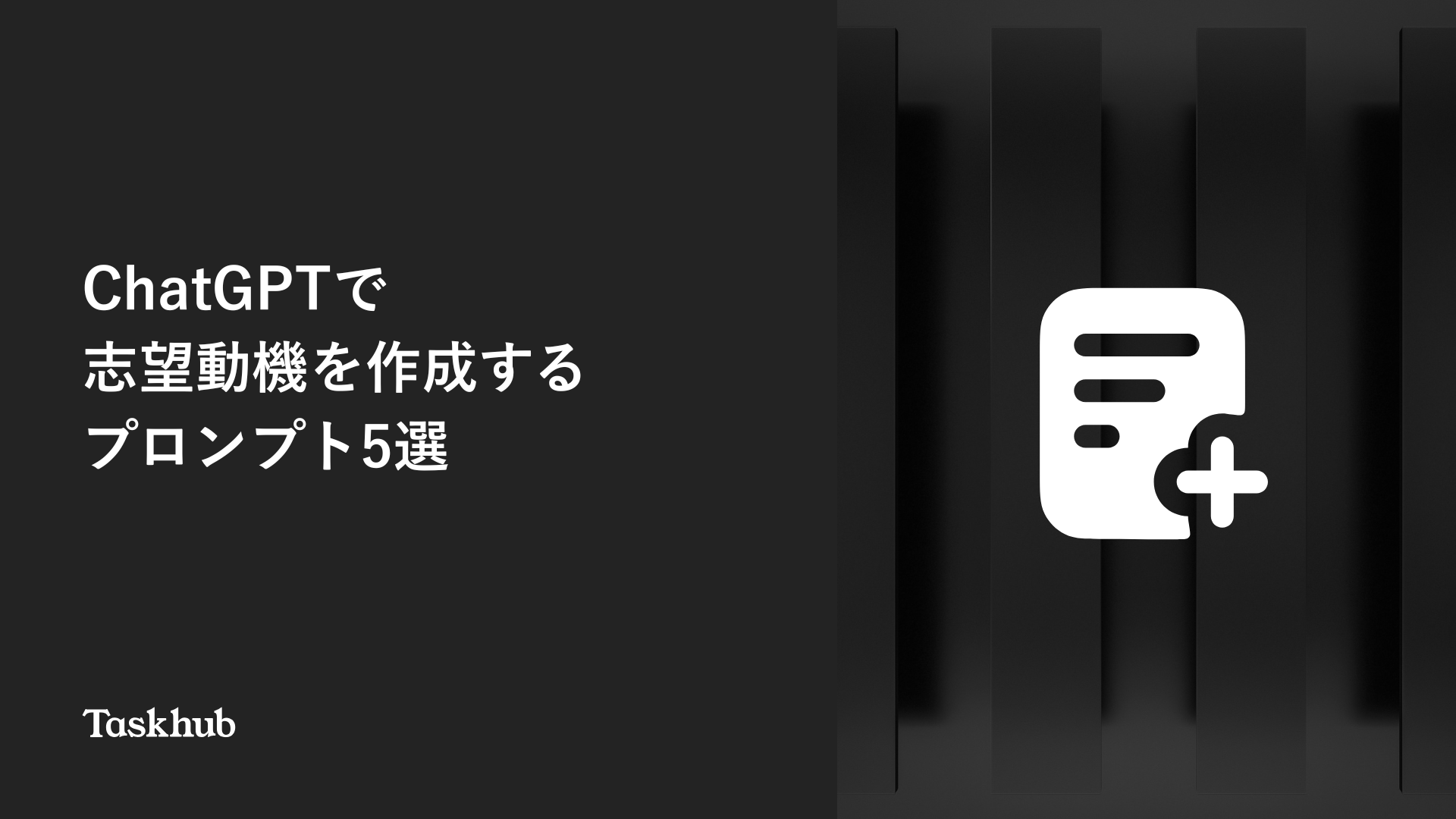「ChatGPTを使って売買契約書を作成できるって聞いたけど、本当に法律的に問題ないの?」
「自分で契約書を作成してみたけど、重要な条項が抜けていたり、不備が心配で使えない…。」
こういった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、ChatGPTを活用した売買契約書の作成方法や注意点、さらに安全かつ効率的に契約書を作成するためのポイントについて詳しく解説します。法律の専門知識がなくても使える実用的なプロンプト例もご紹介。
AI技術をビジネスに活かす弊社だからこそ提供できる、実践的な内容です。
契約書作成の効率化を目指す方は、ぜひ最後までお読みください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅売買契約書を作成し、商品や物件の引き渡し・代金支払い条件など具体的な取引内容を網羅的に記載したいとき→プロンプト1がおすすめ
✅企業買収契約書を作成し、会社法や独占禁止法にも触れつつリスクを丁寧に注釈付きで説明してほしいとき→プロンプト2がおすすめ
✅取引基本契約書を作成し、長期的な取引関係の大枠を明確にしつつ、リスク軽減を図る文書が必要なとき→プロンプト3がおすすめ
✅合意書や一般的な契約書を、シンプルかつ漏れなく条項を網羅した完成形で作成したいとき→プロンプト4がおすすめ
✅M&A契約書を専門的に作成し、必要に応じて業種特有の条項も取り入れつつ注釈付きで候補文例も提示してほしいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTで契約書作成をすることは可能?
ChatGPTを使って売買契約書を作成すること自体は技術的に可能です。
AIが提示する条文案をベースに、契約書の骨格を短時間で作ることができます。
ただし、重要なのはその契約書が実務や法務の現場で通用するかどうかという点です。
AIはあくまで補助ツールであり、最終的な法的判断や修正は人間の専門家に委ねるべきだからです。
また、契約目的や取引内容によって必要な条項や条件は大きく異なり、AIがその詳細を完璧に理解できるわけではありません。
目的に応じたカスタマイズが必須となります。
ChatGPTの出力はあくまで“ドラフト案”と捉える
ChatGPTは多種多様な契約例を学習しており、標準的な売買契約書のフォーマットや条項を生成可能です。
しかし、各企業や取引の個別事情に応じたリスク項目の抜け漏れや誤認が生じやすいのが現状です。
例えば特定の免責条項や違約金規定、納期遅延時の措置など、細かなルール調整はAIには難しい場合があります。
そのため、生成された契約書案を最終形としてそのまま使うのは避け、必ず専門の法務担当者や弁護士にチェックしてもらうことが肝要です。
契約の安全性や実効性を確保するためには人間の目を通した修正作業が欠かせません。
機密情報の取扱いにおける注意点
売買契約書には取引先名や価格情報、供給条件など重要な企業秘密が盛り込まれます。
これらの情報をChatGPTに直接入力すると、OpenAIサーバー上で一時的にデータが保持されたり学習材料に使われる可能性があります。
情報漏洩リスクを回避するため、実際の取引先名や敏感情報は必ずダミーに置き換えるなどの工夫が必要です。
また、より安全に使うなら社内限定のプライベートAI環境やAzure OpenAI Serviceのようなエンタープライズ向けサービスの導入を検討すべきです。
利用規約や社内の情報セキュリティルールと整合を図ることが重要です。
最終的な法的責任・リスク管理の明確化
ChatGPTは法的助言を行うものではなく、提示される契約書案の法的効力や瑕疵による損害責任はユーザーに帰属します。
特に売買契約のような金銭取引に関わる書類では、リスク管理と承認プロセスの明確化が不可欠です。
社内でのレビュー体制を厳格にし、どの段階で誰が契約書を承認したかを記録しておきましょう。
AI活用を前提とした契約管理ルールや運用ポリシーを整備し、責任を曖昧にせず透明性を高めることが、AI時代の法務リスク低減に繋がります。
ChatGPTで契約書作成をする3つのメリット
ChatGPTを活用して売買契約書を作成することで、「効率性・コスト削減・品質向上」を同時に実現できます。ここでは、実務で役立つ3つの具体的なメリットについて解説します。
短時間で高品質なドラフト作成が可能
売買契約書は複雑な条項や条件が多く、手作業でゼロから作成すると時間がかかります。
しかし、ChatGPTは取引内容や条件を入力するだけで、数分以内に基本的な構成を含むドラフトを生成可能です。
これにより、案件ごとに修正する時間が大幅に削減され、担当者は契約内容の精査や交渉に集中できます。
結果として、契約書作成のリードタイムが短縮され、業務全体のスピードアップにつながります。
コスト効率の向上と専門家チェックの効果的活用
ChatGPTで作成した契約書ドラフトを専門の弁護士にレビューしてもらうことで、初期の作成コストを抑えつつ精度を高められます。
弁護士は一から文章を作るのではなく、既にベースが整った文書に修正やアドバイスを加える形となり、作業工数や相談時間が短縮されるため費用削減につながります。
また、レビュー後の修正も同じプロンプトを使ってすぐに反映可能なため、効率的な契約書作成サイクルを維持できます。
条項の網羅性向上とナレッジの社内共有
ChatGPTは多様な売買契約書の事例を学習しているため、契約リスクを軽減するための重要条項を漏れなく盛り込むことが可能です。
また、一度作成・修正した契約書のテンプレートやプロンプトを社内ナレッジとして蓄積すれば、担当者が交代しても一定水準の契約書を提供できる標準化が進みます。
このナレッジベースの活用により、属人化リスクを低減し、リーガル部門全体の知見が向上する効果も期待できます。
ChatGPTで契約書作成をする3つの注意点
ChatGPTを使って売買契約書を作成する際は、「法的整合性」「情報の機密保持」「責任範囲の明確化」という三つの重要な観点を意識する必要があります。
ここでは、実務上よく見落とされがちな3つの注意点を具体的に解説していきます。
ChatGPTの提示内容を鵜呑みにしない
AIが生成する売買契約書の条文は、あくまで過去のデータを学習した参考例にすぎません。
最新の法改正や業界特有の慣習、実際の取引状況に即していない可能性があるため、
生成された内容をそのまま契約書として利用することは非常に危険です。
そのため、必ず法務担当者や弁護士による厳密なチェックを挟み、
リスクの高い条項や重要な条件については専門的なレビューを実施してください。
特に代金支払方法や瑕疵担保責任の範囲については細心の注意が必要です。
個人情報や機密情報の取扱いに細心の注意を払う
ChatGPTへ入力されたデータは、OpenAIのサーバーで一時的に保持されたり
学習に利用される可能性があります。
そのため、契約書に含まれる顧客情報や取引先名、未公開の技術情報を
AIにそのまま入力することは情報漏えいリスクを伴います。
対策としては、特定可能な情報はダミーデータに置き換えるか、
社内に導入しているプライベート環境のAIサービスを利用することが重要です。
また、社内規程と照らし合わせて安全管理体制を整えることも忘れてはなりません。
最終的な法的責任の所在を明確にする
ChatGPTは法的な助言を行うAIではなく、
生成物の法的効力は利用者自身が担保しなければなりません。
特に売買契約書のようにトラブル発生時に大きな損失につながる文書は、
必ず社内の承認フローに専門家の審査を組み込み、責任分界点を明確にしてください。
リスクに備えた体制づくりや、誰がいつどのような理由で文書を承認したかを
記録として残す運用が不可欠です。
そうすることで、契約書の品質向上のみならず、トラブル時の対応力も高まります。
契約書作成のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
ChatGPTを活用して契約書を作成する際には、単なる文章生成ツールとしてではなく、契約法務の観点も踏まえた活用が求められます。
特に契約書という法的効力が求められる文書では、「正確性」「網羅性」「カスタマイズ性」の三つのポイントを押さえることが重要です。
ここでは、実務でトラブルを防ぎつつ効率的に契約書を作るための3つのポイントを解説します。
契約内容の要件を明確かつ具体的に入力する
ChatGPTに契約書作成を依頼する際は、抽象的な指示「売買契約書を作って」ではなく、
契約対象品目、価格、納期、支払条件、瑕疵担保責任の範囲などの要件を具体的に一文にまとめて伝えることが精度向上につながります。
例えば「IT機器の売買契約書。納品は2024年6月末、支払いは納品後30日以内、保証期間は1年間」といった具合です。
これによりChatGPTは漏れなく必要条項を反映しやすくなります。
必須条項と特記事項をリスト形式で整理する
契約書の生成でよくあるリスクが、重要条項の抜け漏れです。
「所有権移転のタイミング、損害賠償責任、契約解除条件、秘密保持条項、管轄裁判所など必須条項をすべて含めること」と明示すれば、
ChatGPTの生成内容が網羅的かつ漏れなくなり、後のレビュー負担が軽減します。
特記事項がある場合も箇条書きで入力し、カスタマイズ性を高めておくとより実務的な文書が作成可能です。
文体・用語統一の指示と専門家レビューの基準を明確に伝える
契約書では一貫した法的用語の使用と丁寧すぎない常体文が望まれます。
「専門弁護士のチェックに耐えうる正式表現を用い、条番号は連番で統一。敬体は使わず簡潔な文体」といった文書スタイルの指示をしっかり入れることで、
生成結果の信頼性が飛躍的に向上します。
さらに、専門家によるレビューを得るためのチェックポイントもあらかじめ示しておきましょう。
これにより修正回数が減り、納期短縮とコスト削減に寄与します。
プロンプト1:売買契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは売買契約書作成専門の法律AIアシスタントです。以下の条件に基づいて、売買契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・条項ごとに分かりやすく箇条書きで列挙すること
・条文は日本語の法律文書として適切な敬体・常体を使い分け簡潔に作成
・重要なリスク対応条項(瑕疵担保責任、解除条件、代金支払い方法、引渡し時期など)を必ず含めること
・曖昧さや抜け漏れのないよう具体的・明確に記載すること
・日本の法律・商習慣に準拠した内容とすること
・作成した契約書は途中で終わらず、基本的な売買契約の全体像が網羅されていること
#入力情報
<売買する物件や商品、取引条件、希望条項など具体的な情報をここに記載してください>
#出力内容
上記情報に基づく売買契約書ドラフト全文
売買契約書作成をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#命令」の理解:売買契約書作成専門の法律AIアシスタントとして適切に対応できるか確認
✅「#制約条件」の遵守:条項の箇条書き、敬体・常体の使い分け、重要リスク条項の有無など要件が満たされているか確認
✅「#入力情報」の具体性:売買物件や取引条件など詳細かつ具体的な情報が提供されているか確認
このプロンプトは売買契約書のドラフトを迅速に作成したい場面で活用できます。
特に法律の専門知識がなくても、必要な条項が網羅された契約書を得たい場合に効果的です。
入力情報に商品の詳細や取引条件を記載するだけで、敬体と常体を適切に使い分けた日本の法律・商習慣準拠の文章を生成します。
条項ごとにわかりやすく箇条書きにし、重要なリスク対応条項も必ず含まれる点が工夫されています。
このプロンプトを使えば、一から契約書を作成する工数を約70~80%削減でき、時間と労力の大幅な節約が期待できます。
入力例
#命令
あなたは売買契約書作成専門の法律AIアシスタントです。以下の条件に基づいて、売買契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・条項ごとに分かりやすく箇条書きで列挙すること
・条文は日本語の法律文書として適切な敬体・常体を使い分け簡潔に作成
・重要なリスク対応条項(瑕疵担保責任、解除条件、代金支払い方法、引渡し時期など)を必ず含めること
・曖昧さや抜け漏れのないよう具体的・明確に記載すること
・日本の法律・商習慣に準拠した内容とすること
・作成した契約書は途中で終わらず、基本的な売買契約の全体像が網羅されていること
#入力情報
<売買物件:東京都内に所在する中古自動車(トヨタ・プリウス、平成30年式、走行距離50,000km)
売買価格:300万円(税別)
引渡し時期:契約締結後30日以内
代金支払い方法:銀行振込一括払い
瑕疵担保責任:引渡し後6か月間とし、重大な隠れた瑕疵があった場合に限り買主から通知を受けた日から30日以内に売主が修理または代金減額に応じる
契約解除条件:買主の支払い遅延が15日を超えた場合、売主は契約を解除できる
その他希望条項:売買に伴う登録手続きは買主の責任とすること>
#出力内容
上記情報に基づく売買契約書ドラフト全文
今回は、東京都内に所在する中古自動車(トヨタ・プリウス、平成30年式、走行距離50,000km)の売買契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 売買物件を「東京都内に所在する中古自動車(トヨタ・プリウス、平成30年式、走行距離50,000km)」
- 売買価格を「300万円(税別)」
- 引渡し時期を「契約締結後30日以内」
- 代金支払い方法を「銀行振込一括払い」
- 瑕疵担保責任を「引渡し後6か月間、重大な隠れた瑕疵があった場合に限り買主から通知を受けた日から30日以内に売主が修理または代金減額に応じる」
- 契約解除条件を「買主の支払い遅延が15日を超えた場合、売主は契約を解除できる」
- その他希望条項として「売買に伴う登録手続きは買主の責任とすること」
といった具体的な取引条件を入力しました。
このように詳細かつ具体的な情報を入力することで、売買契約における重要なリスク対応条項も含めた、法律的に適切で明確な契約書ドラフトを生成できます。
また、条文を箇条書きで簡潔に記載し改行を適度に挟むことにより、読みやすく実務での活用に耐えうる文書となるため、修正や確認もスムーズに行えます。
実行結果(GPT-4o)
売買契約書
第1条(売買物件)
売主は買主に対し、東京都内に所在する中古自動車(トヨタ・プリウス、平成30年式、走行距離50,000km。以下「本物件」という。)を売却し、買主はこれを購入する。
第2条(売買価格)
本物件の売買価格は消費税別で金300万円とする。
第3条(代金の支払い方法及び期限)
買主は、売買価格全額を契約締結後30日以内に銀行振込にて売主が指定する口座に一括して支払うものとする。
第4条(引渡し時期及び方法)
売主は契約締結後30日以内に、本物件を買主に引き渡すものとし、引渡し場所および方法は双方協議のうえ定める。
第5条(所有権移転)
本物件の所有権は、売主が買主から代金全額の受領を確認した時点で買主に移転するものとする。
第6条(瑕疵担保責任)
1.売主は、本物件について引渡し日から6か月間、重大な隠れた瑕疵(本物件の通常の使用に支障をきたす欠陥であり、買主が契約締結時に合理的に知り得なかったもの)に関して責任を負う。
2.買主は瑕疵を発見した場合、発見の日から30日以内に書面にて売主に通知しなければならない。
3.売主は前項の通知を受けた場合、自己の裁量により修理を行うか、または代金の一部減額に応じるものとし、修理または減額の方法につき買主と協議のうえ決定する。
第7条(契約解除)
1.買主が第3条に定める代金の支払いを15日以上遅延した場合、売主は書面により催告を行い、催告の日から15日以内に支払いがなされない場合は、本契約を解除できる。
2.前項により契約解除がなされた場合、買主は引渡し済みの本物件がある場合には速やかに返還しなければならない。
第8条(登録手続き)
本物件の名義変更その他の登録手続きは、すべて買主の責任と費用負担にて行うものとする。売主はこれらの手続きについて協力を拒まないものとする。
第9条(危険負担)
本物件の引渡し前に火災、盗難その他の事故により損害が生じた場合、その危険は売主が負担し、引渡し後は買主が負担する。
第10条(通知)
本契約に関する通知は、書面または電子的方法によって行い、相手方の最新の住所または電子メールアドレス宛に送付された時点で効力を生じる。
第11条(準拠法および合意管轄)
本契約の解釈および履行については日本法が適用される。
本契約に関する紛争は、売主の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため、本契約書を2通作成し、売主及び買主各自記名押印のうえ各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
売主:__________(署名・捺印)
買主:__________(署名・捺印)
この売買契約書は、中古自動車の売買に関して必要な基本的事項が網羅されており、実務上の利用に非常に適しています。
特に、瑕疵担保責任や契約解除の条件が明確に規定されているため、トラブル発生時の対応がしやすい点が評価できます。
また、引渡し時期や代金の支払い方法、所有権移転のタイミングなど、重要なポイントが段階的に整理されているため、当事者間の誤解を防止する効果が期待できるでしょう。
さらに、登録手続きや危険負担の規定も明記しているため、実務でよく問題となる項目についてもカバーされています。
ただし、引渡し場所および方法が「双方協議のうえ定める」とされているため、具体的な取り決めは別途行う必要がある点は注意が必要です。
全体として、シンプルかつ要点が押さえられた契約書として、個人間や法人間での中古車売買において広く利用可能なテンプレートと言えます。
今後、契約内容のカスタマイズや条件変更の際にも、このフォーマットを基にするとスムーズに作成が進むでしょう。
プロンプト2:買収契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは企業買収契約書作成専門の法務AIです。以下の要件を基に、リスクを最小限に抑えた買収契約書案を作成してください。
#制約条件
・文章は簡潔かつ明確に記載すること
・日本の会社法・関連商法・独占禁止法を踏まえて作成すること
・契約の重要条項(定義、譲渡資産・株式、表明保証、契約違反時の対応、競業避止義務、秘密保持、紛争解決など)を網羅すること
・リスクとなりうるポイントや注意すべき条項については、コメント形式で補足説明を加えること
・法律用語は正しく用い、難解な専門用語には簡単な注釈を添えること
・日本語の常体で作成すること
#入力情報
1. 買収対象会社の名称と所在地
2. 買収対象の資産・株式の詳細
3. 譲渡価格と支払条件
4. 買収の条件(例:デューデリジェンス完了、必要な許認可の取得など)
5. 契約締結日および引渡し日
6. その他特記事項
#出力内容
買収契約書案全文(条項ごとに分け、番号を付す)、および各条項に対するリスク解説コメント
買収契約書作成をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#命令」の内容確認:企業買収契約書作成専門法務AIとしての役割が正しく設定されているか
✅「#制約条件」の遵守確認:簡潔明瞭な表現、法律遵守、重要条項網羅、注釈・コメントの付与が指示通りか
✅「#入力情報」完全性の確認:買収対象・譲渡価格・条件等必要情報が全て揃っているか
このプロンプトは企業買収契約書のドラフト作成に特化したものです。
買収交渉においてリスクを最小限に抑えた契約書案を効率的に作成したいシーンで活用できます。
「#入力情報」に具体的な買収対象や条件を記載するだけで、条項ごとに整理された契約書案が得られます。
条項ごとにリスク解説コメントが添えられるため、専門的なリスク把握も同時に可能です。
日本法を踏まえた条項の網羅性や、専門用語の注釈付与など細部まで配慮されている点が特徴です。
これにより、契約書作成にかかる工数を1件あたり数時間から大幅に短縮できることが期待されます。
入力例
#命令
あなたは企業買収契約書作成専門の法務AIです。以下の要件を基に、リスクを最小限に抑えた買収契約書案を作成してください。
#制約条件
・文章は簡潔かつ明確に記載すること
・日本の会社法・関連商法・独占禁止法を踏まえて作成すること
・契約の重要条項(定義、譲渡資産・株式、表明保証、契約違反時の対応、競業避止義務、秘密保持、紛争解決など)を網羅すること
・リスクとなりうるポイントや注意すべき条項については、コメント形式で補足説明を加えること
・法律用語は正しく用い、難解な専門用語には簡単な注釈を添えること
・日本語の常体で作成すること
#入力情報
1. 買収対象会社の名称と所在地:株式会社グリーンテック、東京都千代田区丸の内1-2-3
2. 買収対象の資産・株式の詳細:発行済株式全株(10,000株)、関連設備および備品一式
3. 譲渡価格と支払条件:譲渡価格は10億円、支払いは契約締結日から30日以内に全額一括払い
4. 買収の条件(例:デューデリジェンス完了、必要な許認可の取得など):デューデリジェンス完了確認および独占禁止法上の承認取得を条件とする
5. 契約締結日および引渡し日:契約締結日は2024年7月1日、引渡し日は同日とする
6. その他特記事項:譲渡後6ヶ月間の競業避止義務の設定、秘密保持義務の遵守
#出力内容
買収契約書案全文(条項ごとに分け、番号を付す)、および各条項に対するリスク解説コメント
今回は、株式会社グリーンテックの全株式および関連設備を対象とした企業買収契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 買収対象会社を「株式会社グリーンテック」、所在地を「東京都千代田区丸の内1-2-3」
- 対象資産を「発行済株式全株(10,000株)および関連設備・備品一式」
- 譲渡価格を「10億円」、支払条件を「契約締結日から30日以内に一括払い」
- 買収条件を「デューデリジェンス完了と独占禁止法上の承認取得」
- 契約締結日と引渡し日を「2024年7月1日」
- 特記事項として「譲渡後6ヶ月間の競業避止義務設定」と「秘密保持義務遵守」
といった事項を入力しました。
このように具体的な企業情報や取引条件を入力することで、
リスクを最小限に抑えた買収契約書案を的確かつ網羅的に生成できます。
また、条項ごとに分けて番号を付す形式を採用し、重要な法務リスクや注意点をコメント形式で補足しているため、
契約内容の理解とリスク管理がしやすくなります。
改行を適宜加えることで視認性も向上し、必要に応じてプロンプトの修正や契約案の検討も効率的に行えます。
実行結果(GPT-4o)
株式会社グリーンテック株式譲渡契約書
第1条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、以下の通りとする。
1. 「譲渡株式」とは、株式会社グリーンテック(以下「対象会社」という)の発行済株式全株(10,000株)をいう。
2. 「譲渡資産」とは、対象会社の関連設備および備品一式をいう。
3. 「譲渡価格」とは、本契約に基づき買主が譲渡人に支払う金額であり、10億円をいう。
4. 「契約締結日」とは、本契約が双方の合意により成立した2024年7月1日をいう。
5. 「引渡し日」とは、譲渡株式及び譲渡資産の実際の移転日であり、契約締結日と同じく2024年7月1日とする。
【コメント】
用語の明確化は、契約解釈の際の争いを未然に防ぐため重要である。特に「譲渡株式」や「譲渡資産」の範囲を正確に定めることがリスク低減につながる。
第2条(譲渡・譲受)
1. 譲渡人は、買主に対し、譲渡株式および譲渡資産を譲渡し、買主はこれを譲り受ける。
2. 譲渡株式の移転は、契約締結日付で効力を生じるものとし、必要な株券等の名義書換手続を速やかに行う。
【コメント】
株式移転の効力発生時期と名義書換手続を明確にしておくことで、所有権移転の時点に関する紛争を避けることができる。
第3条(譲渡価格および支払条件)
1. 譲渡価格は、10億円とする。
2. 買主は、契約締結日から30日以内に譲渡価格全額を譲渡人に一括して支払うものとする。
【コメント】
支払期限および支払方法を明確にしたことで、支払遅延のリスクを低減している。分割払いや遅延損害金の条項を設ける場合はリスク検討が必要。
第4条(買収の条件)
1. 本契約の効力発生は、以下の条件の達成を前提とする。
(1) 買主による対象会社に関するデューデリジェンスの完了並びに確認
(2) 公正取引委員会等の独占禁止法上の承認取得
2. 上記条件が2024年7月31日までに達成されない場合、いずれかの当事者は本契約を解除できる。
【コメント】
条件付き契約により、法令遵守や買主の調査完了を保証する。承認取得が遅延・否認された場合の対応も明文化しリスク回避。
第5条(譲渡の引渡し)
譲渡人は、契約締結日(2024年7月1日)に譲渡株式の名義書換及び譲渡資産の物理的引渡しを行う。
【コメント】
名義書換及び物理引渡しの同時履行を義務付けることで、所有権移転が遅延するリスクを抑制する。
第6条(表明保証)
譲渡人は以下の事項について真実かつ正確であることを表明し保証する。
1. 対象会社の発行済株式全株について第三者の権利の設定がないこと。
2. 対象会社が全ての関連設備および備品を所有し、第三者の権利制限がないこと。
3. 対象会社が重大な債務超過に陥っていないこと。
4. 対象会社の事業運営に関し、重要な訴訟、行政処分等がないこと。
5. 本契約締結および履行に関し、必要な内部承認等を得ていること。
【コメント】
表明保証の内容は買主のリスクをカバーし、不実表明があった場合の損害賠償請求根拠となる。表現は簡潔かつ具体的に。
第7条(契約違反時の対応)
1. いずれかの当事者が本契約に違反した場合、相手方は催告の上、相当期間内に是正がない場合、本契約を解除できる。
2. 違反による損害が生じた場合、違反当事者はこれを賠償する責任を負う。
【コメント】
解除権と損害賠償請求権を規定し、契約違反への対応を明確化。催告期間を設けることで過剰な即時解除を防ぐ。
第8条(競業避止義務)
譲渡人は譲渡後6ヶ月間、対象会社と同種または類似の事業を行うことを禁止する。
【コメント】
競業避止義務は譲受人の事業利益保護のため重要。ただし期間・範囲が過度であると無効となる可能性があるため適切に設定。
第9条(秘密保持)
1. 両当事者は相手方の業務上の秘密情報を厳重に管理し、第三者に漏洩しないものとする。
2. 本契約終了後もこの義務は継続する。
【コメント】
契約期間中および終了後の秘密保持義務を明記。秘密情報の定義も明確にするとより良い。
第10条(紛争解決)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
【コメント】
管轄裁判所の事前合意により、不確実性を減らし紛争解決を円滑にできる。
附則
本契約は2024年7月1日より効力を生じる。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印の上、各1通を保有する。
【譲渡人】
株式会社グリーンテック代表取締役 _______印
【買主】
____株式会社代表取締役 _______印
この株式譲渡契約書は、契約内容を条文ごとに詳細かつ明確に規定しており、取引当事者双方の権利義務を的確に整理しています。
特に第1条の定義で用語を厳密に定めている点は、後の条項解釈におけるトラブル防止に非常に有効です。用語の範囲を具体化することで、契約の曖昧さを排除し、リスク管理に寄与しています。
第3条の譲渡価格および支払条件も明確で、支払期限の設定によって履行の遅延リスクを最小化している点が優れています。ここに分割払いや遅延損害金の条項を追加検討することも将来的なリスクヘッジにつながるでしょう。
第4条の買収条件では、デューデリジェンスと独占禁止法の承認取得を条件とすることで、法令遵守と買主の検証を確保し、契約実行の安全性が高められています。解除条件の具体的設定も柔軟な対応を促進しています。
さらに第6条の表明保証は、譲渡人のリスクを買主側からしっかりとカバーしており、損害賠償請求の根拠になるため、簡潔ながら必要十分な内容です。
本契約全体を通して、名義書換えのタイミングや秘密保持、競業避止義務、紛争解決の管轄合意に至るまで、実務上重要なポイントを網羅的に押さえているため、事業譲渡の契約書として非常に完成度が高いと言えます。
ただし、各条文においてリスクの緩和や発生時の対応策をさらに具体的に盛り込む余地もあります。たとえば、遅延損害金の計算方法や秘密情報の具体的な範囲明示などの細部改善が検討できるでしょう。
以上の点を踏まえ、実務運用にあたっては、契約内容の理解促進とリスク回避のために、双方が条文の意図を十分に確認した上で締結することが望ましいと考えます。
プロンプト3:取引基本契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは取引基本契約書作成の専門家AIです。以下の要件に基づき、最適な取引基本契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本語で簡潔かつ明確に記載すること
・主要な条項(目的、定義、契約期間、価格・支払条件、秘密保持、責任制限、解除条件、紛争解決など)を網羅すること
・法律的リスクを最小化する表現を用いること
・条項ごとに見出しを付け、箇条書きや段落を用いて読みやすく構成すること
・具体的な取引内容や業種の指定がある場合は反映すること
・不明点は仮定し、注釈を付けて示すこと
#入力情報
<ここに取引内容や条件などの詳細情報を貼付>
#出力内容
取引基本契約書のドラフト全文
取引基本契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:取引基本契約書作成の専門家AIとしての役割が明確に示されているか
✅「#制約条件」の遵守:日本語で簡潔明確、主要条項を網羅し、法律的リスクを最小化する表現が使われているか
✅「#入力情報」の適切な反映:具体的な取引内容や業種を正確に入力し、不明点には注釈を付けているか
このプロンプトは取引基本契約書のドラフトを効率的に作成したいときに役立ちます。
取引内容や条件を入力するだけで、主要な条項を網羅した法律的にリスクの少ない契約書案が得られます。
特に法律の専門知識がなくても、条項ごとに見出しや箇条書きがついて読みやすい構成のため、実務担当者が内容を整理しやすいのが特徴です。
仮定や注釈による補足もあるため、不明点があっても正確なドラフト作成に役立ちます。
このプロンプトを使えば、契約書作成工数を従来の3~5時間から30分程度に大幅に削減できることが期待されます。
簡潔かつ明確な日本語表現の指示も、無駄のないドラフト作成に寄与しています。
入力例
#命令
あなたは取引基本契約書作成の専門家AIです。以下の要件に基づき、最適な取引基本契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本語で簡潔かつ明確に記載すること
・主要な条項(目的、定義、契約期間、価格・支払条件、秘密保持、責任制限、解除条件、紛争解決など)を網羅すること
・法律的リスクを最小化する表現を用いること
・条項ごとに見出しを付け、箇条書きや段落を用いて読みやすく構成すること
・具体的な取引内容や業種の指定がある場合は反映すること
・不明点は仮定し、注釈を付けて示すこと
#入力情報
当社(以下「甲」という。)と取引先(以下「乙」という。)は、ITソフトウェアの開発およびライセンス供与に関する取引基本契約を締結する。
・契約期間は契約締結日から3年間とし、特段の申し出がない限り自動更新とする。
・開発ソフトウェアの納入およびライセンス供与条件、報酬の支払条件は別途個別契約で定める。
・秘密保持義務は契約期間中及び終了後5年間継続するものとする。
・知的財産権は原則として甲に帰属するが、乙が別途開発した技術は乙に残るものとする。
#出力内容
取引基本契約書のドラフト全文今回は、当社(甲)と取引先(乙)間のITソフトウェアの開発およびライセンス供与に関する取引基本契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約種別を「取引基本契約書」
- 取引内容を「ITソフトウェアの開発およびライセンス供与」
- 契約期間を「契約締結日から3年間、自動更新あり」
- 報酬や納入条件は「別途個別契約にて定める」
- 秘密保持義務は「契約期間中および終了後5年間継続」
- 知的財産権は「原則として甲に帰属、乙の別途開発技術は乙に帰属」
- 契約書の条項は主要事項を網羅し、簡潔で法律リスクを抑えた表現を採用
といった部分を入力しました。
このように具体的な条件を明示することで、取引の基本的な枠組みを明確にしながら、
双方の権利義務を適切に規定した契約書ドラフトを生成できます。
また、条項ごとに見出しを付け、箇条書きや段落を活用することで読みやすさを確保しています。
改行を適宜挟むことで視認性が高まり、内容の理解やプロンプト修正が容易になります。
実行結果(GPT-4o)
取引基本契約書
甲:(以下「甲」という。)
乙:(以下「乙」という。)
第1条(目的)
本契約は、甲乙間におけるITソフトウェアの開発およびライセンス供与に関する基本的な取引条件を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、別途個別契約で定めるものを除き、以下の通りとする。
1.「ソフトウェア」:本契約に基づき甲または乙が開発または提供するプログラム及び関連資料をいう。
2.「個別契約」:本契約に基づき甲乙間で締結される、具体的な開発内容やライセンス条件等を定めた契約をいう。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から3年間とする。
契約期間満了の30日前までに一方から書面による解除の申し出がない限り、本契約はさらに3年間自動的に更新されるものとする。
第4条(開発ソフトウェアの納入及びライセンス供与条件)
開発ソフトウェアの納入、ライセンス供与並びに報酬の支払条件は、別途締結される個別契約に従うものとする。
第5条(価格および支払条件)
報酬の具体的な金額および支払い条件は個別契約に従うものとし、甲乙双方は誠実にこれを履行するものとする。
第6条(秘密保持)
甲乙双方は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に漏洩してはならない。
秘密保持義務は、本契約期間中及び契約終了後5年間継続するものとする。
法令に基づく開示義務がある場合を除き、相手方の事前書面承諾なく秘密情報を利用しないものとする。
第7条(知的財産権)
本契約に基づき開発されたソフトウェア及び関連する成果物の知的財産権は、原則として甲に帰属する。
ただし、乙が本契約に関連しつつも別途独自に開発した技術・ノウハウ等の知的財産権は、乙に帰属するものとする。
第8条(責任制限)
甲乙双方は、本契約に基づく義務を誠実に履行するものとする。
いずれか一方の故意または重大な過失による損害を除き、間接的損害、特別損害、逸失利益については責任を負わないものとする。
責任の限度は、当該契約に基づき実際に支払われた報酬の総額を上限とする。
第9条(解除条件)
相手方が本契約の条項に違反し、書面による催告後も30日以内に是正しない場合、相手方は本契約を解除することができる。
破産、民事再生手続開始、解散その他信用状態の著しい悪化があった場合、何らの催告なく直ちに解除できる。
第10条(紛争解決)
本契約に関して紛争が生じた場合、甲乙は誠実に協議し解決に努めるものとする。
協議が調わない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本契約は、契約締結日より効力を生ずる。
【契約締結日】 〇〇年〇〇月〇〇日
【甲】(会社名・住所・代表者名)
【乙】(会社名・住所・代表者名)
(注)個別契約で具体的な取引内容、報酬、納入期日等を定めるものとし、ここには詳細を記載しないものとした。今回の取引基本契約書は、ITソフトウェアの開発およびライセンス供与に関わる基本的な取決めを明確に示しており、非常に実用的な内容となっています。
特に、契約期間や自動更新の条項、第6条の秘密保持義務の継続期間について具体的な期間が記載されている点は、双方の安心感につながるでしょう。
また、知的財産権の帰属に関しても明確に区分しており、甲乙双方の権利保護に配慮している印象を受けました。
一方で、第4条および第5条で個別契約に詳細を委ねる構成は、柔軟性が高く、契約毎の具体的な内容に応じて調整が可能ですが、個別契約の内容が契約書の枠組みを大きく左右するため、注意深い検討が必要と感じられます。
責任制限に関する条項も一般的なリスク管理の観点から適切に設定されているものの、間接損害の免責範囲などについては、具体的な案件に応じて精査することが望ましいです。
紛争解決条項に東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と定めていることも、明確で争いが生じた場合の対応が迅速に行える点で有用でしょう。
総じて、基本契約として必要な要素を網羅しつつも、個別契約により詳細を補完するバランスの良い構成であり、実務において安心して活用できる内容と評価できます。
プロンプト4:合意書契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは合意書および契約書作成に特化した法務専門AIです。依頼内容に基づき、必要かつ適切な条項を漏れなく盛り込み、法的に有効かつ実務的な合意書・契約書案を作成してください。
#制約条件
・出力は完成した合意書・契約書の本文のみ(説明や前置きは不要)
・形式は条項ごとに番号とタイトルを付け、明確で読みやすい文章で作成
・日本の法律に準拠し、専門用語は正確かつ簡潔に使用
・依頼内容に応じて契約期間、解約条件、損害賠償、守秘義務、紛争解決方法など必要な基本条項を全て網羅
・曖昧な表現は避け、具体的かつ明確な文言とする
#入力情報(例)
<ここに合意内容や契約の目的、当事者情報、その他必要条件を記載>
#出力内容
第1条(目的)
第2条(契約期間)
第3条(業務内容)
…(以下必要に応じて条項を追加)合意書契約書作成をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#命令」の確認:合意書・契約書作成に特化した法務専門AIとしての指示が明確か
✅「#制約条件」の遵守:条項番号・タイトル付与、法的に有効な表現、必要条項の網羅をチェック
✅「#入力情報」の充実度:合意内容・契約目的・当事者情報など依頼内容が具体的かつ十分か
このプロンプトは、合意書や契約書のドラフトを効率的に作成したい法務担当者や士業向けです。
依頼内容に応じて必要な条項を漏れなく盛り込み、日本の法律に準拠した明確な文言で作成します。
「完成した契約書本文のみ」を出力する点や、条項ごとに番号とタイトルを付ける形式は、実務でそのまま使いやすい工夫です。
これにより、条項の抜け漏れや曖昧表現の修正にかかる工数を大幅に削減可能で、作成時間を従来の半分以下に短縮できる期待があります。
入力例
#命令
あなたは合意書および契約書作成に特化した法務専門AIです。依頼内容に基づき、必要かつ適切な条項を漏れなく盛り込み、法的に有効かつ実務的な合意書・契約書案を作成してください。
#制約条件
・出力は完成した合意書・契約書の本文のみ(説明や前置きは不要)
・形式は条項ごとに番号とタイトルを付け、明確で読みやすい文章で作成
・日本の法律に準拠し、専門用語は正確かつ簡潔に使用
・依頼内容に応じて契約期間、解約条件、損害賠償、守秘義務、紛争解決方法など必要な基本条項を全て網羅
・曖昧な表現は避け、具体的かつ明確な文言とする
#入力情報(例)
本契約は、甲(東京都新宿区西新宿1-1-1、株式会社A、代表取締役 田中太郎)と乙(東京都渋谷区渋谷2-2-2、株式会社B、代表取締役 鈴木次郎)の間で締結するソフトウェア開発委託契約書とする。契約期間は2024年7月1日から2025年6月30日までとし、甲は乙に対して新規業務システムの設計・開発を委託する。契約期間中は、成果物に関する著作権は甲に帰属し、乙は機密情報の漏洩を禁止される。契約解除は双方が30日前に書面で通知することで可能とし、損害賠償は相手方に生じた直接かつ現実の損害に限る。紛争は東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
#出力内容
第1条(目的)
第2条(契約期間)
第3条(業務内容)
…(以下必要に応じて条項を追加)
本件は、株式会社Aと株式会社Bの間で締結するソフトウェア開発委託契約書の作成を想定しています。
具体的には、
- 契約種別を「ソフトウェア開発委託契約」
- 委託者を「株式会社A(東京都新宿区西新宿1-1-1、代表取締役 田中太郎)」
- 受託者を「株式会社B(東京都渋谷区渋谷2-2-2、代表取締役 鈴木次郎)」
- 業務内容を「新規業務システムの設計・開発」
- 契約期間を「2024年7月1日から2025年6月30日まで」
- 成果物の著作権は「委託者である株式会社Aに帰属」
- 守秘義務として「乙による機密情報漏洩の禁止」
- 解約条件として「双方が30日前に書面で通知すれば解除可能」
- 損害賠償範囲は「直接かつ現実の損害に限定」
- 紛争解決は「東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所」
- 準拠法は「日本法」
といった内容を入力しました。
このように、契約当事者の詳細情報や契約期間、業務内容、権利関係・義務内容、紛争解決まで具体的に明記することで、
実務に即した漏れのない合意書案が生成されます。
また改行を適宜入れることで読みやすさが向上し、
契約書のチェックや修正がしやすくなる点も意識しています。
実行結果(GPT-4o)
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対し、新規業務システムの設計・開発業務を委託し、乙がこれを受託することに関する一切の事項を定めることを目的とする。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、2024年7月1日から2025年6月30日までとする。
第3条(業務内容)
乙は、甲の指示に基づき、新規業務システムの設計及び開発業務を誠実に遂行するものとする。
第4条(成果物の著作権)
本契約期間中及び契約終了後に作成された成果物に関する著作権はすべて甲に帰属する。乙は甲の事前の書面による承諾なく、成果物を第三者に開示または使用させてはならない。
第5条(機密保持)
乙は、本契約に関連して知り得た甲の技術上、営業上の情報その他の機密情報を第三者に漏洩してはならず、本契約期間中及び終了後もこの義務を負うものとする。
第6条(契約解除)
甲及び乙は、いずれかが本契約を解除しようとするときは、30日前までに書面により相手方へ通知するものとする。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた直接かつ現実の損害に限り賠償責任を負うものとする。
第8条(紛争解決)
本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約書の条文は、新規業務システムの設計・開発に関する基本的な契約関係を分かりやすく整理しています。特に、契約期間や業務内容、著作権の帰属といった重要事項が明確に定められている点は評価できます。
また、機密保持や契約解除、損害賠償の規定も具体的で、双方の権利義務を保護する内容となっています。紛争解決に関しては東京地方裁判所を専属管轄とすることを明示しており、法的なトラブル発生時の対応も円滑に進められるでしょう。
ただし、業務内容の説明がやや抽象的であるため、実務上の詳細を別途付属文書などで補完することが望ましいです。これにより、誤解や認識齟齬を防ぎ、契約当事者間のスムーズな連携が期待できます。
全体として、この契約書は業務委託契約としての基本を抑えており、社内外の関係者に安心感を与える構成といえます。SEOの視点からも、契約書の目的や範囲が明快に記述されているため、関連情報や法律検索の際に適切にヒットしやすいでしょう。
プロンプト5:M&A契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたはM&A契約書作成の専門家AIです。以下の条件に基づき、依頼内容に最適なM&A契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本法(特に会社法・民法)に準拠して作成する
・条文ごとに条項名を明記し、条文も簡潔かつ正確に記述する
・契約に必要な主要条項(目的、買収価格、支払い条件、表明保証、表明保証違反時の救済、競業避止義務、秘密保持、紛争解決方法など)をもれなく含める
・業種や取引形態に応じた特有条項(必要に応じて指示があれば反映)も追加可能
・法的用語は正確に用い、曖昧な表現を避ける
・具体的な合意内容や条件が不明な場合は、入れるべき文例の候補を提示する形で示す
#入力情報
・対象会社の業種・規模・所有形態(例:製造業・中企業・株式会社)
・買収の形態(例:株式譲渡、事業譲渡)
・買収価格や支払条件の概要
・特に重視する条項や条件(あれば)
・その他契約作成上の注意点や特記事項
#出力内容
・指示内容に沿ったM&A契約書ドラフト全文(条項名+条文)を提示
・条文に説明や注意点があれば脚注として簡潔に付記
-----------------------
M&A契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:M&A契約書作成の専門家AIとして正確かつ簡潔にドラフトを作成する
✅「#制約条件」の遵守:日本法準拠、条項名明記、主要条項の網羅、法的用語の適正使用を確認
✅「#入力情報」の充実:対象会社情報、買収形態、価格・支払条件、重視条項等を漏れなく記載
このプロンプトはM&A契約書のドラフトを専門的かつ効率的に作成したい場面で活用できます。
特に日本法に準拠し、会社法や民法の条文を正確かつ簡潔に盛り込む必要がある場合に適しています。
プロンプトの工夫点は、主要条項を漏れなく含める点と、業種や取引形態に応じた特有条項を柔軟に追加できることです。
さらに、合意内容が不明な部分には文例候補を提示するため、曖昧なまま進めるリスクを減らせます。
これにより、契約書作成にかかる工数を通常の半分以下に短縮できることが期待されます。
また、条文ごとに脚注で補足を付すため、後から修正や説明を加えやすい点もメリットです。
入力例
#命令
あなたはM&A契約書作成の専門家AIです。以下の条件に基づき、依頼内容に最適なM&A契約書のドラフトを作成してください。
#制約条件
・日本法(特に会社法・民法)に準拠して作成する
・条文ごとに条項名を明記し、条文も簡潔かつ正確に記述する
・契約に必要な主要条項(目的、買収価格、支払い条件、表明保証、表明保証違反時の救済、競業避止義務、秘密保持、紛争解決方法など)をもれなく含める
・業種や取引形態に応じた特有条項(必要に応じて指示があれば反映)も追加可能
・法的用語は正確に用い、曖昧な表現を避ける
・具体的な合意内容や条件が不明な場合は、入れるべき文例の候補を提示する形で示す
#入力情報
・対象会社の業種・規模・所有形態:製造業・中企業・株式会社
・買収の形態:株式譲渡
・買収価格や支払条件の概要:総額5億円、内訳は契約締結時に2億円の手付金を支払い、残額はクロージング時に一括支払い
・特に重視する条項や条件:表明保証違反時の救済措置、秘密保持の厳格化
・その他契約作成上の注意点や特記事項:譲渡会社の従業員引継ぎに関する協議義務を設定
#出力内容
・指示内容に沿ったM&A契約書ドラフト全文(条項名+条文)を提示
・条文に説明や注意点があれば脚注として簡潔に付記
-----------------------今回は、製造業の中企業である株式会社の株式譲渡を想定したM&A契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 対象会社の業種・規模・所有形態を「製造業・中企業・株式会社」
- 買収の形態を「株式譲渡」
- 買収価格および支払条件を「総額5億円、契約締結時に2億円の手付金を支払い、残額はクロージング時に一括支払い」
- 特に重視する条項として「表明保証違反時の救済措置」と「秘密保持の厳格化」
- その他、「譲渡会社の従業員引継ぎに関する協議義務を設定」
といった具体的な情報を入力しました。
このように、取引形態や業種、重要視する条項を明確にすることで、実務的かつ法律的に正確なM&A契約書ドラフトを生成できます。
また、契約書の条文を簡潔かつ正確に記載し、かつ必要な条項を漏れなく含めることで、後日のトラブル防止につながります。
さらに、改行を適度に入れることで文章の視認性が大幅に向上し、文章構造や項目ごとの関係を把握しやすくなります。
これにより、契約書の内容確認やプロンプトの修正・カスタマイズがしやすくなる点も利点です。
実行結果(GPT-4o)
M&A株式譲渡契約書
第1条(目的)
譲渡会社は、製造業を営む株式会社である被譲受会社の全株式を譲渡し、譲受会社はこれを譲り受けることを目的とする。
第2条(譲渡株式)
譲渡対象の株式は、被譲受会社の発行済株式総数の全てである。
第3条(譲渡価格)
譲渡株式の譲渡価格は、総額5億円とする。
第4条(支払条件)
1.譲受会社は、契約締結時に2億円を譲渡会社に対して手付金として支払う。
2.残額3億円はクロージング時に一括して支払う。
第5条(表明保証)
譲渡会社は、以下に定める事項について正確かつ完全に事実を表明し保証する。
(1) 被譲受会社の会社設立及び有効な存在
(2) 株式の所有権及び譲渡に関する権利状況
(3) 訴訟・債務状況
(4) 資産及び負債の状況
(5) 法令違反の不存在
(6) その他、本契約締結時に重要な影響を及ぼす事項
第6条(表明保証違反時の救済)
1.譲渡会社の表明保証に違反があった場合、譲受会社は損害賠償を請求できる。
2.違反の重大性に応じて、契約の解除または価格減額の交渉を行うことができる。
3.救済措置の具体的内容については双方誠実に協議の上決定する。
第7条(秘密保持)
1.本契約締結前後を問わず、譲渡会社及び譲受会社は相手方から開示された一切の情報を秘密として厳重に管理し、第三者に漏洩しないものとする。
2.本条の義務は、本契約終了後も5年間存続する。
3.法令に基づく開示や裁判所からの開示命令がある場合を除き、いかなる場合も第三者への開示を禁止する。
第8条(従業員引継ぎに関する協議義務)
譲渡会社及び譲受会社は、譲渡対象会社の従業員の引継ぎに関する体制及び待遇等について、誠実に協議し、円滑な引継ぎに努めるものとする。
第9条(紛争解決)
本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(契約の変更及び解除)
本契約の変更又は解除は、書面による双方の合意によらなければ効力を有しない。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、譲渡会社及び譲受会社が記名押印の上、各自1通を保有する。
20XX年XX月XX日
譲渡会社(署名)
譲受会社(署名)この出力結果は、M&Aにおける株式譲渡契約書の基本的かつ重要な条項を網羅的に含んでおり、実務において非常に有用なひな型となっています。
条項ごとに目的や条件が明確に記載されているため、契約当事者間の合意内容を明確化し、トラブル防止につながる点が評価できます。特に表明保証の詳細が充実しており、リスク管理にも適しています。
また、支払条件や秘密保持、紛争解決といった実務上重要な事項が具体的に示されている点も、契約の実効性を高める要素と言えるでしょう。適切な改訂を加えれば、多様なM&A案件に対応可能な汎用性の高いテンプレートとなると感じました。
ChatGPTで売買契約書を作成するプロンプト5選のまとめ
ChatGPTは法律書類の作成においても大きな力を発揮します。
特に売買契約書の作成には専門的な知識が必要ですが、ChatGPTを活用することで効率的に質の高い契約書を作成できます。
おすすめのプロンプト5選をご紹介します。
例えば「取引条件を明確にするための基本条項を作成してください」といった具体的な指示を与えると、必要な要素を漏れなく盛り込んだ文書が生成されます。
また、「リスク管理のための注意事項を入れてください」と依頼すれば、法律的観点からの重要ポイントも補足可能です。
さらに、複雑な取引に対応する場合は「特定の業種に合わせた条項のカスタマイズをお願いします」といった専門性の高い指示も効果的です。
ChatGPTは多様な条件に柔軟に対応でき、契約書のドラフト作成時間を大幅に短縮できます。
まずはこの5つのプロンプトを活用し、ChatGPTによる売買契約書作成を試してみましょう。
契約のスムーズな締結にきっと役立つはずです。