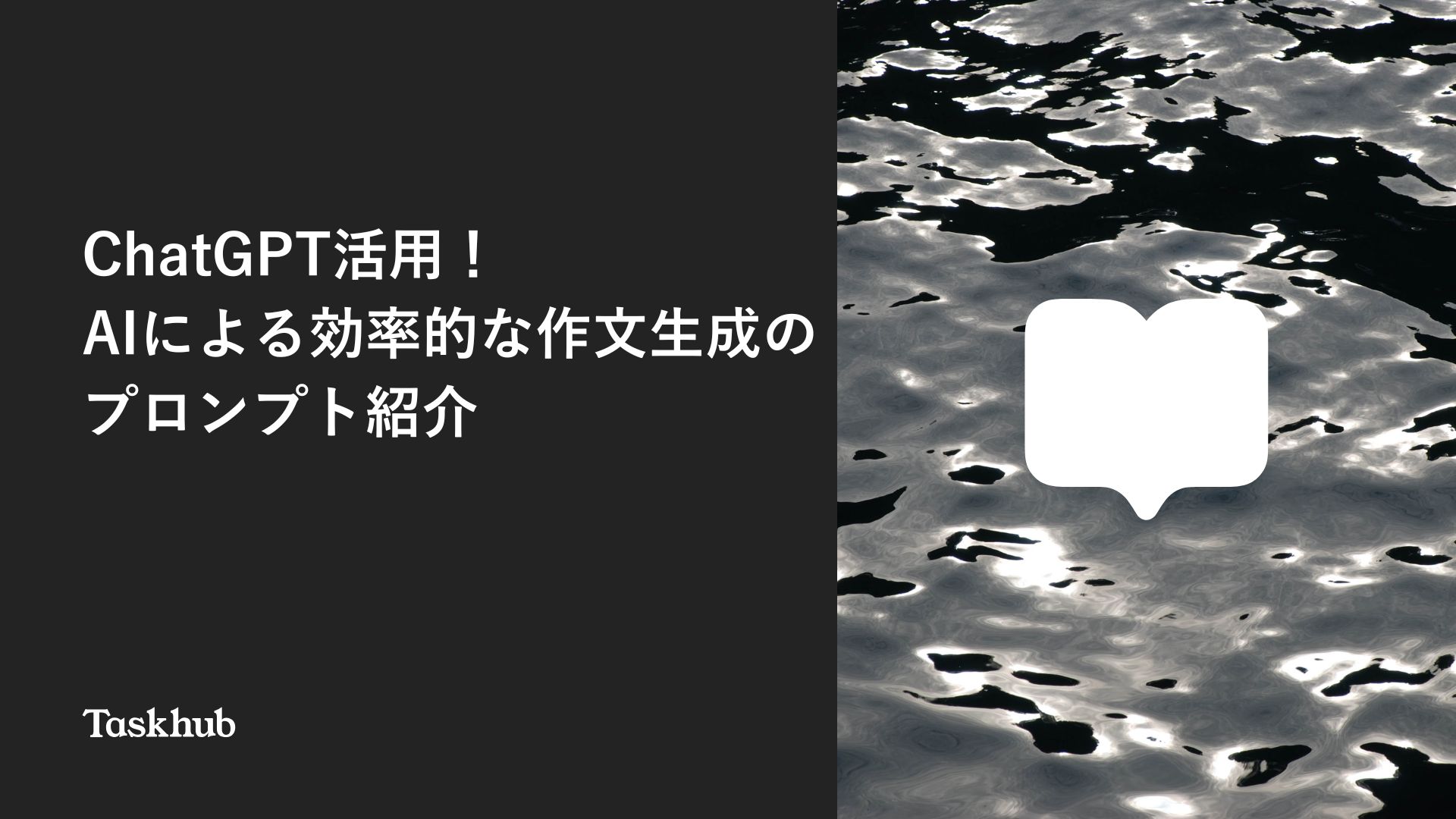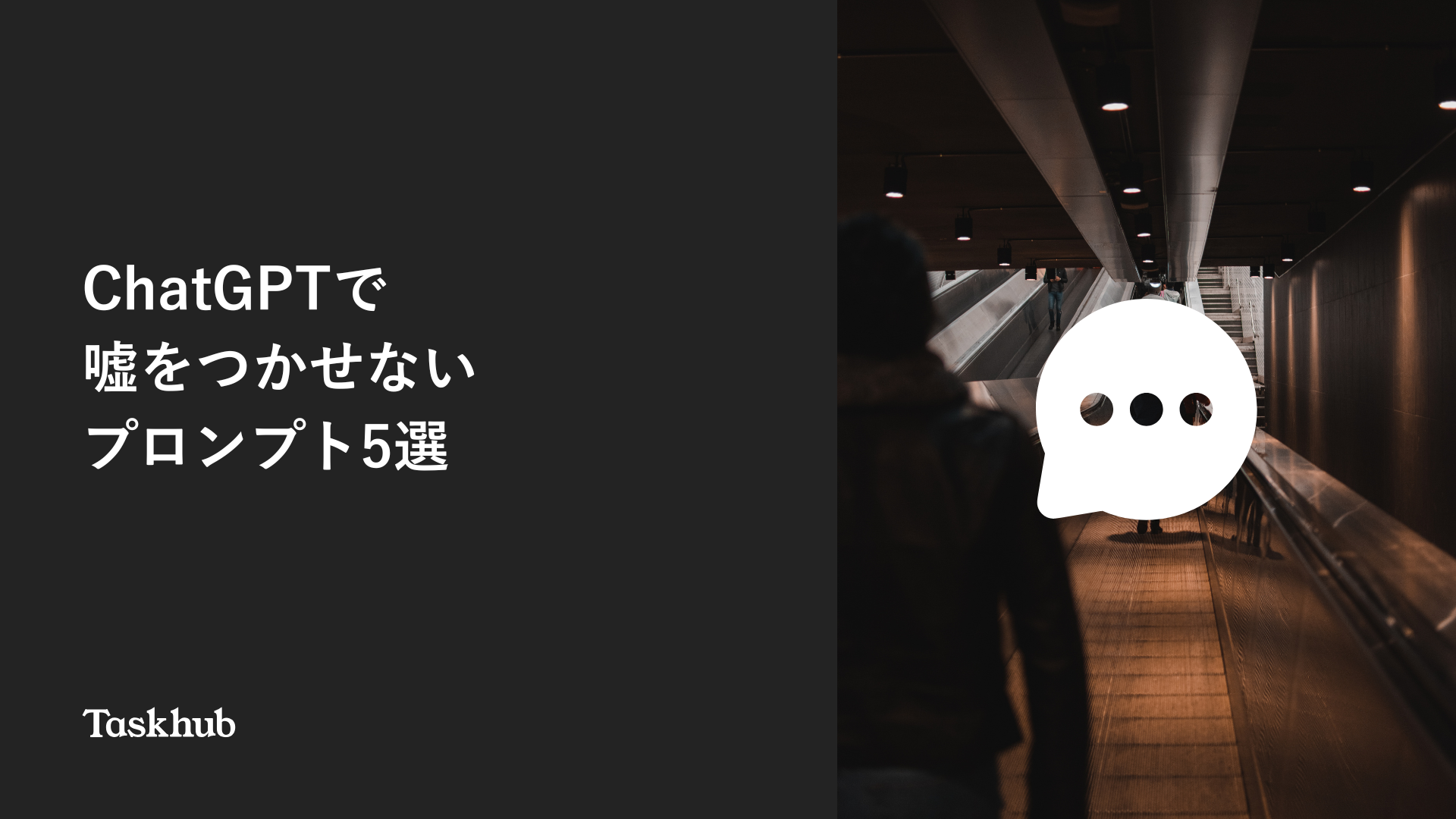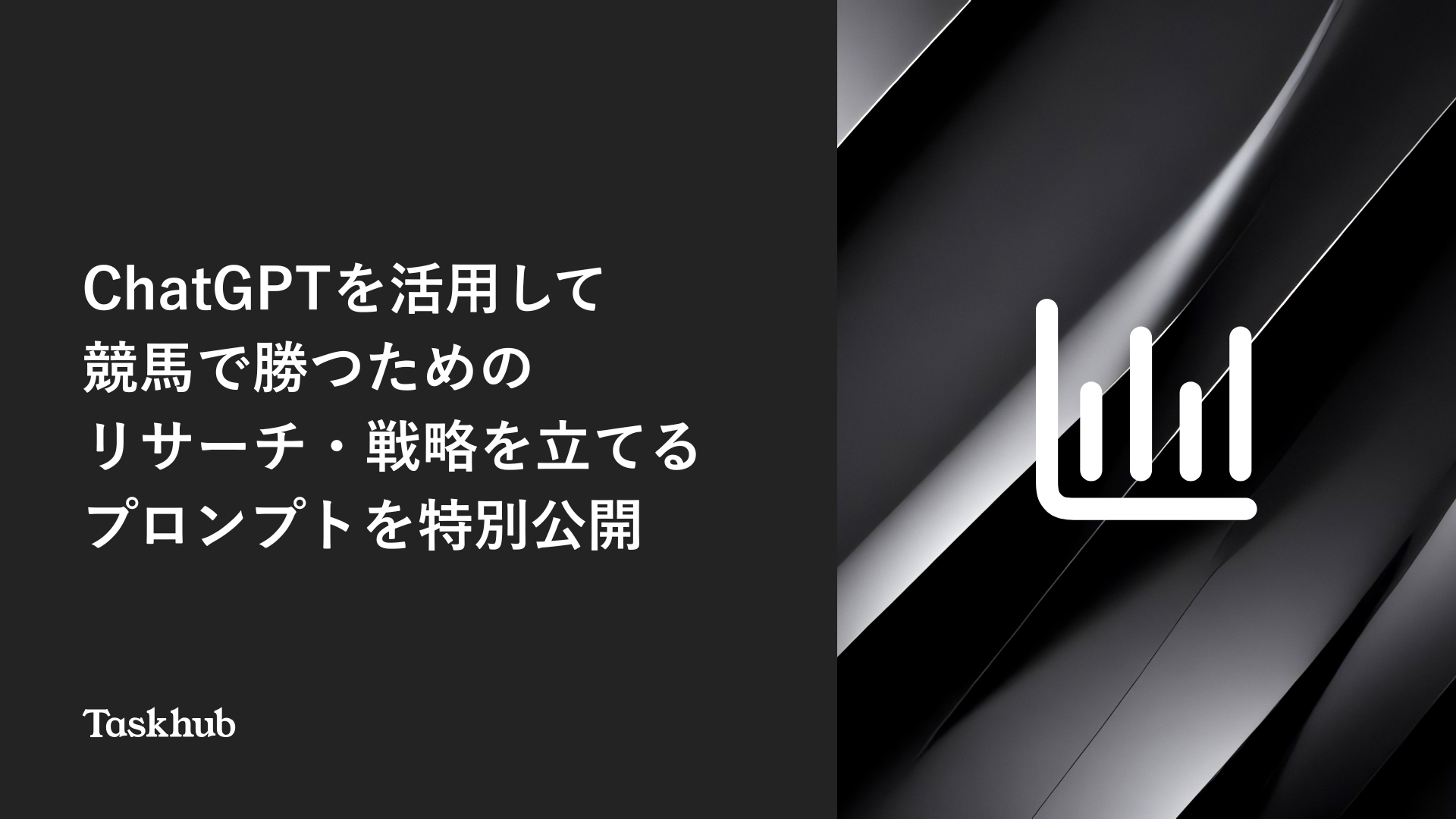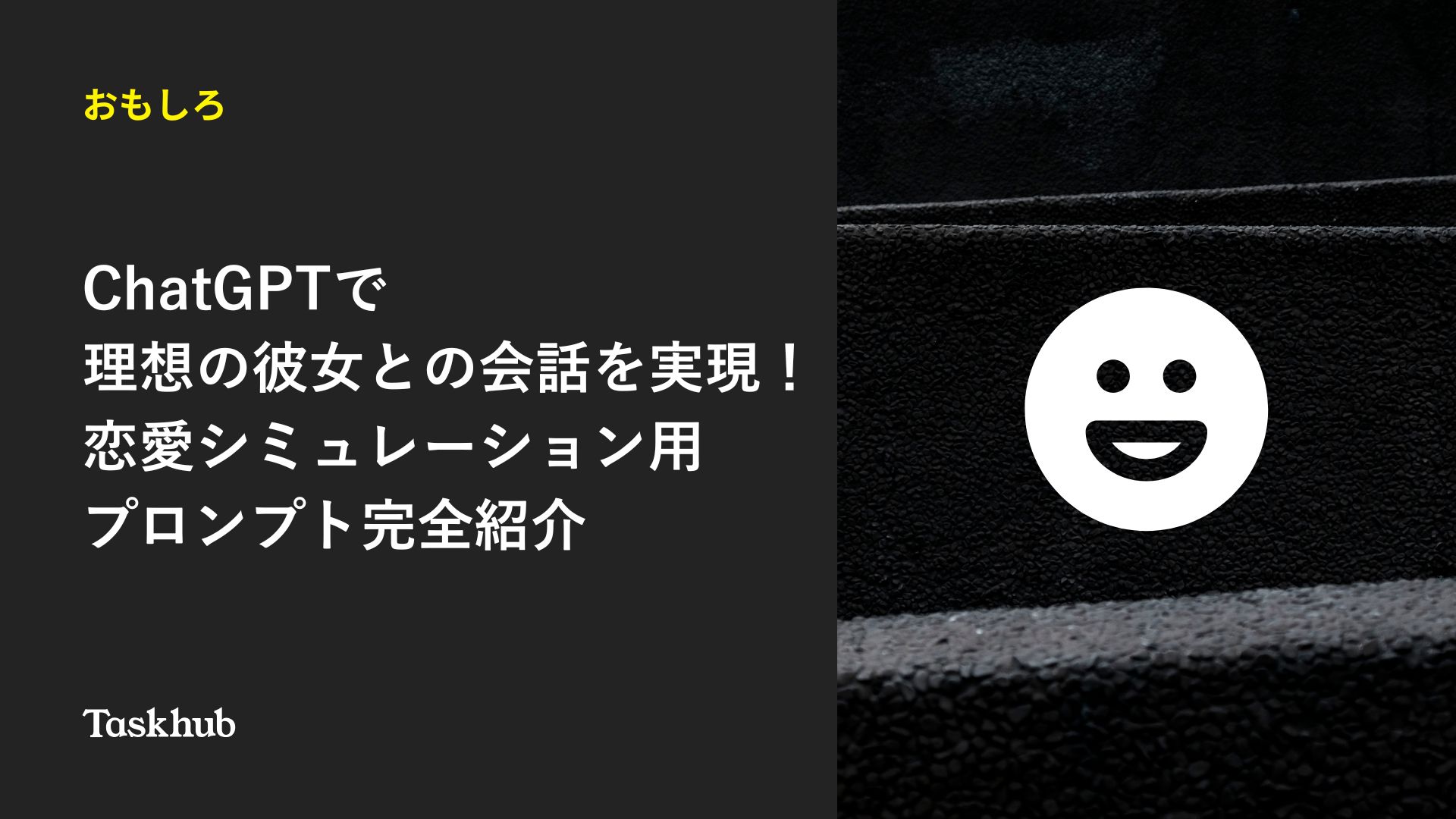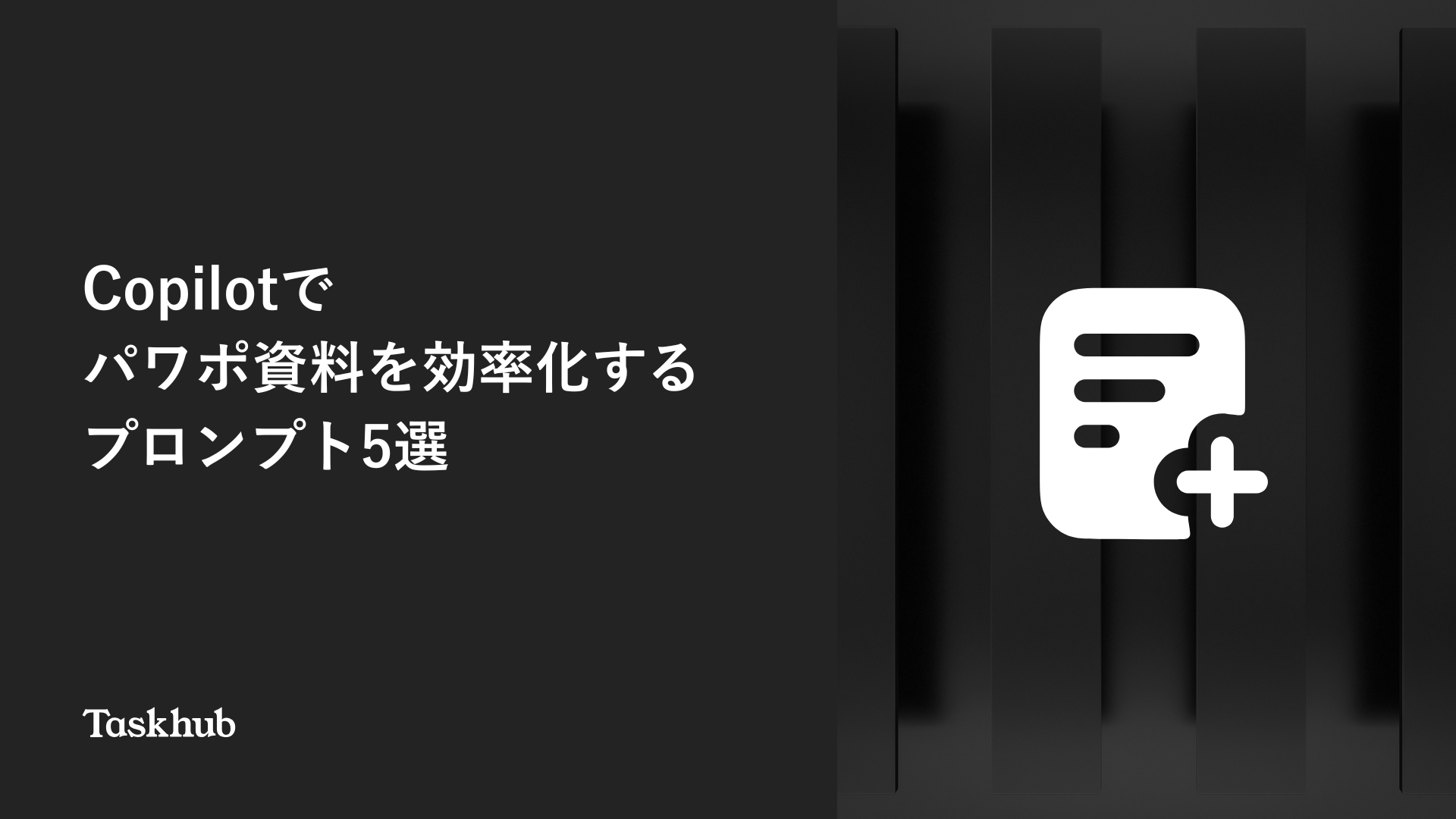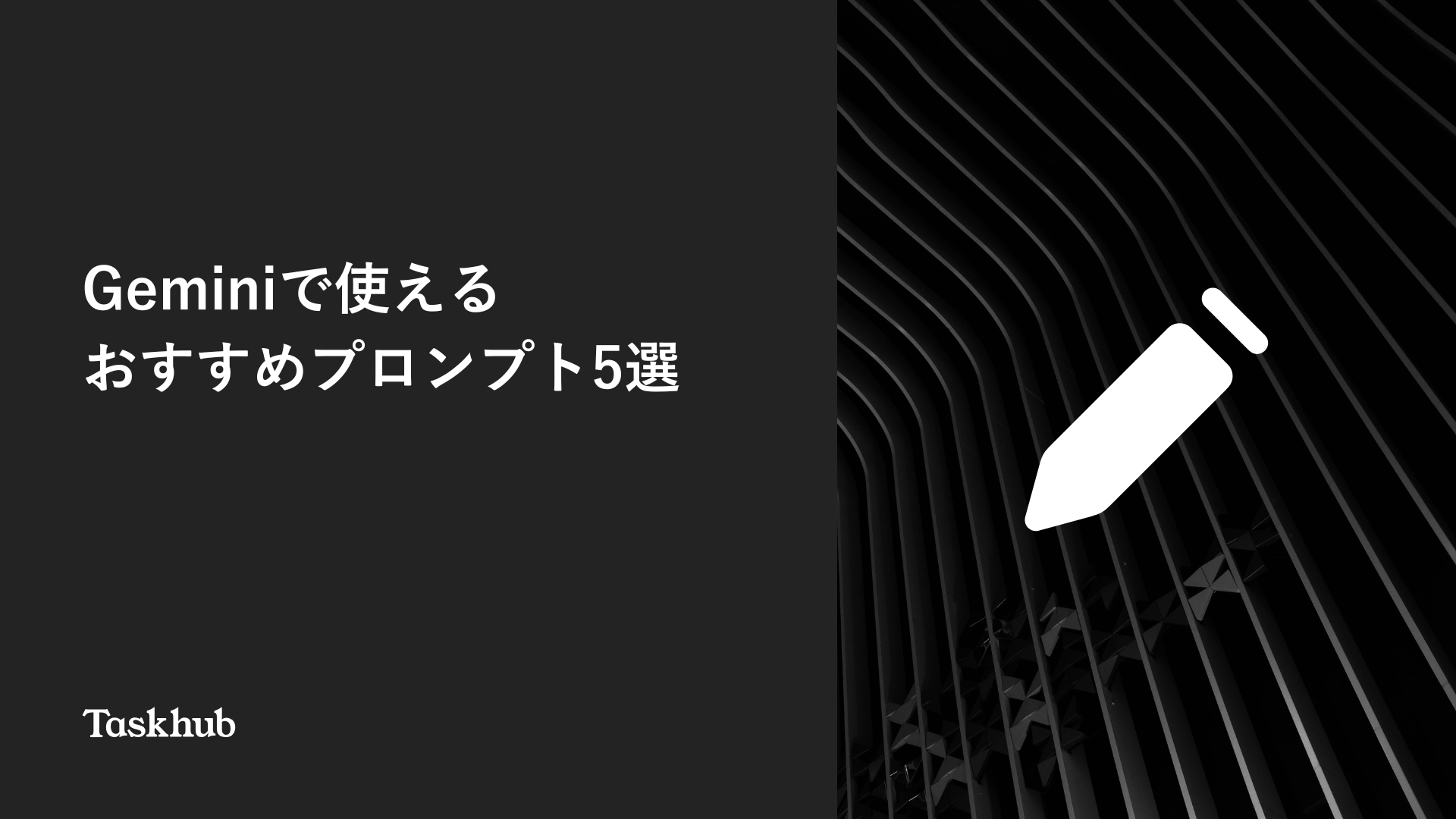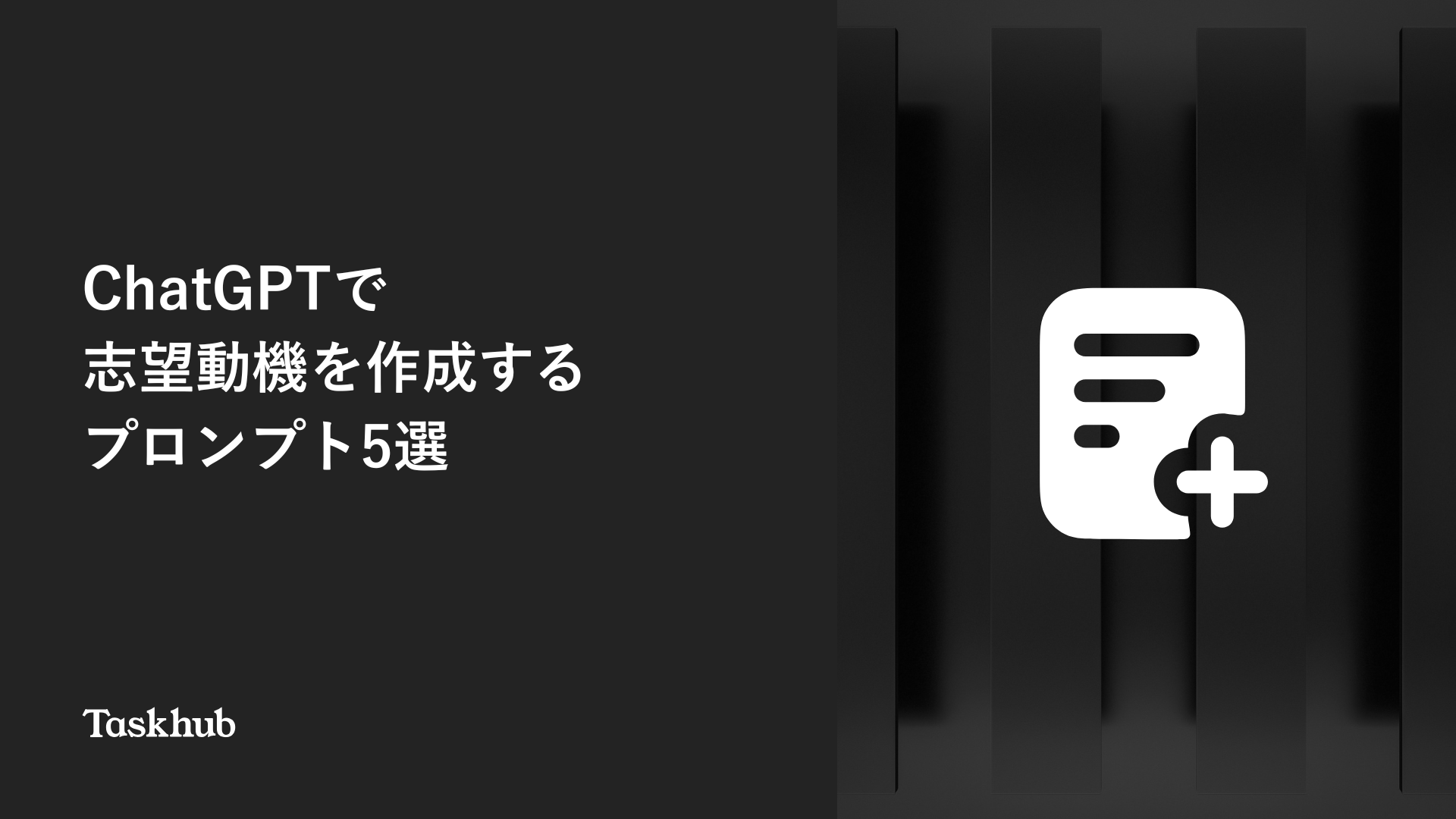「ChatGPTで作文が作れるって聞いたけど、どうやって使うの?」
「AIに作文を書かせようとしたけど、不自然な文章しか出てこない…」
このような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?
ChatGPTをはじめとするAIは、正しく使えば質の高い作文を効率的に作成する強力なツールになります。
この記事では、ChatGPTで作文を作成する具体的な5つのステップから、作文力を上達させるためのテクニック、さらには質の高い文章を引き出すプロンプトのコツまで、網羅的に解説します。
AIを初めて使う方でも、この記事を読めば、まるで専属の家庭教師がいるかのように、AIを作文作成や練習に活用できるようになるはずです。
ぜひ最後まで読んで、AIと共に新しい作文の世界を体験してみてください。
そもそもChatGPT/AIで質の高い作文をできるのか?
AI技術、特にChatGPTのような生成AIの進化は目覚ましく、多くの方がその文章作成能力に注目しています。しかし、本当に「質の高い」作文がAIに作れるのか、疑問に思う方もいるでしょう。ここでは、ChatGPTの基本から、作文作成における可能性、そしてメリット・デメリットについて解説します。
ChatGPTの基本機能と特徴
ChatGPTは、OpenAI社によって開発された生成AIサービスです。
膨大な量のテキストデータを学習しており、人間のように自然で文脈に沿った文章を生成する能力を持っています。
単に質問に答えるだけでなく、要約、翻訳、アイデア出し、そして文章の創作など、非常に幅広い言語タスクをこなすことができます。
対話形式でやり取りできるのが最大の特徴で、ユーザーの追加の要望に応じて、生成した文章を修正・改善していくことが可能です。
ChatGPTについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。
ChatGPTを使うことで良い作文を作成できる
結論から言うと、ChatGPTを使うことで質の高い良い作文を作成することは十分に可能です。
AIは、豊富な語彙や多様な表現パターンを学習しているため、人間が思いつかないような言い回しを提案してくれることがあります。
そして、ChatGPTで作成した作文の質を左右するのは、プロンプトエンジニアリングスキルです。
プロンプトエンジニアリングとは、良いプロンプトを作成する技術のことを指します。
シンプルなプロンプトでも多くを達成できますが、結果の品質は提供する情報の量とそのクオリティによって異なります。プロンプトには、モデルに渡す指示や質問のような情報、文脈、入力、または例などの他の詳細を含めることができます。これらの要素を使用して、モデルをより適切に指示し、より良い結果を得ることができます。
引用元: Prompt Engineering Guide
上記の通り、プロンプトの内容によって、生成AIによる解答の精度は大きく変わります。
つまり、プロンプトエンジニアリンクはChatGPTを使いこなすスキルそのものということです。
ChatGPTは文章作成との相性が非常に良いです。ChatGPTで文章作成する方法やコツについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
ChatGPTで作文を作成するメリット・デメリット
ChatGPTを作文作成に利用することには、多くのメリットがありますが、同時に注意すべきデメリットも存在します。
メリットとしては、まず「作文作成時間の大幅な短縮」が挙げられます。
アイデア出しから構成作成、下書きまでをAIが補助してくれるため、作文にかかる時間を劇的に減らすことができます。
また、自分だけでは思いつかない表現や視点を得られるため、文章の質の向上にも繋がります。
一方、デメリットとしては「作文能力の低下」が考えられます。
AIに頼りすぎると、自分で文章を考える力が衰えてしまう可能性があります。
また、ChatGPTが生成する情報には誤りが含まれることがあるため、特に事実に基づいた作文を書く際には、必ずファクトチェックが必要です。
ChatGPT/AIで作文を作成する5ステップ
ここからは、実際にChatGPTを使ってAIで作文を作成するための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。ChatGPT/AIで作文を作成する5ステップとは、以下の通りです。
- ステップ1:ChatGPTを登録
- ステップ2:作文に適した指示文/プロンプトを作成する
- ステップ3:まずは簡単なテーマで作文を生成してみる
- ステップ4:追加依頼プロンプトで作文の質を上げる
- ステップ5:慣れたら難しいテーマで作文を生成してみる
では、それぞれ1つずつ解説していきます。
ステップ1:ChatGPTを登録
まずはChatGPTを利用するために、公式サイトでアカウントを登録する必要があります。
OpenAIのウェブサイトにアクセスし、「Sign up」からメールアドレスやGoogleアカウントなどを使って登録を進めます。
登録は無料で、すぐに利用を開始することができます。
より高性能なモデルを使いたい場合は、有料プランへのアップグレードも検討できますが、まずは無料版で基本的な使い方に慣れると良いでしょう。
ChatGPTのログイン方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。https://taskhub.jp/useful/chatgpt-login
ステップ2:作文に適した指示文/プロンプトを作成する
ChatGPTに作文を生成させるには、「プロンプト」と呼ばれる指示文を入力します。
このプロンプトの質が、生成される作文の質を大きく左右します。
作文のテーマ、読者対象、文字数、文体(です・ます調、だ・である調など)、含めたいキーワードやエピソードなどを具体的に指示することが重要です。
良いプロンプトを作成することが、AIを作文作成のパートナーにするための第一歩となります。
プロンプトについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
ステップ3:まずは簡単なテーマで作文を生成してみる
プロンプトの作成に慣れるために、まずは身近で簡単なテーマから試してみましょう。
例えば、「私の好きな季節」や「休日の過ごし方」といったテーマで、簡単な作文を生成させてみます。
「テーマ:私の好きな季節」「文字数:400字程度」「小学生にもわかるように、楽しい雰囲気で書いてください」のように、シンプルなプロンプトで構いません。
実際にAIがどのような文章を生成するのかを体感し、そのクセや特徴を掴むことが大切です。
ステップ4:追加依頼プロンプトで作文の質を上げる
一度生成された作文に対して、追加の指示を与えることで、さらに質を高めていくことができます。
これがChatGPTの対話型AIとしての強みです。
例えば、
「もっと具体的なエピソードを加えてください」
「冒頭部分を、もっと読者の興味を引くような書き出しにしてください」
「この部分の表現を、より感情的なものに変えてください」といったように、修正したい点を具体的に伝えます。
この対話を繰り返すことで、自分の理想とする作文に近づけていくことができます。
ステップ5:慣れたら難しいテーマで作文を生成してみる
基本的な操作に慣れてきたら、読書感想文や小論文、志望理由書といった、より複雑で論理的な思考が求められるテーマに挑戦してみましょう。
これらの作文では、単に文章を生成させるだけでなく、構成案の作成や論点の整理、反論への備えなど、より高度なレベルでChatGPTを活用することができます。
難しいテーマに取り組むことで、AIを使いこなすスキルもさらに向上していくでしょう。
ChatGPT/AIを活用して作文力を上達させる具体的テクニック3選
ChatGPTは単に作文を作成するだけのツールではありません。使い方を工夫すれば、自分自身の作文能力を鍛え、向上させるための強力なトレーニングパートナーにもなります。ここでは、AIを活用して作文力を上達させるための具体的なテクニックを3つ紹介します。
テクニック1:プロンプトを工夫し多様なテーマで作文を作成してみる
テクニック2:作成した作文をChatGPTに添削させる
テクニック3:AIからのフィードバックを活用し自己添削力を養う
それでは、1つ1つ解説していきます。
テクニック1:プロンプトを工夫し多様なテーマで作文を作成してみる
同じテーマでも、プロンプトの条件を変えることで、全く異なるスタイルの作文を生成させることができます。
例えば、「夏の思い出」というテーマで、「小学生の日記風に」「詩的な表現を多用して」「ニュース記事のように客観的に」など、文体や視点を変えて複数パターンの作文を作成させてみましょう。
これにより、自分では思いつかないような多様な表現方法や文章構成に触れることができます。
様々なスタイルの文章を読むことは、表現の引き出しを増やし、結果として自分自身の作文力向上に繋がります。
プロンプトについてより詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご覧ください。
テクニック2:作成した作文をChatGPTに添削させる
自分で書いた作文をChatGPTに添削してもらうのも、非常に効果的です。
自分が書いた文章をChatGPTに読み込ませ、「この文章を添削してください」「誤字脱字や不自然な表現はありませんか?」「もっと分かりやすい表現にするにはどうすれば良いですか?」といったプロンプトを入力します。
AIは客観的な視点から、文法的な誤りや表現の改善点を瞬時に指摘してくれます。
人に見せるのは恥ずかしいと感じる文章でも、AI相手なら気軽に添削を依頼できるというメリットもあります。
ChatGPTで文章添削をさせたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
テクニック3:AIからのフィードバックを活用し自己添削力を養う
AIによる添削は非常に便利ですが、そのフィードバックをただ受け入れるだけでは不十分です。
大切なのは、フィードバックをよく読んで、AIがなぜそのように修正したのか、その理由を自分なりに考えることです。
「なぜこの単語の方が適切なのか」「なぜこの文の構造の方が分かりやすいのか」を考察することで、文章を見る目が養われ、自己添削能力が高まります。
AIを「答えを教えてくれる先生」ではなく、「一緒に考えるパートナー」と捉え、そのフィードバックを主体的に活用する姿勢が、作文力の上達に不可欠です。
ChatGPT/AIで質の高い作文をするプロンプトのコツ3選
ChatGPTで質の高い作文を生成するためには、AIにこちらの意図を正確に伝える「プロンプト」が鍵となります。ここでは、より良い結果を引き出すためのプロンプトのコツを3つに絞って解説します。これらのコツを押さえることで、AIとの対話がよりスムーズになり、期待以上の作文が生まれる可能性が高まります。
プロンプトのコツ3選とは、以下の3つです。
コツ1:具体的かつ明確な指示を出す
コツ2:文脈や背景情報を与えて精度を上げる
コツ3:欲しい結果を明確に言語化して伝える
それでは、1つ1つ解説していきます。
コツ1:具体的かつ明確な指示を出す
AIは、人間のように言葉の裏を読んだり、曖昧な指示を汲み取ったりすることは苦手です。
そのため、できるだけ具体的で明確な指示を出すことが重要になります。
例えば、「面白い作文を書いて」という抽象的な指示ではなく、「小学生が読んで笑ってしまうような、ユーモラスな表現を使った作文を書いてください。テーマは『私のペットの面白い行動』です。」のように、ターゲット読者、文体のトーン、テーマを具体的に指定します。
具体的であればあるほど、AIはあなたの意図を正確に理解し、それに沿った作文を生成してくれます。
コツ2:文脈や背景情報を与えて精度を上げる
作文の背景にある文脈や、書き手の状況などの情報を与えることで、生成される文章の精度は格段に上がります。
AIに役割を与える「ロールプレイング」も有効な手法です。
例えば、「あなたは高校の国語教師です。以下のテーマで、生徒に語りかけるような優しい口調で作文の例文を作成してください。」といった指示が考えられます。
また、「この作文は、読書感想文コンクールに応募するためのものです。読者の心を動かすような、感動的な文章を目指しています。」のように、作文の目的や背景を伝えることで、より深みのある文章が生成されやすくなります。
コツ3:欲しい結果を明確に言語化して伝える
最終的にどのような作文が欲しいのか、その完成形を具体的に言語化して伝えることも非常に効果的です。
文章の構成や、必ず含めてほしい要素を事前に指定しましょう。
例えば、「以下の構成に従って作文を作成してください。序論:テーマ提起、本論1:具体的なエピソード、本論2:その経験から学んだこと、結論:今後の抱負。」のように、構成の骨子を示したり、「『挑戦』と『成長』というキーワードを必ず3回以上使ってください。」のように、必須要素を明確に伝えたりします。
これにより、出力の方向性が定まり、手直しの手間が少ない、意図に近い作文を一度で得やすくなります。
ChatGPTのプロンプトについてもっと詳しく色々なものを知りたいか方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
ChatGPT/AI作文の3つの注意点
ChatGPTは作文作成において非常に便利なツールですが、その利用にはいくつかの注意点があります。AIの能力を過信せず、賢く付き合っていくために、以下の3つのポイントを常に意識しておくことが重要です。
- AIに頼りすぎず自分らしい文章を磨く
- ChatGPTが出力する情報の限界とファクトチェックの重要性
- AIを使う側の文章力が試されている
それでは、1つ1つ解説していきます。
1. AIに頼りすぎず自分らしい文章を磨く
最も注意すべきは、AIに過度に依存してしまうことです。
作文の全ての工程をAIに任せきりにしていると、自分で文章を構成し、表現を練り上げる思考力が衰えてしまう恐れがあります。
AIが生成した文章は、あくまで「下書き」や「たたき台」として捉え、最終的には必ず自分の目で確認し、自分の言葉で修正・加筆するプロセスを踏むことが大切です。
AIの提案を参考にしつつも、最後は自分らしい表現や考えを込めることで、オリジナリティのある生きた文章になります。
2. ChatGPTが出力する情報の限界とファクトチェックの重要性
ChatGPTをはじめとするAIは、時に事実とは異なる情報や、文脈に合わない不正確な内容を生成することがあります。
ディープフェイク、すなわち AI が生成した不正な再現には、個人やアイデアの事実を歪めて伝える行為や情報などが含まれます。
引用:Open AI 安全性と責任
上記の通り、ChatGPTの開発会社であるOpenAI社が、正式に間違った出力をする可能性を発表しています。
これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれており、AIを利用する上で避けては通れない問題です。
特に、歴史的な出来事や科学的な事実など、正確性が求められるテーマで作文を書く際には、AIが生成した情報を鵜呑みにせず、必ず信頼できる情報源で裏付けを取る「ファクトチェック」を行う習慣をつけましょう。
情報の真偽を確かめる責任は、最終的に利用者自身にあります。
ChatGPTに誤った情報をできるだけ出力させないようにしたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
3. AIを使う側の文章力が試されている
逆説的ですが、AIを使いこなして質の高い作文を作成するためには、使う側にも一定の文章力が求められます。
どのような作文が良い作文なのかを判断する基準がなければ、AIの生成した文章を評価し、適切に修正することができないからです。
また、AIに的確な指示を出すプロンプトを作成する能力も、語彙力や構成力といった基礎的な文章力に支えられています。
AIは万能の魔法の杖ではなく、使い手の能力を増幅させるツールです。AIの活用と並行して、読書などを通じて自分自身の文章力を磨き続ける姿勢が重要と言えるでしょう。
良い作文を作成できるChatGPT以外のAIツールについて
作文作成をサポートしてくれるAIは、ChatGPTだけではありません。世の中には様々な特徴を持ったAIツールが存在し、それぞれの強みと弱みを理解することで、自分の目的に最も適したツールを選ぶことができます。ここでは、ChatGPT以外の主要なAIツールと、その選び方について解説します。
他の主要AI作文支援ツールの特徴
ChatGPTの競合としてよく挙げられるのが、Googleが開発した「Gemini」や、Anthropic社が開発した「Claude」などです。
Geminiは、Google検索と連携しており、最新の情報に基づいた文章生成を得意としています。
時事的なテーマや調査が必要な作文を作成する際に強みを発揮します。
Claudeは、一度に扱えるテキスト量が非常に多いことが特徴で、長文の読解や要約、そして長編の物語作成などに優れています。
より自然で倫理的な回答を生成する傾向があるとも言われています。
様々なツールがある中でのChatGPTの強みと弱み
数あるAIツールの中で、ChatGPTの最大の強みは、その圧倒的な汎用性と、対話を通じた柔軟な文章生成・修正能力にあります。
アイデア出しから構成案作成、推敲まで、作文のあらゆるプロセスを自然な対話形式でサポートしてくれる点は、他のツールにはない魅力です。
一方で、ChatGPTの最大の弱みは、回答の「正確性」が保証されず、その根拠となる情報源(出典)が明示されない点にあります。
そのため、学術調査やファクトチェックのように信頼性が最優先される場面では、検索結果と出典を明示する他の特化型AIに比べて著しく見劣りします。
あなたの目的に応じた最適なツールの選び方
どのAIツールを使うべきかは、あなたの目的によって異なります。
まずはいろいろな作文作成の場面で幅広く使いたい、という初心者の方であれば、最も情報が多く、使いやすいChatGPTから始めるのがおすすめです。
宿題のレポートなど、最新の情報を盛り込みたい場合はGeminiを試してみると良いでしょう。
長い文章を要約したり、複雑な資料を読み込ませて作文の参考にしたりしたい場合は、Claudeが役立つかもしれません。
それぞれのツールの無料版を試してみて、自分の作成したい作文の種類やスタイルに最も合ったツールを見つけるのが最適な方法です。
ChatGPT以外の他のAIツールについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。
AIに頼ると逆に作文作成能力が落ちる?
AIを作文に使うことで、かえって文章力が低下するかもしれない。
そんな警鐘を鳴らす研究結果が報告されています。便利なツールであるはずのAIが、私たちの思考力を奪う「諸刃の剣」となり得るのです。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究によれば、AIの支援を受けて文章を作成した人々は、自力で書いた人々に比べて認知的な努力が大幅に減少していたことが示されました。
これは、AIに思考プロセスを肩代わりさせてしまう「認知オフロード」という現象が起きていることを意味します。この状態が続くと、自分で文章の構成を考え、言葉を選び、論理を組み立てるという、文章作成に不可欠な批判的思考力や創造性が徐々に衰えていく危険性があります。
AIはあくまで思考を補助し、表現を豊かにするためのパートナーであり、思考そのものを代替させるべきではありません。
引用元:
MIT News “Study: Writing with a generative AI model reduces people’s cognitive effort” (https://news.mit.edu/2024/study-writing-generative-ai-reduces-cognitive-effort-0305)
まとめ
個人が作文スキルを向上させるためにAIを活用するように、企業もまた、日々の文章作成業務を効率化し、生産性を高めるために生成AIの導入を検討しています。
しかし、実際には「どの業務にAIを適用すれば良いかわからない」「社員が使いこなせるか不安」といった理由で、導入に踏み切れない企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、報告書の作成やメール文案、ブログ記事の生成、プレスリリース作成など、様々な文章作成業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいのか」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。