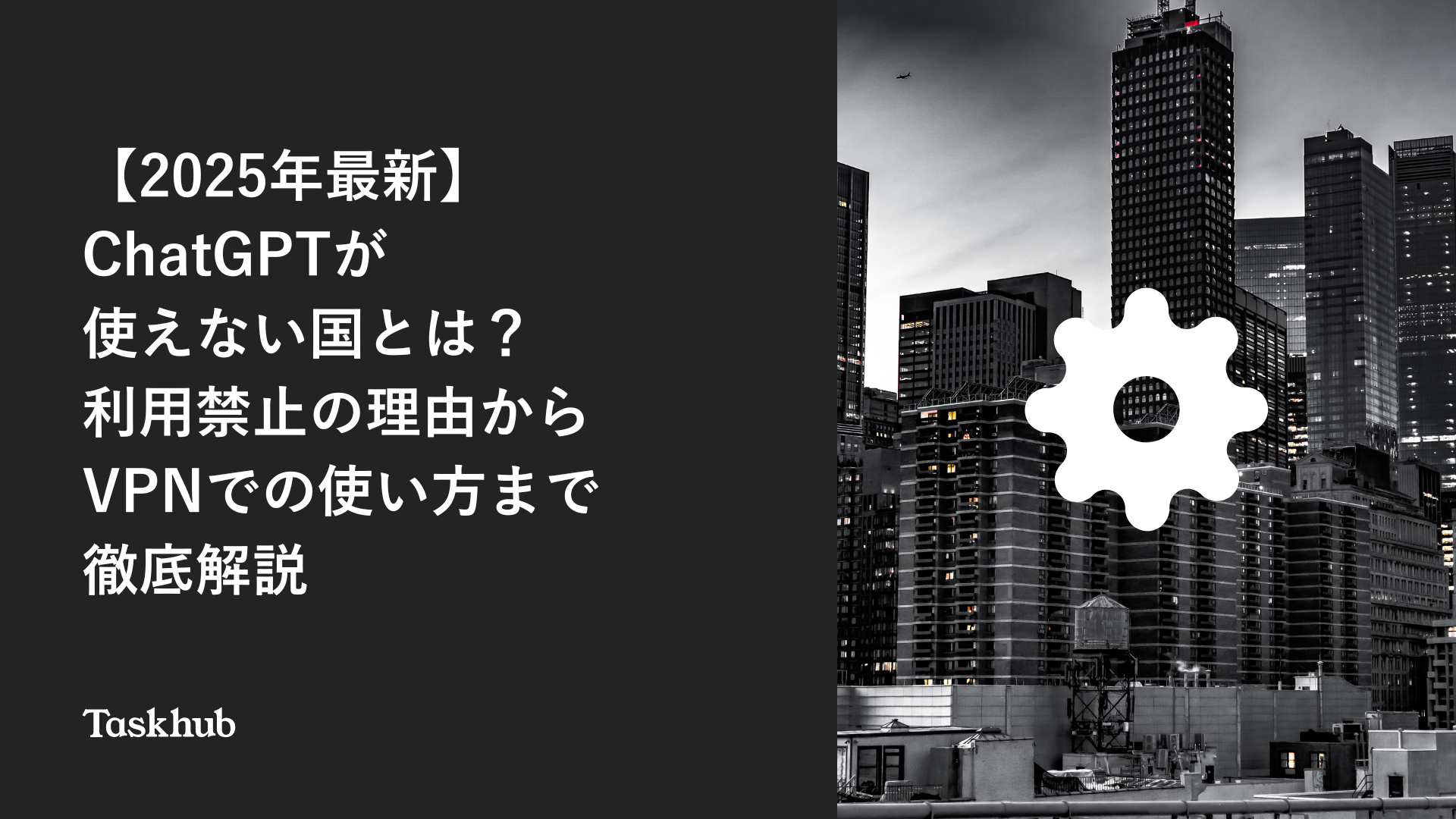「ChatGPTを海外で使いたいけど、どの国で利用が禁止されているんだろう?」
「ChatGPTが国に規制されている理由や、規制されている国で安全に使う方法が知りたい。」
こういった疑問や悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
本記事では、2025年最新の情報に基づき、ChatGPTの利用が禁止・制限されている国の一覧、各国が規制に踏み切る理由、そしてVPNを利用して安全に使う方法まで、網羅的に解説します。
上場企業向けに生成AIのコンサルティングを行う弊社が、専門的な知見を基に、複雑な各国の状況やVPNの選び方を分かりやすくお伝えします。きっとあなたの疑問を解消する一助となるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
ChatGPTの利用が禁止・制限されている国一覧
ChatGPTは世界中で利用が拡大していますが、一部の国では政府の方針や法律によって、その利用が完全に禁止されていたり、何らかの形で制限されたりしています。ここでは、利用が「完全に禁止されている国」と「一部制限や懸念がある国」に分けて、それぞれの状況を解説します。
【利用不可】ChatGPTが完全に禁止されている国
インターネットに対する厳しい検閲や情報統制を行っている国々では、ChatGPTへのアクセスが完全にブロックされています。これらの国では、政府が国民のアクセスできる情報を管理しており、自由な情報生成や海外サービスへの接続を好まない傾向があります。
具体的には、中国、北朝鮮、イラン、ロシア、キューバ、シリアなどが挙げられます。これらの国では、政府のファイアウォールなどによって技術的にアクセスが遮断されているため、通常の方法ではChatGPTを利用することはできません。ロシアのように、地政学的な理由から西側諸国のサービスへのアクセスを制限しているケースもあります。これらの国々でChatGPTを利用しようとすると、エラーメッセージが表示されるか、そもそもサイトに接続することすらできません。
こちらはOpenAIが公式に発表している、ChatGPTが利用可能な国の一覧です。最新の情報を合わせてご確認ください。 https://help.openai.com/en/articles/7947663-chatgpt-supported-countries
【一部制限】ChatGPTに部分的な規制や懸念がある国
完全な禁止には至っていないものの、国民のプライバシー保護やデータセキュリティの観点から、ChatGPTの利用に懸念を示し、部分的な規制や調査を行っている国々も存在します。特に欧州連合(EU)の国々でこの動きが顕著です。
代表的な例として、イタリアは2023年に一時的にChatGPTの使用を禁止しました。理由として、EUの厳格な個人情報保護規則であるGDPR(一般データ保護規則)への違反の可能性や、利用者の年齢確認が不十分であることなどが挙げられました。その後、OpenAI社が改善策を講じたことで禁止は解除されましたが、この一件は他のEU諸国(ドイツ、フランス、スペインなど)にも影響を与え、各国でデータ保護当局が調査を開始するきっかけとなりました。これらの国々では、企業が業務でChatGPTを利用する際に、個人情報の取り扱いに関する厳しいガイドラインを設けるなどの動きが見られます。
世界のChatGPTと国の規制状況【海外編】
ChatGPTの開発国であるアメリカを含め、主要な国々ではどのような規制の動きがあるのでしょうか。ここでは、各国の具体的な状況を詳しく見ていきます。
アメリカ
アメリカでは、政府による一律のChatGPT利用禁止措置は取られていません。しかし、バイデン政権は2023年に「AIの安全、安心で信頼できる開発と利用に関する大統領令」を発表するなど、AIがもたらすリスクに対して強い関心を示しています。連邦レベルでの包括的な規制よりも、各州が独自のAI規制法を制定する動きや、政府機関内での利用ガイドラインを策定する動きが中心となっています。安全性、プライバシー、偽情報対策などが主な論点となっており、自由な開発を促進しつつも、責任ある利用を確保するための枠組み作りが進められています。
カナダ
カナダもアメリカと同様に、現時点で国としての明確な利用禁止措置は講じていません。しかし、プライバシー保護に関しては強い懸念を示しており、プライバシー・コミッショナー事務局がOpenAI社に対して調査を開始しています。調査の焦点は、ChatGPTがユーザーの同意なしに個人情報を収集、使用、開示していないかという点です。カナダは、イノベーションを阻害しない範囲で、国民の個人情報が適切に保護されるような規制のあり方を模索している段階にあります。
中国
中国は、国内のインターネットサービスを厳しく管理する「グレート・ファイアウォール」で知られており、ChatGPTへのアクセスは完全にブロックされています。中国政府は、生成AIが政府の見解と異なる情報を生成・拡散することを警戒しており、国内企業に対しては、政府の検閲基準を満たした独自のAIモデル開発を奨励しています。そのため、AlibabaやBaiduといった中国のテック企業が、独自の生成AIサービスを展開しています。国民は、政府が認めたAIサービスのみを利用できる状況です。
ロシア
ロシアもまた、政府による情報統制が厳しい国の一つであり、ChatGPTの利用を禁止しています。ウクライナ侵攻以降、西側諸国のインターネットサービスへのアクセスを積極的に遮断しており、その一環としてChatGPTもブロックの対象となっています。ロシアは、国内のIT企業が開発する独自のAI技術を推進する方針を掲げており、情報空間における独立性を維持しようとする狙いがあります。
イギリス
イギリスは、EUを離脱したこともあり、EUのAI規制とは異なる独自のアプローチを取っています。政府は「イノベーションを促進する」という立場を明確にしており、過度な規制には慎重な姿勢を見せています。包括的な法律で縛るのではなく、既存の規制当局(情報コミッショナー事務局や競争・市場庁など)がそれぞれの管轄内でAIのリスクに対応していく方針です。ただし、安全性や公平性に関する議論は活発に行われており、将来的に特定の分野で新たなルールが導入される可能性はあります。
EU諸国(イタリア・ドイツ・フランスなど)
EUは、世界に先駆けて包括的なAI規制法案「AI Act」の制定を進めており、生成AIに対する規制でも主導的な役割を果たそうとしています。前述のイタリアによる一時的な利用禁止は、EU全体に大きな影響を与えました。ドイツやフランスのデータ保護当局も、ChatGPTがGDPRに準拠しているかどうかの調査を進めています。EU全体の方針としては、AIのリスクを4段階に分類し、リスクの高さに応じて異なるレベルの義務を課すというものです。生成AIについては、透明性の確保(AIによって生成されたコンテンツであることの明示など)が重要な義務として課される見込みです。
こちらは欧州議会による「AI Act」の解説ページです。EUの具体的な規制内容について、より詳しく知りたい方は合わせてご覧ください。 https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence
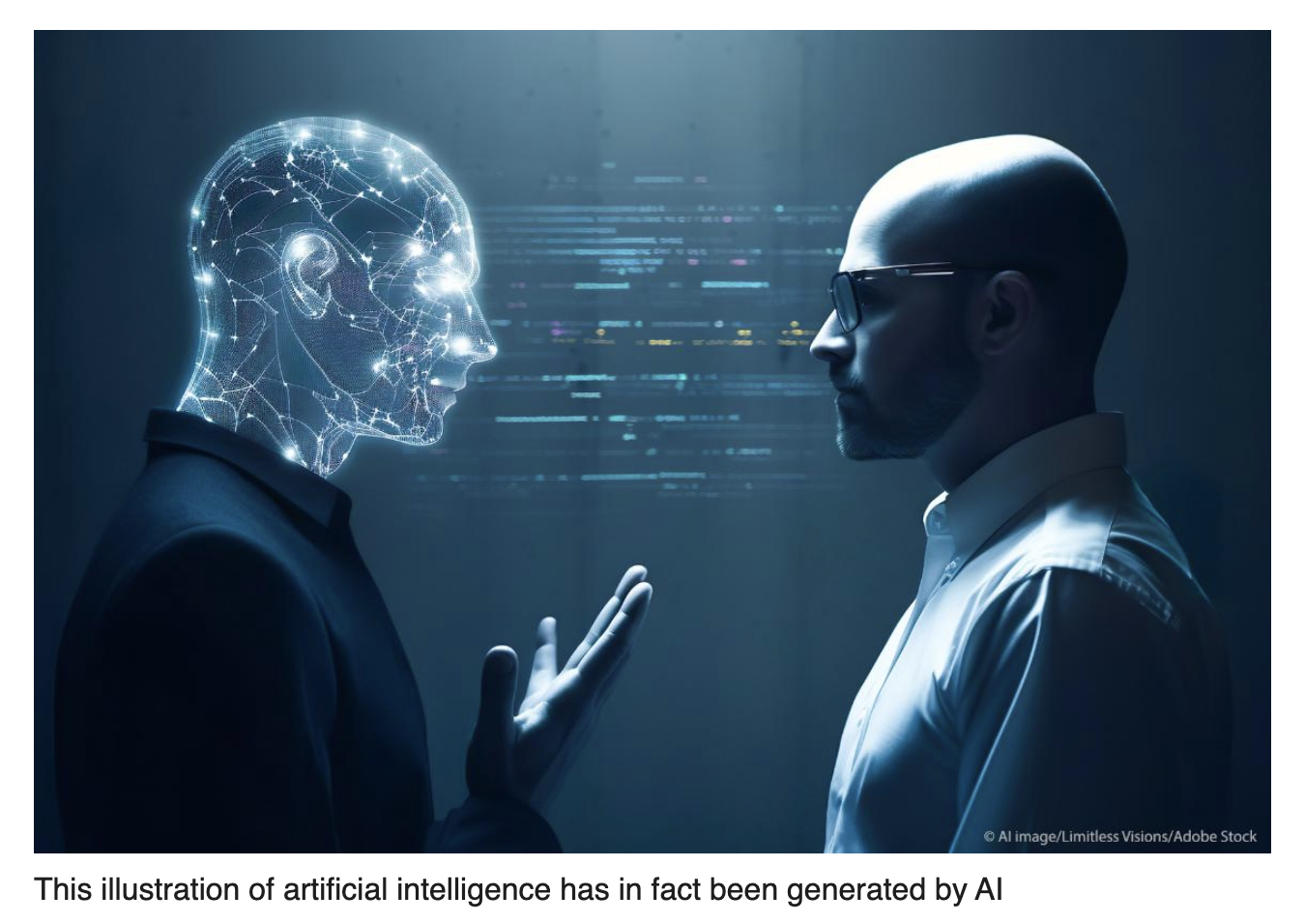
各国の事情は?ChatGPTが国に規制される4つの理由
なぜ多くの国がChatGPTをはじめとする生成AIに懸念を抱き、規制に乗り出しているのでしょうか。その背景には、主に4つの理由があります。
プライバシーとデータ保護の問題
ChatGPTは、ユーザーが入力した情報を学習データとして利用することがあります。この仕組みが、個人情報や企業の機密情報が意図せず外部に漏洩したり、AIの学習に利用されたりするリスクを生み出します。
特にEUでは、GDPR(一般データ保護規則)という厳格なルールがあり、個人データをEU域外に持ち出すことや、本人の明確な同意なく処理することを厳しく制限しています。イタリアが一時的にChatGPTを禁止した主な理由も、このGDPR違反の疑いでした。ユーザーの会話データがどのように収集・利用・保管されているのか、その透明性が不十分であることが大きな問題点とされています。
こちらはGDPR(一般データ保護規則)の概要について分かりやすく解説したページです。合わせてご覧ください。 https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
著作権と知的財産権の課題
ChatGPTは、インターネット上に存在する膨大なテキストデータを学習して文章を生成します。その学習データには、著作権で保護された書籍、記事、ウェブサイトなどが含まれている可能性があります。
そのため、ChatGPTが生成した文章が、既存の著作物と酷似してしまい、意図せず著作権を侵害してしまうリスクが指摘されています。誰かの小説の一部をそのまま出力してしまったり、特定のアーティストの作風に酷似したイラストを生成してしまったりするケースです。
AIが生成したコンテンツの著作権は誰に帰属するのか、学習データの利用はどこまで許されるのかといった法的な枠組みがまだ整備されておらず、クリエイターや企業にとって大きな課題となっています。
こちらは世界知的所有権機関(WIPO)が発行した、生成AIと知的財産権に関するファクトシートです。国際的な視点での課題について、合わせてご覧ください。 https://www.wipo.int/documents/d/frontier-technologies/docs-en-pdf-generative-ai-factsheet.pdf
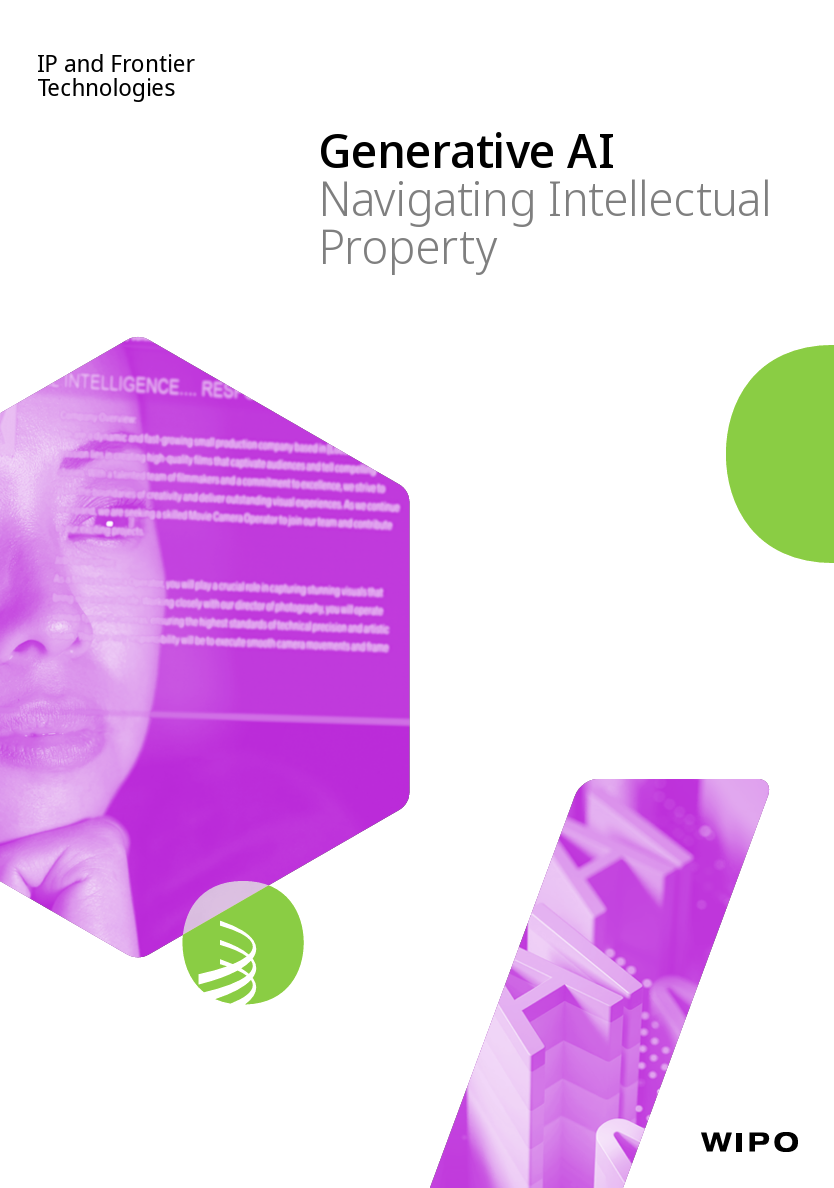
倫理的・社会的影響(嘘や偏った情報の出力)
ChatGPTは、もっともらしい嘘の情報を生成してしまうこと(ハルシネーション)があります。また、学習データに含まれる偏見や差別的な考え方を反映して、不適切で偏った内容を出力してしまう可能性もゼロではありません。これらの偽情報や偏見を含んだ情報が社会に大量に拡散されれば、世論が誤った方向に誘導されたり、特定の集団への差別が助長されたりする危険性があります。特に、選挙や公的な意思決定に影響を与えるような偽情報が生成されることへの懸念は、各国政府が規制を検討する大きな動機となっています。
こちらは、AIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法について詳しく解説した記事です。合わせてご覧ください。
情報漏洩のリスク
個人利用だけでなく、企業が業務でChatGPTを利用するケースも増えています。その際、社員が業務上の機密情報や顧客の個人情報をChatGPTに入力してしまうと、そのデータがOpenAI社のサーバーに送信され、AIの学習データとして利用されたり、あるいはサイバー攻撃などによって外部に漏洩したりするリスクがあります。実際に、ある大手企業では、社員が機密情報を含むソースコードをデバッグ目的でChatGPTに貼り付けてしまい、情報漏洩インシデントにつながった事例も報告されています。こうしたリスクを防ぐため、企業内での利用ルールを厳格に定めたり、利用そのものを禁止したりする国や企業も出てきています。
生成AIを企業で利用する際のリスクと、その具体的な対策についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ChatGPTを規制のある国で利用する裏技:VPNとは?
ChatGPTが規制されている国からでも、ある方法を使えばアクセスできる場合があります。それが「VPN」の利用です。ここでは、VPNの仕組みと、それを使って安全にChatGPTにアクセスする方法について解説します。
VPNの仕組みと必要性
VPNは「Virtual Private Network(仮想専用線)」の略で、インターネット上に仮想的な暗号化された通信トンネルを作り出し、安全にデータのやり取りを行うための技術です。
通常、インターネットに接続すると、あなたのデバイスにはIPアドレスという、インターネット上の住所のようなものが割り当てられます。このIPアドレスから、あなたがどの国や地域からアクセスしているかが分かってしまいます。
VPNを利用すると、VPNサービスが提供する海外のサーバーを経由してインターネットに接続します。すると、あなたのIPアドレスは、接続先の海外サーバーのものに置き換えられます。例えば、中国から日本のVPNサーバーに接続すれば、ウェブサイト側からは、あなたが日本からアクセスしているように見えます。
この仕組みを利用することで、自国ではアクセスがブロックされているサービス(ChatGPTなど)でも、利用が許可されている国のサーバーを経由することで、アクセスできるようになるのです。また、通信内容が暗号化されるため、第三者によるデータの盗み見や改ざんを防ぎ、セキュリティを高める効果もあります。
VPNを使って安全にChatGPTにアクセスする方法
VPNを使ってChatGPTにアクセスする手順は非常にシンプルです。
- VPNサービスに登録する: 信頼できるVPNプロバイダーを選び、アカウントを登録します。
- 専用アプリをダウンロードする: 利用したいデバイス(PC、スマートフォンなど)に、そのVPNサービスの専用アプリをインストールします。
- ChatGPTが利用可能な国のサーバーに接続する: アプリを起動し、サーバーリストから日本やアメリカなど、ChatGPTが問題なく使える国を選択して接続します。
- ChatGPTにアクセスする: VPNに接続した状態で、ブラウザからChatGPTの公式サイトにアクセスします。
たったこれだけの手順で、規制されている国からでもChatGPTを利用できるようになります。利用中は、VPN接続を維持したままにしてください。途中で接続が切れると、元の国のIPアドレスに戻ってしまい、アクセスできなくなる可能性があります。
アクセス情報が漏れる危険性について
VPNは非常に便利なツールですが、利用には注意点もあります。特に、無料のVPNサービスの中には、セキュリティが脆弱であったり、ユーザーの通信ログを記録・販売したりする悪質な業者が存在する可能性があります。
信頼性の低いVPNを利用すると、通信内容が漏洩したり、個人情報が盗まれたりする危険性があります。ChatGPTの利用に限らず、安全なインターネット利用のためには、信頼できる有料のVPNサービスを選ぶことが重要です。実績のあるサービスは、通信ログを一切保存しない「ノーログポリシー」を掲げていることが多く、プライバシー保護の観点からも安心です。
【5選】ChatGPTが使える国に接続できるおすすめVPN
ChatGPTを利用するためにVPNを選ぶなら、どのサービスが良いのでしょうか。ここでは、実績、通信速度、セキュリティ、使いやすさなどを総合的に評価し、おすすめのVPNサービスを5つご紹介します。
NordVPN
NordVPNは、世界的に最も人気のあるVPNサービスの一つです。業界最高水準の通信速度と、強力なセキュリティ機能が特徴です。世界60カ国以上に5,000台以上のサーバーを設置しており、接続先の選択肢が豊富です。脅威対策機能により、マルウェアや悪質な広告をブロックしてくれるため、安全にインターネットを利用できます。日本語のアプリやサポートも充実しており、初心者でも安心して利用を開始できます。料金は長期契約をすることで、月額数百円からと非常にリーズナブルになります。
こちらはNordVPNの公式サイトです。料金プランや機能の詳細について、合わせてご覧ください。 https://nordvpn.com/ja/

Surfshark
Surfsharkは、コストパフォーマンスの高さで注目を集めているVPNサービスです。最大の特徴は、1つの契約で利用できるデバイスの台数が無制限である点です。パソコン、スマートフォン、タブレットなど、家族全員のデバイスをまとめて保護したい場合に最適です。通信速度も安定しており、世界100カ国以上にサーバーを展開しています。機能も豊富で、広告ブロッカーや個人情報漏洩アラートなども利用できます。2年プランなどの長期契約を選ぶと、月額料金を大幅に抑えることが可能です。
CyberGhost VPN
CyberGhost VPNは、使いやすさに定評のあるVPNサービスです。特に、初めてVPNを利用する人にとって、分かりやすいインターフェースが魅力です。ストリーミングやトレントなど、用途に最適化された専用サーバーが用意されており、ワンクリックで最適なサーバーに接続できます。サーバー設置国も90カ国以上と豊富です。業界最長クラスの45日間返金保証を提供しているため、じっくりとサービスを試してから利用を決められるのも嬉しいポイントです。
PureVPN
PureVPNは、長年の運営実績を持つ老舗のVPNサービスです。世界78カ国以上に6,500台以上のサーバーネットワークを誇ります。セキュリティ監査を定期的に受けており、信頼性が高いのが特徴です。最大10台のデバイスで同時接続が可能で、家族での利用にも十分対応できます。通信速度も比較的安定しており、日常的な利用でストレスを感じることは少ないでしょう。シンプルな料金プランで、分かりやすいのも魅力の一つです。
ExpressVPN
ExpressVPNは、業界トップクラスの通信速度と安定性を誇るプレミアムなVPNサービスです。独自の「Lightway」プロトコルにより、高速かつ安全な接続を実現しています。世界105カ国にサーバーを展開しており、どこにいても快適な接続が期待できます。アプリの使いやすさにも定評があり、あらゆるデバイスで直感的に操作できます。料金は他のサービスと比較するとやや高めですが、その分、最高のパフォーマンスと信頼性を求めるユーザーに適しています。24時間365日のライブチャットサポートも高く評価されています。
ChatGPTを規制国で使う際のVPN選びのポイント
数あるVPNサービスの中から、自分に合ったものを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、VPN選びで特に注目すべき5つのポイントを解説します。
VPNの速度
VPNを経由すると、通信が暗号化され、海外のサーバーを通るため、どうしても通信速度は若干低下します。しかし、サービスの品質によってその低下率は大きく異なります。ChatGPTとのやり取りはテキストが中心ですが、速度が遅いとレスポンスが悪くなり、ストレスを感じることがあります。動画視聴やオンラインゲームなど、他の用途でも快適に使いたい場合は特に、高速な通信プロトコル(例: NordVPNのNordLynx, ExpressVPNのLightway)を提供しているか、第三者機関による速度テストで良い結果が出ているかなどを確認しましょう。
料金
VPNサービスの料金は、月額数百円から2,000円程度まで様々です。一般的に、1ヶ月ごとの短期契約よりも、1年や2年といった長期契約の方が月額あたりの料金は大幅に安くなります。まずは自分の利用したい期間を考え、総額で比較検討することが大切です。多くのVPNサービスでは、30日間程度の返金保証期間を設けています。この期間を利用して、実際に自分の環境で速度や使い勝手を試し、満足できなければ返金してもらうという方法も賢い選択です。
日本語対応の有無
海外製のVPNサービスが多いですが、公式サイトやアプリ、サポートが日本語に対応しているかは、特に初心者にとって重要なポイントです。設定方法で分からないことがあったり、トラブルが発生したりした際に、日本語でスムーズに問い合わせができると安心です。本記事で紹介した5つのVPNは、いずれも日本語にしっかりと対応しているため、安心して利用できます。
同時接続台数
1つのVPN契約で、同時に何台のデバイスを接続できるかも確認しておきましょう。PC、スマートフォン、タブレットなど、複数のデバイスでVPNを利用したい場合、同時接続台数が多いほど便利です。Surfsharkのように接続台数が無制限のサービスもあれば、5〜10台程度が一般的です。自分の持っているデバイスの数や、家族と共有するかどうかを考えて、十分な台数のサービスを選びましょう。
サポート体制
万が一、接続がうまくいかない、設定が分からないといった問題が発生した際に、迅速で的確なサポートを受けられるかは非常に重要です。24時間365日対応のライブチャットを提供しているサービスは、いつでもすぐに問題を解決できるため心強いです。また、ウェブサイト上に詳細なFAQや設定ガイドが用意されているかも確認しておくと良いでしょう。サポートの評判については、ユーザーのレビューなどを参考にすることも有効です。
日本という国におけるChatGPTの現状と今後の展望
海外で規制の動きがある一方、日本ではChatGPTに対してどのような対応が取られているのでしょうか。ここでは、日本の現状と今後の見通しについて解説します。
日本のChatGPT規制状況
2025年現在、日本政府はChatGPTの利用を直接的に禁止するような法律や規制は導入していません。世界的に見ても、比較的寛容な姿勢を取っていると言えます。岸田首相がOpenAIのCEOと面会するなど、政府としてはAI技術の活用に前向きな姿勢を示しています。
ただし、無条件に利用を推奨しているわけではありません。政府は「AI戦略会議」などを通じて、偽情報のリスク、著作権の問題、個人情報の保護といった課題について議論を進めています。また、各省庁や地方自治体では、業務で利用する際のガイドライン策定が進められており、機密情報を入力しない、生成された情報のファクトチェックを徹底するといった基本的なルールが定められつつあります。
こちらは首相官邸が公開しているAI戦略会議の資料です。日本政府の具体的な議論の内容について、合わせてご覧ください。 https://www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202506/02ai.html
企業や教育現場での活用事例
日本では、多くの企業がChatGPTを業務効率化に活用し始めています。メールや企画書の草案作成、議事録の要約、プログラミングコードの生成、顧客からの問い合わせ対応など、その用途は多岐にわたります。パナソニック コネクトや大和ハウス工業といった大企業が、全社的にセキュアな環境で利用できる独自のChatGPT環境を導入する事例も出てきています。
教育現場においても、文部科学省が暫定的なガイドラインを公表し、情報活用能力の育成や教員の業務負担軽減といった観点から、限定的で適切な活用を模索する動きが始まっています。レポート作成の補助や、ディスカッションのテーマ出しなど、生徒の思考力や創造性を引き出すためのツールとしての可能性が期待されています。
こちらは文部科学省が公表した、教育現場における生成AIの利活用に関するガイドラインです。合わせてご覧ください。 https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf
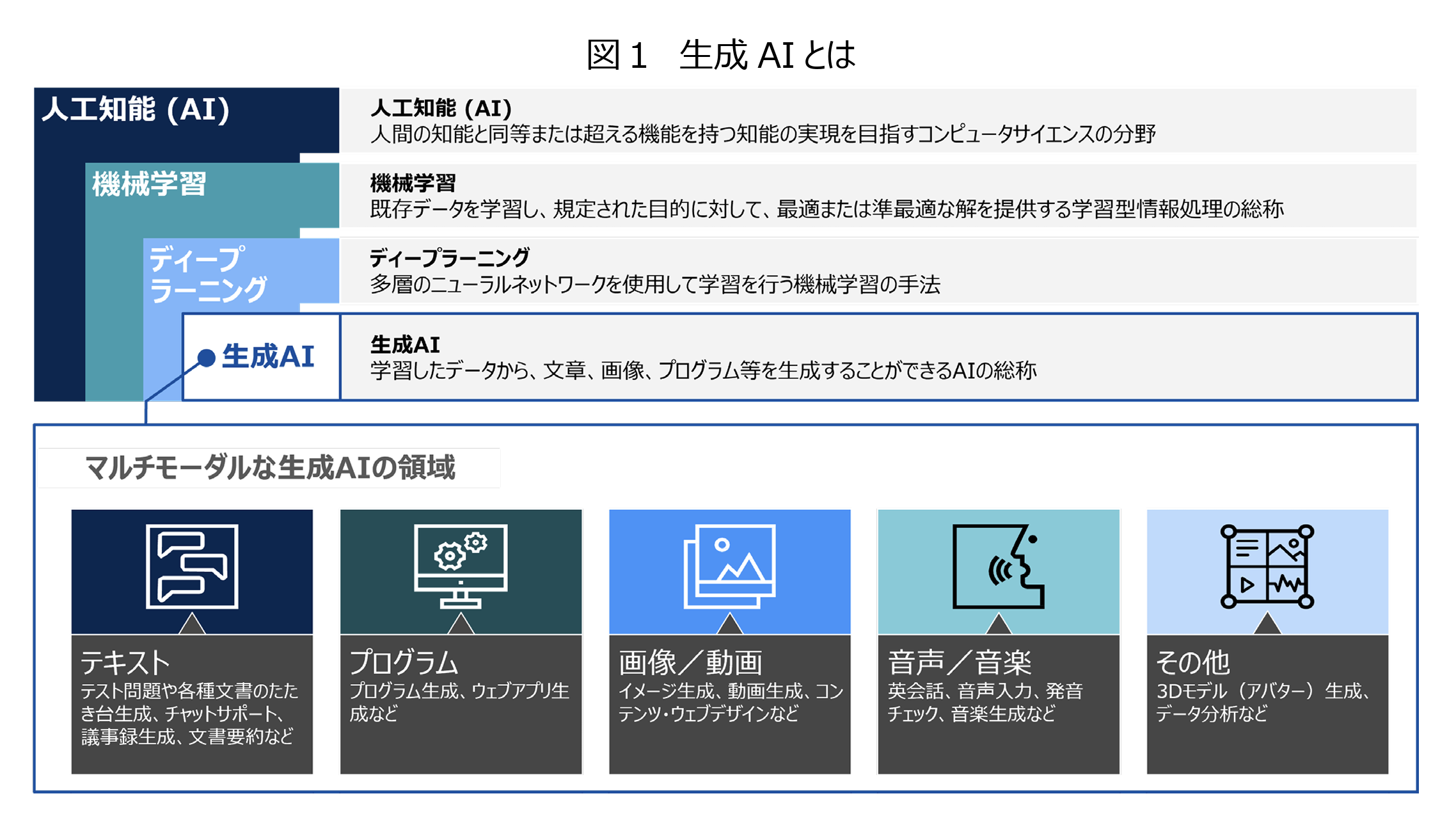
今後の法整備や将来性
今後は、EUの「AI Act」など国際的な規制の動向も踏まえながら、日本国内での法整備が進むと予想されます。特に、著作権法との関係については、文化庁を中心に議論が続けられており、AIの学習データ利用に関するルールや、AI生成物の著作権保護のあり方などが今後の焦点となります。
また、AIが生成した情報であることを利用者に明示する義務や、偽情報対策に関する事業者の責任など、より具体的なルール作りが進められていくでしょう。政府は、イノベーションを阻害しないように配慮しつつ、国民がAIを安全・安心に利用できる環境を整備していく方針であり、日本は今後、AIの社会実装における先進国の一つとなる可能性があります。
ChatGPTと国の関係性に関するよくある質問
最後に、ChatGPTと各国の規制や法律に関する、よくある質問とその回答をまとめました。
ChatGPTが悪用された事例はありますか?
はい、残念ながら悪用事例は報告されています。代表的なものとして、フィッシング詐欺が挙げられます。ChatGPTを使って、本物の企業やサービスから送られてきたように見える、非常に巧妙な詐EメールやSMSを作成し、受信者を偽サイトに誘導して個人情報やクレジットカード情報を盗み出す手口です。
また、マルウェア(コンピューターウイルス)の作成に利用されるケースもあります。サイバー攻撃者が、特定の機能を持つマルウェアのコードをChatGPTに生成させ、攻撃に利用するのです。その他にも、SNS上で特定の人物になりすまして詐欺を働いたり、偽ニュースを作成して社会を混乱させたりするといった目的で悪用される可能性が指摘されています。
ChatGPTの利用は違法になる場合がありますか?
ChatGPTを利用すること自体が直ちに違法となる国は、本記事で紹介した利用禁止国を除けば、ほとんどありません。しかし、使い方によっては違法行為に該当する可能性があります。
最も注意すべきなのは著作権侵害です。既存の小説や歌詞、記事などをChatGPTに入力して、酷似した内容を生成させ、それを自分の作品として公開したり販売したりすると、著作権侵害に問われる可能性があります。
また、ChatGPTを使って他人を誹謗中傷する文章を作成し公開すれば名誉毀損罪に、犯罪を助長するような情報を生成・拡散すれば犯罪教唆にあたる可能性もあります。ツールの利用自体ではなく、その利用目的や生成されたコンテンツの扱い方が法に触れるかどうかを判断する上で重要になります。
ChatGPTを利用する上で知っておくべき注意点やリスク、社会的影響については、こちらの記事で詳しく解説しています。
VPNを安く利用する方法はありますか?
VPNサービスをできるだけ安く利用するには、いくつかの方法があります。最も効果的なのは、長期プランを契約することです。ほとんどのVPNサービスでは、1ヶ月契約よりも1年や2年といった長期契約の方が、月額換算の料金が大幅に割引されます。
また、VPNプロバイダーは、ブラックフライデーやサイバーマンデー、年末年始などの特定の時期に、大幅な割引キャンペーンを実施することがよくあります。急いでいなければ、こういったセール時期を狙って契約するのも一つの手です。
さらに、VPNの興味深い活用法として、サブスクリプションサービスを安く契約するという裏技もあります。YouTube PremiumやNetflixなどのサービスは、国によって月額料金が異なります。VPNを使って物価の安い国(例:トルコ、アルゼンチンなど)のサーバーに接続し、その国経由で契約することで、日本で契約するよりも料金を安く抑えられる場合があります。ただし、サービスの利用規約に違反する可能性もあるため、自己責任で行う必要があります。
ChatGPTが使えない?国境を越えるAI活用とセキュリティの壁
海外出張やグローバルな業務の最中に、いつも使っているChatGPTが突然アクセスできなくなったらどうしますか?現在、中国やロシア、EUの一部の国々では、プライバシー保護や情報統制を理由に、ChatGPTをはじめとする生成AIの利用に厳しい制限が設けられています。これは、グローバルに事業を展開する企業にとって、業務効率の低下や情報収集の遅延に直結する大きな課題です。安易に無料VPNなどを使えばアクセスできるかもしれませんが、そこには企業の機密情報が漏洩する深刻なリスクが潜んでいます。各国のデータ保護当局は、個人情報の越境移転に厳しい目を光らせており、規制違反は大きな問題に発展しかねません。便利なツールであるはずのAIが、企業のセキュリティホールになってしまう危険性があるのです。
引用元:
欧州連合(EU)では、GDPR(一般データ保護規則)に基づき、個人データの保護が厳格に求められており、イタリアのデータ保護当局は実際に一時的な利用禁止措置を取りました。また、カナダのプライバシー・コミッショナー事務局も、個人情報の収集方法についてOpenAI社への調査を開始するなど、西側諸国でもデータプライバシーに関する懸念は高まっています。
まとめ
企業がグローバルに事業を展開する上で、生成AIの活用は業務効率化や情報収集の強力な武器となります。
しかし、本記事で解説したように、国ごとに異なるAI規制や、プライバシー、情報漏洩のリスクは無視できない課題です。
社員が個人で危険なVPNを利用したり、機密情報を入力したりするシャドーITは、企業の深刻なセキュリティインシデントに直結しかねません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、海外拠点向けのメール作成や議事録作成、現地のレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏洩の心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「各国の規制を考慮した安全な使い方がわからない」という企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに安全な環境で業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“安全な生成AI活用”を体験し、御社のグローバルDXを一気に加速させましょう。