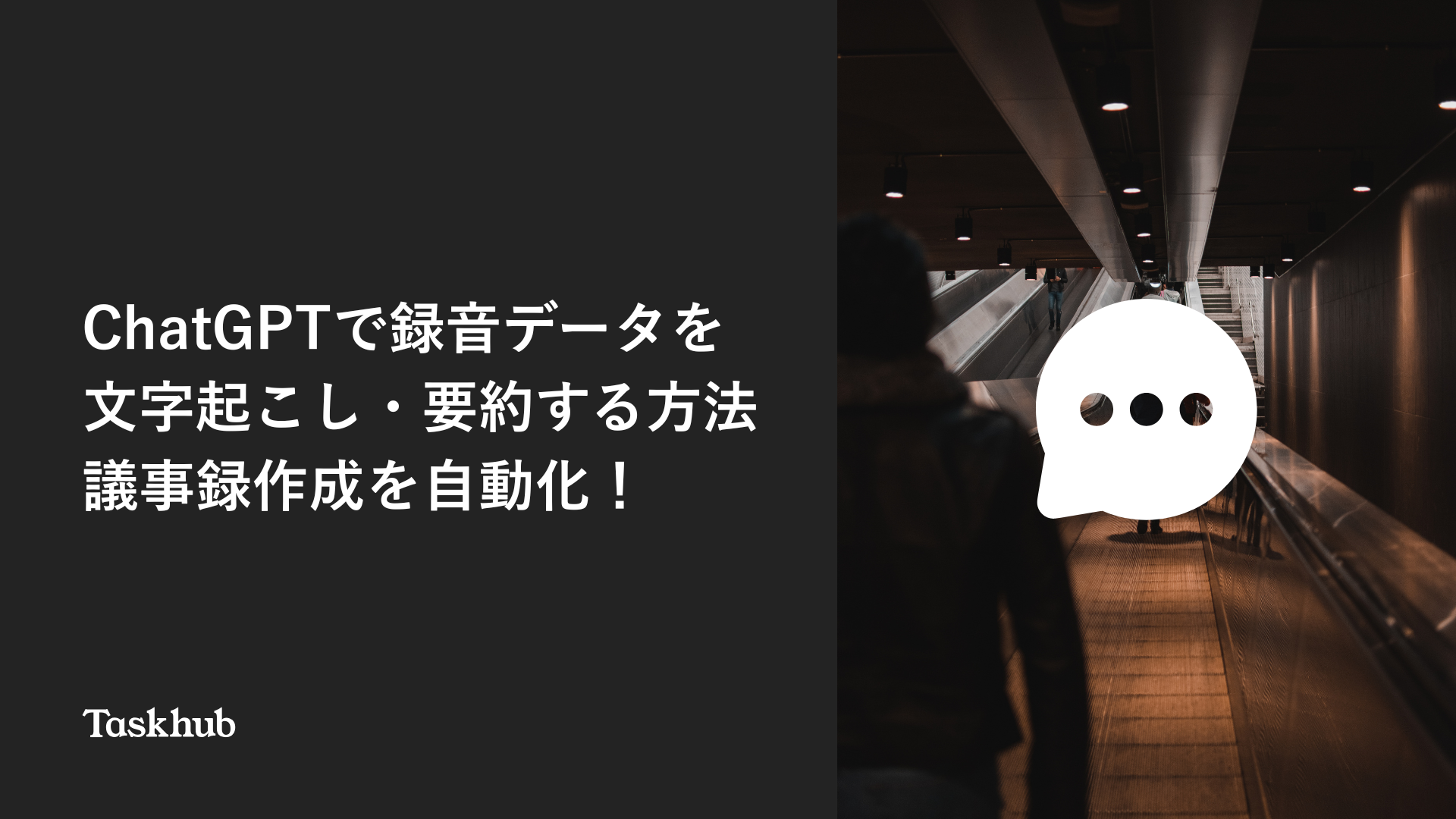「ChatGPTで会議の録音データを文字起こしできるって本当?」
「録音データをアップロードしてみたけど、うまく要約してくれない…。」
こういった悩みや疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
ChatGPTの機能を活用すれば、録音データの文字起こしから要約、議事録作成までを自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
本記事では、ChatGPTで録音データを扱う具体的な方法から、コピペで使えるプロンプト集、さらに精度を上げるためのコツまで、網羅的に解説します。
こちらはChatGPTの業務活用事例40選と注意点、成功の秘訣を網羅したガイドです。 合わせてご覧ください。
生成AIの活用支援を行う専門家の知見を基に、実践的な内容だけをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ChatGPTで録音データの文字起こしや議事録作成はできる?
まずはじめに、ChatGPTを使って録音データから議事録を作成することが、どの程度可能なのかについて解説します。
結論から言うと、いくつかの方法を使い分けることで、文字起こしから議事録の清書までを十分に自動化できます。
結論:専用ツールとの連携やプロンプトの工夫で実現可能
ChatGPTには音声認識機能が搭載されており、音声ファイルをアップロードするだけで簡単に文字起こしができます。
しかし、より高精度な文字起こしや話者の特定を求める場合は、専用のAI文字起こしツールと連携するのがおすすめです。
また、文字起こししたテキストをChatGPTに読み込ませ、適切なプロンプト(指示文)を与えることで、要約や議事録形式への清書、ToDoリストの抽出などを自動で行えます。
ChatGPTで録音データを活用してできること
ChatGPTと録音データを組み合わせることで、以下のような様々なタスクを自動化できます。
- 会議の録音データを文字起こしする
- 文字起こししたテキストを要約する
- 議事録・レポート形式に清書する
- 決定事項やToDoリストを抽出する
- 特定のキーワードに関する発言部分を探し出す
これらの作業を自動化することで、これまで議事録作成に費やしていた時間を大幅に削減し、より重要な業務に集中できるようになります。
【簡単】ChatGPTで録音データを文字起こしする方法4選
ここからは、ChatGPTで録音データを文字起こしするための具体的な方法を4つ紹介します。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適なものを選んでください。
それでは、1つずつ順に解説します。
方法1:【PC・スマホ】音声ファイルや録音データを直接アップロードして文字起こしする(公式機能)
最も基本的な方法が、ChatGPTの公式機能を使って音声ファイルを直接アップロードすることです。
PCのブラウザ版、スマートフォンのアプリ版ともに、チャット入力欄にあるクリップマークから音声ファイル(MP3, M4A, WAVなど)を選択して送信するだけで、自動的に文字起こしが開始されます。
特別なツールは不要で、誰でもすぐに試せるのが大きなメリットです。
ただし、非常に長い音声ファイルや、音質が悪い録音データの場合、文字起こしの精度が落ちることがあります。
方法2:【一番手軽】スマホアプリに直接話しかけてリアルタイムで文字起こしする
短い音声を手軽にテキスト化したい場合は、スマートフォンのChatGPTアプリのマイク機能が便利です。
アプリを開いてヘッドフォンマークをタップし、スマートフォンに直接話しかけるだけで、リアルタイムで音声を認識し、テキストに変換してくれます。
会議全体の文字起こしには向きませんが、個人のアイデアをメモしたり、簡単な打ち合わせの内容を備忘録として残したりする際に非常に役立つ方法です。
移動中や外出先でも手軽に利用できるのが魅力です。
方法3:【Web会議に】Zoom等の文字起こし結果をコピペして要約・清書する
ZoomやGoogle Meet、Microsoft Teamsといった主要なWeb会議ツールには、会議中の音声を自動で文字起こしする機能が備わっています。
この機能を使って生成されたテキストデータをコピーし、ChatGPTに貼り付けて「この内容を要約して」「議事録の形に整えて」といった指示を出す方法も非常に効率的です。
この方法であれば、ChatGPTに直接録音データをアップロードする必要がなく、すでにテキスト化されたデータを活用できるため、スムーズに作業を進められます。
方法4:【高精度】Notta等のAI文字起こしツールと連携する
最も高い精度を求めるなら、AI文字起こし専門ツールとの連携が最適です。
「Notta」や「Rimo Voice」といったツールは、話者分離(誰が話したかを特定する)機能や、専門用語に強い高精度な文字起こしエンジンを搭載しています。
これらのツールで完璧に近いテキストデータを作成し、そのテキストをChatGPTに読み込ませて要約や清書を行わせるのが、最も質の高い議事録を作成するための王道パターンと言えるでしょう。
手間は一つ増えますが、その分、手戻りの少ない正確な成果物が得られます。
こちらは、記事内でも紹介されているAI文字起こしツール「Notta」について、他のツールとの比較も交えてレビューしている記事です。合わせてご覧ください。 https://www.meetjamie.ai/blog/otter-ai-vs-notta
【コピペで使える】録音データの要約・議事録作成プロンプト集
文字起こしが完了したら、次はそのテキストデータをChatGPTに読み込ませ、議事録として整形していきます。
ここでは、コピー&ペーストしてすぐに使える5つの便利なプロンプトをご紹介します。
こちらは、より効果的なプロンプトを作成するための基本的なテクニックを解説したMicrosoftの公式ドキュメントです。合わせてご覧ください。
テキスト プロンプトは、ユーザーが GPT モデルと対話する方法です。 すべての生成言語モデルと同様に、GPT モデルも、前のテキストから続く可能性が最も高い次の一連の単語を生成しようとします。 これは、”私が
<prompt>と言ったとき、最初に頭に浮かぶことは何ですか?” と質問するのと同じです。次の例は、この動作を示しています。 有名なコンテンツの最初の単語を指定すると、モデルはテキストを正確に続けることができます。
引用元:プロンプトエンジニアリング技術 – Azure OpenAI | Microsoft Learn
会議の要点を簡潔にまとめさせるプロンプト
まずは、文字起こししたテキスト全体の要点を掴むためのプロンプトです。
長い会議の内容を短時間で把握したい場合に役立ちます。
#命令書
以下の会議の文字起こしテキストから、主要なトピックと結論を抽出し、箇条書きで簡潔に要約してください。
#文字起こしテキスト
(ここにテキストを貼り付ける)
決定事項と担当者、期限(ToDo)を抽出させるプロンプト
会議で決まったこと、誰がいつまでに行うべきかを明確にするためのプロンプトです。
アクションアイテムの抜け漏れを防ぐのに非常に効果的です。
#命令書
以下の会議の文字起こしテキストから、すべての決定事項とToDo(タスク)を抽出してください。
それぞれのToDoについて、「担当者」と「期限」を明記し、テーブル形式で出力してください。
#文字起こしテキスト
(ここにテキストを貼り付ける)
「あの」「えーっと」などの不要な言葉を削除して清書させるプロンプト
文字起こしテキストには、「あのー」「えーっと」といった、議事録には不要なフィラー(つなぎ言葉)が含まれています。
これらを自動で削除し、読みやすい文章に整形するプロンプトです。
#命令書
以下の文字起こしテキストに含まれる「あのー」「えーっと」などの不要なフィラーワードをすべて削除し、発言の意図を保ったまま、自然で読みやすい文章に清書してください。
#文字起こしテキスト
(ここにテキストを貼り付ける)
会話形式のまま議事録を作成させるプロンプト
会議の臨場感や議論の流れをそのまま残したい場合に有効なプロンプトです。
誰がどのような発言をしたのかを時系列で追いやすくなります。
#命令書
以下の文字起こしテキストを元に、話者ごとの発言がわかる会話形式の議事録を作成してください。
話者の名前を明確にし、議論の流れが理解しやすいように構成してください。
#制約条件
・話者が不明な場合は「不明」と記載してください。
#文字起こしテキスト
(ここにテキストを貼り付ける)
文字起こしデータからFAQを作成させるプロンプト
会議やセミナーの録音データから、よくある質問とその回答の形式で情報をまとめるプロンプトです。
ナレッジの共有や、顧客向けの説明資料を作成する際に役立ちます。
#命令書
以下の文字起こしテキストの内容を分析し、想定される質問とそれに対する回答をまとめたFAQリストを作成してください。
質問と回答は、一対一で分かりやすく記述してください。
#文字起こしテキスト
(ここにテキストを貼り付ける)
文字起こし・要約の精度を格段に上げる5つのコツ
ChatGPTによる文字起こしや要約の精度は、いくつかのコツを押さえることで格段に向上します。
ここでは、今日から実践できる5つのテクニックを紹介します。
コツ1:クリアな音質で録音する
最も重要なのは、元となる録音データの音質です。
AIはノイズや反響が多い環境、話者の声が小さい録音を正確に認識するのが苦手です。
可能な限り静かな場所で、マイクを使ってクリアに録音することを心がけましょう。
「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れたらゴミしか出てこない)」の原則は、AIにおいても同様です。
質の高いインプットが、質の高いアウトプットにつながります。
コツ2:プロンプトで専門用語や話者の情報を事前に与える
文字起こしや要約を依頼する際に、会議の背景情報をChatGPTに与えることで精度が向上します。
「これは〇〇というプロジェクトに関する定例会議の録音です」「登場人物はAさん(部長)、Bさん(担当者)です」「〇〇という専門用語が出てきます」のように、固有名詞や文脈を事前にインプットしておきましょう。
これにより、AIが文脈を理解しやすくなり、誤認識や不自然な要約を防ぐことができます。
コツ3:長文の場合は分割して処理する
ChatGPTには一度に処理できるデータ量(トークン数)に上限があります。1時間を超えるような長時間の録音データを一度に処理しようとすると、エラーが発生したり、後半部分が無視されたりする可能性があります。
長い録音データの場合は、10分〜15分程度のセグメントに分割してからアップロードするか、文字起こし後のテキストを分割して入力するのが確実です。
面倒に感じるかもしれませんが、結果的に正確なアウトプットを得るための近道となります。
コツ4:段階的に指示を出して精度を調整する(要約→清書→ToDo抽出など)
一度のプロンプトで全ての作業を完璧に終わらせようとせず、対話を重ねるように段階的に指示を出すのが精度を高めるコツです。
例えば、まずは「文字起こしテキストを要約して」と指示し、出力された内容を確認します。
次に、その要約を元に「この内容を議事録形式に清書して」と依頼し、最後に「この議事録からToDoを抽出して」というように、ステップを踏むことで、各段階で微調整が可能になり、最終的な成果物の質を高めることができます。
コツ5:最新モデル(GPT-5など)を利用する
OpenAIは常に新しい言語モデルを開発しており、最新のモデルほど性能が高くなります。
現在、多くのユーザーが利用できる高性能モデルはGPT-4oですが、2025年8月にはさらに進化したGPT-5もリリースされています。
GPT-5はより複雑な推論や文脈理解に長けているため、文字起こしや議事録作成の精度も飛躍的に向上しています。
有料プランに加入している場合は、可能な限り最新・最高性能のモデルを選択することで、より満足のいく結果を得られるでしょう。
こちらはGPT-5の機能、料金、GPT-4との違いを解説した記事です。 合わせてご覧ください。
ChatGPTで録音データを活用する3つのメリット
ChatGPTで録音データを文字起こし・要約することは、単なる時短術にとどまらない多くのメリットをもたらします。
ここでは、代表的な3つのメリットをご紹介します。
議事録作成にかかる時間と手間を大幅に削減できる
最大のメリットは、やはり業務効率化です。
従来、数時間の会議の議事録を作成するには、録音を聞き返しながら数時間以上かかることも珍しくありませんでした。
ChatGPTを活用すれば、文字起こしから清書まで、このプロセスにかかる時間を数分の一に短縮できます。
これにより創出された時間を、より創造的で付加価値の高い業務に充てることが可能になります。
会議中は議論に集中できる
議事録作成を担当すると、どうしてもメモを取ることに意識が向いてしまい、本来参加すべき議論に集中できないことがあります。
「後で録音から議事録を作成できる」という安心感があれば、会議中はメモを取る必要がなくなり、参加者全員が議論そのものに100%集中できます。
これにより、会議の質が向上し、より良い意思決定につながる可能性が高まります。
重要な発言の聞き逃しや解釈のズレを防げる
人間の記憶は曖昧で、会議後に「言った、言わない」といった問題が発生することがあります。
録音データから客観的なテキスト記録を作成しておくことで、すべての発言が正確に記録され、後からいつでも確認できます。
これにより、重要な発言の聞き逃しや、担当者間の解釈のズレを防ぎ、プロジェクトをスムーズに進行させるための共通認識を形成するのに役立ちます。
【重要】ChatGPTで録音データを扱う際の注意点とリスク
非常に便利なChatGPTの録音データ活用ですが、利用する上で必ず知っておくべき注意点とリスクが存在します。
安全に活用するために、以下のポイントを必ず守ってください。
機密情報・個人情報を含む音声は入力しない
ChatGPTのデフォルト設定では、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があります。
そのため、企業の未公開情報や取引先の情報、個人情報といった機密情報を含む録音データを、安易にアップロードするべきではありません。
業務で利用する場合は、入力データが学習に使われない設定(オプトアウト申請)を行うか、セキュリティが担保された法人向けプランやAPI、もしくは専用の法人向けAIサービスを利用することを徹底してください。
こちらは、大規模言語モデルを企業で利用する際の具体的なリスクについて分析した日本の学術論文です。合わせてご覧ください。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2024/0/JSAI2024_2I6GS1004/_article/-char/ja
文字起こしや要約の精度は100%ではないため最終確認は必須
AIによる文字起こしや要約の精度は飛躍的に向上していますが、決して100%完璧ではありません。
特に、固有名詞、専門用語、数値、同音異義語などは誤って認識されることがあります。
AIが生成したテキストはあくまで「下書き」と捉え、必ず人間の目で最終的なファクトチェックと修正を行うことが不可欠です。
内容の正確性が求められる公式な議事録などでは、この確認作業を怠らないようにしましょう。
こちらはChatGPTのハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
長時間の録音データは一度に処理できない場合がある
前述の通り、ChatGPTには一度に処理できるデータ量に制限があります。
特に無料版では、アップロードできるファイルサイズや処理時間に厳しい制約が設けられている場合があります。
数十分に及ぶ会議の録音データを丸ごと処理しようとすると、途中で処理が止まってしまったり、エラーが表示されたりすることがあります。
長いデータを扱う際は、ファイルを分割するなどの工夫が必要です。
もっと効率化したい人へ!おすすめAI議事録作成ツール3選
ChatGPTは非常に汎用性が高いツールですが、議事録作成に特化したAIツールも数多く存在します。
これらのツールは、より高い精度や便利な機能を備えており、さらなる業務効率化を実現します。
こちらは、本文で紹介したツール以外も含む、最新のAI文字起こしツールを10個厳選して比較している記事です。合わせてご覧ください。 https://www.interview-ai.site/en/article/comparison-of-the-latest-ai-transcription-tools-2024-edition-selected-top-10-recommendations/
Rimo Voice
Rimo Voiceは、日本語の文字起こし精度に定評があるツールです。
話者分離機能はもちろん、「あのー」「えーと」といったフィラーを自動で除去する機能や、要点をまとめたサマリーを自動生成する機能が強力です。
特に日本語の会議が多い企業におすすめのツールです。
YOMEL
YOMELは、ZoomやTeamsと連携し、Web会議の内容をリアルタイムで文字起こし・要約してくれるツールです。
会議中にリアルタイムで文字起こし結果を確認できるため、聞き逃した部分をすぐに参照できます。
会議終了後には自動で議事録が生成されるため、スピード感を重視する現場で重宝されています。
Notta
Nottaは、104言語に対応する高精度なAI文字起こしツールです。
Web会議の録画や音声ファイルのインポートはもちろん、リアルタイム文字起こしも可能です。
話者分離やタイムスタンプ機能も充実しており、世界中の様々なビジネスシーンで活用されています。
多言語対応が必要なグローバルな環境で働く方におすすめです。
ChatGPT単体と専用ツールの違い
ChatGPT単体での利用は、手軽に始められる点が魅力ですが、議事録作成に特化した専用ツールは、話者分離、タイムスタンプ、リアルタイム文字起こしといった機能面で優れています。
コストや求める機能に応じて使い分けるのが良いでしょう。
最も効率的なのは、専用ツールで高精度な文字起こしを行い、そのテキストをChatGPTでさらに加工・分析するというハイブリッドな活用方法です。
ChatGPTの録音活用に関するよくある質問
最後に、ChatGPTの録音活用に関して、ユーザーからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
無料でどこまでできますか?
無料プランでも、音声ファイルのアップロードによる文字起こし機能を利用することは可能です。
ただし、最新モデル(GPT-5など)の利用には制限があり、例えば5時間あたり10メッセージまでといった制約が設けられています。
また、一度にアップロードできるファイルのサイズや、処理の速度においても有料プランの方が優遇されています。
簡単な文字起こしを試す程度であれば無料でも十分ですが、本格的に業務で活用する場合は有料プランの検討をおすすめします。
何分くらいの録音データまで対応できますか?
公式に明確な時間制限は発表されていませんが、一般的にファイルサイズやモデルが処理できるトークン数に依存します。
経験上、10分〜15分程度(ファイルサイズにして25MB以内)の音声ファイルであれば、比較的安定して処理できることが多いです。
それ以上の長さになる場合は、前述の通り、ファイルを分割するか、専門の文字起こしツールを利用するのが確実です。
日本語の精度はどのくらいですか?
GPT-4o以降のモデルでは、日本語の認識精度が大幅に向上しており、非常に高いレベルにあります。
明瞭な発音で、雑音が少ない環境であれば、ほとんど修正が不要なケースも少なくありません。
ただし、方言や早口、専門用語が多い会話、複数人が同時に話すような場面では精度が低下する傾向があります。
過信はせず、あくまで最終確認は人間が行うという前提で利用することが重要です。
こちらは、医療現場のような専門用語が多く、高い正確性が求められる環境でAI文字起こしツールがどのように評価されているかを示した学術レビューです。合わせてご覧ください。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12220090/
AIによる自動化は思考力を奪う?議事録作成の先にある未来
ChatGPTによる議事録作成の自動化は、間違いなく私たちの業務を効率化してくれます。しかし、その便利さの裏で、私たちは本当に「成長」できているのでしょうか。単純作業をAIに任せ続けることで、私たちの脳から重要なスキルが静かに失われていく危険性はないでしょうか。世界経済フォーローラムの報告書は、AI時代にこそ人間の「分析的思考」や「創造的思考」が不可欠になると警告しています。この記事では、AIによる自動化の恩恵を受けつつも、思考停止に陥らないための新しい仕事術を探ります。
AIに頼りすぎると失われるかもしれない3つのビジネススキル
議事録作成のような業務をAIに完全に依存してしまうと、次のようなビジネスに不可欠なスキルが鈍化する可能性があります。
- 文脈を読み解く力:会議のテキストだけでは分からない、発言者の表情や声のトーン、その場の雰囲気といった非言語情報を汲み取り、議論の真の意図を理解する能力が低下する恐れがあります。
- 情報を要約し構造化する力:AIが生成した要約を鵜呑みにするだけでは、膨大な情報の中から何が本当に重要かを取捨選択し、論理的に再構築する思考プロセスが省略されてしまいます。
- 批判的に思考する力:AIの生成したToDoリストや決定事項を無批判に受け入れることで、「本当にそれが最善の策か?」「他に選択肢はないのか?」と問い直す、より高いレベルでの思考機会が失われかねません。便利なツールは、使い方を間違えれば、私たちの思考力を徐々に蝕んでいく諸刃の剣にもなり得るのです。
引用元:
世界経済フォーラムの「仕事の未来レポート2023」では、今後5年間でビジネスリーダーが最も重要だと考えるスキルとして、「分析的思考」「創造的思考」が挙げられています。これは、AIによる自動化が進む中で、人間にしかできない高次の認知能力の価値が相対的に高まることを示唆しています。(World Economic Forum “The Future of Jobs Report 2023” 2023年)
AIを「思考の補助線」として活用する新手法
では、思考停止を避け、AI時代に価値を高める人材になるにはどうすればよいのでしょうか。答えは、AIを「作業の代行者」ではなく「思考を深めるためのパートナー」として捉え直すことです。
- AIの要約を「壁打ち」に使う:AIが作成した議事録の要約を読んだ後、一度自分自身の言葉で「この会議の最も重要なポイントは何か」を再定義してみましょう。そして、自分の要約とAIの要約を比較することで、視点の違いや思考の癖を発見できます。
- ToDoリストを「戦略立案」の題材にする:AIが抽出したToDoリストを、ただの作業リストとして受け取るのではなく、「なぜこのタスクが必要なのか?」「どのタスクから着手すれば最もインパクトが大きいか?」という問いを立て、優先順位付けや実行計画を自ら組み立てることで、戦略的思考を鍛えることができます。
- 別の視点をAIに要求する:完成した議事録をAIに読み込ませ、「この議論について、もしあなたが全く別の部署の人間だったら、どのような懸念点を挙げますか?」と質問してみましょう。これにより、自分一人では気づけなかったリスクや新たな可能性を発見し、多角的な視点を養うことができます。AIは答えを出す機械ではなく、私たちの思考を刺激し、新たな視点を与えてくれる触媒です。AIの出力結果をゴールではなく、思考のスタートラインとすることで、私たちは自動化の波に乗りこなし、より創造的な存在へと進化できるのです。
まとめ
ChatGPTを活用すれば、議事録作成のような時間を要する業務を効率化できることは間違いありません。
しかし、本文で解説したように、情報漏えいのリスク管理や、用途に応じた複雑なプロンプトの作成、そしてAIの出力精度をいかに担保するかといった、企業で本格的に活用するには多くの課題が残ります。
そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。
Taskhubは、議事録作成や文字起こしといった日常業務を、誰でもワンクリックで実行できる「アプリ」として200種類以上搭載した、日本初の生成AIプラットフォームです。
面倒なプロンプトを考える必要はなく、目的に合ったアプリを選ぶだけで、AIの専門知識がない社員でも直感的に最新のAI技術を業務に活用できます。
基盤にはセキュリティが強固なAzure OpenAI Serviceを採用しているため、企業の機密情報や個人情報を含む会議内容でも、情報漏えいの心配なく安心して処理させることが可能です。
さらに、専門のAIコンサルタントが導入から活用までを徹底的にサポートするため、「AIをどう業務に活かせばいいかわからない」という企業でも、具体的な成果に繋げることができます。
まずは、Taskhubがどのように御社の業務を変革できるか、その具体的な活用事例をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてご確認ください。
Taskhubで、安全かつ簡単な生成AI活用を始め、企業の生産性を一気に引き上げましょう。