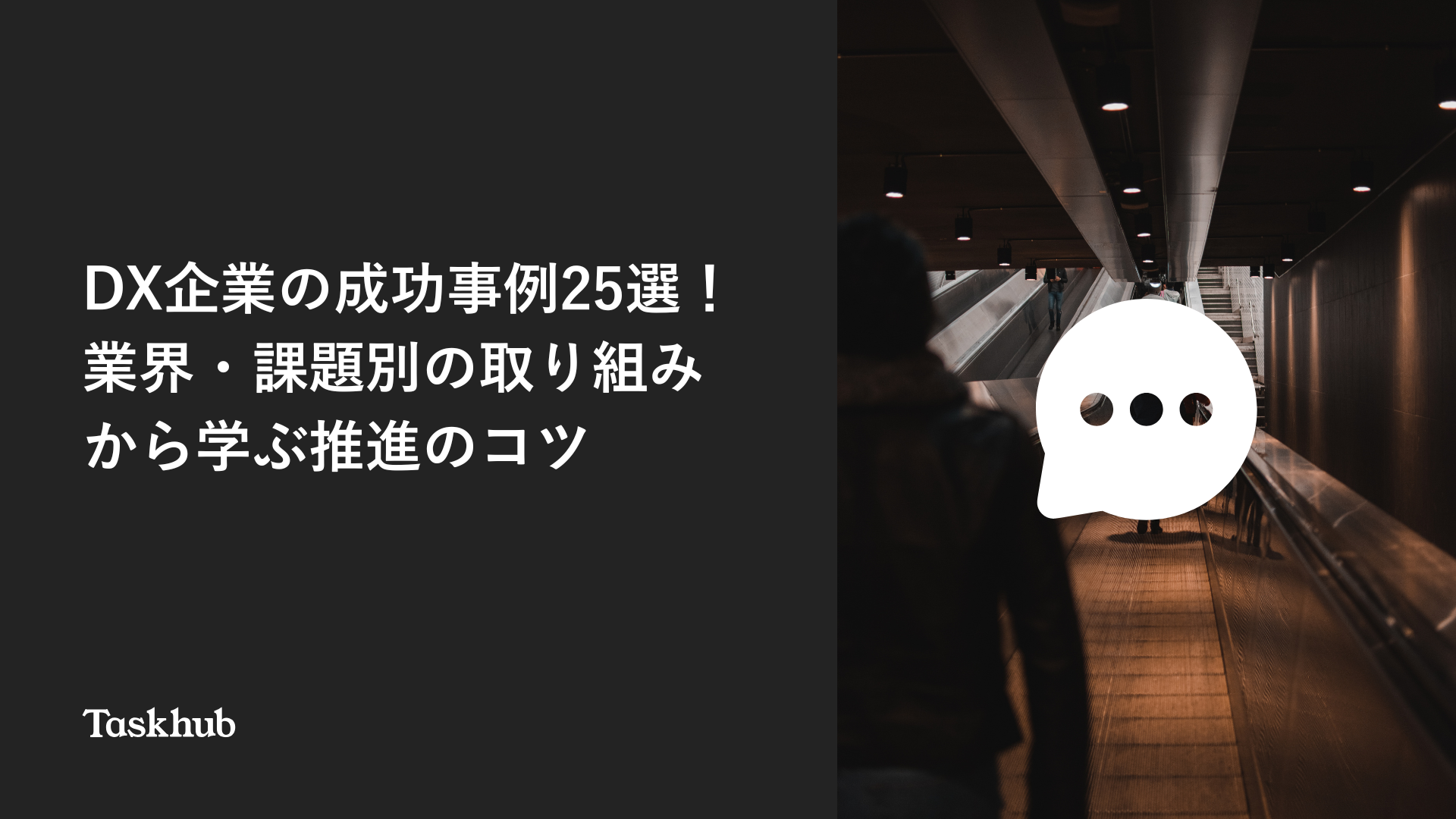「DXを推進したいが、何から手をつければ良いかわからない」
「他の企業がどんな取り組みで成功しているのか、具体的な事例を知りたい」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
本記事では、業界別に25社のDX成功事例を具体的に解説し、そこから見えてくるDX推進のコツを詳しくご紹介します。
自社の課題解決や新たなビジネス創出のヒントがきっと見つかるはずです。
ぜひ最後までご覧いただき、自社のDX戦略の参考にしてください。
まず押さえたいDXの基本と注目される企業の事例
ここでは、DXの基本的な定義や、なぜ今多くの企業で推進が求められているのか、そして日本国内の現状と課題について解説します。
成功事例を見る前に、まずはDXの全体像を正しく理解することが重要です。
それでは、1つずつ見ていきましょう。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義とは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にITツールを導入して業務を効率化することだけを指すのではありません。
経済産業省の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。
つまり、デジタル技術を前提として、ビジネスの仕組みそのものを根本から変革し、新たな価値を創造していく取り組みがDXの本質です。
なぜ今DXの推進が企業に求められるのか
現在、多くの企業でDXの推進が急務とされている背景には、いくつかの要因があります。
消費者の価値観や行動が多様化し、従来のビジネスモデルでは対応しきれない場面が増えています。
また、デジタル技術を活用した新興企業の台頭により、業界の垣根を越えた競争が激化しています。
さらに、少子高齢化による労働人口の減少や、老朽化した既存システムが足かせとなる「2025年の崖」問題も深刻です。
これらの課題に対応し、企業が持続的に成長するためには、DXによる変革が不可欠なのです。
日本国内におけるDXの現状と課題
日本国内のDXは、世界的に見て遅れをとっていると指摘されています。
多くの企業では、紙媒体の業務をデジタル化する「デジタイゼーション」や、特定の業務プロセスをITで効率化する「デジタライゼーション」の段階に留まっています。
ビジネスモデルの変革まで至る真のDXを実現するには、レガシーシステムの存在、DXを推進できるデジタル人材の不足、そして変化を恐れる組織文化などが大きな課題となっています。
これらの課題をいかに乗り越えるかが、DX成功の鍵を握ります。
こちらはDXによる業務効率化ガイドについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-business-efficiency-improvement/
【製造業】のDX推進に取り組む企業の事例
ここからは、製造業におけるDX推進企業の事例を3つ紹介します。
- 株式会社トプコン
- コマツ
- 株式会社ブリヂストン
製造業では、スマートファクトリー化や熟練技術のデジタル化など、生産性向上と品質維持を目的としたDXが進んでいます。
それでは、1社ずつ具体的に解説します。
株式会社トプコン:スマートファクトリー化による生産性向上
測量機器や眼科用医療機器メーカーのトプコンは、生産拠点である山形にスマートファクトリーを構築しました。
工場内のあらゆる機器をIoTで接続し、生産ラインの稼働状況や品質データをリアルタイムで収集・分析。
これにより、生産プロセスのボトルネックを特定し、改善サイクルを高速化させることに成功しました。
また、AR(拡張現実)技術を活用した遠隔作業支援システムも導入し、熟練技術者が若手作業員に遠隔で指示を出せる体制を構築。
結果として、生産性の大幅な向上と技術伝承の課題解決を両立させています。
コマツ:建設機械の稼働データ活用サービス「KOMTRAX」
建設機械大手のコマツは、自社の建設機械にGPSや通信システムを搭載し、車両の稼働状況を遠隔で把握できる「KOMTRAX(コムトラックス)」を早くから展開しています。
収集した位置情報、稼働時間、燃料消費量、エラーコードなどのビッグデータを分析。
顧客に対して、最適なメンテナンス時期の通知や、効率的な車両の運用方法などを提案しています。
このサービスは、単に機械を販売するだけでなく、顧客の課題解決に貢献する「ソリューション事業」への転換を象徴する事例であり、製造業のサービス化におけるDXの成功モデルと言えます。
株式会社ブリヂストン:熟練技術のデジタル化による品質向上
タイヤメーカーのブリヂストンは、タイヤ製造における熟練技能者の「匠の技」をデジタル化する取り組みを進めています。
AIと画像認識技術を活用し、熟練技能者がゴムを混ぜる際の微妙な状態変化や、タイヤを成形する際の手の動きなどをデータ化。
このデータを基に、製造設備を制御することで、技能者の経験や勘に頼っていた工程を自動化し、品質の均一化を実現しました。
これにより、製品の品質向上はもちろん、技能者の育成にかかる時間とコストの削減にも成功しており、技術伝承という製造業共通の課題に対する有効なDX事例となっています。
【卸売・小売業】のDX推進に取り組む企業の事例
ここでは、卸売・小売業でDXを推進している企業の事例を3つ紹介します。
- トラスコ中山株式会社
- マクニカホールディングス株式会社
- 株式会社ニトリホールディングス
在庫管理の最適化や、オンラインとオフラインを融合させた新たな顧客体験の創出が、この業界のDXのポイントです。
それでは、順に見ていきましょう。
トラスコ中山株式会社:在庫管理・物流システムの最適化
工場などで使われるプロツール(生産現場のプロが使う機械・工具など)の専門商社であるトラスコ中山は、DXによって物流と在庫管理を大きく変革しました。
自社開発の在庫管理システムと、需要予測AIを導入。
全国の物流センターにある膨大な在庫をリアルタイムで可視化し、AIが過去の販売データや季節変動を基に最適な在庫量を算出します。
また、顧客の工場内に同社の在庫を置ける「MROストッカー」というサービスも展開。
これにより、顧客は必要な時に必要な分だけ工具を使え、同社は顧客の需要を直接把握できるという、双方にメリットのある新たなビジネスモデルを構築しました。
マクニカホールディングス株式会社:半導体供給網のデータ活用
半導体やネットワーク機器を扱う技術商社のマクニカホールディングスは、複雑なサプライチェーンの最適化にDXを活用しています。
世界中のサプライヤーや顧客から得られる需要・供給に関する膨大なデータを一元的に集約し、AIを用いて分析。
これにより、半導体の需要予測の精度を大幅に向上させ、過剰在庫や品切れのリスクを低減しています。
また、顧客に対しては、単に製品を供給するだけでなく、データに基づいた市場トレンドや技術情報を提供。
専門商社としての付加価値を高め、顧客との強固なパートナーシップを築くことに成功しています。
株式会社ニトリホールディングス:OMO戦略による顧客体験の向上
家具・インテリア小売大手のニトリホールディングスは、「OMO(Online Merges with Offline)」戦略を推進し、顧客体験の向上を図っています。
自社アプリを中心に、オンラインストアと実店舗の顧客情報や購買履歴、在庫情報を一元管理。
例えば、店舗で気になった商品のバーコードをアプリでスキャンすれば、オンラインでレビューを確認したり、後からECサイトで購入したりできます。
また、アプリ上で部屋のサイズを登録しておくと、購入したい家具が搬入可能かどうかを自動で判定してくれる機能も提供。
デジタルとリアルをシームレスに繋ぐことで、顧客一人ひとりに合わせた快適な購買体験を実現している好事例です。
【金融・保険業】のDX推進に取り組む企業の事例
金融・保険業界から、DX推進に取り組む企業の事例を2つ紹介します。
- 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
- 東京センチュリー株式会社
従来の対面中心のサービスから脱却し、デジタル技術を活用した新たなサービス創出や業務効率化が求められています。
それでは、1社ずつ見ていきましょう。
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ:デジタル技術を活用した新サービス創出
九州を地盤とするふくおかフィナンシャルグループは、デジタルバンク「みんなの銀行」を設立し、金融業界のDXをリードしています。
「みんなの銀行」は、口座開設から振込、残高照会まで、すべてのサービスがスマートフォンアプリで完結するのが特徴です。
従来の銀行の常識を覆すUI/UXで、特にデジタルネイティブ世代の若者から高い支持を得ています。
また、BaaS(Banking as a Service)事業として、自社が開発した銀行システムを他の事業者にも提供。
金融機能をサービスとして外部に開放することで、新たな収益源を確立しており、地方銀行のDXモデルとして注目を集めています。
東京センチュリー株式会社:AI審査モデルの導入による業務効率化
リース・ファイナンス大手の東京センチュリーは、法人向けリースの与信審査にAIを導入し、業務効率化と審査精度の向上を実現しました。
過去の膨大な審査データと財務データをAIに学習させることで、独自のAI審査モデルを開発。
従来は担当者の経験と勘に頼る部分が大きかった審査プロセスを、データに基づいた客観的な評価へと転換しました。
これにより、審査にかかる時間が大幅に短縮され、より多くの案件を迅速に処理できるようになりました。
また、AIによる分析は、人間の目では見抜けなかった潜在的なリスクの発見にも繋がり、与信管理の高度化にも貢献しています。
【医療・医薬品業】のDX推進に取り組む企業の事例
ここでは、医療・医薬品業界におけるDX推進企業の事例を2つ紹介します。
- 中外製薬株式会社
- オリンパス株式会社
新薬開発の効率化や、医療現場の課題を解決するデジタルソリューションの提供など、人々の健康に直結する分野でのDXが進んでいます。
それでは、1社ずつ解説します。
中外製薬株式会社:AI創薬とデジタルバイオマーカーの開発
大手製薬会社の中外製薬は、AIを活用した創薬(AI創薬)と、デジタル技術で取得した生体データを治療に役立てる「デジタルバイオマーカー」の開発を積極的に進めています。
AI創薬では、AIを用いて膨大な数の化合物の中から新薬の候補となる物質を高速で探索。
これにより、従来は10年以上かかっていた新薬開発の期間を大幅に短縮し、コストを削減することを目指しています。
また、ウェアラブルデバイスなどから得られる日常の活動データを分析し、病気の進行度や治療効果を客観的に評価するデジタルバイオマーカーの開発にも注力。
個別化医療の実現に向けたDXの先進事例と言えます。
オリンパス株式会社:医療現場を支援するデジタルソリューション
内視鏡で世界トップシェアを誇るオリンパスは、医療機器メーカーから「科学的なソリューションカンパニー」への変革を目指し、DXを推進しています。
同社の最新の内視鏡システム「EVIS X1」には、AI技術が搭載されており、医師が病変を発見するのをリアルタイムで支援します。
AIが画像診断をサポートすることで、見逃しのリスクを低減し、診断精度の向上に貢献しています。
さらに、手術室内のさまざまな医療機器をネットワークで繋ぎ、情報を一元管理するシステム「EasySuite」も提供。
これにより、手術の準備や進行を効率化し、医療従事者の負担を軽減するなど、医療現場全体の課題解決に取り組んでいます。
【建設・不動産業】のDX推進に取り組む企業の事例
建設・不動産業界から、DXを推進する企業の事例を2つ紹介します。
- 清水建設株式会社
- SREホールディングス株式会社
人手不足が深刻なこの業界では、設計・施工プロセスの効率化や、データ活用による新たなサービス提供がDXの鍵となります。
それでは、1社ずつ見ていきましょう。
清水建設株式会社:BIMを活用した設計・施工プロセスの革新
大手ゼネコンの清水建設は、BIM(Building Information Modeling)を核としたDXを全社的に推進しています。
BIMは、建物の3次元モデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性データを追加したデータベースです。
設計段階からBIMを活用することで、建物の完成形を関係者全員で視覚的に共有でき、手戻りや意思疎通のミスを大幅に削減できます。
さらに、施工段階では、BIMモデルと連携した建設ロボットを導入し、作業の自動化も推進。
設計から施工、そして維持管理まで、建設プロセス全体の生産性を劇的に向上させており、建設DXのフロントランナーとなっています。
SREホールディングス株式会社:AIによる不動産価格の自動査定
ソニーグループから独立したSREホールディングスは、AIと不動産を掛け合わせた「不動産テック」企業としてDXを牽引しています。
同社が開発した「不動産価格査定AI」は、過去の成約事例や周辺環境、物件情報など、1億件を超える不動産関連データを学習。
これにより、高精度な不動産価格の自動査定を瞬時に行うことが可能です。
この技術は、自社の不動産仲介サービスで活用されるだけでなく、金融機関の担保評価業務などにもSaaSとして提供されています。
不動産業界の長年の課題であった「価格の不透明性」をデータとAIで解決する、画期的なDX事例です。
【農林水産業】のDX推進に取り組む企業の事例
農林水産業からは、マルハニチロ株式会社の事例を紹介します。
この業界では、担い手不足や高齢化が深刻な課題となっており、デジタル技術による生産性向上が期待されています。
マルハニチロ株式会社:スマート養殖による生産管理の高度化
水産最大手のマルハニチロは、ブリやマグロなどの養殖事業にIoTやAIを活用する「スマート養殖」に取り組んでいます。
養殖場の生け簀に水中ドローンやセンサーを設置し、水温、酸素濃度、魚の生育状況などをリアルタイムでデータ収集。
これらのデータをAIが分析し、最適な餌の量やタイミングを自動で判断して給餌を行います。
これにより、餌の無駄をなくしコストを削減するとともに、環境負荷の低減にも繋がっています。
勘と経験に頼りがちだった養殖業をデータドリブンな産業へと変革し、持続可能な水産業の実現を目指す先進的なDX事例です。
【エネルギー業】のDX推進に取り組む企業の事例
エネルギー業界からは、中国電力株式会社の事例を紹介します。
電力の安定供給を支える膨大なインフラ設備の保守・点検業務の効率化が、この業界のDXにおける重要なテーマです。
中国電力株式会社:ドローンやAIを活用した設備保全
中国電力は、送電線の点検といった設備保全業務にドローンやAIを導入し、安全性と効率性の向上を図っています。
従来は、作業員が鉄塔に登って目視で行っていた点検作業を、ドローンによる空撮に切り替えました。
これにより、高所作業のリスクをなくし、点検にかかる時間を大幅に短縮しました。
さらに、ドローンが撮影した膨大な画像データをAIが解析し、サビやひび割れなどの異常箇所を自動で検出するシステムも開発。
これにより、点検の精度を均一化し、見落としを防ぐことにも成功しています。
インフラ保全におけるDXの成功モデルとして、他の電力会社からも注目されています。
【IT・情報通信業】のDX推進に取り組む企業の事例
IT・情報通信業界から、DXを推進する企業の事例を2つ紹介します。
- 株式会社大塚商会
- ソフトバンク株式会社
自社のデジタル技術や知見を活かし、他社のDXを支援するサービスや、社会全体の課題解決に繋がる取り組みが特徴です。
それでは、1社ずつ見ていきましょう。
株式会社大塚商会:中小企業向けDX支援サービスの展開
オフィス用品通販で知られる大塚商会は、ITソリューションベンダーとして、特に中小企業のDX支援に力を入れています。
同社の強みは、IT機器の販売からシステム構築、運用サポートまでをワンストップで提供できることです。
IT人材が不足しがちな中小企業に対して、それぞれの業種や課題に合わせた最適なITツールやサービスを提案し、導入から定着までを伴走支援しています。
「たのめーる」で築いた顧客基盤と、長年のIT導入支援で培ったノウハウを掛け合わせ、中小企業のDXパートナーとしての地位を確立。
自社の強みを活かして新たな市場を開拓したDX事例と言えます。
ソフトバンク株式会社:5GとIoTを活用した社会課題解決
通信キャリアのソフトバンクは、自社が持つ最先端の通信技術である5GやIoTを活用し、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。
例えば、交通分野では、車両や信号機から得られるデータをリアルタイムで解析し、渋滞緩和や自動運転の実現を目指す実証実験を行っています。
農業分野では、農地に設置したセンサーから得られる情報を基に、水やりや肥料の量を最適化するスマート農業を支援しています。
このように、自社のコア技術を社会インフラと掛け合わせることで、新たな価値を創造。
一企業のDXに留まらず、社会全体のデジタルトランスフォーメーションを牽引する存在となっています。
【運輸・物流業】のDX推進に取り組む企業の事例
運輸・物流業界から、DX推進に取り組む企業の事例を2つ紹介します。
- ヤマトホールディングス株式会社
- アジア航測株式会社
EC市場の拡大による荷物量の増加や、ドライバー不足といった課題に対応するため、データ活用による輸配送ネットワークの最適化が急務となっています。
ヤマトホールディングス株式会社:データドリブンな輸配送ネットワークの構築
宅配便最大手のヤマトホールディングスは、「データドリブン経営」を掲げ、輸配送ネットワーク全体の変革を進めています。
2021年には、全国の輸配送データを一元的に集約・可視化し、AIによる分析を行うための巨大な物流ターミナル「羽田クロノゲート」を稼働。
ここで、荷物の量や交通状況などのデータをリアルタイムで分析し、最も効率的な配送ルートや人員配置を算出しています。
また、個人向けには、受け取り日時や場所をLINEなどで手軽に変更できるサービス「EAZY」を提供。
顧客の利便性を向上させると同時に、再配達の削減にも成功しており、顧客起点と業務効率化を両立したDX事例です。
アジア航測株式会社:航空測量データとAIを組み合わせたインフラ維持管理
航空測量大手の アジア航測は、航空機から撮影した高精細な画像データとAIを組み合わせ、社会インフラの維持管理を効率化するサービスを提供しています。
例えば、道路の路面を撮影した画像をAIが解析し、ひび割れの箇所や深刻度を自動で判定。
従来は人手で行っていた点検作業を大幅に効率化し、自治体などのインフラ管理者の負担を軽減しています。
また、土砂災害の危険がある斜面の変化を時系列データで監視するなど、防災・減災分野にも技術を応用。
自社が持つ独自のデータとデジタル技術を掛け合わせることで、新たなソリューションを生み出しているDXの好事例です。
【自治体・教育機関】のDX推進に取り組む企業の事例
ここでは、企業だけでなく、自治体や教育機関におけるDXの事例を3つ紹介します。
- 大阪府堺市
- 富山県
- 岡山大学
行政手続きの効率化による住民サービスの向上や、次代を担うデジタル人材の育成が、公共分野におけるDXの重要なテーマです。
大阪府堺市:AI-OCR導入による行政手続きの効率化
大阪府堺市では、手書きの申請書などを読み取り、テキストデータ化する「AI-OCR」を導入し、行政手続きの効率化を実現しました。
従来、市民から提出される紙の申請書は、職員が手作業でシステムに入力しており、膨大な時間と労力がかかっていました。
AI-OCRの導入により、この入力作業が自動化され、職員は内容の確認など、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
これにより、業務時間が大幅に削減されただけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも防止。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)と組み合わせることで、さらなる業務自動化を進めており、自治体DXのモデルケースとなっています。
富山県:電子申請システムの導入と県民の利便性向上
富山県では、県民が行うさまざまな行政手続きをオンラインで完結できる電子申請システムを導入し、県民サービスの向上に取り組んでいます。
これまで窓口や郵送でしか行えなかった許認可の申請や届け出などを、24時間365日、どこからでもスマートフォンやパソコンで行えるようにしました。
これにより、県民は県庁に出向く必要がなくなり、利便性が大幅に向上しました。
また、申請データの管理もデジタル化されたことで、行政内部の事務処理も効率化。
県民と行政、双方にとってメリットのあるDXを実現しており、デジタルデバイド対策として高齢者向けのスマホ教室なども併せて実施しています。
岡山大学:データサイエンス教育の全学展開
国立大学である岡山大学は、文系・理系を問わず、全学部の学生がデータサイエンスの基礎を必修で学ぶ教育プログラムを導入しています。
現代社会では、あらゆる分野でデータを読み解き、活用する能力が不可欠になっているとの考えから、AIや統計学の基礎、プログラミングなどを学ぶ機会を全学生に提供。
専門分野の知識とデータサイエンスのスキルを併せ持つ、社会のDXを推進できる人材の育成を目指しています。
特定の学部だけでなく、全学的にデジタル教育を推進するこの取り組みは、日本の高等教育におけるDXの先進事例として、他の大学からも注目を集めています。
【海外】における先進的なDX企業の事例
ここでは、海外に目を向け、先進的なDXを推進する企業の事例を3つ紹介します。
- IKEA
- Netflix
- Tesla
日本企業が学ぶべき、顧客体験の変革や、製品とサービスを融合させた新たなビジネスモデルのヒントがここにあります。
IKEA:AR技術を活用した家具の試し置きアプリ
スウェーデン発の家具大手IKEAは、AR(拡張現実)技術を活用したスマートフォンアプリ「IKEA Place」を提供しています。
このアプリを使うと、スマートフォンのカメラを通して、自分の部屋にIKEAの家具を実物大で配置してみることができます。
色やサイズが部屋に合うかどうかを、購入前にリアルにシミュレーションできるため、「買ってみたけどイメージと違った」という失敗を防ぐことができます。
オンラインでの購買体験に「試す」という価値を加え、顧客の不安を解消することで、ECサイトのコンバージョン率向上に繋げています。
デジタル技術を用いて顧客の課題を解決する、顧客中心DXの優れた事例です。
Netflix:独自のアルゴリズムによるパーソナライズとコンテンツ制作
動画配信サービスの巨人であるNetflixは、DXの代名詞とも言える企業です。
同社の強みは、徹底したデータ活用にあります。
全ユーザーの視聴履歴、検索ワード、再生を止めた箇所などの膨大なデータを収集・分析。
独自のアルゴリズムを用いて、ユーザー一人ひとりの好みに合わせたおすすめ作品をトップページに表示します。
さらに、このデータはオリジナルコンテンツの制作にも活かされています。
どんな俳優や監督、ストーリーがヒットしやすいかをデータに基づいて判断することで、「ハウス・オブ・カード」のような世界的大ヒット作を生み出してきました。
データ活用がビジネスの根幹を成す、究極のDX企業と言えるでしょう。
Tesla:OTAによるソフトウェアアップデートと自動運転技術
電気自動車(EV)メーカーのTeslaは、自動車業界に破壊的な変革をもたらしたDX企業です。
同社の最大の特徴は、「OTA(Over-the-Air)」によるソフトウェアアップデートです。
インターネット経由で車両のソフトウェアを更新することで、購入後も自動運転機能の向上や、新しいエンターテイメント機能の追加など、車の性能が継続的に進化し続けます。
これにより、Teslaの車は「買って終わり」の製品ではなく、「常に最新の状態にアップデートされるサービス」という新たな価値を提供しています。
ハードウェア(車体)とソフトウェアを高度に融合させ、ビジネスモデルそのものを変革した革新的な事例です。
DXを成功に導いた企業の事例から学ぶ共通のポイント
これまで見てきた多くの成功事例には、いくつかの共通するポイントがあります。
ここでは、DXを成功に導くための重要な要素を4つ解説します。
- 明確なビジョンと経営トップのコミットメント
- アジャイルな開発体制でスモールスタートする
- 全社的なデジタル人材の確保・育成と組織文化の醸成
- 顧客中心のアプローチとデータ活用の徹底
これらのポイントを押さえることが、自社のDXを推進する上での道しるべとなります。
明確なビジョンと経営トップのコミットメント
DXの成功には、経営トップが明確なビジョンを示すことが不可欠です。
「デジタル技術を使って、自社をどのような姿に変えたいのか」「それによって顧客や社会にどのような価値を提供するのか」という大きな方向性をトップが示し、全社に共有する必要があります。
また、DXは既存の業務プロセスや組織構造の変革を伴うため、現場からの抵抗が起こることも少なくありません。
そうした際に、経営トップが強いリーダーシップを発揮し、変革を断行する覚悟(コミットメント)を示すことが極めて重要になります。
アジャイルな開発体制でスモールスタートする
DXの取り組みは、最初から大規模で完璧な計画を立てて進めようとすると、失敗しがちです。
ビジネス環境の変化は速く、長期間にわたる計画は陳腐化してしまうリスクがあります。
成功している企業の多くは、まず小規模なプロジェクトから始め(スモールスタート)、試行錯誤を繰り返しながら改善していく「アジャイル」なアプローチを採用しています。
小さく始めて素早く検証し、学びを得ながら徐々に取り組みを拡大していくことが、不確実性の高いDXプロジェクトを成功に導く鍵となります。
全社的なデジタル人材の確保・育成と組織文化の醸成
DXを推進するのは、最新のテクノロジーではなく「人」です。
DXを担うデジタル人材を、外部から確保するだけでなく、社内で育成していく視点が重要になります。
全社員を対象としたリスキリング(学び直し)の機会を提供し、組織全体のデジタルリテラシーを底上げすることが求められます。
また、失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる文化や、部門の壁を越えて協力し合う文化を醸成することも不可欠です。
DXは、技術の導入だけでなく、組織文化の変革でもあるのです。
顧客中心のアプローチとデータ活用の徹底
成功しているDXは、常に「顧客」が中心にあります。
「このデジタル技術を導入すれば、顧客のどのような課題を解決できるのか」「顧客体験をどのように向上させられるのか」という視点が、すべての取り組みの出発点となります。
そして、顧客を深く理解するために不可欠なのが、データの活用です。
顧客の行動データやフィードバックを収集・分析し、そこから得られたインサイト(洞察)に基づいてサービスや製品を改善していくサイクルを回すことが、DX時代の競争優位性を築く上で最も重要です。
DX推進に失敗した企業の事例から学ぶ教訓
成功事例から学ぶと同時に、失敗事例から教訓を得ることも非常に重要です。
ここでは、DX推進がうまくいかない企業によく見られる失敗パターンを3つ紹介します。
- 目的と手段の混同(ITツール導入が目的化)
- 既存事業部門との連携不足と抵抗
- 短期的な成果を求めすぎる計画
これらの罠に陥らないよう、自社の状況と照らし合わせながら確認してください。
目的と手段の混同(ITツール導入が目的化)
DX推進における最も典型的な失敗例が、「ITツールの導入」そのものが目的になってしまうケースです。
「AIを導入せよ」「クラウド化を進めよ」といった号令のもと、最新ツールを導入したものの、それをどうビジネス価値に繋げるかという戦略が欠けているため、結局使いこなせずに終わってしまいます。
重要なのは、まず「自社のビジネス課題は何か」「その課題を解決するために、どのようなデジタル技術が有効か」という順番で考えることです。
あくまでもビジネス課題の解決が目的であり、ITツールはそれを実現するための手段に過ぎません。
既存事業部門との連携不足と抵抗
DXを推進するために、社長直下に専門の「DX推進室」のような部署を設置する企業は多いです。
しかし、この専門部署が孤立し、既存の事業部門との連携がうまくいかないケースが少なくありません。
既存事業部門からすれば、DX推進室は「現場の仕事も知らないのに、理想論ばかり押し付けてくる」存在に見えてしまいます。
結果として、現場の協力が得られず、変革への抵抗勢力が生まれてしまいます。
DXは全社的な取り組みです。企画段階から現場を巻き込み、一体となって進める体制を構築することが不可欠です。
短期的な成果を求めすぎる計画
DXは、企業の文化やビジネスモデルを変革する、長期的で継続的な取り組みです。
しかし、経営陣がDXを単なるコスト削減策と捉え、短期的なROI(投資対効果)を求めすぎると、プロジェクトは頓挫しがちです。
多くの場合、DXの成果が目に見える形で現れるまでには、ある程度の時間がかかります。
目先の成果を焦るあまり、本来取り組むべきだった本質的な変革を諦め、小手先の業務改善に終始してしまうのは、非常にもったいないことです。
長期的な視点を持ち、腰を据えて取り組む覚悟が経営層には求められます。
あなたの会社のDXは大丈夫?成功企業と失敗企業を分ける「たった一つ」の視点
多くの企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を掲げる今、その取り組みが本当にビジネスの変革に繋がっていますか?実は、経済産業省のレポートが示す通り、多くの企業が単なるITツールの導入、つまり「デジタイゼーション」の段階で足踏みしているのが現実です。最新ツールを導入したにもかかわらず、なぜ成果が出ないのか。それは、成功する企業と失敗する企業とで、DXの「目的」が根本的に異なるからです。この記事では、あなたの会社のDXが「ITツール導入ごっこ」で終わらないための、本質的な視点を解説します。
なぜ多くのDXは「失敗」に終わるのか?
DXが失敗する企業には、共通する落とし穴があります。それは、「手段の目的化」です。
- 課題:AIやクラウドといった最新技術を導入すること自体がゴールになってしまう。
- 結果:現場の課題と技術が結びつかず、誰にも使われない「無用の長物」と化す。
このような状態では、高額な投資をしたにもかかわらず、業務効率は上がらず、むしろ現場の混乱を招くだけです。これは、DXを「技術導入プロジェクト」としか捉えられていないことに起因します。
引用元:
経済産業省「DXレポート2 中間とりまとめ(概要)」では、DX推進の課題として、多くの企業が既存業務の効率化(デジタイゼーション)に留まっており、ビジネスモデルの変革に至っていない現状が指摘されています。(経済産業省, 2021年)
成功企業が持つ「顧客価値」という視点
一方、DXを成功させている企業は、技術を「顧客に新しい価値を届けるための手段」と明確に位置付けています。彼らにとってのDXの主語は「技術」ではなく、常に「顧客」です。
- 思考の出発点:「この技術を使えば、顧客のどんな不満を解消できるか?」「どうすれば、もっと良い顧客体験を提供できるか?」
例えば、Netflixが視聴データをもとにユーザー一人ひとりに合わせた作品を推薦するのは、顧客に「自分だけの映画館」という価値を提供するためです。テスラがOTAで車の機能をアップデートし続けるのは、顧客に「購入後も進化し続ける車」という価値を提供するためです。
彼らは、まず顧客に提供したい価値を定義し、それを実現するために最適なデジタル技術を選択・活用しています。この「顧客価値起点」の発想こそが、DXを単なる業務改善で終わらせず、ビジネスモデルそのものを変革する原動力となるのです。あなたの会社のDXは、一体誰のために行われていますか?その問いに明確に答えることが、成功への第一歩です。
まとめ
多くの企業が労働力不足や競争激化といった課題に直面し、DXの推進が急務となっています。
しかし、実際には「何から手をつければ良いかわからない」「社内にデジタル人材がいない」といった理由で、DXの第一歩を踏み出せずにいる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな定型業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用し、業務を自動化できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、まずは身近な業務からDXを始めることが可能です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の業務効率化”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。