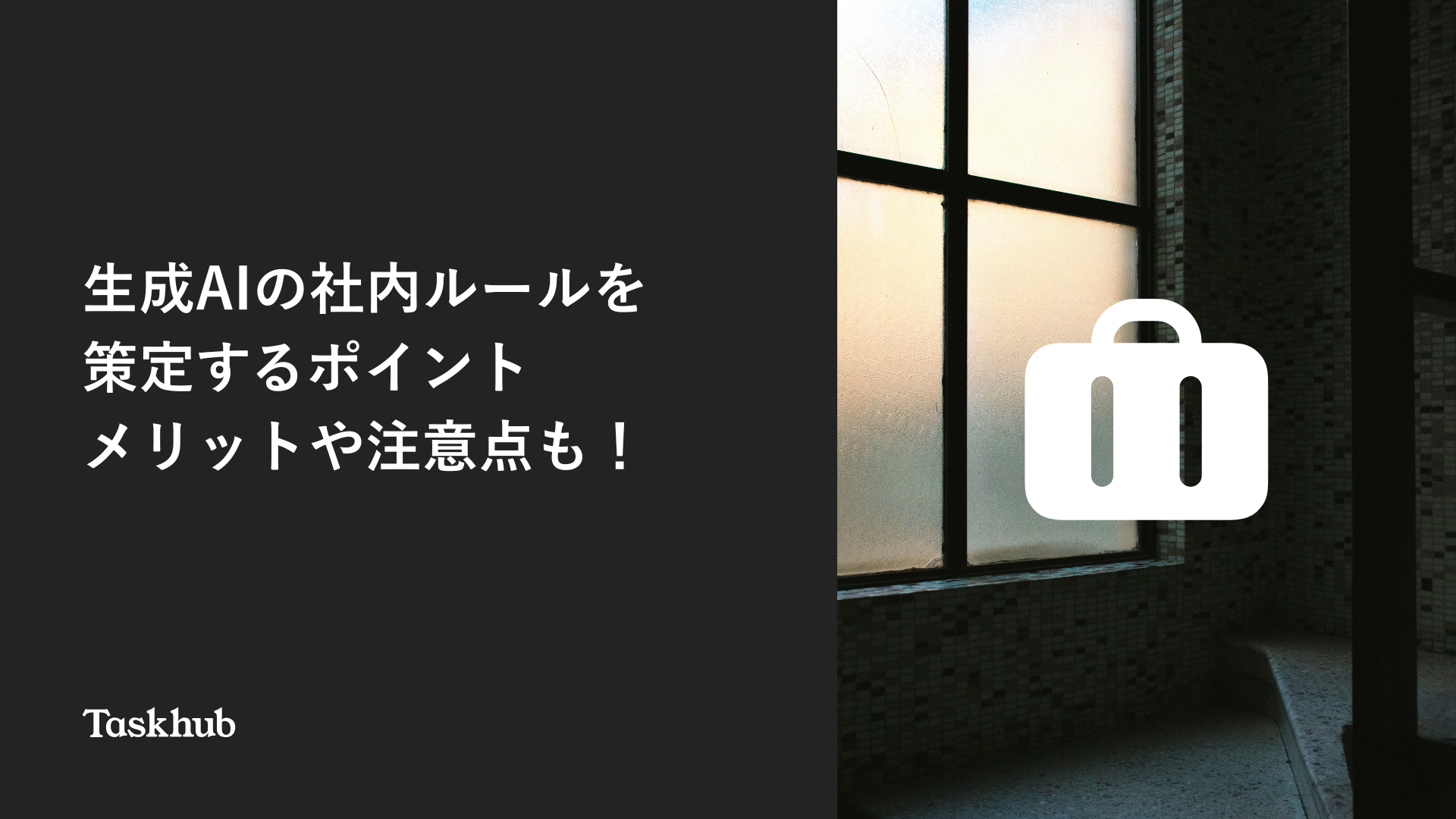「生成AIを業務で使いたいけど、どんなルールを作ればいいのかわからない」
「社内でのAI利用を推奨したいが、セキュリティや著作権が心配」
こういった悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
生成AIの活用は、業務効率化や新しいアイデア創出に大きく貢献する一方、情報漏洩や著作権侵害といったリスクも伴います。しかし、適切なルールを策定し、社員に周知することで、これらのリスクを最小限に抑えつつ、AIのメリットを最大限に享受することが可能です。
本記事では、生成AIを安全に、そして効果的に活用するための社内ルール策定について、その重要性から具体的な策定ステップ、注意点までを徹底的に解説します。
そもそも生成AIとは|社内ルールが必要な背景
ここからは、そもそも生成AIとは何か、そしてなぜ社内ルールが必要とされるのかについて解説します。
生成AIとは
生成AIとは、テキストや画像、音声、動画などの新しいコンテンツを自律的に生成するAI技術の総称です。具体的には、与えられたプロンプト(指示)に基づいて、人間が書いたような自然な文章や、オリジナリティのある画像を瞬時に作り出すことができます。この技術は、OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」に代表される大規模言語モデル(LLM)の進化によって、急速に普及しました。
生成AIの最大の特徴は、ゼロから新しいものを「創造」する点にあります。これまでのAIが特定のタスク(画像認識やデータ分析など)を効率化するものであったのに対し、生成AIは人間の創造的な活動をサポートし、場合によっては代替する可能性を秘めています。例えば、企画書の骨子作成、メール文面の自動生成、マーケティング用画像の作成など、多岐にわたる業務で活用され始めています。この汎用性の高さが、多くの企業が導入を検討する理由です。
ChatGPTの企業での導入方法や具体的な活用事例については、こちらの完全ガイドで詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-company-use/
生成AIに社内ルールが求められる理由
生成AIが急速に普及する一方で、その利用にはいくつかのリスクが伴います。そのため、企業は社員が安全かつ適切にAIを活用できるよう、社内ルールの策定が不可欠です。
第一に、セキュリティリスクへの対応です。機密情報や個人情報を含むデータを生成AIに入力した場合、そのデータが外部に流出し、不正利用される可能性があります。多くの生成AIは、入力されたデータをモデルの学習に利用することがあり、意図せず重要な情報が公開されてしまうリスクもゼロではありません。
第二に、著作権や知的財産権の問題です。生成AIが作成したコンテンツが、既存の著作物と類似していたり、権利侵害にあたる可能性も指摘されています。企業が生成AIを利用する際には、これらのリスクを把握し、適切な対策を講じなければ、法的なトラブルに発展する可能性も考えられます。
これらのリスクを未然に防ぎ、社員が安心して生成AIを利用できる環境を整えるためには、明確なガイドラインが不可欠です。
生成AIの社内ルールを作成する3つのメリット
ここからは、生成AIの社内ルールを策定することで得られる具体的なメリットについて解説します。ルールは単なる制約ではなく、組織全体の利益に繋がります。
法令違反やセキュリティリスクの回避
生成AIの利用には、個人情報保護法や著作権法など、さまざまな法令が関わってきます。ルールを策定することで、意図しない法令違反を未然に防ぐことが可能です。特に、顧客情報や社内の機密情報を扱う業務においては、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための明確なガイドラインが求められます。
例えば、個人情報を含むデータは生成AIに入力しないこと、外部のサービスを利用する際は、その利用規約やセキュリティポリシーを事前に確認することをルールとして定めることで、万が一の事態を防ぐことができます。また、情報システム部門が利用ツールを一元管理し、承認されたサービスのみ利用可能とすることで、シャドーIT(情報システム部門の管理外で利用されるITサービス)を抑制し、セキュリティを強化することも重要です。
社員のAIリテラシー向上と生産性向上
生成AIの社内ルールを策定するプロセスは、社員のAIリテラシーを向上させる絶好の機会です。ルールを周知する過程で、生成AIの仕組みやリスク、適切な利用方法について学ぶことで、社員一人ひとりの知識が深まります。これにより、単にツールを使うだけでなく、その特性を理解した上でより効果的に活用できるようになります。
例えば、効果的なプロンプトの書き方や、生成された情報のファクトチェックの重要性などをルールに盛り込むことで、社員はAIをより賢く使いこなす術を身につけられます。その結果、業務の効率が上がり、生産性の向上に繋がります。また、AIに関する知識は、現代ビジネスにおいて必須のスキルとなりつつあるため、社員のキャリアアップにも貢献します。
社員の積極的な生成AI利用を促進
「ルールが厳しすぎて、誰も使わなくなるのでは?」と心配する声もあるかもしれませんが、実はその逆です。明確なルールがない状態では、社員は「何をしていいかわからない」「もしトラブルになったらどうしよう」と不安を感じ、AI利用をためらってしまいます。
しかし、リスクと利用範囲を明確にしたルールが存在することで、社員は安心して生成AIを業務に取り入れることができます。ルールが「やってはいけないこと」だけでなく、「推奨される使い方」も示していれば、社員は自信を持ってAIを活用できるようになります。これにより、部署やチームを横断したAI活用が活発化し、イノベーションの促進にも繋がります。
生成AIの社内ルールに記載すべき5つのポイント
ここからは、具体的な社内ルールに盛り込むべき5つのポイントを解説します。これらのポイントを押さえることで、実効性のあるガイドラインを作成できます。
禁止事項と利用範囲
生成AIを導入する上で最も重要なのが、禁止事項と利用範囲の明確化です。まず、絶対にAIに入力してはいけないデータを具体的にリストアップします。これには、顧客の個人情報、会社の機密情報、未公開の事業計画、他社の知的財産などが含まれます。特に、個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号など)や、パスワード、認証情報などは厳禁とする必要があります。
次に、利用範囲を定めます。例えば、「業務効率化を目的としたテキスト生成や要約に限定する」「最終的な成果物の作成には利用しない」「社内向けの文章作成のみに利用する」といった具体的な制限を設けることで、社員は迷わずにAIを利用できます。また、利用を許可するツールを限定し、そのツール以外は利用禁止とする「ホワイトリスト方式」も有効です。これにより、セキュリティリスクの高いツールの利用を防ぐことができます。
知的財産権と著作権への対応
生成AIが作成したコンテンツの著作権や知的財産権は、複雑な問題を抱えています。そのため、社内ルールでは、生成物の著作権が誰に帰属するのか、そしてどのように取り扱うべきかを明確にする必要があります。
一般的な見解として、AIが生成したコンテンツそのものには著作権は発生しないとされています。しかし、人間がプロンプトを工夫し、生成物を編集・加工することで、著作権が発生する可能性もあります。ルールには、AIが生成したコンテンツをそのまま公開・利用せず、必ず人間が確認・編集することを義務付けるべきです。また、生成物が既存の著作物と類似していないか、著作権侵害の疑いがないかをチェックする体制を構築することも重要です。他社のロゴや商標、著作物を学習データとして利用する可能性があるため、特に商用利用においては細心の注意を払う必要があります。
こちらは生成AIが抱えるバイアス、データ漏洩、知的財産権などのリスクと、その軽減策について包括的に解説したレポートです。合わせてご覧ください。
https://research.aimultiple.com/risks-of-generative-ai/
データ入力時の注意点
生成AIの社内ルールでは、入力データに関する具体的な注意点を詳細に記載することが不可欠です。まず、個人情報や機密情報、未公開の事業計画など、外部に漏洩してはならない情報を絶対に入力しないことを徹底させます。これは、生成AIの多くが入力されたデータを学習に利用する可能性があり、意図しない情報漏洩に繋がるためです。
次に、入力データの匿名化や非個人情報化(マスキング)を義務付けることが効果的です。例えば、顧客情報を取り扱う際は、氏名や住所を伏せ字にする、個人が特定できないように加工するといった手順を定めます。また、入力する情報の最小化も重要です。質問に必要な情報のみを簡潔に入力するように促し、余計な情報を入力しない習慣をつけさせることで、リスクを低減できます。さらに、利用する生成AIのプライバシーポリシーや利用規約を事前に確認し、入力データがどのように扱われるかを理解しておくこともルールに盛り込むべきです。
生成物の利用時の注意点
生成AIによって出力されたコンテンツは、あくまで参考情報として扱うべきであり、そのまま利用することには多くのリスクが伴います。そのため、生成物の利用に関するルールを明確に定める必要があります。
まず、生成された情報のファクトチェックを義務付けることです。AIは、誤った情報や古い情報を生成する「ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつく現象)」を起こすことがあります。そのため、重要な意思決定や公開情報に利用する際は、必ず複数の信頼できる情報源と照らし合わせて内容が正しいか確認する手順をルール化します。また、著作権や知的財産権を侵害していないかの確認も必須です。例えば、生成された画像や文章が、既存の著作物と酷似していないかを目視でチェックする体制を構築します。さらに、生成物を最終的な成果物として利用する際には、必ず人間の手で修正・加筆し、その責任の所在を明確にすることもルールとして盛り込むべきです。
トラブル発生時の対応と報告体制
万が一、生成AIの利用によってトラブルが発生した場合に備え、迅速かつ適切に対応するためのルールを定めておくことが重要です。トラブルの種類としては、情報漏洩、著作権侵害、誤情報の拡散などが考えられます。
まず、トラブルが発生した際の報告先と報告ルートを明確にします。例えば、「直属の上司と情報システム部門に即座に報告すること」といった具体的な手順を定めます。これにより、社員は迷うことなく、迅速に事態を共有できます。次に、報告すべき内容を定めます。いつ、誰が、どのようなツールで、どのようなデータを入力したのか、そしてどのようなトラブルが発生したのかを詳細に記録するフォーマットを用意しておくことで、スムーズな情報共有が可能です。また、トラブル発生後の対応についても、あらかじめルールを定めておくべきです。例えば、「該当する生成AIの利用を一時停止する」「関連するログを保全する」といった具体的なアクションを明記しておくことで、被害の拡大を防ぐことができます。
生成AIの社内ルールを作る3つのステップ
ここからは、実際に社内ルールを策定するための3つのステップを解説します。これらのステップに沿って進めることで、実効性のあるルールを効率的に作成できます。
ステップ1:既存のガイドラインを参考にする
まずは、すでに公開されている他の組織のガイドラインを参考にすることから始めます。政府機関や業界団体、先進的な企業のガイドラインは、生成AIに関する一般的なリスクや対応策を網羅しており、自社のルールを策定する上で非常に有用です。例えば、日本ディープラーニング協会(JDLA)や東京都デジタルサービス局などが公開しているガイドラインは、基本的な考え方や注意点が体系的にまとめられており、参考になります。
これらのガイドラインを参考にすることで、自社が考慮すべきリスクや、盛り込むべき項目を網羅的に把握することができます。ただし、他社のガイドラインをそのまま流用するのではなく、あくまで自社の状況に合わせたカスタマイズが必要です。
こちらは日本の科学技術振興機構(JST)が発行した、AI研究の最新動向とリスクへの対処法をまとめた調査報告書です。合わせてご覧ください。
https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-07.html
ステップ2:自社の業務とポリシーを整理する
次に、自社の業務内容と既存のセキュリティポリシー、コンプライアンスポリシーを整理します。生成AIの利用が想定される部署や業務内容を洗い出し、それぞれの業務でどのようなリスクが考えられるかを分析します。例えば、マーケティング部門では外部への公開情報に関わる著作権リスク、開発部門ではソースコードの機密性に関するリスクが考えられます。
また、すでに存在する情報セキュリティポリシーや個人情報保護に関する規程との整合性を確認することも重要です。既存のルールと矛盾しないように、生成AIに関する特有の事項を追記する形でルールを策定することで、組織全体のポリシーに一貫性を持たせることができます。
ステップ3:自社独自の生成AIルールを策定する
最後に、ステップ1とステップ2で得た情報を基に、自社独自の生成AIルールを策定します。ルールは、社員が理解しやすく、実行しやすいものであることが重要です。専門用語を避け、具体的な事例を交えながら、誰が読んでも内容が理解できるように工夫します。
また、ルールは一度策定したら終わりではありません。生成AIの技術は日々進化しており、新たなリスクや活用方法が次々と生まれています。そのため、定期的にルールを見直し、最新の状況に合わせてアップデートしていく必要があります。社内での利用状況をモニタリングし、社員からのフィードバックを収集する体制を構築することも重要です。
参考になる生成AIの社内ルール・ガイドライン4選
ここからは、実際に公開されている生成AIの社内ルールやガイドラインを4つ紹介します。自社で策定する際の参考にしてください。
日本ディープラーニング協会(JDLA)
日本ディープラーニング協会(JDLA)は、生成AIの倫理的利用に関するガイドラインを公開しています。このガイドラインは、AI技術の専門家や法律家によって作成されており、技術的な観点と法的な観点の両方から、AI利用の原則やリスク、注意点が詳細に解説されています。特に、著作権やプライバシー、セキュリティに関する項目は非常に参考になります。
このガイドラインは、AI技術の健全な発展と社会への浸透を目指しており、企業がAIを活用する上での羅針盤となります。ただし、専門的な内容も含まれているため、自社のビジネスに落とし込む際には、内容をかみ砕いて分かりやすくする必要があります。
東京都デジタルサービス局
東京都は、行政機関が生成AIを安全に利用するためのガイドラインを公開しています。このガイドラインは、情報漏洩や著作権侵害といったリスクを回避するための具体的なルールや、適切なプロンプトの作成方法などが分かりやすくまとめられています。行政機関が利用することを想定しているため、特にセキュリティやコンプライアンスに関する項目が厳格に定められており、民間企業にとっても非常に参考になります。
また、このガイドラインは、行政サービスの効率化を目指しており、業務でのAI活用を積極的に推奨する姿勢も示しています。民間企業がAIの利用を促進しつつも、リスクを管理するバランスの取れたルールを策定する上で、良いモデルとなります。
サイダス(CYDAS)
株式会社サイダスは、従業員情報など機密性の高い情報を扱う企業として、生成AIの利用に関するガイドラインを策定・公開しています。このガイドラインは、「使わないリスク」を認識し、適切なルールのもとで積極的に利用を推奨する姿勢が特徴です。特に、機密情報を取り扱う業務での具体的な利用方法や、AIが生成したコンテンツの取り扱いについて、詳細なルールが定められています。
このガイドラインは、従業員のAI利用を積極的に促進しつつも、セキュリティリスクを最小限に抑えるための具体的な方法が示されており、特に個人情報や機密情報を扱う企業にとって参考になるでしょう。
上智大学
上智大学は、学生と教職員が生成AIを学習や研究に利用する際のガイドラインを策定しています。このガイドラインは、「AIの特性を理解する」「安易な利用をしない」「情報の真偽を確認する」といった基本的な原則から始まり、学術分野における生成AIの適切な利用方法について詳細に解説されています。
このガイドラインは、教育機関という性質上、特に倫理的な利用や情報源の確認に重点が置かれています。企業においても、社員のAIリテラシー教育や、AIが生成した情報のファクトチェックを義務付ける際の参考になるでしょう。
生成AIの社内ルールを策定する際の注意点
ここからは、社内ルールを策定する際に特に注意すべき点を解説します。これらの点を考慮することで、より実効性のあるルールを作成できます。
正確性を過信しない
生成AIの最大のリスクの一つは、その出力内容の「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」です。AIは、あたかも正しいかのように誤った情報を生成することがあります。特に、複雑な質問や専門性の高い内容、最新の出来事に関する質問では、この傾向が顕著に現れます。
そのため、社内ルールには「AIが生成した情報は、あくまで参考情報として扱うこと」を明確に記載する必要があります。重要な意思決定や顧客への提供情報、公開資料に利用する際は、必ず人間がその内容を検証し、複数の信頼できる情報源と照らし合わせることを義務付けます。AIの出力はあくまで「たたき台」であり、最終的な責任は人間が負うという認識を全社員で共有することが不可欠です。
ChatGPTのハルシネーションを防ぐ具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/
商用利用の可否
生成AIサービスには、個人利用は許可されていても、商用利用が禁止されている、または追加のライセンスが必要な場合があります。社内ルールを策定する際には、利用を許可するサービスの商用利用に関する利用規約を事前に確認し、ルールに明記する必要があります。
例えば、無料版のサービスの中には、生成物を商用目的で利用できないものや、入力したデータが学習に利用されてしまうものがあります。これらのリスクを社員に周知し、業務での利用を制限することで、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。
入力データの機械学習への利用の有無
多くの生成AIサービスは、ユーザーが入力したデータを自社のAIモデルの学習に利用しています。これにより、AIの精度は向上しますが、機密情報や個人情報が意図せず学習データとして利用され、第三者に公開されるリスクが生じます。
社内ルールには、利用を許可するサービスが入力データをどのように扱うか、その利用規約を必ず確認することを義務付けます。特に、機密情報を扱う場合は、入力データが学習に利用されない設定(オプトアウト機能)があるサービスを選定し、その設定を徹底させる必要があります。また、入力データが暗号化されるか、通信が安全かといった点も考慮すべき重要な要素です。
利用規約の確認
生成AIサービスを利用する際は、その利用規約を必ず確認する必要があります。利用規約には、著作権の帰属、データプライバシー、商用利用の可否、免責事項などが詳細に記載されています。
社内ルールでは、「利用する前に必ず利用規約を確認し、内容を理解すること」を義務付けます。特に、無料で利用できるサービスの中には、予期せぬリスクをはらんでいる場合があるため、注意が必要です。情報システム部門が、利用を許可するサービスの利用規約を一元的に管理し、社員に周知する体制を構築することも有効です。
生成AI導入を成功させるための4つのポイント
生成AIを単に導入するだけでなく、組織全体でそのメリットを最大限に引き出すためには、ルールの策定と併せていくつかのポイントを押さえる必要があります。
業務内容の棚卸しと活用方針の検討
生成AIを導入する前に、まずどの業務でAIが有効に活用できるかを検討します。例えば、議事録作成、メール文面の自動作成、データ分析の初期段階など、定型的な業務や繰り返し作業が多い業務は、AIによる効率化の恩恵を大きく受けやすいです。
業務の棚卸しを行い、AIを活用する目的(業務効率化、新サービスの創出、コスト削減など)を明確にすることで、導入後の効果を最大化できます。また、活用方針を定めることで、社員はAIをどのように使うべきかを理解しやすくなります。
投資対効果の高い活用方法の選定
生成AIの活用には、無料ツールから有料のエンタープライズ向けサービスまで、さまざまな選択肢があります。導入コストと得られる効果を比較し、最も投資対効果の高い活用方法を選定することが重要です。
例えば、小規模なチームでの利用であれば、無料ツールや安価な有料プランから試してみるのが良いでしょう。一方で、全社的な導入を検討している場合は、セキュリティやサポート体制が充実したエンタープライズ向けプランを選ぶことで、長期的なリスクを回避できます。まずは小規模なパイロットプロジェクトで効果を検証し、その結果を踏まえて本格的な導入を検討することも有効です。
リスク管理体制の構築
生成AIの利用には、情報漏洩や著作権侵害といったリスクが伴います。これらのリスクに備え、事前にリスク管理体制を構築しておくことが不可欠です。
例えば、生成AIの利用に関する責任者を明確にし、問題が発生した場合の報告・対応体制を整備します。また、定期的なセキュリティチェックや、社員への啓発活動を行うことで、リスクを未然に防ぎます。万が一、トラブルが発生した場合に備え、インシデント対応計画を策定しておくことも重要です。
研修による社員のリテラシー向上
生成AIを組織全体で活用するためには、社員一人ひとりのAIリテラシーを高めることが不可欠です。ルールの周知だけでなく、AIの仕組みや適切な利用方法、リスクに関する研修を定期的に実施します。
研修では、単なる知識の伝達に留まらず、具体的なワークショップなどを通じて、実際にAIを使ってみる機会を提供することも効果的です。社員がAIを身近なツールとして捉え、積極的に活用できるような環境を整えることが、生成AI導入成功の鍵となります。
生成AIの社内ルール策定は専門家への相談もおすすめ
生成AIの社内ルール策定は、法務やセキュリティに関する専門知識が求められる複雑なプロセスです。自社内だけで完璧なルールを作成するのが難しいと感じた場合は、生成AIに詳しい専門家やコンサルティング会社に相談することも有効な手段です。
専門家は、最新の技術動向や法的リスクを熟知しており、自社のビジネスモデルや業務内容に合わせた、最適なルールの策定をサポートしてくれます。これにより、リスクを最小限に抑えつつ、AIのメリットを最大限に引き出すことができるでしょう。
もし、どこから手を付ければいいかわからない、専門家のアドバイスがほしいとお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。
なぜChatGPTを使うと「思考停止」するのか?
便利なツールとして多くの人に使われているChatGPTですが、使い方を間違えると、私たちの「考える力」を低下させる危険性があることをご存知でしょうか。これは、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究でも示唆されています。同大学の研究によると、AIを使って文章を作成した人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することが明らかになりました。これは、脳が考える作業をAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、深く考える力が衰えたり、アイデアが湧きづらくなったりするリスクがあります。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
まとめ
企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用はDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、「どこから手を付ければいいかわからない」「セキュリティや著作権が心配」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。例えば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。