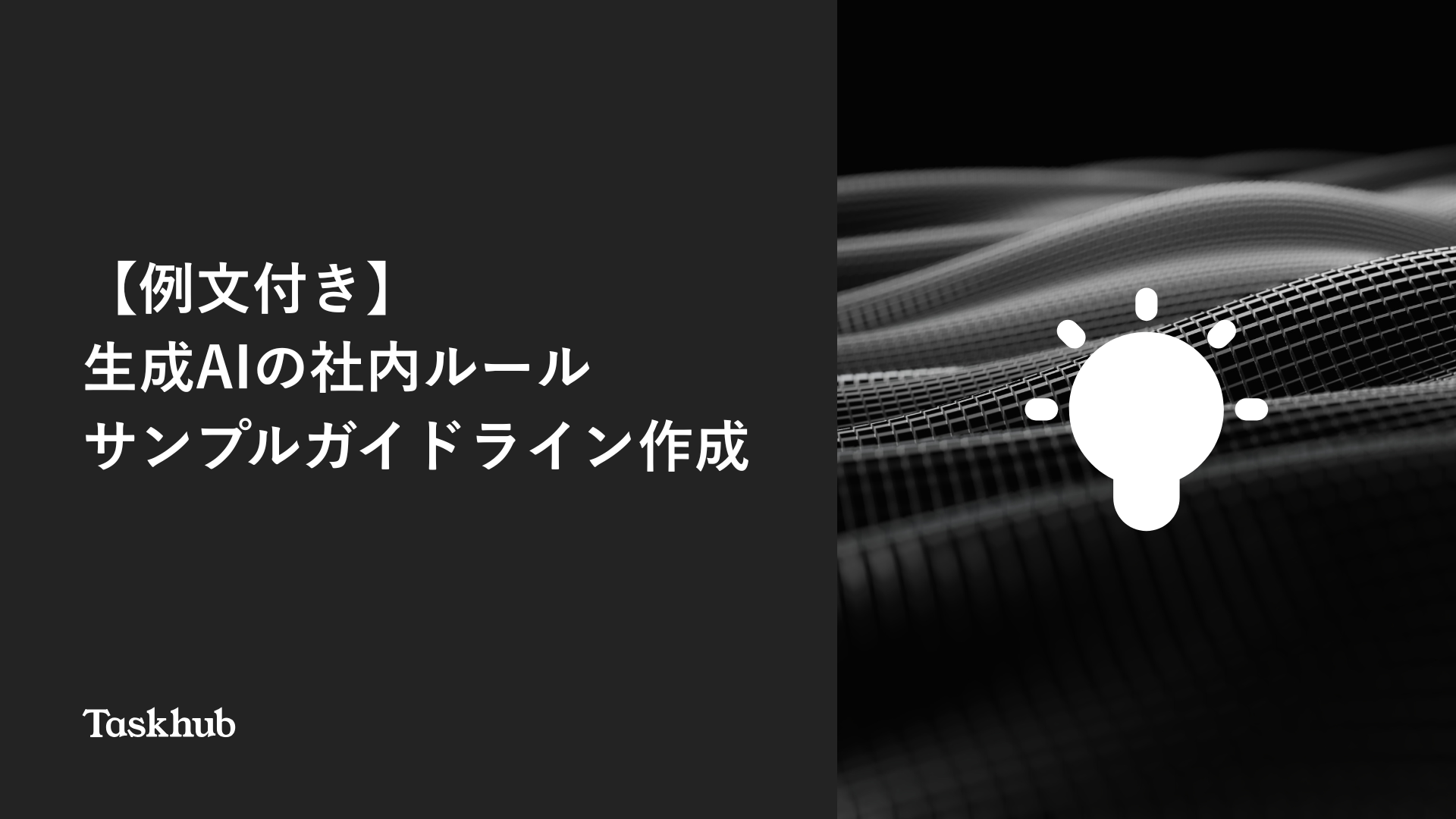ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は、ビジネスのあり方を大きく変えようとしています。業務効率化や新たなアイデア創出に役立つ一方、情報漏洩や著作権侵害といったリスクも潜んでおり、多くの企業がその扱いに頭を悩ませているのではないでしょうか。
「生成AIを導入したいが、何から手をつければいいかわからない」
「社員が勝手に使うことによるリスクが怖い」
「安全に活用するためのルール作りの方法や例文が知りたい」
この記事では、そんなお悩みを持つ企業の担当者様に向けて、生成AIを安全かつ効果的に活用するための社内ルールの作り方を、具体的なサンプルやテンプレートを交えて徹底解説します。本記事を読めば、リスクを管理しつつ、生産性を最大化するガイドライン策定のすべてがわかります。
生成AIの社内ルールとは?ガイドラインと利用規程の違いを解説
まず、生成AIの社内ルールを策定するにあたり、その重要性と基本的な用語の定義を理解しておくことが重要です。
生成AIの社内ルールを定める重要性
生成AIの社内ルールがない状態は、いわば「交通ルールのない道路」と同じです。便利さの裏で、いつ重大な事故が起きてもおかしくありません。具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
- 情報漏洩リスク: 社員が機密情報や個人情報をプロンプトに入力し、外部に漏洩する。
- 著作権侵害リスク: 生成AIが作成したコンテンツが、既存の著作物を無断で利用している。
- コンプライアンス違反リスク: 不正確または偏った情報を含む生成物を、そのまま社外に公開してしまう。
こうしたリスクを未然に防ぎ、社員全員が安心して生成AIの恩恵を受けられる環境を整備するために、明確な社内ルールが不可欠なのです。
AIへの指示であるプロンプトについて、基本的な知識から具体的なプロンプト例まで紹介している記事もございます。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/
生成AIガイドラインと利用規程の違い
社内ルールを検討する際、「ガイドライン」と「利用規程」という言葉が出てきます。両者は似ていますが、少しニュアンスが異なります。
| 項目 | ガイドライン | 利用規程 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 考え方や行動の「指針」「推奨事項」 | 遵守すべき「公式なルール」「規則」 |
| 目的 | AI活用の方向性を示し、リテラシー向上を促す(攻めの側面) | 禁止事項や罰則を定め、リスクを管理する(守りの側面) |
| 表現 | 「〜することが望ましい」「〜を推奨する」 | 「〜してはならない」「〜しなければならない」 |
多くの場合、まず大枠の方針として**「ガイドライン」を定め、その中で具体的な禁止事項や手続きを「利用規程」**として明記する構成がとられます。本記事では、これらを総称して「社内ルール」と呼び、解説を進めます。
生成AIの社内ルールを作成する3つのメリット
面倒に思えるルール作りですが、企業にとっては大きなメリットがあります。
法令違反やセキュリティリスクを未然に防ぐ
最大のメリットは、セキュリティリスクの低減です。ルールによって「入力してはいけない情報(機密情報、個人情報など)」や「出力物の正しい扱い方(ファクトチェックの義務化など)」を明確にすることで、情報漏洩や著作権侵害といった重大なインシデントを未然に防ぐことができます。
社員のAIリテラシーが高まり生産性が向上する
ルール策定の過程や、その後の研修を通じて、社員は生成AIの正しい使い方、リスク、そして可能性を体系的に学ぶことができます。これにより、全社的なAIリテラシーが向上。結果として、各々が適切な判断のもとでAIを使いこなし、組織全体の生産性向上に繋がります。
社員が積極的にAIを活用するようになる
意外に思われるかもしれませんが、明確なルールはAI活用を促進します。「何をしてはいけないか」がはっきりすることで、社員は「この範囲内なら大丈夫」と安心してAIを試せるようになります。ルールがない無法地帯では、リスクを恐れて誰も使わないか、一部の社員が隠れて使うといった不健全な状態に陥りがちです。心理的安全性を確保することが、積極的な活用に繋がるのです。
生成AIの社内ルール・サンプルに記載すべき項目
効果的な社内ルールには、以下の項目を盛り込むことが推奨されます。自社の状況に合わせてカスタマイズしましょう。
利用目的と禁止事項の明記
- 利用目的: なぜ会社として生成AIの利用を許可するのか、その目的を明記します。(例:「業務効率化及び生産性向上」「新たな企画・アイデアの創出支援」など)
- 禁止事項: 最も重要な項目です。会社の信用や資産を損なう行為を具体的にリストアップします。(例:機密情報・個人情報の入力、差別的・誹謗中傷的なコンテンツの生成、違法行為への利用など)
入力データに関する注意点
プロンプトに入力する情報に関するルールです。多くの生成AIサービスでは、入力情報がAIの学習データとして利用される可能性があるため、厳格な規定が必要です。
- 入力禁止情報の定義: 機密情報、個人情報、顧客情報、未公開の財務情報、ソースコードなど、具体的に列挙します。
- 学習データ利用のオプトアウト設定: 利用するAIサービスに学習データをオフにする設定(オプトアウト)がある場合、その設定を義務付けることを明記します
こちらは個人情報保護委員会が発表した、生成AIサービス利用における個人情報保護法遵守の注意点に関する資料です。合わせてご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/3kai/kojinjouhou.pdf
出力物の取り扱いと責任範囲
生成AIの出力物は、必ずしも正確・適切とは限りません。その取り扱いについて定めます。
- ファクトチェックの義務: 出力された情報は必ず真偽を確認し、鵜呑みにしないことを義務付けます。
- 著作権の確認: 生成物が他者の著作権を侵害していないか確認するよう注意喚起します。特に画像生成AIでは重要です。
- 最終責任の所在: 生成物を利用したことによる最終的な責任は、利用者本人(またはその監督者)にあることを明確にします。
データ管理・ログ管理の方針
万が一のインシデントに備え、利用状況を追跡できる体制を整えます。
- 利用履歴の記録: 誰が、いつ、どのAIサービスを利用したかのログを取得・保管する方針を定めます。
- 監査: 定期的に利用ログを監査し、不適切な利用がないかチェックする体制について記載します。
教育・研修の実施
ルールを形骸化させないために、教育の機会を設けることを明記します。
- 研修の義務化: 全社員または利用希望者に対して、ガイドラインに関する研修の受講を義務付けます。
- 情報提供: AIに関する最新情報や注意喚起を定期的に社内へ発信する旨を記載します。
利用申請の流れ
全社で統一されたAIサービスを利用する場合や、有料プランを利用する場合の申請フローを定めます。
- 申請方法: 誰に、どのような書式で申請するのかを明確にします。
- 承認プロセス: 申請後の承認ルート(例:直属の上長→情報システム部)を定めます。
生成AIの社内ルール・サンプル作成のステップ
実際にルールを作成する際の、おすすめの3ステップをご紹介します。
ステップ1:現状把握と活用方針の策定
まずは自社の状況を把握することから始めます。経営層、法務、情報システム、そして現場の代表者などを巻き込み、以下の点を議論しましょう。
- 現状把握: 社内では既に誰かが生成AIを使っているか?(シャドーITの実態調査)
- 方針策定: 我が社は生成AIをどう位置づけるか?(リスク回避優先の「守り」か、積極活用を目指す「攻め」か)
- 対象ツールの選定: 全社で標準利用するAIツールは何か?(セキュリティの高い法人向けプランを検討)
ステップ2:テンプレートを基にしたルール文面の作成
方針が固まったら、具体的なルールを作成します。ゼロから作るのは大変なので、本記事のサンプルや、後述する他社事例、公的機関が公開しているテンプレートなどを参考に、自社向けにカスタマイズしていくのが効率的です。この段階では、法務部や情報システム部が中心となってドラフトを作成します。
ステップ3:現場とのすり合わせと周知・浸透
作成したルール案は、必ず現場の社員にも意見を求めましょう。「このルールでは業務が回らない」「こういうケースはどうなるのか」といった現場の声を反映させることで、実用的なルールになります。
最終版が完成したら、全社説明会や研修を実施し、内容を隅々まで周知・浸透させます。
生成AIの社内ルール・サンプル【活用例】
ここでは、コピーして使える具体的なサンプル(利用規程)をご紹介します。
利用規程テンプレート(全体像)
まずは規程全体の構成イメージです。
【生成AIサービス利用規程】
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用範囲)
第4条(利用対象者)
第2章 利用手続き
第5条(利用申請と承認)
第3章 利用上の遵守事項
第6条(基本原則)
第7条(入力情報の取扱い)
第8条(禁止事項)
第9条(出力情報の取扱い)
第4章 管理体制
第10条(管理責任者)
第11条(利用履歴の記録)
第12条(教育・研修)
第5章 その他
第13条(免責事項)
第14条(懲戒処分)
第15条(規程の改定)
附則
利用規程(サンプル)
特に重要な条文について、具体的な文面例を記載します。
(禁止事項)
第8条 利用者は、生成AIサービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
- 次の情報を入力する行為
(1) 個人情報保護法に定める個人情報、および特定個人情報
(2) 弊社の営業秘密、技術情報、その他社外秘として管理される機密情報
(3) 顧客、取引先から得た情報のうち、秘密保持義務を負う情報
(4) 未公開のインサイダー情報
(5) その他、弊社が非公開と定めた情報 - 法令、または公序良俗に違反するコンテンツを生成、または利用する行為
- 第三者の著作権、商標権、その他知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為
- 他者を誹謗中傷し、またはその名誉・信用を毀損するコンテンツを生成、または利用する行為
- 会社の許可なく、業務外の目的で利用する行為
(出力情報の取扱い)
第9条 利用者は、生成AIサービスから得た出力情報の取扱いに関し、以下の各号を遵守しなければならない。
- 出力情報に、虚偽、不正確、または偏見を含む情報が含まれる可能性があることを常に認識し、その真偽および正確性を自らの責任で確認(ファクトチェック)すること。
- 出力情報を社外向け資料、公開コンテンツ、納品物等に利用する場合は、必ず上長の承認を得ること。
- 出力情報が第三者の著作権等の権利を侵害するものでないかを確認し、利用すること。
- 出力情報を利用したことによって生じた結果について、最終的な責任は利用者本人が負うものとする。
生成AIの社内ルール・サンプル作成の注意点とよくある失敗
ルール作成時に陥りがちな失敗と、その対策を知っておきましょう。
現場の実態に即していない
法務部や管理部門だけで作成したルールは、理想論に走り、現場の業務実態と乖離してしまうことがあります。結果として、誰も使わない「形骸化したルール」になりかねません。必ず開発、営業、企画など、様々な部門の意見を取り入れましょう。
「禁止」ばかりで社員の活用意欲を削ぐ
リスクを恐れるあまり、「禁止」「禁止」と制限ばかりを並べたルールは、社員のチャレンジ精神や活用意欲を削いでしまいます。「守りのルール」と同時に、「攻めの活用」を後押しする姿勢を示すことが重要です。「何がダメか」だけでなく、「どうすれば安全に使えるか」という視点でルールを設計しましょう。
作成しただけで満足してしまう
ルールは作って終わりではありません。AI技術は日進月歩であり、新たなリスクや活用法が次々と登場します。一度作ったルールも定期的に見直し、PDCAサイクルを回していく必要があります。また、新入社員への研修など、継続的な周知活動も不可欠です。
生成AIの社内ルール作成で参考になるガイドライン事例
自社でルールを作成する際、他社の動向や公開されているガイドラインが非常に参考になります。
利用を「全面禁止」している企業の傾向
情報漏洩リスクが事業の根幹を揺るがす金融機関や、厳格な情報管理が求められる一部の業界では、リスク回避を最優先し、現時点では利用を「全面禁止」としているケースもあります。しかし、これは少数派になりつつあります。
利用を「条件付き許可」している企業の取り組み
多くの企業は、リスク対策を講じた上で利用を認める「条件付き許可」のスタンスをとっています。パナソニックコネクト社や富士通社などは、早くから社内実践を重ね、独自のガイドラインを策定・運用していることで知られています。
ガイドラインを公開している企業の事例
中には、自社のガイドラインを社外に公開している企業もあります。これらは非常に参考になるため、一読をおすすめします。
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA): 「AI倫理・プライバシーポリシー」を公開し、AI開発・利用における基本原則を示しています。
- LINEヤフー株式会社: 「AI利用の基本方針」を定め、グループ全体でのAI活用における考え方を明確にしています。
- 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA): 「生成AIの利用ガイドライン」を公開しており、企業がルールを策定する上での汎用的な雛形として活用できます。
こちらは富士通が実際に一般公開している「生成AI利活用ガイドライン」です。合わせてご覧ください。
https://global.fujitsu/ja-jp/technology/key-technologies/news/ta-generative-ai-utilizationguideline-20240112

生成AIの社内ルールを効果的に運用するポイント
最後に、作成したルールを絵に描いた餅にしないための運用ポイントを3つ紹介します。
定期的なアップデートと社内周知
前述の通り、AI技術や社会の状況は常に変化します。最低でも半年に一度、できれば四半期に一度はルールを見直す機会を設け、必要に応じてアップデートしましょう。改定した際は、その内容を必ず全社に周知徹底することが重要です。
フォローアップ体制の整備
「このケースはガイドラインに違反する?」「新しいAIツールを使いたいが問題ないか?」といった社員からの疑問や相談に応えるための窓口(ヘルプデスクや専門チーム)を設置しましょう。気軽に相談できる体制があることで、ルール遵守と活用の両方が促進されます。
システムとルールの両面からのリスク管理
ルール(人の意識)だけに頼るのには限界があります。可能であれば、システム的な制御も組み合わせましょう。
- アクセス制御: 会社が許可したAIサービス以外にはアクセスできないようにする。
- DLP(Data Loss Prevention): 機密情報などが社外に送信されそうになった際に、自動で検知・ブロックするツールを導入する。
ルールによる「ソフトな制御」と、システムによる「ハードな制御」を組み合わせることで、より強固なリスク管理体制を構築できます。
ChatGPTの利用における注意点やリスクについて詳しく解説した記事もございます。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/
なぜあなたの会社はChatGPTのような生成AI活用をためらってしまうのか?
企業が生成AIの導入に二の足を踏んでしまう背景には、情報漏洩や著作権侵害といった具体的なリスクへの懸念があります。特に、従業員が個人的な判断でAIを利用する「シャドーIT」の状態は、いつ重大なインシデントに繋がるか予測できません。多くの企業が「AIは便利そうだが、何から手をつければいいかわからない」「従業員が勝手に使うのが怖い」といった課題に直面しているのではないでしょうか。
この課題を解決するためには、ただ単に利用を禁止するのではなく、安全かつ効果的に活用するための明確な社内ルールを定めることが不可欠です。しかし、ルールの策定には法務や情報システム部門など、複数の部署が連携する必要があり、多くの労力が伴います。さらに、現場の業務実態と乖離したルールは形骸化し、誰も使わない状態に陥ってしまうリスクもあります。
引用元:
情報漏洩や著作権侵害といったリスクは、生成AIの社内利用における主要な懸念事項として広く認識されています。また、従業員が会社の管理外でAIツールを使用する「シャドーIT」は、サイバーセキュリティの観点からも大きな問題となっています。(総務省「AIネットワーク社会推進会議」資料、経済産業省「生成AI時代のDX推進」に関する報告書など)
まとめ
企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。