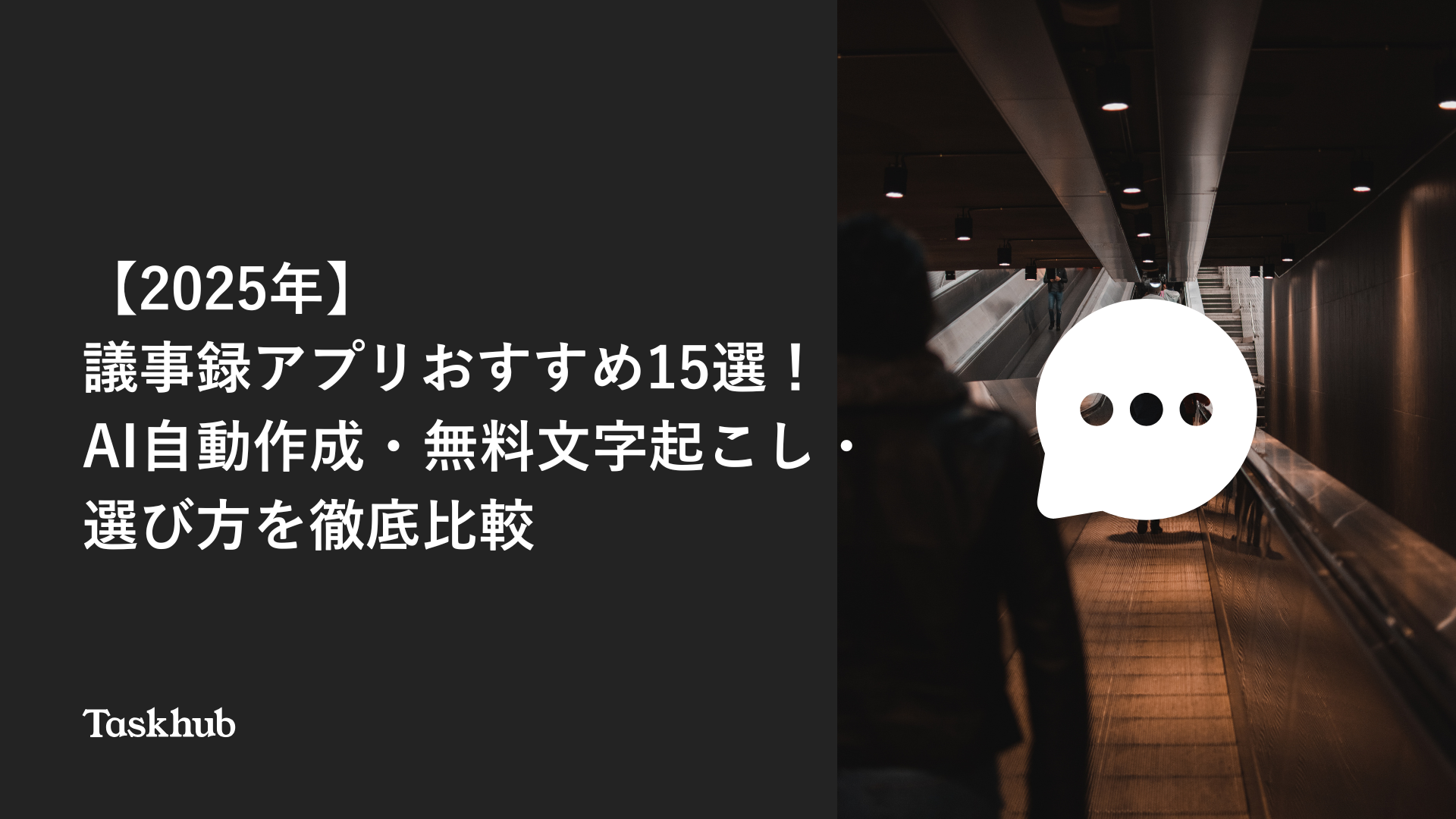「会議のたびに、議事録作成に何時間もかかっている…」
「AIが自動で文字起こしや要約をしてくれるアプリが欲しい」
「無料の議事録アプリを試したけど、精度が低くて使い物にならなかった」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
近年、AI技術の進化により、議事録アプリの精度は飛躍的に向上しています。
本記事では、2025年の最新情報に基づき、AI機能を搭載したおすすめの議事録アプリ15選を徹底比較します。
無料プランで使えるアプリから、セキュリティ重視の高性能アプリ、導入で失敗しないための5つの選び方まで、網羅的に解説しました。
議事録作成の工数を劇的に削減し、本来の業務に集中するための最適なアプリがきっと見つかります。
ぜひ最後までご覧ください。
議事録アプリとは?AIで文字起こし・要約・作成を自動化
議事録アプリとは、会議中の音声をAIがリアルタイムまたは録音データから認識し、自動で文字起こしを行うツールです。
単なる文字起こしに留まらず、AIによる要約、話者の識別、タスクの抽出まで行い、議事録作成のプロセス全体を自動化・効率化します。
従来の手作業による議事録作成の負担を大幅に軽減できるため、多くの企業で導入が進んでいます。
議事録アプリの主な機能(文字起こし、AI要約、話者分離など)
最新の議事録アプリには、議事録作成を効率化するための多様な機能が搭載されています。
多くのアプリで共通して提供されている主な機能は以下の通りです。
高精度な自動文字起こし:
会議中の会話をリアルタイムでテキスト化します。
また、録音・録画ファイルをアップロードして文字起こしすることも可能です。
近年のAI技術の進歩により、専門用語や業界用語を学習させる辞書登録機能や、高い認識精度を持つアプリが増えています。
AIによる自動要約・清書:
文字起こしされた膨大なテキストデータから、AIが自動で重要なポイントを抽出し、簡潔な要約を作成します。
「です・ます」調への統一や、不要な「えー」「あのー」といったフィラー(間投詞)の削除など、読みやすい形に清書する機能も充実しています。
AIによる要約機能をより深く理解し、使いこなすためのプロンプト活用術はこちらで解説しています。
話者分離(話者識別):
会議の参加者それぞれの発言をAIが声紋などから識別し、「誰が」「何を」話したかを明確に分けて記録します。
これにより、議事録の可読性が格段に向上し、議論の流れを追いやすくなります。
タスク・決定事項の抽出:
AIが会話の内容を解析し、「(誰が)いつまでに何をすべきか」といったタスクや、会議での決定事項を自動で抽出し、リスト化します。
会議後のタスク漏れを防ぎ、実行力を高めるのに役立ちます。
データ共有・連携機能:
作成した議事録データ(テキスト、要約、音声)は、URLや各種ファイル形式(Word, txtなど)で簡単にチーム内に共有できます。
また、Slack、Teams、Googleカレンダーなどの外部ツールと連携し、通知やスケジュール管理を自動化できるアプリも多いです。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
議事録アプリを導入するメリット(工数削減、情報共有の円滑化)
議事録アプリの導入は、単に「楽になる」だけでなく、企業やチーム全体に大きなメリットをもたらします。
最大のメリットは、議事録作成にかかる工数の劇的な削減です。
会議時間と同じか、それ以上かかっていた文字起こしや清書の時間がほぼゼロになり、担当者は本来のより創造的な業務にリソースを割くことができます。
こちらは、PwCが実施した日米比較における生成AIの業務効果に関する実態調査です。合わせてご覧ください。 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/generative-ai-survey2024-us-comparison.html
また、議事録作成の負担がなくなることで、会議中は発言や議論に集中できるようになります。
第二に、情報共有の迅速化と質の向上が挙げられます。
会議終了後すぐに、正確な議事録(または要約)が共有されるため、参加できなかったメンバーへの情報伝達がスムーズになります。
「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、決定事項やタスクが正確に記録されることで、プロジェクトの進行が円滑になります。
さらに、過去の議事録データが検索可能なナレッジベースとして蓄積される点も重要です。
過去の議論の経緯を簡単に検索・参照できるようになり、組織全体の知識資産となります。
議事録アプリの導入は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として、業務効率化を大きく前進させます。こちらの記事も合わせてご覧ください。
失敗しない議事録アプリの選び方【5つの重要ポイント】
議事録アプリは種類が多く、どれを選べばよいか迷ってしまいがちです。
自社やチームの目的に合わないアプリを選ぶと、かえって手間が増えたり、コストが無駄になったりする可能性もあります。
ここでは、議事録アプリの導入で失敗しないために確認すべき、5つの重要な選定ポイントを解説します。
1. AI機能(自動要約・清書・タスク抽出)は充実しているか
単なる文字起こし(Speech to Text)だけを求めるのか、その先の「議事録作成」まで自動化したいのかを明確にしましょう。
AIによる自動要約機能は、今や多くのアプリに搭載されていますが、その「質」はアプリによって差があります。
単純なキーワードの羅列になるのか、文脈を理解した自然な要約を生成してくれるのか、無料トライアルなどで試すことが重要です。
こちらは、AI(GPT-3.5)による会議要約の有効性を評価した研究レポートです。AI要約の技術的側面にご興味がある方はご覧ください。 https://repository.tudelft.nl/file/File_ccf89f60-1f3f-46d5-82b4-42f4369689f2
また、文字起こし結果をそのまま使うのではなく、「要点を抽出して清書する」「会話からタスクを自動でリストアップする」といった、議事録として即座に使えるレベルまでAIが処理してくれるかどうかが、業務効率に直結します。
求めるAIのレベルと機能が搭載されているかを確認しましょう。
2. 文字起こしの精度は高いか(専門用語・話者認識)
議事録の土台となる文字起こしの精度は、最も重要なポイントです。
一般的な会話の精度が高くても、自社の業界の専門用語や、社内特有の略語を正しく認識できなければ、結局、手作業での修正に多くの時間を取られてしまいます。
多くのアプリでは、特定の単語を登録できる「辞書登録機能」が用意されています。
この機能の有無や、登録できる語数を確認しましょう。
また、複数人が同時に発言するような活発な会議や、声が似ている参加者がいる場合でも、AIが正確に「話者」を分離できるかも重要です。
特にWeb会議だけでなく、対面の会議室で利用する場合、マイクからの距離によって認識精度が変わることもあるため、実際の利用シーンを想定してテストすることが不可欠です。
こちらは、日本語の音声認識におけるベンチマークテストに関する京都大学の研究資料です。精度の技術的背景としてご参照ください。 http://sap.ist.i.kyoto-u.ac.jp/EN/bib/intl/KAW-SSPR03.pdf
3. 無料プランの範囲と有料プランの料金体系
議事録アプリの料金体系は、大きく分けて「無料プラン(またはトライアル)」「月額固定プラン」「従量課金プラン」があります。
まず、無料プランや無料トライアルで、前述した「AI機能」や「文字起こし精度」を必ず試しましょう。
無料プランは、「1回あたり10分まで」「月間60分まで」といった時間制限や、「AI要約は月5回まで」「話者分離は不可」などの機能制限が設けられている場合がほとんどです。
お試しで使う分には十分でも、本格的に業務で使うには不十分なケースが多いため、制限内容をしっかり確認する必要があります。
有料プランを検討する際は、利用頻度や時間、利用人数(ID数)に応じた最適なプランを選びます。
利用時間が月によって変動する場合は、使った分だけ支払う従量課金制が有利なこともありますが、利用上限がある月額固定プランの方が結果的に安くなる場合もあります。
チーム全員で使うのか、特定の部署だけで使うのかによっても、ID課金制と時間課金制のどちらが適しているか変わってきます。
4. 利用シーンに合っているか(Web会議連携、スマホアプリ対応)
議事録アプリを「いつ」「どこで」「どのように」使いたいかを具体的にイメージしましょう。
主な利用シーンがZoomやMicrosoft Teams、Google MeetなどのWeb会議であれば、これらのツールと直接連携できるアプリが便利です。
会議にAIボットを自動で参加させ、録画と文字起こしを同時に行ってくれる機能は非常に効率的です。
一方で、対面(オフライン)の会議が多い場合は、スマートフォンのアプリで手軽に録音・文字起こしができるか、あるいは専用のICレコーダー(ボイスレコーダー)と連携できるアプリが適しています。
PCのマイク性能に依存せず、クリアな音声を録音できるため、結果として文字起こしの精度向上にも繋がります。
総務省の最新調査でも示されている通り、ビジネスシーンを含む個人のインターネット利用はスマートフォンが主流です。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd21b120.html
5. セキュリティは万全か(情報漏洩対策)
会議では、社外秘の情報や個人情報など、機密性の高い内容が扱われることも少なくありません。
議事録アプリを利用するということは、これらの音声データやテキストデータを外部のクラウドサーバーにアップロードすることを意味します。
そのため、事業者のセキュリティ体制は必ず確認すべきです。
通信や保存データが暗号化されているか、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの第三者認証を取得しているか、といった点は最低限のチェックポイントです。
さらに機密性が求められる場合は、データを外部サーバーに一切送信しない「オンプレミス(自社内設置型)」や「完全オフライン対応」のアプリを選ぶ必要があります。
自社のセキュリティポリシーに準拠したアプリを選定しましょう。
こちらは、IPA(情報処理推進機構)が公開している、AI利用時におけるセキュリティ脅威とリスクに関する調査報告書です。 https://www.ipa.go.jp/security/reports/technicalwatch/20240704.html
【無料プランあり】AI議事録アプリおすすめ5選
まずは無料で試してみたい、あるいは利用頻度が低いので無料で済ませたい、という方向けに、無料プラン(または長期の無料トライアル)が充実しているAI議事録アプリを紹介します。
ただし、多くは機能や時間に制限があるため、本格導入前のお試しと位置づけるのがよいでしょう。
tl;dv(無料プランの特徴とおすすめポイント)
tl;dv(ティーエルディーブイ)は、特にWeb会議(Google Meet, Zoom, Teams)の利用が多いチームにおすすめのツールです。
無料プランでも録画・文字起こしが利用できますが、無制限ではありません。 無料プランでは、録画データの保存期間(例:3ヶ月)や視聴方法(例:視聴待機時間の発生)に一部制限がある点に注意が必要です。
また、AIによる「要約」は、最初の10回までは全機能を利用できますが、それ以降は会議の冒頭部分のみに制限されます。 Web会議の録画と文字起こし、要約を試すには十分な機能を備えています。
40以上の言語に対応しており、グローバルな会議にも強いツールです。
まずはWeb会議の議事録作成を自動化したい場合の、試用候補となるアプリです。
Notta(無料プランの特徴とおすすめポイント)
Notta(ノッタ)は、スマホアプリ(iOS, Android)とPC(Web, Chrome拡張機能)の両方で利用できる、高精度な文字起こしアプリです。
無料プラン(フリープラン)が用意されており、AI要約機能も月間30回まで利用可能です。
ただし、無料プランの最大の注意点は、リアルタイム文字起こし・ファイルインポートともに「1回のセッションが3分まで」という制限に加え、「月間の合計利用時間が120分まで」という二重の制限があることです。
そのため、無料プランは「Nottaの文字起こし精度やAI要約の質を試す」ためのお試し版と割り切るのが現実的です。
短い音声メモの文字起こしなどには使えますが、通常の会議の議事録作成に無料プランで対応するのは難しいでしょう。
とはいえ、日本語の認識精度は非常に高いと評価されており、有料プラン(月額1,200円程度~)を検討する前提で試す価値は十分にあります。
Fireflies.ai(無料プランの特徴とおすすめポイント)
Fireflies.ai(ファイアフライズ・エーアイ)は、Web会議に特化したAI議事録アシスタントです。
Google Meet, Zoom, Teamsなど主要なWeb会議ツールと連携し、会議にAIボット(Fred)を自動で参加させることができます。
無料プラン(Free)では、文字起こしが時間無制限で利用可能です。
ただし、ストレージ容量に制限(800分/シート)があり、容量を超えると古い録音が削除される可能性があります。
AIによる要約(AI Summaries)も利用できますが、有料プランに比べて機能が制限されています。
tl;dvと似ていますが、Fireflies.aiは英語圏での利用者が多く、英語の会議における精度や機能が特に充実していると評価されています。
無料プランで文字起こしを無制限に利用できる点は魅力的であり、Web会議中心かつ英語での利用が多い場合に適しています。
スマート書記(無料プランの特徴とおすすめポイント)
スマート書記は、日本のビジネスシーンに特化して開発されたAI議事録サービスです。
金融機関や大手メーカーなど、セキュリティ要件が厳しい企業での導入実績が豊富です。
スマート書記には常時利用可能な「無料プラン」はありませんが、「14日間の無料トライアル」が提供されています。
このトライアル期間中は、有料プラン(Businessプラン)とほぼ同等の機能をすべて試すことができます。
特徴は、Web会議はもちろん、対面会議(スマホアプリや専用マイク)、電話音声など、あらゆるシーンの音声を高精度に文字起こしできる点です。
AIによる要約、話者分離、重要箇所の自動抽出(AIタグ付け)など、議事録作成に必要な機能が網羅されています。
無料プランではありませんが、高性能な国産ツールをじっくり試したい場合におすすめです。
AI議事録取れるくん(無料プランの特徴とおすすめポイント)
AI議事録取れるくんは、シンプルな操作性とコストパフォーマンスを追求したAI議事録ツールです。
このツールには、常時利用可能な無料プランに関する明確な情報が少ないものの、「3日間の無料トライアル」が提供されています。
このトライアル期間で、リアルタイム文字起こしや録音ファイルのアップロード、AIによる要約機能を試すことができます。
特徴は、利用のハードルが低く、すぐに使い始められる点です。
複雑な設定なしに、Web会議(Zoom, Teams, Meet対応)や対面の会議で利用できます。
有料プランも比較的安価な設定がされているため、まずは無料トライアルで操作感や精度が自社に合うかを確認し、スモールスタートしたい企業に適しています。
無料プラン比較表(利用時間、機能制限など)
| アプリ名 | 無料プランの主な特徴 | 主な制限(無料プラン) |
| tl;dv | 録画・文字起こし(機能制限あり)、AI要約(回数制限あり) | 録画の保存期間・視聴に制限、AI要約は一定回数以降機能制限 |
| Notta | AI要約(月30回)、高精度文字起こし | 1回の文字起こしが3分まで |
| Fireflies.ai | 文字起こし無制限、Web会議自動参加 | AI要約の機能制限、ストレージ制限(800分) |
| スマート書記 | 14日間の無料トライアル(全機能利用可) | 常時無料プランは無し |
| AI議事録取れるくん | 3日間の無料トライアル | 常時無料プランは情報不明瞭 |
【機能・精度重視】高性能なAI議事録アプリおすすめ5選
無料プランでは機能が物足りない、あるいはセキュリティや文字起こし精度を最重要視する企業向けに、高性能な有料AI議事録アプリを紹介します。
多くは無料トライアルが用意されているため、導入前に性能を確かめることが可能です。
AutoMemo(ソースネクスト株式会社)
AutoMemo(オートメモ)は、翻訳機「ポケトーク」で知られるソースネクストが提供するサービスです。
最大の特徴は、専用のAIボイスレコーダー端末とクラウドサービスが一体となっている点です。
専用端末(オートメモ Sなど)の録音ボタンを押すだけで、録音データが自動でクラウドに転送され、AIが文字起こしを行います。
PCやスマホの操作が不要で、対面での取材や会議が多い場合に圧倒的な手軽さを誇ります。
もちろん、スマホアプリでの録音や、既存の音声ファイルをアップロードして文字起こしすることも可能です。
2025年現在、AI要約機能も標準搭載され、文字起こしサービスは月額1,480円(月30時間まで)から利用できます。
高精度な文字起こしとハードウェアの利便性を両立したい人におすすめです。
YOMEL(アーニーMLG株式会社)
YOMEL(ヨメル)は、「日本語に特化した高精度」を謳うAI議事録アプリです。
開発元はAIベンチャーのアーニーMLGで、特に日本語の文脈理解や要約の精度に強みを置いています。
料金体系がユニークで、一般的なユーザー(ID)課金ではなく、利用時間に応じた課金制(スタータープラン:月額28,000円/30時間~)を採用しています。
IDは無制限に発行できるため、全社的に利用を広げたいが、実際に使うのは一部の部署やメンバーに限られる、といった場合にコストメリットが出やすいです。
合計10時間のフリートライアルが提供されており、その精度の高さをじっくりと試すことができます。
とにかく日本語の要約精度にこだわりたい企業に適しています。
Rimo Voice(Rimo合同会社)
Rimo Voice(リモボイス)は、日本語の文字起こし精度90%以上を誇る高機能なAI議事録ツールです。
Web会議へのBot参加、録音ファイルのアップロード、スマホ録音に対応しています。
大きな特徴は、2025年に個人向けプランが新設されたことです。
法人向けの高機能サービスが、個人でも「文字起こしプラン」(月額1,650円/月2,100分まで)や「プロプラン」(月額4,950円/無制限+AI機能)として利用できるようになりました。
もちろん、法人向けのチームプランも用意されています。
AIによる要約、AIアシスタントとの対話による内容整理、タイムスタンプ付きのテキストなど、議事録作成に必要な機能が網羅されています。
60分間の無料トライアル(文字起こしプラン)もあり、個人事業主から大企業まで幅広く対応できるサービスです。
ScribeAssist(株式会社アドバンスト・メディア)
ScribeAssist(スクライブアシスト)は、音声認識技術の国内最大手であるアドバンスト・メディア社が提供する文字起こし支援アプリケーションです。
長年の研究開発に裏打ちされた音声認識エンジン「AmiVoice」を搭載しており、圧倒的な認識精度を誇ります。
最大の特徴は、2025年に追加された「スタンドアローン要約」機能です。
これにより、文字起こしからAI要約まで、インターネットに接続しない「完全オフライン環境」で完結できます。
機密情報を一切外部サーバーに送信したくない、という最高レベルのセキュリティ要件に応えることができます。
料金は法人向けの小規模プラン(1~5人)で月額80,000円~と高価格帯ですが、14日間の無料トライアル(法人限定)も提供されています。
金融、医療、官公庁など、セキュリティと精度を最重要視する組織向けのプロフェッショナルツールです。
SecureMemo(Nishika株式会社)
SecureMemo(セキュアメモ)は、その名の通り「セキュリティ」に徹底的に特化したAI議事録作成サービスです。
開発元のNishika株式会社は、データサイエンスのコンペティションプラットフォームを運営する企業です。
ScribeAssistと同様に、機密情報を扱う企業向けに「完全オフライン」での利用(オンプレミス版)に対応しています。
クラウド版においても、ブラウザ上で直接録音できる機能(2025年リリース)を搭載し、ローカルPCに音声ファイルを残さない運用も可能です。
世界水準の音声認識AIと、実用レベルの議事録自動生成(要約、話者分離)機能を、高いセキュリティ環境で利用できる点が強みです。
料金プランは非公開となっており、個別の「要問い合わせ」となっています。
機密保持契約(NDA)が必須となるような会議が多い企業向けのソリューションです。
【無料で使える】文字起こし・議事録作成に便利なツール5選
高機能なAI議事録アプリでなくても、日常的なメモや簡単な議事録であれば、無料で使えるツールで十分対応できる場合があります。
ここでは、議事録作成にも活用できる無料のツールを5つ紹介します。
Google ドキュメント(音声入力機能)
多くの人が利用しているGoogle ドキュメントには、標準で「音声入力」機能が搭載されています。
PC(Chromeブラウザ)の「ツール」メニューから「音声入力」を選択し、マイクアイコンをクリックするだけで、マイクが拾った音声をリアルタイムで文字起こしできます。
スマートフォンのGoogleドキュメントアプリでも、キーボードのマイクボタンから同様に音声入力が可能です。
完全に無料で、時間制限も特にありません。
ただし、話者分離やAI要約機能はなく、あくまで「聞いたままをテキスト化する」機能です。
また、既存の録音ファイルを直接文字起こしする機能は標準では備わっていません(PCのサウンド設定を工夫すれば可能)。
個人のメモや、簡易的な議事録の下書き作成に便利です。
LINE WORKS AiNote(旧CLOVA Note)
LINE WORKS AiNote(ラインワークス・エーアイノート)は、LINEのAI技術を活用した高精度な文字起こしサービスで、以前は「CLOVA Note」として知られていました。
無料プラン(フリー)が提供されており、精度の高い日本語の文字起こしとAIによる要約機能を利用できます。
LINE WORKSのアカウントが必要ですが、個人でも開設可能です。
Zoom, Teams, Google MeetなどのWeb会議ツールとも連携できます。
無料プランでは利用時間に制限がありますが(例:月300分までなど、変更の可能性あり)、その精度の高さから人気のあるツールです。
話者分離にも対応しており、無料ツールの中では非常に高機能な選択肢の一つです。
Microsoft Translator
Microsoft Translator(マイクロソフト・トランスレーター)は、本来は多言語翻訳のためのアプリですが、強力な「会話」機能を備えています。
この機能を使うと、複数人(最大100人)が各自のスマートフォンやPCから会話に参加し、それぞれの言語で話した内容がリアルタイムで翻訳・文字起こしされます。
話者も色分けされて表示されるため、簡易的な議事録として利用できます。
特に、多言語が飛び交うグローバルな会議において真価を発揮します。
ただし、無料版では1回のセッションが短い時間(例:1分)に制限されるといった情報もあり、長時間の議事録作成には制約がある可能性も否めません。
あくまで翻訳がメインのツールですが、特定のシーンでは非常に役立ちます。
ユーザーローカル音声議事録システム
株式会社ユーザーローカルが提供する「音声議事録システム」は、ブラウザ上で動作する完全に無料のAI議事録ツールです。
アカウント登録も不要で、サイトにアクセスすればすぐに利用を開始できます。
マイクからのリアルタイム文字起こしに加え、音声ファイルのアップロードにも対応しています。
無料でありながら、AIによる話者識別(話者分離)や、発言の分析(キーワード抽出、ポジネガ判定)まで行ってくれる高機能なツールです。
ただし、クラウドベースのサービスであるため、機密性の高い会議での利用は、自社のセキュリティポリシーを確認の上、慎重に行う必要があります。
手軽にAI議事録作成を試してみたい場合に最適です。
toruno(トルノ)
toruno(トルノ)は、リコージャパンが提供する会議記録サービスです。
法人向けの有料プランがメインですが、個人向けにもプランが用意されています。
最大の特徴は、個人向けに「無料プラン」が提供されている点です(2025年時点)。
この無料プランでは、累計で3時間までの会議を記録(文字起こし、録音、画面キャプチャ)することができます。
3時間を超えると利用できなくなりますが、「まずは試してみたい」というニーズには十分応えられます。
Windowsのデスクトップアプリとして動作し、ZoomやTeamsなどのWeb会議と連携します。
「累計3時間」という制限はあるものの、完全無料で試せる貴重な高機能ツールの一つです。
議事録アプリ利用時の注意点とリスク
議事録アプリは非常に便利ですが、利用にあたってはいくつかの注意点とリスクを理解しておく必要があります。
これらを軽視すると、重大な情報漏洩や、かえって業務効率の低下を招くことにもなりかねません。
機密情報・個人情報の取り扱いに注意
議事録アプリ、特にクラウド型のサービスを利用する場合、会議の音声データやテキストデータは事業者のサーバーに送信・保存されます。
このデータに、顧客の個人情報、新製品の開発情報、M&Aに関する情報など、社外秘の機密情報が含まれる場合、情報漏洩のリスクを伴います。
アプリを選定する際は、その事業者がどのようなセキュリティ対策(データの暗号化、アクセス管理、ISMS認証取得など)を講じているかを必ず確認し、自社のセキュリティポリシーと照らし合わせる必要があります。
また、会議の参加者(特に社外の人物)に対して、「本日の会議は、AIによる文字起こしのために録音・記録します」と事前に必ず同意を得ることも、ビジネスマナーとして、またコンプライアンスの観点からも不可欠です。
無断での録音・記録は、信頼関係を損ねる原因となります。
クラウド型のサービスを利用する際は、情報漏洩リスクへの対策が必須です。こちらの記事も合わせてご覧ください。
AIの生成結果(文字起こし・要約)は必ず確認する
2025年現在、AIによる文字起こしや要約の精度は劇的に向上していますが、決して「100%完璧」ではありません。
特に、早口、強い訛り、専門用語、あるいは複数人が同時に発言した箇所などでは、AIが誤った認識をする可能性が常に残ります。
AIが生成した要約も同様です。
AIは文脈を理解しているように見えても、人間が暗黙的に理解している「議論の本当のニュアンス」や「発言の裏にある意図」までは汲み取れず、重要なポイントが要約から抜け落ちてしまうこともあります。
議事録アプリは、あくまで「作成を補助するアシスタント」と捉えるべきです。
AIが生成したテキストや要約を鵜呑みにせず、最終的には必ず人間の目で内容を確認し、必要な修正や補足を加えるというプロセスを怠ってはいけません。
この最終確認を省略すると、間違った情報が公式な議事録として共有されてしまうリスクがあります。
AIによる要約の「事実整合性(Factual Consistency)」は技術的な課題でもあり、その精度を高める研究も進められています。 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0302104
議事録アプリに関するよくある質問(FAQ)
iPhoneやAndroidのスマホだけでも使えますか?
はい、多くの議事録アプリがiPhone(iOS)およびAndroidに対応したスマートフォンアプリを提供しています。
Notta, Rimo Voice, AutoMemo, LINE WORKS AiNoteなどは、スマホアプリ単体で録音から文字起こし、要約の確認まで完結できます。
対面での会議や、外出先での打ち合わせのメモとして非常に便利です。
ただし、PCのWeb版の方が編集機能が充実している場合もあります。
ZoomやTeamsなどのWeb会議とどう連携するのですか?
連携方法はアプリによって異なりますが、主に2つのパターンがあります。
1つ目は、tl;dvやFireflies.aiのように、AIボット(アプリの分身)を会議の参加者として招待する方式です。
カレンダーと連携しておけば、スケジュールされた会議に自動で参加し、録画と文字起こしを開始します。
2つ目は、torunoやNottaのChrome拡張機能のように、PC上で起動しているWeb会議の音声を直接キャプチャ(録音)する方式です。
いずれの場合も、Web会議の音声を高精度で記録し、議事録作成に繋げることができます。
対面(オフライン)の会議でも使えますか?
はい、使えます。
最も手軽な方法は、前述のスマホアプリ(Notta, Rimo Voiceなど)を使い、会議室のテーブルの中央にスマートフォンを置いて録音する方法です。
より高音質で録音したい場合は、AutoMemoのような専用のAIボイスレコーダー端末を利用するか、PCに高性能な外部マイクを接続し、ScribeAssistやユーザーローカル音声議事録システムなどでリアルタイム文字起こしを行う方法があります。
完全無料で使えるアプリはありますか?
はい、あります。
Google ドキュメントの音声入力機能や、ユーザーローカル音声議事録システムは、機能制限なしに完全に無料で利用できます。
ただし、これらのツールはAI要約や高度な話者分離には対応していない場合があります。
LINE WORKS AiNoteやtorunoのように、機能や時間に制限がある「無料プラン」を提供している高機能アプリもあります。
まずはこれらの無料ツールや無料プランを試してみて、機能が不足すると感じたら有料プランを検討するのが良いでしょう。
あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い
ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。
【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない
「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。
これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。
- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。
- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方
では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「壁打ち相手」にする
自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」
これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「無知な生徒」として教える
自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」
AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」
AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。
まとめ
「議事録作成の工数を削減したい」といった課題認識からAI活用を検討する企業が増える一方、生成AIの導入はDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「議事録アプリ以外にも色々あるが、どれが最適かわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、本格的な導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、本記事で紹介したような議事録作成や文字起こしはもちろん、メール作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。