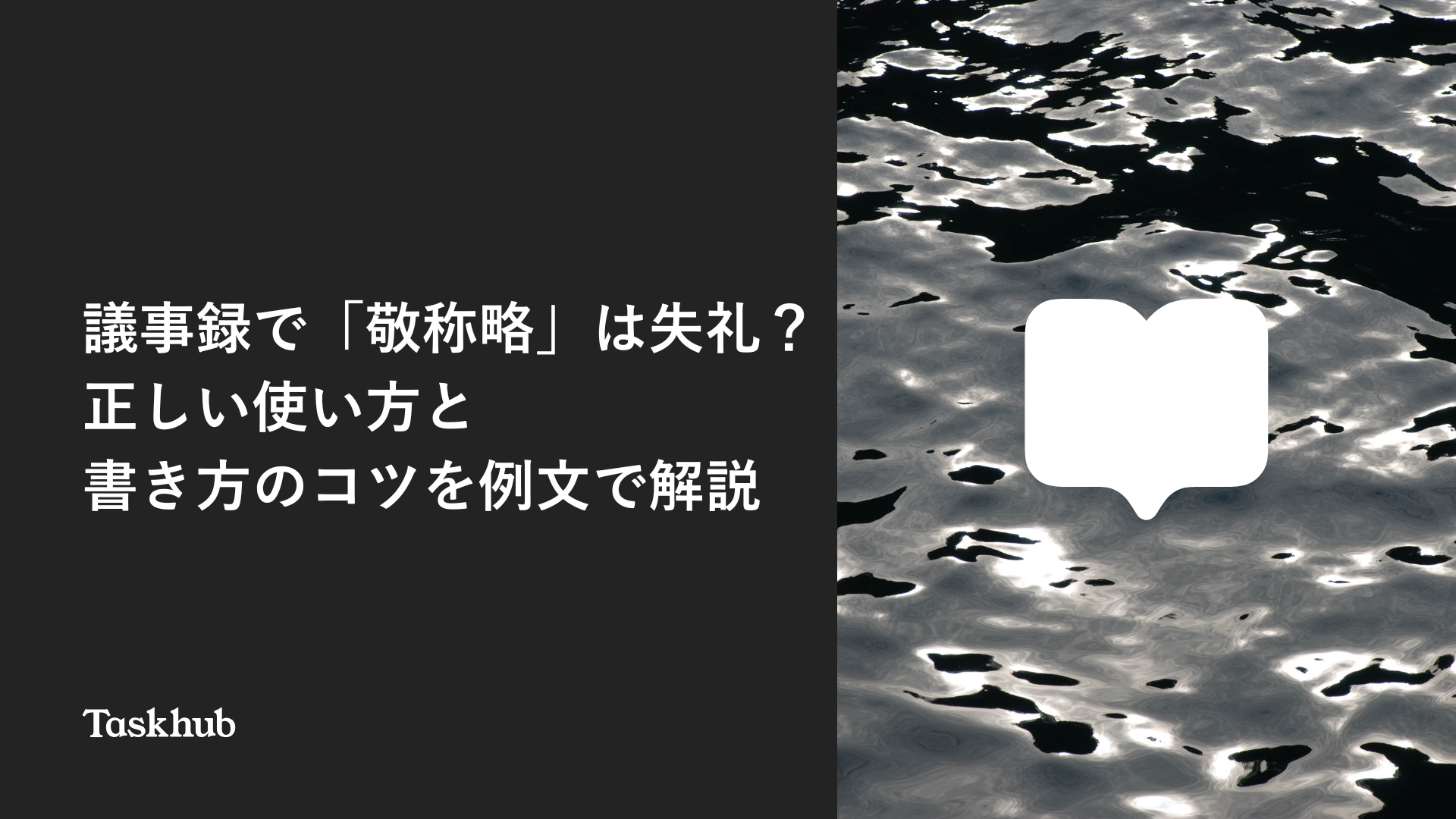「議事録の出席者名に『敬称略』を使いたいけど、失礼にあたらないか不安…」
「社外の人が参加する会議の議事録でも、敬称略にして良いもの?」
ビジネスシーンで議事録を作成する際、このような悩みを持つ方は少なくないでしょう。
「敬称略」は便利な言葉ですが、使い方を誤ると相手に不快感を与えかねません。
本記事では、議事録における「敬称略」の基本的な意味から、失礼にあたらないための判断基準、正しい使い方、具体的な記載例までを詳しく解説します。
この記事を読めば、議事録作成時に「敬称略」を使うべきか迷うことがなくなります。
ぜひ最後までご覧ください。
議事録で使う「敬称略」とは?意味と使用する理由
まず初めに、議事録で使われる「敬称略」という言葉の基本的な意味と、なぜそれが使われるのかについて解説します。
「敬称略」の意味を正しく理解することは、適切な場面で使いこなすための第一歩です。
主な理由は以下の2点です。
- 「敬称略」が持つ基本的な意味
- なぜ議事録で「敬称略」が使われるのか
それぞれ詳しく見ていきましょう。
「敬称略」が持つ基本的な意味
「敬称略(けいしょうりゃく)」とは、文字通り「敬称を省略すること」を意味します。
敬称とは、「様」「殿」「さん」「先生」など、相手への敬意を示すために氏名や役職に付け加える言葉のことです。
議事録や名簿、座席表など、複数の人物名を一覧で記載する際に、これらの敬称をあえて省略することを指します。
これは、日本のビジネス慣習において広く用いられている表現方法の一つです。
ただし、単に敬称を省略するだけではなく、それを行うことへの断りとして「(敬称略)」と明記するのが一般的です。
この表記によって、「本来は敬称を付けるべきところですが、ここでは便宜上省略させていただきます」という意図を読み手に伝えています。
あくまでも「省略させてもらう」というスタンスであり、相手への敬意を欠いているわけではない、という前提で使われる言葉です。
文化庁の指針でも、敬語は「話や文章の相手に対して丁重に述べる」ためのものと定義されています。敬称略は、この敬意を前提とした上での便宜的な措置であることを解説した資料です。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/keigo/keigo_09/pdf/keigo_shouiinkai181002_siryou_2.pdf
なぜ議事録で「敬称略」が使われるのか
議事録で「敬称略」が使われる主な理由は、効率性と可読性の向上、そして中立性を保つためです。
まず、会議の出席者が多い場合、全員の氏名に「様」や「殿」といった敬称を付けると、出席者リストが長くなり、作成に手間がかかります。
また、役職が異なる人々が多数参加する場合、「部長には『様』、課長には…」と敬称の使い分けを考えると非常に複雑になります。
「敬称略」として氏名のみを記載することで、リストがすっきりと見やすくなり、誰が参加したのかを一目で把握しやすくなります。これが可読性の向上です。
さらに、議事録は会議の事実を客観的に記録する公式な文書です。
特定の人物にだけ過剰な敬称を使ったり、敬称の有無に差があったりすると、記録としての中立性や公平性が損なわれる可能性があります。
全員を「敬称略」として平等に扱うことで、特定の個人への忖度(そんたく)や序列を排除し、客観的な記録であることを担保する役割も果たしています。
これらの理由から、特に多くの人が参加する公式な会議の議事録において、「敬称略」は合理的な慣習として定着しています。
議事録のような公的な文書での敬称の扱いは、自治体でも基準が定められています。こちらは東京都中野区の公文書における敬称の取扱い基準を示した資料で、対内・対外文書の区別についても触れられています。 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00001673.html
議事録作成の効率化については、ChatGPTを利用した会議の議事録作成方法を解説したこちらの記事も大変参考になります。 合わせてご覧ください。
議事録での「敬称略」は失礼にあたる?判断基準を解説
議事録で「敬称略」を使うこと自体は、ビジネスマナーとして広く認知されています。しかし、状況や相手によっては「失礼だ」と受け取られてしまう可能性もゼロではありません。
ここでは、議事録で「敬称略」を使う際に失礼にあたらないための判断基準を、具体的なケース別に解説します。
- 「敬称略」が失礼と受け取られやすいケース
- 社内と社外で使い分けるべきか?
- 少人数の会議では使わない方が良い?
これらのポイントを押さえ、状況に応じた適切な対応を心がけましょう。
「敬称略」が失礼と受け取られやすいケース
「敬称略」の使用が失礼と受け取られやすいのは、主に相手への敬意が特に重視される場面や、事前の共通認識が取れていない場合です。
例えば、非常に格上の相手(取引先の社長や役員、重要な顧客など)が少数だけ参加している会議で、いきなり「敬称略」を使用すると、相手は軽んじられたと感じるかもしれません。
また、議事録を配布する相手が「敬称略」の慣習に詳しくない場合、特に社外秘の文書でないにもかかわらず外部の人の目に触れる可能性がある場合も注意が必要です。
さらに、最も基本的なマナーとして、「(敬称略)」の断り書きを入れ忘れると、単に敬称を付け忘れた失礼な文書と見なされてしまいます。
「敬称略」は、あくまで「敬称を省略します」という事前のアナウンスがあって初めて成り立つビジネスマナーです。
この断り書きがない状態での氏名の羅列は、呼び捨てと同じであり、非常に失礼にあたります。
議事録を作成する際は、必ず出席者欄のどこかに「(敬称略)」と明記することを徹底してください。
敬称の使い方一つで相手に不快感を与えかねないことは、実際の調査でも明らかです。こちらは、ビジネスパーソンの5割以上が「言葉遣い・敬語の使い方」で不快な思いをした経験があることを示す調査結果です。 https://jma-news.com/archives/5581
社内と社外で使い分けるべきか?
議事録における「敬称略」の使用は、社内向けか社外向けかによって使い分けるのが賢明です。
社内の会議であれば、日常的に「さん」付けや役職名で呼び合っている関係性がベースにあるため、「敬称略」を使用することへの抵抗感は少ないでしょう。
効率性を重視し、出席者一覧は「(敬称略)」として氏名のみを記載するのが一般的です。
一方、社外の人間が参加する会議の議事録では、慎重な判断が求められます。
特に取引先や顧客が参加している場合、議事録の配布先も社外に及ぶことが多いため、相手の企業文化や考え方によっては「敬称略」を不快に感じる人がいる可能性も考慮しなければなりません。
安全策としては、社外の参加者名には「様」を付け、社内の参加者は「(敬称略)」とするか、全員「様」で統一する方が無難です。
ただし、頻繁にやり取りがあり、お互いの暗黙の了解として「敬称略」が定着している関係性であれば、使用しても問題ないケースもあります。
迷った場合は、社外の参加者には敬称(様)を付ける、と覚えておくと良いでしょう。
特に社外向けのビジネスマナーが企業イメージの構築に直結することは、学術的にも研究されています。こちらは、新入社員研修におけるマナー教育が「企業イメージ」のために機能していることを分析した研究です。 https://scholarworks.uni.edu/context/sac_facpub/article/1000/viewcontent/Speaking_Politely_Kindly_and_Beautifully.pdf
少人数の会議では使わない方が良い?
会議の出席者が少ない場合、例えば3名から5名程度の少人数の場合は、「敬称略」は使わずに、全員に「様」などの敬称を付ける方が丁寧な印象を与えます。
前述の通り、「敬称略」が使われる主な理由の一つは、大人数のリストをすっきりと見やすくするためです。
出席者が数名であれば、全員に「様」を付けてもリストが煩雑になることはありませんし、作成の手間も大きくは変わりません。
むしろ、少人数なのにわざわざ「敬称略」と断って氏名だけを記載すると、冷たい印象や、形式張った印象を与えてしまう可能性があります。
特に、社外の人が1名でも含まれている少人数の会議では、敬意を示すためにも「様」を付けるのがマナーです。
社内のみの会議であっても、参加者が少ない場合は「敬称略」を使わず、「さん」や「様」を付けた方が、円滑なコミュニケーションにつながる場合もあります。
明確な人数の決まりはありませんが、リストの見た目や作成の手間を考えて、「敬称略」を使うメリットがあまりないと感じる人数であれば、敬称を付けるようにしましょう。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
議事録で「敬称略」を使う際の正しいルールとマナー
議事録で「敬称略」を使うと決めた場合、相手に失礼な印象を与えないために守るべきルールやマナーが存在します。
ここでは、議事録作成時に押さえておきたい「敬称略」の正しい使い方を4つのポイントに分けて解説します。
- 原則として「(敬称略)」と明記する
- 出席者の役職はどう記載する?
- 「さん」付けは「敬称略」に含まれる?
- 記載漏れや二重敬語に注意する
これらのルールを守ることで、議事録の信頼性と正確性を高めることができます。
原則として「(敬称略)」と明記する
「敬称略」を使用する際、最も重要なルールは、出席者名のリストのどこかに「(敬称略)」と必ず明記することです。
この一文があることで、「敬称を省略することへの断り」が成立します。
これがないと、単なる「呼び捨て」となり、ビジネスマナー違反と見なされてしまいます。
記載する場所については、出席者リストの最後尾に(敬称略)と小さく記載するのが一般的です。
あるいは、出席者リストの冒頭、例えば「出席者(敬称略):」のように記載する方法もあります。
どちらの場合でも、リスト全体に対して敬称を省略していることが明確に伝わるように記載することが重要です。
また、「敬称略」と記載したにもかかわらず、リスト内の一部の人のみに「様」などの敬称が残っていると、かえって失礼にあたる場合があります。
記載漏れや、逆に特定の人だけを立てているような誤解を招かないよう、表記の統一を徹底する必要があります。
出席者の役職はどう記載する?
「敬称略」を使用する場合、氏名のみを記載するのが基本ですが、役職を併記することも一般的です。
役職は、その人が会議でどのような立場で参加していたかを示す重要な情報であり、敬称とは別のものとして扱われます。
そのため、「敬称略」として「様」や「さん」を省略しつつ、役職を記載することに問題はありません。
記載方法としては、「(役職) 氏名」の順で書くのが通例です。
例:
(出席者一覧:敬称略)
部長 山田 太郎
課長 鈴木 一郎
佐藤 花子
このように、役職がある人は役職名を氏名の前に()書きなどで付け、役職がない人は氏名のみを記載します。
ただし、社外の人が含まれる議事録で役職を記載する場合は注意が必要です。
自社の人間の役職だけを記載し、社外の人の役職を省略すると失礼にあたる可能性があります。
逆に、社外の人の役職を記載する場合は、自社の人間も役職を記載し、表記の仕方を統一するのが望ましいでしょう。
議事録の目的に応じて、役職情報が必要かどうかを判断し、記載する場合は全員の表記を統一するように心がけましょう。
組織内での呼称(役職や氏名)の管理は、時に複雑です。こちらは経団連による、社内での通称使用と公的文書での戸籍姓使用の使い分けに関する調査結果です。議事録での正式な記載を考える上で参考になります。 https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/044_kekka.pdf
「さん」付けは「敬称略」に含まれる?
「さん」は「様」よりもフランクな表現ではありますが、立派な敬称の一つです。
したがって、「敬称略」と記載した場合は、「さん」付けも省略するのが原則です。
「(敬称略)」と断り書きをした上で、出席者リストに「山田さん」「鈴木さん」のように記載するのは、ルールとして矛盾しています。
これは「敬称を省略すると言ったのに、敬称(さん)が付いている」という状態であり、文書としての体裁が整っていません。
社内向けの比較的カジュアルな議事録で、親しみを込めて「さん」付けで統一したい場合もあるかもしれません。
その場合は、「(敬称略)」という表記は使わず、単に出席者全員を「さん」付けで記載する方が自然です。
例:
(出席者)
山田 太郎さん
鈴木 一郎さん
佐藤 花子さん
このように、「敬称略」を使う場合は氏名(と役職)のみを記載し、「さん」付けで統一する場合は「敬称略」の表記を使わない、というように明確に使い分けることが重要です。
記載漏れや二重敬語に注意する
議事録で「敬称略」を使用する際は、表記の揺れやミスが起こらないよう細心の注意が必要です。
最も避けたいのは、記載漏れです。
例えば、「(敬称略)」と記載したにもかかわらず、リストの中で一人だけ「様」が付いている、あるいは一人だけ敬称が抜けている(他の人には付いている)といった状態です。
これは、特定の人物を特別扱いしている、あるいは軽視していると誤解される可能性があり、非常に失礼にあたります。
「敬称略」と決めたら、出席者全員の敬称を漏れなく省略し、統一されているかを必ず確認してください。
また、二重敬語にも注意が必要です。
「敬称略」とは直接関係ありませんが、例えば「山田部長様」のように、役職名(部長)と敬称(様)を重ねてしまうのは誤った日本語表現です。
役職名自体に敬意が含まれているため、役職を記載する場合は「部長 山田太郎様」のように役職を氏名の前に置くか、「山田部長」と記載するのが一般的です。
議事録は公的な記録文書であるため、正確な日本語表現を心がけ、記載ミスや表記の不統一がないよう、提出前に必ず見直しを行いましょう。
敬語や敬称の正しい使用は、単なる丁寧さだけでなく、組織のアイデンティティ構築にも関わります。こちらは、会議における敬語使用が持つ機能について分析した社会言語学の論文です。 https://www.researchgate.net/publication/251586010_Are_honorifics_polite_Use_of_referent_honorifics_in_a_Japanese_Committee_Meeting
【そのまま使える】議事録への「敬称略」の書き方例文
ここまでは、「敬称略」の意味やルールについて解説してきました。
このセクションでは、実際に議事録で「敬称略」をどのように記載すればよいか、そのまま使える具体的な書き方例文を紹介します。
- 出席者欄での基本的な記載例
- 「敬称略」を記載する正しい位置
- 「順不同」もあわせて記載するべき?
これらの例文を参考に、ご自身の議事録作成に役立ててください。
出席者欄での基本的な記載例
議事録の出席者欄で「敬称略」を使う際の、最も一般的で基本的な記載例を紹介します。
通常、出席者は社内と社外(または顧客側と自社)に分けて記載すると、議事録の読み手にとって分かりやすくなります。
【出席者】
株式会社〇〇(A社)
営業部長 山田 太郎
営業担当 鈴木 一郎
弊社(B社)
事業部長 佐藤 花子
マネージャー 田中 実
(敬称略)
この例のように、出席者リストの末尾に「(敬称略)」と記載するのが最もシンプルな方法です。
また、役職を記載することで、誰がどのような立場で会議に参加していたかが明確になります。
社内のみの会議で役職を省略する場合は、以下のように氏名のみを記載します。
【出席者】
佐藤 花子
田中 実
高橋 健太
(敬称略)
このように、議事録のフォーマルさや参加者の属性に応じて、役職の有無を使い分けると良いでしょう。
「敬称略」を記載する正しい位置
「敬称略」を記載する位置に厳格な決まりはありませんが、一般的に推奨される位置が2つあります。
一つは、前のセクションで紹介した「出席者リストの末尾」です。
リスト全体を記載し終えた後、最後に「(敬称略)」と小さく付け加える方法です。これは最も多く見られる形式です。
もう一つは、「出席者欄の冒頭」に記載する方法です。
【出席者】(敬称略)
株式会社〇〇
山田 太郎
鈴木 一郎
弊社 佐藤 花子 田中 実
このように、見出しの直後や、リストのすぐ上に記載することで、読み手は「これから続くリストは敬称が省略されている」と認識した上で読み進めることができます。
どちらの方法でもマナー違反にはなりませんが、社内や部署で議事録のフォーマットが決まっている場合は、それに従うのが一番です。
フォーマットがない場合は、リストの末尾に記載する方法が無難であり、一般的と言えます。
大切なのは、出席者リストの「近く」に記載し、リスト全体に適用されていることが明確に分かるようにすることです。
「順不同」もあわせて記載するべき?
「順不同(じゅんふどう)」とは、リストの並び順に特別な意味(役職順や年功序列など)がないことを示す言葉です。
「敬称略」と「順不同」は、意味が異なるため、必要に応じて併記することがあります。
例えば、多くの人が参加する会議で、役職の上下関係などを考慮せずに名前を羅列した場合、以下のように併記します。
【出席者】(順不同・敬称略)
山田 太郎 鈴木 一郎 佐藤 花子 田中 実 高橋 健太 (以下略)
「敬称略」は敬称を省略することを示し、「順不同」は並び順に意図がないことを示します。
特に社外の人が複数参加している場合、リストの並び順が序列を示していると誤解されるのを避けるために「順不同」が使われることがあります。
ただし、議事録の出席者リストでは、序列を明確にするために、あえて役職順(または組織ごと)に並べるのが一般的です。
例えば、「部長」「課長」「担当」の順に並べる場合、そこには明確な意図があるため「順不同」は使いません。
その場合は、「(敬称略)」のみを記載します。
出席者をランダムに並べた場合や、序列を気にする必要がない(あるいはあえて序列を示したくない)場合にのみ、「順不同」を併記すると覚えておきましょう。
「敬称略」に関するよくある質問
最後に、議事録の「敬称略」に関して、実務で迷いやすいよくある質問にお答えします。
明確なルールがない部分についても、判断の目安となる考え方を解説します。
- 出席者が何人以上なら「敬称略」を使えますか?
- 「敬称略」の使用が不適切な場面はありますか?
これらの疑問を解消し、自信を持って「敬称略」を使いこなせるようになりましょう。
出席者が何人以上なら「敬称略」を使えますか?
「敬称略」を使い始めるべき出席者の人数について、明確なビジネスマナーはありません。
しかし、一般的には5名から10名程度が
一つの目安となるでしょう。
前述の通り、出席者が3名や4名といった少人数の場合、全員に「様」を付けても手間はかからず、リストも見にくくなりません。
この人数で「敬称略」を使うと、かえって形式張った冷たい印象を与える可能性があります。
一方、出席者が10名を超えてくると、全員に敬称を付けるとリストが長くなり、可読性が下がってきます。
このあたりから「敬称略」を使用するメリットが出てくると言えます。
ただし、これはあくまで目安です。
重要なのは、議事録の読みやすさと、参加者への敬意のバランスです。
社外の重要な顧客が1名でも含まれている場合は、たとえ合計10名以上になったとしても、その顧客だけ、あるいは全員に「様」を付けるといった配慮が求められることもあります。
人数の基準を機械的に適用するのではなく、会議の性質や参加者の顔ぶれを見て、柔軟に判断することが大切です。
「敬称略」の使用が不適切な場面はありますか?
「敬称略」は、あくまで複数の名前を一覧にする際の便宜的な措置として使われるものです。
そのため、不特定多数の目に触れる公式な文書や、敬意を最優先すべき場面では使用が不適切とされます。
例えば、以下のような場面では「敬称略」は使いません。
- 招待状や式典の案内状参加者への敬意を最大限に示す必要があるため、一人ひとりに「様」などの正しい敬称を使います。
- 謝罪文やお詫び状相手への謝意や敬意を伝える文章で敬称を省略することは、非常に失礼にあたります。
- 冠婚葬祭に関する文書祝辞や弔辞、芳名帳など、儀礼的な意味合いが強い場面では「敬称略」は用いられません。
- 議事録本文での発言者表記出席者リストで「敬称略」を使っていても、議事録の本文中で「〇〇が発言」のように呼び捨てにするのは不適切です。「〇〇様」「〇〇部長」「〇〇さん」など、適切な敬称を付けて記載するのが一般的です。
議事録は、主に会議の参加者や関係者間で情報を共有するための「業務上の文書」です。
この限定された範囲内で、効率化と可読性のために使われるのが「敬称略」であると理解しておきましょう。
どのような文書でも使えるわけではない、という点に注意が必要です。
敬語や敬称は、文脈を誤ると意図せず失礼にあたる場合があります。こちらは、敬語が戦略的に「非丁寧さ(impoliteness)」のために使われることもあると指摘した研究です。場面に応じた使い分けの重要性がわかります。 https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/li/article/download/37494/40056/100604
あなたは大丈夫?その「マルチタスク」が脳の生産性を破壊しているかもしれない
「仕事を早く終わらせたいから」と、メールをチェックしながら資料を作り、チャットにも即レスする…。そんな「できるビジネスパーソン」を演じていませんか?実は、その習慣があなたの生産性を著しく低下させているかもしれません。スタンフォード大学の研究が、その衝撃的な事実を明らかにしています。しかし、心配はいりません。最新のAI活用術を実践する企業では、この「マルチタスクの呪縛」から解放され、むしろ集中力を高める方法が浸透し始めています。この記事では、「生産性が下がる人」と「集中力を維持する人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なAIテクニックを交えて解説します。
【警告】マルチタスクはあなたの「集中力を奪う」
「同時に進めれば効率的だ」——。もしそう信じているなら、危険なサインです。スタンフォード大学の研究によると、日常的に高度なマルチタスクを行う人は、そうでない人に比べて、タスクを切り替える際の「認知コスト(スイッチング・コスト)」が非常に高く、無関係な情報を遮断する能力が低いことがわかりました。
これは、脳が常に「次は何だっけ?」と混乱し、一つの物事に深く集中することを忘れてしまう状態です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- ミスの増加: 注意が散漫になり、単純な見落としやミスが増える。
- 思考の浅化: 深く考える前に次のタスクに移るため、表面的な仕事しかできなくなる。
- 慢性的な疲労: 脳が常にオーバーヒート状態で、仕事が終わっても疲れが取れない。便利さ(即時対応)を追求するうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「深い集中力」が失われていくのです。
引用元:
スタンフォード大学の研究チームは、複数のデジタルメディアを同時に使用する「ヘビー・メディア・マルチタスカー」の認知制御能力について調査しました。その結果、彼らはタスクの切り替えや無関係な情報のフィルタリングにおいて、著しく低いパフォーマンスを示すことが明らかになりました。(Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. “Cognitive control in media multitaskers.” 2009年)
【実践】AIを「集中力の盾」に変える最新の活用術
では、「集中力を維持する人」はAIをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「タスクを処理する機械」ではなく、「集中を阻害するノイズを処理する秘書」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「アジェンダ設定」パートナーにする
集中力の源泉は「今、何に集中すべきか」を明確にすることです。そこで、AIに今日のタスクを整理させ、優先順位を決めさせます。
魔法のプロンプト例:
「(今日のタスク一覧)があります。私は今日『(最も重要なゴール)』を達成したいです。これらのタスクを緊急度と重要度のマトリクスで分類し、今日私が集中すべき『トップ3のタスク』だけを抜き出して、その理由も説明してください。」
これにより、雑多なタスクに振り回されず、最も重要な仕事に脳のリソースを集中できます。
使い方②:あえて「情報収集」を丸投げする
調べ物を始めると、ついネットサーフィンしてしまうのが人間です。集中力を維持するため、情報収集という「ノイズの多い作業」をAIに任せます。
魔法のプロンプト例:
「(調べたいテーマ)』について、最新の動向を3つのポイントに要約してください。情報源は信頼できる(公的機関や主要メディアなど)ものに限定し、それぞれの要約の後に引用元URLを必ず付けてください。」
AIが一次情報を整理してくれるため、あなたは情報の海に溺れることなく、本質的な「考える」作業に集中できます。
使い方③:コミュニケーションを「非同期」にする
集中力最大の敵は「割り込み」です。チャットやメールの返信作業をAIに任せ、自分の時間を守ります。
魔法のプロンプト例:
「(受信したメールやチャットの要約)に対して、『内容確認しました。〇〇(自分の担当箇所)については明日中に返信します。××(相手の担当箇所)については、先に進めておいてください』という丁寧な返信文案を作成してください。」
即レスの呪縛から解放され、まとまった「集中時間(ディープワーク)」を確保することが可能になります。
まとめ
「議事録の敬称略」のようなビジネスマナーへの配慮はもちろん、多くの企業では議事録作成そのものの非効率性や、定型業務の多さに課題を抱えています。生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どの業務にAIを使えば効果的かわからない」「社内にAIを使いこなせる人材がいない」「情報漏洩が怖くて導入できない」といった理由で、活用に踏み切れない企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、面倒なメール作成や、まさに今回のテーマである議事録の自動作成(要約・文字起こし含む)、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力した情報が外部に漏れる心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務をAI化すればいいのか」といった初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、議事録作成のような日常業務からすぐに効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。