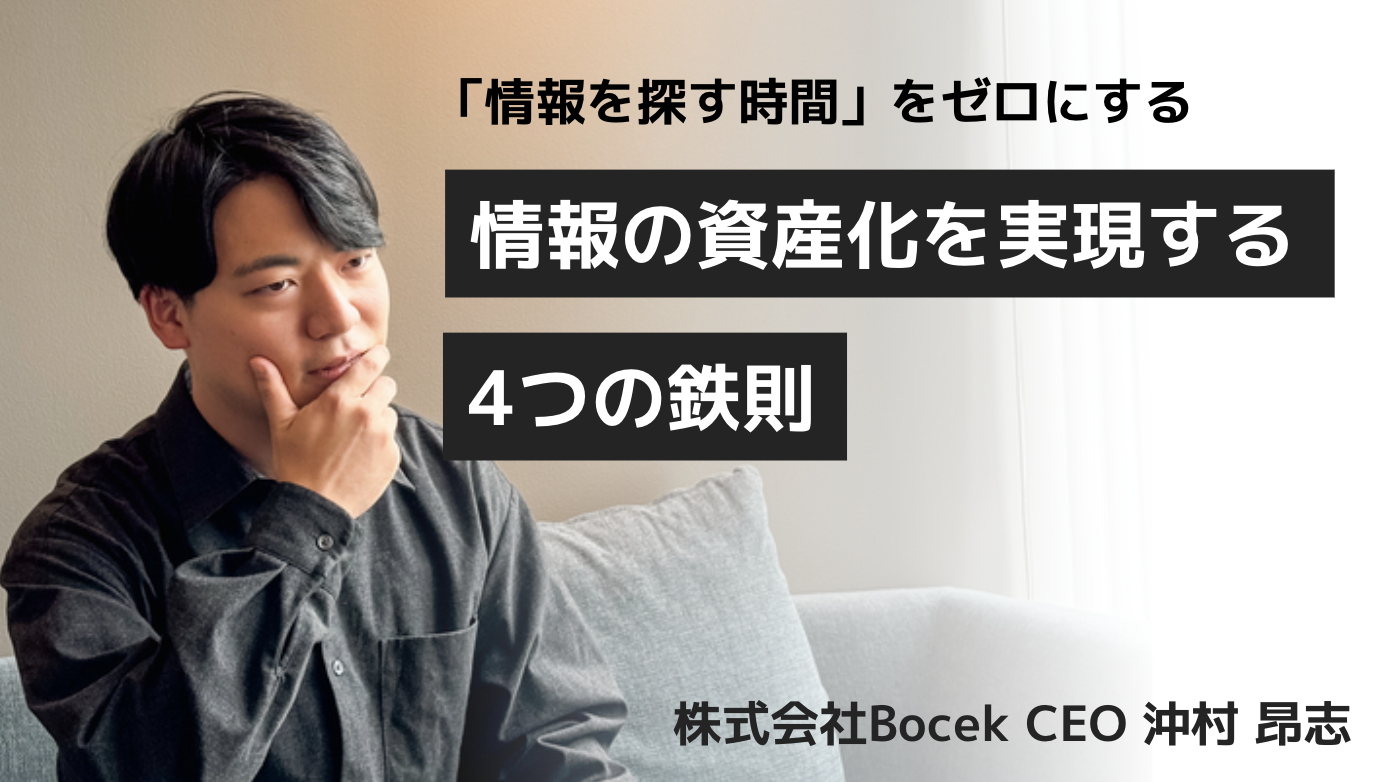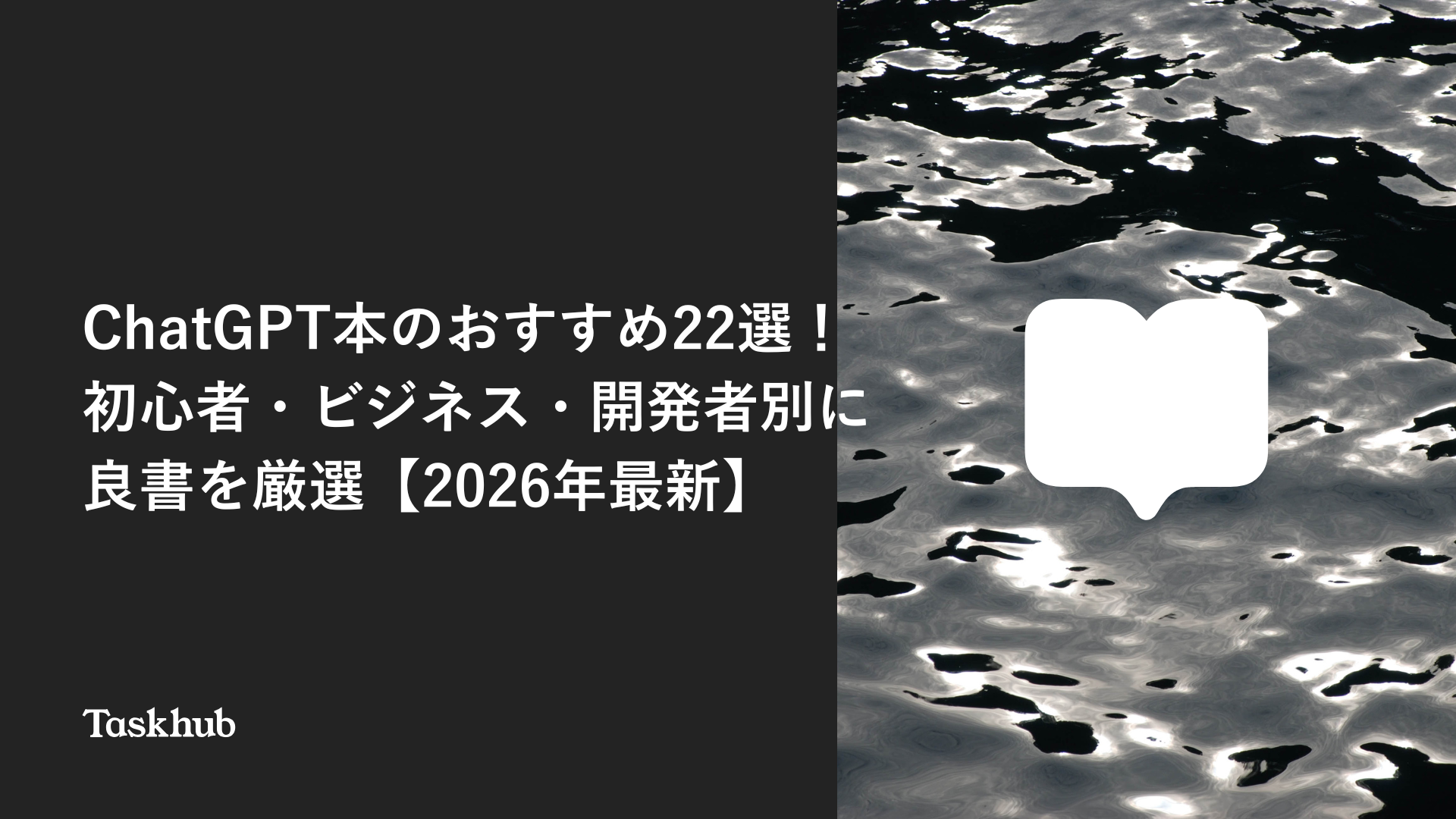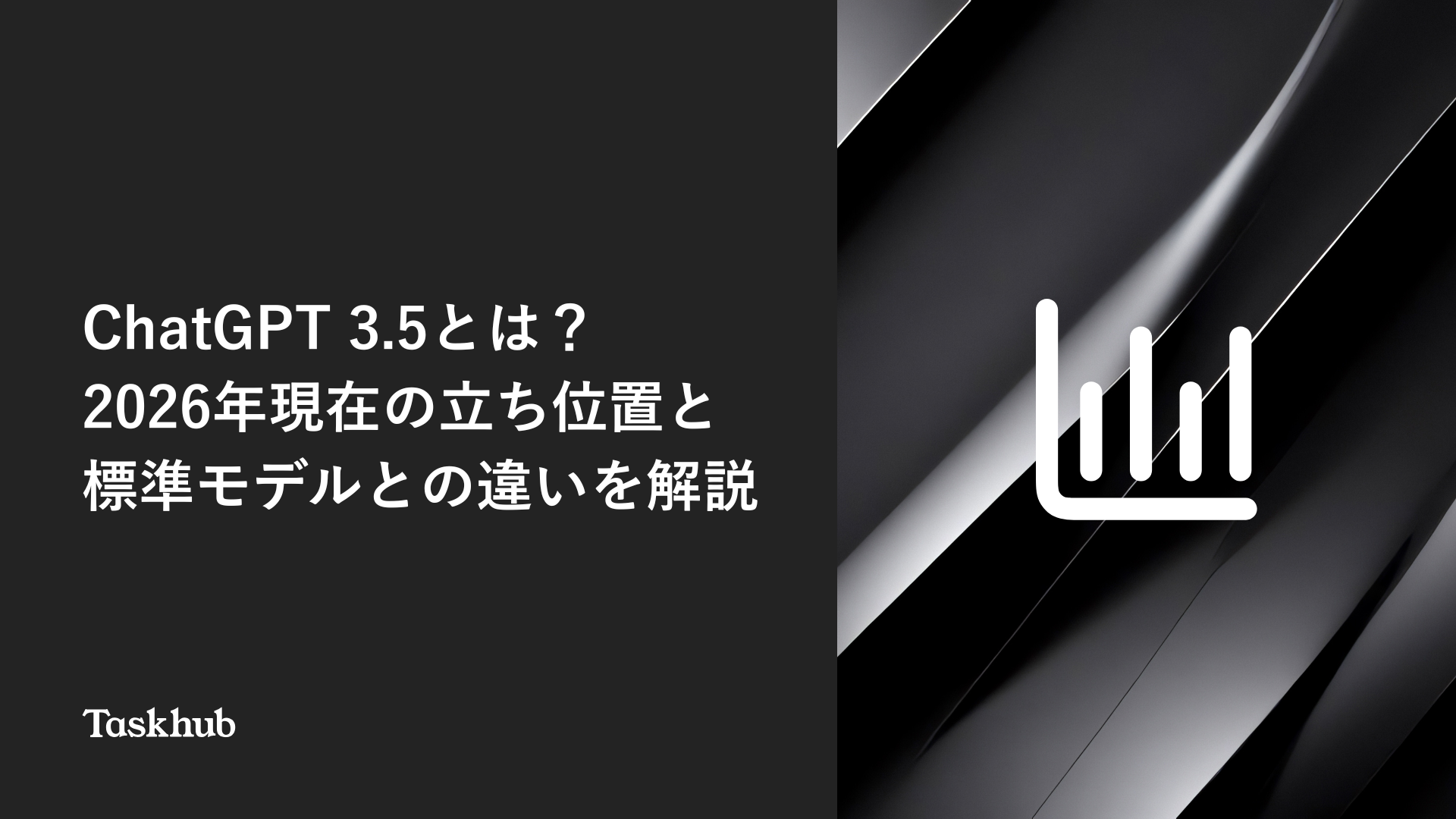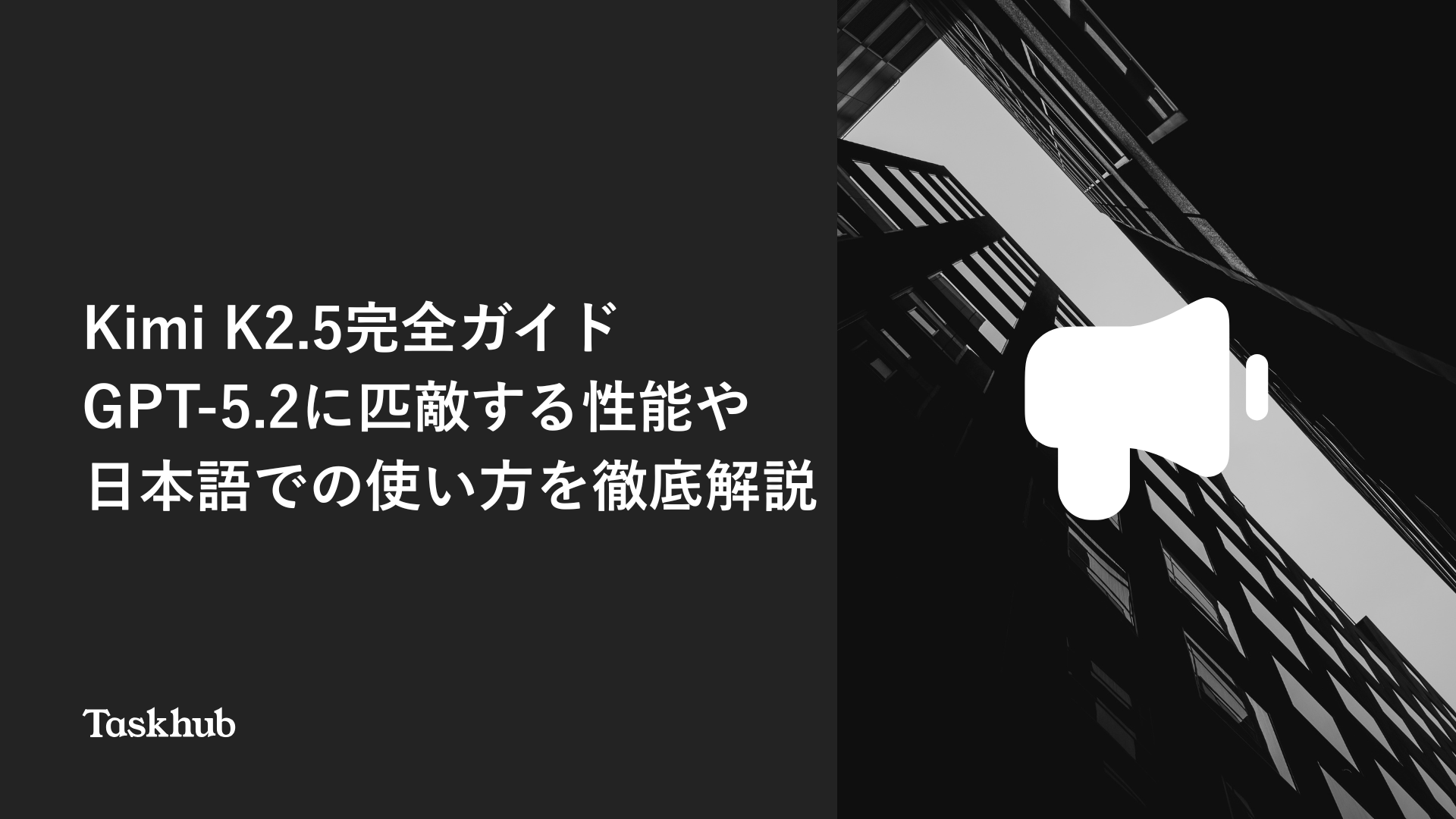皆さんは普段、会社の業務で多くの時間を何に使っているでしょうか。実は、一説には労働時間の3分の1近くが、社内の情報を探すことに費やされていると言われています。例えば、「過去の企画書はどこに保存しただろうか」「先週作成したあのファイルが見つからない」「休暇の申請方法はどうだったか」といった日常的な探し物は、意識しないうちに私たちの貴重な時間を奪っています。この「情報を探す」という行為は、現代のビジネスにおける非常に大きな課題となっているのです。
今回は、この「情報検索」というテーマを深掘りし、なぜ多くの会社で情報探しに時間がかかってしまうのか、そしてその時間をいかにして新しい価値を生み出す「創造する時間」に変えていけるのかを解説します。普段当たり前になっているデータの検索や整理は、実は目に見えないコストになっています。

情報検索と収集に日頃のタスクの20%を費やしている ーー引用:McKinsey & Company
仮に労働時間の20%を情報検索に費やしているとすると、月160時間働く人であれば、実に月32時間もの時間を失っている計算になります。この時間を半分、あるいはゼロに近づけることができれば、その分を本来の業務やイノベーションの創出に充てることができ、企業の成長に大きく貢献するでしょう。情報を探す時間は、機会損失そのものなのです。
なぜ会社のデータは「資産」にならないのか?3つの課題
データが適切に管理されていないと、情報検索の時間が増えるだけでなく、様々な問題を引き起こします。例えば、データが個々の社員に依存する「属人性」が高まり、新入社員の教育や業務の引き継ぎに多大な工数がかかります。また、「必要な資料が見つからないから、また一から作る」という非効率な作業も頻発します。もし社内の情報が整理され、誰でもアクセスできれば、作成する必要のない資料もたくさんあるはずです。まさに「データを制する者は時短を制し、DXを制する」と言っても過言ではありません。では、なぜ多くの企業でデータがうまく資産として活用されないのでしょうか。その原因は、主に以下の3つの課題に集約されます。
- データのサイロ化
多くの企業では、ファイルサーバー、メール、そしてSlack、Notion、Salesforce、Chatworkといった様々なチャットツールやクラウドサービスが部署や目的ごとに乱立しています。その結果、データが各所に散らばってしまう「サイロ化」という状態に陥ります。これでは必要な情報を横断的に検索することができず、一つ一つのツールをしらみつぶしに探すという非効率な作業が必要になってしまいます。 - 低い検索精度
昨今、生成AIが大きな注目を集めていますが、社内データを本当に問題なく検索できるツールはまだ多くありません。従来のファイル名などによるキーワード検索では「完全一致」でなければヒットせず、本当に欲しい情報にたどり着けないことがよくあります。一方で、LLM(大規模言語モデル)を活用したRAG(Retrieval-Augmented Generation)という新しい検索技術も登場していますが、まだ研究段階の側面も強く、誤った情報を生成する「ハルシネーション」のリスクも存在します。このように、情報検索技術自体がまだ発展途上であることも課題の一つです。 - 暗黙知の属人化
データが特定の個人に紐づいてしまう問題も深刻です。経験豊富な社員が退職すると、その人が持っていたノウハウやデータが失われてしまいます。また、個人のパソコンに重要なファイルが保存されていると、そのデータは誰にも共有されず、組織の資産にはなりません。このように、情報が個人に溜まり、人の入れ替わりによって失われ続けるというリスクが常に存在しているのです。
「探す時間」をなくすための4つのステップ
それでは、これらの課題を解決し、社内の情報を誰もが活用できる「資産」に変えていくためには、具体的にどうすればよいのでしょうか。ここでは、そのための具体的な4つのステップをご紹介します。
ステップ1:紙媒体のデジタル化
まず最初のステップは、社内に残っている紙媒体をなくし、すべてをデジタルデータに変換することです。契約書や過去の図面、議事録などが紙のままでは、そもそもAIで検索することはできませんし、一箇所に集約することも困難です。OCR(光学的文字認識)技術などを活用して、紙の書類をどんどんデジタル化していきましょう。その際、単なる画像データとして保存するのではなく、できるだけ検索可能な「文字データ」に変換しておくことが、将来の検索性を高める上で非常に重要になります。例えば、一部のツールでは書類の画像をアップロードするだけで自動的にOCR処理を行い、文字データとして扱える機能も提供されています。
ステップ2:全データの集約と構造化
次に、デジタル化した全てのデータを一箇所に集約し、一元管理します。多くの企業ではGoogle ドライブやSharePoint、Boxといったクラウドストレージサービスが利用されていますが、自社のセキュリティポリシーに合ったツールを選定し、データを安全に管理することが大切です。
そして、ただデータを集めるだけでなく、「構造化」して格納することが極めて重要になります。kintoneのようなノーコードツールなどを活用し、「どの情報を」「どの項目に」格納するのかというデータ設計を事前に行いましょう。例えば、過去の商談情報を蓄積する際に、会社名の表記が「(株)A社」と「A社株式会社」で揺れていたり、そもそも会社名が入力されていなかったりすると、後から正確に検索することができません。
このような事態を避けるため、会社としてデータ入力のガイドラインを策定し、「会社名は必須項目とする」「表記は正式名称に統一する」といったルールを定める必要があります。将来的にどのような検索をするかを想定した上で、データを整備していくことが求められます。昨今のRAG(生成AIの検索技術)で回答精度が上がらない原因の多くは、元となるデータが構造化されていなかったり、画像データのままでAIが読み込めなかったりすることに起因します。
| 項目 | 悪い例(非構造化) | 良い例(構造化) |
|---|---|---|
| 会社名 | (株)〇〇、〇〇株式会社、〇〇、未入力 | 株式会社〇〇(表記統一・必須入力) |
| データ形式 | 画像、PDF(画像ベース) | テキスト、構造化データ(JSON, CSVなど) |
| 入力ルール | 各自の判断に任せる | 会社全体で統一されたガイドラインが存在する |
ステップ3:検索のためのガイドライン作成
データが完璧に整備されても、社員がその使い方を知らなければ宝の持ち腐れです。ありがちなのが、システムは導入したものの、社員教育が追いつかず、結局誰も使わずに形骸化してしまうケースです。これは生成AIの導入でもよく見られる失敗例です。
「この情報を探すには、このデータベースでこう検索すれば見つかる」ということが、全ての社員にわかるようなガイドラインやマニュアルを作成し、周知徹底することが不可欠です。DXを推進する際には、ツールの導入とセットで、ユーザー教育の計画を立てることが成功の鍵となります。
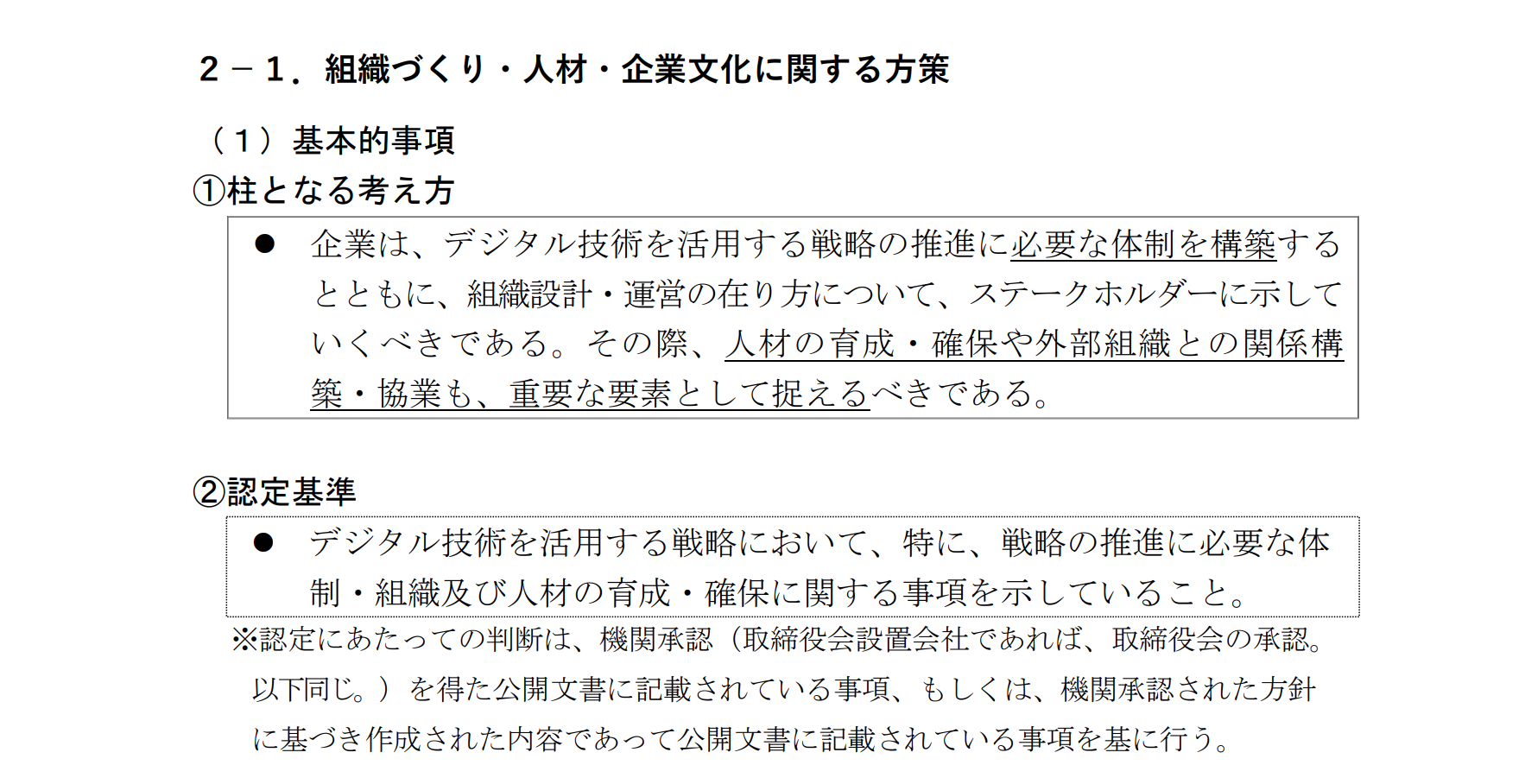
経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」を見てみても、人材育成は重要要素として推奨されている項目です。 ー引用:経済産業省
ステップ4:AIによる検索精度の飛躍的向上
ここまでのステップが完了し、データが整理・集約され、誰もが使い方を理解できる状態になって初めて、AIの力を最大限に活用する準備が整います。近年、整備された社内データと連携し、高度なAI検索を実現するサービスが登場しています。
例えば、クラウドストレージのBoxには「Box AI」が搭載されています。また、Google製の「NotebookLM」は、ファイルをアップロードするだけで、その内容に関する質問にAIが回答してくれる非常にシンプルなツールです。このように、ファイルを起点として完全一致検索や意味の近さで検索するベクトル検索を組み合わせ、精度の高い回答を生成する仕組みが一般化しつつあります。自社の外部連携の要件やセキュリティポリシーを踏まえ、どのようなツールが最適かしっかりと見定めていく必要があります。
成功に導くプロジェクト推進の3つの注意点
情報検索の改革プロジェクトを成功させるためには、進め方にもいくつかのポイントがあります。
- 情報の棚卸しとスモールスタート
まず、そもそもAIに何を学習させるべきか、という情報の棚卸しが重要です。ナレッジとして特におすすめなのは、過去の受注情報や見積書、商談情報といった営業関連データ、契約書や重要事項説明書といった法務関連の書類、そしてコールセンターに蓄積されたQ&Aなどです。生成AIは、キーワードが完全に一致しなくても、意味が近ければ情報を探し出せる点が強みです。プロジェクトを始める際は、最初から全社導入を目指すのではなく、まずは特定の部署でPoC(概念実証)を行い、効果を検証してから段階的に展開していくスモールスタートが堅実です。 - 現場の声を聞くアジャイルな開発
DX推進部や情報システム部が主導するプロジェクトでよくある失敗が、現場のニーズを無視して「作りたいもの」を作ってしまうことです。プロトタイプが完成したらすぐに現場の社員に使ってもらい、その意見を反映して改良を重ねていく、アジャイル開発のような進め方が求められます。「1年かけて作ったシステムが、いざリリースしたら全く使われなかった」という悲劇を避けるためにも、常に現場の声に耳を傾けることが大切です。 - 目的を明確にしたツール選定
AIツールは多種多様です。単に流行っているからという理由で導入するのではなく、「どの部署の」「どの課題を解決したいのか」という目的を明確にし、自社のセキュリティ要件や既存システムとの連携性を考慮して、最適なツールを慎重に選定する必要があります。
検索体験は「探す」から「進める」へ。
将来的には、AIによる情報検索はさらに進化し、「探す」という行為から、次のアクションを「進める」ことへとパラダイムシフトが起こります。これまでは検索窓にキーワードを打ち込み、表示された結果一覧から目的の情報を探していました。しかし生成AI時代には、まるで優秀なアシスタントがいるかのように、その使い方が一変します。
AIアシスタントに「昨日の予定は何だった?」と自然な言葉で話しかけると、「承知しました。昨日のGoogleカレンダーの予定はこちらです」と即座に情報を提示してくれます。まるでドラえもんのように、あらゆる社内情報を学習したAIが、あなた専用のパーソナルアシスタントとして機能する時代がすぐそこまで来ています。
さらに、AIはただ情報を回答するだけでなく、その先の業務まで実行します。「昨日の予定で連絡が漏れている人に、リマインドのメールを送って」と指示すれば、AIが該当者を特定し、メールを作成・送信するといった、情報検索からアクションの創出までをシームレスに繋ぐことが当たり前になるでしょう。様々な外部サービスと連携し、チャット形式で命令するだけでタスクが完了する、そんな世界が実現されようとしています。
今から始めるデータ整理が未来の競争力を創る
もしあなたの会社で情報がバラバラになってしまっているのなら、今すぐにでもデータの整理と構造化に着手することをお勧めします。整理されないデータは、時間が経つほどに積み重なり、企業の成長を妨げる「負債」となっていくからです。その負債は、探し物という形で社員一人ひとりの時間を奪い続けます。
逆に、データが整理されていればいるほど属人性は減り、社員一人ひとりの能力を最大化させ、新たな時間を創出することができます。これから日本社会は人口減少の時代を迎えますが、AIを使いこなすことで生産性の課題を補い、人間がより創造的な仕事に集中できる時代が訪れます。その未来を実現するためにも、まずは社内の情報という資産を見直し、整理することから始めてみてはいかがでしょうか。