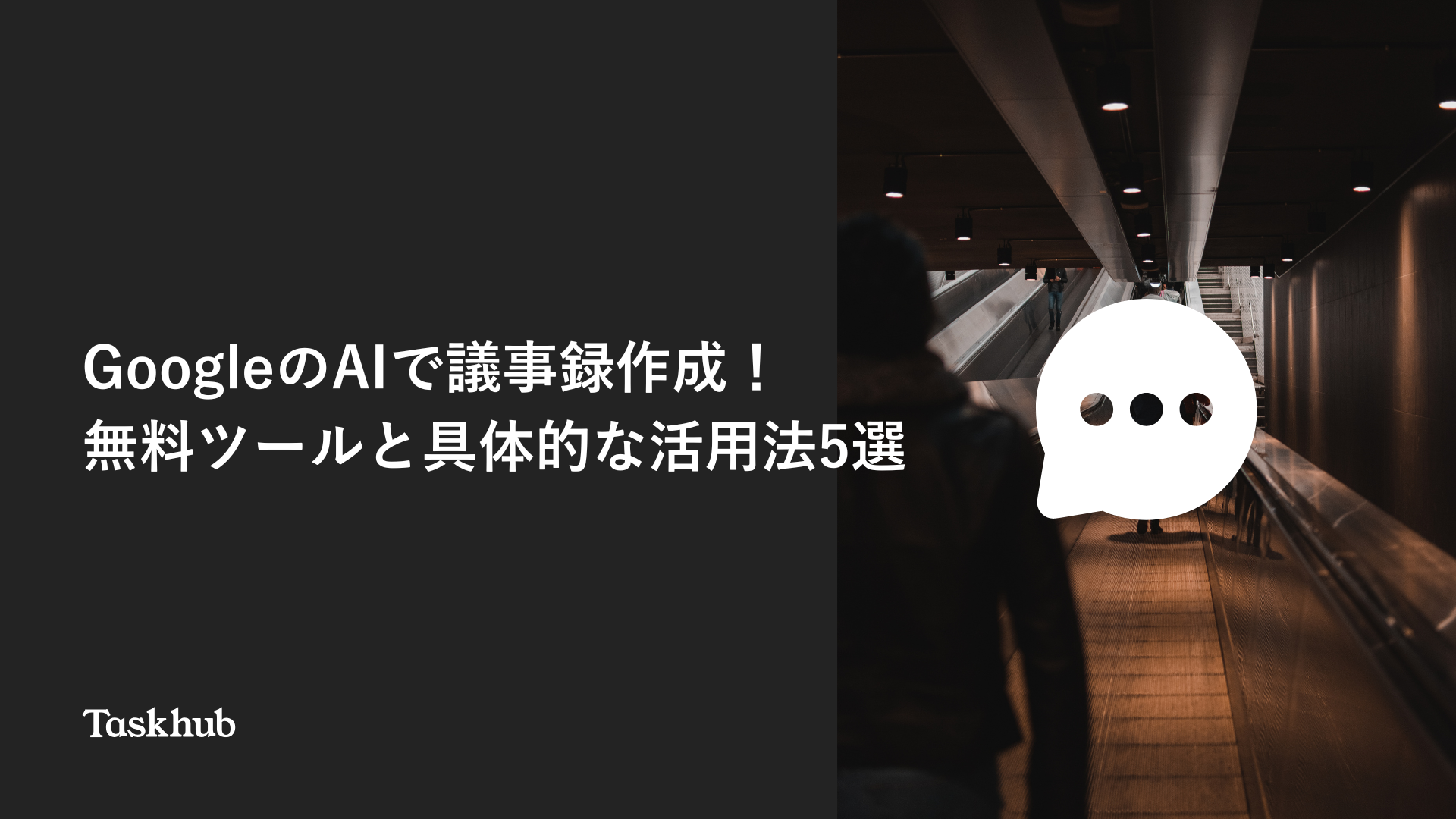「Google Meetの議事録、AIで自動作成できないかな?」
「Googleドキュメントの音声入力を使ってみたけど、精度が低くて実用的じゃない…。」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
Googleが提供するAIや各種ツールを活用することで、これまで時間のかかっていた議事録作成の工数を劇的に削減できます。
本記事では、GoogleのAIを活用した議事録作成の具体的な方法5選、精度の低い文字起こしテキストをGemini(AI)で高品質な議事録に仕上げるプロンプト例、そして活用時の注意点について解説しました。
Google Workspaceの活用を推進する企業が、実際の業務で使っているテクニックのみをご紹介します。
きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
なぜGoogleのAIで議事録作成が注目されるのか?3つの理由
Googleが提供するAIやツールを活用した議事録作成が、なぜ今これほど注目を集めているのでしょうか。
主に以下の3つの理由が挙げられます。
- 議事録作成の工数を大幅に削減できる
- 情報共有がスピードアップし、質も向上する
- 検索しやすいナレッジとして蓄積できる
これらのメリットは、日常的にGoogleのツール(Gmail, Googleドライブ, Google Meetなど)を使っている企業ほど大きくなります。
Google Workspaceの導入がもたらす経済的インパクトについて、Forrester Consultingが分析したレポート(336%のROIなど)です。 合わせてご覧ください。 https://tei.forrester.com/go/google/workspace/?lang=en-us
それでは、1つずつ順に解説します。
議事録作成の工数を大幅に削減できる
会議の議事録作成は、録音データの聞き直しや文字起こし、要点の整理など、非常に時間と手間がかかる作業です。
特に重要な会議ほど、発言のニュアンスや決定事項を正確に記録する必要があり、担当者の負担は大きくなります。
GoogleのAIを活用すれば、会議中の音声をリアルタイムまたは録音データから自動でテキスト化できます。
さらに、生成されたテキストデータをAI(Gemini)に読み込ませることで、要約、決定事項の抽出、ToDoリストの作成までを自動化することが可能です。
従来、数時間かかっていた作業が数分で完了するようになり、本来集中すべきコア業務により多くの時間を割けるようになります。
Google WorkspaceのパートナーであるSADAが報告した、Gemini導入により従業員の96%が時間節約を実感したというクライアント事例です。 合わせてご覧ください。 https://sada.com/blog/google-workspace-ai-5-ways-gemini-transforms-workplace-productivity/
情報共有がスピードアップし、質も向上する
従来の議事録作成では、会議終了後、担当者が時間をかけて作成し、上長レビューを経てから共有されるため、参加者や関係者へのフィードバックに数日のタイムラグが発生することが一般的でした。
Google Meetの文字起こし機能やGeminiの要約機能を活用すれば、会議終了直後、あるいは会議中であっても、議事録のドラフト(草稿)を即座に共有できます。
Geminiを活用した議事録作成以外にも、明日から使える活用事例30選とプロンプト集をまとめた記事はこちらです。 合わせてご覧ください。
これにより、会議の決定事項やネクストアクションが迅速に関係者へ伝達され、プロジェクトの進行スピードが格段に向上します。
また、AIが客観的にテキスト化・要約するため、作成者による解釈の違いや聞き逃しによる情報の偏り(バイアス)を防ぎ、議事録の質そのものを高める効果も期待できます。
検索しやすいナレッジとして蓄積できる
作成された議事録データは、GoogleドキュメントやGoogleドライブ上にテキストデータとして保存されます。
これにより、Googleの強力な検索機能を使って、過去の議事録を瞬時に検索・参照できるようになります。
「あのプロジェクトの決定経緯は、いつの会議だっけ?」
「半年前に議論したあの件、どういう結論になった?」
といった場合でも、関連キーワードで検索するだけで、必要な情報にすぐにアクセスできます。
議事録が単なる記録(アーカイブ)ではなく、組織全体で活用できる「検索可能なナレッジベース」として機能し始めるのです。
これは、組織の生産性向上やノウハウの継承において、非常に大きな資産となります。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
【方法①】Googleドキュメントの音声入力で文字起こしする手順
最も手軽に試せるのが、Googleドキュメントの標準機能である「音声入力」です。
この機能は無料で利用でき、マイクからの音声をリアルタイムでテキスト化します。
ここでは、基本的な使い方と、PC内部の音声(録音データなど)を文字起こしする応用テクニックを紹介します。
Googleドキュメント「音声入力」機能の基本的な使い方
この方法は、自分のマイクに向かって話した内容を直接テキスト化する場合や、小規模な対面ミーティングの音声をPCのマイクで拾って文字起こしする場合に有効です。
手順は非常にシンプルです。
まず、Googleドキュメントで新しいドキュメントを開きます。
上部のメニューバーから「ツール」をクリックし、ドロップダウンメニューから「音声入力」を選択します。
画面の左側にマイクのアイコンが表示されるので、これをクリックすると音声認識が開始されます。
マイクが赤くなったら、PCのマイクに向かって話しかけてください。
話した内容がリアルタイムでドキュメントに入力されていきます。
句読点(「、」や「。」)や改行も、「てん」や「まる」、「あたらしいぎょう」と発声することで入力できます。
ただし、認識精度はマイクの品質や周囲のノイズ、滑舌に大きく左右されるため、クリアな音声入力が求められます。
終了する場合は、再度マイクのアイコンをクリックします。
PCの音声を文字起こしする設定方法 (ステレオミキサー活用)
すでに録音されているICレコーダーの音声データや、Web会議の録画ファイルなど、PC内部で再生される音声を文字起こししたい場合もあるでしょう。
その場合、PCのマイクではなく、PCの内部音声をGoogleドキュメントに認識させる設定が必要です。
Windowsの場合、「ステレオミキサー」という機能を使います。
まず、タスクバーの音量アイコンを右クリックし「サウンド」設定を開きます。
「録音」タブを選択し、何もないところを右クリックして「無効なデバイスの表示」にチェックを入れます。
「ステレオミキサー」が表示されたら、それを右クリックして「有効」にし、さらに右クリックで「既定のデバイスとして設定」します。
この状態で、Googleドキュメントの音声入力をオンにし、PC上で音声データを再生すると、その音声が文字起こしされます。
ただし、この設定がうまくいかないPCも多く、環境によっては別途仮想オーディオデバイス(VB-Audio Virtual Cableなど)のインストールが必要になる場合があります。
(補足) 画像やPDFファイルから文字起こしする方法
音声ではありませんが、Googleは画像やPDF内のテキストを抽出する機能(OCR)も提供しています。
これは議事録そのものではなく、会議で配布された紙資料やホワイトボードの写真をテキスト化する際に役立ちます。
まず、テキストを抽出したい画像(JPEG, PNGなど)やPDFファイルをGoogleドライブにアップロードします。
次に、アップロードしたファイルを右クリックし、「アプリで開く」から「Googleドキュメント」を選択します。
そうすると、画像やPDFの内容がGoogleドキュメントで開かれ、元の画像の下に、AIによって抽出されたテキストが表示されます。
手書きの文字や画質が低い画像の場合、認識精度は低下しますが、印刷された資料であれば高い精度でテキスト化が可能です。
これにより、紙の資料をわざわざ手入力する手間を省くことができます。
【方法②】Google Meetの機能で議事録を自動作成する手順
オンライン会議(Web会議)が主流の場合、Google Meetの標準機能を使うのが最も効率的です。
特定のプランでは、会議中の会話を自動で文字起こしし、議事録として保存する機能が提供されています。
ここでは、その機能と使い方について解説します。
Google Meet標準の「文字起こし機能」とは?
Google Meetの「文字起こし機能」は、会議中のすべての発言をリアルタイムでテキスト化し、会議終了後にGoogleドキュメントファイルとして自動で保存する機能です。
単なる字幕(キャプション)表示とは異なり、議事録として後から編集・共有できる形で出力されるのが最大の特徴です。
この機能は、Google Workspaceの一部の有料プラン(Gemini機能が搭載されたBusinessエディションやEnterpriseエディションなど)で利用可能です。
無料版のGoogleアカウントでは、リアルタイムの「字幕」機能は使えますが、議事録としてドキュメントに保存する「文字起こし」機能は利用できません。(2025年11月現在)
以前は英語のみの対応でしたが、現在は日本語にも正式対応しており、実用性が大幅に向上しています。
Google Meetの文字起こし機能が対応している言語(日本語を含む)や、データの保存場所に関する公式ヘルプドキュメントです。 合わせてご覧ください。 https://support.google.com/meet/answer/12849897?hl=ja
文字起こし機能の使い方と設定
この機能は、会議の主催者または共同主催者が開始できます。
会議中、画面下部のアクティビティアイコン(▲■●のマーク)をクリックします。
メニューから「文字起こし」を選択します。
「文字起こしの開始」というウィンドウが表示されるので、文字起こしの言語が「日本語」になっていることを確認します。(もし他言語になっていれば変更します)
「文字起こしを開始」ボタンをクリックすると、画面右側に文字起こしパネルが表示され、リアルタイムで会話がテキスト化されていきます。
参加者全員に「文字起こしが開始されました」という通知が表示されるため、必ず事前に参加者の同意を得てから開始するようにしてください。
文字起こしを終了したい場合は、再度アクティビティから「文字起こしを停止」を選択します。
文字起こしデータの保存場所と形式
会議が終了すると、文字起こしされた内容は自動的にGoogleドキュメントとして保存されます。
保存場所は、会議の主催者のGoogleドライブ内にある「Meetの録画」フォルダ(または「Meet Recordings」)です。
録画機能を使った場合と同じ場所に保存されます。
ファイル名は「[会議名] ([日付]) – 文字起こし」といった形式になります。
このドキュメントには、発言者と発言時刻、発言内容が時系列で記録されています。
会議終了後、数分〜数十分程度でドライブに生成されるため、すぐに議事録のドラフトとして共有、編集、コメントの追加が可能です。
これにより、議事録作成のリードタイムがほぼゼロになります。
(補足) Google Meetの議事録作成を効率化する拡張機能
Google Meetの標準機能(有料プラン)以外にも、議事録作成をサポートするサードパーティ製のChrome拡張機能が存在します。
無料版のGoogle Meetを利用している場合や、標準機能にはない追加機能が欲しい場合に検討の価値があります。
例えば、「こえもじ」のような拡張機能は、無料版のGoogle Meetでもリアルタイムの文字起こしを行い、テキストファイルとして保存することができます。
また、海外製の拡張機能の中には、文字起こししたテキストをAI(ChatGPTなど)に連携させ、自動で要約やToDoリストを生成する高機能なものもあります。
ただし、これらの拡張機能はGoogleが公式に提供しているものではないため、セキュリティ面でのリスク(会話データが外部サーバーに送信される可能性など)を考慮する必要があります。
企業のルールを確認し、機密情報を扱わない会議などで、自己責任の範囲で利用を検討しましょう。
【方法③】Google Pixelのレコーダー機能で文字起こしする手順
GoogleのAI技術は、PCだけでなくスマートフォン、特にGoogle Pixelシリーズにも搭載されています。
Pixelスマートフォンに標準搭載されている「レコーダー」アプリは、非常に高精度な文字起こし機能で知られています。
対面のインタビューやオフラインの会議を録音する際に絶大な効果を発揮します。
Pixel「レコーダー」アプリの強力な文字起こし機能
Google Pixelの「レコーダー」アプリの最大の特徴は、デバイス上で(オフラインでも)高精度なリアルタイム文字起こしができる点です。
録音を開始すると同時に、話した内容が画面上にテキストとして表示されていきます。
このAI処理は、Googleの強力なAIチップ(Google Tensor)によってデバイス内で完結するため、インターネット接続が不安定な場所でも問題なく利用できます。
また、サーバーに音声データをアップロードしないため、機密性の高い会話を録音する際もセキュリティ面で安心です。
録音したデータは、音声とテキストが完全に同期しており、テキスト上の特定の単語をタップすると、その部分の音声を即座に再生できます。
「あの部分、なんて言ってたかな?」と録音を聞き返す作業が非常に効率的になります。
Google Pixelのレコーダーアプリが、ネットワーク接続なしで高精度な文字起こしを実現する「オンデバイス機械学習」の仕組みを解説したGoogle Researchの技術ブログです。 合わせてご覧ください。 https://research.google/blog/the-on-device-machine-learning-behind-recorder/
リアルタイム文字起こしと話者分離機能の使い方
使い方はシンプルで、「レコーダー」アプリを開いて録音ボタンを押すだけです。
録音が開始されると、自動的に文字起こしがスタートします。
言語は自動で検出されますが、日本語の録音であれば高精度でテキスト化されます。
さらに、Pixel 6以降のモデルでは「話者分離(スピーカー ラベル)」機能が搭載されています。
これは、AIが複数の声を聞き分け、「話し手1」「話し手2」のように、誰の発言かを自動でラベリングする機能です。
録音後に「話し手1」を「Aさん」、「話し手2」を「Bさん」のように編集することも可能です。
ただし、非常に残念な点として、2025年11月現在、この強力な「話者分離」機能は英語のみの対応となっており、日本語の会話では利用できません。
日本語の文字起こし自体は高精度に行われますが、誰が話したかまでは分離されないため、議事録作成時にはこの点を考慮する必要があります。
今後のアップデートによる日本語対応が強く期待されます。
【方法④】Gemini (AI) で議事録を要約・清書する手順
方法①~③で作成した文字起こしデータは、いわば「素材」です。
会議の発言が時系列で並んでいるだけで、「えー」「あのー」といった不要な言葉も含まれており、そのままでは議事録として使えません。
ここで活躍するのが、Googleの対話型AI「Gemini」です。
Geminiモデルが、会議の要約に関するベンチマーク(QMSum)でどの程度の性能スコアを達成したかを示す技術論文です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2405.01121
Geminiを使って、冗長なテキストデータを「読める議事録」に清書・要約する方法を紹介します。
文字起こししたテキスト(音声ファイル)を準備する
まず、GoogleドキュメントやMeetの機能、Pixelのレコーダーなどで作成した文字起こしのテキストデータ(.txt, .docxなど)を準備します。
あるいは、Googleドキュメントにエクスポートしたテキストを丸ごとコピーします。
GeminiのWebインターフェース(旧Bard)には、一度に入力できる文字数に制限があります。
数時間にわたる長文の議事録の場合、一度にすべてを処理させようとするとエラーになるか、処理が途中で打ち切られる可能性があります。
その場合は、議事録のテキストを「議題ごと」や「30分ごと」など、意味のあるかたまりで分割し、複数回に分けてGeminiに処理させるのが現実的です。
あるいは、Google Workspace向けのGemini機能(旧Duet AI)が利用可能なプランを契約している場合は、ドキュメント内で直接、長文の要約指示が可能です。
Geminiに議事録の要約を指示するプロンプト例
準備した文字起こしテキストをGeminiのチャット画面に貼り付け、その上で「何をしてほしいか」を指示するプロンプト(指示文)を入力します。
AIへの指示(プロンプト)の基本的な構造や、そのまま使える日本語のプロンプト例については、こちらの記事で詳しく紹介しています。 合わせてご覧ください。
最も基本的なプロンプトは「要約」です。
しかし、単に「要約して」と指示するだけでは、どのようなアウトプットが欲しいのかがAIに伝わりません。
以下のように、目的と形式を具体的に指定することが重要です。
以下の会議の文字起こしテキストを要約してください。
目的:
会議の全体像を3分で把握するため。
出力形式:
重要なトピックを5つの箇条書きでまとめる。
制約:
各項目は100文字以内。
#文字起こしテキスト:
[ここにGoogleドキュメントなどからコピーしたテキストを貼り付ける]
このように指示することで、Geminiは冗長な会話の中から重要なポイントを抽出し、指定された形式で簡潔にまとめてくれます。
Geminiに決定事項やToDoを抽出させるプロンプト例
議事録の最も重要な役割は、「何が決まったか(決定事項)」と「誰がいつまでに何をするか(ToDo)」を明確にすることです。
Geminiは、こうした特定の情報をテキストから抜き出すタスクも得意です。
要約とは別に、以下のようなプロンプトを追加で実行すると、実用的な議事録が完成します。
以下の会議の文字起こしテキストから、次の3つの項目を抽出してください。
1. 決定事項:
会議で正式に決定したこと。
2. 保留・確認事項:
今回決めきれず、次回以降に持ち越したことや、確認が必要なこと。
3. ToDo(ネクストアクション):
「誰が」「何を」「いつまでに」行う必要があるか。担当者名が不明な場合は「担当者未定」と記載する。
出力形式:
上記1〜3の項目立てで、それぞれ箇条書きで出力する。
#文字起こしテキスト:
[ここにテキストを貼り付ける]
このプロンプトにより、単なる要約ではなく、会議の成果と次の行動が明確になった実用的な議事録が生成されます。
出力内容の確認と編集のポイント
Gemini(AI)は非常に優秀ですが、万能ではありません。
特に、数値(売上、予算、日付)や固有名詞(人名、会社名、製品名)を誤って認識したり、文脈を完全に取り違えたりする可能性がゼロではありません。
AIが生成した要約やToDoリストは、必ず「ドラフト(草稿)」として扱い、人間の目で最終確認(ファクトチェック)を行う必要があります。
特に「誰がやるか(担当者)」や「いつまでか(期限)」、「いくらか(金額)」といった重要な情報は、元の文字起こしテキストや録音データと照らし合わせて、間違いがないかを入念にチェックしてください。
AIの出力を鵜呑みにせず、あくまで「面倒な作業を肩代わりしてくれるアシスタント」と捉え、最後の仕上げは人間が行うという意識が重要です。
【方法⑤】GoogleのAIで議事録アプリを自作する方法 (応用編)
これまでは既存のツールを活用する方法でしたが、より高度な使い方として、GoogleのAI技術(Gemini API)を利用して、自社専用の議事録作成アプリを開発することも可能です。
これは主にエンジニアや開発者向けの応用編となります。
なぜ自作するのか?(既製アプリとの違い)
市販のAI議事録作成ツールは多数存在しますが、自社開発には以下のようなメリットがあります。
第一に、セキュリティの担保です。
Vertex AIなど、Google Cloudのエンタープライズ向けサービスを利用すれば、入力した音声データやテキストデータがAIの学習に使用されることを防ぎ(オプトアウト)、機密情報を安全に取り扱うことが可能です。
第二に、自社の業務フローに合わせた徹底的なカスタマイズが可能です。
例えば、自社内の専門用語や業界用語をAIに事前学習させたり、特定の議事録フォーマット(例えば、必ず「課題」「対策」「決定事項」の3点で出力する)に固定したり、社内のプロジェクト管理ツール(Asana, Trelloなど)と連携して、抽出したToDoを自動でタスク登録したり、といった独自の連携が実現できます。
Gemini API (Vertex AI) を使った要約システムの概要
自作する場合、Google Cloudが提供する「Vertex AI」プラットフォーム上で、最新のAIモデルである「Gemini API」を利用するのが一般的です。
大まかな流れは以下のようになります。
- 音声データのテキスト化: Googleの「Speech-to-Text API」を利用して、会議の録音データ(mp3, wavなど)を高精度なテキストデータに変換します。
- テキストデータの処理: 変換された長文のテキストデータを、Gemini APIが処理できる適切な長さ(チャンク)に分割します。
- Gemini APIによる処理: 分割された各テキストチャンクをGemini API(
gemini-1.5-proなど)に送信し、要約、ToDo抽出、トピック分類などの指示(プロンプト)を与えて実行させます。 - 出力結果の統合: 各チャンクの処理結果を統合し、一つの議事録として整形します。
この仕組みを構築することで、録音ファイルをアップロードするだけで、指定したフォーマットの議事録が自動生成される社内システムを作ることができます。
(参考) Streamlitを使った簡単なWebアプリ開発手順
上記のシステムを、プログラマーが手軽にWebアプリケーションとして構築するためのツールとして「Streamlit」がよく使われます。
StreamlitはPythonのライブラリで、数行のコードでデータの可視化やAIモデルを操作するためのWebインターフェースを簡単に作成できます。
例えば、「①録音ファイルをアップロードするボタン」と「②議事録フォーマット(要約のみ、ToDo抽出、など)を選択するドロップダウン」をStreamlitで作成します。
ファイルがアップロードされたら、バックエンドで上記で解説したSpeech-to-Text APIとGemini APIが実行され、処理結果(生成された議事録)がWeb画面に表示される、といったアプリケーションが比較的容易に開発できます。
これにより、エンジニアでない一般社員でも、ブラウザ上から簡単に高機能なAI議事録作成システムを利用できるようになります。
Google AIの議事録作成の精度を上げる5つのコツ
GoogleのAIは高精度ですが、使い方によっては精度が大きく低下します。
特に文字起こしや要約の質を高めるためには、AIに「分かりやすい」インプットを提供することが不可欠です。
ここでは、議事録作成の精度を格段に上げるための5つの具体的なコツを紹介します。
1. ノイズの少ないクリアな音声を録音する
AI議事録の精度は、元となる「音声の品質」に9割依存すると言っても過言ではありません。
「ガー」というエアコンの音、書類をめくる音、周囲の雑談、PCのタイピング音などは、AIにとって発言を妨げる「ノイズ」です。
会議室で録音する場合は、できるだけ話者に近い位置に高性能なマイク(指向性マイクなど)を設置してください。
オンライン会議(Google Meetなど)の場合は、参加者全員がヘッドセットやマイク付きイヤホンを使用し、発言時以外はミュートにするルールを徹底するだけで、文字起こしの精度は劇的に改善します。
クリアな音声は、AIが言葉を正確に認識するための最低条件です。
2. Geminiなど最新のAIモデルを使う
文字起こしされたテキストを要約・清書する際、使用するAIモデルの性能も重要です。
GoogleのGeminiは非常に高性能ですが、AIの世界は日進月歩です。
例えば、ユーザーから提供された最新情報(2025年8月リリース)によると、OpenAIの最新モデル「GPT-5」は、質問の難易度に応じてじっくり考える「Thinking(長考)」モードを備えています。
最新モデルとして言及したGPT-5のリリース日、機能、料金、GPT-4との違いを詳細に解説した記事はこちらです。 合わせてご覧ください。
複雑な議論が入り混じった長時間の議事録から、単なる要約ではなく、発言の裏にある意図や議論の対立点を深く分析させたい場合、こうした最新のAIモデルの「推論能力」を活用することも有効な選択肢となります。
GoogleのGemini(特に有料版やVertex AIで提供される最新モデル)も同様に進化しており、目的に応じて最適なAIモデルを選択することが、質の高い議事録を得るためのコツです。
3. 議事録のフォーマット(形式)をプロンプトで指定する
Geminiに要約を依頼する際、「いい感じにまとめて」という曖昧な指示では、望んだ結果は得られません。
AIが迷わず作業できるよう、完成形の「型(フォーマット)」を明確に指定する必要があります。
例えば、以下のように具体的な出力形式を指示します。
「以下の形式で議事録を作成してください。」
「## 1. 会議概要」
「・日時:」
「・場所:」
「・参加者:」
「## 2. 決定事項」
「・(ここに箇条書き)」
「## 3. ToDoリスト」
「・[P1] 〇〇さん: △△の資料作成(〜11/10)」
このようにマークダウン記法などを使って構造を指示する(ゼロショットプロンプト)、あるいは一度良い例(見本)をAIに見せる(フューショットプロンプト)ことで、AIは毎回同じフォーマットで安定して出力してくれるようになります。
4. 決定事項やToDoなど、含めるべき要素を指示する
AIは、あなたが議事録のどこを重要視しているかを知りません。
単に「要約して」と頼むと、議論が白熱した部分(しかし結論は出ていない)を詳細に要約し、一方で、さらっと決まった重要な決定事項を見落とす可能性があります。
プロンプトで「何を」抽出してほしいかを明確に定義することが重要です。
「この会議で最も重要な『決定事項』を3つ抽出してください」
「議論の内容よりも、『誰が何をするか』という『ToDo』を優先してリストアップしてください」
「否定的な意見やリスクに関する発言があれば、それも必ず含めてください」
このように、議事録の読み手が知りたい情報(=含めるべき要素)を具体的に指示することで、AIの出力とあなたのニーズが一致し、手直しの少ない議事録が完成します。
5. 専門用語や固有名詞は事前にリストアップする
AIは一般的な知識は豊富ですが、あなたの会社独自の専門用語、プロジェクト名、社内の通称(あだ名)、取引先の固有名詞などは知りません。
これらは、文字起こしの段階で誤認識されやすい最大の要因です。
例えば、「KGI(重要目標達成指標)」が「景気合い」と文字起こしされたり、プロジェクト名「Project Phoenix」が「プロジェクト 不死鳥」と訳されたりすることがあります。
Geminiに要約させる際も、これらの単語を知らなければ文脈を正しく理解できません。
これを防ぐため、プロンプトの冒頭で「用語リスト」としてAIに事前知識を与えることが有効です。
「以下の用語リストを参考にして、議事録を作成してください。」
「#用語リスト」
「・GTM: Go-To-Market」
「・山田(営): 営業部の山田部長」
「・プロP: Project Phoenixの略称」
このように固有名詞を定義しておくだけで、AIの文脈理解度が向上し、議事録全体の精度が大きく向上します。
AIによる自動音声認識(ASR)が、なぜ専門用語や固有名詞(語彙外:OOV)の認識に失敗しやすいのかを分析した研究論文です。 合わせてご覧ください。 https://repository.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=13214&context=theses
GoogleのAIで議事録を作成する際の3つの注意点
GoogleのAIは議事録作成を劇的に効率化しますが、万能の魔法ではありません。
その特性を理解せず安易に使うと、思わぬトラブルや情報漏洩につながる危険性もあります。
ここでは、業務で安全に活用するために最低限知っておくべき3つの注意点を解説します。
1. 文字起こしや要約が100%正確とは限らない
まず大前提として、AIによる文字起こしや要約は100%の正確性を保証するものではありません。
特に、早口、複数の人が同時に発言、方言や訛り、専門用語が多用される場合、AIは音声を正しく認識できないことがあります。
また、Geminiによる要約も、文脈のニュアンスを完全には汲み取れない場合があります。
例えば、皮肉や冗談を真剣な意見として要約してしまったり、議論の最も重要な核となる部分を「冗長な会話」と判断して省略してしまったりする可能性もゼロではありません。
AIの出力はあくまで「下書き」であり、完璧な成果物ではないことを常に認識しておく必要があります。
2. 必ず人間の目でファクトチェック(事実確認)を行う
AIが100%正確ではない以上、AIが生成した議事録をそのまま正式な記録として共有・保存することは非常に危険です。
必ず、会議の参加者、あるいは内容を理解している人間が、最終的な「ファクトチェック(事実確認)」を行う必要があります。
特に確認すべきは、以下の点です。
- 数値: 売上目標、予算、納期、人員数などの数字に間違いはないか。
- 固有名詞: 参加者名、顧客名、製品名、プロジェクト名に誤りはないか。
- 決定事項: 議論の経緯と「決まったこと」が正確に記載されているか。
- ToDo: 「誰が」「何を」「いつまでに」やるのか、担当と期限が明確か。
AIは「それらしい文章」を作るのが得意なため、一見すると完璧な議事録に見えても、中身が事実と異なる場合があります。
この最終確認を怠ると、AIが生成した「嘘」がオフィシャルな記録として残り、後で大きな問題に発展する可能性があります。
3. 機密情報や個人情報の取り扱いに注意する
これが最も重要な注意点です。
会議の音声やテキストデータには、顧客の個人情報、未発表の製品情報、財務情報、人事情報など、企業の最高レベルの機密情報が含まれることが多々あります。
これらの情報を、セキュリティポリシーを確認せずにAIサービスに入力することは、情報漏洩のリスクを伴います。
特に、無料版のGemini(Web UI)など一般消費者向けのAIサービスは、デフォルト設定で入力されたデータがAIの品質向上のために「学習データ」として利用される可能性があります。
機密情報を扱う場合は、必ず、入力したデータが学習に使われない(オプトアウト)設定が可能な法人向けサービス(Google Workspace搭載のGemini(旧Duet AI)やVertex AI、あるいは「ChatSense」のような法人向けAIサービスなど)を利用してください。
また、社内の情報セキュリティ部門に、どのAIツールまでなら業務利用が許可されているか、利用する際のルール(例:個人名は匿名化する、など)を必ず確認する必要があります。
一般消費者(無料)版Geminiに入力されたデータが、品質向上のために人間のレビュー担当者によって確認され、最大3年間保持される可能性があることを明記した公式ヘルプページです。 合わせてご覧ください。 https://support.google.com/gemini/answer/13594961?hl=ja
GoogleのAI議事録作成に関するよくある質問 (FAQ)
最後に、GoogleのAIを使った議事録作成に関して、多くの人から寄せられる質問とその回答をまとめます。
Q. 無料で使える機能はどこまでですか?
無料で利用できる機能と、有料プランが必要な機能があります。
無料で利用できる主な機能:
- Googleドキュメントの音声入力: PCのマイクや内部音声(ステレオミキサー設定時)からのリアルタイム文字起こし。
- Google Meetの字幕機能: 会議中のリアルタイム字幕表示(日本語対応)。
- Google Pixelのレコーダー: スマートフォンでの高精度な録音と文字起こし(話者分離は英語のみ)。
- Gemini (Web UI): 文字起こしテキストのコピー&ペーストによる要約・清書(文字数制限あり。最新モデルの利用に制限がある場合あり)。
有料プラン(Google Workspaceなど)が必要な主な機能:
- Google Meetの文字起こし機能: 会議の会話をGoogleドキュメントとして自動保存する機能。
- Google Workspace搭載のGemini (旧Duet AI): GoogleドキュメントやGmail内で直接AIを呼び出し、長文の要約や作成支援を行う機能。
- Vertex AI (Gemini API): データが学習に使われない設定で、自社システムにAIを組み込む開発者向け機能。
Q. Google Meetの文字起こしはどの言語に対応していますか?
はい、日本語に完全対応しています。
以前は英語のみの対応でしたが、アップデートにより日本語の認識精度が大幅に向上し、実用的なレベルになっています。
日本語のほか、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、韓国語など、多くの主要言語に対応しています。(2025年11月現在)
会議の参加者が複数の言語を話す場合でも、文字起こしを開始する際に主要な言語を一つ選択する必要があります。
Q. 議事録の精度が低い場合、どうすれば良いですか?
議事録の精度が低い場合、原因は「入力(音声)」か「処理(AI)」か「指示(プロンプト)」にあります。
以下の点を確認・実行してみてください。
- 音声品質の改善(入力):最も多い原因です。ノイズの多い場所を避け、参加者全員が高品質なマイク(ヘッドセット)を使うようにしてください。発言は「はっきりと、明瞭に」行うよう意識することも重要です。
- AIモデルの見直し(処理):無料版のAIで精度が出ない場合、有料版の高性能なモデル(Gemini Advancedや、GPT-5など)を試すと、複雑な文脈の理解度が向上する可能性があります。
- プロンプトの改善(指示):本記事の「精度を上げる5つのコツ」で解説したように、AIへの指示を具体的にすることが非常に有効です。「用語リスト」の提供や「出力フォーマット」の指定を試してください。
これらの対策を行っても精度が改善しない場合、現状のAI技術の限界である可能性もあります。
その場合は、AIによる自動化の範囲を「完全な議事録作成」から「文字起こしのドラフト作成」や「ToDoの叩き台作成」に留め、人間による編集作業の比重を増やすといった運用上の調整が必要です。
あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い
ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。
【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない
「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。
これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。
- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。
- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方
では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「壁打ち相手」にする
自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」
これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「無知な生徒」として教える
自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」
AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」
AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。