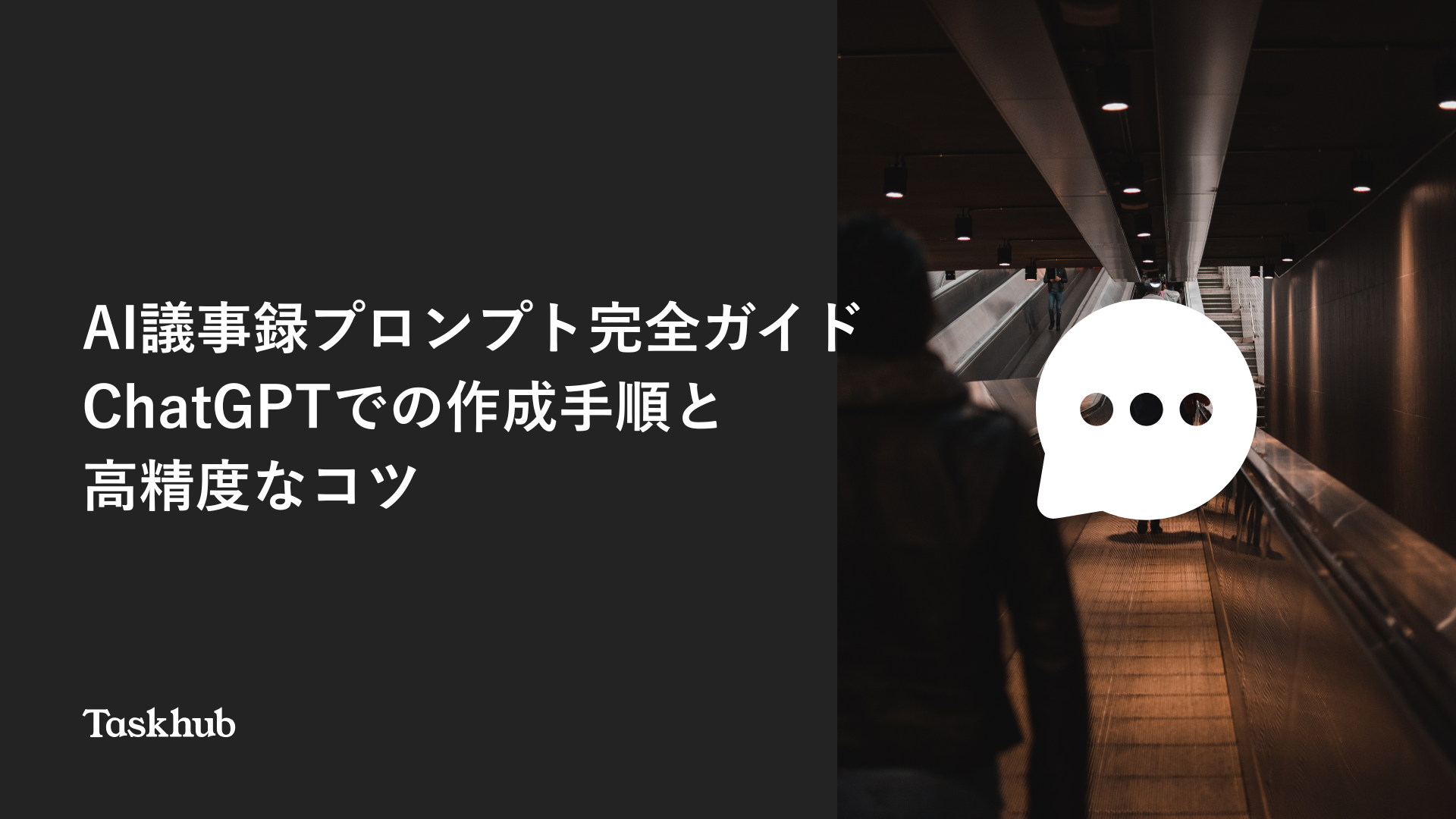「ChatGPTで議事録を作成できるらしいけど、具体的なAIプロンプトが知りたい」
「AIで議事録を作ってみたけど、精度が低くて使い物にならない…」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
会議の文字起こしテキストをAIに入力するだけで、高精度な議事録が作成できたら便利ですよね。
本記事では、ChatGPTを使った議事録作成の手順、コピペで使える具体的な4つのAIプロンプト例、そして生成精度を格段に上げる8つのコツを徹底解説します。
上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実務で活用しているノウハウのみをご紹介します。
きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
AI(ChatGPT)で議事録を作成する3つのメリット
はじめに、ChatGPTのような生成AIを活用して議事録を作成するメリットを3つ紹介します。
- 議事録作成にかかる作業時間の大幅な短縮
- 人的な聞き間違いや要点の記載漏れを防止
- 客観的な内容で均一な品質を担保できる
これらのメリットを理解することで、AI議事録作成の導入がなぜ多くの企業で進んでいるのかが明確になります。
それでは、1つずつ順に解説します。
議事録作成にかかる作業時間の大幅な短縮
AI(ChatGPT)で議事録を作成する最大のメリットは、作業時間の大幅な短縮です。
従来の議事録作成プロセスでは、会議の録音を聞き返し、重要な発言をピックアップし、それを分かりやすい文章にまとめるという一連の作業が必要でした。
特に1時間を超えるような会議では、議事録作成だけに1〜2時間以上かかることも珍しくありません。
会議に参加するたびにこの作業が発生すると、本来のコア業務に割くべき時間が圧迫されてしまいます。
しかし、AIを活用すれば、会議の文字起こしデータ(テキスト)さえあれば、適切なプロンプト(指示文)を入力するだけで、数分程度で議事録の草案が完成します。
AIが自動で要点を抽出し、指定したフォーマットに整形してくれるため、人間が行う作業は最終的な確認と微修正のみとなります。
この効率化によって削減された時間は、より生産的な業務や、次のアクションプランを練るための時間に充てることが可能になります。
特に、定例会議やクライアントとの打ち合わせが多い職種において、この時間短縮効果は計り知れません。
人的な聞き間違いや要点の記載漏れを防止
会議中、人間は集中して議論に参加しながら、同時に要点を正確に記憶し、メモを取る必要があります。
しかし、集中力の低下や、議論が白熱する中でのマルチタスクは非常に困難であり、どうしても聞き間違いや重要な決定事項の記載漏れといったヒューマンエラーが発生しがちです。
後から録音を聞き直す場合でも、長時間の音声データから全ての重要情報を漏れなく拾い上げるのは骨の折れる作業です。
AI、特にChatGPTのような高度な言語モデルは、大量のテキストデータを処理する能力に長けています。
あらかじめ会議の全容がテキスト化(文字起こし)されていれば、AIはそのテキスト全体を網羅的に分析します。
人間が見落としがちな細かなニュアンスや、会話の途中で出た重要なキーワード、決定事項、ToDo(宿題)などを、客観的にかつ網羅的に抽出することが可能です。
これにより、議事録の正確性が飛躍的に向上し、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことにも繋がります。
AIは疲れることなく、常に一定の基準でテキストを処理するため、ヒューマンエラーの介在する余地を最小限に抑えることができます。
こちらは大規模言語モデル(LLM)が特定の分野において、人間による要約よりも好まれる傾向にあることを示した研究論文です。 合わせてご覧ください。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10635391/
客観的な内容で均一な品質を担保できる
議事録は、作成する担当者によってその品質にバラツキが出やすいドキュメントの一つです。
ある人は詳細に記述する一方で、別の人は要点のみを簡潔にまとめるかもしれません。
また、担当者の主観や解釈が入り込むことで、会議の意図とは異なるニュアンスで記録されてしまうリスクもあります。
AI(ChatGPT)に議事録作成を任せることで、この問題を解決できます。
AIは、プロンプトで指示されたフォーマットやルールに基づき、常に一貫した基準でテキストを処理します。
例えば、「会議の目的」「決定事項」「ToDoリスト」「懸念事項」といった項目をあらかじめ指定しておけば、どのような会議の文字起こしデータであっても、必ずそのフォーマットに沿って情報が整理されます。
AIは感情やバイアスを持たないため、入力されたテキストデータを客観的に分析し、事実に基づいた議事録を作成します。
これにより、誰がAIを使っても、常に一定の品質(クオリティ)が担保された議事録を安定して作成することが可能になります。
組織全体で議事録のフォーマットを統一し、情報共有の質を高める上でも、AIの活用は非常に有効な手段と言えるでしょう。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
ChatGPTを使った議事録作成の4ステップ
ここからは、実際にChatGPTを使って議事録を作成するための具体的な手順を4つのステップで解説します。
- Step 1. 会議の音声を録音する
- Step 2. 音声データを文字起こし(テキスト化)する
- Step 3. 文字起こしテキストとプロンプトをChatGPTに入力する
- Step 4. 出力された議事録を修正・確認する
このプロセスは非常にシンプルですが、各ステップで精度を高めるための小さなコツが存在します。
AI議事録作成を成功させるために、順を追って確認していきましょう。
Step 1. 会議の音声を録音する
全ての基本は、正確な音声データを取得することから始まります。
議事録作成の精度は、この最初のステップである「録音の品質」に大きく左右されると言っても過言ではありません。
なぜなら、後のステップで行う「文字起こし」の精度が、録音品質に直結するからです。
オンライン会議(Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなど)の場合は、会議ツールの録音機能を活用するのが最も簡単で確実です。
これらのツールは、参加者の音声を比較的クリアに録音できるよう設計されています。
録音を開始する際は、必ず会議の参加者全員に録音の許可を取ることを忘れないでください。
対面での会議の場合は、ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリを使用します。
この時、できるだけ発言者の近くにマイクを設置することが重要です。
会議室が広い場合や参加人数が多い場合は、発言者の声を均等に拾うために、高性能な360度集音マイクの使用を推奨します。
雑音(エアコンの音、書類をめくる音、タイピング音など)が入り込まないよう、静かな環境を整えることも大切です。
Step 2. 音声データを文字起こし(テキスト化)する
次に、Step 1で録音した音声データをテキストデータに変換します。
この「文字起こし」作業は、AI議事録作成の根幹をなす非常に重要なプロセスです。
ここで注意が必要なのは、2025年11月現在、ChatGPT(GPT-5やGPT-4o)自体には、長時間の音声ファイル(例:1時間の会議録音)を直接アップロードして文字起こしさせる機能は標準搭載されていない点です。
(※一部のサードパーティツールやAPI連携を除き、基本的なWebインターフェースでの話です)
そのため、別途「文字起こしAIツール」を利用する必要があります。
高精度な文字起こしツールとしては、「Notta」や「CLOVA Note」、「AmiVoice」などが有名です。
これらのツールは、AIを活用して高精度に音声をテキスト化し、発言者ごとの分離(話者分離)にも対応している場合があります。
精度の高い文字起こしツールを選ぶことが、最終的な議事録の品質を決定づける鍵となります。
多少のコストがかかったとしても、専門の文字起こしツールを利用する価値は非常に高いです。
ここで生成されたテキスト(.txtファイルやコピー&ペーストできる形式)を、次のステップでChatGPTに入力します。
こちらはChatGPTで文字起こしを行う方法や、その際のプロンプト、注意点について詳しく解説した記事です。 合わせてご覧ください。
Step 3. 文字起こしテキストとプロンプトをChatGPTに入力する
Step 2で精度の高い文字起こしテキストが準備できたら、いよいよChatGPTの出番です。
このステップでは、ChatGPTの入力欄に「プロンプト(指示文)」と「文字起こしテキスト」を一緒に入力します。
プロンプトとは、「何をしてほしいか」をAIに伝えるための命令書のようなものです。
議事録作成におけるプロンプトの質が、AIの出力(生成される議事録)の質を決定します。
例えば、単に「要約して」と指示するだけでは、どのような議事録が欲しいのかがAIに伝わりません。
「以下のテキストを、指定するフォーマットで議事録にしてください」「会議の決定事項とToDoを抽出してください」といった、具体的かつ明確な指示が必要です。
具体的なプロンプトの例文については、後ほどの章(【コピペOK】議事録作成AIプロンプト 例文集)で詳しく紹介します。
プロンプトと文字起こしテキストをChatGPTに入力し、送信ボタンを押せば、AIが分析を開始し、数秒から数分で議事録の草案を出力します。
こちらはChatGPTのプロンプトの形式、基本構造、作成のコツについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。
Step 4. 出力された議事録を修正・確認する
ChatGPTが出力した議事録は、あくまで「草案」であると認識することが重要です。
AIは非常に優秀ですが、完璧ではありません。
必ず人間の目で最終的なチェックと修正(レビュー)を行ってください。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 要点や決定事項に漏れはないか?
- 日付、数値、固有名詞(人名、会社名、製品名)に誤りはないか?
- 文脈の解釈が間違っている箇所はないか?
- 発言者の意図と異なるニュアンスになっていないか?
特に、文字起こしツールが音声を誤認識している場合(例:「経済」を「軽罪」と認識するなど)、AIもその誤ったテキストを前提に議事録を作成してしまいます。
元の録音を聞き返す必要はなくても、文字起こしテキストとAIの出力を見比べながら、不自然な点や誤りがないかを精査する作業は不可欠です。
この最終確認のステップを怠ると、間違った情報が議事録として共有されてしまい、後のトラブルの原因にもなりかねません。
AIを「優秀なアシスタント」として活用し、最後の仕上げは人間が責任を持って行う、という意識が大切です。
ChatGPTで効果的な議事録を作成する方法を詳しく知りたい方は、こちらの記事を必ずご覧ください。画像付きでわかりやすく手順を解説しております。
ChatGPTが議事録作成でできること
ChatGPTは、単にテキストを要約するだけではありません。
議事録作成というタスクにおいて、AIプロンプトを工夫することで以下のような多様な処理が可能です。
- 長文テキストの要約と構成
- 重要な決定事項やToDoリストの抽出
- 話し言葉(口語)を書き言葉(文語)に変換
- 発言者ごとの内容整理
これらの機能を理解することで、より質の高い議事録を効率的に作成するためのプロンプトを設計できるようになります。
一つずつ見ていきましょう。
長文テキストの要約と構成
ChatGPTの最も得意とする能力の一つが、長文のテキストを理解し、その核心的な内容を短い文章にまとめる「要約」です。
1時間にわたる会議の文字起こしテキストは、数万文字に及ぶこともあります。
これを人間がすべて読み返して要点を把握するのは大変な労力です。
ChatGPTに適切なプロンプトを与えることで、この膨大なテキストデータから主要なトピックを自動で識別させることが可能です。
さらに、ただ要約するだけでなく、「会議の目的」「議論の経緯」「結論」といった、議事録に必要な「構成」に沿って情報を再配置させることができます。
例えば、「以下のテキストを、アジェンダごとの議論の概要が分かるように要約してください」と指示すれば、時系列でだらだらと続く会話の記録を、トピックごとに整理された分かりやすい議事録の形に整形してくれます。
これにより、会議に参加しなかった人でも、短時間で議論の全体像を把握できるようになります。
こちらは要約の評価に使われるROUGEスコアの限界と、セマンティックな評価の重要性について解説した研究論文です。 合わせてご覧ください。https://arxiv.org/html/2404.11124v1
重要な決定事項やToDoリストの抽出
議事録の最も重要な役割の一つは、「会議で何が決まったのか(決定事項)」そして「次に誰が何をすべきか(ToDoリスト)」を明確に記録し、関係者全員で共有することです。
会議中の議論が盛り上がると、これらの重要な情報が会話の中に埋もれてしまいがちです。
ChatGPTは、テキスト全体をスキャンし、「〜を決定します」「〜はAさんが担当します」「〜までにBさんが対応」といった、行動や決定に関連するキーワードや文脈を認識する能力に長けています。
プロンプトで「テキストから『決定事項』と『ToDo』を箇条書きで抽出してください」と具体的に指示することで、AIは会話の海の中からこれらの重要な情報を正確に釣り上げてリスト化します。
さらに、「ToDoについては、担当者と期限も併記してください」と指示を追加すれば、より実用的なアクションリストを作成できます。
これにより、会議後のタスク実行の漏れを防ぎ、プロジェクトの推進力を高めることができます。
こちらはLLMによるアクションアイテム(決定事項)の抽出効率が、人間と比較して約1/180の速度であることを示した研究論文です。 合わせてご覧ください。https://arxiv.org/html/2510.16551v3
話し言葉(口語)を書き言葉(文語)に変換
会議の文字起こしテキストは、そのままでは「えー」「あのー」といったフィラー(間投詞)や、文法的に不完全な文章、重複した表現など、いわゆる「話し言葉(口語)」で満たされています。
これをそのまま議事録として共有すると、非常に読みにくく、プロフェッショナルな文書とは言えません。
ChatGPTは、こうした口語表現を、ビジネス文書として適切な「書き言葉(文語)」に変換するタスクも得意としています。
プロンプトで「フィラー(えー、あのーなど)を削除し、口語表現を文語表現に修正してください」や「『です・ます調』の丁寧な文章に整えてください」と指示するだけです。
AIは文脈を理解しながら、不要な部分をカットし、冗長な表現を簡潔にまとめ、文法的に正しい文章(例:「〜って感じ」→「〜という印象である」)に自動で変換します。
これにより、人間が手作業で「てにをは」を修正する手間をかけることなく、瞬時に読みやすく整った議事録の草案を手に入れることができます。
発言者ごとの内容整理
文字起こしツールの中には、誰が話したかを識別する「話者分離」機能を持つものがあります。
(例:[Aさん] 00:10: 〜, [Bさん] 00:15: 〜)
この話者情報が含まれたテキストをChatGPTに入力することで、発言者ごとに議論を整理させることが可能です。
例えば、「発言者ごとに、主要な意見や発言内容を要約してください」とプロンプトで指示します。
するとAIは、Aさんがどのような主張をし、Bさんがそれにどう反論し、Cさんがどのような提案をしたのかを、人物ごとにまとめて出力します。
これは、特に複数の部門や関係者が参加する複雑な会議において非常に有効です。
誰がどのようなスタンスで、何にコミットしたのかが明確になるため、議論の経緯を正確に把握し、後の責任の所在を明らかにする上で役立ちます。
もし話者分離ができていないテキストであっても、「議論の論点Aについての賛成意見と反対意見をまとめてください」といった指示を出すことで、内容ベースでの整理も可能です。
【コピペOK】議事録作成AIプロンプト 例文集
お待たせしました。ここからは、ChatGPTでの議事録作成に今すぐ使える、コピペOKのAIプロンプト例文集を紹介します。
- 【基礎】シンプルな要約プロンプト
- 【応用】フォーマット指定ありの詳細プロンプト
- 【TIPS】決定事項とToDoリストを抽出するプロンプト
- 【TIPS】発言者別に要点をまとめるプロンプト
これらのプロンプトはあくまで土台(テンプレート)です。
ご自身の目的に合わせて項目をカスタマイズしながら活用してください。
【基礎】シンプルな要約プロンプト
まずは、最も基本的で使いやすいプロンプトです。
会議の概要を素早く把握したい場合や、詳細なフォーマットが不要な内部メモとして使用する場合に便利です。
とにかく早く、全体の流れを掴みたいときにおすすめです。
#プロンプト
あなたはプロの書記です。
以下の「文字起こしテキスト」を読み、会議の全体概要を300文字程度で要約してください。
#文字起こしテキスト (ここに文字起こしテキストを貼り付ける)
このプロンプトのポイントは、「プロの書記です」という役割を与えることで、AIの回答の質を高めている点です。
また、「300文字程度」と具体的な文字数を指定することで、出力される要約の長さをコントロールしています。
このプロンプトを使えば、長時間の会議データでも、その核心的な内容(主要なトピックや議論の流れ)を凝縮した形で素早く確認することができます。
ただし、これはあくまで全体の概要を掴むためのものです。
具体的な決定事項やToDoを正確に抽出したい場合は、次の「応用プロンプト」や「TIPSプロンプト」を使用する必要があります。
【応用】フォーマット指定ありの詳細プロンプト
実務で最も使用頻度が高く、汎用的なプロンプトがこちらです。
議事録に必要な項目(フォーマット)をあらかじめ指定することで、AIに構造化された議事録を出力させます。
このフォーマットを一度作成しておけば、毎回同じ品質の議事録を生成できます。
#プロンプト
あなたはプロの議事録作成アシスタントです。
以下の「文字起こしテキスト」を読み、下記の「出力フォーマット」に従って、会議の議事録を作成してください。
#制約条件
・「文字起こしテキスト」から読み取れない情報は、「該当なし」と記載してください。
・口語表現(「えー」「あのー」など)は削除し、文語表現(「です・ます調」)に統一してください。
#出力フォーマット
- 会議名: (不明な場合は「(会議名不明)」と記載)
- 日時: (不明な場合は「(日時不明)」と記載)
- 参加者: (不明な場合は「(参加者不明)」と記載)
- 会議の目的:
- アジェンダ:
- 議論の要点(トピック別):
- [トピック1]:
- (議論の内容を箇条書きで要約)
- [トピック2]:
- (議論の内容を箇条書きで要約)
- [トピック1]:
- 決定事項:
- (決定した内容を箇条書きで記載)
- ToDo(宿題):
- [担当者] [タスク内容]([期限])
- その他(懸念事項・次回アジェンダなど):
#文字起こしテキスト (ここに文字起こしテキストを貼り付ける)
このプロンプトの鍵は、「出力フォーマット」を非常に具体的に指定している点です。
AIは「7. 決定事項」や「8. ToDo」といった項目を見ることで、テキストの中からそれらの情報を重点的に探し出すようになります。
「制約条件」で文体を指定しているのもポイントです。
【TIPS】決定事項とToDoリストを抽出するプロンプト
会議の概要はすでに把握しており、とにかく「決まったこと」と「やること」だけを素早く確認したい、というニーズに応えるプロンプトです。
アクションアイテムの確認や、タスク管理ツールへの転記に最適です。
#プロンプト
あなたは優秀なアシスタントです。
以下の「文字起こしテキスト」を分析し、「決定事項」と「ToDoリスト」のみを抽出して、箇条書きで出力してください。
#制約条件
・「決定事項」は、会議で合意・決定された内容を簡潔に記載してください。
・「ToDoリスト」は、[タスク内容] / [担当者] / [期限] の形式で記載してください。
・該当する情報がない場合は、「特になし」と記載してください。
#文字起こしテキスト (ここに文字起こしテキストを貼り付ける)
このプロンプトは、AIのタスクを「抽出」のみに限定しているのが特徴です。
要約や構成の変更を求めず、特定の情報(決定事項とToDo)だけを抜き出すように指示することで、AIは他のノイズに惑わされることなく、目的の情報に集中します。
「[タスク内容] / [担当者] / [期限]」のようにフォーマットを指定することで、AIはテキストの中から「誰が」「何を」「いつまでに」やるのかを必死に探します。
期限が明言されていない場合、AIは「期限:言及なし」などと補完してくれることもあります。
会議後のタスク漏れを防ぐために非常に有効なプロンプトです。
【TIPS】発言者別に要点をまとめるプロンプト
文字起こしツールが「話者分離」(誰が話したか)に対応している場合、このプロンプトが非常に役立ちます。
[Aさん][Bさん]といった話者タグが含まれたテキストを使用する前提です。
誰がどのような意見を持っていたのか、議論の対立点や合意形成のプロセスを後から振り返るのに便利です。
#プロンプト
あなたは議論の分析家です。
以下の「文字起こしテキスト」は、[発言者名] の形式で話者が記録されています。
発言者ごとに、主要な発言内容や意見の要点をまとめてください。
#制約条件
・発言者ごとに見出しを作成し、その下に発言の要点を箇条書きで記載してください。
・単なる発言の書き起こしではなく、その人の「主張」や「提案」が分かるように要約してください。
#出力フォーマット
[発言者A]
- (発言要点1)
- (発言要点2)
[発言者B]
- (発言要点1)
- (発言要点2)
#文字起こしテキスト (ここに[Aさん]…[Bさん]…といった話者情報を含む文字起こしテキストを貼り付ける)
このプロンプトは、時系列の議論を「人物軸」で再構成するようAIに指示しています。
「単なる発言の書き起こしではなく、その人の『主張』や『提案』が分かるように要約して」という一文が重要です。
これにより、AIは単語を拾うのではなく、その発言の「意図」を汲み取ろうとします。
例えば、クライアント(Aさん)の要望と、開発担当者(Bさん)の懸念事項が明確に分離されて出力されるため、論点が整理され、次の打ち手(例:Bさんの懸念を払拭する資料準備)を考えるのに役立ちます。
議事録プロンプトの精度を格段に上げる8つのコツ
コピペOKのプロンプトを紹介しましたが、AIの出力をさらに高品質にするためには、プロンプトの「質」を高めるコツを知っておく必要があります。
ここでは、議事録AIプロンプトの精度を格段に上げる8つのコツを紹介します。
- 「議事録作成のプロ」などの役割を与える
- 目的(例:決定事項の確認)を明確に伝える
- 出力フォーマット(項目、箇条書きなど)を具体的に指定する
- 文体(「です・ます調」「だ・である調」)を指定する
- 元となる文字起こしデータの精度を高める
- 一度に処理させず、タスクを分割して依頼する
- 出力が不十分な場合は追加で修正を指示する
- 性能の高いモデル(GPT-5など)を利用する
これらのコツを意識するだけで、AIの反応が劇的に変わります。
それでは、1つずつ順に解説します。
1. 「議事録作成のプロ」などの役割を与える
AIプロンプトの冒頭で、「あなたはプロの書記です」「あなたは優秀な議事録作成アシスタントです」といった「役割(ロール)」を与えることは、非常に効果的なテクニックです。
これは「役割設定(ロールプレイング)」と呼ばれる手法です。
AIに特定の専門家としてのペルソナを与えることで、AIはその役割になりきり、その専門家が持っているであろう知識や思考パターンを(擬似的に)使って回答を生成しようとします。
単に「議事録を作って」と指示するよりも、「プロの書記として」と前置きする方が、AIは「プロの書記なら、どのような点に注意して議事録を作成すべきか」を考慮します。
例えば、客観性を保つこと、要点を簡潔にまとめること、フォーマットを整えることなどを、指示されなくてもある程度予測して実行してくれるようになります。
役割は具体的であればあるほど効果的です。「外資系コンサルタントのように、MECEを意識して論点を整理してください」といった指定も可能です。
こちらはプロンプトエンジニアリングにおける役割付与(Role Prompting)が、LLMの応答のスタイルやタスク性能を向上させることを解説したドキュメントです。 合わせてご覧ください。https://learnprompting.org/docs/advanced/zero_shot/role_prompting
2. 目的(例:決定事項の確認)を明確に伝える
あなたは、なぜその議事録を作成したいのでしょうか?
AIにタスクを依頼する際は、その「目的」や「背景」を伝えることが重要です。
例えば、同じ文字起こしテキストでも、目的によって必要な議事録の形は変わってきます。
- 目的A:会議に参加できなかった人に、議論の概要を共有したい
- → この場合、議論の全体像や背景、結論が簡潔にまとまっている要約が望ましいです。
- 目的B:会議で決まったタスク(ToDo)を関係者にリマインドしたい
- → この場合、他の議論は省略してでも、決定事項とToDoリスト(担当者、期限)が正確に抽出されていることが最優先です。
プロンプトに「この議事録の目的は、会議後のタスク漏れを防ぐことです。決定事項とToDoリストを最優先で、正確に抽出してください」と一言加えるだけで、AIはあなたの意図を理解します。
そして、その目的に沿って、情報の優先順位(この場合はToDo)を判断し、より目的に合致したアウトプットを生成しようと努力します。
3. 出力フォーマット(項目、箇条書きなど)を具体的に指定する
AIは、あいまいな指示よりも具体的な指示を好みます。
特に「どのような形式で出力してほしいか」は、プロンプトの中で最も具体的に指定すべき項目の一つです。
「いい感じにまとめて」といった指示では、AIは「いい感じ」が何を指すのか分からず、一般的な要約を返すことしかできません。
前の章の「応用プロンプト」で示したように、「出力フォーマット」を明記することが非常に有効です。
- 見出し(例:1. 決定事項)
- 箇条書き(「・」を使うのか、「1.」のような番号付きリストか)
- 表形式(Markdown形式のテーブルで出力させることも可能)
- 特定の記号(例:ToDoは[ ]のチェックボックス形式で)
このようにフォーマットを細かく指定することで、AIは「クリエイティブな文章作成」から「穴埋めクイズ」のモードに切り替わります。
指定された枠(フォーマット)を埋めるために、テキストの中から必要な情報を探すタスクに集中するため、結果として情報の抽出精度が向上します。
また、出力形式が統一されるため、後で利用する際(メールへの転記、社内システムへの登録など)の作業効率も上がります。
4. 文体(「です・ます調」「だ・である調」)を指定する
議事録の文体は、その用途によって異なります。
クライアントに提出する正式な議事録であれば「です・ます調(敬体)」が望ましいでしょうし、社内の開発チーム用メモであれば「だ・である調(常体)」で簡潔にまとめた方が読みやすいかもしれません。
ChatGPTは、これらの文体を自在に使い分けることができます。
プロンプトに「文体は『です・ます調』で統一してください」や「『だ・である調』で簡潔に出力してください」と明記するだけで、AIはその指示に従います。
さらに、文体だけでなく「トーン&マナー」を指定することも可能です。
「客観的な事実のみを淡々と記述してください」「ポジティブな表現を多めに、前向きな議事録にしてください」といった指示も、ある程度反映されます。
特に重要なのは、「話し言葉(口語)を書き言葉(文語)に変換してください」という指示です。
これを入れないと、文字起こしの「えー」「あのー」といったフィラーまで議事録に残ってしまう可能性があるため、必ず指定するようにしましょう。
5. 元となる文字起こしデータの精度を高める
これはプロンプトのコツとは少し異なりますが、AI議事録作成において最も重要な成功要因の一つです。
AIは入力されたテキストデータを「正」として処理します。
「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れたら、ゴミしか出てこない)」という言葉があるように、元となる文字起こしデータの品質が低ければ、どれだけ優れたプロンプトを使っても、高品質な議事録を作成することはできません。
例えば、
- 音声認識がうまくいかず、誤字脱字だらけのテキスト
- 発言者が全員「不明」になっており、誰の意見か分からないテキスト
- 専門用語が正しく認識されていないテキスト(例:「GPT」が「GTT」になっている)
このような低品質なテキストをAIに入力しても、AIは誤った情報を基に要約や抽出を行ってしまいます。
前述の通り、精度の高い文字起こしツール(Notta, CLOVA Noteなど)に投資することは、議事録作成の全プロセスを効率化する上で非常に重要です。
クリアな録音(Step 1)と、高精度な文字起こし(Step 2)こそが、高精度なAI議事録(Step 4)の土台となります。
こちらは自動音声認識(ASR)の性能評価指標であるWER(単語誤り率)や、ベンチマークについて解説した論文です。 合わせてご覧ください。https://arxiv.org/html/2510.12827v1
6. 一度に処理させず、タスクを分割して依頼する
1時間の会議の文字起こしテキストは、数万文字に及ぶことがあります。
このような長文テキストを一度にChatGPTに入力し、「要約もして、ToDoも抽出して、発言者ごとにもまとめて」と、複数の複雑なタスクを一度に依頼すると、AIの処理能力が追いつかず、情報の抜け漏れが発生したり、指示の一部が無視されたりする可能性があります。
AIの精度を高める基本原則は「タスクの分割(Small Task)」です。
人間が複雑な仕事に取り組むときに手順を分けるのと同じです。
- ステップ1(要約): まず、長文テキストをAIに入力し、「まずは、この会議の主要なトピックを5つ挙げてください」と、全体像を把握させます。
- ステップ2(詳細化): 次に、「ありがとうございます。では、その中の『トピック2』について、議論の詳細を教えてください」と深掘りします。
- ステップ3(抽出): 最後に、「全体の議論を踏まえて、決定事項とToDoリストを抽出してください」と、特定のタスクを依頼します。
このように、AIと対話しながら段階的に作業を進めることで、AIは各ステップで一つのタスクに集中できるため、処理の精度が格段に向上します。
時間はかかりますが、最終的な成果物の質は高くなります。
また、長文テキストがモデルの入力文字数制限(コンテキストウィンドウ)を超える場合も、テキスト自体を分割して入力する必要があります。
7. 出力が不十分な場合は追加で修正を指示する
AIの最初の出力(ファーストドラフト)が、常に完璧であるとは限りません。
「決定事項が一つ漏れている」「ここの表現が分かりにくい」といった不満点が出てくるのは普通のことです。
その際、AIの出力をコピーして自分で修正するのではなく、ChatGPTとの「対話」を続けることが重要です。
AIは直前の会話の文脈を記憶しています。
「先ほどの議事録ですが、ToDoリストに『Aさんが来週までに資料を準備する』という項目が漏れています。追加してください」
「『議論の要点』の項目が長すぎるので、各トピックを3行程度で、もっと簡潔にまとめてください」
このように、不十分な点を具体的にフィードバックし、追加で修正を指示します。
AIは、このフィードバック(修正指示)を「新たなプロンプト」として受け取り、出力を改善しようと試みます。
この対話的な修正プロセス(イテレーション)を経ることで、議事録の完成度を効率的に高めていくことができます。
AIを「一度きりのツール」ではなく、「対話可能なアシスタント」として扱うことがコツです。
8. 性能の高いモデル(GPT-5など)を利用する
議事録作成のような、長文を理解し、要点を抽出し、構成し直すという複雑なタスクは、AIモデルの「賢さ」(=推論能力)に大きく依存します。
利用可能なAIモデルが複数ある場合、できるだけ性能の高いモデルを選択することが、精度を上げる最も簡単な方法です。
2025年11月現在、OpenAIの最新フラッグシップモデルは「GPT-5」です。
GPT-5は、2025年8月にリリースされ、簡単な質問には素早く、コーディングやデータ分析、そして長文の要約といった複雑な質問にはじっくり考えて回答する(Thinkingモード)能力が特徴です。
以前のGPT-4oやGPT-4と比較しても、文脈の理解度や指示の忠実性(プロンプトにどれだけ正確に従うか)が大幅に向上しています。
特に、長文の文字起こしテキストから、議論の微妙なニュアンスや暗黙の前提を読み取り、正確な議事録を作成するタスクにおいて、その差は顕著に現れます。
無料版のChatGPTユーザーもGPT-5を利用できますが、制限(5時間あたり10メッセージ、Thinkingモードは1日1回)があるため、業務で頻繁に高精度な議事録を作成する場合は、Plusなどの有料プランに登録し、GPT-5の利用上限を緩和することを強く推奨します。
こちらは最新のフラッグシップモデルであるGPT-5の機能、料金、GPT-4との違いについて詳しく解説した記事です。 合わせてご覧ください。
【徹底比較】ChatGPT・Gemini・Claude 議事録作成AIプロンプトの実力
議事録作成に使えるAIはChatGPTだけではありません。
Googleの「Gemini」やAnthropicの「Claude」も、長文処理能力に優れた強力なライバルです。
ここでは、同じ文字起こしテキストとプロンプトを使って、各AIの議事録作成の実力を比較検証します。
- 比較に使用する文字起こしテキストとプロンプト
- ChatGPT(GPT-4o)の出力結果と評価
- Gemini(Advanced)の出力結果と評価
- Claude 3(Opus)の出力結果と評価
こちらはChatGPTの強力なライバルであるClaude 3とChatGPTの違いについて徹底比較した記事です。 合わせてご覧ください。
比較に使用する文字起こしテキストとプロンプト
比較の公平性を期すため、以下の「文字起こしテキスト(サンプル)」と「プロンプト」を全てのAIに共通で入力します。
テキストは、架空の新商品開発に関する社内会議を想定したものです。
#文字起こしテキスト(サンプル)
[田中] 00:05: えー、では、新商品(コードネーム:Aurora)の進捗会議を始めます。まずデザインチームからお願いします。
[鈴木] 00:15: はい、鈴木です。デザイン案ですが、A案とB案でアンケートを取りまして、結果、A案の評価が非常に高かったです。特に20代女性からの支持が厚いですね。
[田中] 00:30: ほう、A案ですか。良いですね。佐藤さん、開発側の懸念点はありますか?
[佐藤] 00:40: 開発の佐藤です。A案の流線型デザイン、技術的には可能ですが、製造コストが現行モデル比で15%増しになる試算です。B案ならコストは抑えられますが…。
[田中] 00:55: 15%増しか…それは大きいですね。マーケティングの山田さんはどう見ますか?
[山田] 01:05: マーケの山田です。20代女性ターゲットなら、デザインの妥協は致命的です。A案のコスト増は、販売価格で吸収できませんか?
[佐藤] 01:15: 価格に転嫁すると、競合優位性が…。
[田中] 01:20: うーん。分かりました。一旦、佐藤さんはA案のコストをあと5%削減できないか、来週水曜までに再検討お願いします。鈴木さんはA案のデザインをベースに、カラバリの検討に入ってください。
[鈴木] 01:35: 承知しました。
[佐藤] 01:36: 5%…厳しいですが、やってみます。
[田中] 01:40: では、本件は以上です。
#共通プロンプト
あなたはプロの書記です。
以下の「文字起こしテキスト」を読み、下記の「出力フォーマット」に従って議事録を作成してください。
・口語表現(「えー」など)は削除し、「です・ます調」に統一してください。
#出力フォーマット
- 会議名: 新商品「Aurora」進捗会議
- 参加者: 田中、鈴木、佐藤、山田
- 議論の要点:
- (デザイン案に関する議論の要約)
- (コストに関する議論の要約)
- 決定事項:
- (決定した内容)
- ToDo(宿題):
- [担当者] [タスク内容]([期限])
ChatGPT(GPT-4o)の出力結果と評価
ChatGPT(GPT-4o)は、OpenAIの高性能モデル(GPT-5登場以前の最上位モデルの一つ)です。
指示への忠実性と要約の精度に定評があります。
【GPT-4oの出力結果】
- 会議名: 新商品「Aurora」進捗会議
- 参加者: 田中、鈴木、佐藤、山田
- 議論の要点:
- デザイン案については、A案とB案でアンケートを実施した結果、A案が特に20代女性から高い評価を得ました。
- コスト面では、A案を採用した場合、製造コストが現行比で15%増加する見込みであることが開発(佐藤氏)から報告されました。マーケティング(山田氏)は、ターゲット層(20代女性)にはデザインの妥協は難しく、価格転嫁の可能性を指摘しましたが、競合優位性への懸念も示されました。
- 決定事項:
- 新商品のデザインは、A案をベースに進める。
- ToDo(宿題):
- [佐藤さん] A案の製造コストを現行比+15%から、さらに5%削減する検討([来週水曜日まで])
- [鈴木さん] A案のデザインをベースに、カラーバリエーションの検討を開始する([期限言及なし])
【評価】
非常に高精度な議事録が生成されました。
プロンプトの指示通り、口語表現を排除し「です・ます調」で統一されています。
議論の要点では、「デザイン」と「コスト」の対立構造と、山田さんの意見(価格転嫁)まで正確に要約できています。
決定事項(A案採用)と、2名のToDo(佐藤さん、鈴木さん)を、担当者、内容、期限(佐藤さんのみ)まで正確に抽出できており、実用性が非常に高いです。
ChatGPTで議事録作成を効率化したい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
Gemini(Advanced)の出力結果と評価
Gemini(Advanced)は、Googleの最上位モデルです。
Google検索との連携や、Gmail、Googleドキュメントなどとの連携に強みを持ちますが、ここでは純粋な長文処理能力を評価します。
【Gemini (Advanced) の出力結果】
- 会議名: 新商品「Aurora」進捗会議
- 参加者: 田中、鈴木、佐藤、山田
- 議論の要点:
- デザイン案について:鈴木氏より、A案が20代女性に高評価であると報告されました。
- コストについて:佐藤氏より、A案はコストが15%増しになると報告。山田氏はデザインを優先し、価格転嫁を提案しました。
- 決定事項:
- デザインはA案で進める方針が決定されました。
- ToDo(宿題):
- [佐藤] A案のコスト削減(5%)を再検討([来週水曜まで])
- [鈴木] A案のカラーバリエーションを検討([期限なし])
【評価】
ChatGPT(GPT-4o)とほぼ同等の、非常に優れた結果を出力しました。
必要な情報は全て網羅されており、フォーマットへの準拠も完璧です。
要点のまとめ方も簡潔で分かりやすいです。
ToDoの抽出精度も高く、期限(来週水曜)もしっかりと認識しています。
(※出力のニュアンスは実行タイミングによって若干変わる可能性がありますが、性能は互角と言えます)
Google Workspaceを多用する企業であれば、Geminiを選択するメリットは大きいでしょう。
Geminiで議事録作成を効率化したい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
Claude 3(Opus)の出力結果と評価
Claude 3(Opus)は、Anthropic社の最上位モデルです。
特に長文の読解や、複雑な指示の理解(プロンプトの解釈)において非常に高い性能を持つと評価されています。
【Claude 3 (Opus) の出力結果】
- 会議名: 新商品「Aurora」進捗会議
- 参加者: 田中、鈴木、佐藤、山田
- 議論の要点:
- デザイン案の選定:デザインチーム(鈴木氏)より、アンケート結果に基づきA案が20代女性に高評価であると報告されました。
- A案のコスト問題:開発(佐藤氏)から、A案採用時はコストが15%増加するとの懸念が示されました。マーケティング(山田氏)は、ターゲット層を考慮しデザイン優先と価格転嫁を提案しましたが、競合優位性の問題が残りました。
- 決定事項:
- デザイン案はA案を採用し、プロジェクトを推進する。
- ToDo(宿題):
- [佐藤さん] A案のコストについて、さらに5%削減する方策を検討する([来週水曜日まで])
- [鈴木さん] A案をベースとしたカラーバリエーションの検討を開始する([期限の言及なし])
【評価】
こちらもGPT-4o、Geminiと遜色ない、完璧に近い議事録が生成されました。
特に「議論の要点」において、文脈の理解が深い印象を受けます。
「ターゲット層を考慮しデザイン優先と価格転嫁を提案した」という山田さんの発言の「意図」まで汲み取って要約しています。
ToDoの抽出も正確無比です。
Claudeは、他のモデルよりも長いプロンプトや、より複雑な指示(例:複数の文書を比較分析させる)に強いとされており、議事録作成においてもその能力を遺憾なく発揮しています。
Claudeで議事録作成を効率化したい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
Copilotの出力結果と評価
Microsoft Copilotは、OpenAI社のGPT-4技術をベースに、Microsoft 365アプリ(Teams、Word、Outlookなど)との強力な連携機能を持たせたAIアシスタントです。 ビジネスの現場でそのまま使える「実用性」と、セキュリティの堅牢さが大きな特徴です。
【Microsoft Copilot の出力結果】
会議の概要: 新商品「Aurora」進捗会議
■ 議論のポイント
- デザイン選定: デザインチームの鈴木氏より、アンケート結果に基づき20代女性からの支持が高い「A案」が推奨されました。
- コストと価格設定: 開発担当の佐藤氏より、A案採用による15%のコスト増が懸念されました。マーケティング担当の山田氏から価格転嫁の提案がありましたが、競合優位性の観点から議論が交わされました。
■ 決定事項
- デザイン案は「A案」を採用し、プロジェクトを進行する。
■ 次のアクション (ToDo)
- [佐藤氏] A案のコストについて、5%の削減案を策定する(期限:来週水曜日まで)。
- [鈴木氏] A案のカラーバリエーション展開について検討を開始する。
【評価】
ベースがGPT-4であるため、要約の正確性や論理構成はGPT-4oと遜色なく、非常に高品質です。 Copilotの出力の特徴は、「ビジネス文書としての簡潔さ」にあります。
Claude 3が「文脈や発言の意図」まで丁寧に記述するのに対し、Copilotは箇条書きや太字を効果的に使い、「決定事項」と「ネクストアクション」をパッと見て把握しやすい形式に落とし込むのが得意です。
特にTeams会議の文字起こし機能と連携させた場合、発言者を自動で特定して紐づける精度が高く、「誰が何をやるか」というタスク管理の観点では最も実務的なアウトプットを出してくる傾向があります。情緒的なニュアンスよりも、業務効率を最優先した質実剛健な議事録と言えます。
Copilotで議事録作成を効率化したい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
ChatGPTで議事録を作成する際の注意点とリスク
ChatGPTは議事録作成の強力なツールですが、万能ではありません。
利用方法を誤ると、重大なセキュリティインシデントや業務上のトラブルに繋がる可能性があります。
AIを活用する上で、必ず理解しておくべき注意点とリスクを解説します。
- 機密情報や個人情報を入力しない(情報漏洩リスク)
- AIの出力は鵜呑みにせず必ずファクトチェックを行う
- ChatGPT単体では文字起こしはできない
- 長文の文字起こしは一度に処理できない(文字数制限)
これらのリスクを正しく管理することが、AIを安全に活用するための鍵となります。
機密情報や個人情報を入力しない(情報漏洩リスク)
ChatGPTで議事録を作成する上で、最も注意すべき点です。
標準設定のChatGPT(無料版・有料版問わず)では、入力されたデータ(プロンプトや文字起こしテキスト)は、AIモデルの学習やサービス改善のために利用される可能性があります。
もし、会議の文字起こしテキストに以下のような情報が含まれていた場合、それらがOpenAIのサーバーに送信され、AIの学習データとして使われてしまうリスクがあります。
- クライアントの非公開情報、新製品の仕様、経営戦略
- 会議参加者の氏名、住所、電話番号、人事評価などの個人情報
これらの機密情報がAIの学習に使われ、将来的に別のユーザーへの回答として(意図せずとも)出力されてしまう可能性はゼロではありません。
このリスクを回避するためには、機密情報を含む会議の議事録作成に、標準のChatGPTを使用すべきではありません。
対策として、OpenAIはAPI経由での利用や、法人向けプラン(ChatGPT Enterpriseなど)を提供しており、これらは入力データをAIの学習に利用しない(オプトアウト)設定が可能です。
また、「ChatSense」のような、セキュリティを強化した法人向けAIサービスを利用することも有効です。これらはデータがAIの学習に悪用されないことを保証しており、安全に機密情報を扱うことができます。
こちらはNISTが提供する、AIシステムにおけるセキュリティとリスク管理のためのフレームワークを解説した公式ドキュメントです。 合わせてご覧ください。https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-2e2025.pdf
AIの出力は鵜呑みにせず必ずファクトチェックを行う
AIは、入力されたテキストを基に「それらしい」議事録を生成します。
しかし、AIはテキストの「意味」を人間のように深く理解しているわけではありません。
時には、文脈を誤解したり、重要な情報を見落としたり、あるいは存在しない情報(ハルシネーション)を生成したりすることさえあります。
特に、以下のような情報はAIが間違いやすいポイントです。
- 数値: 売上目標、コスト、期限、日付など。
- 固有名詞: 人名、会社名、製品名、専門用語など。(文字起こしが間違っていると、AIもそのまま間違えます)
- 決定事項のニュアンス: 「検討する」と「決定する」では意味が大きく異なります。AIがこの微妙なニュアンスを取り違える可能性があります。
AIが出力した議事録は、あくまで「草案(ドラフト)」です。
「Step 4. 出力された議事録を修正・確認する」でも強調した通り、必ず人間の目(できれば会議の内容を理解している人)が、内容の正確性をファクトチェックする必要があります。
AIの出力を鵜呑みにしてそのまま共有し、後で「数値が間違っていた」「決定事項が違った」となれば、AIを使った意味がありません。
AIを過信せず、最終的な責任は人間が持つという意識が不可欠です。
こちらはAIの出力するハルシネーション(嘘)を防ぐ方法や対策について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
ChatGPT単体では文字起こしはできない
これは実務上の重要な制約です。
多くの人が「会議の録音データ(MP3やWAVファイル)をChatGPTにアップロードすれば、議事録が完成する」と誤解していますが、2025年11月現在、標準のWeb版ChatGPTにその機能はありません。
ChatGPTが処理できるのは、基本的に「テキストデータ」のみです。
(※GPT-4oなどのマルチモーダル機能で短時間の音声認識は可能になりつつありますが、1時間のような長時間の会議録音を正確に文字起こしする用途には設計されていません)
したがって、議事録作成AIプロンプトを活用するための「前工程」として、必ず「Step 2. 音声データを文字起こし(テキスト化)する」作業が必要になります。
この作業には、前述の通り「Notta」や「CLOVA Note」といった、専用のAI文字起こしツールを利用するのが最も効率的です。
「ChatGPTを使えば、録音から議事録まで全自動」ではない、という現状の技術的制約を正しく理解しておく必要があります。
長文の文字起こしは一度に処理できない(文字数制限)
ChatGPTには、一度に入力できるテキストの量(トークン数、おおよそ文字数)に上限があります。
この上限は「コンテキストウィンドウ」と呼ばれます。
例えば、1時間の会議の文字起こしテキストが10万文字あったとします。
しかし、使用するAIモデル(例:GPT-4o)のコンテキストウィンドウが、仮に8万文字分(プロンプトやAIの回答分も含む)までだとすると、10万文字のテキスト全てを一度に入力することができません。
テキストが長すぎてエラーになるか、上限を超えた部分(例:テキストの末尾)が自動的に切り捨てられてしまい、AIの分析対象から漏れてしまいます。
これでは、会議の後半の重要な決定事項が議事録に反映されない、といった事態が起こり得ます。
GPT-5のような最新モデルではコンテキストウィンドウが大幅に拡大していますが、それでも物理的な上限は存在します。
対策としては、「タスクの分割」のコツでも触れたように、文字起こしテキスト自体を分割して入力する必要があります。
例えば、アジェンダごとや、15分ごとなど、意味のある単位でテキストを分割し、複数回に分けてChatGPTに読み込ませ、最後に全体をまとめるよう指示する、といった工夫が必要です。
こちらはChatGPTの最新モデル「GPT-4o」の最大コンテキストウィンドウの公式制限について記載されたOpenAIの公式ドキュメントです。 合わせてご覧ください。https://platform.openai.com/docs/models/gpt-4o
議事録AIプロンプトに関するよくある質問(FAQ)
最後に、議事録AIプロンプトに関して、ユーザーから寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
- 文字起こしにおすすめのツールはありますか?
- 発言者が不明な文字起こしデータでも議事録は作れますか?
- 無料版のChatGPTでも議事録は作成できますか?
文字起こしにおすすめのツールはありますか?
AI議事録作成の土台となる、高精度な文字起こし(テキスト化)は非常に重要です。
2025年現在、多くの高精度なAI文字起こしサービスが存在します。
選定のポイントは、「認識精度の高さ」「話者分離機能の有無」「専門用語への対応」などです。
代表的なツールとしては、以下のようなものがあります。
- Notta(ノッタ):非常に高い音声認識精度を誇るツールです。リアルタイム文字起こしや、録音データのインポートに対応しています。話者分離機能も強力で、多くのビジネスシーンで利用されています。
- CLOVA Note(クローバノート):LINE AIが開発したツールで、特に日本語の認識精度が高いと評価されています。スマートフォンアプリで手軽に録音・文字起こしができ、話者分離にも対応しています。
- AmiVoice(アミボイス):音声認識の老舗であるアドバンスト・メディアが提供するサービスです。医療、金融、製造など、業界特有の専門用語に強い辞書を搭載しているのが特徴で、専門的な会議の文字起こしに適しています。
これらのツールは、多くの場合、無料プラン(時間制限あり)やトライアルを提供しています。
ご自身の会議の録音データを実際に試してみて、最も認識精度が高いと感じるツールを選ぶことをお勧めします。
発言者が不明な文字起こしデータでも議事録は作れますか?
はい、作成可能です。
話者分離([Aさん][Bさん]といったタグ)がされていない文字起こしテキストであっても、ChatGPTはテキスト全体の内容を読み取り、議事録を作成することができます。
ただし、その場合、出力される議事録は「誰が言ったか」という情報が欠落したものになります。
例えば、「ToDoリスト」を抽出する際、テキスト内に「(佐藤さんが)来週までにやります」という発言があったとしても、話者情報がなければAIは「担当者:佐藤」と特定できません。
その結果、「担当者:不明」のタスクリストになったり、そもそもタスクとして認識されなかったりする可能性があります。
もし話者分離ができていないテキストから議事録を作る場合は、プロンプトを工夫する必要があります。
例えば、「発言者ごとの要約」を求めるのは諦め、「議論のトピックごとの要約」や「決定事項の抽出」にタスクを絞り込むのが現実的です。
AIはテキストから読み取れない情報を捏造することはできませんので、議事録の精度は、話者分離ができているテキストを使用した場合よりも低下することを許容する必要があります。
無料版のChatGPTでも議事録は作成できますか?
はい、無料版のChatGPTでも議事録の作成は可能です。
2025年8月にリリースされたGPT-5は、無料版を含む全てのユーザーにデフォルトで提供されています。
ただし、無料版のGPT-5利用にはいくつかの制限があります。
2025年11月現在の主な制限は以下の通りです。
- メッセージ数の制限: 5時間あたり10メッセージまで。(※議事録作成のように、長文テキストを入力し、修正を繰り返す作業は、この上限に達しやすい可能性があります)
- 思考モード(Thinkingモード)の制限: 1日1回まで。(※Thinkingモードは、長文の要約や複雑な推論など、議事録作成の精度を高めるために非常に有効な機能です)
簡単な会議の短い要約であれば無料版でも十分対応可能です。
しかし、1時間を超える会議の長文テキストを処理させたり、複雑なフォーマットを指定して高精度な議事録を日常的に作成したりするなど、業務レベルでAI議事録を本格的に活用したい場合は、これらの制限がボトルネックになります。
有料プラン(ChatGPT Plusなど)に登録することで、メッセージ上限が大幅に緩和され、Thinkingモードもより柔軟に利用できるようになります。
また、最新の高性能モデルや新機能への優先アクセスも得られます。
業務効率化への投資として、有料プランの利用を検討することをお勧めします。
AI時代を勝ち抜く「思考の錬金術」:あなたの脳を最強の「思考ジム」に変える方法
ChatGPTを日々の業務に取り入れているあなた。その便利さに頼りすぎるあまり、もしかしたら脳が“怠け者”になりかけているかもしれません。実際、マサチューセッツ工科大学(MIT)が発表した衝撃的な研究結果は、AIの使用が人間の認知活動を低下させる可能性を示唆しています。
しかし、これはAIの進化を止めるべきだという意味ではありません。東京大学をはじめとする世界トップクラスの研究機関では、ChatGPTを「答えを出すツール」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として活用し、逆に生産性と能力を向上させる「AI時代の賢い使い方」が実践されています。
この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」を分ける決定的な違いを、最新の知見を交えて徹底解説します。AIを真の「脳のジム」に変え、あなたのビジネススキルを飛躍的に向上させる具体的かつ実践的なAIプロンプト活用術を紹介します。
【警告】AIへの丸投げが「あなたの思考力を半減させる」かもしれない
もしあなたが「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」と考えているなら、それは危険なサインかもしれません。
AIが引き起こす「思考の外部委託」リスク
MITの研究結果によると、ChatGPTを使って文章作成を行った被験者は、自力で考えた人たちに比べて脳の活動が半分以下に低下することが確認されました。これは、人間が考えるというプロセスをAIに「外部委託」してしまい、脳が省エネモードに慣れてしまうことの証拠です。
この状態が習慣化すると、以下のような深刻なリスクが生じます。
- 深い洞察力の減退: AIの答えを鵜呑みにする習慣がつき、「本当に正しいか?」と多角的に疑い、検証する力が鈍ります。
- 創造性の低下: 脳が自発的な発想をサボるようになり、ゼロから斬新なアイデアを生み出す力が弱くなります。
- 記憶の定着不良: 楽をして手に入れた情報は、苦労して調べた情報と比べて、脳に定着しにくいことが認知科学的に知られています。
便利なツールに頼るうち、気づかぬうちに、本来あなたが持っていたはずの「考える力」という最も重要なビジネス資産を失う可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】東大・トップ企業が使う「AIを思考ツールに変える」3つの技術
AIを「思考停止の温床」ではなく、「思考加速の触媒」として使うにはどうすれば良いでしょうか。
「賢くなる人」は、AIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を拡張するパートナー」として利用しています。ここでは、誰でもすぐに実践できる、AIを「脳のジム」に変えるための3つの具体的なプロンプト活用術をご紹介します。
1. 最強の「反論・壁打ち相手」にする
自分のアイデアを磨くには、客観的な反論や別の視点からの検証が不可欠です。しかし、人間相手では遠慮が生じがちです。そこでChatGPTを、あなたの意見の「弱点を遠慮なく指摘するプロの専門家」として設定します。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げ、それぞれに対して代替案も提案してください。」
これにより、一人では見落としていた思考の穴やリスク要因を発見し、より強固で完成度の高い論理を構築する力が鍛えられます。
2. あえて「無知な生徒」として教える
「人に教えること」は、自分の理解度を試す最高の訓練です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にし、あなたが先生になって専門テーマを分かりやすく教え込むシミュレーションを行います。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問し、例を求めてください。」
AIから返ってくる「素朴な疑問」に答える過程で、自分の知識の曖昧な部分や、説明が抽象的だった箇所が明確になります。アウトプットを通じて知識が驚くほど深く整理され、記憶に定着します。
3. アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
「面白いアイデアを出して」とAIに頼むのは思考停止の始まりです。賢い人は、自分のアイデアの“種”や“キーワード”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせる「触媒」として利用します。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』に関する新しい企画を考えています。現在のキーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。その際、必ず『AとBの組み合わせ』といった形で提案理由も添えてください。」
AIが提案する意外な組み合わせや切り口は、あなたの発想を刺激する強力なヒントになります。最終的なアイデアに昇華させるのはあなた自身であり、このプロセスを通じて創造性が大きく向上します。
まとめ
企業が直面する労働力不足やDX推進の課題において、生成AIの活用は業務効率化の切り札として不可欠です。しかし、「何から始めればいいか分からない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルを感じている企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。
Taskhubは、日本初のアプリ型インターフェースを採用した生成AI活用プラットフォームです。200種類以上の実用的なAIタスクを、スマートフォンアプリのように「メール作成」「議事録作成」「画像からの文字起こし」「レポート自動生成」といったアプリとして選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
特に、会議の効率化においては、本記事で解説したような複雑なプロンプト入力は不要です。Taskhubの議事録アプリを使えば、高精度な議事録作成をはじめとする業務を、専門知識なしで実現できます。
セキュリティ面も万全で、TaskhubはAzure OpenAI Serviceを基盤に採用しているため、情報漏えいのリスクを最小限に抑え、機密情報を安全に扱うことが可能です。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートが付いているため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。導入後すぐに効果を実感できる設計になっており、複雑なプログラミングや高度なAI知識は一切不要です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードし、その全貌をご確認ください。Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。