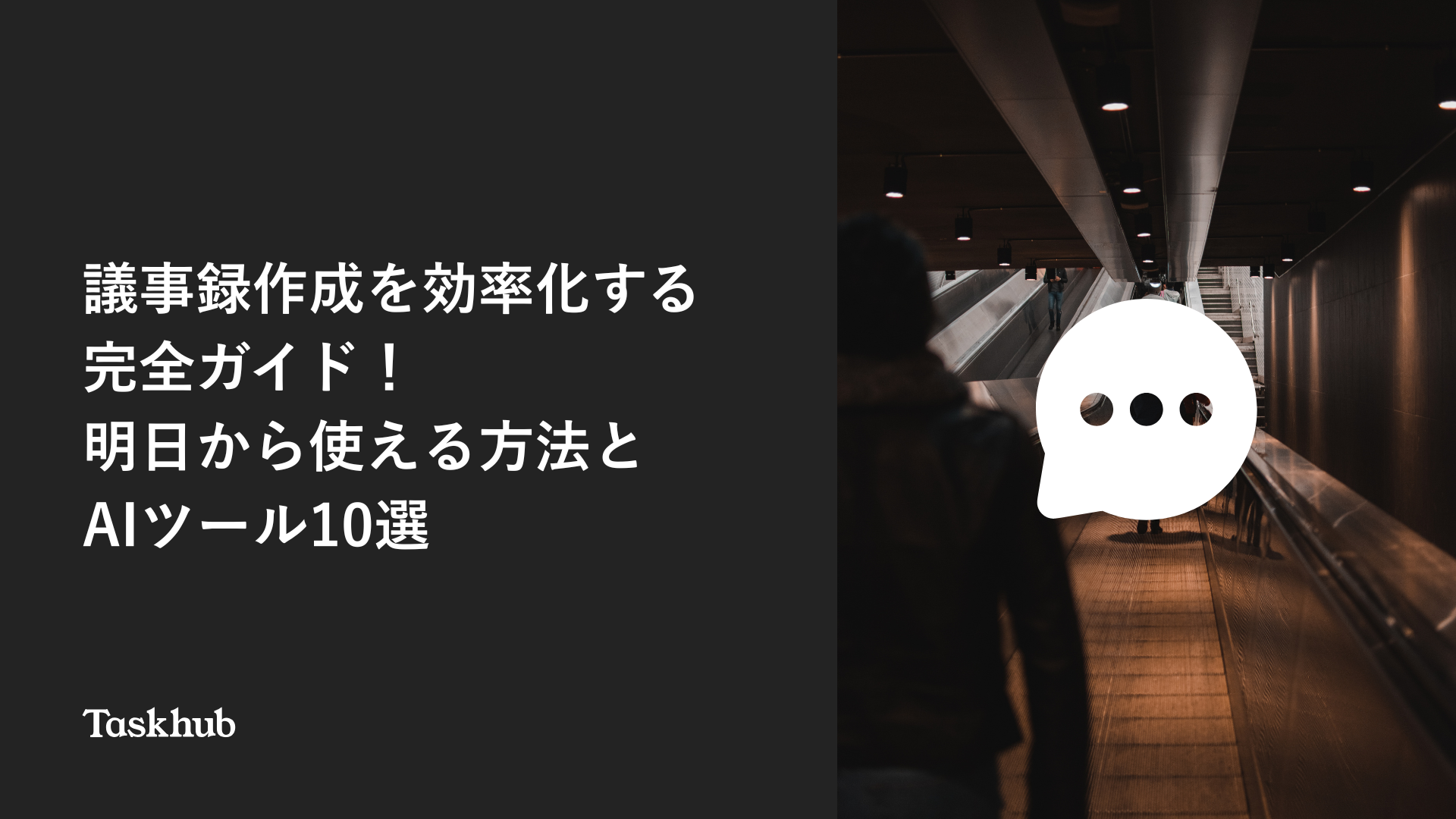「議事録の作成に時間がかかりすぎて、他の業務が進まない…。」
「会議の内容をうまくまとめられず、効率化したいけどどうすればいいか分からない。」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
本記事では、議事録作成を効率化する具体的なコツと、おすすめのAIツール10選、ツールの選び方について解説しました。
議事録作成の負担を軽減し、生産性を高めるための実践的な情報のみをご紹介します。
きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
議事録の効率化が必要とされる3つの理由
まず、なぜ議事録の効率化が求められるのか、その理由を3つ解説します。
- 決定事項とタスク(Todo)を明確にし、共有するため
- 会議内容を正確に記録し、後から振り返るため
- 議事録作成の時間を削減し、コア業務に集中するため
議事録の目的を再確認することで、効率化すべきポイントが見えてきます。
それでは、1つずつ順に解説します。
決定事項とタスク(Todo)を明確にし、共有するため
議事録の最も重要な役割の一つは、会議で「何が決まったのか」そして「誰が・いつまでに・何をするのか」を明確にすることです。
会議で多くの議論が交わされても、最終的な決定事項やネクストアクションが曖昧なままでは、プロジェクトは前進しません。
議事録作成を効率化するプロセスは、単に時間を短縮するだけでなく、会議の成果を確実に行動に移すための仕組み作りでもあります。
作成が遅れたり、要点が不明瞭だったりすると、参加者間の認識にズレが生じ、タスクの実行漏れや遅延が発生する原因となります。
効率化されたプロセスで作成された議事録は、会議直後に関係者へ迅速に共有され、全員が同じ方向を向いて次の行動を起こすための「共通の地図」として機能します。
これにより、プロジェクトの推進力が格段に向上します。
会議内容を正確に記録し、後から振り返るため
会議には、決定事項だけでなく、そこに至るまでの議論のプロセスや背景、共有された重要な情報が含まれています。
これらを正確に記録することで、議事録は「公式な記録」としての価値を持ちます。
会議に参加できなかったメンバーへの情報共有はもちろん、後日プロジェクトの経緯を振り返る際や、類似の課題に直面した際の参照資料として活用できます。
しかし、この記録作業が非効率だと、内容が不正確になったり、重要な情報が抜け落ちたりしがちです。
例えば、手書きのメモだけに頼ると、詳細なニュアンスや具体的な発言内容を再現するのは困難です。
議事録作成を効率化し、録音データとテキストを紐づけるなどの工夫をすることで、記録の正確性が向上します。
正確な記録は、組織のナレッジ蓄積にも繋がり、将来的な意思決定の質を高める資産となります。
議事録作成の時間を削減し、コア業務に集中するため
多くのビジネスパーソンにとって、議事録作成は本来のコア業務(企画、開発、営業など)に付随するノンコア業務です。
しかし、会議が多ければ多いほど、この議事録作成にかかる時間は膨大になります。
例えば、1時間の会議の議事録作成に1時間かかっている場合、週に5回の会議があれば、週5時間、月20時間も費やしている計算になります。
この時間を大幅に削減できれば、その分をより生産性の高い、企業の利益に直結するコア業務に充てることができます。
議事録の効率化は、単なる「時短」を超え、個人の生産性を最大化し、組織全体の競争力を高めるための重要な経営課題と言えます。
こちらは、不要な会議が従業員の生産性に与える金銭的コストについて具体的に分析したレポートです。 合わせてご覧ください。 https://softwarefinder.com/resources/productivity-cost
時間をかけて完璧な議事録を作ることよりも、必要な情報を素早く正確にまとめ、次のアクションに移るスピード感を重視することが求められています。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
なぜ議事録作成に時間がかかってしまうのか?
議事録の効率化が必要な理由は分かりましたが、そもそもなぜ作成に時間がかかってしまうのでしょうか。
主な原因として以下の3つが挙げられます。
- 会議の要点をリアルタイムで整理できない
- 音声の聞き直しと文字起こしに時間が取られる
- フォーマットが統一されておらず清書に手間がかかる
これらのボトルネックを解消することが、効率化への第一歩です。
それでは、1つずつ順に解説します。
会議の要点をリアルタイムで整理できない
議事録作成に時間がかかる大きな原因は、会議中にリアルタイムで情報を整理できていないことです。
会議中は、複数の参加者が同時に発言したり、議論が脱線したり、論点が多岐にわたったりすることがよくあります。
その中で、「決定事項」「タスク」「重要な意見」「背景情報」を瞬時に判別し、構造化しながらメモを取るのは高度なスキルが必要です。
多くの人は、まず発言された内容をすべて書き出すことに集中してしまい、後からそれらを整理し直すという二度手間をかけています。
また、会議の議論に集中するあまり、メモを取るのが追いつかなくなってしまうケースも少なくありません。
結果として、会議終了後にメモを見返しても、何が重要だったのか分からなくなったり、情報の整理に膨大な時間がかかったりしてしまいます。
リアルタイムで要点を整理する能力の欠如が、議事録作成時間を長引かせる根本的な原因の一つです。
音声の聞き直しと文字起こしに時間が取られる
会議の内容を正確に記録しようとするほど、ICレコーダーなどで録音した音声を後から聞き直す作業が発生します。
特に、専門用語が多い会議や、発言が聞き取りにくい部分があると、何度も再生と停止を繰り返し、文字起こし(テープ起こし)を行うことになります。
一般的に、1時間の会議の音声を全て文字起こしするには、3時間から5時間程度かかると言われています。
これは非常に時間のかかる作業であり、議事録作成における最大のボトルネックです。
また、文字起こしが完了した後も、その膨大なテキストデータから要点を抜き出し、議事録の形にまとめる作業が別途必要になります。
「言った言わない」のトラブルを防ぐために正確性を期すことは重要ですが、音声を一から聞き直すプロセスが非効率であることは間違いありません。
この「聞き直し」と「文字起こし」の時間をいかに短縮するかが、議事録効率化の鍵となります。
フォーマットが統一されておらず清書に手間がかかる
議事録のフォーマット(テンプレート)が組織やチーム内で統一されていないことも、時間を浪費する原因です。
フォーマットが決まっていないと、作成者は毎回「どのような項目を」「どのような順序で」「どの程度の詳細さで」書けばよいか迷ってしまいます。
その結果、不要な情報を詳細に書きすぎたり、逆に必要な情報(決定事項やタスク)が抜け落ちたりします。
また、作成者によって議事録のスタイルがバラバラだと、読む側も必要な情報を素早くキャッチすることができません。
さらに、メモ書きの状態から、他人が読めるように文章を整える「清書」の作業にも時間がかかります。
特に、「話し言葉」をそのままメモしている場合、それを「書き言葉」に直したり、冗長な表現を削除したりする作業に手間がかかります。
フォーマットの不統一と清書の手間が、議事録作成の最終段階で時間を奪っているのです。
議事録作成を効率化する8つの具体的なコツ
ここからは、議事録作成を効率化するための具体的な8つのコツを紹介します。
- コツ1:会議前にアジェンダとテンプレートを準備・共有する
- コツ2:会議中に要点・決定事項・Todoを整理しながらメモする
- コツ3:「書き言葉」を意識してメモを取る
- コツ4:複数人でリアルタイムに共同編集する
- コツ5:WEB会議ツールの録画や文字起こし機能を活用する
- コツ6:ドキュメントツールの校正機能を利用する
- コツ7:Wチェック(校正・レビュー)で手戻りを防ぐ
- コツ8:議事録作成の専用ツールを導入する
これらのコツを実践することで、議事録作成のスピードと質を向上させることができます。
それでは、1つずつ順に解説します。
コツ1:会議前にアジェンダとテンプレートを準備・共有する
議事録作成の効率化は、会議が始まる前から始まっています。
まず、会議のアジェンダ(議題)を事前に明確にし、参加者に共有しておくことが極めて重要です。
アジェンダが明確であれば、会議のゴールがはっきりし、議論が脱線しにくくなります。
議事録作成者も、アジェンダの項目に沿ってメモを取る準備ができるため、会議中の情報整理が格段に楽になります。
次に、議事録のテンプレートを準備します。
テンプレートには、「会議名」「日時」「場所」「参加者」といった基本情報に加え、「アジェンダ」「議論の要点」「決定事項」「Todo(担当者・期限)」といった項目をあらかじめ用意しておきます。
このテンプレートをアジェンダと合わせて事前に共有することで、参加者全員が「この会議で何を決め、何を記録すべきか」を意識できます。
会議当日は、このテンプレートを埋めていくだけで議事録の骨格が完成するため、清書の手間が大幅に削減されます。
こちらは、会議の有効性を高めるため、アジェンダを「少なくとも24時間前」に共有することを強く推奨している米国国立衛生研究所(NIH)の論文です。 合わせてご覧ください。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6743516/
コツ2:会議中に要点・決定事項・Todoを整理しながらメモする
会議中は、発言のすべてを記録しようとするのではなく、「要点」「決定事項」「Todo」を意識してメモを取ることが重要です。
前述の通り、すべてを文字起こししようとすると、情報整理が追いつかなくなります。
アジェンダの項目ごとに、議論のポイントは何か、結論として何が決まったのか、誰が何をいつまでに行うのか、という点を中心に記録します。
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると、情報が整理しやすくなります。
特に「決定事項」と「Todo」は、議事録の中で最も重要な項目です。
これらが曖昧にならないよう、会議の最後にもう一度口頭で確認し、議事録に明確に記載する習慣をつけると良いでしょう。
例えば、「(決定)〇〇の施策を実行する」「(Todo)Aさんが、Bの資料をCさんへ今週金曜までに送付する」といった具体的な記述を心がけます。
会議中にここまで整理できていれば、会議終了後の作業はほぼゼロに近づきます。
コツ3:「書き言葉」を意識してメモを取る
議事録を効率的に作成するために、メモを取る段階から「書き言葉」を意識することも有効なコツです。
会議中の発言は、「えー」「あのー」といったフィラー(言い淀み)や、冗長な表現、倒置法などが含まれる「話し言葉」が中心です。
これらをそのままメモしてしまうと、後から清書する際に、文章を整える作業に多くの時間が必要になります。
例えば、「〇〇さんは、A案がいいんじゃないかって、思うんですよね、理由は…」という発言をメモする際、
「〇〇さん:A案を推奨。理由…」というように、瞬時に要約し、簡潔な書き言葉に変換して記録します。
もちろん、全てのメモを完璧な書き言葉にする必要はありませんが、特に重要な発言や決定事項については、後から見返しても意味が通じるように意識してメモを取ることが重要です。
この一手間を会議中にかけることで、会議後の清書作業の負担を劇的に減らすことができます。
コツ4:複数人でリアルタイムに共同編集する
会議の規模や重要度に応じて、議事録の作成を複数人(例えば、書記とサブ書記)で分担し、リアルタイムで共同編集するのも非常に効率的な方法です。
GoogleドキュメントやMicrosoft 365などのクラウドベースのドキュメントツールを使えば、同じ文書に同時にアクセスし、編集することが可能です。
例えば、一人がメインの議論の流れや決定事項を記録し、もう一人がタスクや詳細な補足情報を記録するといった役割分担ができます。
また、ファシリテーターがアジェンダに沿って議論を進めながら、その場で決定事項を画面共有された議事録に直接打ち込んでいく方法もあります。
これにより、会議の進行と議事録の作成が同時に完了します。
会議終了時には議事録のドラフトがほぼ完成しているため、参加者全員でその場で内容を確認し、認識のズレを修正することも可能です。
一人で全てを背負い込むのではなく、テクノロジーを活用して共同作業を行うことで、作成の負担と時間を大幅に削減できます。
こちらは、リアルタイム共同編集ツールの実際の利用ログを分析したところ、真の「同時」編集は稀であり、多くは「交互に(非同期的に)」編集されていたことを示した研究です。 合わせてご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/328679433_Spacetime_Characterization_of_Real-Time_Collaborative_Editing
コツ5:WEB会議ツールの録画や文字起こし機能を活用する
近年、ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetといった主要なWEB会議ツールには、会議を録画する機能や、リアルタイムで文字起こし(トランスクリプション)を行う機能が標準搭載またはオプションで提供されています。
これらの機能を活用することは、議事録の効率化に直結します。
特に、後から「あの発言は何だったか」と確認したい場合に、録音データだけでなく録画データ(誰が話していたか)があると、文脈の理解が容易になります。
また、AIによるリアルタイム文字起こし機能を使えば、会議中にメモが追いつかなかった部分も、後からテキストで素早く検索・確認できます。
ただし、AIの文字起こしは100%完璧ではありません。
専門用語や固有名詞の誤認識、話者の識別ミスなども発生するため、あくまで「メモの補助」として活用するのが賢明です。
すべての文字起こしを鵜呑みにするのではなく、決定事項やタスクを中心に、重要な部分の確認用として利用することで、聞き直しの時間を大幅に削減できます。
コツ6:ドキュメントツールの校正機能を利用する
議事録の清書段階で時間を取られがちなのが、「誤字脱字」や「日本語の誤用」のチェックです。
作成した議事録を何度も読み返し、修正する作業は意外と時間がかかります。
ここで役立つのが、GoogleドキュメントやWordなどに搭載されている「校正機能」です。
これらのツールは、単純な誤字脱字だけでなく、「ら抜き言葉」や「二重敬語」といった文法的な誤り、不自然な言い回しなどを自動で検出し、修正候補を提示してくれます。
完璧ではありませんが、機械的なチェックをツールに任せることで、人間は内容の正しさや要点の抜け漏れといった、より本質的な部分の確認に集中できます。
また、より高度な文章校正を行いたい場合は、専門の校正ツールを導入することも一つの手です。
こうした機能を活用して、文章の体裁を整える時間を短縮し、議事録完成までのスピードを上げることが、効率化に繋がります。
コツ7:Wチェック(校正・レビュー)で手戻りを防ぐ
議事録を効率化する上で、スピードは重要ですが、それ以上に「正確性」が求められます。
特に決定事項やTodoの記述に誤りがあると、後で大きな手戻りやトラブルに発生する可能性があります。
そこで有効なのが、Wチェック(ダブルチェック)の体制です。
議事録の作成者がドラフトを完成させた後、会議の主要な参加者やファシリテーターなど、別の人にレビュー(校正)を依頼します。
レビュー者は、客観的な視点で内容を読み、事実誤認がないか、決定事項やタスクの担当・期限に間違いがないか、ニュアンスが正しく伝わるかなどを確認します。
作成者本人では気づきにくいミスや、認識のズレをこの段階で修正することで、議事録の質と正確性を担保できます。
一見、レビューの時間が追加でかかるように思えますが、不正確な議事録によって後から発生する手戻りや混乱のコストに比べれば、遥かに効率的です。
迅速なレビューと承認のフローを確立することが、結果として全体の効率化に貢献します。
コツ8:議事録作成の専用ツールを導入する
これまで紹介したコツを実践するだけでも、議事録作成は大幅に効率化できます。
しかし、さらなる飛躍的な効率化を目指すのであれば、「議事録作成の専用ツール」の導入が最も強力な解決策となります。
これらのツールは、AI(人工知能)を活用して、会議の音声データを高精度に文字起こしするだけでなく、話者の識別、キーワードの抽出、さらには自動で要約を作成する機能まで備えています。
手作業での文字起こしにかかっていた膨大な時間をほぼゼロにできる可能性があります。
また、文字起こしされたテキストと音声データが紐づいているため、気になる部分をクリックするだけで該当箇所の音声をピンポイントで聞き直すことも可能です。
ツールの導入にはコストがかかりますが、議事録作成に費やしていた人件費や、コア業務に集中できる時間を考慮すれば、十分に投資対効果が見込めるケースが多いです。
次のセクションでは、具体的なおすすめのAIツールを紹介します。
企業でのAI活用を検討されている場合は、こちらのChatGPT企業利用の完全ガイドも合わせてご覧ください。
議事録の効率化におすすめのAIツール9選
ここからは、議事録の効率化を劇的に進める、おすすめのAI搭載ツールを9個紹介します。
こちらは、AIミーティングアシスタント市場が2035年にかけて年平均25%以上で急成長するという市場予測レポートです。 合わせてご覧ください。 https://www.marketresearchfuture.com/reports/ai-meeting-assistants-market-12218
- スマート書記
- Rimo Voice
- AI議事録取れる君
- AmiVoice ScribeAssist
- YOMEL
- Notta
- ワンミニッツ
- toruno
- CrewWorks
これらのツールは、文字起こしの精度や要約機能、連携機能などにそれぞれ特徴があります。
それでは、1つずつ順に解説します。
おすすめツール1:スマート書記
スマート書記は、議事録作成にかかる時間を最大90%削減することを謳うAI議事録サービスです。
最大の特徴は、高精度の文字起こし機能に加えて、議事録の「清書」作業をAIが強力にサポートしてくれる点です。
例えば、文字起こし結果から不要なフィラー(「あー」「えー」など)を自動で除去したり、発言の要点をAIが自動で要約したりする機能を備えています。
また、議事録エディタ機能が充実しており、文字起こしされたテキストと音声がタイムスタンプで紐づいているため、確認・修正作業が非常にスムーズです。
テキストをクリックすれば該当の音声が再生され、聞き直しにかかる時間を大幅に短縮できます。
さらに、最大20名までの話者を自動で分離する機能も搭載しており、「誰が何を言ったか」が明確になります。
大手企業や自治体での導入実績も豊富で、セキュリティ面でも安心して利用できるため、議事録の作成から管理までを一気通貫で効率化したい企業におすすめです。
おすすめツール2:Rimo Voice
Rimo Voiceは、「1時間の音声を5分で文字起こし」できるスピードと、日本語に特化した高い認識精度が特徴のAI議事録サービスです。
日本語特有の言い回しや専門用語、方言などにも強く、自然な日本語の文章を生成することに優れています。
このツールの便利な点は、文字起こしされたテキストと音声・動画データが完全にシンク(同期)していることです。
テキストの任意の箇所をクリックするだけで、該当する音声や動画の部分を即座に再生できます。
これにより、議事録の確認や編集、特定の発言内容の聞き直し作業が劇的に効率化されます。
また、最新のAIを活用した要約生成機能も搭載しており、長い会議の文字起こし結果から、要点を素早く抽出することが可能です。
操作インターフェースもシンプルで直感的に使いやすく、ITツールに不慣れな人でも安心して導入できる点も評価されています。
おすすめツール3:AI議事録取れる君
AI議事録取れる君は、AIによる高精度の文字起こしと自動要約機能を備えたツールです。
ZoomやMicrosoft Teamsとの連携に強みがあり、会議に参加者全員の声を識別しながら議事録を作成できる点が特徴です。
単に文字起こしをするだけでなく、AIが会議の重要なポイントを自動で抽出し、読みやすい議事録の形式に整形してくれます。
これにより、会議終了後すぐに共有可能な議事録が完成し、情報伝達のスピードを格段に向上させることができます。
また、多言語対応もしており、自動翻訳機能によって発言と翻訳を並べて表示することが可能です。
グローバルなチームでの利用にも適しています。
さらに、固有名詞や専門用語などをあらかじめ登録しておく「単語登録機能」も充実しており、特定の業界や企業独自の言葉に対しても認識精度を高めることができます。
おすすめツール4:AmiVoice ScribeAssist
AmiVoice ScribeAssistは、音声認識技術で高い実績を持つアドバンスト・メディア社が提供する議事録作成支援ツールです。
最大の特徴は、「スタンドアローン型」である点です。
インターネットに接続していないオフラインの環境でも音声認識が可能で、機密情報を外部のサーバーに送信する必要がありません。
そのため、金融機関や官公庁、医療機関など、特に高度なセキュリティ要件が求められる組織でも安心して導入できます。
もちろん、リアルタイムでの文字起こしだけでなく、録音済みの音声ファイルを取り込んで文字起こしするバッチ認識にも対応しています。
AIが発言者を自動で判別する「AI話者識別機能」や、用途に応じて使い分けられる「エディットモード」と「ファシリテーションモード」など、議事録作成を効率化するための便利な機能が豊富に搭載されています。
オフライン環境でも利用可能なAI自動要約機能も搭載されています。
おすすめツール5:YOMEL
YOMEL(ヨメル)は、「会議後、ワンクリックで9〜10割の議事録が完成する」という手軽さと実用性を追求したAI議事録ツールです。
対面会議でもWEB会議でも利用可能で、専用のデバイスなどは不要です。
ワンクリックで録音、文字起こし、AI要約までを自動で行います。
このツールのユニークな特徴は、料金体系です。
多くのツールがユーザー数に応じて課金される「ユーザー課金」なのに対し、YOMELは利用できるID(ユーザー数)が無制限の「時間課金」モデルを採用しています(プランによる)。
そのため、特定の部署やチームだけでなく、全社的に導入する場合でもコストを抑えやすく、利用の定着を促進しやすいメリットがあります。
複雑な議論でも的確に要点をまとめる要約機能や、シンプルな操作画面も魅力で、組織全体の生産性向上に貢献します。
おすすめツール6:Notta
Notta(ノッタ)は、世界58カ国語に対応する高精度なAI音声自動文字起こしサービスです。
個人からビジネスチームまで幅広く利用されています。
リアルタイムでの文字起こしはもちろん、録音済みの音声ファイルや動画ファイルのインポートにも対応しており、あらゆる音声データをテキスト化できます。
WEB会議ツールとの連携も可能で、会議の内容を自動で録音・文字起こしします。
Nottaの強みは、その高い編集機能とデータ同期機能にあります。
文字起こし結果は簡単に編集でき、誤認識した部分を素早く修正できます。
また、データはクラウドで同期されるため、PC(Windows/Mac)でもスマートフォン(iOS/Android)でも、同じデータにアクセスして作業の続きを行うことができます。
AIによる要約機能も搭載しており、長いテキストから重要なポイントを瞬時に把握するのに役立ちます。専用のAIボイスレコーダー端末との連携も特徴です。
おすすめツール7:ワンミニッツ
ワンミニッツ(OneMinutes)は、100以上の言語に対応した多言語翻訳機能が特徴であるAI議事録ツールです。
会議で話された言葉をリアルタイムで翻訳・変換し、文字起こしを行います。
グローバルなチームや海外の取引先との会議が多い企業にとって、非常に強力なサポートとなります。
議事録はリアルタイムで参加者全員に共有・編集が可能で、会議中に聞き逃した内容もテキストで即座に確認できます。
AIによる自動要約機能も搭載しており、会議全体のサマリーや議題ごとの課題、決定事項を自動で出力します。商談分析機能なども充実しています。
また、業界特有の専門用語などを辞書登録することで、文字起こしや翻訳の精度をさらに高めることができます。
ZoomやTeamsなど主要なWEB会議ツールとも設定不要で連携でき、手軽に利用開始できる点も魅力です。
おすすめツール8:toruno
toruno(トルノ)は、テキスト(文字起こし)だけでなく、音声と画面キャプチャ(画像)の3つを同時に記録できるWindows専用のAI議事録ツールです。
「会議を丸ごと記録する」というコンセプトが特徴です。
会議中に「このスライド、重要だったな」という場面で、後から録画を見返すのは大変ですが、torunoなら自動で記録された画面キャプチャと文字起こし結果を照らし合わせながら、効率的に会議を振り返ることができます。
操作は非常に簡単で、WEB会議ツールと一緒に起動して録音開始ボタンを押すだけです。
面倒な連携設定は不要で、インストール後すぐに使えます。
AIによる自動要約機能も搭載されており、会議中の発言にタグ付け(重要、タスクなど)する機能と合わせて、議事録作成時の要点整理に役立ちます。
主に個人利用や小規模チームでの利用に適していますが、法人向けプランも提供されています。
おすすめツール9:CrewWorks
CrewWorks(クルーワークス)は、単なる議事録ツールではなく、チャット、Web会議、タスク管理、ファイル共有など、ビジネスコミュニケーションに必要な機能を一つにまとめた「統合コミュニケーションプラットフォーム」です。
その機能の一部として、AIによる議事録作成機能が搭載されています。
最大の特徴は、議事録と他の情報がシームレスに連携することです。
Web会議を録画すると、AIが自動で文字起こしを行い、議事録を作成します。
さらに、その議事録内で発生したタスクをそのままタスク管理機能に登録したり、関連するチャットやファイルと紐づけたりすることができます。
情報がCrewWorks内に一元管理されるため、「あの会議の決定事項、どこだっけ?」と探す手間がなくなります。
議事録作成の効率化だけでなく、プロジェクト管理全体の効率化を目指す企業に適したオールインワンツールです。
議事録 効率化ツールを選ぶ際の3つのポイント
最後に、数ある議事録 効率化ツールの中から自社に最適なものを選ぶための3つのポイントを解説します。
- ポイント1:文字起こしや要約の精度は十分か
- ポイント2:操作は簡単で編集しやすいか
- ポイント3:セキュリティ対策や連携機能は充実しているか
これらのポイントを比較検討することで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。
こちらは、IDC MarketScapeがベンダー評価の主要基準として、短期的な「実行力(Capabilities)」と中長期的な「戦略(Strategy)」の2軸を使用していることを示すレポートです。 合わせてご覧ください。 https://www.genesys.com/resources/idc-marketscape-worldwide-conversational-intelligence-and-analytics-2024-vendor-assessment
それでは、1つずつ順に解説します。
ポイント1:文字起こしや要約の精度は十分か
議事録 効率化ツールの根幹となる機能は、AIによる「文字起こし」と「要約」です。
ここの精度が低いと、結局、手作業での修正に多くの時間がかかり、期待した効率化が実現できません。
文字起こしの精度を判断する際は、単なる認識率の高さだけでなく、自社の業界特有の専門用語や固有名詞をどの程度正確に認識できるかが重要です。
多くのツールには無料トライアル期間が設けられているため、実際の会議(特に専門用語が飛び交う会議)でテストし、その精度を必ず確認しましょう。
また、話者を正しく識別できるか(話者分離機能)も重要なポイントです。
要約機能についても、AIが生成した要約が、会議の論点や決定事項を的確に捉えているかを確認する必要があります。
ツールのデモやトライアルを活用し、自社のニーズに合った精度のツールを選びましょう。
こちらは、Zoom、Copilot、TeamsなどのAI要約・文字起こし精度を比較し、ツールによっては「マイナーな ハルシネーション(誤情報生成)」が見られたと評価したレポートです。 合わせてご覧ください。 https://www.zoom.com/en/resources/ai-performance-report/
ポイント2:操作は簡単で編集しやすいか
どれだけ高機能なツールであっても、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。
特に、議事録作成ツールは、ITリテラシーが高い人だけでなく、社内の誰もが簡単に使える必要があります。
導入後の定着を成功させるためには、「直感的な操作性」が不可欠です。
例えば、録音の開始・停止がワンクリックでできるか、文字起こし結果の編集(修正や削除)がスムーズに行えるか、といった点をチェックします。
また、文字起こしされたテキストと音声データが連動しており、テキストをクリックするだけで該当箇所の音声をピンポイントで再生できる機能は、編集作業の効率を大きく左右するため、必須と言えるでしょう。
無料トライアル期間中に、実際に議事録を作成する可能性のある複数の従業員に触ってもらい、操作感に関するフィードバックを集めることをお勧めします。
ポイント3:セキュリティ対策や連携機能は充実しているか
議事録には、社外秘の情報や未公開のプロジェクト内容、人事に関する情報など、機密性の高い情報が含まれることが多々あります。
こちらは、AI(またはAI活用SaaS)に起因するセキュリティ事故の経験率が58.5%に達するという、国内の実態調査レポートです。 合わせてご覧ください。 https://assured.jp/column/shadow-ai-survey
そのため、ツールのセキュリティ対策は最も重要視すべきポイントの一つです。
データがどのように暗号化されているか、国内外のどのデータセンターで管理されているか、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの第三者認証を取得しているかなどを確認しましょう。
特に機密性が高い会議で利用する場合は、インターネットに接続せずに利用できる「スタンドアローン型(オフライン型)」のツール(例:AmiVoice ScribeAssist)を選ぶという選択肢もあります。
また、既存の業務フローを妨げない「連携機能」も重要です。
ZoomやTeamsなどのWEB会議ツールとシームレスに連携できるか、作成した議事録をGoogleドライブやSlack、Chatworkなどに簡単に共有できるか、といった点を確認し、自社のIT環境にスムーズに組み込めるツールを選びましょう。
機密情報を取り扱う際のセキュリティリスク対策として、生成AIの社内規定について詳しく解説した記事もあります。 合わせてご確認ください。
AIで仕事が楽に?その裏で忍び寄る「スキル陳腐化」の罠
議事録作成などのノンコア業務がAIで効率化され、喜んでいませんか?しかし、AIはすでに「コア業務」にも進出しています。スタンフォード大学の研究では、AIが新人のスキルを急速に向上させる一方で、経験豊富なベテランのスキルが相対的に目立たなくなる「スキルの均質化」が示唆されています。
【警鐘】AIはあなたの「専門スキル」をコモディティ化する
スタンフォード大学がコールセンターで行った研究によると、生成AIの支援を受けた従業員は生産性が平均14%向上しました。特に影響が大きかったのは、経験の浅い従業員でした。彼らはAIの助けを借りて、ベテランのノウハウをすぐに習得できたのです。
これは一見良いことのように思えますが、裏を返けば、AIを使えば「誰もが平均点」を出せるようになるということです。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 判断力の低下:AIが示す「最適解」に頼りきりになり、例外的な状況や複雑な背景を考慮する力が鈍る。
- スキルの停滞:AIの補助なしでは仕事ができなくなり、自ら困難な課題を乗り越えてスキルを磨く機会が失われる。
- 市場価値の低下:あなたの「専門性」がAIによって平均化され、他の人との差別化が困難になる。便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、あなたが長年培ってきたはずの「専門的な価値」が失われていく可能性があるのです。引用元:スタンフォード大学の研究では、生成AI(チャットボット)の導入により、コールセンター従業員の生産性が平均14%向上し、特に新人やスキルの低い労働者のパフォーマンスが大幅に改善したことが示されました。これにより、スキル格差が縮小する可能性が示唆されています。(Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. “Generative AI and Firm-Level Productivity” 2023年)
実践:AIを「専門性を磨く砥石」に変える使い方
では、「賢くなる人」はAIをどう使っているのでしょうか。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「自らの専門性を高めるパートナー」として利用しています。
- AIの提案を「レビュー」する:AIの出した答えを鵜呑みにせず、あえて批判的に検討し、改善点やリスクを指摘する。
- AIに「困難な課題」をぶつける:自分の専門分野で最も難しい課題をAIに相談し、その回答をたたき台にして、さらに深い考察を行う。
- AIに「説明」させる:AIの回答の根拠や思考プロセスをAI自身に説明させ、その論理の穴を見つけ出す訓練をする。
まとめ
「議事録作成に時間がかかりすぎる」「会議の要点をまとめるのが大変」といった課題を抱える中で、AIツールの導入が注目されています。
しかし、実際には「どのツールを選べばいいかわからない」「セキュリティが心配で導入できない」「社内にAIを活用できる人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、本記事で紹介したような「議事録作成」や「会議の要約」はもちろん、メール作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、議事録のような機密情報を含む内容でも情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに議事録作成をはじめとする業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や議事録作成機能の詳細をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社の業務効率化を一気に加速させましょう。