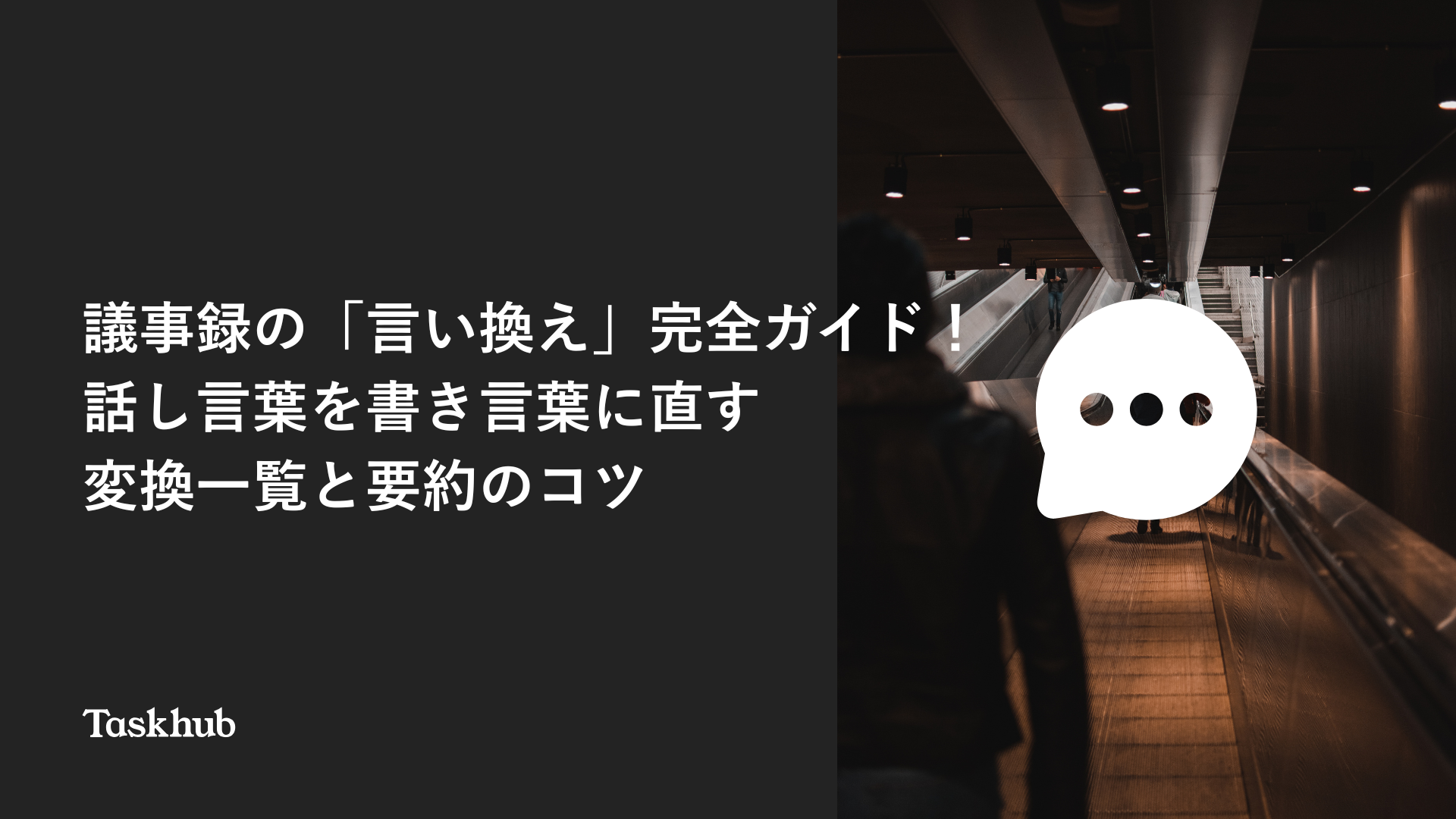「会議の音声をそのまま文字起こししたけれど、読みづらくて内容が入ってこない」
「話し言葉をビジネスに適した書き言葉に直すのに、毎回膨大な時間がかかってしまう」
議事録作成において、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?
そのままの発言録は、どうしても冗長になりがちで、後から読み返す資料としての価値が下がってしまいます。
本記事では、議事録の質を劇的に向上させるための「言い換え」テクニックと、具体的な変換フレーズ一覧、そして最新AIを活用した効率化の手法について解説します。
多くの企業のドキュメント改善を支援してきた知見をもとに、誰でもすぐに実践できるノウハウを凝縮しました。
この記事を読めば、読みやすく質の高い議事録を、これまでの半分の時間で作成できるようになるはずです。
なぜ議事録に「言い換え」が必要なのか?話し言葉と書き言葉の違い
会議中の発言をそのまま文字にするだけでは、優れた議事録とは言えません。
読み手にとって価値ある記録にするためには、話し言葉から書き言葉への適切な「言い換え」が不可欠です。
ここでは、単なる記録とビジネス文書としての議事録の違い、そして最低限押さえておくべき書き言葉のルールについて解説します。
この基本を理解するだけで、議事録の読みやすさは格段に向上します。
話し言葉と書き言葉の音声学的・言語学的な違いについて、より専門的な見地から学びたい方は、国立国語研究所の資料も参考になります。 https://www2.ninjal.ac.jp/tanken/2021/hanashikotoba-to-kakikotoba/
そのまま記録するのはNG?「発言録」と「議事録」の決定的な違い
会議の内容を録音し、それを一字一句漏らさずに文字に起こしたものは「発言録(逐語録)」と呼ばれます。
これは、裁判の記録やインタビュー記事の素材としては有用ですが、ビジネスの現場における「議事録」としては不適切です。
なぜなら、ビジネスにおける議事録の目的は「決定事項の確認」や「次回アクションの共有」にあるからです。
「あー」や「えー」といった意味のない言葉や、話の脱線まで含んだ発言録は、要点をつかむのに時間がかかり、読み手にストレスを与えてしまいます。
一方で、優れた議事録は、発言の意図を汲み取り、要約し、整えられた文章で構成されています。
つまり、情報の取捨選択と言い換えが行われているのです。
読み手の時間を奪わず、必要な情報を瞬時に理解できるように加工することこそが、議事録作成者の重要な役割といえるでしょう。
読み手がストレスを感じない「書き言葉」の基本ルール
話し言葉(口語)と書き言葉(文語)は、明確に使い分ける必要があります。
普段の会話では問題なくても、文章になると稚拙に見えたり、信頼性を損なったりする表現があるからです。
例えば、「ちゃんと確認する」は「適切に確認する」へ、「いろんな意見」は「多様な意見」へと変換するのが基本です。
また、「ら抜き言葉」や「い抜き言葉」にも注意が必要です。
「見れる」ではなく「見られる」、「書いてる」ではなく「書いている」と正しく記述することで、文書全体の品格が保たれます。
さらに、主語と述語のねじれを解消することも重要です。
話し言葉では、主語が省略されたり、途中で主語が変わったりすることが頻繁に起こります。
議事録にする際は、「誰が」「どうするのか」を明確にし、論理的に破綻のない文章へと修正しましょう。
日本語の話し言葉を書き言葉へ自動変換するコーパス構築や分析については、言語処理学会のこちらの論文で詳細に論じられています。
音声認識を用いたアプリケーションの増加に伴い,音声言語を精緻に捉える需要性が高まっている.しかし,音声認識の出力結果は,自然会話で生成される音声言語をそのまま書き起こすため,言い淀みや冗長表現を含む話し言葉テキストとなっており,可読性が低いことが課題である.そこで,音声認識結果の可読性を向上させるため,話し言葉を書き言葉に変換する技術に我々は着目する.この技術は,音声認識の後段の処理である翻訳や要約など,書き言葉テキストの入力が望ましいタスクにおいても有用だと考えられる.
引用:https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2020/pdf_dir/P2-4.pdf
文末の統一(「です・ます」調と「だ・である」調の使い分け)
議事録を作成する際、最初に決めておくべきなのが文体の統一です。
一般的に、社内向けの報告書や公式な議事録では「だ・である」調(常体)が好まれる傾向にあります。
これは、文章が簡潔になり、客観的な事実を伝えるのに適しているためです。
一方で、顧客向けの確認事項メモや、柔らかい雰囲気のミーティング記録であれば、「です・ます」調(敬体)が適している場合もあります。
重要なのは、一つの文書の中でこれらが混在しないようにすることです。
混在していると、読み手はリズムの悪さを感じ、内容への集中力が削がれてしまいます。
「昨年の売上は増加した。しかし、利益率は減少傾向にあります。」のような書き方は避け、
「昨年の売上は増加した。しかし、利益率は減少傾向にある。」と統一することで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
【一覧表】すぐに使える!議事録の言い換え・変換フレーズ集
ここからは、実際の議事録作成現場ですぐに使える、具体的な言い換えフレーズを紹介します。
ついつい使ってしまいがちな口語表現も、適切な書き言葉を知っていれば瞬時に変換可能です。
この一覧表を辞書代わりに活用し、文章のブラッシュアップに役立ててください。
近年では、文脈を考慮して話し言葉を書き言葉へ変換する技術(CoS2W)の研究も進んでいます。最新の技術動向に興味がある方は、こちらの文献もご覧ください。 https://arxiv.org/html/2408.09688v2
【基本編】よく使う動詞・形容詞の言い換え(やる→実施する、すごい→著しい 等)
日常会話で多用される基本的な動詞や形容詞は、そのまま議事録に使うとカジュアルすぎる印象を与えます。
以下のようなビジネス用語への変換を意識しましょう。
まず、「やる」は状況に応じて使い分けます。
単純な作業なら「実施する」「行う」、何かに取り組むなら「遂行する」「従事する」などが適切です。
「見直す」は「再考する」や「検討する」、「調べる」は「調査する」や「確認する」と言い換えると、ぐっと引き締まります。
形容詞についても同様です。
「すごい」は「著しい」や「顕著な」、「大きい」は「多大な」や「甚大な」、「難しい」は「困難な」などに変換します。
例えば、「すごい成果が出た」ではなく「顕著な成果が得られた」と書くことで、客観的かつ具体的な報告として受け取られます。
これらの語彙を適切に選ぶことで、議事録の説得力が増します。
【接続詞編】文脈をつなぐ接続詞の言い換え(だから→したがって、でも→しかしながら 等)
文章の論理構造を示す接続詞は、議事録の読みやすさを左右する重要な要素です。話し言葉の接続詞をそのまま使うと、稚拙な印象になりがちですので注意しましょう。
順接の「だから」は「したがって」「よって」「そのため」と言い換えます。
逆接の「でも」「だけど」は「しかし」「しかしながら」「もっとも」などが適切です。
「あと」「それと」といった並列や添加を表す言葉は、「また」「さらに」「加えて」と表現します。
また、話の転換で使われる「じゃあ」「さて」などは、議事録では不要な場合が多いですが、あえて残すなら「次に」「おいては」などで文脈をつなぎます。
接続詞を洗練された表現にすることで、議論の流れが論理的に整理され、読み手が結論に至るプロセスをスムーズに理解できるようになります。
【クッション言葉編】丁寧すぎる表現をビジネス文章にする言い換え
会議中は、人間関係を円滑にするために多くのクッション言葉や敬語が使われます。しかし、議事録においては、過度な敬語やクッション言葉はノイズとなります。
例えば、「~していただければと思います」は「~すること」や「~を依頼する」と簡潔にします。
「恐れ入りますが」や「お手数ですが」といった表現は、事実のみを記録する議事録では基本的に削除して構いません。
「~という形になります」という表現も、単に「~である」や「~となる」と言い切る方が明確です。
誰が発言したかを記録する場合も、「佐藤部長がおっしゃいました」ではなく、「佐藤部長:~と発言」や「~との指摘あり」と記述します。
議事録は相手への手紙ではなく、事実の記録であることを意識し、敬意は保ちつつも簡潔な表現を心がけましょう。
【曖昧表現編】「たぶん・思う」を事実ベースに直す言い換えテクニック
会議では、確証がない段階での発言として「たぶん」「~だと思う」「~気がする」といった言葉が飛び交います。これらをそのまま記載すると、決定事項なのか単なる感想なのかが判別しづらくなります。
「たぶん~だ」という発言は、文脈に応じて「~の可能性がある」や「~と推測される」と言い換えます。
「~だと思う」は、単なる感想であれば削除することもありますが、意見として残す場合は「~との見解である」や「~と考える」とします。
また、「ちょっと」や「だいたい」といった表現も、「一部」「概ね」「約」などに変換します。
曖昧な表現を排除し、事実や推論としての輪郭をはっきりさせることで、後から読み返した際に誤解が生じるリスクを減らすことができます。
議事録担当者は、発言者の意図が「事実」なのか「推測」なのかを見極めて記載するスキルが求められます。
【数量・程度編】「たくさん・ちょっと」を具体化する書き方
ビジネスの現場では、数字や程度を具体的に記録することが極めて重要です。発言者が感覚的に使った言葉を、より定量的な表現や、ビジネスに適した言葉に変換しましょう。
「たくさん」は「多数の」「多くの」、「かなり」は「相当数」「大幅に」と言い換えます。
逆に「ちょっと」や「少し」は、「若干」「一部」「わずかに」と表現します。
「もっと増やす」であれば「さらに拡充する」「増加させる」などが適切です。
もし会議中に具体的な数字が出ている場合は、必ずその数字を記載します。
例えば「かなり売上が伸びた」という発言に対し、資料に「120%」とあるなら、「売上が前年比120%伸長した」と補足して記載するのが親切です。
抽象的な言葉を具体的な表現に落とし込むことで、議事録の資料的価値は大きく向上します。
ダラダラした発言をスッキリ要約する「短縮・言い換え」テクニック
会議の発言は、必ずしも整然としているわけではありません。
思いつくままに話されたり、内容が重複したりすることは日常茶飯事です。
ここでは、そのような「ダラダラした発言」を、意味を変えずに短くスッキリとまとめる要約のテクニックを解説します。
文章のダイエットを行うことで、読み手の負担を大幅に軽減できます。
オンライン会議の要約において、どのようなポリシーで情報を抽出・評価すべきかという技術的な指標については、こちらの論文が参考になります。 https://arxiv.org/html/2502.03111v1
意味のない「フィラー(えー、あのー)」や「相槌」の削り方
要約の第一歩は、徹底的なノイズカットです。
「えー」「あのー」「そのー」といったフィラー(言い淀み)は、議事録には一切不要です。
これらを削除するだけで、文章量は大幅に減り、内容がクリアになります。
また、「なるほど」「そうですね」といった相槌も、基本的には記録する必要はありません。
ただし、その相槌が「同意」の意思表示として重要な意味を持つ場合(例:決裁者の承認など)は、「承認」「合意」という言葉に変換して記録します。
さらに、「なんか」「一応」といった、意味を曖昧にするだけの口癖も積極的に削りましょう。
これらの無駄な言葉を削ぎ落とすことで、発言の本来の骨組みが見えてきます。
まずは勇気を持って「削る」ことから始めてみてください。
重複する発言を一つにまとめる「統合」の技術
会議では、同じ内容が言葉を変えて何度も繰り返されることがよくあります。
また、複数の参加者が似たような意見を述べることもあります。
これらを時系列順にすべて記述すると、議事録が冗長になります。
このような場合は、発言を「統合」する技術が役立ちます。
一人の発言内で繰り返しがある場合は、最も明確な一文を採用し、他はカットします。
複数人が同じ意見の場合は、「A氏、B氏より、~という点について賛同の意見あり」のようにまとめて記述します。
議論が行ったり来たりした場合も、時系列にこだわらず、トピックごとに内容を整理して記載する方が親切です。
「最終的に何が決まったのか」「どのような意見が出たのか」という結果に焦点を当てて情報を再構築することで、スッキリとした議事録になります。
否定疑問文や二重否定を「肯定文」に言い換えてわかりやすくする
回りくどい否定表現を肯定的な表現に変換することで、文章のインパクトが強まり、意味がダイレクトに伝わるようになります。
簡潔さを追求する議事録において、肯定文への変換は非常に効果的なテクニックです。
日本語の話し言葉では、「~じゃないかと思う」「~しなくもない」といった否定表現を用いた言い回しが多く使われます。
しかし、二重否定や否定疑問文は、読み手に一瞬考えさせる負担を与え、誤解を招く原因にもなります。
例えば、「進めないわけにはいかない」という発言は、「進める必要がある」と言い換えます。
「コスト削減が必要なんじゃないでしょうか?」という発言は、「コスト削減が必要であるとの指摘」と肯定文の形で記録します。
「無理ではない」は「可能である」とシンプルにします。
主語と述語を近づけて文章を短くするコツ
一文が長く、ダラダラと続く文章は、主語と述語が離れすぎていることが原因の場合が多いです。
話し言葉では、一つの文の中に複数の事柄詰め込まれ、接続詞で延々と繋がれていくことがよくあります。これを解消するには、一文を短く区切ることが鉄則です。
「今回はA案を採用することになりましたが、B案にも良い点があり、将来的には検討の余地があるので、完全に廃案にするわけではありません」
といった発言は、次のように分割します。
「今回はA案を採用する。ただし、B案にも利点があるため、将来的な検討事項として残す。」
主語と述語の距離を近づけ、「一文一義(一つの文には一つの情報だけ)」を意識することで、論理構成が明確になります。
読点は少なく、句点を多くするイメージを持つと、キレのある読みやすい文章になります。
議事録の質を上げるための「ポジティブ・ネガティブ」言い換え術
議事録は、単なる記録であると同時に、チームの士気や今後のアクションに影響を与える文書でもあります。
特に、ネガティブな内容や感情的な対立が含まれる場合、その表現方法には細心の注意が必要です。
ここでは、事実を歪めることなく、かつ建設的な方向へ議論が進むような「ポジティブ・ネガティブ」の言い換え術について解説します。
批判的な意見を建設的な表現に変換するポイント
会議中に「その案は全然ダメだ」「使い物にならない」といった強い批判が出ることがあります。
これをそのまま記録すると、議事録全体が攻撃的な雰囲気になり、後から読んだ関係者が不快な思いをする可能性があります。
このような批判的意見は、その裏にある「改善への要望」や「懸念点」に変換して記録します。
「全然ダメだ」は「改善の余地がある」「見直しが必要」とします。
「使い物にならない」は「実用性に課題がある」「機能要件を満たしていない」と言い換えます。
単なる否定ではなく、「課題の指摘」として記述することで、次のアクションに繋がりやすい建設的な記録となります。
批判の感情ではなく、批判の「内容」を抽出するのがポイントです。
日本の職場環境において、批判を伝える際にどのようなポライトネス(配慮)戦略が用いられているか、社会言語学の観点から分析した研究はこちらです。 https://www.researchgate.net/publication/394227293_Politeness_Strategies_for_Criticizing_in_the_Japanese_Workplace_A_Pragmatic_Study
感情的な発言を客観的な事実に書き換える方法
議論が白熱すると、感情的な発言が飛び出すこともあります。
「どうしても気に入らない」「絶対に嫌だ」といった主観的な感情は、議事録という公的な文書には馴染みません。
こうした感情的な発言は、客観的な事実に落とし込んで記述します。
「気に入らない」という感情の背景に何があるのかを読み取り、「デザインの一貫性に欠けるとの指摘」や「運用フローへの懸念」といった形に変換します。
「絶対に嫌だ」であれば、「強い反対意見あり」や「導入に対する慎重な姿勢」と表現します。
感情的な言葉をそのまま残すと、水掛け論のような印象を与えてしまいますが、客観的な表現に直すことで、検討すべきリスクや課題として冷静に捉え直すことができます。
決定事項か検討事項かを明確にする語尾の選び方
議事録で最も重要なのは、「何が決まって、何が決まっていないのか」を明確にすることです。
曖昧な語尾を使ってしまうと、決定事項なのか、単なる検討事項なのかが曖昧になり、後のトラブルの元となります。
決定事項であれば、「~することに決定」「~とする」「~を実施する」と言い切ります。
一方で、まだ決まっていないことや継続して話し合うことは、「~について継続審議」「~を検討する」「~の方向で調整する」と明確に区別します。
「~という話が出た」といった記述では、それが採用されたのかどうかが分かりません。
「~という意見を踏まえ、〇〇と決定した」あるいは「~という意見があったため、次回会議で再確認する」のように、ステータスが確定する語尾を選ぶように心がけましょう。
話し言葉の中から「指示」や「決定」に関する内容を抽出し、生成要約を行う技術については、こちらの研究論文で詳しく解説されています。 https://arxiv.org/abs/2008.09676
【時短】ChatGPT等のAIを使って議事録の言い換えを自動化する方法
ここまで紹介した言い換え技術をすべて手作業で行うのは、高いスキルと時間を要します。
しかし、現在はChatGPTをはじめとする生成AIを活用することで、このプロセスを大幅に自動化・短縮化することが可能です。
ここでは、AIを使って議事録の言い換えや要約を効率的に行うための具体的なプロンプトや手順、そして最新モデルの活用法について解説します。
箇条書きのメモを整った文章に言い換えてもらうプロンプト例
会議中に取ったラフな箇条書きメモを、AIに整ったビジネス文書へ変換してもらうのは、最も効果的な活用法の一つです。
以下のプロンプトを使用することで、短時間で高品質な文章が生成されます。
プロンプト例:
「あなたはプロのライターです。以下の【会議メモ】を元に、社内報告用の議事録形式に書き換えてください。文体は『だ・である調』で統一し、話し言葉は適切なビジネス用語(書き言葉)に変換してください。重要な決定事項とネクストアクションが明確になるように構成してください。」
このように役割と出力形式、文体のルールを明確に指示することで、AIは意図を汲み取った文章を出力してくれます。
メモ書きレベルの入力でも、AIが文脈を補完し、きれいな日本語に整えてくれるため、一から文章を書く手間が省けます。
その他、ビジネスでそのまま使える日本語のAIプロンプトテンプレート集はこちらの記事でまとめています。 合わせてご覧ください。
冗長な長文を要約してすっきりさせてもらう手順
文字起こしツールなどで生成された全文テキストがある場合は、AIに要約を依頼しましょう。
ただし、長い文章を一度に投げると重要なポイントが漏れることがあるため、議題ごとに分割して入力するのがコツです。
手順としては、まず「以下のテキストから、フィラーや重複を取り除き、要点を3つにまとめてください」と指示します。
その上で、「それぞれの要点について、誰がどのような発言をしたか、客観的な事実に基づいて要約してください」と深掘りさせます。
また、最新のAIモデルを活用することも重要です。
OpenAIの「OpenAI o1」シリーズなどは、時間をかけて深く考える推論能力を搭載しています。 複雑な議論の整理や要約といったタスクにおいて、AIが回答前に「思考(推論)」を行うことで、文脈の裏にある意図まで汲み取った精度の高い要約を行います。
以前のモデルよりも格段に「行間を読む」能力が向上しているため、議事録作成の強力なパートナーとなるでしょう。
ChatGPTを使ったより高度な長文要約テクニックや、プロンプトのコツについては、こちらの記事で詳細に解説しています。 合わせてご覧ください。
AIによる言い換え作成時の注意点と手直しのポイント
AIは非常に優秀ですが、完璧ではありません。出力された議事録は、必ず人の目でチェックし、手直しする必要があります。
特に注意すべきなのは、固有名詞や専門用語の誤り、そして「ニュアンスの取り違え」です。
AIは文脈から推測して言葉を補うことがありますが、それが会議の実際の合意内容と微妙に異なる場合があります。
例えば、AIが「決定した」と要約していても、実際は「前向きに検討する」レベルだったというケースはよくあります。
また、機密情報の取り扱いにも注意が必要です。
社内のセキュリティ規定に従い、個人情報や機密データは伏せ字にするか、「ChatSense」のような学習データに利用されない法人向け環境でAIを利用するようにしてください。
AIはあくまで「下書き作成のツール」と割り切り、最終的な責任は人間が持つことが重要です。
大規模言語モデル(LLM)が生成するハルシネーション(事実に基づかない内容)の種類や評価ベンチマークについては、こちらの論文で詳細に検証されています。 https://arxiv.org/html/2504.17550v1
完成した議事録の言い換え最終チェックリスト
議事録を書き終えたら、公開する前に必ず推敲を行いましょう。
自分では完璧だと思っていても、時間が経ってから読み返すと改善点が見つかるものです。
最後に、言い換えが適切に行われているかを確認するための「最終チェックリスト」を用意しました。
これらに目を通すだけで、議事録の品質は確実にワンランクアップします。
一文が長くなりすぎていないか(一文一義の確認)
まず確認すべきは、文章の長さです。一文が3行以上続いている場合は、どこかで区切れないか検討しましょう。
「~であり、~ですが、~ので」といった接続助詞での長々とした連結は、読み手を混乱させます。
チェックの際は、声に出して読んでみるのが効果的です。
息継ぎなしで読み切れない文章は、視覚的にも読みづらい文章です。
「一文一義」の原則に立ち返り、一つの文には一つのメッセージだけを込めるように修正します。
句点(。)が増えるほど、文章のリズムが良くなり、論理が明確になっていきます。
指示代名詞(あれ、それ)が多用されていないか
会議中は、資料を見ながら話しているため「これ」「その件」で通じますが、文章になった途端に意味が分からなくなるのが指示代名詞です。議事録では、指示代名詞をできるだけ具体的な名詞に書き換えましょう。
「それについては問題ない」ではなく、「A社の見積もり金額については問題ない」と記述します。
「例の件はどうなりましたか?」ではなく、「次期プロジェクトのリーダー選定の進捗は?」と書きます。
こうすることで、会議に参加していない人が読んでも、あるいは数ヶ月後に読み返しても、内容を正確に把握できるドキュメントになります。
第三者が読んでも誤解のない表現になっているか
最後のチェックポイントは、「その会議に参加していない第三者」の視点を持つことです。
議事録は、欠席者や将来の担当者、あるいは経営陣など、その場にいなかった人々への共有ツールでもあります。
内輪ネタや、その場限りの暗黙の了解に基づいた表現が含まれていないか確認しましょう。
前提知識がなくても理解できる論理構成になっているか、専門用語には補足が必要ないかを見直します。
「客観性」と「再現性」のある文章になっているかを確認して、議事録作成の完了となります。
このチェックリストを活用し、読み手への配慮が行き届いた、価値ある議事録を作成してください。
【評価の分かれ目】「仕事ができる人」は議事録をどう書く?単なるメモ係で終わらないための思考法
会議が終わった後、録音した音声をそのまま文字に起こして満足していませんか?実は、その「真面目な記録」こそが、あなたの評価を下げている原因かもしれません。ビジネスの最前線では、議事録は単なる記録ではなく、プロジェクトを推進させるための「戦略的ツール」として扱われています。ここでは、評価される人が実践している議事録作成の思考法と、避けるべき落とし穴について解説します。
【警告】「発言録」と「議事録」を混同するリスク
「一言一句漏らさずに書かなければならない」という思い込みは、今すぐ捨てましょう。発言をそのまま書き起こしただけの「発言録(逐語録)」は、読み手に対して「要点を探す」という余計な労力を強いることになります。
記事で触れられている通り、ビジネスにおける議事録の価値は「決定事項」と「ネクストアクション」の明確化にあります。
話し言葉特有のノイズ(「えー」「あのー」などのフィラー)や、感情的な表現、曖昧な推測をそのまま残すことは、情報のノイズを増やすだけでなく、誤解を生むリスクすらあります。
「書く」ことよりも「削る・整える」ことに時間を割く意識変革が必要です。
【実践】情報を「翻訳」するスキルが信頼を生む
仕事ができる人は、会議中の話し言葉を、読み手に伝わる書き言葉へと脳内で瞬時に「翻訳」しています。
例えば、「たぶん大丈夫だと思います」という発言をそのまま書くのではなく、「懸念点はないとの見解」や「進捗に問題なし」といった、客観的事実に基づいたビジネス文書へ変換するのです。
また、批判的な意見が出た際も、感情的な言葉尻を捉えるのではなく、「改善への要望」として前向きな表現にリフレームします。
このように、情報を整理し、論理的な文章へと昇華させるプロセスこそが、読み手への配慮であり、あなたのビジネスパーソンとしての信頼性を高める鍵となります。
引用元:
多くの企業のドキュメント改善支援を行ってきた専門的な知見によると、優れた議事録は、情報の取捨選択と言い換えによって、読み手の確認時間を大幅に短縮し、迅速な意思決定に寄与することが示されています。(ビジネスドキュメント改善支援の現場知見より)
まとめ
議事録作成における「言い換え」や「要約」のスキルは、質の高いアウトプットを出すために極めて重要です。
しかし、日々の業務に追われる中で、すべての会議記録に対して高度な編集作業を手動で行うのは、時間的にもリソース的にも限界があるのが現実です。
「議事録作成に時間がかかりすぎる」「要約の質が担当者によってバラバラ」といった課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは、日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
今回の記事で紹介したような「話し言葉から書き言葉への変換」や「会議の要約」、「重要事項の抽出」といった作業も、専用のAIタスクを選ぶだけで、誰でも瞬時に高品質なレベルで実行可能です。
ChatGPTなどの生成AIを直接使う際にハードルとなる「プロンプト作成」の必要がなく、直感的な操作で業務効率化を実現できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、会議の内容などの機密情報もしっかり守られ、データセキュリティの面でも安心して利用できます。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、AI活用に不慣れな企業でもスムーズに運用を開始できます。
個人のスキルアップも大切ですが、AIの力を借りてチーム全体の生産性を底上げすることも、これからのビジネスには不可欠です。
まずは、Taskhubの議事録作成支援機能やその他の活用事例を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。