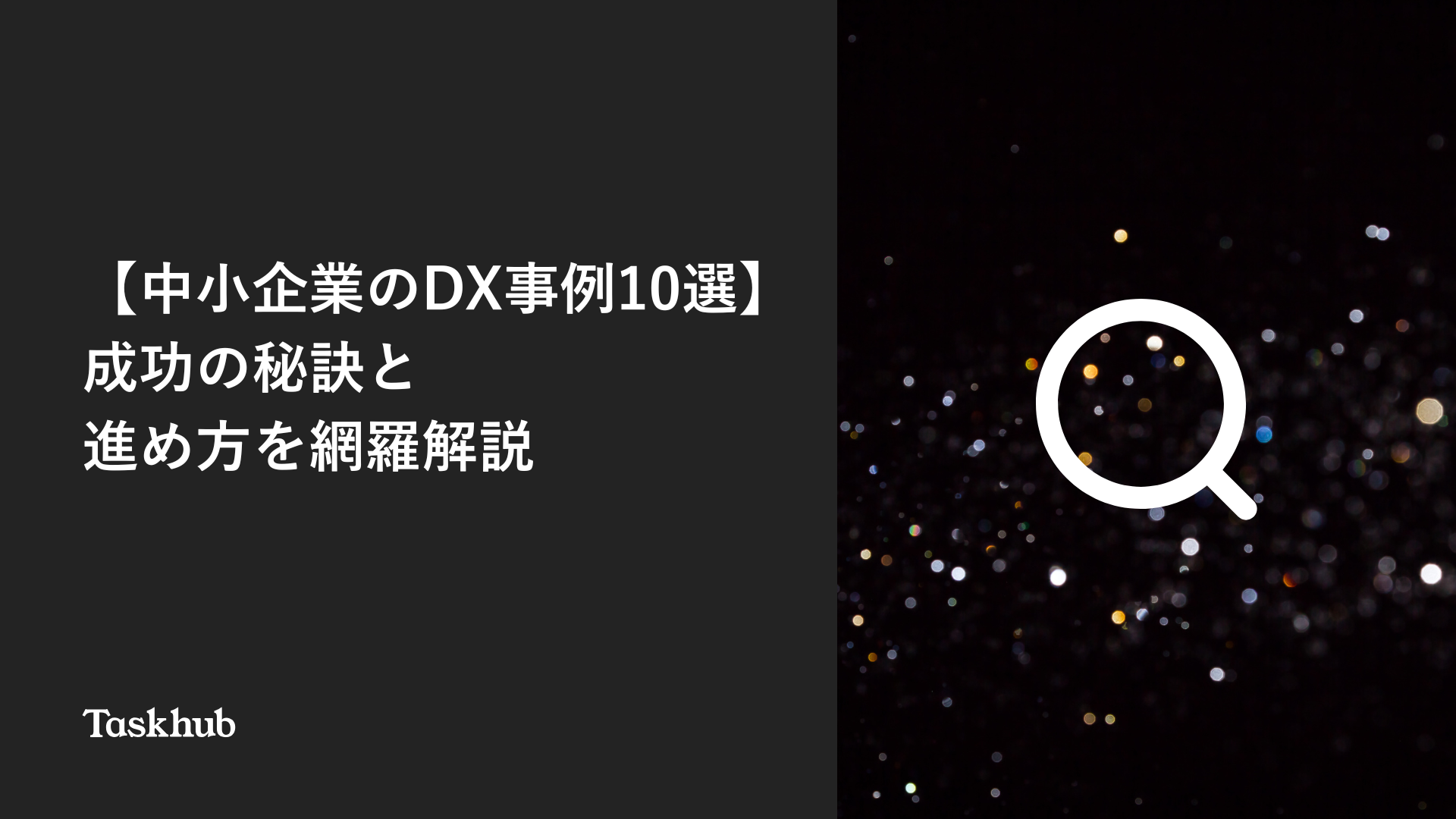「中小企業でもDXって本当に成功するの?」
「具体的なDXの事例や、何から手をつければ良いのかがわからない…。」
こういった悩みを持っている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか?
本記事では、日本国内の中小企業におけるDXの成功事例10選を課題別・業種別にご紹介します。
さらに、DXの定義や必要性、推進する上での障壁と乗り越え方、そして具体的な進め方まで網羅的に解説しました。
この記事を読めば、自社でDXを推進するための具体的なヒントがきっと見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
DX事例を知る前に|中小企業のDXの定義と現状
まずは、DXの基本的な定義や、現在の中小企業が置かれている状況について正しく理解することが重要です。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質や、IT化との違い、そしてなぜ今注目されているのかを解説します。
そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。
その本質は、「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化そのものを根本的に変革し、新たな価値を創出すること」にあります。
つまり、ITツールはあくまで変革のための「手段」であり、目的は企業の競争力を高め、持続的な成長を実現することです。
変化の激しい市場環境において、顧客や社会のニーズに迅速に対応できる企業体制を築くための経営戦略そのものと言えるでしょう。
中小企業におけるDX化の現状と注目される背景
現在、多くの中小企業がDXの重要性を認識しつつも、具体的な取り組みには至っていないのが現状です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によれば、DXに「取り組んでいる」と回答した中小企業は全体の約3割に留まっています。
しかし、深刻化する人手不足、働き方改革の要請、そしてグローバルな競争激化といった背景から、中小企業にとってDXはもはや避けて通れない課題となりました。
デジタル技術を活用して生産性を向上させ、限られたリソースで最大限の成果を出すことが、企業の存続と成長に不可欠であると認識され始めています。
DXと単なるIT化・デジタル化の誤解
DXと「IT化」や「デジタル化」は混同されがちですが、その意味は明確に異なります。
IT化やデジタル化は、主に既存の業務プロセスを効率化するために行われます。
例えば、紙の書類を電子化したり、手作業のデータ入力をRPAで自動化したりすることがこれにあたります。
一方で、DXはこれらの取り組みのさらに先を見据えています。
デジタル技術を駆使して、従来にはなかった新しい製品やサービスを生み出したり、顧客との関係性を再構築したりと、ビジネスモデルそのものを変革することがDXの目指すゴールです。
IT化はDXの第一歩ではありますが、それ自体が目的ではないという点を理解することが重要です。
こちらは独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する、日本企業のDX動向に関する最新の調査レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-2023.html
なぜ必要?DX事例が示す中小企業こそ取り組むべき理由
DXは大企業だけの話ではありません。むしろ、経営資源が限られている中小企業こそ、DXによって大きなメリットを得ることができます。
ここでは、DXが中小企業にもたらす3つの主要な利点を解説します。
生産性向上と業務効率化
中小企業がDXに取り組むべき最大の理由の一つが、生産性の劇的な向上です。
例えば、会計ソフトや勤怠管理システムを導入すれば、経理や人事といったバックオフィス業務にかかる時間を大幅に削減できます。
また、RPA(Robotic Process Automation)を活用して、受発注データの入力や請求書発行などの定型作業を自動化することも可能です。
これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになり、企業全体の生産性が向上します。
こちらはDXによる業務効率化ガイドについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-business-efficiency-improvement/
人手不足の解消と働き方改革の実現
少子高齢化が進む日本では、多くの中小企業が深刻な人手不足に悩まされています。
DXは、この課題に対する有効な解決策となり得ます。
業務の自動化や効率化によって、少ない人数でも事業を継続できる体制を構築できます。
さらに、クラウドツールやコミュニケーションツールを導入すれば、場所や時間に縛られない柔軟な働き方が可能になります。
リモートワークの導入は、多様な人材の確保や従業員の定着率向上にも繋がり、魅力的な職場環境の実現に貢献します。
競争優位性の確立と新たなビジネスモデルの創出
DXは、単なる業務効率化に留まらず、企業の競争力を根本から高める可能性を秘めています。
顧客管理システム(CRM)や販売データを分析することで、顧客のニーズをより深く理解し、パーソナライズされたサービスを提供できるようになります。
また、IoT技術を活用して製品にセンサーを取り付け、使用状況をデータとして収集・分析することで、新たな保守サービスやサブスクリプションモデルといった、従来にないビジネスモデルを創出することも可能です。
これにより、他社との差別化を図り、市場での優位性を確立できます。
【課題別】中小企業のDX事例に見る障壁と乗り越え方
多くの中小企業がDXの必要性を感じながらも、推進にはいくつかの障壁が存在します。
- 予算の確保ができない
- DX化に関する知識や理解度の不足
- ITリテラシーが高い人材不足
- 古くから根付いている企業文化
ここでは、代表的な4つの課題とその乗り越え方について解説します。
①予算の確保ができない
DX推進には初期投資が必要となるため、予算の確保は多くの中小企業にとって大きな課題です。
しかし、必ずしも大規模な投資が必要なわけではありません。
月額数千円から利用できるクラウドサービスも多く存在します。
まずは、コストを抑えながら高い効果が期待できる領域からスモールスタートすることが重要です。
また、国や地方自治体が提供する「IT導入補助金」などの支援制度を積極的に活用することで、導入コストの負担を大幅に軽減できます。
これらの補助金を活用し、成功事例を積み重ねていくことが賢明な進め方です。
こちらは中小企業・小規模事業者様向けのITツール導入を支援する「IT導入補助金」の公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://it-shien.smrj.go.jp/

②DX化に関する知識や理解度の不足
経営層や従業員のDXに対する理解不足も、推進を妨げる大きな要因です。
「DXとは何か」「なぜ必要なのか」という根本的な部分が共有されていないと、全社的な協力は得られません。
この課題を乗り越えるためには、まず経営者自身がDXの重要性を深く理解し、明確なビジョンを社内に示すことが不可欠です。
外部の専門家を招いて研修会を実施したり、他社の成功事例を共有したりすることで、従業員の知識や意識を高めていく地道な取り組みが求められます。
③ITリテラシーが高い人材不足
DXを推進したくても、それを実行できるIT人材が社内にいないという問題も深刻です。
特に地方の中小企業では、専門知識を持つ人材の採用は容易ではありません。
この場合、全てを内製化しようと考える必要はありません。
DX支援を専門とする外部のコンサルティング会社やITベンダーとパートナーシップを組むことが有効な解決策です。
専門家の知見を借りながら、まずは自社の従業員のITリテラシーを底上げしていく育成の視点も重要になります。
簡単なITツールの導入から始め、徐々に社内のスキルレベルを高めていきましょう。
④古くから根付いている企業文化
「これまでのやり方を変えたくない」といった、変化に対する抵抗感もDXの大きな障壁です。
特に、長年の慣習が根付いている企業では、新しいツールの導入や業務プロセスの変更に対して、従業員から反発が生まれることも少なくありません。
この課題を克服するには、経営者の強いリーダーシップが不可欠です。
DXによって「誰の業務が」「どのように改善されるのか」を具体的に、そして繰り返し説明し、従業員の不安を払拭する必要があります。
一部の部門でスモールスタートし、成功体験を共有することで、「自分たちにもメリットがある」と実感してもらうことが、全社的な協力体制を築く鍵となります。
【業務別】中小企業のDX事例で成果が出やすい領域
DXを推進するにあたり、どこから手をつけるべきか迷うことも多いでしょう。
ここでは、特に中小企業において成果が出やすい3つの業務領域を紹介します。
定型作業が多いバックオフィス業務
経理、人事、総務といったバックオフィス業務は、DXの成果を最も実感しやすい領域の一つです。
これらの業務には、請求書の発行、経費精算、勤怠管理など、毎月決まった手順で行う定型作業が多く含まれます。
会計ソフトや給与計算ソフト、RPAツールなどを導入することで、これらの作業を自動化し、大幅な時間短縮とヒューマンエラーの削減が可能です。
空いた時間をより戦略的な業務に充てられるため、企業全体の生産性向上に直結します。
データ入力や集計・分析業務
多くの企業では、日々の営業活動や顧客からの問い合わせなど、様々なデータが蓄積されています。
しかし、これらのデータがExcelファイルなどで属人的に管理され、有効活用されていないケースが少なくありません。
顧客管理システム(CRM)や営業支援ツール(SFA)を導入することで、データを一元管理し、リアルタイムで集計・分析できるようになります。
これにより、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定が可能となり、営業戦略の精度を高めることができます。
情報共有やコミュニケーション活性化
「担当者しか状況を知らない」「部署間の連携が取れていない」といった課題は、情報共有の仕組みが整備されていないことが原因です-。
ビジネスチャットツールやWeb会議システム、クラウドストレージなどを活用することで、社内のコミュニケーションは大きく改善されます。
リアルタイムでの情報共有が可能になることで、意思決定のスピードが向上し、部署の垣根を越えた連携がスムーズになります。
また、テレワークなどの柔軟な働き方にも対応しやすくなるというメリットもあります。
中小企業のDX事例に学ぶ!DX推進の具体的なステップ
やみくもにDXを始めても、思うような成果は得られません。
ここでは、成功事例から見えてくるDX推進の具体的な4つのステップを解説します。
ステップ1:DXの目的とビジョンを明確にする
DX推進の最初のステップは、「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にすることです。
「人手不足を解消したい」「新たな顧客層を開拓したい」「生産性を20%向上させたい」など、自社が抱える経営課題と紐づけて具体的なゴールを設定します。
この目的が曖昧なままでは、適切なツール選定もできず、途中でプロジェクトが頓挫しかねません。
経営者が主導し、DXによって会社をどのような姿に変えたいのかというビゾジョンを全社で共有することが、成功への第一歩です。
ステップ2:自社の課題に合ったDXツールを選定する
DXの目的が明確になったら、次はその課題解決に最適なITツールを選定します。
市場には多種多様なツールが存在するため、流行っているからという理由で選ぶのではなく、自社の目的や業務フロー、そして予算に合っているかを慎重に見極める必要があります。
複数の製品を比較検討し、無料トライアルなどを活用して実際に使い勝手を試してみるのがおすすめです。
また、導入後のサポート体制が充実しているかどうかも重要な選定基準の一つとなります。
ステップ3:スモールスタートで成功体験を積む
いきなり全社的に大規模なシステムを導入しようとすると、現場の混乱を招き、失敗するリスクが高まります。
まずは特定の部署や特定の業務に限定して、小規模にDXを始める「スモールスタート」が成功の鍵です。
例えば、営業部門の顧客管理や、経理部門の経費精算など、課題が明確で効果を測定しやすい領域から始めましょう。
小さな成功体験を積み重ねることで、従業員のDXに対する心理的なハードルが下がり、次の展開へと繋げやすくなります。
ステップ4:全社的に展開し社員の理解と協力を得る
スモールスタートで得られた成功事例やノウハウを基に、DXの取り組みを他の部署へと横展開していきます。
この段階では、なぜDXを全社に広げる必要があるのか、それによって従業員一人ひとりにどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。
導入したツールに関する勉強会を開催したり、各部署にDX推進のキーパーソンを配置したりするなど、全社を巻き込むための仕組み作りも並行して行いましょう。
DXは一部の部署だけの取り組みではなく、全社一丸となって進めるべきプロジェクトです。
中小企業のDX化を成功に導くポイント【DX事例から分析】
成功している中小企業のDX事例には、いくつかの共通したポイントがあります。
ここでは、DXを成功に導くために押さえておきたい4つの重要なポイントを解説します。
経営者の強いリーダーシップと意識改革
DXは単なるITツールの導入ではなく、企業文化の変革を伴う大きなプロジェクトです。
そのため、経営者自身がDXの重要性を深く理解し、トップダウンで改革を推進する強いリーダーシップが不可欠です。
経営者が明確なビジョンを示し、DX推進のための予算や人材を確保するというコミットメントを示すことで、従業員も安心して変革に取り組むことができます。
「ITのことは担当者に任せている」という姿勢では、DXの成功は望めません。
身近な業務から取り入れて小さく始める
DXの成功確率を高めるためには、壮大な計画を立てるよりも、まずは身近な業務課題の解決から始めることが重要です。
例えば、「会議のたびに資料を印刷するのが手間」「日報の提出と確認が面倒」といった、多くの従業員が日々感じている小さな不満を解消することから始めましょう。
チャットツールやWeb会議システム、クラウド型の勤怠管理システムなど、比較的低コストで簡単に導入できるツールから試してみるのがおすすめです。
小さな成功体験が、より大きな変革への自信と意欲に繋がります。
外部の専門家やパートナーを積極的に活用する
社内にITやDXの専門知識を持つ人材がいない場合、無理に自社だけで進めようとする必要はありません。
DXコンサルタントやITコーディネーター、システム開発会社など、外部の専門家の力を積極的に活用しましょう。
専門家は、客観的な視点から自社の課題を分析し、最適な解決策を提案してくれます。
また、補助金の申請支援やツール導入後の運用サポートなど、幅広い支援を受けることができます。
信頼できるパートナーを見つけることが、DX成功への近道となります。
IT導入補助金などの資金調達(補助金の活用)
DX推進における大きな障壁の一つが、初期投資の費用です。
この課題を解決するために、国や自治体が提供している補助金制度を最大限に活用しましょう。
代表的なものに、中小企業や小規模事業者を対象とした「IT導入補助金」があります。
この制度を活用すれば、会計ソフトや受発注システム、決済ソフトなどの導入費用のうち、一部(通常は1/2~2/3程度)の補助を受けることができます。
自社の事業に合った補助金がないか、中小企業庁のウェブサイトなどで定期的に情報をチェックすることが重要です。
【業種別】中小企業のDX成功事例10選を徹底紹介
ここでは、様々な業種の中小企業がどのようにDXを成功させたのか、具体的な事例を10個紹介します。
自社の状況と照らし合わせながら、DX推進のヒントを見つけてください。
【製造業】株式会社木幡計器製作所のDX事例
圧力計の製造を行う同社は、自社製品にIoTセンサーと通信機能を搭載。
顧客の工場に設置された圧力計の状態を遠隔で監視できるサービスを開発しました。
これにより、異常検知やメンテナンス時期の予測が可能となり、従来の「モノ売り」から「コト売り(サービス提供)」へのビジネスモデル転換に成功。
新たな収益源を確立しました。
【製造業】日進工業株式会社のDX事例
金属プレス加工を手掛ける同社は、生産管理システムを自社開発で導入しました。
各工程の進捗状況や設備の稼働状況をリアルタイムで「見える化」することで、生産計画の精度が向上し、リードタイムの短縮と生産性向上を実現しました。
熟練工の勘や経験に頼っていた部分をデータで補うことで、技術継承の問題にも対応しています。
【建設・不動産業】株式会社ヒサノのDX事例
建設業の同社では、現場管理にドローンや3Dスキャナを導入。
従来、人の手で行っていた測量や進捗確認を自動化し、安全性と作業効率を大幅に向上させました。
また、施工データをデジタルで一元管理することで、関係者間の情報共有がスムーズになり、手戻りの削減にも繋がっています。
【宿泊業】株式会社陣屋のDX事例
神奈川県の老舗旅館である同社は、自社で開発したクラウド型の旅館管理システム「陣屋コネクト」を活用。
予約管理から顧客情報、会計までを一元化し、従業員間の情報共有を徹底しました。
顧客の好みや過去の利用履歴を全スタッフが把握することで、質の高い「おもてなし」を実現し、顧客満足度とリピート率を大幅に向上させました。
【小売業】トヨタレンタリース兵庫のDX事例
同社は、AIを活用した需要予測システムを導入。
過去の利用実績や天候、地域のイベント情報などのデータを分析し、店舗ごとの最適な車両配置を自動で算出します。
これにより、顧客が借りたいときに車がないという機会損失を減らし、車両の稼働率を最大化することに成功しました。
【農業】「ソイルマン」開発に成功した企業のDX事例
ある農業法人は、畑の土壌状態をリアルタイムで測定できるセンサー「ソイルマン」を開発・導入しました。
センサーから得られる水分量や肥料成分のデータをクラウドで分析し、スマートフォンで確認できるようにしました。
データに基づいて最適なタイミングで水や肥料を与えることで、作物の品質向上と収穫量の増加、さらに農業資材のコスト削減を実現しています。
【陸運業】RPAで業務効率化を実現した企業のDX事例
ある運送会社では、RPAを導入して配車管理や請求書発行業務を自動化しました。
毎日大量に発生するこれらの定型作業をロボットに任せることで、事務スタッフの残業時間を大幅に削減。
スタッフはドライバーのサポートや顧客対応といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、従業員満足度の向上にも繋がりました。
【情報・通信業】データ活用を推進した企業のDX事例
Webサービスを提供するある企業は、顧客の行動ログデータを分析するツールを導入しました。
ユーザーがどの機能をよく使い、どこで離脱しているのかをデータで可視化することで、サービスの改善点を客観的に把握。
データに基づいたUI/UXの改善を迅速に繰り返すことで、顧客満足度を高め、解約率の低下に成功しました。
【卸売業】サプライチェーンを最適化した企業のDX事例
食品卸売業を営むある企業は、需要予測と在庫管理を連携させたシステムを導入しました。
AIが過去の販売データや季節変動を分析して発注量を自動で最適化するため、過剰在庫や品切れのリスクを大幅に削減。
サプライチェーン全体の効率化を図り、食品ロスの削減と収益性の向上を両立させています。
【サービス業】顧客体験価値を向上させた企業のDX事例
美容室を多店舗展開するある企業は、オンライン予約システムと電子カルテを連携させました。
顧客は24時間いつでも好きなスタイリストを予約でき、店舗では過去の施術履歴や好みをすぐに確認できるため、スムーズで質の高いサービス提供が可能になりました。
来店後のフォローアップメッセージを自動で送信するなど、顧客との継続的な関係構築にも成功しています。
成功する中小企業のDX事例に共通する要素
数々の成功事例を分析すると、DXを成功させている中小企業にはいくつかの共通点が見えてきます。
ここでは、特に重要な4つの要素を解説します。
明確なビジョンと経営層のコミットメント
成功事例に共通する最大の要素は、経営者がDXに対する明確なビジョンを持ち、その実現に強くコミットしていることです。
「自社はDXによって何を目指すのか」というゴールを全社に示し、必要な投資や組織改革を断行するリーダーシップが、プロジェクトを成功に導く原動力となります。
顧客中心の価値創造への意識
DXの目的は、単なる社内の業務効率化だけではありません。
成功している企業は、デジタル技術を「顧客にどのような新しい価値を提供できるか」という視点で活用しています。
顧客のニーズを深く理解し、顧客体験を向上させることを常に中心に据えている点が共通しています。
データに基づいた意思決定文化
これまでの勘や経験に頼った経営から脱却し、データに基づいた客観的な意思決定を行う文化が根付いていることも、成功企業の特徴です。
収集したデータを分析し、そこから得られたインサイトを次の戦略に活かすというサイクルを回すことで、変化の激しい市場環境に迅速に対応しています。
導入して終わりではない継続的な改善
DXは、一度システムを導入すれば終わりというものではありません。
市場や顧客のニーズは常に変化するため、導入後もその効果を定期的に測定し、改善を続けていく姿勢が不可欠です。
成功企業は、DXを一時的なプロジェクトではなく、継続的な企業活動として捉え、トライ&エラーを繰り返しながら進化し続けています。
【海外編】グローバルな中小企業のDX事例
最後に、視野を広げて海外の中小企業のDX事例にも目を向けてみましょう。
グローバル市場で戦う企業から学べる点は数多くあります。
ICT先進国における市民目線の行政デジタル化事例
例えば、電子国家として知られるエストニアでは、行政サービスのほとんどがオンラインで完結します。
これは、国全体が「市民の利便性向上」という明確なビジョンを持ってデジタル化を進めた結果です。
企業もこのインフラを活用し、場所を問わずに事業を展開しています。
顧客や市民の視点に立ったDXがいかに重要かを示唆する事例です。
世界市場で戦う中小企業の先進的なDX事例
ドイツでは、「インダストリー4.0」という国家戦略のもと、製造業のデジタル化が進んでいます。
ある中小の部品メーカーは、自社の工場をデジタルでネットワーク化し、顧客からの多様な注文にリアルタイムで対応できる「スマート工場」を実現しました。
これにより、大企業にも劣らない競争力を獲得し、世界中の企業と取引を行っています。
中小企業であっても、先進的なDXによってグローバルなニッチ市場でトップになれる可能性を示しています。
あなたのDXは大丈夫?“成果が出る企業”と“失敗する企業”の決定的な違い
多くの企業がDXの重要性を認識し、様々なツールを導入しています。しかし、その成果は二極化しているのが現実です。なぜ、同じようにDXに取り組んでも、成功する企業と失敗する企業に分かれてしまうのでしょうか。その答えは、ツールの機能ではなく、企業の「ビジョン」と「文化」にありました。経済産業省の警鐘を鳴らすレポートを基に、その決定的な違いを解説します。
【警告】そのDX、「手段の目的化」に陥っていませんか?
「とりあえずチャットツールを入れた」「話題のSFAを導入した」…これだけで満足しているなら、危険なサインです。DXで失敗する企業の多くは、ITツールを導入すること自体がゴールになってしまう「手段の目的化」に陥っています。
経済産業省のDXレポートでは、多くの企業が既存システムの維持管理にIT予算の大半を費やし、戦略的なIT投資に資金を回せていない現状を指摘しています。これは、明確なビジョンがないまま部分的なデジタル化を進めた結果、データが連携されず、かえって業務が複雑化してしまう「デジタル敗戦」のリスクを示唆しています。
このような状態が続くと、次のような問題が発生します。
・部署ごとにツールが乱立し、情報がサイロ化する
・現場の従業員がツールを使いこなせず、むしろ負担が増える
・かけたコストに見合う成果が出ず、DXへの投資意欲が低下する
便利なツールを導入したはずが、気づけば宝の持ち腐れとなり、企業の成長を阻害する足かせになってしまうのです。
引用元:
経済産業省は「DXレポート」およびその後続レポートにおいて、多くの企業が既存システムのブラックボックス化や技術的負債の問題を抱え、戦略的なIT投資ができていない現状を指摘。DXの推進には経営層の強いコミットメントとビジョンの明確化が不可欠であると繰り返し強調している。(経済産業省「DXレポート」シリーズ)
【実践】DXを「企業変革のエンジン」に変える3つの視点
では、“成果が出る企業”は何が違うのでしょうか。彼らはITツールを「業務効率化の道具」としてだけでなく、「企業文化を変革し、新たな価値を生み出すエンジン」として捉えています。
視点①:「誰の、どんな課題を解決するのか」を問い続ける
成功する企業は、常に「顧客」を起点にDXを考えます。自社の業務効率化だけでなく、その先にある「顧客体験の向上」や「新たな顧客価値の創造」を最終目標に設定しています。例えば、顧客データを分析して個別のニーズに合ったサービスを提案したり、IoT技術で製品の利用状況を把握し、故障を予知する保守サービスを提供したりします。この「顧客中心」の視点が、DXを単なるコスト削減で終わらせないための鍵です。
視点②:「失敗」を許容し、高速で改善を回す文化を育む
DXは、最初から完璧な計画を立てて実行できるものではありません。むしろ、小さな仮説検証(PoC)を繰り返し、失敗から学びながら軌道修正していくプロセスが不可欠です。成功企業では、経営層が「まずは試してみよう」という姿勢を示し、現場の挑戦を奨励する文化が根付いています。トライ&エラーを許容する心理的安全性が、全社的なDX推進の土台となります。
視点③:「効率化で生まれた時間」を創造的な仕事に再投資する
DXによって定型業務を自動化し、時間を生み出すことは第一歩に過ぎません。重要なのは、その空いた時間を「人でなければできない創造的な仕事」に再投資することです。例えば、新しいサービスの企画、顧客との対話、従業員のスキルアップなど、企業の未来を創る活動に従事させるのです。これにより、従業員のエンゲージメントが高まり、組織全体のイノベーションが加速します。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、DX推進が不可欠となっています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にITリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。