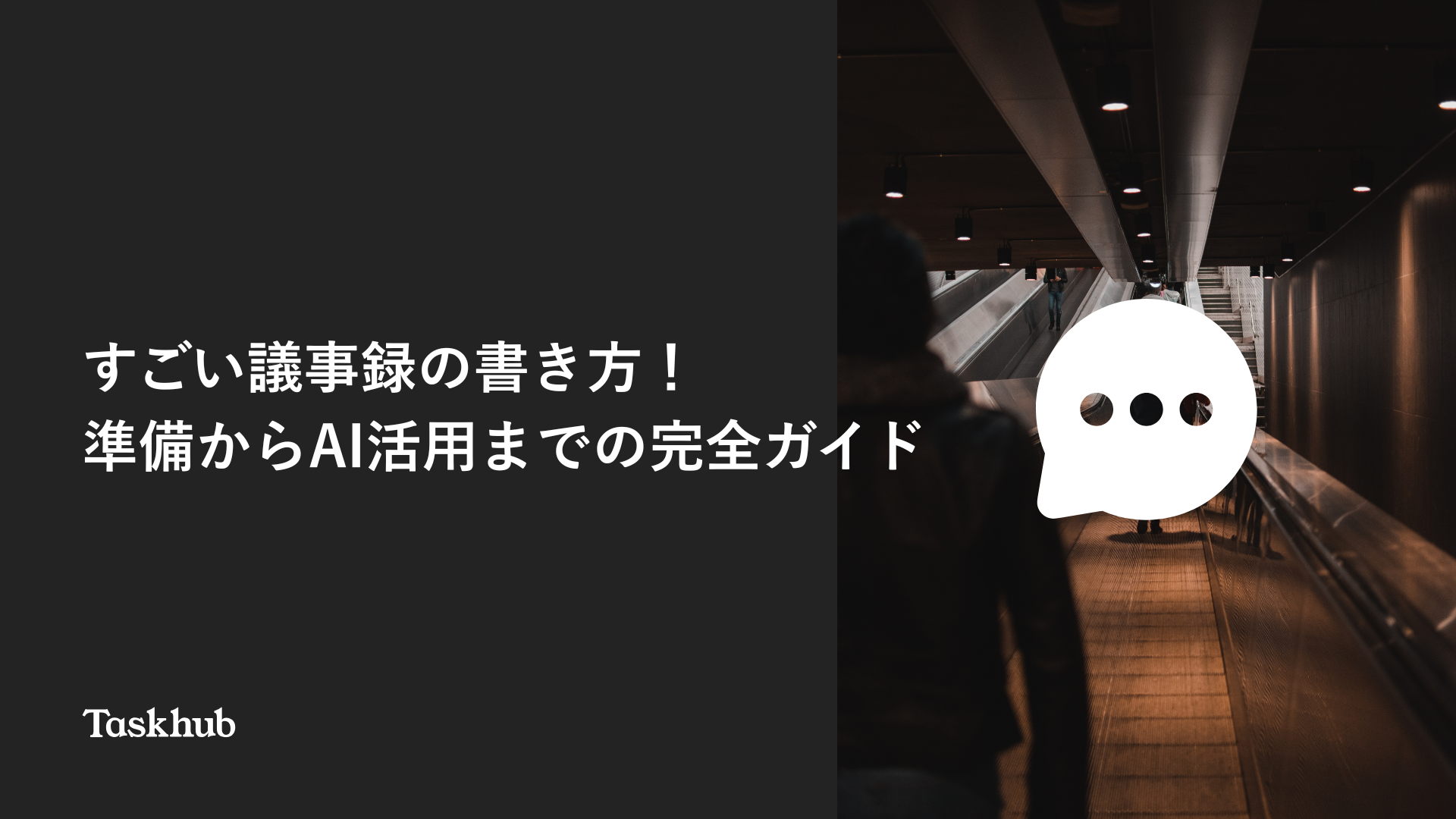「議事録の作成に時間がかかりすぎる…」
「自分が書いた議事録は、後から読んでも内容がよくわからない」
「会議の決定事項やToDoがいつも漏れてしまう」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
議事録は、単なる会議の記録ではありません。会議の成果を可視化し、次のアクションにつなげるための重要なビジネス文書です。
本記事では、「すごい」と言われる議事録を作成するための具体的なステップを、会議前の準備から会議後の仕上げ、そして最新のAI活用術まで徹底的に解説します。
単なる文字起こしではない、関係者から「ありがとう」と言われる議事録の書き方を、テンプレートやプロンプト例を交えてご紹介します。
議事録作成は、DXによる業務効率化の代表的な取り組みの一つです。詳しくは、DXによる業務効率化ガイドをご覧ください。
きっとあなたの議事録作成スキルが格段に向上するはずですので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「すごい議事録」とは?ダメな議事録との決定的な違い
「すごい議事録」と聞いて、どのようなものを想像するでしょうか。
単に発言をすべて書き起こしたものではありません。ビジネスの現場で評価される議事録には、明確な条件があります。
このセクションでは、「すごい議事録」が持つべき条件と、評価が下がってしまう「ダメな議事録」との決定的な違いについて解説します。
「すごい」と言われる議事録が満たすべき7つの条件
「すごい」と評価される議事録には、共通する7つの条件があります。
これらは、議事録が単なる記録ではなく、ビジネスを前に進めるためのツールとして機能するために不可欠な要素です。
第一に、会議の「目的」と「ゴール」が明確に記載されていることです。
何のための会議だったのかが冒頭でわかるため、読み手は内容を理解しやすくなります。
第二に、「決定事項」が具体的であること。
誰が読んでも解釈にズレが生じないよう、明確な言葉で記載されている必要があります。
第三に、「ネクストアクション(ToDo)」が明確であること。
「何を」「誰が」「いつまでに」行うのかが具体的に示されていなければ、行動につながりません。
第四に、議論の「背景」や「プロセス」が簡潔にまとめられていること。
なぜその決定に至ったのか、どのような選択肢が検討されたのかがわかると、会議不参加者でも状況を正確に把握できます。
第五に、「発言者」が明記されていること。
特に重要な意見や決定に関わる発言は、誰によるものかを明確にすることで、責任の所在や意図が明確になります。
第六に、「網羅性」と「簡潔性」が両立していること。
重要な情報は漏れなく記載しつつも、冗長な表現や不要な詳細はそぎ落とし、短時間で読めるようにまとまっていることが求められます。
最後に、会議後「迅速に」共有されること。
会議の熱量が冷めないうちに共有することで、ネクストアクションへの取り掛かりが早くなります。
これら7つの条件を満たすことで、議事録は関係者の認識を統一し、プロジェクトを推進する力強い武器となります。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
なぜ今「すごい議事録」がビジネスで求められるのか?
現代のビジネス環境において、「すごい議事録」の重要性はますます高まっています。
その背景には、働き方の多様化とスピード感の加速があります。
リモートワークやハイブリッドワークが普及し、会議の参加形態は多様化しました。
全員が同じ場所に集まることが減ったため、会議に参加できなかった人や、後から情報を確認する必要がある人にとって、議事録は唯一の公式な情報源となります。
不明瞭な議事録は、情報の格差を生み出し、業務の停滞を引き起こす原因となります。
こちらは、リモートワーク環境下での「会議の非効率性」について、Microsoftが定量的に調査したWork Trend Indexレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index
また、ビジネスのスピードは日々加速しています。
会議で決まったことをいかに早く実行に移せるかが、競争優位性を左右します。
「すごい議事録」は、会議の決定事項とネクストアクションを明確にし、関係者全員が即座に行動を開始できるように促す「指示書」の役割も担います。
さらに、プロジェクトが複雑化し、関わるメンバーが増える中で、正確な情報共有と認識合わせのコストは増大しています。
議事録が「誰が読んでもわかる」状態であれば、認識の齟齬(そご)を防ぎ、無駄な確認作業や手戻りを大幅に削減できます。
コンプライアンスの観点からも、重要な意思決定のプロセスを記録として残すことの価値は高まっています。
このように、議事録は単なる備忘録ではなく、多様な働き方を支え、ビジネスの速度を上げ、リスクを管理するための重要なインフラとなっているのです。
こちらは、非効率な会議がもたらす経済的損失と、構造化されたアジェンダ(議事録の元)のROIについて分析したMIT Sloanの学術論文です。合わせてご覧ください。 https://sloanreview.mit.edu/
やってはいけない!評価が下がる「ダメな議事録」の共通点
一方で、時間と労力をかけて作成したにもかかわらず、評価が下がってしまう「ダメな議事録」にはいくつかの共通点があります。
これらを避けることが、「すごい議事録」への第一歩です。
最も多いのが、「何が決まったのかわからない」議事録です。
議論の内容が時系列で羅列されているだけで、会議の結論や決定事項がハイライトされていないと、読み手は長文の中から結論を探し出さなければなりません。
次に、「ネクストアクション(ToDo)が曖昧」な議事録です。
「〜を検討する」「〜を頑張る」といった具体性に欠ける表現では、誰も行動に移せません。
「誰が」「いつまでに」「何を」するのかが明確でない議事録は、会議をやっただけ、で終わらせてしまいます。
また、「ただの文字起こし」になっている議事録も評価されません。
すべての発言を詳細に記録しても、情報量が多すぎて要点が掴めず、読む気が失せてしまいます。
重要な議論とそうでない部分のメリハリがついていないのです。
「専門用語や社内用語が多すぎる」のも問題です。
その会議の参加者しか理解できない言葉で書かれた議事録は、後から参加したメンバーや他部署の人が読んだときに、情報の障壁となります。
そして、「共有が遅すぎる」議事録です。
会議から数日経ってから共有されても、参加者の記憶は曖昧になり、ネクストアクションへのスピード感も失われます。
会議の翌営業日には共有するのが理想です。
これらの特徴を持つ議事録は、作成者の自己満足で終わり、ビジネスの推進には貢献しません。
「すごい議事録」は単なる「文字起こし」ではない理由
議事録作成の目的は、「会議の内容をすべて記録すること」ではなく、「会議の成果を未来のアクションにつなげること」です。
この根本的な違いを理解することが重要です。
もし議事録が単なる文字起こしであれば、AIによる音声認識ツールが自動生成するテキストで十分なはずです。
しかし、現実にはそれでは不十分です。
なぜなら、会議では本筋と関係のない雑談や、結論に至るまでの冗長な議論、重複する発言が必ず含まれるからです。
文字起こしは、あくまで「素材」に過ぎません。
「すごい議事録」の作成者は、その素材の中から、会議の目的(アジェンダ)に照らして「重要な情報」と「不要な情報」を取捨選択します。
そして、議論の背景、検討された選択肢、採用された理由、そして最終的な「決定事項」と「ネクストアクション」という形で、情報を構造化し、再構築します。
この「編集」と「構造化」のプロセスこそが、議事録の価値を決定づけます。
会議不参加者でも、その議事録を読めば、会議の全体像と結論、次に何をすべきかが5分で理解できる。
これが「すごい議事録」が目指すべき姿です。
文字起こしが「生の魚」だとすれば、すごい議事録は「調理され、美しく盛り付けられた料理」です。
誰でもすぐに美味しく(=理解しやすく)食べられる(=活用できる)状態にして提供すること。
それこそが、議事録作成者に求められる本質的な役割なのです。
【ステップ1】すごい議事録は「会議前」の準備で9割決まる
多くの人は「議事録は会議が始まってから書くもの」と思っていますが、それは間違いです。
「すごい議事録」の作成者は、会議が始まる前の「準備」にこそ最大の重点を置きます。
会議の品質と議事録の品質は、この準備段階でほぼ決まると言っても過言ではありません。
ここでは、会議前に必ず行うべき3つの準備ステップを紹介します。
これを実践するだけで、会議中のメモの取り方と議事録の仕上がりが劇的に変わります。
会議の目的・ゴール・議題(アジェンダ)を正確に把握する
議事録作成者に任命されたら、まず最初に確認すべきことです。
「この会議は、何のために開催されるのか?」
「会議が終わったときに、どのような状態になっていれば成功なのか?」
会議の「目的」と「ゴール」を明確に理解していないと、会議中にどの発言が重要で、どの議論が本筋から逸れているのかを判断できません。
目的があやふやなままでは、単なる文字起こししかできなくなってしまいます。
会議の招集通知やアジェンダ(議題)を熟読しましょう。
もし記載が曖昧であれば、会議の主催者やファシリテーターに事前に確認することが不可欠です。
例えば、目的が「新機能Aの仕様を決定すること」であれば、あなたは「仕様に関する議論」「決定事項」「保留事項」に全神経を集中させるべきです。
一方で、目的が「プロジェクトBの進捗確認」であれば、「各担当者の進捗状況」「発生している課題」「その解決策」「期限の再設定」が記録すべき最重要ポイントとなります。
このように、会議の目的とゴールを正確に把握することで、情報の「取捨選択」の精度が格段に上がり、焦点の定まった議事録を作成できるのです。
関連資料や過去の議事録を読み込んでおく
次に、今回の会議に関連する資料や、過去に開催された同様の会議の議事録に目を通しておきます。
これは、会議の「背景」と「文脈」を理解するために非常に重要です。
事前資料が配布されている場合は、必ず読み込み、会議で議論される内容の前提知識をインプットしておきます。
専門用語や略語が多用される会議であれば、それらの意味も事前に調べておくと、会議中の理解がスムーズになります。
また、前回の議事録を読み返すことで、「前回からの積み残し(ペンディング)事項」や「今回の会議で必ず決めなければならないこと」を再確認できます。
これにより、議論が堂々巡りになるのを防いだり、重要な決定漏れに気づいたりすることができます。
例えば、過去の議事録で「A案とB案で検討中」となっていれば、今回の会議ではそのどちらかに決めるか、あるいはC案が出てくる可能性があると予測できます。
こうした事前インプットがあるかないかで、会議中の議論の理解度、そしてメモの質に天と地ほどの差が生まれます。
文脈を理解しているからこそ、発言の裏にある意図や、議論の「流れ」を正確に捉えることができるのです。
議事録のテンプレート(ひな形)を準備する
会議が始まってから「さて、何を書こうか」と考えるのは遅すぎます。
会議前に入手したアジェンダ(議題)に基づき、議事録の「枠」となるテンプレートをあらかじめ準備しておきましょう。
具体的には、以下の項目を事前にPCのドキュメントに書き出しておきます。
- 会議名
- 日時・場所(またはWeb会議URL)
- 参加者(氏名、部署)
- 会議の目的・ゴール
- アジェンダ(議題)
- (アジェンダごとの議論内容をメモする欄)
- 決定事項
- ネクストアクション(ToDoリスト:担当者、期限)
- 保留事項・次回議題
このように「書くべき箱」を先に用意しておくことで、会議中は「箱を埋めていく」作業に集中できます。
アジェンダごとにメモ欄を区切っておけば、議論があちこちに飛んでも、関連する議題の欄にメモを書き足していけばよいため、混乱を防げます。
特に重要なのが、「決定事項」と「ネクストアクション」の欄をあらかじめ目立つように用意しておくことです。
これにより、会議中に「今、何かが決まった」「誰かが何かをやることになった」瞬間に、その欄に書き込む意識が働きます。
このテンプレート準備が、議事録の品質を担保し、会議後の清書時間を劇的に短縮する鍵となります。
【ステップ2】会議中に押さえるべきメモの取り方と聞き方
準備が整ったら、いよいよ会議本番です。
会議中は、議論の流れを追いながら、後で「すごい議事録」に仕上げるための「素材」を効率的に集める必要があります。
ここでは、会議中に意識すべきメモの取り方と、議論の聞き方のコツを解説します。
すべての発言を記録しようとせず、ポイントを押さえることが重要です。
議論の「骨子」と「流れ」を掴む
会議中のメモは、発言を一言一句書き取ること(逐語録)が目的ではありません。
重要なのは、議論の「骨子(こっし)」、つまり「なぜその議題が議論され」「どのような意見が出され」「最終的にどうなったのか」という全体の「流れ」を掴むことです。
例えば、ある議題についてAさんが賛成意見、Bさんが反対意見を述べたとします。
ダメなメモは、AさんとBさんの発言をそのまま書き写そうとします。
一方、すごい議事録のためのメモは、「【論点】〜について」「【Aさん意見】賛成(理由:〜)」「【Bさん意見】反対(理由:〜)」「【議論】(AとBの懸念点のすり合わせ)」「【結論】〜という条件付きでA案を採用」というように、議論の構造を捉えます。
このように、発言の「要点」と「結論」にフォーカスしてメモを取ることで、後から見返したときに議論の全体像がすぐにわかります。
すべてを記録しようとすると、タイピングが追いつかず、かえって重要な結論を聞き逃すことにもなりかねません。
話を聞く際は、常に「今、アジェンダのどの部分について話しているのか?」「この発言の『要するに』は何か?」を自問自答しながら、情報を整理していく姿勢が求められます。
「決定事項」「ネクストアクション」「担当者」「期限」は絶対に逃さない
会議のメモにおいて、他のすべてを犠牲にしてでも絶対に逃してはならないのが、この4つの要素です。
「決定事項」「ネクストアクション(ToDo)」「担当者」「期限」
これこそが、会議の成果そのものであり、議事録の「核」となる部分です。
会議中に、これらの要素を含む発言が聞こえたら、他のメモを中断してでも、用意しておいたテンプレートの「決定事項」や「ネクストアクション」の欄に即座に書き込みます。
例えば、「じゃあ、その件はCさんが来週金曜までに資料をまとめてください」という発言があったら、
- 【ToDo】新機能Aの競合比較資料作成
- 【担当】Cさん
- 【期限】11月21日(金)
と瞬時にメモします。
この4点が曖昧なまま会議が終わりそうな場合は、議事録作成者から「恐れ入ります、先ほどの件ですが、ご担当はどなたで、期限はいつになりますでしょうか?」と確認する勇気も必要です。
決定事項やToDoが明確になっていない議事録は、残念ながら価値がありません。
この4点を死守することこそが、議事録作成者の最大のミッションであると心得ましょう。
会議後に「あれ、どう決まったんだっけ?」と参加者に確認する手間を発生させないことが、「すごい議事録」の条件です。
こちらは、プロジェクト管理の国際標準であるPMBOKガイドで、議事録を含むプロジェクト文書がどのように「決定事項」や「ネクストアクション」の管理に役立つかを示した資料です。合わせてご覧ください。 https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards
「誰が」「何を」発言したかを明確に記録する
議論の流れを記録する上で、「誰が」発言したのかは非常に重要な情報です。
特に、重要な意思決定、提案、懸念事項、承認などは、必ず発言者を明記するようにしましょう。
例えば、「D部長より、予算超過の懸念が示された」「Eさんより、代替案としてX案が提案された」「(決定)F本部長の承認を得た」といった形です。
発言者を明確にすることで、議事録に「権威性」と「責任の所在」が生まれます。
後から読み返したときに、「なぜこの決定がなされたのか」という背景に説得力を持たせることができます。
また、ネクストアクションの担当者だけでなく、そのアクションを指示した人や、承認した人を記録しておくことも有効です。
ただし、すべての発言に発言者を併記する必要はありません。
あくまでも、議論の方向性を変えた重要な意見や、意思決定に関わる発言に絞り込むことが、読みやすい議事録を作るコツです。
誰の発言かわからない「匿名の意見」ばかりが並んだ議事録は、情報としての信頼性が低くなります。
「誰が」「何を」言ったのかをセットで記録する癖をつけましょう。
メモは構造化し、不明点はその場で確認する
会議中に取るメモは、後で清書しやすいように「構造化」しながら記録することが極めて重要です。
用意したテンプレートのアジェンダごとに、議論の「論点」「意見」「結論」を分けて書くだけでなく、インデント(字下げ)や記号(・、■、→)を活用しましょう。
例えば、
■議題1:新機能Aの仕様について
- 論点:ログイン方法
- (Aさん)メールアドレス認証を提案
- (Bさん)SNS認証も併用すべき(理由:利便性向上)
- (議論)コストと開発工数を比較
- →(結論)今回はメールアドレス認証のみを先行実装。SNS認証はフェーズ2で検討。
このように、トピックごとに階層を分けてメモを取ることで、後から見返したときに議論の構造が一目瞭然となります。
単なる箇条書きの羅列は避けましょう。
また、会議中に専門用語や議論の内容が理解できなかった場合、決してそのままにしてはいけません。
「すごい議事録」は正確性が命です。
議論の流れを止めないよう配慮しつつ、キリの良いタイミングで「恐れ入ります、今の〜という言葉(または、〜の議論)について、もう少し具体的に教えていただけますか?」と簡潔に質問しましょう。
その場で確認することを恐れて曖昧なまま議事録に書くことが、最も信頼を損ねる行為です。
正確な記録を残すために、不明点をその場で解消する姿勢が重要です。
ICレコーダーやAIツールを補助的に使う
人間の記憶とタイピング速度には限界があります。
特に議論が白熱したり、専門的な内容が続いたりすると、メモが追いつかなくなることがあります。
そんな時のために、ICレコーダーやAIの文字起こしツールを「補助的」に使うことは非常に有効な手段です。
会議の開始前に、必ず参加者全員に「議事録作成の補助として、録音(またはAIツールでの記録)をさせていただいてもよろしいでしょうか?」と許可を取りましょう。
無断での録音は、信頼関係を損ねる可能性があるため厳禁です。
録音データがあるという安心感があるだけで、メモを取る際の心理的負担が大きく軽減されます。
会議中は「決定事項」や「ToDo」などの「核」となる部分のメモに集中し、詳細な議論のプロセスは録音データに任せる、という使い分けが可能になります。
ただし、録音に頼りすぎるのは禁物です。
会議後に何時間もの録音データをすべて聞き返すのは、非効率の極みです。
あくまで「メモが追いつかなかった部分」「議論が複雑で理解が追いつかなかった部分」を後からピンポイントで確認するための「保険」として活用しましょう。
最近では、リアルタイムで文字起こしをしてくれるAIツールも増えています。
これらを活用する場合も、AIの文字起こしは完璧ではないことを理解し、自分のメモと併用することが成功の鍵です。
【ステップ3】会議後の「仕上げ」と「共有」で差をつける
会議が無事に終了しても、議事録作成者の仕事は終わりではありません。
むしろ、ここからの「仕上げ」と「共有」のスピードと質こそが、「すごい議事録」と「ダメな議事録」を分ける最大のポイントです。
会議で集めた素材を、いかに早く、正確で、わかりやすい「成果物」にできるかが問われます。
会議の熱量が冷めないうちに、迅速に取り掛かりましょう。
会議後、できるだけ早くメモを整理し清書する
議事録の清書は、記憶が新しいうちに、可能な限り早く着手するのが鉄則です。
理想は会議終了後すぐ、遅くともその日の就業時間内、最低でも翌営業日の午前中までには完了させましょう。
こちらは、会議後すぐに議事録を整理・共有すべき理論的根拠となる「エビングハウスの忘却曲線」に関する学術論文です。合わせてご覧ください。 https://doi.org/10.1177/1529100615620673
時間が経てば経つほど、会議の微妙なニュアンスや、メモしきれなかった議論の文脈、決定の背景などを忘れてしまいます。
記憶が鮮明なうちにメモを見返すことで、「あの発言の意図はこうだった」「この決定にはこういう背景があった」と、メモだけでは不足しがちな情報を補い、より正確で深みのある議事録に仕上げることができます。
会議中に録音やAIツールを使っていた場合は、メモが追いつかなかった箇所や、議論が紛糾して理解が曖昧だった部分をピンポイントで聞き返します。
ダラダラと全体を聞き直すのではなく、自分のメモの「穴」を埋めるために使いましょう。
清書作業は、会議中に取った構造化メモを、準備したテンプレートに流し込み、不要な情報を削ぎ落とし、必要な情報を補足していく「編集作業」です。
スピードを最優先し、まずはドラフト(下書き)を完成させることを目指します。
文章は「簡潔・明瞭」に。5W1Hと定量情報を意識する
議事録の本文は、誰が読んでも理解できるように「簡潔・明瞭」であることが求められます。
冗長な「〜と思いました」「〜という議論がありました」といった表現は避け、「である調」または「です・ます調」で統一し、一文を短く、結論から先に書く(PREP法)ことを意識します。
特に重要な「決定事項」と「ネクストアクション」は、5W1H(When, Where, Who, What, Why, How)を明確に記載します。
中でも「Who(誰が)」「What(何を)」「When(いつまでに)」は必須項目です。
(悪い例)
・資料を準備する。
(良い例)
・【ToDo】A機能の競合比較資料を作成する。(担当:Bさん、期限:11/21(金))
また、議論の内容を記載する際も、できるだけ「定量的」な情報(数値、日付、固有名詞)を用いることで、具体性が増し、認識のズレを防げます。
(悪い例)
・コストが高いという意見が出た。
(良い例)
・C部長より「現行案では予算を約20%オーバーする」との懸念が示された。
会議に参加していない人が読んでも、会議の状況と結果が正確に伝わること。
これをゴールとして、客観的かつ具体的な記述を心がけましょう。
誤字脱字・表記ゆれをチェックし、迅速に関係者へ共有する
議事録のドラフトが完成したら、共有する前に必ず最終チェックを行います。
誤字脱字があると、議事録そのものの信頼性が低下してしまいます。
特に、参加者の氏名、部署名、役職、製品名などの固有名詞は、絶対に間違えてはいけません。
また、「表記ゆれ」にも注意が必要です。
例えば、「Webサイト」「ウェブサイト」「website」や、「AI」「エーアイ」のように、同じ意味の単語が異なる表記で混在していると、非常に読みにくくなります。
あらかじめプロジェクト内で表記ルールを決めておくか、議事録内でどちらかに統一しましょう。
「です・ます調」と「である調」が混在していないかも確認します。
ツール(WordやGoogleドキュメントなど)の校正機能を活用するのも有効です。
最終チェックが完了したら、いよいよ共有です。
共有のスピードは命です。会議の翌営業日までには、必ず関係者全員(参加者+会議には不参加だが関連する人)に送付します。
共有する際は、メールやチャットの本文に「議事録を送るだけ」では不十分です。
本文に「会議の決定事項」と「ネクストアクション(ToDoリスト)」を抜粋して記載し、受け取った人がメール(チャット)を開いた瞬間に、自分に関わるタスクや重要な結論がわかるように配慮しましょう。
このひと手間が、「すごい議事録だ」と評価される最後の分かれ道です。
【見本あり】すぐに使える「すごい議事録」のテンプレート3選
「すごい議事録」を作成するには、優れたテンプレート(ひな形)を使うのが一番の近道です。
会議の目的に合わせて最適なテンプレートを選ぶことで、情報の整理が格段にしやすくなります。
ここでは、ビジネスシーンで特に役立つ3つの型のテンプレートと、その見本をご紹介します。
まずは、議事録に必須の項目から確認しましょう。
「すごい議事録」に必須の7つの項目
どのようなテンプレートを使う場合でも、「すごい議事録」には必ず含めるべき7つの必須項目があります。
これらが欠けていると、議事録としての機能が果たせません。
- 基本情報:会議名、日時、場所(または会議室・URL)
- 参加者:部署名、氏名(敬称略。議事録内での呼称を統一する)
- 会議の目的(ゴール):この会議で何を達成するのかを簡潔に記載
- アジェンダ(議題):事前に合意された、その日の議題リスト
- 決定事項:会議で「決まったこと」を箇条書きで明確に記載
- ネクストアクション(ToDo):会議の結果、「誰が」「いつまでに」「何を」行うのか
- 保留事項・次回議題:今回決まらなかったことや、次回話すべきこと
これらの項目を網羅することで、会議の全体像と成果が誰の目にも明らかになります。
特に「決定事項」と「ネクストアクション」は、議事録の中で最も重要なセクションです。
テンプレート例①:結論ファースト型(決定事項・ToDo重視)
このテンプレートは、会議のプロセスよりも「結論」と「次の行動」を最重要視するものです。
プロジェクトの進捗会議や、迅速な意思決定が求められる会議に最適です。
読み手は、議事録の冒頭で「決まったこと」と「やるべきこと」を即座に把握できます。
【議事録見本:結論ファースト型】
〇〇プロジェクト 第5回定例会議 議事録
- 日時:2025年11月13日(木) 10:00〜11:00
- 場所:オンライン(Teams会議)
- 参加者:山田(PM)、佐藤、鈴木、高橋(以上、開発G)、田中(営業G)
- 会議の目的:新機能Aのリリース日確定と、B機能の仕様FIX
1. 決定事項
- 新機能Aのリリース日を2025年12月1日(月)に決定する。
- B機能の仕様は「案2(SNS認証追加)」を採用する。
- リリース告知は11月25日(火)に実施する。
2. ネクストアクション(ToDo)
| No. | タスク内容 | 担当者 | 期限 |
| 1 | 新機能A 最終QAテスト実施 | 鈴木 | 11/20(木) |
| 2 | B機能 仕様変更に伴う工数再見積もり | 高橋 | 11/17(月) |
| 3 | リリース告知文案作成 | 田中 | 11/19(水) |
| 4 | 上記文案レビュー | 山田 | 11/21(金) |
3. 議論内容(アジェンダ別)
議題1:新機能Aのリリース日について
- (佐藤)開発は11/20(木)に完了見込み。QA期間を考慮すると12/1(月)リリースが妥当。
- (田中)営業としては、月初の12/1(月)リリースを希望。
- →(決定)12/1(月)リリースとする。
議題2:B機能の仕様について
- (高橋)案1(メール認証のみ)と案2(SNS認証追加)の工数差は3人日。
- (田中)顧客からのSNS認証要望が多いため、案2を強く推奨。
- →(決定)案2を採用。工数増は山田が調整。(詳細はToDo No.2参照)
4. 保留事項・次回議題
- C機能の開発優先度について(次回11/20(木)の定例で議論)
テンプレート例②:時系列型(議論プロセス重視)
このテンプレートは、会議で「どのような議論が」「どのような順番で」行われたかを重視するものです。
アイデア出しのブレインストーミングや、複数の選択肢を比較検討した会議、あるいは顧客との重要な商談の記録に適しています。
なぜその結論に至ったのか、という「背景」や「文脈」を後から正確にたどることができます。
【議事録見本:時系列型】
新規事業アイデア検討会議 議事録
- 日時:2025年11月13日(木) 13:00〜15:00
- 場所:第3会議室
- 参加者:伊藤(部長)、渡辺、加藤、木村
- 会議の目的:来期に向けた新規事業のアイデア(A案、B案、C案)の評価
1. 議論の経過(時系列)
(13:00)会議開始、伊藤より本日の目的(3案の評価)を確認。
(13:05)■A案(AIチャットボット事業)について
- (加藤)市場は拡大傾向だが、競合(X社、Y社)が強力。差別化が課題。
- (渡辺)当社の技術リソースで対応可能か? 特に自然言語処理の知見が不足。
- (伊藤)技術面でのハードルが高い。一旦、評価は「中」とする。
(13:45)■B案(法人向けeラーニング事業)について
- (木村)既存顧客(Z社)から類似の要望あり。横展開の可能性。
- (渡辺)コンテンツ制作が鍵。社内リソースだけでは困難。外部パートナーとの協業が必要。
- (伊藤)初期投資は大きいが、ストック型ビジネスとして魅力的。評価は「高」。
(14:15)■C案(SaaS導入コンサル事業)について
- (加藤)当社の強みである業務ノウハウを活かせる。
- (木村)単発の収益になりがち。継続的な収益モデルを設計できるか?
- (渡辺)B案との親和性もある。B案の導入支援としてセット提案も可能か。評価は「高」。
(14:45)■総括と今後の進め方
- (伊藤)B案とC案の実現可能性を深掘りする。
2. 決定事項
- A案(チャットボット)は、競合優位性の確立が困難なため、一旦ペンディング(保留)とする。
- B案(eラーニング)とC案(コンサル)は、実現可能性について追加調査を行う。
3. ネクストアクション(ToDo)
| No. | タスク内容 | 担当者 | 期限 |
| 1 | B案の外部パートナー候補リストアップと概算費用調査 | 渡辺 | 11/27(木) |
| 2 | C案の競合調査と想定収益モデル(3パターン)作成 | 加藤・木村 | 11/27(木) |
4. 次回議題
- B案、C案の調査結果報告と、どちらに注力するかの一次判断。(次回 11/28(金) 13:00〜)
テンプレート例③:アジェンダ型(議題ごと)
このテンプレートは、最も一般的でバランスの取れた形式です。
事前に決められた複数のアジェンダ(議題)に沿って、議論の内容、決定事項、ToDoを議題ごとに整理していきます。
ほとんどの定例会議やプロジェクト会議で活用できます。
【議事録見本:アジェンダ型】
営業部・開発部 連携会議 議事録
- 日時:2025年11月13日(木) 16:00〜17:00
- 場所:第1会議室
- 参加者:田中(営業部長)、中村(営業)、佐藤(開発部長)、鈴木(開発)
- 会議の目的:顧客要望の共有と、次期バージョンの機能優先度すり合わせ
アジェンダ1:営業からの顧客要望(最優先)の共有
- 議論内容
- (田中)最優先要望は「モバイル対応」。特に顧客D社からの要望が強い。
- (中村)現場からも、外出先で使いたいとの声が多数。
- 決定事項
- 次期バージョン(Ver 3.0)で「モバイル対応(レスポンシブデザイン)」を最優先機能として実装する。
- ネクストアクション(ToDo)
- 特になし(決定事項にて合意)
アジェンダ2:開発からの進捗共有
- 議論内容
- (佐藤)現行バージョン(Ver 2.5)のバグ修正は順調。11/20(木)にパッチリリース予定。
- (鈴木)Ver 3.0の開発リソースは現在5名。
- 決定事項
- Ver 2.5のパッチリリースを11/20(木)に実施する。
- ネクストアクション(ToDo)
- (田中)パッチリリースの旨を、営業部から全顧客へアナウンスする。(期限:11/21(金))
アジェンダ3:次期バージョン(Ver 3.0)の機能優先度すり合わせ
- 議論内容
- アジェンダ1の「モバイル対応」を最優先とすることで合意。
- (佐藤)モバイル対応を行う場合、リソース的に「A機能」と「B機能」の同時実装は困難。
- (田中)営業的には、A機能(データ出力)の優先度が高い。
- (鈴木)A機能の実装工数は約10人日、B機能は15人日。
- 決定事項
- Ver 3.0の実装優先度は、1. モバイル対応、2. A機能(データ出力)とする。
- B機能は、Ver 3.1以降で検討する。
- ネクストアクション(ToDo)
- (佐藤・鈴木)モバイル対応とA機能を実装した場合の、Ver 3.0の現実的なリリーススケジュール案を作成し、次回会議で提示する。(期限:次回会議)
4. 次回会議
- 日時:2025年11月27日(木) 16:00〜17:00
- 議題:Ver 3.0のリリーススケジュール案の確認
【上級者向け】さらに評価される議事録の4つのテクニック
基本的な議事録が書けるようになったら、次は「この人の議事録はすごい」と一目置かれるための上級テクニックに挑戦してみましょう。
これらのテクニックは、議事録作成者の枠を超え、会議の生産性そのものを高めることにも貢献します。
単なる「記録係」から「会議のナビゲーター」へとステップアップするための4つのコツをご紹介します。
会議中にリアルタイムでメモを共有する
これは非常に高度なテクニックですが、効果は絶大です。
会議の参加者が見えるように、プロジェクターや画面共有で、あなたの議事録(メモ)をリアルタイムで映し出します。
この方法には、複数のメリットがあります。
第一に、「認識のズレ」をその場で解消できることです。
あなたがメモした「決定事項」や「ToDo」が、参加者の認識と異なっていれば、その場で「今の書き方だと、少しニュアンスが違います」と指摘してもらえます。
これにより、会議後に「言った、言わない」のトラブルが起こるのを防げます。
第二に、会議の「見える化」により、議論が脱線しにくくなることです。
今、どの議題について話しているのか、何が決まったのかが全員の目に見えるため、ファシリテーターが議論を本筋に戻しやすくなります。
第三に、会議終了と同時に、議事録のドラフトがほぼ完成することです。
参加者全員の合意を得ながらメモを取っているため、会議後の清書や確認作業が最小限で済みます。
もちろん、これを行うには、高いタイピングスキルと、議論を即座に要約する能力、そして「人前で書く」ことへの度胸が必要です。
まずは、気心の知れた社内の定例会議などで試してみるのが良いでしょう。
こちらは、リアルタイムでの共同編集がチームの透明性や合意形成にどのような影響を与えるかを研究したGoogleとACMによる学術論文です。合わせてご覧ください。 https://dl.acm.org/
会議の冒頭と最後に「決定事項」と「ToDo」を口頭で確認する
「すごい議事録」の作成者は、ただ黙ってメモを取っているだけではありません。
会議の生産性を高めるために、積極的に発言します。
まず、会議の冒頭(アジェンダ確認の際)に、「前回の議事録によりますと、本日の会議までに〇〇さんが〜を、△△さんが〜を行うことになっておりますが、状況はいかがでしょうか?」と、前回のToDoの確認を促します。
これにより、会議がスムーズに本題に入れます。
そして、最も重要なのが会議の最後、終了の5分前です。
ファシリテーターに許可を得て、「本日の議事録担当として、決定事項とネクストアクションを読み上げます」と宣言します。
そして、自分がメモした「決定事項」と「ToDoリスト(担当者、期限含む)」を口頭で読み上げ、参加者全員の前で「この内容で認識に相違ありませんでしょうか?」と確認を取ります。
もし認識がズレていれば、その場で修正します。
この「締めの一声」があるかないかで、会議の成果は劇的に変わります。
全員が「今日決まったこと」「次にやること」を明確に再認識して解散できるため、行動への移りが早くなります。
ファシリテーターと連携し、議論の脱線を防ぐ
議事録作成者は、会議の「ファシリテーター(進行役)」の最も強力なパートナーです。
ファシリテーターが議論を前に進めることに集中している間に、議事録作成者は「記録」の観点から会議をサポートします。
例えば、議論がアジェンダから脱線し始めたと感じたら、チャットや小声でファシリテーターに「今、アジェンダ2から逸れているようです」とそっと伝えることができます。
また、議論が白熱して結論が出ないまま次の議題に進みそうになったら、「恐れ入ります、先ほどのアジェンダ2ですが、結論(またはネクストアクション)はどのように記録すればよろしいでしょうか?」と、議論を「着地」させるよう促すこともできます。
逆に、ファシリテーターから「今までの議論、ちょっと整理してもらえますか?」と振られることもあります。
その際に、メモを見ながら「Aさんは〜という意見、Bさんは〜という意見で、論点は〜という点ですね」と簡潔に要約できれば、会議の進行に大きく貢献できます。
このように、ファシリテーターと議事録作成者が「二人三脚」で会議を運営する意識を持つことで、会議の質そのものが向上し、結果として「すごい議事録」が生まれやすくなります。
議事録をナレッジとして蓄積する(保管場所・ファイル名のルール化)
作成した「すごい議事録」は、共有して終わりではありません。
それは会社の貴重な「ナレッジ(知識資産)」です。
後から誰かが必要としたときに、すぐに見つけ出せるように管理することが、上級者としての最後の仕事です。
議事録の保管場所(共有フォルダ、Googleドライブ、Notion、Teamsのチャネルなど)をプロジェクトや部署単位で統一しましょう。
あちこちに分散していると、誰も探せなくなってしまいます。
さらに重要なのが、「ファイル名のルール化」です。
「議事録.docx」や「1113会議.pdf」のようなファイル名では、後から中身を推測できません。
【ファイル名の良い例】
「YYYYMMDD_プロジェクト名_会議名.docx」
例:「20251113_〇〇プロジェクト定例_議事録.docx」
例:「20251113_営業開発連携会議_議事録.docx」
このように、日付、プロジェクト名、会議名をファイル名に含めることで、誰でも検索しやすくなります。
「あの時のあの決定、どうだったっけ?」と後から振り返る際、すぐに該当の議事録にたどり着ける環境を整備すること。
これが、議事録を単なる記録から「活用されるナレッジ」へと昇華させる最後のテクニックです。
「すごい議事録」をAIで効率化!おすすめツールと活用術
これまで解説してきた「すごい議事録」の作成ステップは、非常に重要ですが、多くの工数がかかるのも事実です。
特に、会議中のメモ取りや、会議後の文字起こし・清書作業は大きな負担となります。
この負担を劇的に軽減してくれるのが、AI(人工知能)技術です。
ここでは、AI議事録ツールで何ができるのか、おすすめのツール、そしてChatGPTを活用した具体的なテクニックまでをご紹介します。
AI議事録ツールで何ができる?(文字起こし、要約、タスク抽出)
AI議事録作成ツールは、面倒な作業を自動化し、人間が「すごい議事録」の「核」となる部分、つまり「思考」や「編集」に集中できるようにサポートしてくれます。
主な機能は以下の3つです。
- 高精度な「文字起こし」会議中の音声をリアルタイムで、あるいは録音データをアップロードすることで、高精度にテキスト化します。話者分離(誰が話したかを識別する)機能も搭載されているものが多く、人間がゼロから文字起こしする手間をほぼゼロにしてくれます。
- AIによる「要約」長時間の会議の文字起こしデータ全体をAIが解析し、「会議の要点」「アジェンダごとのサマリー」を自動で生成します。これにより、議事録の清書時間を大幅に短縮できます。
- 「ネクストアクション(ToDo)」の抽出AIが会話の中から「〜さんが〜します」「〜を〜までにお願いします」といったタスクに関連する発言を識別し、ToDoリストを自動で作成してくれます。議事録で最も重要なToDoの拾い漏れを防ぐのに役立ちます。
これらの機能を活用することで、議事録作成者は、AIが生成した「下書き(ドラフト)」をベースに、より重要な「決定事項の確認」や「議論の背景の補足」といった、人間にしかできない付加価値の高い作業に時間を使えるようになります。
こちらは、AI議事録ツールを含むエンタープライズ向け対話型AIプラットフォームの市場動向や主要ベンダーを評価したGartnerのレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.gartner.com/
おすすめAI議事録作成ツール3選
2025年現在、多くの優れたAI議事録作成ツールが登場しています。
ここでは、特に人気と実績があり、機能的な特徴が異なる3つのツールを厳選してご紹介します。
- Notta(ノッタ)非常に高精度な音声認識と、100以上の言語に対応する多機能性が特徴のツールです。リアルタイムの文字起こしはもちろん、音声ファイルや動画ファイルのインポートにも対応しています。AIによる要約機能も強力で、文字起こし結果から瞬時に要点をまとめた議事録ドラフトを生成します。Web会議(Zoom, Teams, Google Meet)との連携もスムーズで、国際的な会議が多い企業や、まず高精度な文字起こしを求める場合に最適です。
- スマート書記「誰でも簡単に使える」ことを追求した、シンプルな操作性が魅力のツールです。AIによる「要約」と「要点抽出」に特に強みを持っており、会議の録音データから、重要なポイントをAIが自動でピックアップしてくれます。Web会議だけでなく、専用のスマートフォンアプリを使えば、対面(オフライン)の会議でもクリアに録音・文字起こしが可能です。ITツールが苦手な人でも直感的に使え、議事録作成の「清書」の負担を減らしたい企業に向いています。
- AmiVoice ScribeAssist(アミボイス スクライブアシスト)オフライン環境(インターネットに接続しない状態)でも利用できる、高いセキュリティが最大の特徴です。機密情報や個人情報を扱う、セキュリティ要件が厳しい会議(金融、医療、自治体など)での利用に適しています。音声認識の精度も非常に高く、専門用語を辞書登録する機能も充実しています。ChatGPTとの連携機能も搭載しており、オフラインで安全に文字起こしをした後、必要に応じて要約などをAIに任せることも可能です。
ChatGPTを使った会議の議事録作成については、具体的なプロンプト例を含めてこちらの記事で詳細に解説しています。
【ChatGPT活用】録音データから「すごい議事録」を作るプロンプト例
専用ツールを導入していなくても、多くの人が利用するChatGPT、特に最新のGPT-5モデルを活用することで、議事録作成を効率化できます。
(※注:機密情報や個人情報を含む音声データを、会社の許可なく外部のAIサービスに入力することは、セキュリティポリシーに違反する可能性があるため、必ず社内ルールを確認してください。)
生成AIを企業で利用する際には、情報セキュリティや著作権など、様々なリスク管理が求められます。企業利用リスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
まず、ICレコーダーや他のツールで会議の音声を文字起こしし、そのテキストデータ(逐語録)を準備します。
その上で、ChatGPT(GPT-5)に対して以下のような「プロンプト(指示文)」を入力します。
【ChatGPT(GPT-5)活用プロンプト例】
あなたは、優秀なビジネスアシスタントです。
以下の「会議の文字起こしテキスト」を読み込み、「すごい議事録」の形式で出力してください。
制約条件
- 会議の目的:〇〇
- 出力形式:以下の「議事録テンプレート」に従うこと
- 決定事項:会議で決まったことを明確にリストアップする
- ネクストアクション(ToDo):必ず「担当者」と「期限」を明記する
- 議論の要点:アジェンダごとに、冗長な表現を削除し、議論の骨子を簡潔にまとめる
会議の文字起こしテキスト
(ここに、文字起こししたテキストデータを貼り付ける)
議事録テンプレート
- 決定事項・・
- ネクストアクション(ToDo)| タスク内容 | 担当者 | 期限 || :— | :— | :— || | | |
- アジェンダ別の議論要点議題1:〜・・議題2:〜・・
2025年8月にリリースされたGPT-5は、複雑な長文の理解力や推論能力が飛躍的に向上しています。
このような詳細なプロンプトを与えることで、単なる要約ではなく、文脈を理解し、「決定事項」と「ToDo」を正確に抽出し、指定したフォーマットに整形した、精度の高い議事録ドラフトを生成してくれます。
無料プランでも利用できますが(回数制限あり)、有料プランであればより高速に処理が可能です。
こちらは、AIによる高精度な文字起こし技術(例: OpenAIのWhisperモデル)の基盤となった学術論文です。AIの能力と限界を理解する上で参考になります。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2212.04356
AI活用時の注意点:鵜呑みにせず最終チェックは必須
AIは非常に強力なサポート役ですが、決して万能ではありません。
AI議事録ツールやChatGPTを活用する上で、絶対に忘れてはならない注意点があります。
それは、「AIの生成結果を鵜呑みにしない」ことです。
AIは、文脈を完全には理解できず、事実誤認をしたり、重要なニュアンスを取り違えたりすることがあります。
特に、同音異義語の変換ミス(例:「仕様」と「私用」)、話者分離のミス、専門用語の誤認識は頻繁に発生します。
また、AIが抽出した「決定事項」や「ToDo」が、会議の参加者が意図したものとズレている可能性もあります。
AIが生成した議事録ドラフトは、あくまで「下書き」です。
最終的な責任は、議事録作成者である「人間」にあります。
必ず自分の目で全体をレビューし、会議の記憶と照らし合わせながら、不正確な箇所を修正し、不足している文脈を補足し、AIには汲み取れなかった微妙なニュアンスを加筆する。
この「最終チェックと編集」作業こそが、「すごい議事録」に仕上げるための最も重要なプロセスです。
AIに面倒な作業を任せ、人間は「最終的な品質保証」と「付加価値の追加」に集中する。
これが、現代におけるスマートな議事録作成術と言えるでしょう。
あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い
ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。
【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない
「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。
これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。
- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。
- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方
では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「壁打ち相手」にする
自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」
これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「無知な生徒」として教える
自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」
AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」
AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。