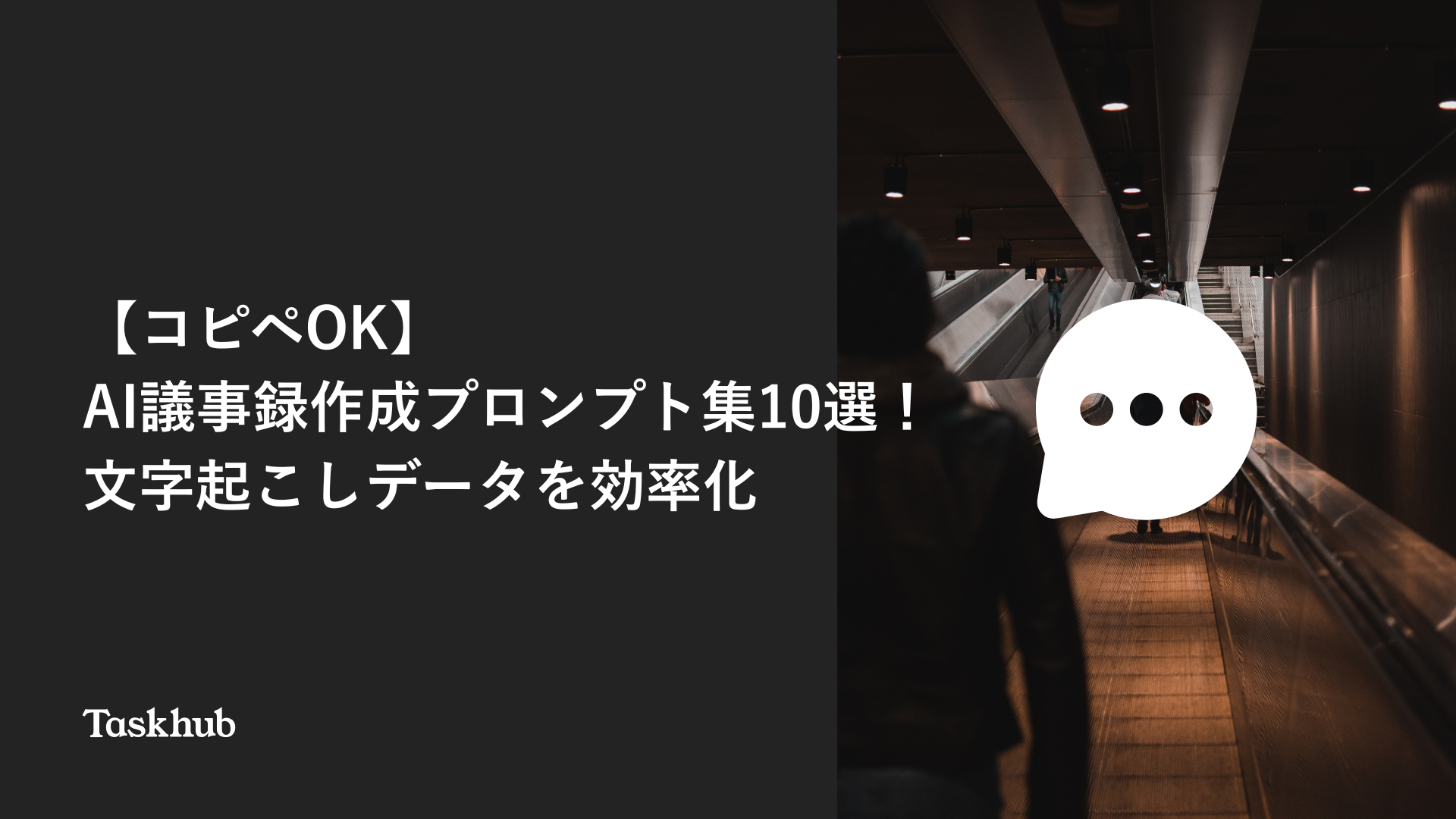「会議の文字起こしデータはあるけど、議事録作成が面倒…」
「ChatGPTで議事録を作らせても、内容が薄くて使い物にならない…」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
AIは、文字起こしデータを貼り付けて「議事録を作って」と指示するだけでは、期待した成果物を生み出しません。重要なのは、AIの能力を最大限に引き出す「プロンプト(指示文)」です。
本記事では、会議の文字起こしデータを高品質な議事録に変えるための具体的なプロンプト例10選、議事録作成を始める前の準備、そしてプロンプトの精度を上げる7つのコツについて解説しました。
生成AIのコンサルティングを専門とする弊社が、実際の業務で活用している効果実証済みのプロンプトのみをご紹介します。
きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
なぜAIプロンプトで議事録を作成するのか?
AI、特にChatGPTやGeminiのような生成AIを活用することで、従来の議事録作成プロセスは劇的に変わります。単なる時短ツールとしてだけでなく、議事録の「質」そのものを向上させる力を持っています。
主な理由は以下の3つです。
- 作業時間とコストを大幅に削減できる
- 議事録の品質が安定し、抜け漏れを防げる
- 客観的な議事録を素早く作成・共有できる
AIプロンプトを使いこなすことが、議事録作成業務のスタンダードになりつつあります。
それでは、1つずつ順に解説します。
作業時間とコストを大幅に削減できる
議事録作成における最大のメリットは、圧倒的な時間短縮です。
従来の議事録作成では、まず会議の録音データを人間が聞き直し、すべてを文字起こしする必要がありました。1時間の会議であれば、この作業だけで2〜3時間かかることも珍しくありません。
さらに、文字起こしされたテキスト(「えー」「あのー」といった不要な言葉が含まれる)を読み解き、議論の要点を抽出し、決定事項やToDoを整理して清書する作業が発生します。この工程にも1時間以上かかることが多く、議事録作成は非常に工数がかかる業務でした。
AIプロンプトを活用すれば、このプロセスが劇的に変わります。
AI文字起こしツールでテキストデータさえ用意すれば、AIはわずか数十秒から数分で議事録の草案を作成します。人間が行う作業は、AIが生成した内容を確認し、必要に応じて修正・追記するだけです。
これまで3時間以上かかっていた作業が、15分から30分程度に短縮されるケースも珍しくありません。
この削減された時間を、議事録作成という単純作業ではなく、次のアクションプランの策定や、より創造的な業務に充てることができます。これがAIを活用する最大の価値です。
こちらは、AI自動文字起こしの導入により、議事録作成の時間が約4割削減された実際の事例を紹介した記事です。 合わせてご覧ください。 https://jichitai.works/articles/1209
議事録の品質が安定し、抜け漏れを防げる
人間が議事録を作成する場合、その品質は担当者のスキルや経験、さらにはその日の体調によって左右されがちです。
会議のテーマに関する知識が浅い担当者では、重要な論点や決定事項のニュアンスを正確に汲み取れない可能性があります。また、長時間の会議では集中力が途切れ、重要な発言を聞き逃す(書き漏らす)リスクも高まります。
AIプロンプトを用いた議事録作成は、この「属人性」を排除します。
あらかじめ「決定事項」「ToDo」「重要な論点」といったフォーマットをプロンプトで指定しておくことで、AIは文字起こしデータ全体を網羅的にスキャンし、指示された項目を忠実に抽出します。
AIは疲れを知らず、集中力を切らすこともありません。
そのため、会議の長さや複雑さに関わらず、常に一定の基準で情報を整理します。これにより、誰が担当しても議事録の品質が安定し、重要な決定事項やタスクの抜け漏れを組織的に防ぐことができます。
特に複数のプロジェクトが並行して進むような環境では、品質が担保された議事録が安定供給されることの業務効率化へのインパクトは計り知れません。
客観的な議事録を素早く作成・共有できる
議事録は、会議に参加しなかった関係者にとっても重要な情報源です。しかし、人間が作成した議事録には、作成者の主観や解釈が意図せず入り込んでしまうことがあります。
特定の発言を重要視しすぎたり、逆に作成者が重要でないと判断した論点を省略してしまったりすることです。
AIは、プロンプトで指示されない限り、主観的な解釈を加えません。
入力された文字起こしデータという「事実」に基づき、議論の構造を客観的に整理・要約します。これにより、会議で何が話され、何が決まったのかがバイアスなく記録されます。
また、AIによる作成スピードは圧倒的です。
会議終了後、すぐに文字起こしデータとプロンプトをAIに投入すれば、数分後には議事録のドラフトが完成します。人間が清書する時間を待つ必要がなく、会議終了からわずか1時間以内に、客観的な議事録を関係者全員に共有することも可能です。
このスピード感は、プロジェクトの推進において極めて重要です。
決定事項やToDoが即座に共有されることで、関係者の認識齟齬が減り、次のアクションへスムーズに移行できるようになります。
議事録作成プロンプトでできること
議事録作成プロンプトは、単に文字起こしデータを要約するだけではありません。
指示(プロンプト)を工夫することで、会議の成果を最大限に活用するための多様なアウトプットをAIに生成させることができます。
具体的には以下のような処理が可能です。
- 会議内容の要約
- 決定事項やToDo(やるべきこと)の抽出
- 話し言葉を書き言葉(文語)に自動で変換
これらの機能を組み合わせることで、目的に応じた最適な議事録を効率的に作成できます。
それでは、それぞれのできることについて詳しく見ていきましょう。
会議内容の要約
AIの最も得意とするタスクの一つが「要約」です。
1時間にわたる会議の膨大な文字起こしデータを読み込ませ、「会議全体の要点を300文字でまとめて」や「主要なトピックごとに要約して」と指示するだけで、AIは瞬時に内容を凝縮します。
これは、会議の概要だけを素早く把握したい上司への報告や、Slackなどのチャットツールでの情報共有に非常に便利です。
従来の議事録では、全文を読まなければ概要がつかめないこともありましたが、AIを使えば「全体像を掴むための要約」と「詳細を記した議事録本体」を同時に生成できます。
また、単に要約するだけでなく、「この会議の目的はAですが、その目的に関連する議論だけを抜き出して要約して」といった、特定の視点に基づいた要約も可能です。
これにより、文字起こしデータを何度も読み返すことなく、必要な情報だけを効率的に抽出できます。
AIは文脈を理解する能力が高いため、単なるキーワードの頻出度ではなく、議論の流れ全体を踏まえた上で、本当に重要なポイントをピックアップして要約を生成してくれます。
決定事項やToDo(やるべきこと)の抽出
会議の最も重要な成果は、「何が決まったのか(決定事項)」と「次に誰が何をするのか(ToDo)」です。
しかし、議事録の中でこれらの情報が本文に埋もれてしまうと、後から確認するのが困難になり、タスクの実行漏れにつながります。
AIプロンプトを使えば、これらの重要な情報を自動で抽出し、リスト化することが可能です。
「会議で決定した事項を箇条書きで抜き出してください」や「発生したToDoを、担当者と期限がわかる形式でリストアップしてください」と具体的に指示します。
AIは文字起こしデータの中から、「〜で決定します」「〜さんが担当してください」「期限は〜まで」といったキーワードや文脈を検出し、それらを整理します。
特にToDoについては、「担当者」「タスク内容」「期限」の3点を明確にさせるプロンプトが有効です。
この機能により、議事録が単なる「記録」から、次のアクションを促す「実行リスト」へと変わります。
こちらは、長い会議の文字起こしデータから「アクションアイテム(ToDo)」を効率的に抽出・要約するAIの技術について解説した研究論文です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/html/2312.17581v2
会議終了後、すぐにこのToDoリストをプロジェクト管理ツールやタスク管理アプリに転記することで、プロジェクトの推進力を格段に高めることができます。
話し言葉を書き言葉(文語)に自動で変換
会議の文字起こしデータは、「えー」「あのー」「〜ですね」といった冗長な表現(ケバ)や、倒置法、口語表現(話し言葉)で満たされています。
これをそのまま議事録として共有すると、非常に読みにくく、意図が伝わりにくい文章になってしまいます。
従来は、この「ケバ取り」と「整文(話し言葉から書き言葉への変換)」を人間が手作業で行っていました。これは非常に時間のかかる作業です。
AIは、この整文作業も得意としています。
「以下の文字起こしデータを、議事録として適切な書き言葉(文語)に変換してください。その際、不要なフィラー(えー、あのー等)は削除し、発言の意図は変えずに読みやすい文章にしてください」といったプロンプトを使います。
AIは、文脈を保ちながら「〜でよろしいですか?」を「〜で問題ないか確認する。」、「めっちゃいいと思います」を「非常に良い提案だと考える。」といったように、ビジネス文書として適切な表現に自動で変換します。
この機能により、人間は面倒な「てにをは」の修正作業から解放され、AIが生成した議事録の内容が「事実として正しいか」「重要なニュアンスが落ちていないか」という、より本質的な確認作業に集中することができます。
こちらは、AIが話し言葉(口語)の文脈を理解し、自然な書き言葉(文語)に変換する「CoS2W」という技術について解説した研究論文です。 合わせてご覧ください。 https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/34642/36797
また、そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
AI議事録作成の準備:文字起こしとツールの選定
AIで議事録を作成するといっても、いきなりAIにプロンプトを入力すれば完成するわけではありません。
精度の高い議事録を作るためには、その前段階である「準備」が非常に重要です。
主に以下の3つの準備が必要になります。
- 準備1:会議の文字起こしデータを用意する
- 準備2:使用するAIツールを選ぶ(ChatGPT, Gemini, Claudeなど)
- 準備3:社内のセキュリティルールを確認する
特に「文字起こしデータの質」と「セキュリティ」は、AI議事録作成の成否を分ける重要なポイントです。
それぞれの手順を具体的に解説します。
準備1:会議の文字起こしデータを用意する
AI議事録作成の品質は、インプットとなる「文字起こしデータ」の品質に大きく依存します。
「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉通り、文字起こしデータの精度が低ければ、AIは文脈を誤解し、不正確な議事録を生成してしまいます。
まず、精度の高い文字起こしデータを用意することが不可欠です。
会議の録音時には、できるだけクリアな音声が取れるよう、専用のマイクを使用したり、静かな環境を選んだりする工夫が求められます。
次に、その音声データをテキスト化します。
現在は高精度なAI文字起こしツール(例:Notta, Rimo Voice, CLOVA Noteなど)が多数存在します。これらのツールの多くは「話者分離機能」を備えており、「Aさん:〜」「Bさん:〜」という形で、誰が何を話したかを自動で識別してくれます。
議事録作成プロンプトをAIに入力する際は、この「話者分離」がされたテキストを使用することが強く推奨されます。
話者が明確でないテキスト(会話がすべて繋がってしまっているテキスト)では、AIは「誰が決定したのか」「誰がToDoを担当するのか」を正確に判断できません。
AI議事録作成の第一歩は、高精度な話者分離済みの文字起こしデータを用意することです。
準備2:使用するAIツールを選ぶ(ChatGPT, Gemini, Claudeなど)
文字起こしデータが準備できたら、次にそれ処理するAIツールを選びます。
代表的な対話型AIには、OpenAIの「ChatGPT」、Googleの「Gemini」、Anthropicの「Claude」があります。
2025年現在、これらのAIは急速に進化しており、特に長文の取り扱い(コンテキストウィンドウ)において大きな違いがあります。
ChatGPT(GPT-5.1など):OpenAIの最新モデル群です。2025年8月にGPT-5がリリースされた後もアップデートが続いており、質問の難易度に応じて思考時間を自動で切り替える機能などが特徴です。有料プラン(ChatGPT Plusなど)では、長文の取り扱いも大幅に改善されています。
Gemini(2.5 Pro):Googleの最新モデルです。最大で100万〜200万トークン(日本語で数十万〜100万文字以上)という巨大なコンテキストウィンドウを持ち、非常に長い会議の文字起こしデータも一度に処理できる可能性があります。
Claude(Opus 4.1 / Sonnet 4.5など):Anthropicの最新モデル群です。こちらも数十万トークンの長文入力に対応しており、複雑な指示の理解度や、出力の自然さに定評があります。
1時間を超えるような長い会議の文字起こしデータを扱う場合、コンテキストウィンドウが広いGeminiやClaudeが有利になる傾向があります。
一方、30分程度の短い会議であれば、ChatGPTでも十分に対応可能です。ツールの特性を理解し、会議の長さや目的に応じて使い分けることが重要です。
ClaudeとChatGPTの性能や料金体系の違いについて詳しく比較した記事です。ツール選定の参考にしてください。
準備3:社内のセキュリティルールを確認する
AIで議事録を作成する上で、最も注意すべき点が「セキュリティ」です。
会議の文字起こしデータには、社外秘の情報、顧客の個人情報、未公開の経営情報など、機密情報が含まれる可能性が非常に高いです。
これらの情報を、セキュリティルールを確認せずに安易に外部のAIサービスに入力すると、重大な情報漏洩インシデントにつながる危険があります。
まず、自社の情報セキュリティ部門に、ChatGPTなどの外部AIサービスの利用が許可されているかを確認してください。
多くのAIサービスでは、入力されたデータをAIの学習に利用する場合があります。これを防ぐ「オプトアウト(学習利用の拒否)」設定が可能か、またはデフォルトで学習に利用しない設定になっているかを確認する必要があります。
無料版のAIツールは、入力データが学習に使われるリスクが高いため、ビジネスでの利用は避けるべきです。
企業向けの有料プラン(ChatGPT Enterprise, Gemini for Google Workspace, Claude Proなど)や、データを学習に利用しないと明記されているAPI経由での利用が推奨されます。
また、そもそも「機密情報AランクはAIに入力禁止」「顧客名は匿名化してから入力する」といった社内ルールが定められている場合もあります。
便利なプロンプトを試す前に、必ず自社のセキュリティポリシーを確認し、定められたルールの中で運用することが鉄則です。
こちらは、AI議事録アシスタントを利用する際の、具体的なセキュリティとプライバシーのリスクについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://fellow.ai/blog/ai-meeting-assistant-security-and-privacy/
AIで文字起こしから議事録を作成する5つのステップ
準備が整ったら、いよいよAIを使って議事録を作成します。
プロセスは非常にシンプルですが、各ステップで精度を高めるための小さなコツがあります。
全体の流れは以下の5ステップです。
- ステップ1:会議の音声データを文字起こしする
- ステップ2:AIツールに文字起こしデータを入力する
- ステップ3:プロンプトを入力して議事録を生成する
- ステップ4:生成された議事録をコピーする
- ステップ5:内容を確認し、必要に応じて修正する
この手順を踏むことで、誰でも効率的に高品質な議事録を作成できます。
それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:会議の音声データを文字起こしする
まず、会議の音声データ(.mp3, .m4a, .wavなど)をAI文字起こしツールにアップロードします。
前述の通り、ここで重要なのは「話者分離」が可能なツールを選ぶことです。
ツールが音声をテキスト化するのを待ちます。
文字起こしが完了したら、生成されたテキスト全体にざっと目を通し、明らかな誤変換がないかを確認します。
特に、会議で頻出する「固有名詞(人名、会社名、製品名)」や「専門用語」は、AIが誤って認識しやすいポイントです。
例えば、「佐藤さん」が「加藤さん」になっていたり、製品名「Project-Alpha」が「プロジェクト・アルファ」とカタカナになっていたりすることがあります。
これらの誤字は、後のステップでAIが議事録を生成する際に、そのまま反映されてしまいます。
完璧に修正する必要はありませんが、議事録の根幹に関わるような重要な単語の誤りは、この段階でテキストデータを修正しておくと、最終的な議事録の品質が向上します。
ステップ2:AIツールに文字起こしデータを入力する
次に、修正した文字起こしデータをコピーし、使用するAIツール(ChatGPT, Gemini, Claudeなど)の入力欄に貼り付けます。
ここで注意すべき点が、AIツールの「文字数制限(コンテキストウィンドウ)」です。
1時間を超える会議の文字起こしデータは、日本語でも数万文字に達することがあります。
多くのAIツール(特に無料版や旧世代のモデル)には、一度に入力できる文字数に上限があります。
上限を超える長文を入力しようとすると、エラーが表示されたり、テキストの後半部分が自動的に切り捨てられたりしてしまいます。
その場合は、文字起こしデータを「前半」「後半」のように、意味の区切りが良いところで2〜3回に分けて入力する必要があります。(詳細は後述のプロンプト8で解説します)
一方で、Gemini 2.5 ProやClaude 4 Opusなど、最新の高性能モデルは非常に大きなコンテキストウィンドウを持っているため、1〜2時間の会議データであれば丸ごと一度に貼り付けても処理できる可能性が高いです。
ステップ3:プロンプトを入力して議事録を生成する
文字起こしデータを貼り付けたら、その直後に(または先に)議事録作成を指示する「プロンプト」を入力します。
ここで「議事録を作って」という曖昧な指示をしてはいけません。
「あなたはプロの編集者です。以下の文字起こしデータから、指定のフォーマットで議事録を作成してください」といった具体的な指示が重要です。
このプロンプトの質が、議事録の品質を決定します。
例えば、以下のように具体的な「出力フォーマット」を指定することが非常に効果的です。
(プロンプト例)
# 指示
以下の会議の文字起こしデータから、下記のフォーマットに従って議事録を作成してください。
# 文字起こしデータ
(ここにデータを貼り付ける)
# 出力フォーマット
1. 会議の概要(300文字以内)
2. 決定事項(箇条書き)
3. ToDoリスト(担当者、タスク内容、期限を明記)
4. 主要な議論のポイント(トピックごと)
5. 保留事項・次回への申し送り
このように、AIに「何を」「どのような形」で出力してほしいのかを明確に伝えることで、AIは迷うことなく期待通りの議事録を生成します。
ステップ4:生成された議事録をコピーする
プロンプトを入力して実行すると、AIが議事録の生成を開始します。
文字起こしデータの量にもよりますが、通常は数十秒から数分で議事録の草案が生成されます。
AIが満足のいく議事録を生成したら、その内容をコピーします。
多くのAIツールには、生成結果の右下や左下に「コピー」ボタンが用意されているため、それをクリックするのが簡単です。
コピーした内容は、Word、Googleドキュメント、Notion、または社内の議事録管理システムなど、普段使用しているドキュメントツールに貼り付けます。
この際、AIツール上(チャット画面上)で直接修正作業を行うのは避けた方が賢明です。チャットの履歴が流れてしまったり、誤ってブラウザを閉じてしまったりすると、作業内容が失われるリスクがあるためです。
必ず、使い慣れたドキュメント編集ツールに一度ペーストし、そこで最終的な仕上げを行います。
ステップ5:内容を確認し、必要に応じて修正する
AIが生成した議事録は、あくまで「草案(ドラフト)」です。
これをそのまま共有してはいけません。必ず人間の目で最終確認(ファクトチェック)を行います。
AIは非常に優秀ですが、100%完璧ではありません。
特に、以下のような点はAIが間違いやすいポイントです。
- ニュアンスの誤解: 皮肉や冗談、あるいは「前向きに検討する(=実際にはやらない)」といった、日本語特有の微妙なニュアンスをAIが真逆に解釈してしまうことがあります。
- 決定事項の取り違え: 「A案とB案が議論された」結果、「最終的にA案が採用された」のか「両方とも保留になった」のか、結論部分をAIが誤って認識することがあります。
- ToDoの抜け漏れ: 「じゃあ、これは佐藤さん、お願い」といった軽い口調でのタスク依頼を、AIが正式なToDoとして検知できない場合があります。
- 事実誤認(ハルシネーション): 稀に、文字起こしデータに存在しない情報(例:会議に参加していない人の名前を出す、言ってもいない結論を捏造する)をAIが生成することがあります。
こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。
これらの誤りがないか、会議に参加した人間の記憶と照らし合わせながら、内容を精査・修正します。
この最終確認のステップを経ることで、初めてAI議事録は「信頼できる公式な記録」となります。
【コピペOK】議事録作成プロンプト例文集10選
ここからは、議事録作成のさまざまなシーンでそのまま使える、具体的なプロンプトの例文を10個紹介します。
これらのプロンプトは、AIに明確な指示を与えるための工夫を含んでいます。
目的に合わせて使い分けてみてください。
- プロンプト1:【基本】要約と決定事項を抽出する
- プロンプト2:【詳細】指定フォーマットで議事録を作成する
- プロンプト3:【発言者別】会話形式で整理する
- プロンプト4:【ToDo抽出】担当者と期限を明確にする
- プロンプト5:【論点整理】議論のポイントと課題をまとめる
- プロンプト6:【時系列】会議の流れに沿って要約する
- プロンプト7:【口語→文語】丁寧な文体に変換する
- プロンプト8:【長文対応】長い文字起こしデータを分割処理する
- プロンプト9:【多言語】会議内容を翻訳して議事録にする
- プロンプト10:【応用】要点がバラバラなメモから議事録を作成する
これらのプロンプトはあくまで土台です。
自分の業務に合わせて「フォーマット」や「指示内容」をカスタマイズすることで、さらに精度の高い議事録作成が可能になります。
プロンプト1:【基本】要約と決定事項を抽出する
最も基本的で、使用頻度の高いプロンプトです。
会議の概要と、最も重要な「決まったこと」だけを素早く抽出したい場合に有効です。Slackなどでの迅速な情報共有に適しています。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、優秀なビジネスアシスタントです。
以下の「文字起こしデータ」を読み込み、会議の「要約」と「決定事項」の2点を抽出してください。
# 制約条件
・要約は、会議の主要なトピックが300文字程度で理解できるようにまとめてください。
・決定事項は、箇条書きで簡潔にリストアップしてください。
・文字起こしデータに存在しない内容は含めないでください。
# 文字起こしデータ
(ここに、話者分離された文字起こしテキストを貼り付ける)
# 出力
## 会議の要約
(ここに要約が出力される)
## 決定事項
* (ここに決定事項1が出力される)
* (ここに決定事項2が出力される)
このプロンプトのポイントは、「要約」と「決定事項」という2点に絞り込んでいることです。
AIにあれもこれもと指示を出すと、出力の焦点がぼやけることがあります。まずは最も重要な情報だけを確実に抜き出すことが重要です。
「300文字程度で」と具体的な文字数を指定することで、AIは情報の粒度を調整しやすくなります。
AIが要約を作成する際は、文字起こしデータ全体を俯瞰し、最も頻繁に議論されたテーマや、議論の転換点となった発言を重視して文章を構成します。決定事項の抽出では、「〜でいきましょう」「〜に決定します」といった確定的な表現をAIが検知し、リストアップします。
プロンプト2:【詳細】指定フォーマットで議事録を作成する
社内での正式な記録として残すため、詳細なフォーマットを指定して議事録を作成するプロンプトです。
このプロンプトは、必要な項目を網羅的にAIに生成させたい場合に非常に強力です。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、上場企業の議事録作成を担当するプロフェッショナルです。
以下の「文字起こしデータ」を分析し、「出力フォーマット」で指定されたすべての項目を埋めて、詳細な議事録を作成してください。
# 制約条件
・発言者の意図を正確に反映し、客観的な事実のみを記述してください。
・「えー」「あのー」などの不要なフィラーは削除し、話し言葉(口語)を書き言葉(文語)に変換してください。
・各項目で該当する内容が文字起こしデータにない場合は、「該当なし」と記載してください。
# 文字起こしデータ
(ここに、話者分離された文字起こしテキストを貼り付ける)
# 出力フォーマット
—
## 1. 会議名
(会議のテーマから推測して記載)
## 2. 日時・場所
(不明な場合は「該当なし」)
## 3. 出席者
(文字起こしデータの話者名からリストアップ)
## 4. 会議の目的
(議論の冒頭から推測して記載)
## 5. 決定事項
(箇条書きで記載)
## 6. ToDo(ネクストアクション)
* 【担当者】(タスク内容)(期限:YYYY/MM/DD)
## 7. 議論の詳細(主要トピック別)
### トピック1:(議論されたテーマ)
* (議論の要点や経緯)
### トピック2:(議論されたテーマ)
* (議論の要点や経緯)
## 8. 保留事項・今後の課題
(今回決まらなかったこと、次回議論すること)
—
このプロンプトのポイントは、「出力フォーマット」を非常に具体的に定義している点です。
AIは与えられたフォーマットに従うことを得意としています。##(H2)や ###(H3)、*(箇条書き)といったマークダウン記法をプロンプトに含めることで、AIも同じ形式で出力します。
「ToDo」の項目では、「担当者」「タスク内容」「期限」を明記するように指示することで、実行可能なタスクリストをAIが作成します。
「議論の詳細」では、AIが文字起こしデータから主要なトピックを自動で判別し、それぞれについて議論の概要をまとめるよう指示しています。
プロンプト3:【発言者別】会話形式で整理する
議論の経緯や、誰がどのような意見を持っていたのかを詳細に把握したい場合に適したプロンプトです。
全体の要約ではなく、会話の流れを時系列で追いながら、不要な部分だけを削ぎ落としたい場合に有効です。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、優秀な速記者です。
以下の「文字起こしデータ」を読み込み、「制約条件」に従って、会議の内容を発言者別に整理してください。
# 制約条件
・発言者ごとに、発言内容の要点をまとめてください。
・会話の時系列は維持してください。
・「えー」「あのー」「えっと」などの不要なフィラー(ケバ)のみを削除してください。
・発言の意図やニュアンスは変更せず、できるだけ元の発言に忠実に整理してください。
・話し言葉(口語)を無理に書き言葉(文語)に変換する必要はありません。
# 文字起こしデータ
(ここに、話者分離された文字起こしテキストを貼り付ける)
# 出力(例)
Aさん:新機能のUIデザインについて、B案の方がユーザーにとって直感的だと思います。
Bさん:B案ですね。ただ、開発工数がA案の1.5倍になる点が懸念です。
Cさん:工数ですか。リリース時期への影響はどれくらいでしょう?
Bさん:B案を採用する場合、スケジュールを2週間後ろ倒しにする必要があります。
Aさん:うーん、それは難しいですね。では、A案をベースに改善する方向でいきましょう。
このプロンプトのポイントは、「ケバ取り」のみを指示し、「文語変換」をあえて指示していない点です。
これにより、AIは議論の生々しい雰囲気や、発言の勢いを残したままテキストをクリーンにします。
「時系列は維持してください」という指示も重要です。AIは情報を整理する際に時系列を並べ替えてしまうことがありますが、この指示によって議論の流れがそのまま再現されます。
この出力は、後から「あの時のあの発言、どういう意図だったか?」と議論の背景を詳細に振り返りたい場合や、法的な証拠として会話の記録を残す必要がある場合に特に役立ちます。
プロンプト4:【ToDo抽出】担当者と期限を明確にする
議事録の他の要素は不要で、とにかく「次に何をすべきか」だけを明確にしたい場合の特化型プロンプトです。
会議の参加者がすぐに次の行動に移れるようにすることを目的としています。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、プロジェクトマネージャーのアシスタントです。
以下の「文字起こしデータ」から、「ToDo(ネクストアクション)」のみをすべて抽出してください。
# 制約条件
・必ず「担当者」「タスク内容」「期限」の3つの要素を抽出してください。
・期限が明確に発言されていない場合は、「期限:要確認」と記載してください。
・担当者が明確に発言されていない場合は、「担当者:要確認」と記載してください。
・決定事項や議論の経緯など、ToDo以外の情報は一切出力しないでください。
# 文字起こしデータ
(ここに、話者分離された文字起こしテキストを貼り付ける)
# 出力フォーマット
## ToDoリスト
* 【担当者】(タスク内容)(期限:YYYY/MM/DD)
* 【担当者】(タスク内容)(期限:要確認)
* 【担当者】(タスク内容)(期限:YYYY/MM/DD)
このプロンプトのポイントは、「ToDo以外の情報は一切出力しないでください」という強い否定形の指示(ネガティブプロンプト)を入れている点です。
AIは時に関連情報を付け加えたがる傾向がありますが、これを制限することで、出力結果をシャープにします。
また、「担当者」や「期限」が曖昧だった場合の対処法(「要確認」と記載)を具体的に指示しているのも特徴です。これにより、AIが不明な情報を無理に推測するのを防ぎ、抜け漏れ防止のリストとして機能します。
このプロンプトの出力結果は、そのままコピーしてタスク管理ツール(Asana, Trello, Backlogなど)に貼り付けることができます。
プロンプト5:【論点整理】議論のポイントと課題をまとめる
会議で決定事項は出なかったものの、重要な議論が行われた場合に有効なプロンプトです。
「何が話し合われたのか」「どのような意見(賛否両論)が出たのか」「どこが課題なのか」を明確にします。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、優れたコンサルタントです。
以下の「文字起こしデータ」は、あるテーマについてのブレインストーミング会議の記録です。
議論の「主要な論点」、それぞれの論点に対する「主な意見(賛成・反対など)」、そして「特定された課題や懸念点」を整理してください。
# 制約条件
・決定事項を無理に探す必要はありません。議論のプロセスを重視してください。
・議論されたトピック(論点)ごとに項目を分けて整理してください。
# 文字起こしデータ
(ここに、話者分離された文字起こしテキストを貼り付ける)
# 出力フォーマット
## 議論の論点整理
### 論点1:(議論されたテーマ)
* **主な意見:**
* (意見A:例)〜という理由で賛成する意見があった。
* (意見B:例)〜のリスクがあるため慎重に進めるべきとの意見があった。
* **特定された課題:**
* (課題A:例)コストが想定を上回る可能性がある。
### 論点2:(議論されたテーマ)
* **主な意見:**
* (意見C:例)〜のメリットが強調された。
* **特定された課題:**
* (課題B:例)具体的な実行体制が未定である。
このプロンプトのポイントは、「決定事項を無理に探す必要はありません」とAIに伝えることで、結論が出ていない議論(ブレストなど)の整理に適応させている点です。
AIは結論や決定事項を抽出しようとする傾向が強いため、この指示でAIの動作を調整します。
「論点」「主な意見」「課題」という3つの視点で情報を整理させることで、会議の参加者が漠然と「色々話したな」で終わらせず、議論の成果を客観的に可視化できます。
この出力結果は、次回の会議のアジェンダ(議題)を設計するための基礎資料として非常に役立ちます。
プロンプト6:【時系列】会議の流れに沿って要約する
議事録を「読む」のではなく「流れを追体験」したい場合に使うプロンプトです。
議論がどのように始まり、どのように展開し、どのような結論(あるいは保留)に至ったのか、そのプロセスを時系列で簡潔にまとめ直します。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、会議の書記担当です。
以下の「文字起こしデータ」を読み込み、会議の議論の流れがわかるように、「時系列」で要点をまとめてください。
# 制約条件
・会議の「開始」「中盤」「終盤」の3つのフェーズに分けて、議論の展開を要約してください。
・「えー」「あのー」などのフィラーは削除し、簡潔な文章にしてください。
・発言者名は不要ですが、誰の意見かはわかるように記述してください。(例:Aさんから〜の提案があった)
・各フェーズの要約は、3〜5行程度にまとめてください。
# 文字起こしデータ
(ここに、話者分離された文字起こしテキストを貼り付ける)
# 出力フォーマット
## 会議の議論サマリー(時系列)
【会議の開始】
(議論が始まったキッカケや、提示されたアジェンダの要約。例:Aさんから新機能Bに関する課題が共有され、議論が開始された。)
【議論の中盤】
(議論が最も発展した部分の要約。例:課題解決のためにC案とD案が提示され、それぞれのメリット・デメリットについて意見が交わされた。C案はコスト面、D案はスケジュール面で課題があることが判明した。)
【会議の終盤】
(議論の着地点や、決定事項・保留事項の要約。例:最終的に、D案のスケジュール課題を解決する方法を次回までに検討することとなり、C案は見送りとなった。BさんがD案の再調査を担当することが決まった。)
このプロンプトのポイントは、「開始」「中盤」「終盤」というフェーズを指定することで、AIに物語の起承転結のように議論を再構成させている点です。
単なる要約ではなく、時間軸に沿った「流れ」を重視することで、会議に参加しなかった人でも、なぜその結論に至ったのかを経緯を含めて理解しやすくなります。
「発言者名は不要」としながらも「誰の意見かはわかるように」という、一見矛盾するような指示を入れることで、AIは「Aさん:」という形式ではなく、「Aさんから〜の提案があった」という自然な文章を生成します。
プロンプト7:【口語→文語】丁寧な文体に変換する
このプロンプトは、特定のタスク(要約やToDo抽出)を指示するものではなく、文字起こしデータそのものをクリーンアップ(整文)するために使います。
顧客への提出資料や、社内の公式な記録として、失礼のない丁寧な文体に整えたい場合に有効です。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、プロのテープ起こし(整文)担当者です。
以下の「文字起こしデータ」を、ビジネス文書として適切な、丁寧な書き言葉(文語・敬体、「です・ます」調)に変換してください。
# 制約条件
・発言の意図や内容は絶対に改変しないでください。
・「えー」「あのー」「なんか」「めっちゃ」などの不要なフィラーや俗語は完全に削除してください。
・「〜っすね」「〜みたいな」といった口語表現を、「〜です」「〜と考えられます」といった丁寧な表現に修正してください。
・話者分離(例:Aさん:)は維持してください。
# 文字起こしデータ
(ここに、話者分離された文字起こしテキストを貼り付ける)
# 変換前の例
Aさん:なんか、B案って、コストめっちゃ高いっすよね?
Bさん:あー、そうなんすよ。でも、クオリティは絶対こっちがいいと思うんすよね。
# 変換後の出力(期待する形式)
Aさん:B案は、コストが非常に高いのではないでしょうか?
Bさん:はい、その通りです。しかし、品質はこちらの方が確実に高いと考えます。
このプロンプトのポイントは、「変換前の例」と「変換後の出力(期待する形式)」という具体例をAIに示すこと(Few-shotプロンプティング)です。
AIは具体例を与えられると、指示の意図をより正確に理解し、期待する文体(この場合は「です・ます」調の丁寧な文語)で出力する精度が格段に上がります。
「俗語は完全に削除」や「口語表現を丁寧な表現に修正」といった具体的な指示と、「発言の意図は改変しない」という制約を組み合わせることで、原文のニュアンスを保ちつつ、フォーマルな文章に変換させることができます。
この整文済みテキストをベースに、ステップ1の要約プロンプトなどを実行すると、さらに高品質な議事録が生成されます。
プロンプト8:【長文対応】長い文字起こしデータを分割処理する
AIには一度に入力できる文字数(トークン数)に上限があります。1時間や2時間を超える会議の文字起こしデータは、この上限を超えることがよくあります。
その場合、データを分割してAIに入力する必要がありますが、単純に分割すると文脈が途切れてしまいます。このプロンプトは、文脈を維持したまま分割処理を行うための指示です。
(1回目のプロンプト:前半のデータを入力)
# あなたへの指示
これから非常に長い会議の文字起こしデータを分割して入力します。
これは全体の「パート1」です。
すべてのデータを入力し終えるまで、要約や議事録作成を開始しないでください。
この「パート1」の内容を読み込んだら、「パート2のデータを入力してください」とだけ返答してください。
# 文字起こしデータ(パート1/全2回)
(ここに、文字起こしデータの前半部分を貼り付ける)
(AIが「パート2のデータを入力してください」と返答したら、2回目のプロンプトを入力)
# あなたへの指示
これが「パート2(最終回)」のデータです。
先ほど入力した「パート1」のデータと、今回の「パート2」のデータをすべて結合し、一つの会議の記録として扱ってください。
# 文字起こしデータ(パート2/全2回)
(ここに、文字起こしデータの後半部分を貼り付ける)
# 実行指示
すべてのデータを読み込みました。
これまでのデータ全体を分析し、以下のフォーマットで議事録を作成してください。
# 出力フォーマット
1. 会議の概要(500文字以内)
2. 決定事項(箇条書き)
3. ToDoリスト(担当者、タスク内容、期限を明記)
4. 議論のポイント
このプロンプトのポイントは、AIとの対話を通じて、長文データを段階的に記憶させる点です。
1回目で「まだ続きます。作業を開始しないでください」と明確に指示し、AIに待機させます。
2回目で「これが最後です。今までのデータと結合してください」と指示し、最後に「実行指示」を与えることで、AIは分割されたデータ全体を俯瞰して議事録を作成します。
Gemini 2.5 ProやClaude Opus 4.1/Sonnet 4.5のような長文対応モデルではこの作業が不要になるケースも増えていますが、ChatGPT(GPT-5系統)や古いモデルを使う場合には必須のテクニックです。
プロンプト9:【多言語】会議内容を翻訳して議事録にする
グローバルなチームでの会議など、英語や他の言語で会議が行われた場合の文字起こしデータを、日本語の議事録に変換するためのプロンプトです。
単なる翻訳ではなく、議事録としての体裁を整える点が重要です。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、バイリンガルの優秀なビジネスアシスタントです。
以下の「英語の文字起こしデータ」を読み込み、日本語で議事録を作成してください。
# 制約条件
・まず、文字起こしデータを日本語に自然な形で翻訳してください。
・その上で、日本語の「出力フォーマット」に従って議事録を整理してください。
・専門用語は無理に意訳せず、適切な日本語訳がない場合はカッコ書きで元の英語(例:KPI)を併記してください。
# 英語の文字起こしデータ
(Example:)
John: OK team, let’s discuss the Q4 marketing plan. The main goal is to increase our leads by 20%.
Sarah: I agree. For the new campaign, I propose we focus on video content for social media.
John: Video content… good. What’s the timeline for that, Sarah?
Sarah: We can start production next week and launch by Dec 1st.
John: OK, approved. Sarah, you are in charge of this task. Deadline is Dec 1st.
# 出力フォーマット(日本語)
## 1. 会議の概要
(日本語で要約)
## 2. 決定事項
* (日本語で記載)
## 3. ToDoリスト
* 【担当者】(タスク内容)(期限:YYYY/MM/DD)
## 4. 議論の詳細
(日本語で記載)
このプロンプトのポイントは、「翻訳」と「議事録作成」という2つのタスクを同時に指示している点です。
AIは高い翻訳能力を持っているため、英語で話された内容の文脈を理解した上で、日本語のビジネス文書として適切な形に再構成します。
「専門用語は無理に意訳しない」という指示により、AIは「Leads」を無理に「見込み客」と訳さず、「リード(Leads)を20%増加させる」といった、ビジネス現場で通じやすい表現を選択します。
このプロンプトにより、言語の壁を越えて、会議の成果を迅速にチーム全体(日本語話者を含む)に共有することが可能になります。
プロンプト10:【応用】要点がバラバラなメモから議事録を作成する
このプロンプトは、AIによる高精度な文字起こしデータがない場合(例:会議中に自分が手書きやタイピングで取った、順不同のメモ)を想定しています。
情報が断片的で時系列もバラバラなメモ(箇条書き)から、AIに文脈を再構築させて議事録を作成させる応用テクニックです。
(以下をコピーして使用してください)
# あなたへの指示
あなたは、非常に優秀な編集者です。
以下の「会議メモ」は、会議中に書き留めたもので、時系列やトピックが順不同になっています。
これらの断片的な情報を分析・再構成し、論理的で読みやすい「議事録」を作成してください。
# 制約条件
・メモの内容から会議の「目的」「議論の論点」「決定事項」「ToDo」を推測し、整理してください。
・メモにない情報は捏造しないでください。ただし、メモの内容を補足し、自然な文章になるように記述してください。
# 会議メモ
(例:)
・新機能UI、デザインB案で決定。
・佐藤さん、コスト試算(B案)を来週水曜まで。
・A案は工数が少ないが、UXがイマイチとの意見。
・リリース時期、遅らせられない。
・デザインB案、開発工数1.5倍(Bさん確認)
・Cさん、B案の工数でもスケジュール死守できるか? → Bさん、2週間遅れると発言。
・(あれ、B案で決定したけどスケジュールは?)→ 佐藤さんのコスト試算次第で再協議?
・今日の目的:UIデザインの決定
# 出力フォーマット
## 1. 会議の目的
・新機能のUIデザイン案(A案・B案)の決定
## 2. 決定事項
・UIデザインは、UXを重視し「B案」を第一候補として進める。
## 3. ToDoリスト
* 【担当者】佐藤さん
* 【タスク内容】B案を採用した場合の正確なコスト試算
* 【期限】来週の水曜日
## 4. 議論のポイントと保留事項
* A案は工数が少ないがUXに懸念があるため、見送りとなった。
* B案は開発工数が1.5倍となり、現行スケジュール(リリース時期)の維持が困難になる可能性がBさんより指摘された。
* **保留事項:** B案の最終採用は、佐藤さんのコスト試算と、スケジュールへの影響を再評価した上で最終決定する。
このプロンプトのポイントは、AIの「推論能力」と「構成能力」を最大限に活用する点です。
人間が読んでも混乱するようなバラバラのメモをAIに与え、「論理的に再構成して」と指示します。
AIは「B案で決定」というメモと「2週間遅れる」というメモを見比べ、メモの最後にある「(あれ、スケジュールは?)」という書き手の混乱を読み取り、「決定事項」としてはB案を第一候補としつつ、「保留事項」としてスケジュールの問題を明記する、という高度な判断を行います。
完璧な文字起こしデータがない場合でも、AIを使えば断片的なメモから構造化された議事録を「復元」できる可能性を示しています。
主要AI別!議事録作成プロンプト(文字起こし要約)の比較
ChatGPT, Gemini, Claude。これらの主要AIは、それぞれ得意分野や特徴が異なります。
特に議事録作成において重要な「長文の取り扱いのうまさ」や「指示の忠実度」には差があります。
ここでは、各AIが議事録作成プロンプト(特に文字起こしデータの要約)に対してどのような反応を示すかを比較解説します。
- 比較に使う文字起こしデータと共通プロンプト
- ChatGPT (GPT-5.1など) の議事録作成結果
- Gemini (2.5 Pro) の議事録作成結果
- Claude (Opus 4.1 / Sonnet 4.5など) の議事録作成結果
(※2025年11月現在の情報に基づき、各モデルの一般的な傾向を解説します。AIの性能は日々アップデートされるため、実際の出力は異なる場合があります。)
比較に使う文字起こしデータと共通プロンプト
比較の前提条件として、約30分(日本語で約15,000文字)の架空の会議(テーマ:新製品のプロモーション戦略)の文字起こしデータを使用することを想定します。
このデータには、「Aさん」「Bさん」「Cさん」の3名の話者が含まれ、話者分離がされているものとします。
そして、すべてのAIに対し、以下の「プロンプト2:【詳細】指定フォーマットで議事録を作成する」と全く同じプロンプトを入力します。
# あなたへの指示
あなたは、上場企業の議事録作成を担当するプロフェッショナルです。
以下の「文字起こしデータ」を分析し、「出力フォーマット」で指定されたすべての項目を埋めて、詳細な議事録を作成してください。
(中略)
# 出力フォーマット
1. 会議名
2. 日時・場所
3. 出席者
4. 会議の目的
5. 決定事項
6. ToDo(ネクストアクション)
7. 議論の詳細(主要トピック別)
8. 保留事項・今後の課題
この共通条件の下で、各AIがどのような議事録を生成するか、その特徴を見ていきましょう。
ChatGPT (GPT-5) の議事録作成結果
ユーザーから提供された最新情報(2025年8月リリース、11月アップデート)に基づき、GPT-5系統のモデルの挙動を解説します。
GPT-5は、質問の難易度に応じて思考時間を自動で切り替える機能(Fast/Thinking)が特徴です。
今回のプロンプトのように、15,000文字のデータを読み込み、詳細なフォーマットに従って議事録を作成するという複雑なタスクは、自動的に「Thinking(長考)」モードが作動する可能性が高いです。
出力の特徴:
- 指示への忠実度: 非常に高いです。指示された「出力フォーマット」の1から8までの項目を忠実に守り、マークダウン記法(
##や*)も正確に再現します。 - 要約の質: 「議論の詳細」において、トピックを的確に分類し、各トピックの要点を簡潔かつ正確にまとめる能力に優れています。
- 推論能力: 「会議名」や「会議の目的」など、文字起こしデータに明記されていなくても、議論の文脈全体から高い精度で推論して記載します。
- 速度: 「Thinking」モードが作動した場合、GeminiやClaudeの高速モデルと比較すると、生成完了までにやや時間がかかる可能性がありますが、その分、出力の質は高い傾向にあります。
総評:
GPT-5系統のモデルは、有料プランで利用する場合、議事録作成において非常に信頼性の高い選択肢です。
特に、指定したフォーマットを厳格に守らせたい場合や、議論の文脈を深く読み取らせたい場合に強みを発揮します。ただし、無料プランの場合は5時間あたり10メッセージ、Thinkingモードは1日1回までという強い制限があるため、長文の議事録作成を頻繁に行う業務利用には有料プランが必須です。
Gemini (2.5 Pro) の議事録作成結果
2025年5月に発表されたGoogleのGemini 2.5 Proは、その圧倒的なコンテキストウィンドウ(100万〜200万トークン)が最大の特徴です。
今回の15,000文字程度のデータは、Geminiにとっては全く問題のない分量です。
1時間や2時間を超えるような、5万文字、10万文字の文字起こしデータであっても、分割せずに一度に処理できる可能性が最も高いモデルです。
出力の特徴:
- 長文処理能力: 他のAIを圧倒します。非常に長い会議データでも、会議の最初から最後まで一貫した文脈を維持し、全体を俯瞰した議事録を作成できます。
- 情報抽出の網羅性: 長文の中から「決定事項」や「ToDo」を漏らさずピックアップする能力に優れています。
- 柔軟性: 指示されたフォーマットには従いますが、時折、AIが「より良い」と判断した形で情報を補足したり、表現を工夫したりする(良くも悪くも「気が利く」)傾向が見られます。
- 速度: 長文の処理速度が非常に速く、ストレスなく結果を得られることが多いです。
総評:
Gemini (2.5 Pro) は、特に「長い会議の文字起こし」を「分割せずに」処理したい場合に、第一の選択肢となります。大量のテキストデータから網羅的に情報を抽出するパワーは随一です。ただし、プロンプトのフォーマットを100%厳格に守るという点では、GPT-5に一歩譲る場合があるかもしれません。
Claude (Opus 4.1 / Sonnet 4.5など) の議事録作成結果
AnthropicのClaude Opus 4.1やSonnet 4.5なども、数十万トークンという非常に大きなコンテキストウィンドウを持ち、長文処理に強いAIです。
特にClaudeは、出力される日本語の「自然さ」や「読みやすさ」、そして複雑な指示の意図を汲み取ること(「拡張思考モード」など)に定評があります。
出力の特徴:
- 出力の自然さ: 生成される議事録の日本語が非常に流暢で、人間が書いたかのような自然な文章(文語変換)を生成するのが得意です。
- 文脈理解: 議論の微妙なニュアンスや、発言の裏にある意図を汲み取り、それを議事録の「議論の詳細」に反映させるのがうまい傾向があります。
- 安全性: AnthropicはAIの安全性・倫理性を重視しており、機密性の高い情報を扱った際に、不適切な推測や出力を避ける(=事実に忠実であろうとする)傾向が強いです。
- 指示への忠実度: GPT-5と同様、指定されたフォーマットへの忠実度は非常に高いです。
総評:
Claude (Opus 4.1 / Sonnet 4.5など) は、議事録の「読み物としての質」や「日本語の美しさ」を重視する場合に非常に適しています。長文処理能力も高いため、Geminiと並んで長時間の会議にも対応可能です。特に、顧客提出用など、フォーマルで洗練された文章表現が求められる議事録作成で強みを発揮します。
議事録作成プロンプトの精度を格段に上げる7つのコツ
AIに議事録を作成させても、「要点がズレている」「ToDoが抜けている」といった経験はありませんか?
その原因は、AIの能力不足ではなく、指示(プロンプト)が曖昧であることかもしれません。
AIから期待通りの議事録を引き出すためには、プロンプトの書き方にいくつかのコツがあります。
- コツ1:具体的かつ明確に指示する
- コツ2:役割(例:敏腕秘書、ベテラン編集者)を与える
- コツ3:出力フォーマット(項目、箇条書きなど)を細かく指定する
- コツ4:元の文字起こしデータの精度を確保する
- コツ5:一度で決めず、追加指示で調整する
- コツ6:長文の場合は分割して入力する
- コツ7:主観を求めず、事実に焦点を当てるよう指示する
これらのコツを押さえることで、AI議事録の精度は劇的に向上します。
それでは、1つずつ順に解説します。
コツ1:具体的かつ明確に指示する
AIは「空気を読む」ことができません。人間なら「議事録よろしく」で伝わるニュアンスも、AIには伝わりません。
最も重要なコツは、「何を」「どうしてほしい」のかを具体的に言語化することです。
悪い例:
この文字起こし、要約して。
→ これでは、AIはどの程度の長さで、どのような視点で要約すればいいか分かりません。結果、単なる文章の圧縮版が出てくる可能性があります。
良い例:
以下の文字起こしデータから、「会議の目的」「決定事項」「ToDo」の3点を抽出してください。
「ToDo」は担当者と期限を必ず明記してください。
このように、「抽出する項目」や「ToDoの形式」を具体的に定義することで、AIは迷わず作業を実行できます。
「簡潔に」「詳しく」「丁寧に」といった形容詞だけではなく、「300文字以内で」「箇条書きで」「ですます調で」といった、AIが解釈に困らない客観的な指示を心がけることが重要です。
コツ2:役割(例:敏腕秘書、ベテラン編集者)を与える
AIに特定の「役割(ペルソナ)」を与えることは、出力のトーン&マナー(文体や視点)をコントロールする上で非常に有効なテクニックです。
これは「ロールプレイング」とも呼ばれます。
役割なしの例:
文字起こしデータを要約して。
→ AIは一般的な「アシスタント」として、当たり障りのない要約文を生成します。
役割ありの例:
あなたは、重要な経営会議の内容をCEOに報告する「敏腕秘書」です。
以下の文字起こしデータから、経営判断に必要な「決定事項」と「未解決の課題(リスク)」のみを抽出し、簡潔に報告してください。
「敏腕秘書」という役割を与えられたAIは、単なる要約ではなく、「CEOへの報告」という視点に切り替わります。
その結果、重要度の低い雑談や議論の詳細は省略し、経営層が知りたいであろう「決定」と「リスク」に焦点を当てた、シャープな出力を行うようになります。
他にも「プロの編集者」「ジャーナリスト」「コンサルタント」など、目的に合わせて役割を変えることで、AIの出力を自在にコントロールできます。
こちらは、大規模言語モデル(LLM)に多様な「役割(ロールプレイ)」を与えるプロンプトが、AIの性能にどのような影響を与えるかを調査した研究論文です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/html/2308.07702v2
コツ3:出力フォーマット(項目、箇条書きなど)を細かく指定する
AIは、指示された「型(フォーマット)」に従って情報を整理することを非常に得意とします。
プロンプト内に、自分が見たい議事録の「完成形(見出しや項目)」をあらかじめ提示してしまうのが、最も確実な方法です。
悪い例:
議事録を作って。
→ AIが「良い」と考えるフォーマットで出力されるため、自分が欲しい項目(例:保留事項)が含まれていない可能性があります。
良い例:
以下の「出力フォーマット」に従って、議事録を作成してください。
# 出力フォーマット
1. 会議の概要
2. 決定事項
3. ToDoリスト(担当者・内容・期限)
4. 保留事項
5. 議論の詳細
このように、見出し(1.や3.)や、箇条書き((担当者・内容・期限))の形式まで具体的に指定します。
AIはこの「出力フォーマット」をテンプレートとして認識し、文字起こしデータから該当する情報を探し出し、それぞれの項目を忠実に埋めていきます。
これにより、AIが独自にフォーマットを考案する余地がなくなり、常に安定した形式で議事録を得ることができます。
コツ4:元の文字起こしデータの精度を確保する
AI議事録の品質は、AIモデルの性能(例:GPT-5)だけに依存するわけではありません。
インプットとなる「文字起こしデータ」の品質が、最終的なアウトプットの品質の上限を決定します。
精度の低い文字起こしデータの問題点:
- 話者分離の失敗: 「Aさん:〜 Bさん:〜」とならず、すべての会話が「Aさん:〜〜〜」のように一人の発言として認識されていると、AIは誰がToDoを担当するのか判断できません。
- 固有名詞の誤変換: 「佐藤さん」が「加藤さん」に、「製品A」が「製品B」に間違って文字起こしされていると、AIはそのまま間違った議事録を作成します。
- 音声の欠落: 会議室のノイズなどで重要な発言が文字起こしデータから欠落していると、AIはその情報を認識できず、議事録からも抜け落ちます。
AIプロンプトを工夫する前に、まず「高精度なAI文字起こしツール」を使用すること、そして「話者分離」が正しく行われていることを確認することが不可欠です。
特に固有名詞や専門用語が多い会議では、文字起こしツールに「単語登録機能」があれば、事前に登録しておくことで誤変換を大幅に減らすことができます。
コツ5:一度で決めず、追加指示で調整する
AIは「対話型」です。一度の指示(プロンプト)で完璧な議事録が出てこなくても、諦める必要はありません。
生成された結果に対して、追加で指示(修正依頼)を出すことで、出力を理想に近づけることができます。
1回目の指示:
(プロンプト2:詳細フォーマットで議事録を作成)
1回目の出力(AI):
(議事録が生成されたが、「議論の詳細」が長すぎる)
2回目の指示(追加指示):
ありがとうございます。完璧です。
ただ、「7. 議論の詳細」が少し長すぎるので、各トピックの要点を「3行以内」に要約し直してください。
それ以外の項目(決定事項やToDo)は変更しないでください。
このように、AIの出力を一度「肯定」しつつ(ありがとうございます。完璧です。)、修正してほしい箇所だけを具体的に指示します。
AIは直前の文脈を記憶しているため、ゼロからやり直す必要はなく、指定された部分だけを効率的に修正します。
「〜の視点が抜けているので追加して」「ToDoの期限をYYYY/MM/DD形式に統一して」など、微調整を繰り返すことで、AIを「教育」し、望み通りの議事録に仕上げていくことができます。
コツ6:長文の場合は分割して入力する
AIには一度に処理できる情報量(コンテキストウィンドウ)に上限があります。
2025年現在、Gemini 2.5 ProやClaude Opus 4.1/Sonnet 4.5などの登場により、この上限は劇的に拡大しましたが、それでも3時間、4時間に及ぶ会議の文字起こしデータや、使用するモデル(特にChatGPTの旧モデルなど)によっては、上限を超えることがあります。
上限を超えると、AIはテキストの後半部分を読み込むことができず、会議の結論部分が議事録から抜け落ちるという致命的なミスが発生します。
これを防ぐのが「プロンプト8:【長文対応】」で紹介した分割入力のテクニックです。
分割入力のコツ:
「これから長いデータを分割して送ります。これはパート1です。まだ作業を始めないでください」とAIに宣言します。- AIが「次をどうぞ」と返答したら、
「これがパート2(最終回)です」と宣言して残りのデータを送ります。 - 最後に、
「すべてのデータを読み込みました。今までのデータ全体を使って、議事録を作成してください」と実行を指示します。
この手順を踏むことで、AIは分割されたデータを頭の中で結合し、会議の全体像を把握した上で議事録を作成できます。
まずは使用するAIがどの程度の長文に対応できるかを確認し、長いデータを入力する際はエラーが出ないか注意深く観察することが重要です。
こちらは、AIが長文を処理する際に、入力テキストの「真ん中」にある情報を見失いやすい(Lost in the Middle)傾向があることを示した有名な研究論文です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2307.03172
コツ7:主観を求めず、事実に焦点を当てるよう指示する
議事録は、会議で起こった「事実」を記録する公式な文書です。AIは時折、良かれと思って「推測」や「主観的な解釈」を加えてしまうことがあります。
良くない指示:
この会議で一番盛り上がったところはどこ?
→ AIが「盛り上がった」という主観的な判断基準で情報を抽出し、重要な決定事項よりも、議論が紛糾しただけの部分をピックアップする可能性があります。
良い指示:
文字起こしデータに基づき、客観的な事実のみを抽出してください。
あなたの推測や、データに存在しない解釈は一切含めないでください。
このように、「事実に焦点を当てる」こと、「推測を含めない」ことをプロンプトで明確に制約します。
AIが生成する議事録は、あくまで「文字起こしデータ」という一次情報に基づいている必要があります。
AIに「この決定は正しいと思いますか?」といった意見を求めるのではなく、「この決定事項を要約してください」と事実の整理に徹させること。これが、信頼性の高い議事録を作成するための鉄則です。
(ただし、ブレストのアイデア出しなど、意図的にAIの主観や創造性を利用する場合はこの限りではありません。)
AI議事録作成プロンプトの注意点とセキュリティ
AI議事録作成は非常に強力なツールですが、使い方を誤ると大きなリスクを伴います。
特に、機密情報の取り扱いには細心の注意が必要です。
業務でAIプロンプトを活用する前に、必ず以下の注意点を確認してください。
- 注意点1:機密情報・個人情報の入力は避ける(セキュリティ)
- 注意点2:生成された内容は必ず人の目で確認(ファクトチェック)
- 注意点3:AIツールの文字数制限(トークン数)に注意する
これらのリスクを理解し、対策を講じることが、安全なAI活用の第一歩です。
注意点1:機密情報・個人情報の入力は避ける(セキュリティ)
これが最も重要な注意点です。
会議の文字起こしデータには、顧客名、住所、電話番号といった「個人情報」や、新製品の価格、経営戦略、未公開の財務情報といった「社外秘の機密情報」が含まれている可能性があります。
これらの情報を、セキュリティ対策が不十分なAIサービスに入力してしまうと、以下のようなリスクが発生します。
- AIの学習データ化: 入力した機密情報がAIの学習データとして利用され、将来的に、他のユーザーがAIに質問した際に、あなたの会社の機密情報が回答として生成されてしまう(情報漏洩)リスク。
- 不正アクセス: AIサービス提供会社のサーバーがサイバー攻撃を受け、入力した文字起こしデータが丸ごと外部に流出するリスク。
対策:
- 社内ルールの確認: まず、自社のセキュリティ部門に、AIサービスの利用ガイドラインを確認します。
- オプトアウト設定: AIサービスを利用する際は、必ず「入力データを学習に利用しない(オプトアウト)」設定が可能なサービスを選び、その設定を有効にします。
- 法人向けプランの利用: 無料版のサービスは避け、セキュリティが強化され、データが学習に利用されないことが契約で保証されている法人向けプラン(例:ChatGPT Enterprise, Gemini for Google Workspaceなど)を利用します。
- 匿名化: 社内ルールで許可されていても、可能な限り、入力前に文字起こしデータの「顧客名」を「A社」、「担当者名」を「X氏」のように匿名化する処理を行うことが推奨されます。
注意点2:生成された内容は必ず人の目で確認(ファクトチェック)
AIが生成した議事録は、どれほど完璧に見えても「草案」でしかありません。
AIは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる、事実に基づかない情報をあたかも本当であるかのように生成することがあります。
例えば、文字起こしデータには存在しない決定事項を捏造したり、ToDoの担当者や期限を間違えたりする可能性がゼロではありません。
また、会議中の皮肉や冗談を真に受けて、そのまま議事録に記載してしまうこともあります。
対策:
- 人間のダブルチェック: AIが生成した議事録は、必ず会議に参加した人間(できれば議論の主要人物)が、内容に誤りがないか、ニュアンスが正しく伝わっているかを確認します。
- 特に確認すべき点: 「決定事項」「ToDo(担当者、期限)」「数値(予算、スケジュール)」は、1文字たりとも間違いがないか、入念にファクトチェックを行います。
- 責任の所在: AIが間違った議事録を作成しても、その責任はAIではなく、AIの生成結果を確認せずに共有した人間(利用者)にあります。AIを「アシスタント」として使い、最終的な文責は自分が負うという意識が重要です。
こちらは、主要なAIモデルがどの程度ハルシネーション(事実に基づかない情報)を生成するかを評価し、ランキング化したリーダーボードです。 合わせてご覧ください。https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard
注意点3:AIツールの文字数制限(トークン数)に注意する
AIは、一度に処理できるテキストの量に物理的な上限(コンテキストウィンドウ、またはトークン数制限)があります。
この上限は、AIモデル(GPT-5, Gemini 2.5 Proなど)や、利用するプラン(無料版/有料版)によって大きく異なります。
発生する問題:
- 入力エラー: 長すぎる文字起こしデータを入力すると、「入力が長すぎます」というエラーが表示され、処理が実行されません。
- テキストの切捨て(最も危険): AIがエラーを出さずに、入力されたテキストの後半部分(例えば、会議の最も重要な結論部分)を黙って切り捨てて処理することがあります。この場合、AIは会議の前半部分だけで議事録を作成してしまい、内容は不完全で誤ったものになります。
対策:
- 長文対応モデルの利用: 1時間を超えるような長い会議データを扱う場合は、Gemini 2.5 ProやClaude Opus 4.1/Sonnet 4.5など、長文処理に強いモデルを選択します。
- ツールの仕様確認: 自分が使用するAIモデルが、最大何トークン(または何文字)まで対応しているかを事前に確認します。(例:Gemini 2.5 Proは100万トークン、ChatGPT(GPT-5系統)は数十万文字など)
- 分割入力の実行: 使用するAIの制限を超える場合は、面倒でも「プロンプト8:【長文対応】」で紹介したテクニックを使い、データを手動で分割してAIに入力します。
議事録作成プロンプトに関するよくある質問
最後に、AIによる議事録作成や文字起こしプロンプトに関して、多くの人が抱く疑問について回答します。
- Q. 議事録作成におすすめのAIツールはどれですか?
- Q. 文字起こしの精度が低いと、議事録の精度も下がりますか?
- Q. 機密情報が含まれる会議でも使えますか?
- Q. プロンプトがうまく機能しません。どうすればいいですか?
Q. 議事録作成におすすめのAIツールはどれですか?
一概に「これがベスト」とは言えません。目的や会議の長さに応じて使い分けるのが最適です。
- Gemini (2.5 Pro):おすすめな人: 1時間半や2時間を超えるような「非常に長い会議」の文字起こしデータを、分割せずに一度で処理したい人。理由: 100万トークンを超える圧倒的なコンテキストウィンドウ(入力上限)を持つため、長文処理において最も強力です。
- Claude (Opus 4.1 / Sonnet 4.5など):おすすめな人: 議事録の「日本語の自然さ」や「読みやすさ」を重視する人。顧客提出用のフォーマルな議事録を作りたい人。理由: 出力が流暢で、人間が書いたような洗練された文章を生成するのが得意です。長文処理能力も非常に高いです。
- ChatGPT (GPT-5.1など):おすすめな人: 指定した「フォーマット」を厳格に守らせたい人。複雑な指示や推論を正確に実行させたい人。理由: 2025年8月にリリースされたGPT-5以降、推論能力が高く、プロンプトの指示(特にフォーマット指定)に対する忠実度が極めて高い傾向にあります。ただし、無料版の制限が厳しいため、業務利用には有料プランが推奨されます。
結論として、まずは高性能な有料プラン(Gemini Advanced, Claude Pro, ChatGPT Plusなど)を契約し、自分の会議データ(長さ、専門性)でそれぞれの出力を比較してみることをお勧めします。
Q. 文字起こしの精度が低いと、議事録の精度も下がりますか?
はい、劇的に下がります。
これはAI議事録作成において最も重要な原則の一つです。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」の法則がそのまま当てはまります。
例えば、文字起こしデータの精度が低く、以下のような状態だとします。
- 「A案を採用します」が「B案を再考します」と誤変換されている。
- 「佐藤さん」が「加藤さん」になっている。
- 話者分離がうまくいかず、Aさんの発言の途中にBさんの発言が混ざっている。
AIは、その間違った文字起こしデータを「正しい原文」として認識してしまいます。
その結果、AIは「B案を再考(決定事項)」「担当者:加藤さん」という、事実と全く異なる議事録を作成します。
AIプロンプトを工夫する以前の問題として、まず高精度なAI文字起こしツールを導入し、クリアな音声を録音することが、高品質なAI議事録作成の前提条件となります。
Q. 機密情報が含まれる会議でも使えますか?
原則として推奨されません。ただし、条件付きで可能です。
機密情報や個人情報が含まれる文字起こしデータを、無料のAIサービス(無料版ChatGPTなど)に入力することは絶対に避けてください。入力データがAIの学習に使われ、情報漏洩につながる重大なリスクがあります。
利用するための条件:
- 法人向けプランの契約:OpenAIの「ChatGPT Enterprise」やGoogleの「Gemini for Google Workspace」、またはAPI経由での利用など、「入力データをAIの学習に利用しない(オプトアウト)」ことが契約上明記されている、セキュリティが担保された法人向けサービスを利用することが必須です。
- 社内ガイドラインの遵守:自社の情報セキュリティ部門が定めた「AI利用ガイドライン」に従う必要があります。「顧客名は匿名化必須」「財務情報は入力禁止」などのルールがある場合は、それを厳守しなければなりません。
- (推奨)オンプレミス型または専用ツールの利用:最高レベルのセキュリティを求める場合、外部のクラウドにデータを送信しない「オンプレミス型(自社サーバー内で動作する)」のAIモデルや、法人向けに特化したセキュリティ機能(例:ChatSense)が備わったツールを利用することが最も安全です。
これらの対策を講じない限り、機密情報を含むデータをAIに入力すべきではありません。
Q. プロンプトがうまく機能しません。どうすればいいですか?
AIが期待通りの議事録を生成しない場合、いくつかの原因が考えられます。以下の点を確認し、プロンプトを修正してみてください。
- 指示が曖昧すぎないか?
- NG:
いい感じにまとめて。 - OK: 決定事項とToDoを箇条書きで抽出して。(→「コツ1:具体的かつ明確に指示する」を参照)
- NG:
- フォーマットを指定しているか?
- AIにフォーマットを丸投げするのではなく、# 出力フォーマット のように、自分が見たい形を先に提示してください。(→「コツ3:出力フォーマットを細かく指定する」を参照)
- 役割を与えているか?
- あなたはプロの編集者です。といった役割を与えるだけで、出力の視点が変わることがあります。(→「コツ2:役割を与える」を参照)
- 文字起こしデータが長すぎないか?
- AIの文字数制限を超えている可能性があります。会議の後半が丸ごと無視されているかもしれません。(→「コツ6:長文の場合は分割して入力する」を参照)
- 追加指示を試したか?
- 一度で完璧を求めず、「さっきの出力ですが、〜の部分を修正してください」と対話形式で修正を依頼してみてください。(→「コツ5:一度で決めず、追加指示で調整する」を参照)
多くの場合、プロンプトがうまく機能しない原因は、AIの能力不足ではなく、人間の「指示の出し方」にあります。AIが理解しやすいように、より具体的に、より明確に指示を出すことを心がけてみてください。
あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い
ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。
【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない
「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。
これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。
- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。
- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方
では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「壁打ち相手」にする
自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」
これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「無知な生徒」として教える
自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」
AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」
AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。