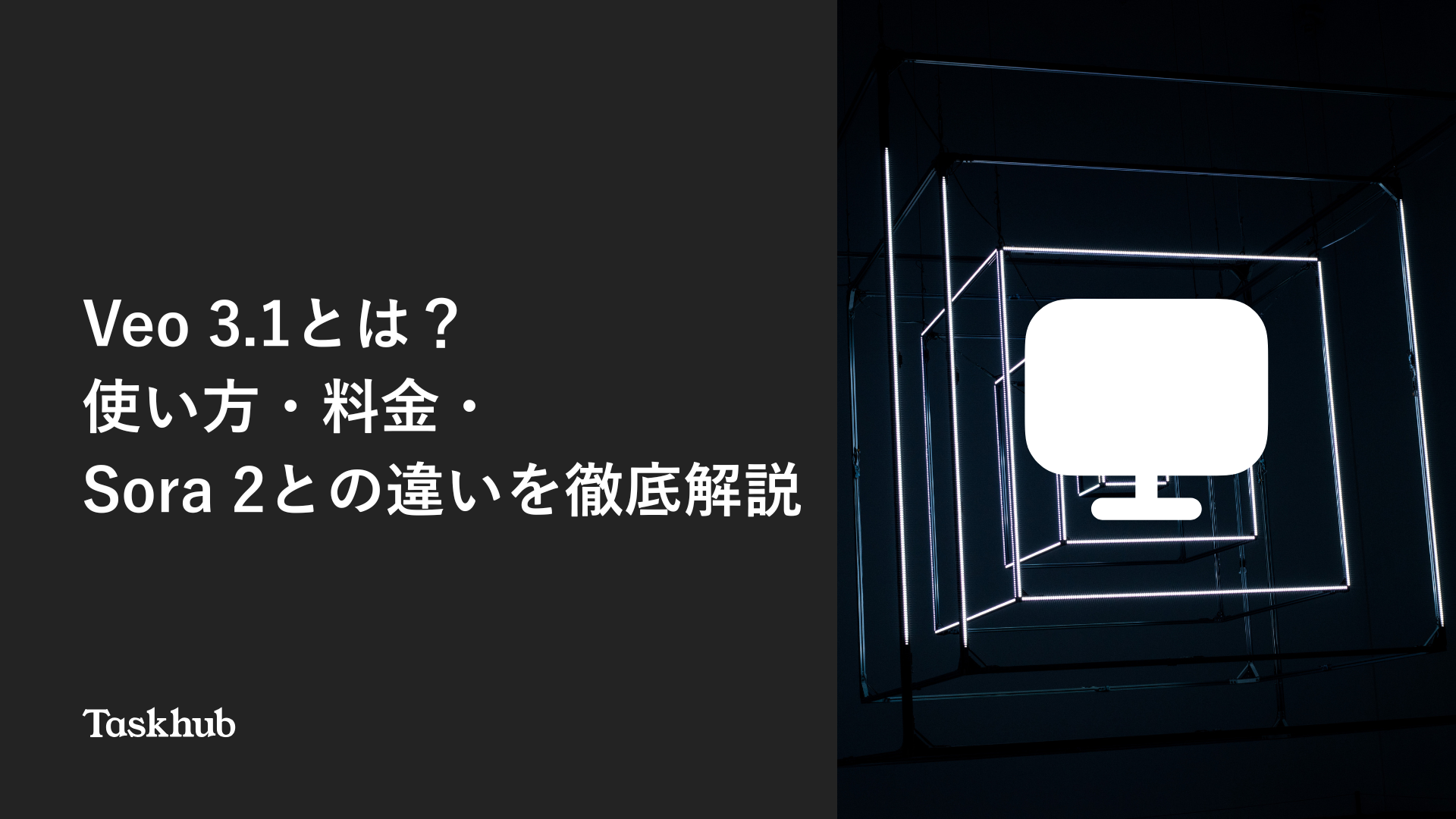「Googleのveo3.1がすごいらしいけど、具体的に何ができるの?」
「Sora 2と比べてどう違うのか、料金や使い方も知りたい…。」
こういった疑問や悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
2025年10月に発表されたGoogleの最新動画生成AI「veo3.1」は、従来のモデルから飛躍的な進化を遂げ、映像制作の常識を覆す可能性を秘めています。
本記事では、veo3.1の驚くべき新機能から、具体的な使い方、料金体系、そして最大のライバルであるOpenAIのSora 2との徹底比較まで、SEOの専門家が網羅的に解説します。
最新の公式情報と実際の活用事例に基づいた情報のみをご紹介します。
きっとあなたの動画制作や情報収集に役立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
Googleの動画生成AI「veo3.1」とは?驚きの進化を解説
ここからは、Googleが発表した最新の動画生成AI「veo3.1」の概要と、従来モデルからどのような進化を遂げたのかを解説します。
- Googleが発表した最新の動画生成モデル「veo3.1」
- 従来モデルVeo 3からの驚きの進化点
- veo3.1がもたらす動画制作の未来
veo3.1は、単なるテキストからの動画生成を超え、音声との完全同期や高度な編集機能を搭載した、まさに次世代のクリエイティブツールです。
それでは、1つずつ順に見ていきましょう。
Googleが発表した最新の動画生成モデル「veo3.1」
veo3.1は、Googleが2025年10月に発表した、最新の動画生成AIモデルです。
これは、2025年上半期に発表された「Veo 3」を大幅にアップデートした後継モデルであり、特に「ネイティブオーディオ(音声生成)」機能の劇的な向上が最大の特徴です。
従来の動画生成AIの多くは、まず映像(サイレントビデオ)を生成し、その後で別途、効果音やBGM、ナレーションを追加する必要がありました。
しかし、veo3.1はプロンプト(指示文)に基づいて、映像と完全に同期した音声(会話、環境音、効果音など)を同時に生成できます。
例えば、「雨が降るカフェで二人が会話している」と指示すれば、雨音、カップを置く音、そして自然な会話の音声までが映像と一体となって出力されます。
この進化により、単なる「動く絵」の生成から、音を含めた「一つのシーン」を丸ごと創り出すことが可能になりました。
品質面でも1080pの高解像度が標準となり、プロンプトへの忠実度やキャラクターの一貫性も向上しており、プロの映像制作者から一般ユーザーまで、幅広い層のニーズに応えるモデルとなっています。
こちらは、Google DeepMindによるVeoモデルファミリー全体の公式概要ページです。Veoの開発コンセプトや進化の系譜について詳しく解説されています。 https://deepmind.google/models/veo/
従来モデルVeo 3からの驚きの進化点
veo3.1は、従来モデルのVeo 3から複数の驚くべき進化を遂げています。
最大の進化点は、前述した「ネイティブオーディオ」機能の搭載です。
Veo 3でも音声の同期は試みられていましたが、veo3.1ではその精度とリアリティが飛躍的に向上しました。
さらに、クリエイティブなコントロール機能が大幅に強化されています。
「Ingredients to Video」機能がその代表例で、最大3枚の参照画像(キャラクター、背景、スタイルなど)を組み合わせて、一貫性のある動画を生成できるようになりました。
これにより、複数のショットで同じキャラクターを登場させるなど、ストーリー性のある動画制作が容易になっています。
また、「Frames to Video」機能を使えば、動画の「開始時点の画像」と「終了時点の画像」を指定するだけで、その間をAIが滑らかに補間し、自然なトランジション動画を生成します。
これらの新機能にも音声生成が統合されており、Veo 3が持っていた映像生成能力をベースに、音と編集の自由度を格段に高めた点が、veo3.1の最大の進化点と言えるでしょう。
veo3.1がもたらす動画制作の未来
veo3.1の登場は、動画制作の未来に革命的な変化をもたらす可能性を秘めています。
これまで高度なスキルと多くの時間を要した映像制作プロセスが、AIによって劇的に効率化・民主化されるためです。
例えば、広告業界では、プロンプト一つで高品質なCMのドラフトを音声付きで何パターンも即座に生成できるようになります。
映画やアニメ制作の現場では、プリビジュアライゼーション(絵コンテの動画化)や、複雑なシーンのたたき台作成に活用できるでしょう。
また、個人のクリエイターや中小企業にとっても、高価な機材や専門知識なしに、プロ品質のプロモーションビデオやSNSコンテンツを低コストで制作する道が開かれます。
「Ingredients to Video」や「Extend」機能により、単発のクリップ生成に留まらず、一貫性のあるキャラクターやストーリーを持った短編映像の制作も現実的になりました。
veo3.1は、アイデアさえあれば誰でも映像作家になれる時代の到来を告げる、重要なマイルストーンとなるAIモデルです。
「veo3.1」の注目すべき新機能と特徴を徹底解説
ここからは、veo3.1に搭載された注目すべき新機能と、その具体的な特徴を詳しく解説します。
- ①音声生成機能:映像と完全同期するネイティブオーディオ
- ②Ingredients to Video:複数画像を組み合わせて動画生成
- ③Frames to Video:始まりと終わりの画像を指定
- ④Extend機能:最大60秒以上の長尺動画に延長
- ⑤Insert/Remove機能:オブジェクトの追加・削除
- 素材や動画をより正確に編集する高度なコントロール
これらの機能を理解することで、veo3.1がいかに強力な動画生成ツールであるかが分かります。
1つずつ見ていきましょう。
①音声生成機能:映像と完全同期するネイティブオーディオ
veo3.1の核となる機能が、映像と完全に同期する「ネイティブオーディオ」の生成です。
これは、AIが映像の内容を深く理解し、そのシーンに最もふさわしい音を自動で創り出す技術です。
例えば、「森の中を歩く男性」というプロンプトであれば、男性の足音(落ち葉を踏む音)、遠くで鳴く鳥の声、風で木々が揺れる音などが、映像の動きと完璧にタイミングを合わせて生成されます。
さらに、veo3.1は会話やナレーションの生成にも対応しています。
プロンプトでセリフを指定すれば、映像内の人物がそのセリフを話す動画を生成可能です。
この機能により、映像と音声が一体となった没入感の高いコンテンツ制作が、ワンステップで完了します。
従来のように、無音の動画を生成してから、フリー素材サイトで効果音を探したり、ナレーションを別途録音したりする手間が一切不要になります。
この音声生成機能は、veo3.1の他の新機能(Ingredients to Video, Frames to Videoなど)にも標準搭載されており、あらゆる動画生成において音のリアリティを追求できます。
外部リンク提案Gem
カスタム Gem
はい、承知いたしました。SEOの観点から、権威性(公式情報)と専門性(詳細な技術情報・比較)を担保し、読者のさらなる情報収集をサポートするために最適な外部リンクを7つ厳選しました。
挿入位置、指定のフォーマットに沿った挿入文章、およびURLは以下の通りです。
厳選した外部リンク挿入案(7選)
1. 「Googleが発表した最新の動画生成モデル「veo3.1」」の末尾
こちらは、Google DeepMindによるVeoモデルファミリー全体の公式概要ページです。Veoの開発コンセプトや進化の系譜について詳しく解説されています。 https://deepmind.google/models/veo/
2. 「①音声生成機能:映像と完全同期するネイティブオーディオ」の末尾
こちらは、Veo 3.1(Standardモデル)の技術仕様に関するGoogle Cloudの公式ドキュメントです。機能や制限事項について詳細に記載されています。 https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/veo/3-1-generate-preview
②Ingredients to Video:複数画像を組み合わせて動画生成
「Ingredients to Video(材料から動画へ)」は、veo3.1の創造性を象徴する新機能です。
これは、テキストプロンプトに加えて、最大3枚までの参照画像(=Ingredients)を指定することで、それらの要素を一貫して反映させた動画を生成する機能です。
例えば、特定の「キャラクターの画像」、「背景となる風景の画像」、「特定の画風(例:アニメ調)の画像」の3枚をインプットとして指定できます。
AIはこれらの画像の特徴を抽出し、「指定したキャラクターが、指定した背景の中で、指定した画風で動く」動画を生成します。
この機能の最大のメリットは「一貫性の担保」です。
従来のAI動画生成では、同じプロンプトでもショットごとにキャラクターの顔や服装が変わってしまう問題がありました。
しかし、この機能を使えば、参照画像を指定し続けることで、同じキャラクターが異なるシーンに連続して登場する、ストーリー性のある動画制作が可能になります。
もちろん、この機能で生成される動画にも、ネイティブオーディオが自動で付与されます。
③Frames to Video:始まりと終わりの画像を指定
「Frames to Video(フレームから動画へ)」は、動画の「開始フレーム(最初の画像)」と「終了フレーム(最後の画像)」の2枚を指定するだけで、その間をAIが滑らかに補間して動画を生成する機能です。
これは、映像のトランジション(場面転換)や、特定の変化を直感的にコントロールしたい場合に非常に強力です。
例えば、朝焼けの空の画像を開始フレームに、日中の青空の画像を終了フレームに指定すれば、時間が経過して空の色が変わっていく様子を自然な動画として生成します。
また、閉じていた花がつぼみから開花するまでの様子や、ある地点から別の地点へ視点が移動するようなカメラワークも、開始と終了の画像を指定するだけで実現可能です。
この機能は、AIに全てを任せるのではなく、制作者が映像の「始点」と「終点」という重要なポイントをコントロールできる点で画期的です。
「Ingredients to Video」と同様に、生成される動画にはシーンに適した音声が自動で付与され、よりドラマチックな場面転換を演出できます。
④Extend機能:最大60秒以上の長尺動画に延長
従来のAI動画生成は、数秒から十数秒程度の短いクリップの生成が主流でした。
しかし、veo3.1に搭載された「Extend(延長)」機能は、この制約を打ち破ります。
この機能は、すでにveo3.1で生成した動画の続きを、AIが違和感なく生成し、動画をシームレスに延長していくものです。
例えば、最初に8秒間の動画を生成した後、Extend機能を実行すると、その動画の最後のシーンから自然につながる次の数秒間が生成され、動画が延長されます。
このプロセスを繰り返すことで、理論上は60秒を超える長尺の動画を作成することが可能になりました。
Googleの映像制作ツール「Flow」などと連携することで、この延長機能はより強力に機能します。
単に動画を長くするだけでなく、シーンの展開をコントロールしながら物語を構築していくことができます。
これにより、SNS用のショート動画だけでなく、CM、ミュージックビデオ、短編映画など、より複雑な構成が求められるコンテンツ制作にもveo3.1が活用される道が開けました。
⑤Insert/Remove機能:オブジェクトの追加・削除
veo3.1は、Googleの映像制作ツール「Flow」と統合されることで、生成後の動画に対する高度な編集機能も提供します。
その代表が「Insert/Remove(挿入/削除)」機能です。
これは、生成した動画内の特定の領域を指定し、プロンプトで指示するだけで、その部分に新しいオブジェクトを自然に追加したり、逆に不要なオブジェクトを消去したりできる機能です。
例えば、生成した街並みの動画に「空に飛行機を追加して」と指示すれば、違和感なく飛行機が飛んでいる映像に修正されます。
逆に、テーブルの上に不要なカップが映り込んでしまった場合、そのカップを指定して「これを削除して」と指示すれば、AIが背景を予測して補い、カップが元からなかったかのように修正します。
これは、動画生成における「Inpainting(インペインティング)」や「Outpainting(アウトペインティング)」技術の応用であり、撮影後の編集作業(VFX)に匹敵する高度な修正を、AIが瞬時に行うことを可能にします。
素材や動画をより正確に編集する高度なコントロール
veo3.1は、単にプロンプトから動画を生成するだけでなく、制作者の意図をより正確に反映させるための高度なコントロール機能を備えています。
前述の「Ingredients to Video」(参照画像)や「Frames to Video」(始点・終点の指定)、「Insert/Remove」(挿入・削除)は、その中核となる機能です。
これらに加え、プロンプト自体でカメラワーク(ドリー、ズーム、パンなど)やレンズの種類(広角、望遠など)を細かく指定することも可能です。
veo3.1は、これらの映画制作に関する専門用語や文脈を深く理解し、忠実に映像に反映させる能力が非常に高いと評価されています。
また、Googleの映像制作ツール「Flow」のタイムライン上で、複数のAI生成クリップを並べたり、Extend機能で長さを調整したりと、従来の動画編集ソフトに近い感覚でAI動画を組み立てていくことができます。
これらの高度なコントロール機能により、veo3.1は単なる「おもちゃ」ではなく、プロのクリエイターが要求する精密な映像表現に応える「ツール」としての地位を確立しつつあります。
「veo3.1」のFastとStandardの違いとは?
veo3.1には、主に「Fast(ファスト)」と「Standard(スタンダード)」という2つのモデル(またはモード)が用意されています。
- Veo 3.1 Fast:速度重視のモデル
- Veo 3.1 Standard:品質重視のモデル
- 用途に応じた使い分けのポイント
こちらは、Veo 3.1 Fastモデルの技術仕様に関するGoogle Cloudの公式ドキュメントです。Standardモデルとの違いを技術的な観点から確認できます。 https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/veo/3-1-fast-generate-preview
これらの違いを理解することは、コストと品質のバランスを取る上で非常に重要です。
それぞれの特徴を解説します。
Veo 3.1 Fast:速度重視のモデル
Veo 3.1 Fastは、その名の通り、動画の生成速度を最優先に設計されたモデルです。
Standardモデルと比較して、プロンプトを入力してから動画が出力されるまでの待ち時間が大幅に短縮されています。
これは、アイデアを素早く形にしたい場合や、SNS投稿用のショート動画を大量に試作したい場合に非常に有効です。
例えば、広告のキャッチコピーに合わせて複数の映像パターンを試す際、Fastモデルを使えば短時間で多くのバリエーションを比較検討できます。
ただし、速度を優先する代わりに、生成される動画の品質(解像度、ディテールの精細さ、プロンプトへの忠実度など)は、Standardモデルに比べてやや劣る傾向があります。
とはいえ、Veo 3からの進化により、Fastモデルでも従来のAI動画生成モデルを凌駕する十分な品質を持っており、多くの用途で実用的なレベルに達しています。
主にGoogle AI Proプラン(有料)などで利用が提供されています。
Veo 3.1 Standard:品質重視のモデル
Veo 3.1 Standardは、生成速度よりも出力される動画の品質(クオリティ)を最優先するモデルです。
Fastモデルよりも生成に時間はかかりますが、より高い解像度(1080p対応)、精細なディテールの表現、複雑なプロンプトへの高い忠実度、そしてより自然で一貫性のある動きを実現します。
特に、映画的な表現、リアルな質感、複雑なカメラワーク、キャラクターの一貫性などが求められる場合に真価を発揮します。
プロの映像制作者が作品の一部として使用する場合や、企業の公式なプロモーションビデオ、高品質なシネマティック映像を追求したい場合に適しています。
「Quality(品質)」モデルと呼ばれることもあり、Google AI Ultraプランなどの上位プランや、API経由での利用が想定されています。
当然ながら、その高い品質と引き換えに、Fastモデルよりも利用コスト(クレジット消費量やAPI料金)は高く設定されています。
用途に応じた使い分けのポイント
veo3.1のFastモデルとStandardモデルは、どちらが優れているかではなく、目的に応じて使い分けることが重要です。
まず、アイデアの試作(プロトタイピング)や、SNS用の短尺動画、ラフな絵コンテ作成など、スピードと量が求められる場面では「Fast」モデルが最適です。
コストを抑えながら、多くのパターンを迅速に試すことができます。
一方、最終的な納品物としてのクオリティを追求する場面や、クライアント向けのプレゼンテーション、ポートフォリオ用の作品制作など、細部の美しさやリアリズムが重要となる場面では「Standard」モデルを選択すべきです。
具体的なワークフローとしては、まずFastモデルでプロンプトを調整しながら基本的な構成やカメラワークを固め、方向性が定まったら、最後に同じプロンプトでStandardモデルを使い、高品質な本番映像を生成する、といった使い分けが最も効率的でしょう。
GeminiアプリやFlowなどのプラットフォームでは、生成時にこれらのモードを選択できるUIが提供されています。
「veo3.1」の使い方とアクセス方法|利用可能なプラットフォーム
veo3.1は、Googleの様々なサービスやサードパーティのプラットフォームを通じて利用が開始されています。
- Geminiアプリ(有料プラン)での使い方
- Flow(Googleの映像制作ツール)での使い方
- Gensparkでの使い方
- 開発者向けAPIでの利用方法
- サードパーティプラットフォームでの利用
現時点(2025年10月)での主なアクセス方法と、それぞれの使い方を解説します。
Geminiアプリ(有料プラン)での使い方
最も手軽にveo3.1を体験できる方法の一つが、Googleの対話型AIサービス「Gemini」(旧Bard)のアプリ(Web版含む)です。
veo3.1の機能は、Geminiの有料プラン(例:Google AI ProプランやGoogle AI Ultraプラン)に統合されています。
使い方は非常にシンプルで、Geminiのチャット画面で、動画生成のオプションを選択(または「動画を作って」と指示)し、通常のプロンプトと同じように「〇〇な動画を生成して」とテキストで入力するだけです。
例えば、「夕焼けのビーチをドローンで空撮した、穏やかな波音が入った動画」と入力すれば、veo3.1が動画(音声付き)を生成し、チャット画面に表示します。
Geminiアプリ経由では、主にFastモデルが中心となる可能性がありますが、プランによってはStandardモデルも利用可能です。
アイデアを素早く視覚化したり、手軽にAI動画生成を試したりするのに最適な方法です。
Googleの対話型AI「Gemini」の基礎知識や使い方については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。
Flow(Googleの映像制作ツール)での使い方
「Flow」は、Googleが提供するAIネイティブの映像制作・編集ツールです。veo3.1は、このFlowに深く統合されています。
Flowは単なる動画生成インターフェースではなく、タイムラインベースの編集機能を備えています。
Flow内では、プロンプトからの動画生成はもちろん、veo3.1の強力な編集機能である「Extend(延長)」、「Ingredients to Video」(参照画像からの生成)、「Frames to Video」(始点・終点指定)、「Insert/Remove」(挿入・削除)などを直感的に操作できます。
例えば、生成したクリップをタイムラインに並べ、Extend機能で長さを調整し、Insert機能で不要なオブジェクトを消す、といった一連の編集作業をシームレスに行えます。
プロのクリエイターや、より本格的な動画作品をAIで制作したいユーザーにとって、Flowはveo3.1のポテンシャルを最大限に引き出すための主要なプラットフォームとなります。
利用にはFlowへのアクセス権(有料プレビューなど)が必要となる場合があります。
こちらは、記事中で紹介したAIフィルムメイキングツール「Flow」の公式サイトです。Veo 3.1と連携するFlowの機能や料金プランについて紹介されています。 https://labs.google/flow/about
Gensparkでの使い方
Gensparkは、Googleも出資するAI検索・生成プラットフォームであり、veo3.1をいち早く導入したサードパーティサービスの一つです。
Gensparkは、検索と生成を融合させたインターフェースが特徴で、ユーザーが何かを調べたり作成したりするプロセス全体をAIがサポートします。
その中で、動画生成機能の一部としてveo3.1が採用されています。
Gensparkのプラットフォーム内で、テキストや画像から動画を生成する際に、バックエンドでveo3.1(またはVeo 3.1 Fast)が動作します。
使い方はGensparkのUIに従いますが、基本的にはGeminiアプリと同様に、プロンプトを入力して動画を生成する流れとなります。
Genspark独自のクレジットシステムや料金プラン内でveo3.1を利用することになり、Googleのサービスとは異なる利用体験や機能が提供される可能性があります。
開発者向けAPIでの利用方法
veo3.1は、開発者が自身のアプリケーションやサービスに動画生成機能を組み込むためのAPIとしても提供されています。
主に「Gemini API」およびGoogle Cloudの「Vertex AI」プラットフォームを通じて、プレビュー版(例:veo-3.1-generate-preview)としてアクセスが可能です。
APIを利用することで、自社のウェブサービスやアプリ内で、ユーザーの入力に基づいてカスタマイズされた動画をオンデマンドで生成する、といったシステムを構築できます。
例えば、不動産サイトが物件データから自動でルームツアー動画を生成したり、Eコマースサイトが商品画像からプロモーション動画を生成したりする活用が考えられます。
APIの利用には、Google Cloudプロジェクトの設定、認証キーの取得、専門的なプログラミング知識が必要となり、生成リクエストごとに従量課金が発生します。
サードパーティプラットフォームでの利用
Genspark以外にも、veo3.1のAPIを利用して動画生成機能を提供するサードパーティのプラットフォーム(AIツール提供サービス)が今後増えていくことが予想されます。
検索結果によれば、Higgsfield, Imagine Art, Envatoといったプラットフォームでもveo3.1へのアクセスが提供され始めているか、または予定されています。
これらのプラットフォームは、それぞれ独自のUI、料金プラン、追加機能(例:特定のスタイルに特化したテンプレート、簡単な編集機能など)を提供することが一般的です。
Googleの公式ツール(Gemini, Flow)が合わない場合や、特定のワークフローに特化した機能が必要な場合、これらのサードパーティ製ツールも選択肢となります。
ただし、プラットフォームによって利用できるモデル(Fast/Standard)や機能に差があるため、導入前に各サービスの詳細を確認することが重要です。
「veo3.1」の料金体系まとめ|無料で使える?
veo3.1の利用料金は、アクセスするプラットフォームや利用形態によって異なります。
- veo3.1は無料で使えるのか?
- Geminiアプリ経由の料金プラン
- FlowやGenspark利用時の料金
- API経由での料金体系(推定含む)
ここでは、veo3.1の料金体系について、現時点で判明している情報をまとめます。
veo3.1は無料で使えるのか?
結論から言うと、veo3.1の機能を「完全無料」で「無制限に」使うことは難しい可能性が高いです。
ただし、Googleアカウントを持つユーザーであれば、Geminiの無料プランの範囲内で、機能や回数に制限付きでveo3.1(おそらくFastモデル)を試用できる可能性があります。
Googleは新機能をプロモーションするために、無料ユーザーにも限定的なアクセスを提供することが多いためです。
しかし、高品質なStandardモデルの利用や、長尺動画の生成、API経由での利用など、本格的な活用には基本的に有料プランへの登録が必要となります。
「お試し」は無料で可能だが、実用的な利用は有料、というのが基本的なスタンスになると考えられます。
Geminiアプリ経由の料金プラン
Geminiアプリ(Web版含む)でveo3.1を本格的に利用する場合、有料プランへの加入が必要です。
2025年10月時点の情報によれば、以下のようなプランが提供されています。
- Google AI Proプラン: 月額$19.99程度。月間のクレジット(例:1,000クレジット)が付与され、veo3.1 Fastモデルを中心としたAI機能を利用できます。クレジットを消費して動画を生成する仕組みです。
- Google AI Ultraプラン: 月額$249.99程度。より多くの月間クレジット(例:12,500クレジット)が付与され、Veo 3.1 Fastに加えて高品質なStandardモデルへのフルアクセスが可能です。ヘビーユーザーや法人向けのプランです。
これらのプランでは、veo3.1以外にも、Geminiの高度なテキスト生成機能や他のAI機能も併せて利用できます。
FlowやGenspark利用時の料金
Google FlowやGensparkなどのプラットフォームを利用する場合、それぞれのサービスが設定する独自の料金体系に従います。
Flow:
Flowはプロフェッショナル向けの映像制作ツールと位置付けられているため、Geminiアプリとは異なるサブスクリプション料金が設定される可能性が高いです。
利用できる機能(Extend, Insert/Removeなど)の豊富さや、生成できる動画の品質・本数に応じて、複数のティア(階層)が設けられることが予想されます。
Genspark:
Gensparkのようなサードパーティプラットフォームは、独自のクレジットシステムを採用している場合が多いです。
月額プランで一定量のクレジットを購入し、動画生成(veo3.1の利用)1回あたりに設定されたクレジットを消費していく形式が一般的です。
API経由での料金体系(推定含む)
開発者がGemini APIやVertex AI経由でveo3.1を利用する場合、従量課金制となります。
公式な確定料金はプレビュー段階では変動する可能性がありますが、2025年10月時点での業界の非公式な推定によれば、以下のような料金が目安とされています。
- Veo 3.1 Standard (Quality): 生成される動画1秒あたり 約$0.40
- Veo 3.1 Fast: 生成される動画1秒あたり 約$0.15
例えば、Standardモデルで8秒の動画を1本生成すると、約$3.20($0.40 × 8秒)のコストがかかる計算です。
これはあくまで推定であり、実際の料金はリージョンや利用量によって変動する可能性があります。
API利用は、生成リクエストが大量になる場合、コストが大きくなる可能性があるため、利用前に必ずGoogle Cloudの公式料金ページで最新の価格を確認する必要があります。
こちらは、Veo 3.1を含むVertex AIの生成AIモデルに関する公式の料金ページです。API利用時の最新の価格体系を確認できます。 https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing
「veo3.1」と従来モデル・Sora 2・競合他社との性能比較
veo3.1は、Googleの従来モデルや、最大のライバルであるOpenAIのSora 2、その他の動画生成AIと比べてどのような違いがあるのでしょうか。
- veo3.1とVeo 3の決定的な違い【比較表】
- veo3.1とOpenAI Sora 2との性能比較
- その他の競合動画生成AIとの違い
ここでは、veo3.1の性能を他モデルと比較して解説します。
veo3.1とVeo 3の決定的な違い【比較表】
veo3.1は、Veo 3の直接的な後継モデルであり、多くの点で機能が強化されています。
主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | veo3.1 (2025年10月) | Veo 3 (2025年上半期) |
| 音声生成 | ネイティブオーディオ(高品質) 映像と完全同期した会話・効果音・環境音を高品質に同時生成 | 限定的な音声同期 (主に効果音や環境音) |
| 参照画像 | Ingredients to Video 最大3枚の画像を参照し、一貫性を保持(音声含む) | 限定的な画像toビデオ機能 |
| 編集機能 | Frames to Video (始点・終点指定) Extend (最大60秒以上への延長) Insert/Remove (オブジェクト挿入・削除) | 限定的な延長機能(ベータ) |
| 品質 | 1080pが標準、リアリズムと忠実度が向上 | 最大1080p、品質は高いがveo3.1に劣る |
| モデル | Standard (品質重視) と Fast (速度重視) の2モデル体制 | 単一モデルまたは初期のFastモデル |
最も決定的な違いは、「ネイティブオーディオ」の品質と、「Ingredients to Video」「Frames to Video」といった高度なコントロール機能が音声付きで統合された点です。
veo3.1は、Veo 3をベースに、よりクリエイティブな編集と音響表現を可能にした、まさに「次世代」のモデルと言えます。
veo3.1とOpenAI Sora 2との性能比較
veo3.1の最大のライバルは、OpenAIが開発した「Sora 2」(またはSoraの最新版)です。
両者はAI動画生成の頂点を競うモデルであり、それぞれに得意分野があります。
veo3.1の強み:
- プロンプトへの忠実度: 特にカメラワーク(「ドローンショット」「ズームイン」など)や専門的な映像用語に対する理解が深く、指示に忠実な映像を生成する傾向があります。
- 物理シミュレーションとリアリズム: オブジェクトの動きや質感、光の反射など、物理法則に基づいたリアルな「ワンシーン」の描写力に優れています。
- ネイティブオーディオ: 映像と同期した高品質な音声生成機能は、veo3.1の大きなアドバンテージです。
- 編集・コントロール機能: Flowとの連携によるExtend, Insert/Removeなど、生成後の編集やコントロール機能が充実しており、「映像制作ツール」としての側面が強いです。
Sora 2の強み:
- 言語理解と構成力: ChatGPTの強力な言語理解能力をベースに持つため、プロンプトの意図や文脈を深く理解し、ストーリー性のある「動画全体の構成」を生成するのが得意とされます。
- 世界のシミュレーション: 「歯医者のCM」といった抽象的な指示でも、CMとして成立するような一連の流れ(複数のショット)をAIが解釈して生成する能力に優れているとされます。
- キャラクターの一貫性: 長い動画内でのキャラクターやオブジェクトの一貫性を保つ能力も高いと評価されています。
現時点では、「映画的なワンシーンのクオリティと忠実性、音響」を求めるならveo3.1、「プロンプトの意図を汲んだストーリー全体の構成力」を求めるならSora 2、という使い分けが考えられます。
こちらは、Veo 3.1とSora 2の性能を動画の長さ、一貫性、音声機能などの観点から実用的に比較・分析した技術レポートです。 https://skywork.ai/blog/veo-3-1-vs-sora-2-2025-comparison/
その他の競合動画生成AIとの違い
veo3.1やSora 2以外にも、多くの企業が動画生成AIを開発しています。
- Pika (Pika Labs):クリエイティブな表現やアート的なスタイルに強く、既存の動画のスタイルを変更したり、部分的に編集(例:服装を変える)したりする機能に定評があります。veo3.1に比べて、よりアーティスティックな映像制作や、短いクリップの編集・加工に強いと言えます。
- Runway (Gen-2):AI動画生成の分野をリードしてきた企業の一つです。テキストtoビデオ、画像toビデオに加え、動画から動画を生成する(Gen-1)など、多彩なモードを持っています。veo3.1やSora 2ほどのリアリズムや忠実性には及ばない面もありますが、編集ツールとしての機能が豊富で、クリエイター向けのUIが充実しています。
- Stability AI (Stable Video Diffusion):オープンソースモデルをベースにしていることが多く、カスタマイズ性や透明性に強みがあります。品質はveo3.1などに追いついていない部分もありますが、特定の用途にファインチューニングして使うといった柔軟な活用が可能です。
veo3.1は、これらの競合と比較して、Googleの持つ膨大なデータと研究開発力を背景にした「リアリズム」「音声統合」「高度なコントロール」の3点において、頭一つ抜けた存在になりつつあります。
「veo3.1」のプロンプト例・活用例5選【動画生成サンプル】
veo3.1は、その高度な機能により、様々なジャンルの動画を生成できます。
ここでは、具体的なプロンプト例と、それによって期待される活用例を5つ紹介します。
- 活用例①:カフェでの日常シーン(人物描写)
- 活用例②:壮大な自然風景(カメラワーク)
- 活用例③:ペットの愛らしい動画(動物)
- 活用例④:商品紹介・広告動画
- 活用例⑤:料理・食べ物のシズル動画
これらの例は、veo3.1の能力を示すための一例です。
活用例①:カフェでの日常シーン(人物描写)
プロンプト例:
「雨が降る窓際のカフェのテーブルで、2人の女性がコーヒーを飲みながら笑顔で会話している。カメラはゆっくりと2人にズームインする。高品質、シネマティック。
音声:静かなジャズBGM、雨音、食器の音、女性たちの穏やかな話し声。」解説と活用:
このプロンプトは、人物の描写、カメラワーク(ズームイン)、雰囲気(シネマティック)、そして音声(BGM、環境音、会話)を具体的に指示しています。
veo3.1は、これらの要素を組み合わせて、雨音とBGMが流れ、2人の女性が自然に会話する(口の動きと音声が同期した)リアルなシーンを生成できます。
Webサイトの背景動画、ドラマや映画のワンシーンの試作、企業のイメージビデオなどに活用できます。
活用例②:壮大な自然風景(カメラワーク)
プロンプト例:
「雪を頂いた雄大な山脈の上空を、ドローンが高速で飛行する空撮映像。太陽が山頂から昇る瞬間。広角レンズ、4K、壮大な雰囲気。
音声:力強い風切り音、遠くで響く壮大なオーケストラ音楽。」解説と活用:
この例では、「ドローン飛行」「空撮」「広角レンズ」といった専門的なカメラワークの指示と、特定のシチュエーション(日の出)を指定しています。
veo3.1はこれらの指示を正確に解釈し、ダイナミックなカメラの動きと、プロンプトで指定した「風切り音」や「オーケストラ音楽」を伴った高解像度の風景動画を生成します。
旅行関連のプロモーションビデオ、ドキュメンタリー映像の挿入カット、リラクゼーションコンテンツなどに最適です。
活用例③:ペットの愛らしい動画(動物)
プロンプト例:
「ゴールデンレトリバーの子犬が、緑豊かな芝生の上で赤いボールを追いかけてはしゃいでいる。スローモーション。
音声:子犬の楽しそうな息遣い、芝生を駆ける音、鳥のさえずり。」解説と活用:
動物の自然な動きや毛並みの質感をリアルに描写するのもveo3.1の得意分野です。
「スローモーション」というエフェクトの指示にも対応できます。
生成される動画では、子犬の毛が風になびく様子や、楽しそうにボールを追う姿が、息遣いや環境音とともにリアルに再現されます。
ペット関連商品の広告、SNSで注目を集めるためのコンテンツ、動物の癒し動画などに活用できます。
「Ingredients to Video」機能を使えば、自分のペットの写真を元に動画を生成することも可能になるでしょう。
活用例④:商品紹介・広告動画
プロンプト例:
「黒い背景の中、銀色の高級腕時計がゆっくりと回転しながら浮かんでいる。スポットライトが時計の文字盤を照らし、輝きを強調する。
音声:静かで洗練された電子音楽、時計の秒針がかすかに刻む音(チクタク)。」解説と活用:
このプロンプトは、特定の商品(腕時計)に焦点を当て、その質感や高級感を演出するためのライティング(スポットライト)と動き(回転)を指示しています。
veo3.1は、金属の光沢や質感、光の反射をリアルにシミュレートし、指定された音声(洗練されたBGMと秒針の音)を組み合わせることで、プロ品質の商品紹介動画を生成します。
Eコマースサイトの商品ページ、SNS広告、デジタルサイネージ用の映像など、商用利用に直結する活用が可能です。
活用例⑤:料理・食べ物のシズル動画
プロンプト例:
「熱い鉄板の上でステーキが焼かれている。ジュージューという音とともに湯気が立ち上る。クローズアップ、高精細。
音声:肉が焼ける激しいシズル音、油のはじける音。」解説と活用:
料理動画で重要な「シズル感」(食欲をそそる感覚)の表現にもveo3.1は対応します。
「クローズアップ」で肉の焼けるディテールを捉え、「湯気」や「シズル音」を具体的に指示することが鍵です。
veo3.1は、プロンプトに基づき、肉の表面が焦げる様子や、立ち上る湯気、そして食欲を刺激する「ジュージュー」という音を同期させた動画を生成します。
レストランのメニュー紹介、食品の広告、料理レシピ動画のオープニングなど、飲食関連のマーケティングで絶大な効果を発揮します。
「veo3.1」をうまく活用するプロンプトのコツとポイント
veo3.1の性能を最大限に引き出すには、指示文である「プロンプト」の書き方にコツが必要です。
- 効果的な使い方のコツ:基本的な構文ルール
- プロンプトエンジニアリングのベストプラクティス
- カメラワーク指示で映像品質を向上させる方法
- 音声指示で臨場感をアップさせるコツ
ここでは、veo3.1をうまく使いこなすためのプロンプトのポイントを解説します。
効果的な使い方のコツ:基本的な構文ルール
veo3.1に明確な指示を伝えるためには、基本的な構文(文章の組み立て方)を意識することが重要です。
一般的に、「誰が/何が(被写体)」「どこで(場所・背景)」「何をしているか(行動)」「どのように(スタイル・雰囲気)」の4つの要素を盛り込むと良いとされています。
悪い例: 「犬の動画」
(情報が少なすぎます)良い例: 「(被写体)一匹の柴犬が」「(場所)公園のベンチの上で」「(行動)気持ちよさそうに昼寝をしている」「(スタイル)穏やかで暖かい日差しの下、クローズアップ」このように、具体的な名詞、動詞、形容詞を使ってシーンを詳細に描写することで、AIの解釈の幅を狭め、意図した通りの動画が生成されやすくなります。
まずは、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、情景を文章でスケッチする感覚でプロンプトを作成してみましょう。
プロンプトエンジニアリングのベストプラクティス
より高度な動画を生成するためには、基本的な構文に加えて、いくつかのベストプラクティス(最善の方法)を実践することが推奨されます。
第一に、「具体性」をとことん追求することです。
例えば「車」ではなく「赤いスポーツカー」、「速く」ではなく「高速道路を疾走する」と具体的に記述します。
第二に、「ネガティブプロンプト」の活用です。
これは「〜しないで」という指示ではなく、「望まない要素」を明確に排除する記述方法です(例:「低品質、ぼやけた、手ブレ」など。ただし、プラットフォームがネガティブプロンプトに対応しているか確認が必要です)。
第三に、「試行錯誤(イテレーション)」を前提とすることです。
最初のプロンプトで完璧な結果が出ることは稀です。
生成された動画を見て、意図と違う部分(例:カメラが近すぎる、動きが遅い)を特定し、プロンプトを修正して再度生成する、というサイクルを回すことが上達の近道です。
カメラワーク指示で映像品質を向上させる方法
veo3.1は、映画制作で使われる専門的なカメラワークの指示を高い精度で理解します。
プロンプトにこれらの用語を組み込むことで、単調な映像から、意図を持った「作品」へと品質を向上させることができます。
よく使われるカメラワーク指示の例:
- Zoom in / Zoom out: 被写体に寄る / 被写体から引く
- Pan (left / right): カメラを水平に(左/右に)振る
- Tilt (up / down): カメラを垂直に(上/下に)振る
- Dolly shot: カメラが台車に乗って被写体に近づく/遠ざかる
- Crane shot / High-angle shot: 高い位置から見下ろす
- Low-angle shot: 低い位置から見上げる
- Drone shot / Aerial view: ドローンで撮影したような空撮
- Close-up: 被写体の顔や一部を大きく映す
- Wide shot: 広範囲を映す
これらの指示を「行動」や「スタイル」の部分に加えるだけで、映像のダイナミクスが劇的に変わります。
(例:「…ドローンショットで上空から撮影」)
音声指示で臨場感をアップさせるコツ
veo3.1の最大の特徴であるネイティブオーディオ機能を活かすため、音声に関する指示もプロンプトに明確に含めましょう。
音声指示は主に「BGM(背景音楽)」「SFX(効果音)」「環境音」「会話(Dialogue)」の4種類に分けられます。
プロンプトの最後に、Audio: や Sound: といった接頭辞をつけて、必要な音を具体的にリストアップするのが効果的です。
音声指示の例:
「...(映像の指示)...
音声:
(BGM)静かなピアノジャズ
(環境音)雨が窓に当たる音、遠くの雷鳴
(SFX)カップをテーブルに置く「コツン」という音
(会話)「寒いね」「そうだね」という2人の女性のささやき声」このように音を細かくデザインすることで、映像のリアリティと没入感を飛躍的に高めることができます。
「静かな」や「激しい」といった形容詞を加えることで、音のニュアンスもコントロール可能です。
「veo3.1」を使う上での注意点と商用利用の可否
veo3.1は非常に強力なツールですが、利用にあたってはいくつかの注意点と、権利関係の確認が必要です。
- 注意点①:著作権・肖像権への配慮
- 注意点②:AI生成であることの明示
- 注意点③:個人情報や機密データを入力しない
- veo3.1で生成した動画は商用利用できる?
これらの点を遵守し、トラブルなく安全にAIを活用しましょう。
注意点①:著作権・肖像権への配慮
veo3.1は、インターネット上の膨大なデータを学習していますが、その学習データには著作権で保護された映像や、実在の人物の肖像が含まれている可能性があります。
そのため、プロンプトで「特定の俳優に似せて」や「有名な映画の特定のシーン」といった指示を出すと、著作権や肖像権を侵害する結果物が生成されるリスクがあります。
また、「Ingredients to Video」機能で他人が撮影した写真やイラストを無断で使用すると、その画像の著作権を侵害する可能性があります。
AIで生成したからといって、既存の権利が無視されるわけではありません。
特に商用利用を考える場合は、特定のアーティストのスタイルを模倣させたり、実在の人物やブランドロゴに酷似したものを生成させたりする指示は避けるべきです。
生成AIを企業で利用する際のリスク管理については、著作権やセキュリティを含め、こちらの記事で網羅的に解説しています。 合わせてご覧ください。
注意点②:AI生成であることの明示
AIによって生成されたコンテンツ(特にリアルな人物や出来事)は、時にフェイクニュースや誤情報の拡散に利用されるリスクがあります。
Googleは、AI生成コンテンツの透明性を重視しており、veo3.1で生成された動画には「SynthID」と呼ばれる電子透かし技術が埋め込まれ、AIによる生成物であることを後から検出できるようになっています。
倫理的な観点からも、AIで生成した動画を(特に実在の出来事のように)公開する場合は、それがAIによる生成物であることを視聴者に明示する(例:キャプションに「AI生成」と記載する)ことが推奨されます。
プラットフォームの利用規約によっても、AI生成コンテンツの明示が義務付けられている場合があるため、必ず規約を確認してください。
注意点③:個人情報や機密データを入力しない
veo3.1を利用する際、プロンプトや参照画像として入力したデータは、サービス品質の向上のため、Googleのサーバーに送信され、分析・学習データとして利用される可能性があります。
(※法人向けのVertex AIなど、データが学習に使われない設定が可能なプランもあります)
そのため、一般向けのGeminiアプリなどで利用する場合、プロンプトに個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報や、会社の内部資料、未公開の新製品情報といった機密データを絶対に入力してはいけません。
参照画像として、自分や他人の顔がはっきりと写った写真(個人が特定可能なもの)をアップロードする際も、そのデータがどのように扱われるかを理解した上で、慎重に行う必要があります。
veo3.1で生成した動画は商用利用できる?
veo3.1で生成した動画の商用利用の可否は、利用するプラットフォーム(Gemini, Flow, APIなど)の利用規約によって定められます。
一般的に、Googleのような大手プラットフォームが提供するAIサービスの有料プランでは、生成されたコンテンツの所有権はユーザーに帰属し、商用利用も許可されるケースが多いです。
ただし、いくつかの条件が付くことが予想されます。
例えば、前述の著作権・肖像権を侵害しないこと、公序良俗に反する利用(例:差別的、暴力的、詐欺的コンテンツ)をしないこと、AI生成であることを(必要に応じて)明示することなどが規約で定められます。
無料プランで生成した動画については、商用利用が禁止または制限されている可能性もあります。
veo3.1をビジネス(広告、商品販売、コンテンツ配信など)で利用する前には、必ず利用しているプランの最新の利用規約を熟読し、「商用利用(Commercial Use)」に関する項目を確認してください。
こちらは、Googleが定める生成AIの「禁止されている使用ポリシー」の公式ドキュメントです。商用利用やコンテンツ制作の際に遵守すべきルールが明記されています。 https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy
「veo3.1」をさらに活用したい方へ【最新情報】
veo3.1は発表されたばかりの最新技術であり、機能や利用方法は日々進化しています。
- veo3.1に関する最新情報のキャッチアップ方法
- 関連する無料セミナーやイベント情報
ここでは、veo3.1の最前線を追い続けるための方法を紹介します。
veo3.1に関する最新情報のキャッチアップ方法
veo3.1に関する最新かつ正確な情報を得るためには、以下の公式ソースを定期的にチェックすることをお勧めします。
- Google AI / DeepMind 公式ブログ:veo3.1の基盤技術や大規模なアップデートは、GoogleのAI研究部門(Google AIやDeepMind)の公式ブログで発表されます。技術的な詳細や開発の背景を知ることができます。
- Google Cloud Blog / Developers Blog:APIの提供開始、Vertex AIでの新機能、開発者向けのチュートリアルや料金改定などは、Google Cloudや開発者向けブログで発表されます。
- Gemini / Flow の公式ヘルプ・お知らせ:一般ユーザー向けのGeminiアプリやFlowに新機能としてveo3.1がどのように実装されたか、具体的な使い方やプランの変更などは、各サービスのヘルプセンターや公式X(旧Twitter)アカウントで告知されます。
- 信頼できるAI系ニュースメディア:国内外の主要なテクノロジーメディアや、AI専門のニュースサイトも、アップデート情報を分かりやすく解説してくれるため有用です。
関連する無料セミナーやイベント情報
veo3.1のような革新的な技術が発表されると、その活用方法に関するセミナーやウェビナー(オンラインセミナー)が多数開催されます。
Google自身が主催する開発者向けイベント(Google I/O, Google Cloud Nextなど)では、veo3.1の最新事例や活用デモが紹介される可能性が非常に高いです。
また、Google Cloudのパートナー企業や、AI活用を支援するコンサルティング会社、デジタルマーケティング企業なども、veo3.1の使い方やビジネス活用をテーマにした無料セミナーを開催することがあります。
これらのイベント情報は、connpassやTECH PLAYといったIT勉強会のプラットフォームや、各企業のメールマガジン、SNSなどで告知されます。
実際のデモンストレーションを見ることは、テキストで情報を追うよりも深く技術を理解する助けとなるため、積極的に参加してみることをお勧めします。
veo3.1は創造性を奪う?「AIに作らせる人」と「AIで創造する人」の決定的違い
veo3.1の驚異的な性能にワクワクしているあなた、その使い方で本当に「クリエイティブ」になれていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの創造性はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。スタンフォード大学の最近の研究がそれを裏付けています。
しかし、ご安心ください。ピクサーなどのトップスタジオでは、AIを「最強の制作ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「創造する人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、分かりやすく解説します。
【警告】veo3.1はあなたの「創造性をサボらせる」かもしれない
「veo3.1に任せれば、映像を作らなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。スタンフォード大学の研究によると、AIツールにアイデア生成から実行までを任せたグループは、自力で構想を練ったグループに比べて、独創的な成果を生み出す割合が大幅に低下することがわかりました。
これは、映像制作の核となる「構想力」をAIに丸投げしてしまう「創造性の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 独自の視点が衰える: AIの生成した「それらしい」映像を鵜呑みにし、「本当にこれがベストか?」と疑う力が鈍る。
- 制作意図が希薄になる: 楽して得た映像は、なぜそのカットが必要なのかという論理が伴わない。
- 新しい表現が湧かなくなる: 脳が「テンプレ」に慣れてしまい、自ら困難な表現に挑戦する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「創造する力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
スタンフォード大学の研究者たちは、生成AIが人間の創造的プロセスに与える影響について調査しました。その結果、AI支援によるアイデア生成タスクでは、人間の独創性が低下する傾向が見られました。(Liang, W., et al. “The Impact of Generative AI on Creative Problem-Solving.” 2024年)
【実践】AIを「映像制作のジム」に変えるトップクリエイターの使い方
では、「創造する人」はveo3.1をどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「完成品を出す機械」ではなく、「構想を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「プリビズ(絵コンテ)」相手にする
自分の頭の中にあるイメージを具体化するには、視覚的なフィードバックが不可欠です。そこで、veo3.1をあえて「ラフな指示を具体化するアシスタント」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの構想)について、あえて『最も退屈な表現』と『最も斬新な表現』の2パターンをラフに生成してください。カメラワークは固定で。」これにより、AIの提案を比較検討する中で、自分のイメージが明確になり、より良い演出を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「厳しい監督」としてダメ出しさせる
自分が本当にシーンの意図を理解しているか試したければ、第三者の視点でチェックするのが一番です。veo3.1(または連携するGemini)を「批評的な監督役」にして、あなたの指示を評価させましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが作りたいシーンのプロンプト)』を入力します。あなたは厳しい映画監督だと思って、この指示で意図が伝わるか、曖昧な部分がないか、遠慮なく指摘してください。」AIからの鋭い指摘に答える(プロンプトを修正する)ことで、自分の指示の甘い部分が明確になり、映像の解像度が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に試す「実験場」にする
ゼロから「面白い動画を出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分の構想の核となる要素(例:veo3.1のIngredients to Video機能)をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』の動画を作ります。参照画像は『A(キャラクター)』『B(背景)』です。これらに『C(例:悲しい雰囲気)』という要素を加えて、予期せぬ感情的なシーンを5つ提案してください。」AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なシーンに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、表現の幅が大きく向上します。
まとめ
企業はマーケティングやコンテンツ制作において、高品質な動画の需要増大や制作コストの課題を抱える中で、veo3.1のような生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「動画生成AIをどう業務に組み込むかわからない」「動画以外にもAIを活用したいが、社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、AI導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、動画制作のアイデア出しだけでなく、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、veo3.1で生成した動画のナレーション作成や、その動画を使ったブログ記事作成、SNS投稿文の自動生成、さらに日常業務のメール作成や議事録作成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。