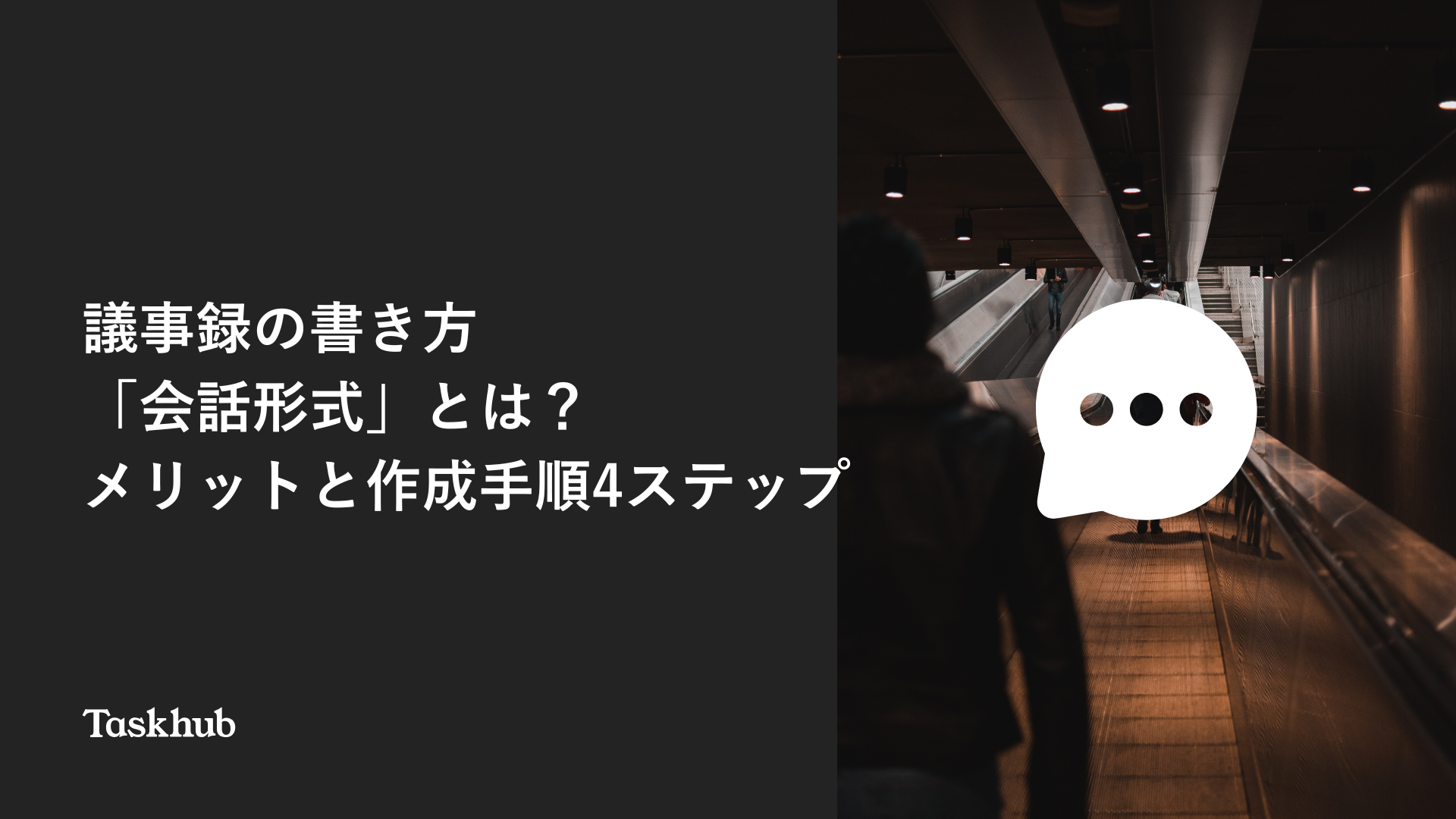「会議の議事録、会話形式で書くように言われたけど、どうやるの?」
「会話形式の議事録は時間がかかりそうだし、要点が伝わるか不安…。」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
会話形式の議事録は、会議の発言を時系列に沿って書き起こす手法で、議論の流れやニュアンスを正確に残せるメリットがあります。
しかし、ただ文字起こしをするだけでは、情報量が多すぎて読みにくい議事録になってしまいます。
本記事では、会話形式の議事録の正しい書き方と手順、要約形式との違い、そして作成を効率化するAIツールまで、網羅的に解説します。
生成AIツールによる議事録作成の効率化は、今や企業のDXに不可欠です。企業向けChatGPTの導入について、料金やセキュリティ、活用事例を網羅的に解説した記事もございます。合わせてご覧ください。
この記事を読めば、会話形式の議事録のメリットを活かしつつ、要点が伝わる議事録を効率的に作成するコツがわかります。
ぜひ最後までご覧ください。
会話形式の議事録とは?要約形式との違い
まずは、会話形式の議事録がどのようなものか、一般的な要約形式とどう違うのかを明確にしておきましょう。
それぞれの特徴と違いを理解することで、会議の目的に合わせて最適な書き方を選択できるようになります。
会話形式の議事録の特徴
会話形式の議事録とは、会議中の発言を「誰が」「何を」話したかが分かるように、時系列に沿って会話のやり取りをそのまま書き起こす形式のことです。
「逐語録(ちくごろく)」とも呼ばれます。
こちらは、逐語録(Verbatim)と非逐語録(Non-Verbatim)の違いや、それぞれの用途について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://waywithwords.net/resource/verbatim-vs-non-verbatim-transcription/
発言者を明記し、発言内容をできるだけ忠実に再現するのが特徴です。
(例)
A部長:「〇〇の件ですが、進捗はいかがですか?」
Bさん:「現在、データの収集中です。来週水曜日までには分析を完了できる見込みです。」
このように、実際の会話の流れを追体験できるように記録します。
ただし、完全に一言一句を文字起こしするのではなく、「えー」「あのー」といった無意味なつなぎ言葉(フィラー)を削除したり、明らかな言い間違いを修正したりする「ケバ取り」という作業を行うのが一般的です。
こちらは、「えー」「あのー」といったフィラー(間投詞)をAIが自動検出する技術に関するMicrosoftの研究論文です。 合わせてご覧ください。 https://www.microsoft.com/applied-sciences/uploads/publications/134/automatic-disfluency-detection.pdf
要約形式(要点整理形式)の議事録との比較
一方、要約形式(要点整理形式)は、会話形式とは対照的です。
会議で議論された内容や決定事項、タスク(ネクストアクション)などを、トピックごとや議題ごとに整理し、要点をまとめて記述する形式です。
(例)
■ 議題1:〇〇の進捗について
・Bさんより、データ収集中であり、来週水曜日に分析完了予定との報告があった。
この形式の最大のメリットは、会議の結果が簡潔にまとめられており、短時間で概要を把握できる点です。
誰が何を言ったかという「過程」よりも、何が決まったかという「結果」を重視する場合に適しています。
多くの企業では、この要約形式が標準的な議事録の書き方として採用されています。
こちらは、ヨーク大学(カナダ)が提供する、効果的な議事録作成(Minute-Taking)のためのテクニックやヒントをまとめた資料です。 合わせてご覧ください。 https://ipo.info.yorku.ca/tool-and-tips/tip-sheet-12-minute-taking-tips-and-techniques/
会話形式は「議論の過程」を詳細に残すことに優れ、要約形式は「議論の結果」を簡潔に伝えることに優れている、と覚えておくと良いでしょう。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
会話形式で議事録を作成するメリット3選
会話形式の議事録は作成に手間がかかるイメージがありますが、それに見合う大きなメリットがあります。
ここでは、会話形式を採用する主なメリットを3つ紹介します。
- 発言者と発言内容が正確にわかる
- 会議の雰囲気や議論の流れが伝わりやすい
- 会議の情報を書き漏らすリスクが低い
これらのメリットを理解することで、会話形式が役立つ場面が明確になります。
それでは、1つずつ順に解説します。
メリット1:発言者と発言内容が正確にわかる
会話形式の議事録の最大のメリットは、記録の正確性です。
「誰が」その発言をしたのかが明確に記録されるため、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。
特に、重要な意思決定や、責任の所在を明確にしておく必要がある会議において、このメリットは非常に大きいです。
要約形式では、議事録作成者の解釈によって発言の意図が異なって伝わるリスクがありますが、会話形式では発言がそのまま記録されるため、発言者の真意やニュアンスが正確に伝わります。
メリット2:会議の雰囲気や議論の流れが伝わりやすい
会議は、単なる決定事項の確認だけでなく、議論が白熱したり、アイデアが生まれたりする「場」でもあります。
会話形式の議事録は、どのような議論を経てその結論に至ったのか、どのような反対意見が出たのか、といった議論のプロセスを時系列で追うことができます。
これにより、会議に参加できなかった人でも、会議の雰囲気や議論の温度感を掴みやすくなります。
特に、ブレインストーミングや活発な意見交換が行われた会議では、要約形式では伝わらない「行間」の情報を共有できるのが強みです。
メリット3:会議の情報を書き漏らすリスクが低い
要約形式の議事録は、作成者が「重要だ」と判断した部分を抜き出して作成します。
そのため、作成者のスキルや解釈によっては、重要な発言や決定事項が抜け漏れてしまうリスクが常に伴います。
一方、会話形式は、基本的にすべての発言を記録(または録音から文字起こし)するため、情報が抜け落ちる心配がありません。
会議中は重要だと思われなかった発言が、後になって重要な意味を持つこともあります。
会話形式で記録を残しておけば、後から詳細を確認したいときに、元の発言にいつでも立ち返ることができるという安心感があります。
会話形式で議事録を作成するデメリット2選
会話形式の議事録には多くのメリットがある一方で、実務で使う際には注意すべきデメリットも存在します。
主なデメリットとして、以下の2点が挙げられます。
- 要点が分かりにくく、情報量が多くなる
- 作成に時間がかかる(文字起こし・清書)
これらのデメリットを理解し、対策を講じることが重要です。
デメリット1:要点が分かりにくく、情報量が多くなる
会話形式は、すべての発言を時系列で記録するため、必然的に議事録のボリュームが非常に大きくなります。
1時間の会議でも、文字起こしをすると数千文字から1万文字を超えることも珍しくありません。
そのため、会議の結果だけを端的に知りたい人にとっては、「どこが重要なポイントなのか」「結局、何が決まったのか」が分かりにくく、読むのに時間がかかってしまいます。
すべての発言が同列に扱われるため、重要な決定事項が雑談や脱線した議論の中に埋もれてしまう可能性もあります。
このデメリットを補うためには、記事の後半で解説する「議論の要点(サマリー)」を議事録の冒頭に別途記載する工夫が必要です。
こちらは、AIによる「会議要約(Meeting Summarization)」の最新技術動向や研究を調査した学術論文です。 合わせてご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/366397596_Meeting_Summarization_A_Survey_of_the_State_of_the_Art
デメリット2:作成に時間がかかる(文字起こし・清書)
会話形式の議事録を作成する上で、最も大きなハードルが「作成時間」です。
会議の内容を録音し、それを聞き返しながら手作業で文字起こしをする場合、一般的に会議時間の4倍から10倍の時間がかかると言われています。
つまり、1時間の会議の議事録を作成するために、4時間以上かかる計算になります。
さらに、文字起こしをした後、発言者を特定したり、文章を整えたりする清書の作業も必要です。
この膨大な作業コストが、会話形式の議事録が敬遠される最大の理由です。
ただし、このデメリットは、後述するAIツールを活用することで大幅に軽減することが可能です。
この作業は、AIツールを活用することで大幅に軽減することが可能です。ChatGPTを使って会議を文字起こしし、議事録を作成する具体的な方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
会話形式の議事録が適しているケース(使い分け)
会話形式と要約形式には、それぞれメリットとデメリットがあります。
全ての会議で会話形式を採用するのは非効率です。
ここでは、会話形式の議事録が特に適している3つのケースを紹介します。
会議の目的や性質に応じて、議事録の書き方を使い分けることが重要です。
質疑応答やブレインストーミングがメインの会議
活発な意見交換や、多様なアイデアを出し合うブレインストーミング(ブレスト)が目的の会議では、会話形式が非常に有効です。
要約形式ではこぼれ落ちてしまうような、議論の過程で出た具体的なアイデアや、質問に対する詳細な回答をそのまま記録できます。
「なぜそのアイデアが出たのか」という背景や文脈も一緒に残るため、後から会議を振り返る際に役立ちます。
また、顧客インタビューやユーザーヒアリングなど、相手の言葉を正確に記録したい場合にも適しています。
会議の雰囲気を詳細に共有したい場合
会議の決定事項だけでなく、その場の雰囲気や議論の熱量、参加者の反応などを共有することが重要な場合にも、会話形式が選ばれます。
例えば、重要な交渉や、意見が対立した議論などです。
要約された結果だけを見ると冷たい印象を受けるかもしれませんが、会話形式で議論の過程を読めば、「Aさんはこういう意図で反対していたが、Bさんのこの提案によって納得した」といった背景が理解できます。
会議に参加していない上司や関係者に、議論のニュアンスを正確に伝えたい場合に役立ちます。
こちらは、ヘルシンキ大学による、職場での会話や議論のプロセス(Institutional Interaction)に関する学術的研究資料です。 合わせてご覧ください。 https://researchportal.helsinki.fi/files/98008543/ArminenInstitutionalJuly25th05.pdf
誰が何を発言したかを明確に残す必要がある場合
責任の所在や合意形成のプロセスを厳密に記録する必要がある会議では、会話形式が必須です。
例えば、契約内容の確認、コンプライアンスに関わる会議、あるいは法的な証拠として残す必要がある場合などです。
「Aさんがこの条件で合意した」「Bさんがこのリスクを指摘した」という事実を、発言者とセットで正確に記録することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
要約形式では「〜という意見が出た」と曖昧になりがちな部分も、会話形式なら明確に残すことが可能です。
会話形式の議事録の書き方 4ステップ
会話形式の議事録は、やみくもに文字起こしをすれば良いわけではありません。
読みやすく、後から活用できる議事録を作成するための基本的な手順を4つのステップで解説します。
この書き方の流れをマスターすることで、効率的に質の高い議事録を作成できます。
- 会議の内容を録音する
- 音声を文字起こしする
- 文章を整える(ケバ取り・発言者の明記)
- 重要なポイントを整理して要約する
ステップ1:会議の内容を録音する
会話形式の議事録を作成する上で、録音は必須の作業です。
会議中にリアルタイムですべての発言をタイピングするのは現実的ではありません。
必ずICレコーダーやスマートフォンの録音アプリ、PCの録音機能などを使用して、会議の音声をクリアに録音しましょう。
オンライン会議(Zoom, Teams, Google Meetなど)の場合は、標準の録音機能を使うのが簡単です。
対面の会議では、マイクの性能や設置場所によって音声の品質が大きく左右されます。
参加者全員の声が均等に拾えるよう、高性能な集音マイクを使用するか、レコーダーを会議室の中央に置くなどの工夫をしてください。
ステップ2:音声を文字起こしする
次に、録音した音声データを聞きながら、テキストに書き起こす作業(文字起こし)を行います。
このステップが、会話形式の議事録作成で最も時間がかかる部分です。
手作業で行う場合は、再生速度を調整できる文字起こし専用のソフトやアプリを使うと効率が上がります。
しかし、前述の通り、会議時間の何倍もの時間が必要です。
現在では、この作業をAIに任せるのが主流です。
「Rimo Voice」や「スマート書記」などのAI議事録ツールを使えば、音声ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で文字起こしを行ってくれます。
これにより、作成時間を劇的に短縮できます。
ステップ3:文章を整える(ケバ取り・発言者の明記)
AIまたは手作業で文字起こしが完了したら、読みやすいように文章を整える「清書」の作業を行います。
まずは、発言者を特定し、誰の発言かが分かるように明記します。
(例)
A部長:「〜」
Bさん:「〜」
次に、「ケバ取り」を行います。
これは、「あー」「えーっと」などの意味のない言葉(フィラー)や、重複している言葉、明らかな言い間違いなどを削除・修正し、文章を読みやすくする作業です。
ただし、会話のニュアンスを残すために、どこまで修正するかは事前にルールを決めておくと良いでしょう。
会話形式であっても、議事録はビジネス文書であるため、最低限の読みやすさを担保することが大切です。
ステップ4:重要なポイントを整理して要約する
会話形式の本文だけでは、情報量が多すぎて要点が伝わりません。
そこで、議事録の冒頭部分に、会議の「要約(サマリー)」を別途記載します。
会話形式の本文はあくまで「詳細な記録」と位置づけ、会議の結果だけを知りたい人がサマリーだけ読めば概要を理解できるようにします。
この要約部分には、後述する「議論の要点」「決定事項」「ネクストアクション」などを簡潔にまとめます。
このステップを踏むことで、会話形式の「正確性」と要約形式の「一覧性」の、両方のメリットを兼ね備えた議事録が完成します。
この要約部分を作成する際にも、AIツールが強力な味方となります。ChatGPTを活用して議事録などの長文を効率的に要約する方法については、こちらの記事をご覧ください。
会話形式の議事録に含めるべき基本項目
会話形式の議事録は、単に会話を書き起こすだけでは不十分です。
ビジネス文書として機能させるためには、会話本文の前後に必要な基本項目を漏れなく記載する必要があります。
ここでは、会話形式の議事録に最低限含めるべき5つの項目を解説します。
会議の基本情報(開催日時・参加者・議題)
議事録の冒頭には、その会議が「いつ」「どこで」「誰が」「何を」話したかを明確にする基本情報を記載します。
・会議名
・開催日時(例:2025年11月12日(水) 14:00〜15:00)
・開催場所(例:第3会議室 / オンライン)
・参加者(例:A部長、Bさん、Cさん)
・欠席者(もしいる場合)
・議事録作成者
・議題(アジェンダ)
これらの情報があることで、後から議事録を探しやすくなり、その会議の前提条件をすぐに理解できます。
議論の要点(サマリー)
基本情報の次に、会議全体の「議論の要点(サマリー)」を記載します。
これは、会話形式のデメリットである「要点の分かりにくさ」を補うために非常に重要です。
会議に参加していない人や、忙しい上司がこの部分を読むだけで、会議の概要と結果を把握できるように、箇条書きなどで簡潔にまとめます。
各議題に対して、どのような議論が行われ、どのような結論(または保留)になったのかを記述します。
会話形式の本文(発言者と発言内容)
ここが議事録の本体となる、会話形式の記録部分です。
ステップ3で整えた、発言者と発言内容を時系列で記載していきます。
議題やトピックごとに見出しを付けて区切ると、後から読み返す際に構成が分かりやすくなります。
(例)
■ 議題1:新商品のプロモーション戦略について
A部長:「まず、現状の課題から確認しましょう。」
Bさん:「はい。現状はWeb広告のCPA(顧客獲得単価)が高騰している点が課題です。」
Cさん:「SNSでの認知拡大も伸び悩んでいます。」
(以下、続く)
決定事項
会議を通じて「何が決まったのか」を明確にリストアップします。
会話本文の中に決定事項が埋もれてしまうと、後から確認するのが大変です。
サマリー部分、あるいは議事録の末尾に、必ず「決定事項」のセクションを設け、誰が読んでも明確に分かるように箇条書きで記載します。
(例)
・新商品のプロモーションは、Web広告からインフルエンサーマーケティングへ予算をシフトする。
・ターゲット層に合わせたインフルエンサーのリストアップを開始する。
保留・検討事項(ネクストアクション)
会議で決まらなかったこと(保留事項)や、次に誰が何をするのか(ネクストアクション)も、議事録の重要な要素です。
ネクストアクションは、「担当者」と「期限」をセットで記載するのが鉄則です。
これが明確でないと、タスクが実行されず、会議が「やりっぱなし」になってしまいます。
(例)
・インフルエンサーのリストアップ(担当:Bさん、期限:11月19日)
・競合他社のSNS戦略の再調査(担当:Cさん、期限:11月19日)
・予算案の再計算(担当:A部長、期限:11月21日)
会話形式の議事録作成でよくある失敗例
会話形式の議事録を作成しようとしても、うまくいかないケースがあります。
ここでは、初心者が陥りがちな2つの失敗例を紹介します。
これらの失敗を避けるための対策も合わせて確認しておきましょう。
録音環境が悪く、音声が聞き取れない
会話形式の議事録は、録音データが命です。
しかし、会議室が広すぎて声が反響してしまったり、マイクから遠い人の声が小さすぎたり、資料をめくる音や空調の音などのノイズが大きすぎたりすると、音声が聞き取れず、文字起こしの精度が著しく低下します。
特にAIツールを使う場合、音声品質が悪いと誤字脱字だらけの結果になり、修正に膨大な時間がかかってしまいます。
こちらは、AIの文字起こし精度に影響する、ノイズに強い自動音声認識(Noise-Robust ASR)技術の概要についてまとめた論文です。 合わせてご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/264587966_An_Overview_of_Noise-Robust_Automatic_Speech_Recognition
対策としては、会議の規模に合った高性能な集音マイク(360度集音できるマイクなど)を準備することが最も重要です。
また、発言者はマイクに向かって明瞭に話すよう、会議の冒頭でアナウンスするのも効果的です。
時系列や発言者が整理されておらず、読みづらい
録音した音声をただ文字起こししただけの議事録は、非常に読みにくいものになります。
誰の発言か分からなかったり、議論があちこちに飛んで時系列がバラバラだったりすると、結局何が話されたのか理解できません。
また、「ケバ取り」が不十分で「えー」「あのー」といった言葉が多すぎると、読むのが苦痛になります。
対策としては、ステップ3で解説した「文章を整える」作業を丁寧に行うことです。
発言者は必ず明記し、可能であれば議題ごとにセクションを分け、時系列に沿って整理します。
AIツールの中には、自動で話者を分離(特定)してくれる機能を持つものもあり、こうしたツールを活用するのも一つの手です。
会話形式の議事録 具体例(サンプル)
ここでは、会話形式の議事録が実際にどのような場面で使われるか、3つのシーン別の具体例(サンプル)を紹介します。
あくまで一部分の抜粋ですが、会話の雰囲気を掴む参考にしてください。
会議の議事録サンプル
(前略)
■ 議題2:来期の営業目標について
A部長:「では次に、来期の営業目標についてです。Bさんから案をお願いします。」
Bさん:「はい。資料の3ページをご覧ください。今期の実績と市場の伸び率を考慮し、来期は全体で売上120%増を目標としたいと考えています。」
Cさん:「120%はかなり高い目標ですね。特にX事業部は今期苦戦しましたが、具体的な施策はあるのでしょうか?」
Bさん:「X事業部については、新商品の投入を予定しており、その分を上乗せしています。Cさん、新商品の進捗はいかがですか?」
Cさん:「現在、最終テスト段階です。来期初頭のリリースには間に合う見込みです。」
A部長:「承知しました。では、この目標をベースに、各チームの詳細なアクションプランを詰めていきましょう。」
(後略)
インタビューの議事録サンプル
(前略)
インタビュアー:「本日はお忙しい中ありがとうございます。まず、〇〇様がこのサービスを導入されようと思ったきっかけを教えていただけますか?」
〇〇様:「はい。以前は別のシステムを使っていたのですが、操作が複雑で社内に浸透しなかったのが一番の悩みでした。もっとシンプルで、誰でも直感的に使えるツールを探していたんです。」
インタビュアー:「なるほど。操作のシンプルさが決め手だったのですね。実際に弊社のサービスを使ってみて、その点はいかがでしたか?」
〇〇様:「非常に満足しています。特にマニュアルを読まなくても、導入初日からほとんどの社員が使いこなせていました。サポート体制もしっかりしていて安心です。」
(後略)
質疑応答(Q&A)の議事録サンプル
(前略)
■ 質疑応答
質問者A:「ご説明ありがとうございました。セキュリティ対策についてですが、データセンターは国内にあるのでしょうか?」
登壇者B:「ご質問ありがとうございます。はい、弊社のデータはすべて国内のデータセンターで厳重に管理しております。ISMS認証も取得しておりますのでご安心ください。」
質問者C:「料金プランについてです。スタンダードプランとプレミアムプランの違いがよく分かりませんでした。具体的にどの機能が異なるのですか?」
登壇者B:「スタンダードプランは基本的な機能が中心ですが、プレミアムプランでは、AIによる高度な分析機能や、専任のコンサルタントによるサポートが追加されます。詳細は後ほど資料をお配りします。」
(後略)
会話形式の議事録に使えるテンプレート(無料ダウンロード)
会話形式の議事録をゼロから作成するのは大変です。
ここでは、すぐに使える基本的なテンプレート(ひな形)を、一般的なビジネスソフト別にご紹介します。
(※実際のダウンロードリンクではなく、構成要素の例示となります)
これらのテンプレートをベースに、自社の運用に合わせてカスタマイズしてご使用ください。
Word(ワード)形式のテンプレート
Wordは、文章作成に特化しており、最も一般的に使われる形式です。
サマリーや決定事項、会話本文を自由にレイアウトしやすいのが特徴です。
(構成例)
議事録
| 会議名 | |
| 開催日時 | 202X年XX月XX日 (X) XX:XX~XX:XX |
| 開催場所 | |
| 参加者 | (敬称略) |
| 議事録作成者 |
1. 議題(アジェンダ)
2. サマリー(議論の要点)
・
・
3. 決定事項
・
・
4. ネクストアクション(担当者・期限)
・(担当:〇〇、期限:X/X)
・
5. 会議内容(会話形式)
■ 議題1:〇〇について
Aさん:「〜」
Bさん:「〜」
■ 議題2:〇〇について
Aさん:「〜」 Cさん:「〜」
Excel(エクセル)形式のテンプレート
Excelは、発言者、発言内容、時間などを列で管理しやすいのが特徴です。
また、ネクストアクションの進捗管理(ステータス)を一覧で管理したい場合に便利です。
(構成例)
| (A列) | (B列) | (C列) |
| 会議名 | (会議名) | |
| 開催日時 | (日時) | |
| 場所 | (場所) | |
| 参加者 | (参加者名) | |
| 決定事項 | 1. 〜 | |
| 2. 〜 | ||
| ネクストアクション | 担当者 | 期限 |
| 1. 〜 | 〇〇 | X/X |
| 2. 〜 | △△ | X/X |
会議内容 | | 議題 | 発言者 | 発言内容 議題1 | Aさん | 〜 | Bさん | 〜 議題2 | Aさん | 〜 | Cさん | 〜
Googleドキュメント形式のテンプレート
Googleドキュメントは、Wordとほぼ同様の形式で作成できます。
最大のメリットは、クラウド上で複数人が同時に編集したり、コメントを付けたりできる点です。
議事録のレビューや共同編集が多い場合におすすめです。
テンプレートの構成は、上記のWord形式と同様のものが利用できます。
共有設定を適切に行い、関係者間ですぐに内容を確認できるようにしておくと効率的です。
会話形式の議事録作成を効率化するAIツール3選
会話形式の議事録作成で最も時間がかかる「文字起こし」と「清書」。
この作業を劇的に効率化してくれるのが、AI議事録作成ツールです。
ここでは、高精度な日本語認識で評価の高い、代表的なAIツールを3つ紹介します。
Rimo Voice
Rimo Voiceは、日本語に特化した高精度なAIを搭載した文字起こしツールです。
1時間の音声データでも、わずか5分程度で高速に文字起こしを完了できるのが最大の特徴です。
文字起こしされたテキストと元の音声が連動しており、テキストをクリックするだけで該当箇所の音声をピンポイントで再生できるため、聞き直しや修正作業が非常に効率的です。
また、AI(ChatGPT活用)による自動要約機能も備えており、文字起こしと同時に議論の要点を素早く把握することができます。
「えー」「あのー」といったフィラーを自動で除去する機能もあり、清書の負担を大幅に軽減してくれます。
スマート書記
スマート書記は、90%以上という高い文字起こし精度を誇るAI議事録ツールです。
特に、AIによる「議事録アシスト」機能が充実しています。
文字起こし結果から、AIが自動で要約を作成したり、重要なポイントを抽出したり、文章を読みやすく清書したりするのをサポートしてくれます。
また、最大20名までの話者を自動で識別する機能も搭載しており、誰が何を話したかを整理する手間を省けます。
会議中にリアルタイムで文字起こしを確認しながら、複数人で同時に議事録を編集できる「議事録エディタ」も強力な機能の一つです。
AI議事録取れる君
AI議事録取れる君は、特にオンライン会議との連携に優れたツールです。
Zoom、Microsoft Teams、Google Meetとスケジュール連携が可能で、設定しておけばAIが自動で会議に参加し、録音と議事録作成(文字起こし・要約)をフルオートで行ってくれます。
1時間の会議内容をわずか1分で要約できるスピード感も魅力です。
また、多言語対応と自動翻訳機能も備えており、グローバルな会議でもリアルタイムで発言内容を翻訳しながら議事録に残すことができます。
句読点や疑問符などもAIが自動で挿入してくれるため、読みやすい議事録が効率的に完成します。
あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い
ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。
【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない
「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。
これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。
- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。
- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方
では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「壁打ち相手」にする
自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」
これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「無知な生徒」として教える
自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」
AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」
AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。
まとめ
会話形式の議事録は、議論の流れやニュアンスを正確に残せるメリットがある一方で、作成に膨大な時間がかかるという課題を抱えています。
記事で紹介されたようなAIツールが注目されていますが、実際には「どのツールを選べばいいかわからない」「議事録以外にもAIを活用したいが、ツールがバラバラになってしまう」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、この記事のテーマである議事録作成や要約はもちろん、メール作成や画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社の議事録作成業務、ひいては全社のDXを一気に加速させましょう。