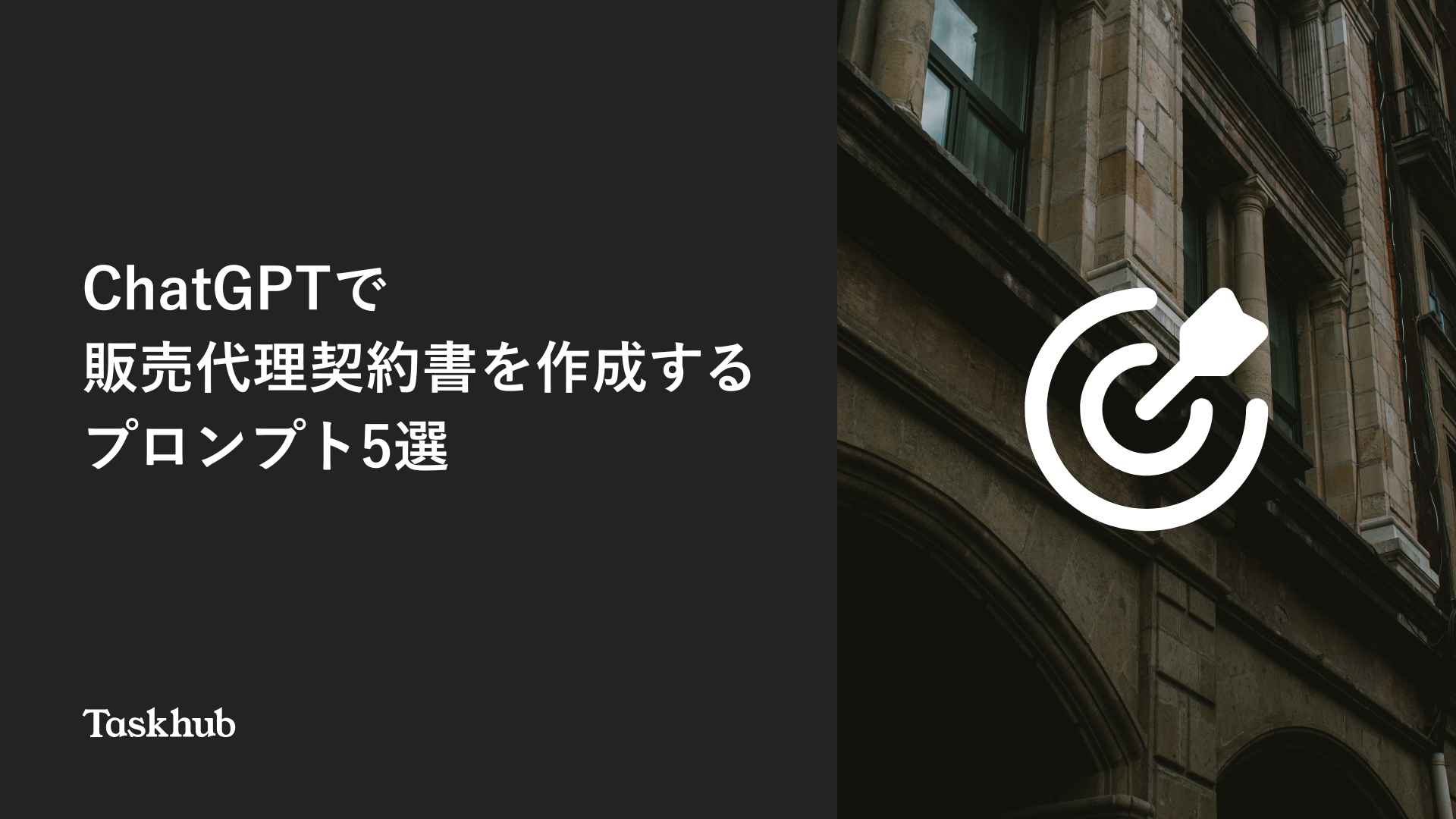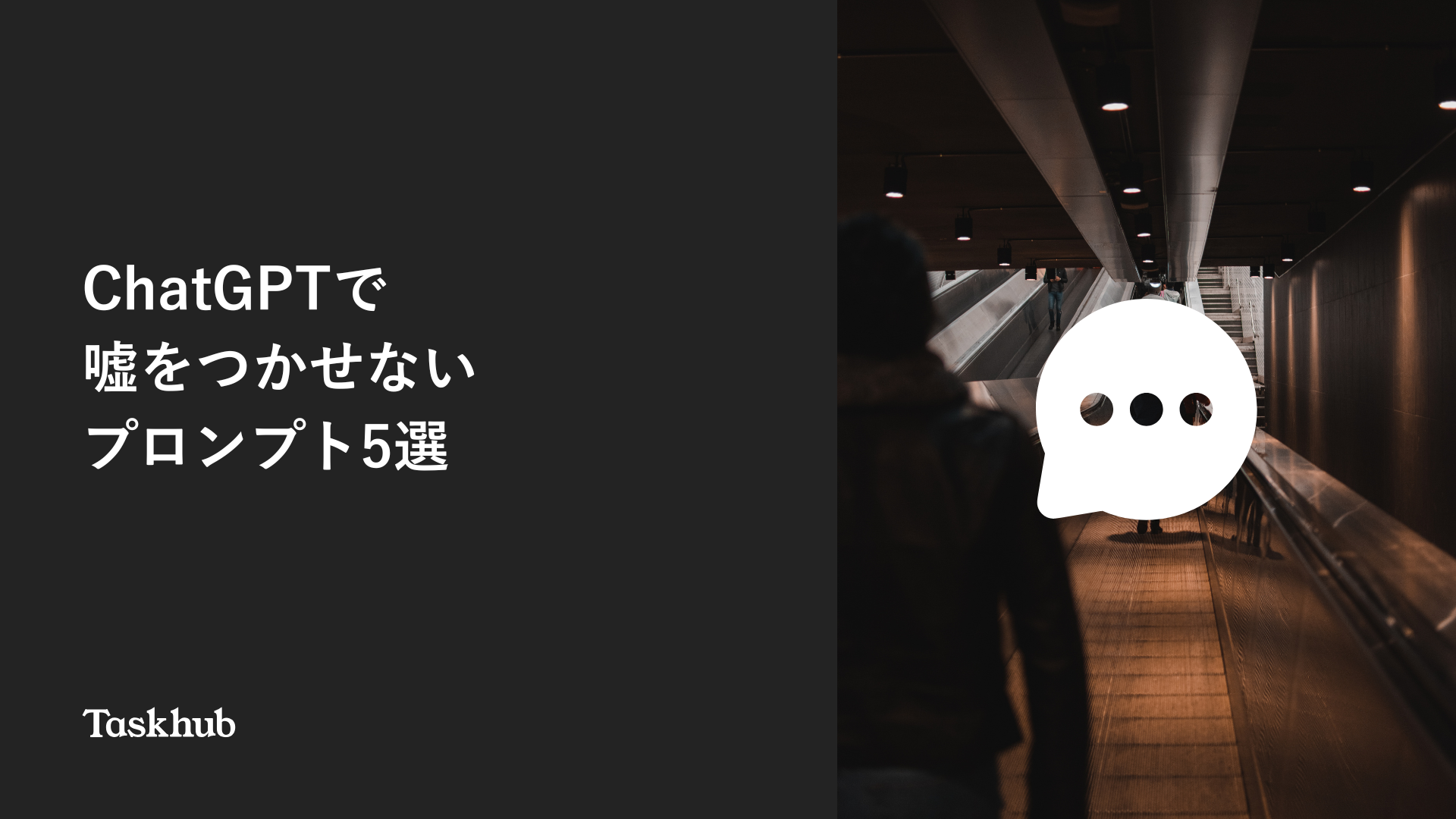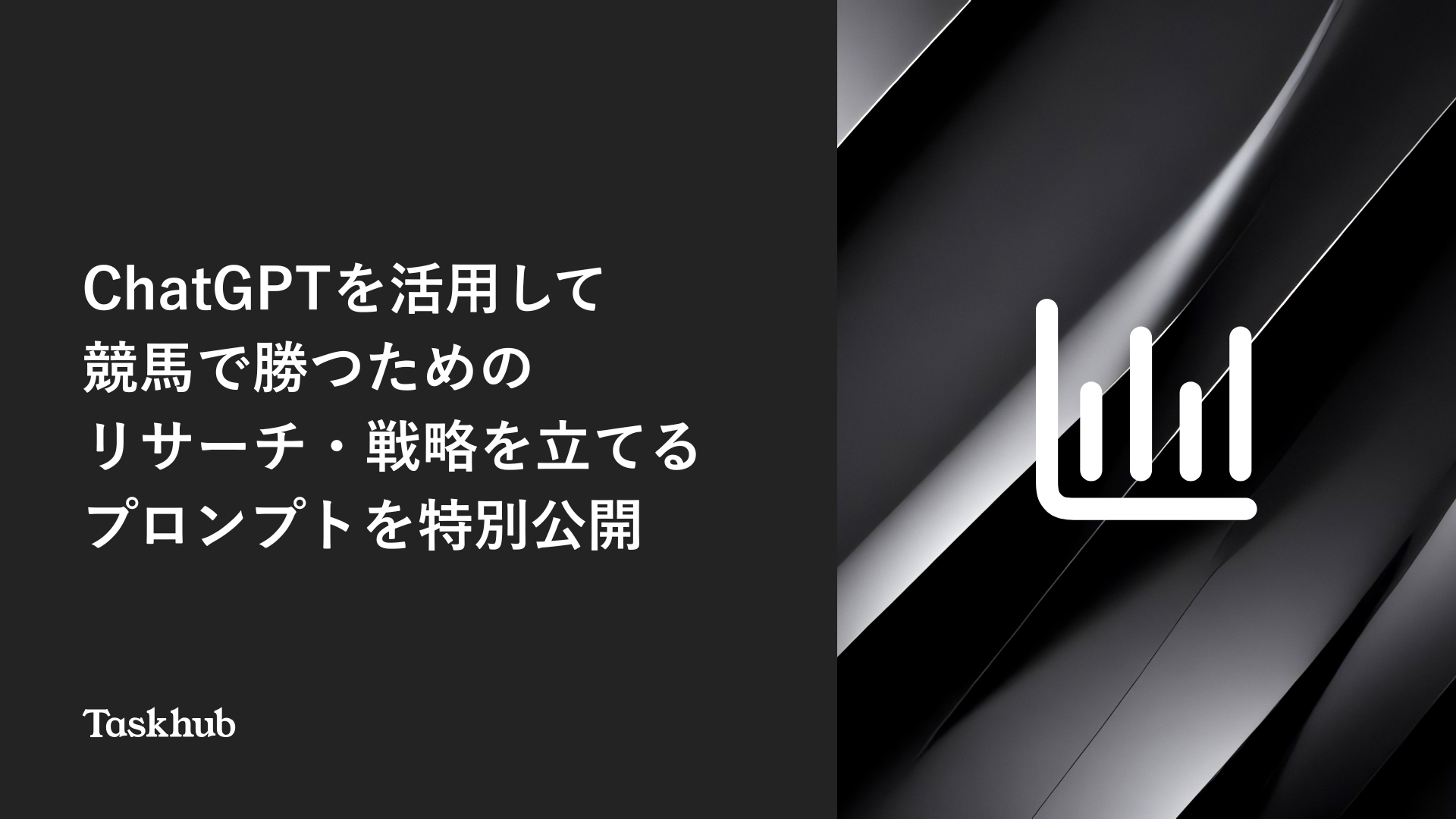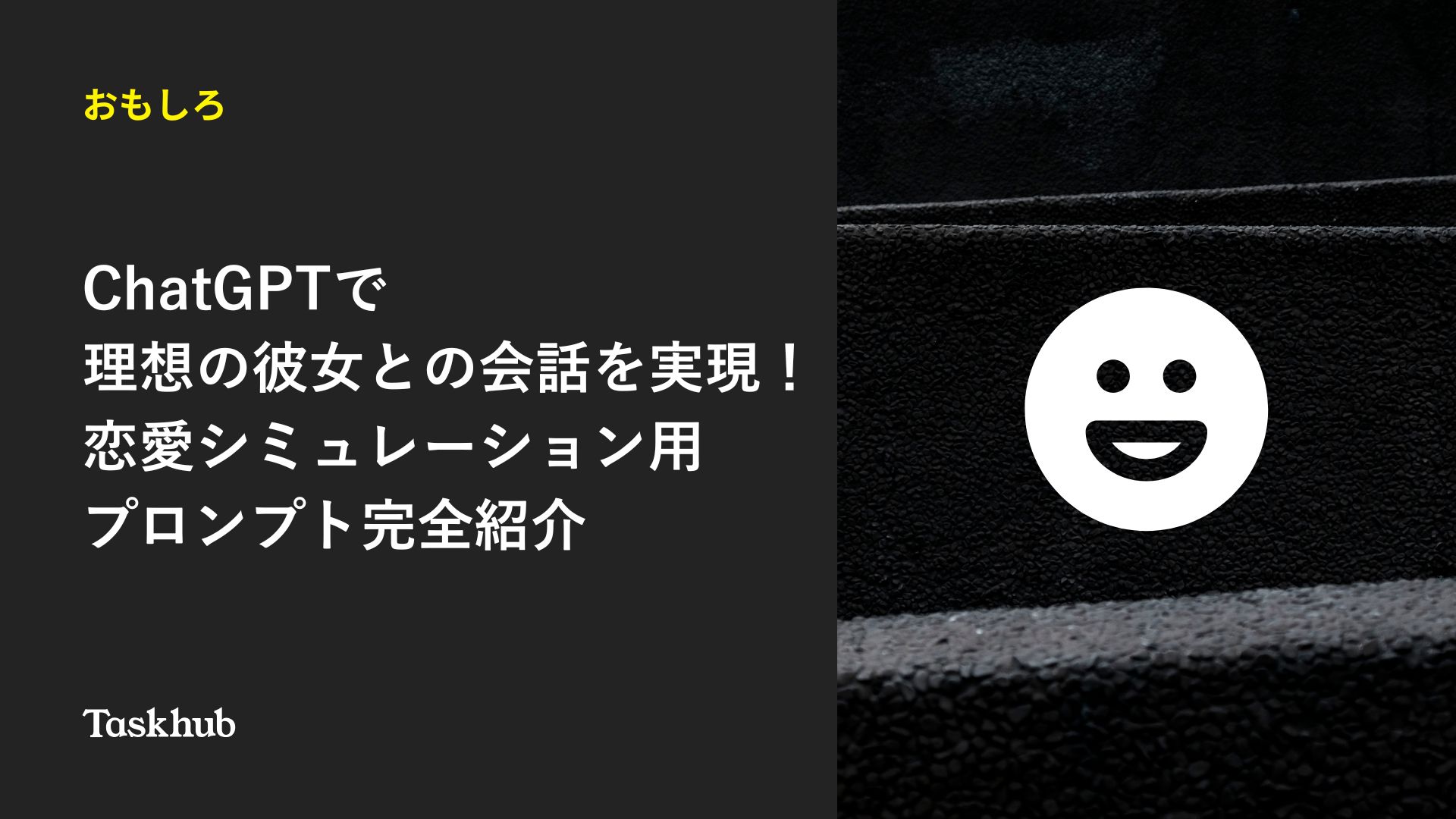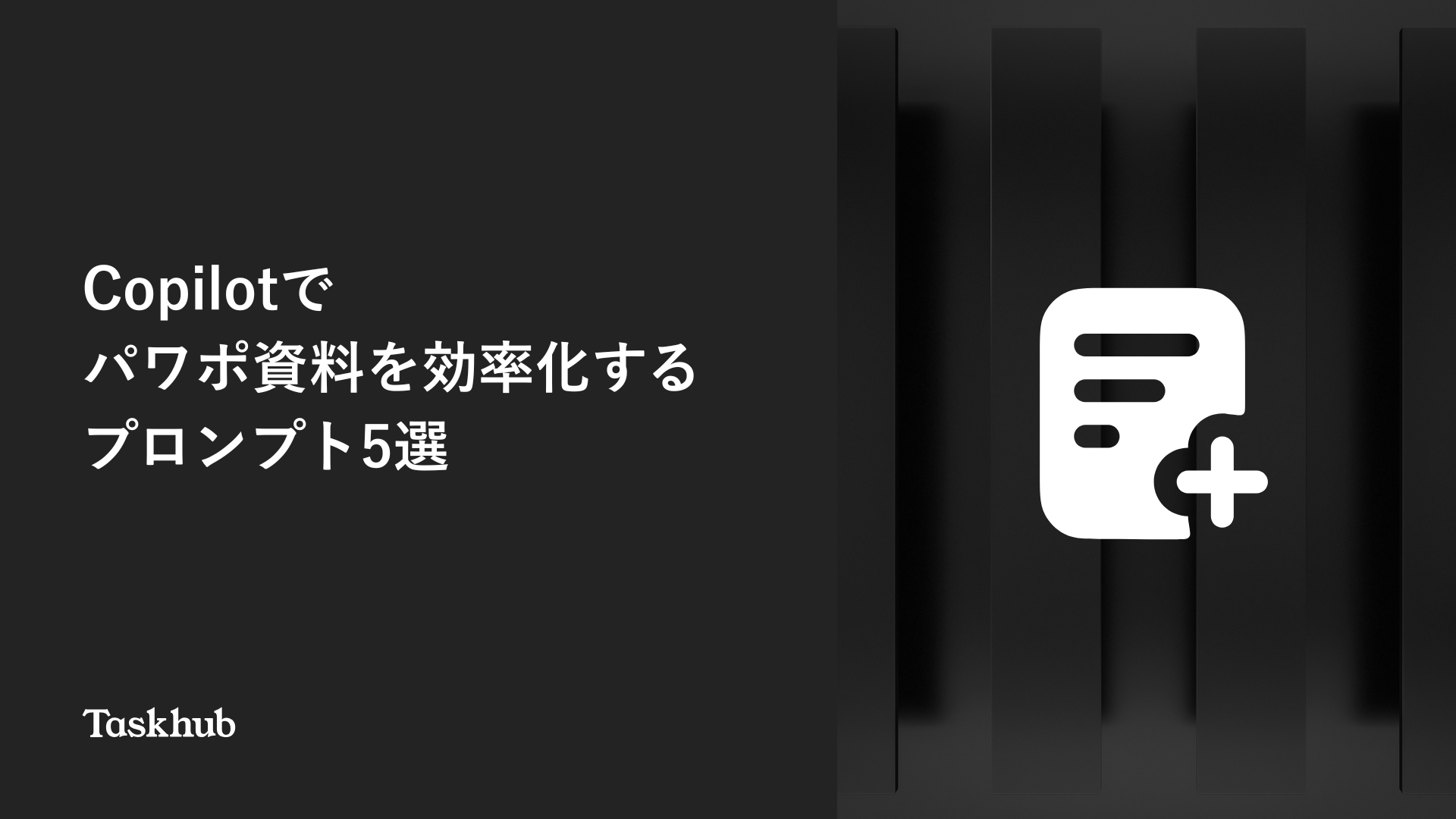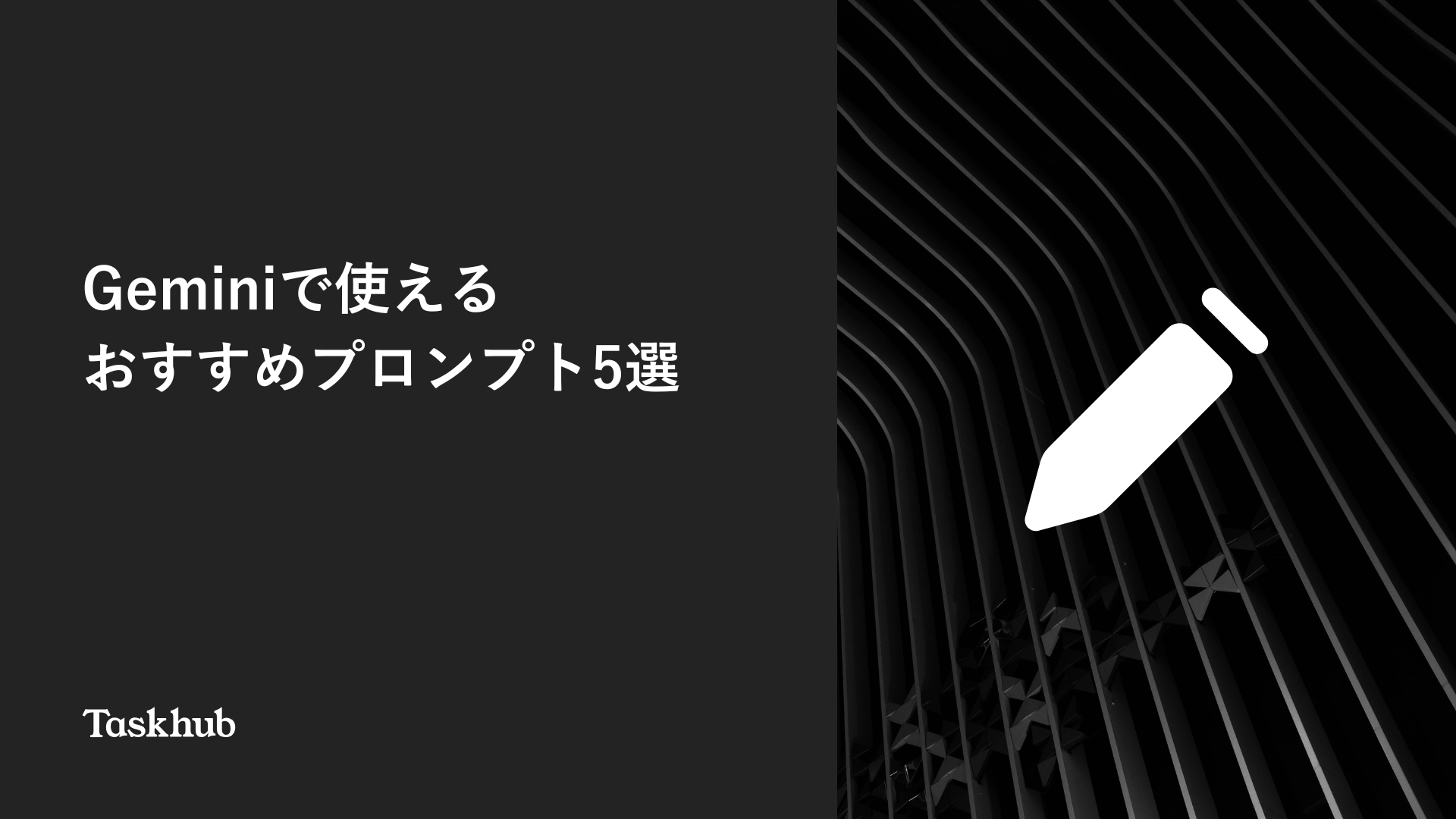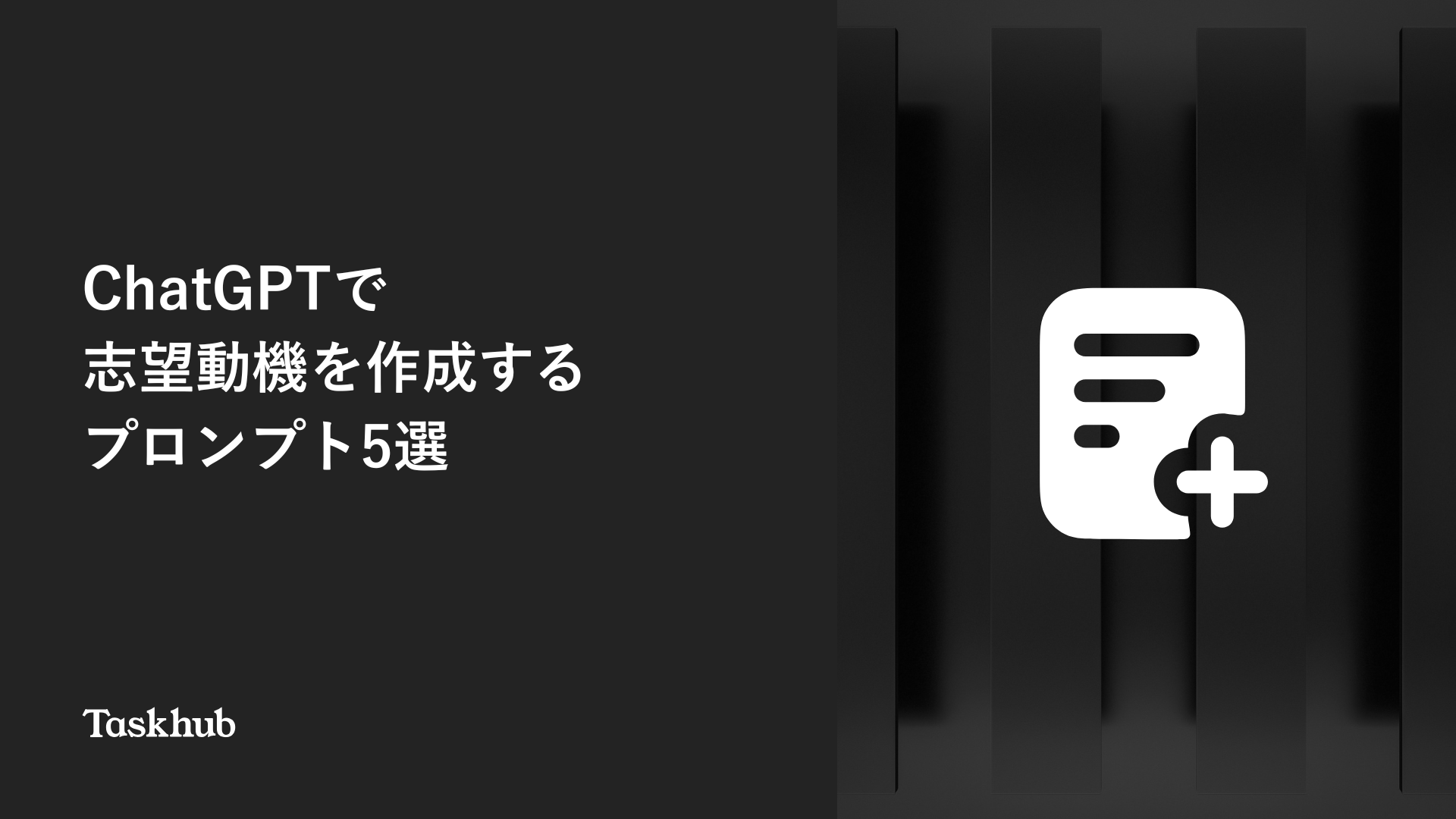「ChatGPT販売代理契約書って何だろう?どんな内容が含まれているの?」
「契約書のポイントや注意点を知りたいけど、専門的すぎてよくわからない…。」
こうした疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、ChatGPTの販売代理契約書に関する基本構成や重要な条項、契約時のチェックポイントについてわかりやすく解説します。
AI関連の法務支援を行う弊社が、実務で活用している契約書のポイントも含めてご紹介するので、
これから代理契約を結ぼうと考えている方にとって有益な内容となっています。
ぜひ最後まで読んで、安心して契約を進めるための知識を身につけてください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅販売代理店に対して日本法準拠の具体的かつ明確な販売代理契約書を作成したいとき→1つ目のプロンプトがおすすめ
✅投資家との間で権利義務やリスク回避を詳細に盛り込んだ投資契約書を作成したいとき→2つ目のプロンプトがおすすめ
✅企業間の技術協力や情報共有に関する相互協力契約書を簡潔かつ明確に作成したいとき→3つ目のプロンプトがおすすめ
✅フランチャイズ事業の加盟契約について、法令に準拠し公平かつ理解しやすい契約書を作成したいとき→4つ目のプロンプトがおすすめ
✅複数パートナーの出資・利益配分を明確に定めたパートナーシップ契約書を日本法準拠で作成したいとき→5つ目のプロンプトがおすすめ
ChatGPTで契約書作成をすることは可能?
ChatGPTは自然言語処理技術を活用し、多様な文章生成に長けています。契約書のドラフト作成も例外ではなく、一定の補助ツールとして利用できる面があります。
とはいえ、ChatGPTで契約書を「完璧に」作成できるかというと、現段階では慎重な判断が必要です。生成AIが持つ特性と限界を理解したうえで、正しく活用することが重要です。
ChatGPTの契約書ドラフト作成のメリット
ChatGPTは契約書の構成案や基本的な条文テンプレートを素早く提示できます。
たとえば、販売代理契約書であれば、代理権の範囲や報酬、秘密保持条項などの標準的な条項を網羅した文面を提案可能です。
これにより、ゼロから文章を作る手間が削減でき、法務担当者の工数短縮や社内理解促進の一助となるでしょう。
さらに、多彩なバリエーションを試せるので、条件調整や追加条項の検討も柔軟に進められます。
ChatGPTで契約書作成する際の課題とリスク
一方でChatGPTの生成内容はあくまで「参考例」であり、法的な正確性や最新の法改正の反映は保証されません。
特に販売代理契約書のような商慣習や業界ルールが複雑に絡む文書では、専門的な法的判断が不可欠です。
また、生成された文章は表現や用語の曖昧さが残るケースがあり、契約の解釈トラブルにつながるリスクも含んでいます。
加えて、機密情報をAIに入力する際の情報管理リスクも見逃せません。顧客名や具体的条件などは適切に伏せるか、専用の管理環境で利用することが求められます。
最終的には専門家のチェックを必須とする運用が鍵
総じて、ChatGPTは契約書作成の初期ドラフト作成やアイデア出しに有用なツールですが、その後の法務チェックや修正を省略できるものではありません。
実務ではAIが示す条文案をベースに、専門家がリスクを洗い出し、社内方針や最新法規制にも照らして最終版を完成させる体制が不可欠です。
このように、「ChatGPTによる契約書作成」はあくまで補助的な支援手段であることを認識し、法的責任や情報保護に配慮した運用ルールを整えることが成功のポイントと言えるでしょう。
ChatGPTで契約書作成をする3つのメリット
ChatGPTを活用して販売代理契約書の作成を行う最大の利点は、「効率性・コスト削減・品質向上」の3つを同時に実現できる点にあります。ここでは、とくに業務に直結する3つのメリットをわかりやすく解説します。
作成時間の大幅短縮と業務効率の向上
販売代理契約書を一から作成する場合、条項の検討や関連法令のチェックに多くの時間を要します。
しかし、ChatGPTを使えば、契約の基本条件や取引先の情報を入力するだけで、わずか数分でドラフトが自動生成されます。
そのため、担当者は細部の調整や取引先とのすり合わせに時間を集中させられ、契約書の完成までのリードタイムを大幅に短縮できます。
また、迅速な対応が可能になることで営業活動のスピードアップも期待できるでしょう。
コスト削減と専門家レビューの効率化
ChatGPTの初期ドラフトを専門の法律家にレビューしてもらうことで、問題点や不足条項を明確にした効率的なチェックが可能となります。
法律家は白紙から作成する必要がなく、精度の高い下地をもとに修正や最終確認に専念できるため、業務の手戻りが減少し外部コストの節約につながります。
さらに、修正後の文章をプロンプトに再入力すれば、迅速に改訂ドラフトを生成できるため、再レビューの負担も軽減されます。
このように、AIと専門家のハイブリッド活用は、品質を確保しながらコスト最適化を実現します。
条項の網羅性向上とナレッジ共有の促進
ChatGPTは大量の契約書データから学習しているため、取引のリスク管理に必須な条項、
たとえば秘密保持、損害賠償、代理権の範囲など、重要な条項を漏れなく盛り込むことができます。
また、生成した契約書のテンプレートやプロンプトは社内のナレッジベースに蓄積し、標準フォーマットとして再利用可能です。
これにより、担当者間のスキル差を埋め、契約書作成の属人化を防止します。
結果として、組織全体の契約書作成品質が上がり、継続的なリーガルコンプライアンス向上にも貢献します。
ChatGPTで契約書作成をする3つの注意点
ChatGPTを活用して販売代理契約書を作成する際には、単に文章生成ツールとしての利便性に注目が集まりがちですが、契約の法的効力を担保しつつ安全に運用するためには、特に次の三つのポイントに注意する必要があります。
自動生成文書を鵜呑みにせず必ず専門家チェックを行う
ChatGPTが作成する契約書の条文は、あくまで一般的なテンプレートや過去の事例に基づいた「参考案」に過ぎません。
販売代理契約特有の権利義務関係や業界慣行、最新の法改正を正確に反映している保証はなく、
そのまま承認すると契約トラブルや法的リスクの温床となります。
したがって完成後は法務担当者や弁護士に必ずレビューしてもらい、
責任範囲や報酬条件、契約解除条項といった重要部分は特に精査してください。
ここを怠ると、リスク管理や紛争対応が困難になる恐れがあります。
機密情報の入力に細心の注意を払うこと
ChatGPTはオンラインサービスの性質上、入力されたデータが外部に保存される可能性があります。
契約書作成時に取引先情報や価格、販売地域の詳細といった機密データを直接送信することは、
情報漏洩リスクを高める重大なミスです。
対応策として、機密性の高い情報は仮名または一般的な表現に変換するか、
ChatGPT Enterpriseのような社内管理型のプライベート環境で利用することが強く推奨されます。
また、社内の情報セキュリティ規定に合致させる運用が欠かせません。
契約書完成後の責任所在を明確にしておく
AIが生成した契約書は法的な専門家の意見ではありません。
最終的に契約の内容や条項に関する責任を負うのは、契約書を承認し交付する法人や個人です。
ChatGPTで作成した販売代理契約書を活用する場合、
社内の決裁プロセスやリーガルチェックのフローを厳格に維持し、
どのタイミングで誰が最終承認したか明確に記録しておくことが重要です。
こうした責任分界点の透明化は、万が一の紛争時に適切な対応ができる土台となります。
販売代理契約書作成においては、AIツールの利便性を最大限活かしつつ、
必ず専門家の関与と情報管理の徹底をセットで行うことが成功の鍵です。
契約書作成のプロンプトを作成する際に考慮すべき3つのポイント
ChatGPTを活用して販売代理契約書を作成する際は、AIの特性を踏まえた上で、正確かつ効率的に文書を仕上げることが求められます。
特に法的なリスクを避けるためには、契約の目的や範囲を明確に示し、必要な条項を過不足なく含めることが肝要です。
ここでは、ChatGPTで販売代理契約書を作成するときに押さえるべき3つのポイントを詳しく解説します。
契約対象や役割分担を具体的に記載する
販売代理契約書作成時には、販売商品やサービスの詳細、代理店の権限範囲を一文で具体的に示しましょう。
たとえば、「ChatGPT搭載AIツールの日本国内における独占販売を担当し、販売価格はメーカー指定の基準価格に準ずる」など、対象や役割を明確に伝えることで、
ChatGPTは適切な条項構成を自動で提案しやすくなります。
曖昧な表現は契約リスクや解釈の違いを生みやすいため避けることが重要です。
必須条項を漏れなく指示しチェックリスト形式で明示する
AIが省略しがちな条項を防ぐため、再委託禁止、秘密保持、契約期間、解約条件、損害賠償範囲など、必ず含めるべき条項をプロンプト内にチェックリスト形式で列挙しましょう。
各条項に簡単な説明を添えると、より適切な文言や条文をChatGPTが生成しやすくなります。
このような明示的な指示は、契約内容の網羅性を担保し、修正工数を抑える効果も期待できます。
契約書の形式や文体、レビュー基準を詳細に指定する
契約書は法律専門家による確認が必須です。
AI生成文書の質を高めるために、「日本法準拠であること」「誤解を避けるため正式用語を統一」「条番号は連番で記載」「堅苦しすぎず読みやすい文体」など、
細やかな書式や文体の指示を前もって与えましょう。
また、レビュー段階でチェックすべきポイントも合わせて伝えると、
初稿の完成度が向上し、契約締結までの時間短縮につながります。
プロンプト1:販売代理契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは販売代理契約作成専門のリーガルAIです。以下の要件をもとに日本法に準拠した販売代理契約書案を作成してください。
#制約条件
・契約書は条文形式で作成すること
・契約の目的、代理店の権限、契約期間、報酬・手数料、秘密保持、契約解除、紛争解決など基本的かつ重要な条項を含めること
・曖昧な表現は避け、具体的かつ明確な文章とすること
・法律用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で記載すること
・日本の商習慣や関連法令(商法、民法等)に準拠して作成すること
#入力情報
・販売代理の対象商品
・契約期間(開始日と終了日または期間)
・代理店の販売権限(独占・非独占の指定)
・報酬体系(歩合率など)
・特別な条件や要望(あれば)
#出力内容
販売代理契約書の全文(条文形式)
販売代理契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の内容確認:販売代理契約作成専門のリーガルAIとして、日本法に準拠した契約書を作成することを指示しているか
✅「#制約条件」の遵守:条文形式・明確な文章・法律用語の正確使用など、指定の条件を漏れなく反映しているか
✅「#入力情報」の具体性確認:対象商品や契約期間、販売権限など必須情報がすべて入力されているかチェックすること
このプロンプトは日本法に基づいた販売代理契約書のドラフト作成に適しています。販売代理店と企業間で契約締結時に、条文形式で明確かつ正確な契約書を手早く作成したい場面で活用可能です。
特徴として、「契約の目的」「権限範囲」「契約期間」など重要条項を網羅しつつ、曖昧さを排除して具体的な表現を心掛けています。これにより法律用語の誤用を防ぎ、契約の信頼性を高める工夫がなされています。
実務での活用により、契約書作成にかかる初期ドラフト作成時間を数時間から数十分に短縮でき、専門家への相談前の面倒な下準備を大幅に省けます。
入力例
#命令
あなたは販売代理契約作成専門のリーガルAIです。以下の要件をもとに日本法に準拠した販売代理契約書案を作成してください。
#制約条件
・契約書は条文形式で作成すること
・契約の目的、代理店の権限、契約期間、報酬・手数料、秘密保持、契約解除、紛争解決など基本的かつ重要な条項を含めること
・曖昧な表現は避け、具体的かつ明確な文章とすること
・法律用語は正確に用い、文章は簡潔な常体で記載すること
・日本の商習慣や関連法令(商法、民法等)に準拠して作成すること
#入力情報
・販売代理の対象商品:電子機器(スマートフォン及び関連アクセサリー)
・契約期間:2024年7月1日から2026年6月30日までの2年間
・代理店の販売権限:非独占販売権
・報酬体系:売上高の10%の歩合制報酬
・特別な条件や要望:契約期間中、代理店は商品知識向上のため年2回の研修を受ける義務を負う
#出力内容
販売代理契約書の全文(条文形式)
今回は、電子機器(スマートフォン及び関連アクセサリー)の販売代理契約書のドラフト作成を行うためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 販売代理の対象商品を「電子機器(スマートフォン及び関連アクセサリー)」
- 契約期間を「2024年7月1日から2026年6月30日までの2年間」
- 代理店の販売権限を「非独占販売権」
- 報酬体系を「売上高の10%の歩合制報酬」
- 特別な条件として「契約期間中、代理店は商品知識向上のため年2回の研修を受ける義務を負う」
といった内容を入力しました。
このように、対象商品や期間、権限、報酬体系、特別条件といった具体的な情報を詳細に入力することで、必要とする販売代理契約書案を日本法に準拠して正確かつ明確に作成できます。
また、ポイントごとに改行を入れることで見やすく、契約書の各条文に対応する内容が確認しやすいため、後からの修正や調整も容易になります。
実行結果(GPT-4o)
販売代理契約書
第1条(目的)
甲(委託者)は、乙(代理店)に対し、甲が製造または販売する電子機器(スマートフォン及び関連アクセサリー。以下「本商品」という)の販売を代理させることを目的として、本契約を締結する。
第2条(代理権)
乙に付与する販売権限は非独占的なものであり、甲は他の者にも本商品の販売代理権を付与できるものとする。乙は甲の指示に従い誠実に販売活動を行うものとする。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、2024年7月1日から2026年6月30日までの2年間とする。
第4条(報酬)
1. 乙の報酬は、本商品に係る乙の売上高の10%を基本歩合制とする。
2. 売上高は、本商品の甲への代金支払い済みの額を基準とする。
3. 報酬の支払時期および方法は、甲と乙の別途合意による。
第5条(研修受講義務)
乙は、本商品の知識及び販売技術向上のため、契約期間中に年2回甲の実施する研修を受講する義務を負う。
第6条(秘密保持)
乙は、本契約に関して知り得た甲の技術情報、顧客情報その他営業上の秘密を第三者に漏洩してはならない。本条の義務は契約終了後も存続する。
第7条(契約解除)
1. 甲および乙は、相手方が本契約に違反し、書面で催告した後30日以内に是正しない場合、本契約を解除できる。
2. 甲は、乙が法令に違反した場合または信用を著しく損なう行為をした場合、催告なく直ちに本契約を解除できる。
3. 契約解除により発生する損害賠償請求は、民法その他の法令の定めるところによる。
第8条(紛争解決)
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第9条(協議解決)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決する。
以上、本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。
2024年7月1日
甲(委託者)
住所:
氏名:
署名:
乙(代理店)
住所:
氏名:
署名:
この販売代理契約書は、電子機器の販売に関わる基本的な契約内容が網羅されており、明確かつ実務に即した文言で構成されている点が評価できます。
特に、代理権が非独占的であることや、報酬の歩合制など、双方の権利義務が具体的に規定されているため、トラブル防止に寄与するでしょう。
また、研修受講義務や秘密保持の条項も含まれており、販売品質の維持や情報管理にも配慮されていることが窺えます。
契約解除の条件や紛争解決の管轄裁判所も明記されているため、万一の際の対応がスムーズに行える点も実務的です。
ただし、報酬の支払時期や方法が別途合意となっているため、具体的な取り決めを別文書で詳細化する必要があります。
全体としては、基本的な条項がバランス良く盛り込まれており、中小企業の代理販売契約書として十分活用可能な案と感じました。
プロンプト2:投資契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは投資契約書作成の専門家AIです。以下の要件をもとに、投資契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に基づき、法的に有効かつ実務的に適切な契約書を作成すること
・文章は正式かつ明確な常体で記述すること
・必要に応じて条項を体系的に分け、条番号・条文名を付けること
・リスク回避や双方の権利義務のバランスを考慮した内容とすること
・各条項は具体的かつ詳細に記述し、曖昧な表現を避けること
・専門用語は正確に用いること
#入力情報(例)
・投資の目的、金額、払込方法
・株式または持分の種類・割合
・投資家の権利(優先株・議決権・配当・開示請求権など)
・契約期間および解除条件
・秘密保持義務
・その他必要と思われる条項
#出力内容
投資契約書全文(条番号・条文名付き)
投資契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の理解:投資契約書作成の専門家AIとして、法的かつ実務的に適切な契約書を全文作成すること
✅「#制約条件」の適用:日本法準拠・明確な常体・体系的な条文付与・リスク回避と権利義務のバランス・具体的詳細記述・専門用語の正確使用を厳守すること
✅「#入力情報」の確認:投資の目的・金額・払込方法、株式種類・割合、投資家の権利、契約期間・解除条件、秘密保持義務など必要情報が漏れなく反映されていること
このプロンプトは日本法に基づく投資契約書を専門的かつ体系的に作成する際に活用します。
投資金額や株式の種類、投資家の権利など具体的な要件を入力するだけで、法的に有効かつ明確な全文ドラフトが得られます。
条番号や条文名の自動付与により、構造化された文書が整い、曖昧表現を排除する工夫も秀逸です。
このため、法律専門家の初期ドラフト作成工数を大幅に削減でき、通常数時間を要する作業を数分程度に短縮可能です。
入力例
#命令
あなたは投資契約書作成の専門家AIです。以下の要件をもとに、投資契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に基づき、法的に有効かつ実務的に適切な契約書を作成すること
・文章は正式かつ明確な常体で記述すること
・必要に応じて条項を体系的に分け、条番号・条文名を付けること
・リスク回避や双方の権利義務のバランスを考慮した内容とすること
・各条項は具体的かつ詳細に記述し、曖昧な表現を避けること
・専門用語は正確に用いること
#入力情報
・投資の目的:新規事業開発資金としての出資
・投資金額:金5000万円
・払込方法:契約締結後30日以内に指定口座へ一括払込
・株式の種類・割合:第三者割当増資による普通株式の発行で発行済株式総数の10%相当
・投資家の権利:議決権付与、普通配当権、四半期ごとの財務状況の開示請求権、株主総会招集請求権
・契約期間および解除条件:契約締結日から5年間有効、期間中重大な契約違反があった場合に解除可能
・秘密保持義務:本契約に関わる一切の情報を第三者に開示しない義務を双方に課す
・その他条項:紛争解決のため東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること
#出力内容
投資契約書全文(条番号・条文名付き)
今回は、新規事業開発資金として金5000万円を第三者割当増資により普通株式の発行で調達する投資契約書の全文作成を依頼するためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 投資の目的を「新規事業開発資金としての出資」
- 投資金額を「金5000万円」
- 払込方法を「契約締結後30日以内に指定口座へ一括払込」
- 株式の種類・割合を「第三者割当増資による普通株式の発行で発行済株式総数の10%相当」
- 投資家の権利を「議決権付与、普通配当権、四半期ごとの財務状況の開示請求権、株主総会招集請求権」
- 契約期間および解除条件を「契約締結日から5年間有効、期間中重大な契約違反があった場合に解除可能」
- 秘密保持義務を「本契約に関わる一切の情報を第三者に開示しない義務を双方に課す」
- 紛争解決を「東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること」
といった具体的な要件を入力しました。
このように詳細かつ明確に条件を指定することで、法的に有効かつ実務的に適切な投資契約書の全文が生成されます。
また、条番号や条文名を付け体系的に構成することで、契約書の内容把握や修正作業が円滑になり、双方の権利義務のバランスやリスク回避が適切に反映されます。
なお、改行を適宜挟むことで視認性が向上し、長文であっても条文ごとの要点を容易に把握できるため、実務上の利便性が高まる点も重要です。
実行結果(GPT-4o)
投資契約書
第1条(目的)
本契約は、株式会社〇〇(以下「甲」という。)が新規事業開発資金の調達を目的として、株式会社△△(以下「乙」という。)に対し第三者割当増資により普通株式を発行し、乙がこれを引き受けることに関する権利義務を定めることを目的とする。
第2条(出資金額および払込方法)
1. 乙は、本契約に基づき、金5,000万円(以下「出資金」という。)を甲に出資する。
2. 乙は、契約締結日から30日以内に、甲が指定する銀行口座へ出資金を一括して払込むものとする。
3. 出資金の払込が遅延した場合、乙は甲に対し年率〇%(具体的利率は双方協議のうえ決定)の遅延損害金を支払うものとする。
第3条(株式の種類および割合)
1. 甲は、第三者割当増資により普通株式を発行し、乙はこれを引き受ける。
2. 出資により発行される普通株式の数は、甲の発行済株式総数に対し10%相当とし、増資後の株主構成に反映されるものとする。
3. 甲は、株式発行に関する法的手続及び会社法上の義務を誠実に履行するものとする。
第4条(投資家の権利)
1. 乙は、出資により取得した普通株式に対し、議決権を含む株主権を有する。
2. 乙は、普通配当を受ける権利を有し、甲に対して公平な配当の実施を請求できる。
3. 乙は、四半期ごとに甲の財務状況の開示を請求する権利を有する。甲はこれに応じ、適時かつ正確な情報を開示しなければならない。
4. 乙は、会社法第298条に基づき株主総会の招集を請求する権利を有し、その請求が正当な理由に基づく場合、甲は速やかに招集手続きを行うものとする。
第5条(契約期間および解除)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から起算して5年間とする。
2. 有効期間中に、いずれかの当事者が本契約に関し重大な契約違反をした場合、相手方は書面による通知のうえ、本契約を解除することができる。
3. 解除の通知後、相当期間を定めて是正の機会を与えたにもかかわらず違反が是正されない場合、解除の効力を生じるものとする。
4. 前項に基づく解除の際、既に払込まれた出資金の返還は原則として行わないものとする。
第6条(秘密保持義務)
1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た一切の情報(技術情報、営業情報、財務情報等を含むがこれに限らない)について、第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 秘密情報は、本契約の有効期間中および終了後も引き続き秘密保持の対象とする。
3. 法令に基づく開示義務が生じた場合、開示当事者は事前に相手方へ書面で通知し、必要最小限の範囲で開示するものとする。
第7条(その他条項)
1. 本契約に関する紛争が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
2. 前項の協議により解決しない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約の変更または追加は、書面による双方の合意により行うものとする。
4. 本契約の条項の一部が法令により無効又は執行不能とされた場合でも、その他の条項の効力はこれに影響を受けないものとする。
以上、契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)
株式会社〇〇
住所:
代表取締役 〇〇〇〇 印
(乙)
株式会社△△
住所:
代表取締役 △△△△ 印
この投資契約書の出力結果は、基本的な構成が非常に整っており、条項ごとに明確で具体的な内容が記載されています。
特に、出資金額の払込方法や遅延損害金の規定、第4条の投資家の権利に関する詳細な記述は、実務上のトラブル防止に有効と考えられます。これにより、投資家と会社双方の権利義務が明確化されている点に好感が持てます。
また、契約期間や解除に関する第5条の規定が丁寧に設けられていることで、契約終了時のリスク管理にも配慮がなされている印象です。
秘密保持義務についても継続的な守秘義務を定めているため、情報漏洩リスクへの対応が十分に意識されていると言えます。
一方で、遅延損害金の具体的な利率や契約解除の「重大な契約違反」の定義については、双方が合意しやすいようより具体的な基準を補足すると、実務運用がスムーズになるでしょう。
さらに、第7条の紛争解決条項においては、協議による解決を優先しつつも、地方裁判所の専属的合意管轄を明記することで法的安定性が確保されている点が評価できます。
総じて、本契約書は新規事業開発の投資を目的とした第三者割当増資に関して必要な条項がバランス良く網羅されており、実務に即した信頼性の高い内容だと感じました。
ただし、今後の実際の契約締結前には、具体的な数値の設定や契約主体の詳細確認など細部のカスタマイズを適宜行うことが重要です。
プロンプト3:相互協力契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIです。以下の要件をもとに、相互協力契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠した内容とする
・条文ごとに番号とタイトルを明記する
・条文は法律用語を適切に用いて簡潔かつ明確に表現する
・重要な契約項目(目的、協力内容、役割分担、秘密保持、契約期間、損害賠償、契約解除など)を必ず含める
・曖昧な表現を避け具体的かつ実務的に記述する
・必要に応じて条文の注釈や解説は加えない
・出力は契約書本文のみとし、前置きや説明文は一切不要
#入力情報(例)
・契約の目的:両者の技術協力と情報共有
・役割分担例:A社は技術提供、B社は市場開拓及び販売支援
・契約期間:契約締結日から1年間(自動更新可)
・秘密保持の範囲
・損害賠償の範囲及び免責事項
・解除条件
#出力内容
<ここに相互協力契約書全文を作成してください>
相互協力契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の理解:契約書作成専門の法務AIとして全文作成することを確認
✅「#制約条件」の遵守:日本法準拠、条文番号・タイトル明記、専門用語使用など全ての条件を満たすか確認
✅「#入力情報」の正確な反映:目的、役割分担、秘密保持、損害賠償、解除条件など必須項目を漏れなく盛り込むか確認
このプロンプトは、日本法に準拠した相互協力契約書を簡潔かつ明確に作成したい際に活用できます。
契約の目的や役割分担、秘密保持など重要な項目をもれなく反映し、条文ごとに番号とタイトルを付けることで構造化されています。
「曖昧な表現を避け、法律用語を適切に用いる」点が工夫されており、実務的かつ信頼性の高い契約書のドラフト作成に適しています。
これにより、契約書起草にかかる工数を大幅に削減し、通常数時間かかる作業を数分程度に短縮可能です。
入力例
#命令
あなたは契約書作成専門の法務AIです。以下の要件をもとに、相互協力契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠した内容とする
・条文ごとに番号とタイトルを明記する
・条文は法律用語を適切に用いて簡潔かつ明確に表現する
・重要な契約項目(目的、協力内容、役割分担、秘密保持、契約期間、損害賠償、契約解除など)を必ず含める
・曖昧な表現を避け具体的かつ実務的に記述する
・必要に応じて条文の注釈や解説は加えない
・出力は契約書本文のみとし、前置きや説明文は一切不要
#入力情報(例)
・契約の目的:両者の技術協力と情報共有
・役割分担例:A社は技術提供、B社は市場開拓及び販売支援
・契約期間:契約締結日から1年間(自動更新可)
・秘密保持の範囲:本契約に関連して知り得た相手方の業務上の機密情報
・損害賠償の範囲及び免責事項:両当事者は故意または重過失による損害に限り賠償責任を負うものとし、間接損害、特別損害については一切責任を負わない
・解除条件:相手方が本契約に違反し、相当期間を定めた書面による是正要求に応じない場合、本契約を解除できること
#出力内容
相互協力契約書
第1条(目的)
本契約は、甲及び乙が相互に技術協力及び情報共有を行うことにより、両者の業務発展を図ることを目的とする。
第2条(協力内容)
甲は技術提供を行い、乙は当該技術を用いた市場開拓及び販売支援を行うものとする。両者は相互に必要な情報を適時提供し、協力関係を維持する。
第3条(役割分担)
1. 甲は以下の役割を担う。
(1) 技術に関する資料及びノウハウの提供
(2) 技術支援及びアドバイスの実施
2. 乙は以下の役割を担う。
(1) 市場調査及びマーケティング活動の実施
(2) 製品の販売支援及び顧客対応
第4条(秘密保持)
1. 両当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の機密情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示しないものとする。
2. 秘密情報は、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。
3. 前項の義務は、本契約終了後も3年間継続する。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結日より1年間とし、期間満了の30日前までに書面による異議申し立てがない限り、さらに1年間自動更新されるものとする。
第6条(損害賠償)
1. 両当事者は、故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合、その直接かつ現実の損害について賠償責任を負うものとする。
2. 間接損害、特別損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
第7条(契約解除)
1. いずれかの当事者が本契約の条項に違反し、相手方からの書面による是正要求を受けた後、合理的な期間内に是正しない場合、相手方は本契約を解除することができる。
2. 前項の場合を除き、いずれの当事者も契約期間満了前に書面により30日前の通知をもって契約を解除することができる。
第8条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各1通を保有する。
(甲)
会社名:株式会社A(以下「甲」という)
代表者:__________
(乙)
会社名:株式会社B(以下「乙」という)
代表者:__________
契約締結日:__年__月__日今回は、株式会社Aと株式会社Bの相互協力契約書の全文作成を依頼するためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約種別を「相互協力契約」
- 契約の目的を「両者の技術協力と情報共有」
- 役割分担として「A社は技術提供、B社は市場開拓及び販売支援」
- 契約期間は「契約締結日から1年間(自動更新あり)」
- 秘密保持の範囲を「本契約に関連して知り得た相手方の業務上の機密情報」
- 損害賠償は「故意または重過失の場合に限定し、間接損害等の責任は負わない」
- 解除条件は「違反があり書面による是正要求に応じない場合に解除可能」
- 準拠法を「日本法」
といった重要な契約項目を詳細に入力しました。
このように具体的かつ実務的な内容を明確に指定することで、法律用語を適切に用いたかつ実務で利用可能な契約書全文を生成できます。
また、条文ごとに番号とタイトルをつけ、文ごとに適宜改行を入れているため、契約書の内容が読みやすく、契約書ドラフトの検討や修正が容易になります。
実行結果(GPT-4o)
相互協力契約書
第1条(目的)
本契約は、甲及び乙が相互に技術協力及び情報共有を行うことにより、両者の業務発展を図ることを目的とする。
第2条(協力内容)
甲は技術提供を行い、乙は当該技術を用いた市場開拓及び販売支援を行うものとする。両者は相互に必要な情報を適時提供し、協力関係を維持する。
第3条(役割分担)
1. 甲は以下の役割を担う。
(1) 技術に関する資料及びノウハウの提供
(2) 技術支援及びアドバイスの実施
2. 乙は以下の役割を担う。
(1) 市場調査及びマーケティング活動の実施
(2) 製品の販売支援及び顧客対応
第4条(秘密保持)
1. 両当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の機密情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示しないものとする。
2. 秘密情報は、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。
3. 前項の義務は、本契約終了後も3年間継続する。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結日より1年間とし、期間満了の30日前までに書面による異議申し立てがない限り、さらに1年間自動更新されるものとする。
第6条(損害賠償)
1. 両当事者は、故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合、その直接かつ現実の損害について賠償責任を負うものとする。
2. 間接損害、特別損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
第7条(契約解除)
1. いずれかの当事者が本契約の条項に違反し、相手方からの書面による是正要求を受けた後、合理的な期間内に是正しない場合、相手方は本契約を解除することができる。
2. 前項の場合を除き、いずれの当事者も契約期間満了前に書面により30日前の通知をもって契約を解除することができる。
第8条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各1通を保有する。
(甲)
会社名:株式会社A(以下「甲」という)
代表者:__________
(乙)
会社名:株式会社B(以下「乙」という)
代表者:__________
契約締結日:2024年6月1日この契約書の出力結果は、ビジネスパートナー間での相互協力関係を明確に規定しており、非常に実務的で包括的な内容になっています。
条項ごとに役割分担や秘密保持、契約解除の条件など重要なポイントが整理されており、双方の責任範囲とリスクが明確化されています。
特に第4条の秘密保持については、契約終了後も3年間の継続義務を定めている点が信頼関係を堅持する上で有効です。
また、第5条の自動更新条項は契約の継続運用を見据えた柔軟な運用を可能にしており、実務上ありがたい内容です。
一方で、第6条の損害賠償については直接損害に限定し、間接損害や逸失利益を免責としているため、損害リスクを過度に負わない配慮が見られます。
これは契約当事者双方にとって、安全装置として働き、無用な訴訟リスクを回避できる構造といえます。
全体として、ビジネスの円滑な推進とリスク管理の両面をバランスよく盛り込んでおり、実務導入に適した完成度の高い契約書です。
今後の運用にあたっては、条項の内容を双方が再確認し、必要に応じて条文の微調整を行うことで、より確実なパートナーシップ形成に寄与できるでしょう。
プロンプト4:フランチャイズ契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたはフランチャイズ契約書作成に特化した法律専門AIです。以下の要件を踏まえ、フランチャイズ契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠し、最新の関連法令に基づいた条文とする
・主要な条項(契約期間、加盟料、ロイヤリティ、営業区域の制限、契約解除、秘密保持、知的財産権、損害賠償、紛争解決など)を必ず含む
・条文は明確かつ具体的に記載し、曖昧な表現を避ける
・条文ごとに見出し(条文名)を付け、条番号を振る
・専門用語は正確に使用し、法律用語に不慣れなユーザーでも理解しやすい日本語で記述する
・契約者双方の権利義務を公平に記述し、トラブル防止を目的とする内容とする
#入力情報(例)
・加盟者の役割や義務
・本部のサポート内容
・ロイヤリティの計算方法
・契約期間及び更新条件
・契約解除の条件と手続き
・営業地域の独占・制限の有無
・秘密保持義務の範囲
・知的財産権の扱い
・損害賠償責任の範囲
・紛争解決方法
#出力内容
フランチャイズ契約書全文(条文形式)
フランチャイズ契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:フランチャイズ契約書作成に特化した法律専門AIとしての役割を明確に設定
✅「#制約条件」の厳守:日本法準拠や主要条項の必須記載、条文の明確性・具体性を必ず守る
✅「#入力情報」の網羅:加盟者・本部の役割や契約詳細など必要情報が漏れなく含まれているか確認
このプロンプトは日本法に準拠したフランチャイズ契約書を全文作成するためのものです。契約書のドラフト作成や契約条件の整理を効率良く行いたい場面で特に役立ちます。
「#入力情報」に加盟者の義務やロイヤリティ計算方法など具体的な内容を反映でき、条番号や見出し付きの明確な条文形式で出力される点が工夫されています。法律用語を正確かつ平易に表現するため、法務初心者でも理解しやすい内容に仕上がります。
これにより、契約書作成にかかる工数を大幅に削減でき、通常数日かかる文案検討が数時間で完了することも期待できます。
入力例
#命令
あなたはフランチャイズ契約書作成に特化した法律専門AIです。以下の要件を踏まえ、フランチャイズ契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠し、最新の関連法令に基づいた条文とする
・主要な条項(契約期間、加盟料、ロイヤリティ、営業区域の制限、契約解除、秘密保持、知的財産権、損害賠償、紛争解決など)を必ず含む
・条文は明確かつ具体的に記載し、曖昧な表現を避ける
・条文ごとに見出し(条文名)を付け、条番号を振る
・専門用語は正確に使用し、法律用語に不慣れなユーザーでも理解しやすい日本語で記述する
・契約者双方の権利義務を公平に記述し、トラブル防止を目的とする内容とする
#入力情報(例)
・加盟者の役割や義務:店舗運営の実施、販売方針の遵守、従業員教育の実施、報告義務の遂行
・本部のサポート内容:研修の提供、商品供給、広告宣伝の支援、経営指導
・ロイヤリティの計算方法:月間売上高の5%(税抜)を毎月末日までに支払う
・契約期間及び更新条件:初回契約期間3年間、更新は双方合意の上1年ごとに自動更新
・契約解除の条件と手続き:債務不履行、法令違反、契約違反があった場合、30日前の書面通知により解除可能
・営業地域の独占・制限の有無:加盟店ごとに営業区域を設定し、本部は同区域内で新たな加盟店を認めない
・秘密保持義務の範囲:契約期間中及び契約終了後3年間、本部及び加盟店の営業秘密を第三者に漏洩禁止
・知的財産権の扱い:本部の商標、ロゴ、ノウハウ等の使用権は契約期間内に限定し、契約終了後は使用停止
・損害賠償責任の範囲:故意または重大な過失による損害についてのみ賠償責任を負う
・紛争解決方法:東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする
#出力内容
フランチャイズ契約書全文(条文形式)
今回は、フランチャイズ契約書の全文作成を目的としたプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約書の種類を「フランチャイズ契約書」
- 加盟者の役割や義務を「店舗運営の実施、販売方針の遵守、従業員教育の実施、報告義務の遂行」
- 本部のサポート内容を「研修の提供、商品供給、広告宣伝の支援、経営指導」
- ロイヤリティの計算方法を「月間売上高の5%(税抜)を毎月末日までに支払う」
- 契約期間及び更新条件を「初回契約期間3年間、更新は双方合意の上1年ごとに自動更新」
- 契約解除の条件と手続きを「債務不履行、法令違反、契約違反があった場合、30日前の書面通知により解除可能」
- 営業地域の独占・制限の有無を「加盟店ごとに営業区域を設定し、本部は同区域内で新たな加盟店を認めない」
- 秘密保持義務の範囲を「契約期間中及び契約終了後3年間、本部及び加盟店の営業秘密を第三者に漏洩禁止」
- 知的財産権の扱いを「本部の商標、ロゴ、ノウハウ等の使用権は契約期間内に限定し、契約終了後は使用停止」
- 損害賠償責任の範囲を「故意または重大な過失による損害についてのみ賠償責任を負う」
- 紛争解決方法を「東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」
といった情報を入力しました。
このように具体的かつ詳細な条項を指定することで、法律専門AIは日本法に準拠した明確で公平な条文に基づくフランチャイズ契約書のドラフトを生成します。
また、文中に適切な改行を挟むことで読みやすさが向上し、項目ごとの確認や修正も容易になります。
これによりユーザーは実務で直ちに利用できる高品質な契約書を短時間で作成可能となります。
実行結果(GPT-4o)
# フランチャイズ契約書
本契約書は、以下の条件に基づき、株式会社○○(以下「本部」という。)と加盟者□□(以下「加盟店」という。)との間でフランチャイズ契約(以下「本契約」という。)を締結する。
## 第1条(契約の目的)
本契約は、本部が有する商標、ロゴ、営業ノウハウ等の知的財産権及び経営指導を加盟店に供与し、加盟店がそれを用いて店舗運営を行うことにより、双方法人の利益を図ることを目的とする。
## 第2条(契約期間および更新)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から起算して3年間とする。
2. 契約期間満了の30日前までにいずれかが書面による更新拒絶の通知をしない限り、本契約は1年間の期間で自動更新されるものとし、以降も同様とする。
3. 更新の際には、双方が協議の上、必要に応じて契約条件を見直すことができる。
## 第3条(加盟店の役割および義務)
加盟店は、以下を誠実に履行するものとする。
1. 本部の定める販売方針及び店舗運営マニュアルに従い、店舗運営を実施すること。
2. 従業員に対し適切な教育と指導を行うこと。
3. 本部に対し、求められた営業報告や経営状況報告を適時かつ正確に提出すること。
4. 法令および公序良俗に反する行為を行わないこと。
## 第4条(本部のサポート内容)
本部は加盟店に対し、次のサポートを提供するものとする。
1. 開業前及び開業後の研修の実施。
2. 商品の安定的かつ適時な供給。
3. 広告宣伝活動の支援。
4. 経営に関する指導および助言。
## 第5条(加盟料)
加盟店は、本契約締結時に本部指定の加盟料として金○○万円を支払うものとする。
## 第6条(ロイヤリティ)
加盟店は、毎月の売上高(税抜)に基づき、その5%に相当する金額をロイヤリティとして当月末日までに本部指定の口座に支払うものとする。
## 第7条(営業区域の設定および制限)
1. 本契約に基づく営業区域は、別紙営業区域図に定める区域とする。
2. 本部は当該営業区域内において、加盟店の同意なく新たな加盟店の営業を認めないものとする。
3. 加盟店は、指定区域外での営業または移転を行う場合、事前に本部の書面承諾を得るものとする。
## 第8条(契約解除)
1. 本契約のいずれか一方が以下のいずれかに該当した場合、相手方は30日前に書面による通知を行うことで本契約を解除できる。
(1) 契約上の義務を履行しない債務不履行が継続した場合。
(2) 本契約または関連法令に違反した場合。
(3) 破産、民事再生その他支払不能状態に陥った場合。
2. 前項に基づく解除通知は、効力発生後も相手方に対して未履行の義務に関する責任を免除しない。
## 第9条(秘密保持)
1. 本契約期間中および契約終了後3年間、双方は相手方の営業秘密を第三者に開示・漏洩してはならない。
2. 営業秘密とは、本部および加盟店の営業上の技術上の情報、顧客情報その他本契約遂行上知り得た秘密情報をいう。
## 第10条(知的財産権の取り扱い)
1. 本部の商標、ロゴ、ノウハウ等の知的財産権は本部に帰属し、加盟店に対しては契約期間中に限り使用権を許諾する。
2. 契約終了時に加盟店は当該知的財産の使用を直ちに停止し、本部の指示に従いこれらの関連物件を返還または破棄するものとする。
## 第11条(損害賠償責任)
加盟店および本部は、相手方に対して故意または重大な過失によって損害を与えた場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとし、それ以外の責任は負わない。
## 第12条(紛争解決)
本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とし、誠実に協議の上解決を図るものとする。
## 第13条(その他)
1. 本契約の変更または追加は、書面にて双方の合意をもって行うものとする。
2. 本契約に定めのない事項は、日本法その他関連法令および商慣習に従って解決する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方が記名押印の上、各自1通を保持する。
令和○年○月○日
本部:株式会社○○
代表取締役 (署名)
加盟店:□□□□
(署名)
このフランチャイズ契約書は、基本的かつ重要な条項が網羅されており、双方の権利義務関係が明確に整理されています。
特に契約期間の自動更新規定や営業区域の設定による独占的営業権の保護、秘密保持義務の詳細な記述は、実務上非常に効果的な内容と言えます。
また、契約解除に関する条件も具体的であり、債務不履行や法令違反等の場合に明確に解除可能であることから、リスク管理の観点でも安心感があります。
一方で、ロイヤリティの支払い方法や額がシンプルに設定されているため、収益管理がしやすい反面、柔軟な交渉余地を持たせる条項があればより実態に即した運用が可能となるでしょう。
知的財産権の帰属や使用権許諾の範囲が契約期間中に限定されていることも、双方の権利保護において重要なポイントであり、契約終了時の取り扱いも明示している点は評価できます。
全体を通じて、実務での利用に十分耐えうる完成度がありますが、契約変更の手続きや紛争解決に関する合意管轄裁判所の指定が具体的に示されているため、契約後のトラブル回避にも配慮されています。
総じて、加盟店と本部の双方にとって公平で透明性の高いフランチャイズ契約書の見本として活用できる内容と感じました。
プロンプト5:パートナーシップ契約書作成をするプロンプト
#命令
あなたは契約書作成専門のリーガルAIです。以下の要件に基づき、パートナーシップ契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠して作成すること
・契約の目的、各パートナーの権利義務、出資額と負担割合、利益・損失の配分方法、期間、契約解除条件、機密保持条項、紛争解決方法を必ず含めること
・条文は明確かつ簡潔に記載し、専門用語を正しく用いること
・重要な条項については注釈や解説を付け加えず、契約書の形態(条文形式)のみで出力すること
・日本語の常体で記載すること
#入力情報(例)
パートナーはA社とB社。事業内容はWeb開発。出資比率はA社60%、B社40%。
#出力内容
パートナーシップ契約書(全文)
パートナーシップ契約書作成をするプロンプトの解説
✅「#命令」の確認:契約書作成専門のリーガルAIとして、パートナーシップ契約書を作成する指示が明確か確認
✅「#制約条件」の遵守:日本法準拠、必須条項の網羅、専門用語の正確な使用、条文形式の厳守、日本語常体の徹底をチェック
✅「#入力情報」の明確化:パートナー名、出資比率、事業内容など必要情報が具体的かを事前に確認
このプロンプトは、パートナーシップ契約書を日本法に基づいて一から作成したい場面で活用します。
契約の核心となる条項を漏れなくかつ明確に含める指示があり、専門用語も正しく使われるため、法律知識が浅くても質の高い契約書を得られます。
特に、「契約書の形態のみで出力する」点が工夫されており、余計な解説が省かれて即実務利用しやすいのも特徴です。
このプロンプトを使うことで、従来数時間かかっていたドラフト作成が数分に短縮され、工数削減効果は大きいと期待できます。
入力例
#命令
あなたは契約書作成専門のリーガルAIです。以下の要件に基づき、パートナーシップ契約書の全文を作成してください。
#制約条件
・日本法に準拠して作成すること
・契約の目的、各パートナーの権利義務、出資額と負担割合、利益・損失の配分方法、期間、契約解除条件、機密保持条項、紛争解決方法を必ず含めること
・条文は明確かつ簡潔に記載し、専門用語を正しく用いること
・重要な条項については注釈や解説を付け加えず、契約書の形態(条文形式)のみで出力すること
・日本語の常体で記載すること
#入力情報
パートナーはA社とB社。事業内容はWeb開発。出資比率はA社60%、B社40%。
#出力内容
パートナーシップ契約書(全文)今回は、パートナーシップ契約書の全文を作成するためのプロンプトを作成しました。
そのため、
- 契約種別を「パートナーシップ契約書」
- パートナーを「A社」と「B社」
- 事業内容を「Web開発」
- 出資比率を「A社60%、B社40%」
- 準拠法を「日本法」
といった情報を入力しています。
このように具体的な情報を明示することで、契約の目的や出資割合、権利義務、利益配分、機密保持、紛争解決方法など必要な条項を盛り込んだ契約書ドラフトを正確に生成できます。
また、条文形式で簡潔に記載し、日本語の常体を用いることで実務での利用を想定した品質を保っています。
さらに、2〜3文ごとに改行を入れることで見やすさを確保し、内容の確認や修正をしやすくしているのもポイントです。
以上のように入力情報と制約条件を適切に設定することが、目的に沿ったパートナーシップ契約書の生成に役立ちます。
実行結果(GPT-4o)
パートナーシップ契約書
第1条(契約の目的)
本契約は、株式会社A(以下「甲」という。)および株式会社B(以下「乙」という。)が共同でWeb開発事業を営むにあたり、両者の権利義務等を定めることを目的とする。
第2条(出資額および負担割合)
1.甲の出資額は全出資額の60%とし、乙の出資額は全出資額の40%とする。
2.出資は金銭をもって行い、それぞれの負担割合に応じて行う。
第3条(権利及び義務)
1.両パートナーは、事業の運営に関し互いに協力し、誠実に履行する義務を負う。
2.重要な経営判断については、両者の合意を必要とする。
3.出資比率に応じて、利益および損失の配分を受けるものとする。
第4条(利益・損失の配分)
事業から生じた利益および損失は、甲60%、乙40%の割合で按分し、それぞれに帰属する。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は締結日より2年間とし、期間満了の30日前までに書面による別段の意思表示がない場合、自動的に同一条件でさらに1年間延長されるものとする。
第6条(契約解除)
1.一方が本契約の条項に重大な違反をし、相当な期間を定めた是正要求にもかかわらず履行しない場合、他方は書面により本契約を解除できる。
2.甲および乙は、相手方に3か月前の書面通知をもって、本契約を解除することができる。
第7条(機密保持)
両者は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の機密情報を第三者に開示または漏洩してはならず、契約終了後も同様とする。
第8条(紛争解決)
本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。
2024年 月 日
甲:株式会社A
代表取締役 _________(署名)
乙:株式会社B
代表取締役 _________(署名)
このパートナーシップ契約書の作成結果は非常に明確かつ体系的であり、基本的な契約内容が過不足なく盛り込まれている点が好印象です。
各条項が番号付きで整理されており、特に出資額の割合や利益配分、契約解除の条件など、パートナー間の権利義務が具体的に定められているため、双方にとってのリスク回避に役立つ内容となっています。
また、契約期間の自動延長条項や機密保持義務、紛争解決手続きについても明記されているため、事業運営上の不確実性を低減できるでしょう。
ただし、改良の余地としては、契約解除に関する条項において「相当な期間を定めた是正要求」の具体的な期間設定や、利益分配のタイミングと方法に関する詳細を追記すると、さらなる明確化が図れます。
加えて、契約期間満了後の手続きや契約更新条件についても、より細かな規定があると双方の認識のズレを防げるでしょう。
総じて、この契約書は共同事業の基本的枠組みを確実に押さえているため、実務での利用に十分耐えうる内容と評価できます。
今後は事業内容の変更やスケールアップに合わせて、必要に応じた条項の追加や修正を検討すると良いでしょう。
ChatGPT販売代理契約書の作成に役立つプロンプト5選のまとめ
ChatGPTの販売代理契約書作成に悩む企業は多く、契約内容の不備やトラブル回避が課題となっています。そこで役立つのが、ChatGPT販売代理契約書の作成に特化したプロンプトです。
これらのプロンプトは、契約の基本条項や報酬体系、契約期間、解除条件などを漏れなく盛り込みやすく、スムーズに契約書の骨子を作成できます。
例えば、「契約条項のポイントを簡潔にまとめるプロンプト」や「代理店報酬の計算方法を明記するためのプロンプト」など、多彩な用途に対応可能です。
さらに、法的リスクを回避するための注意点や最新の法令情報を取り入れた案内も充実。
AIのおかげで、専門知識がなくても質の高い契約書作成が実現できます。
まずは、これらの有効な5つのプロンプトを使って、確実で効率的なChatGPT販売代理契約書作成を始めましょう。
契約トラブルを防ぎ、ビジネスをスムーズに進めるための強力な支援となるはずです。