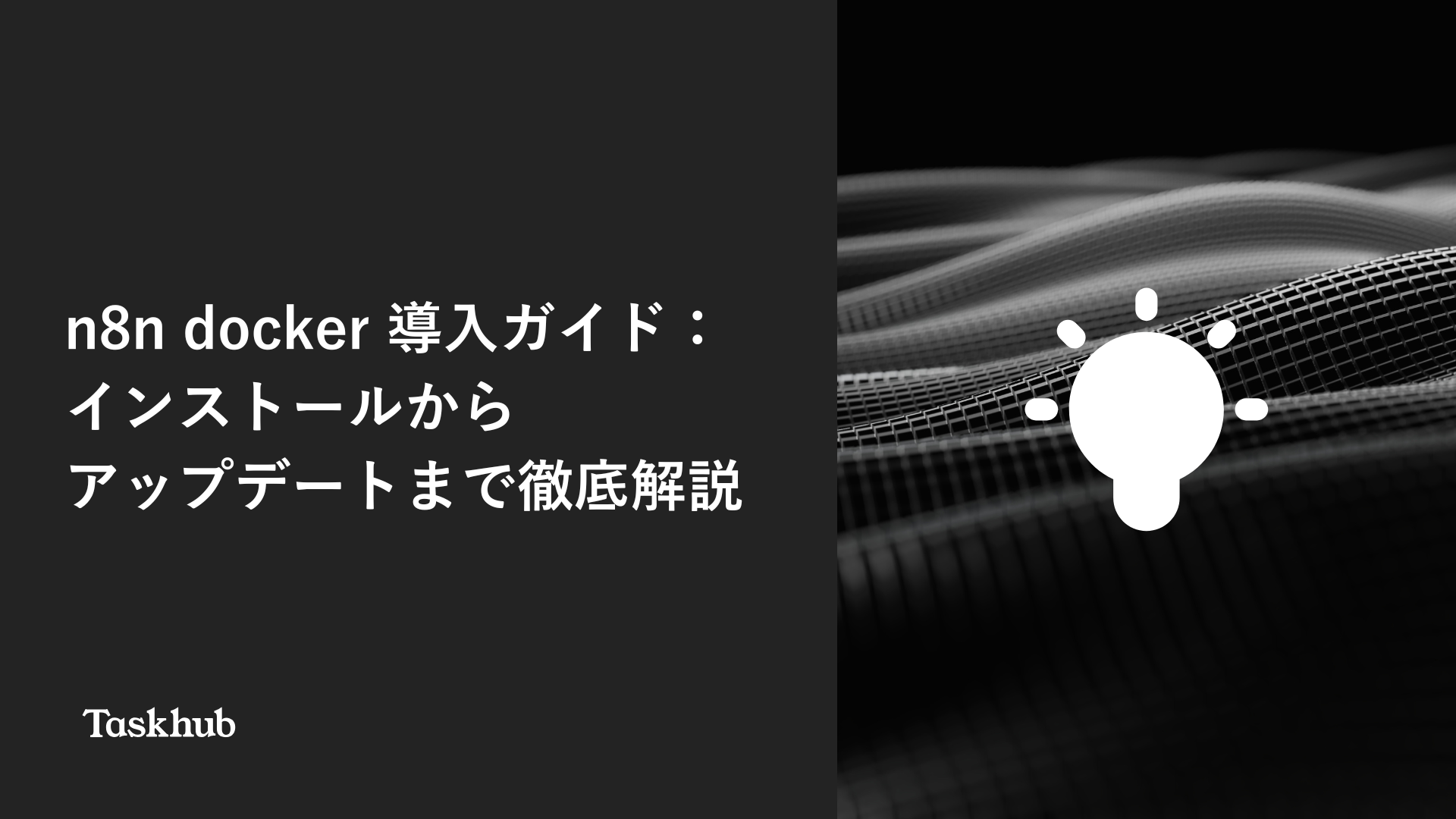「n8nをDockerで使いたいけど、設定が複雑そうで手が出せない…」
「n8n dockerのインストール方法は?データの永続化やアップデートはどうやるの?」
こういった悩みを持っていませんか?
n8nは強力なワークフロー自動化ツールですが、Dockerでのセルフホスト運用は、特にデータ管理やアップデートでつまずきやすいポイントがいくつかあります。
本記事では、n8n docker のインストール手順、特にdocker-composeを使った具体的な設定方法、安全なアップデート手順、そしてトラブルシューティングまでを徹底的に解説します。
この記事を読めば、n8n docker環境を安定して運用するための知識が身につくはずです。
n8nがどのようなツールなのか、詳細は以下の記事でも案内しています。合わせてご覧ください。
ぜひ最後までご覧ください。
n8nをDockerで動かすとは?n8n dockerの基本とメリットを解説
ここでは、n8nの基本的な機能と、なぜn8nをDocker(n8n docker)で動かすのが推奨されるのか、その主なメリットを解説します。
- n8nとは?ノーコードで使えるワークフロー自動化ツール
- なぜDocker(n8n docker)で実行するのか?3つのメリット
Dockerを利用することで、環境構築の手間を大幅に削減できるだけでなく、将来的な管理やアップデートも非常に簡単になります。
それでは、それぞれの詳細を見ていきましょう。
n8nとは?ノーコードで使えるワークフロー自動化ツール
n8n(エヌ・エイト・エヌ)は、オープンソースのワークフロー自動化ツールです。
「Zapier」や「IFTTT」といったSaaS型の自動化サービスとしばしば比較されますが、n8nはセルフホスト(自前のサーバー)で運用できる点が大きな特徴です。
ノーコード・ローコードのアプローチを採用しており、プログラミングの知識が少なくても、ノードと呼ばれる機能ブロックを線でつなぎ合わせることで、直感的にワークフローを構築できます。
例えば、「Gmailで特定のメールを受信したら、その添付ファイルをGoogle Driveに保存し、Slackに通知する」といった一連の作業を自動化できます。
対応しているサービス(ノード)は数百種類に及び、主要なWebサービスやデータベース、さらにはカスタムのHTTPリクエストやスクリプト実行も可能です。
セルフホストであるため、データが外部のサーバーを経由しない(オンプレミスで完結できる)セキュリティ面の利点や、実行回数に基づく課金を気にせず利用できるコスト面のメリットがあります。
こちらはn8nの機能や特徴について紹介している公式サイトです。 合わせてご覧ください。 https://n8n.io/
なぜDocker(n8n docker)で実行するのか?3つのメリット
n8nをセルフホストで実行する方法はいくつかありますが、その中でもDocker(n8n docker)を使った方法が最も一般的かつ推奨されています。
それには、主に3つの大きなメリットがあります。
第一に「環境構築の容易さ」です。
n8nはNode.jsや特定のデータベースなど、いくつかの依存関係を必要としますが、Dockerを使えば、必要なものがすべてパッケージングされた「Dockerイメージ」を利用できます。
これにより、複雑なインストール作業や依存関係の競合を心配することなく、数コマンドでn8nを起動できます。
第二に「環境の分離と再現性」です。
Dockerはコンテナという隔離された環境でn8nを実行します。
これにより、ホストマシン(サーバー)のOS環境を汚すことがありません。
また、設定ファイル(docker-compose.yml)さえあれば、誰でも同じ環境を素早く再現できます。
第三に「管理とアップデートの簡便さ」です。
データの永続化設定(後述)さえ適切に行えば、n8nのバージョンアップは非常に簡単です。
新しいイメージをダウンロードしてコンテナを再起動するだけで完了するため、運用負荷が大幅に軽減されます。
n8n docker 実行環境の準備
n8n docker を動かすためには、まずDocker環境を準備する必要があります。
ここでは、多くの開発者が利用するDocker Desktopのインストール方法について解説します。
- Docker Desktopのインストール手順(Windows/Mac)
Docker Desktopのインストール手順(Windows/Mac)
Docker Desktopは、WindowsやMacといったデスクトップOS上でDockerコンテナを簡単に利用できるようにするための公式アプリケーションです。
これには、Docker本体(Docker Engine)と、複数のコンテナを管理するためのDocker Composeが含まれています。
インストールの手順は非常にシンプルです。
まず、Dockerの公式サイト(docker.com)にアクセスし、ご自身のOS(WindowsまたはMac)に合ったDocker Desktopのインストーラーをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを実行し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
Windowsの場合は、WSL 2 (Windows Subsystem for Linux 2) のバックエンドを使用することが推奨されています。
インストール中にWSL 2の有効化を求められた場合は、指示に従って設定を許可してください。
インストールが完了したら、Docker Desktopを起動します。
ターミナル(WindowsならPowerShellまたはコマンドプロンプト、Macならターミナル.app)を開き、以下の2つのコマンドを実行して、バージョン情報が表示されれば準備完了です。
docker --version
docker compose version
これらのコマンドがエラーなく実行できれば、n8n docker を動かすための基本環境が整いました。
こちらはDocker Desktopの公式概要およびダウンロードページです。 合わせてご覧ください。 https://docs.docker.com/desktop/
n8n docker のインストールと起動手順 (docker-compose編)
n8n docker の起動には、docker run コマンドを直接使う方法もありますが、設定が複雑になりがちです。
ここでは、設定ファイルで環境を管理できる「docker-compose」を使った、最も推奨されるインストール・起動手順を解説します。
- docker-compose.yml ファイルの準備
- docker-compose.yml の設定ポイント(データ永続化とバージョン指定)
- 暗号化キー(ENCRYPTION_KEY)の設定方法
- コマンド実行:n8nコンテナの起動と停止
- ブラウザでn8nにアクセス・動作確認
この手順を踏むことで、誰でも確実かつ安全にn8nの運用を開始できます。
docker-compose.yml ファイルの準備
まず、n8n docker の設定を管理するためのフォルダを任意の場所(例: C:\n8n や ~/n8n)に作成します。
次に、作成したフォルダ内に docker-compose.yml という名前のテキストファイルを作成し、以下の内容をコピーして貼り付けます。
これは、n8n本体と、データを保存するためのPostgreSQLデータベースを一緒に起動するための基本的な設定例です。
YAML
version: '3.7'
services:
n8n:
image: n8nio/n8n:latest
restart: unless-stopped
ports:
- "5678:5678"
environment:
- DB_TYPE=postgresdb
- DB_POSTGRESDB_HOST=db
- DB_POSTGRESDB_PORT=5432
- DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n
- DB_POSTGRESDB_USER=n8n
- DB_POSTGRESDB_PASSWORD=YOUR_STRONG_PASSWORD
- N8N_ENCRYPTION_KEY=YOUR_VERY_LONG_RANDOM_ENCRYPTION_KEY
- TZ=Asia/Tokyo
- GENERIC_TIMEZONE=Asia/Tokyo
volumes:
- n8n_data:/home/node/.n8n
depends_on:
- db
db:
image: postgres:16
restart: unless-stopped
environment:
- POSTGRES_DB=n8n
- POSTGRES_USER=n8n
- POSTGRES_PASSWORD=YOUR_STRONG_PASSWORD
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
volumes:
n8n_data:
postgres_data:
このファイルを保存する際は、必ず docker-compose.yml という名前にしてください。
YOUR_STRONG_PASSWORD と YOUR_VERY_LONG_RANDOM_ENCRYPTION_KEY の部分は、後ほど説明する方法で必ず変更してください。
こちらはn8n公式が提供しているDocker Composeのセットアップガイドです。 合わせてご覧ください。 https://docs.n8n.io/hosting/installation/server-setups/docker-compose/
docker-compose.yml の設定ポイント(データ永続化とバージョン指定)
先ほどの docker-compose.yml ファイルには、n8n docker を安定運用するための重要な設定がいくつか含まれています。
一つ目は「データ永続化」です。
Dockerコンテナは、それ自体が削除されると内部のデータも失われてしまいます。
これを防ぐのが volumes の設定です。
volumes: - n8n_data:/home/node/.n8n という記述により、n8nが作成するワークフローや設定ファイル(コンテナ内の /home/node/.n8n に保存される)が、n8n_data という名前のDockerボリューム(ホストPC側の安全な領域)に保存されるようになります。
同様に postgres_data もデータベースのデータを永続化します。
これにより、n8nコンテナをアップデート(再作成)しても、データが失われることはありません。
二つ目は「バージョン指定」です。
image: n8nio/n8n:latest の :latest は、常に最新版のイメージを取得することを意味します。
安定運用を重視する場合は、latest の代わりに n8nio/n8n:1.118.0 のように、特定のバージョン番号を指定することも可能です。
これにより、意図しないメジャーアップデートによる仕様変更を防ぐことができます。
暗号化キー(ENCRYPTION_KEY)の設定方法
n8n docker 運用において、最も重要な設定の一つが N8N_ENCRYPTION_KEY です。
n8nは、ワークフロー内で使用するAPIキーやパスワードといった「資格情報(Credentials)」を、データベースに保存する前に暗号化します。
この暗号化と復号(読み出し)に使用されるのが、N8N_ENCRYPTION_KEY です。
もしこのキーを設定しないまま起動すると、n8nが初回起動時にランダムなキーを自動生成し、コンテナ内の設定ファイルに保存します。
しかし、その状態でコンテナ(とボリューム)を誤って完全に削除してしまうと、キーも失われます。
キーを失うと、データベースに保存されている暗号化された資格情報を二度と復号できなくなり、すべての資格情報を再設定する必要が出てしまいます。
これを防ぐため、docker-compose.yml で YOUR_VERY_LONG_RANDOM_ENCRYPTION_KEY の部分に、必ず自分で生成した32文字以上のランダムな文字列(例:パスワード生成ツールなどで作成)を設定してください。
この docker-compose.yml ファイル自体を、パスワードなどと一緒に安全にバックアップしておくことが重要です。
こちらはn8nの暗号化キー(Encryption Key)の設定について公式に解説したドキュメントです。 合わせてご覧ください。 https://docs.n8n.io/hosting/configuration/configuration-examples/encryption-key/
コマンド実行:n8nコンテナの起動と停止
docker-compose.yml ファイルの準備(パスワードと暗号化キーの変更を含む)ができたら、いよいよn8n dockerを起動します。
ターミナル(PowerShellやコマンドプロンプト)を開き、docker-compose.yml を保存したフォルダに移動します。
cd C:\n8n (Windowsの場合)
cd ~/n8n (Mac/Linuxの場合)
そして、以下のコマンドを実行します。
docker compose up -d
-d は「デタッチドモード」を意味し、コマンド実行後もバックグラウンドでコンテナが起動し続けます。
初回はn8nとPostgreSQLのイメージダウンロードが実行されるため、少し時間がかかります。
done や healthy といった表示が出れば起動成功です。
コンテナの状態を確認したい場合は docker compose ps を実行します。
n8nを停止したい場合は、同じフォルダで以下のコマンドを実行します。
docker compose down
これによりコンテナは停止・削除されますが、volumes で指定したデータ(n8n_data と postgres_data)は保持されます。
次回再び docker compose up -d を実行すれば、同じデータのまま再開できます。
ブラウザでn8nにアクセス・動作確認
n8n docker コンテナが正常に起動したら、Webブラウザを開き、以下のアドレスにアクセスします。
http://localhost:5678
docker-compose.yml の ports: - "5678:5678" という設定により、ホストPCのポート5678番へのアクセスが、n8nコンテナのポート5678番に転送されます。
初回アクセス時には、n8nのオーナー(管理者)アカウントを設定する画面が表示されます。
ここでEメールアドレス、名前、パスワードを設定すると、n8nのダッシュボード(ワークフロー編集画面)が表示されます。
この画面が無事に表示されれば、n8n docker のインストールと起動は成功です。
もしアクセスできない場合は、ターミナルで docker compose logs n8n コマンドを実行し、n8nコンテナのログを確認してエラーの原因を探してください。
n8n起動後の初期設定(オーナーアカウント作成)
n8n docker の起動に成功し、ブラウザで http://localhost:5678 にアクセスすると、最初に行うべき初期設定があります。
それがオーナーアカウントの作成です。
- オーナーアカウントの作成手順
- ライセンスキーの設定について(オプション)
オーナーアカウントの作成手順
n8nに初めてアクセスすると、「Set up owner account」(オーナーアカウントの設定)という画面が表示されます。
このアカウントは、そのn8nインスタンスの管理者アカウントとなります。
画面の指示に従い、以下の情報を入力してください。
- First Name(名)
- Last Name(姓)
- Email(Eメールアドレス)
- Password(パスワード)
パスワードは忘れないように、安全な場所に保管してください。
入力が完了し、「Next」または「Set up」ボタンを押すと、アカウントが作成され、n8nのメイン画面(ワークフローのキャンバス)にリダイレクトされます。
これで、n8nを自由に使い始める準備が整いました。
このオーナーアカウント作成は、n8nのインストール(正確にはデータベースの初期化)後に一度だけ行う作業です。
docker compose down でコンテナを停止しても、volumes によってデータベースは保持されているため、次回 docker compose up -d で起動した際は、この設定画面は表示されず、ログイン画面が表示されます。
ライセンスキーの設定について(オプション)
オーナーアカウント作成後、n8nの画面設定(右上のアカウントアイコンなど)を見ていると、「License key」や「Upgrade」といった項目に気づくかもしれません。
n8nはオープンソース(ソースコードが公開されている)ですが、そのライセンス形態は「fair-code」と呼ばれるものを採用しています。
基本的なワークフロー自動化機能は、セルフホストであればすべて無料で利用できます。
一方で、チームでの利用を想定した高度なユーザー管理機能、SSO(シングルサインオン)連携、特定のエンタープライズ向けノードなど、一部の機能は有償プラン(n8n Enterpriseなど)でのみ提供されます。
これらの有償機能を利用したい場合は、n8nと契約してライセンスキーを取得し、設定画面から入力する必要があります。
しかし、個人での利用や、基本的な自動化(本記事で解説している docker-compose での起動)を行うだけであれば、ライセンスキーの設定は一切不要です。
無料で強力な自動化機能を使い続けることができます。
こちらはn8nの価格プランとライセンスの詳細について記載された公式ページです。 合わせてご覧ください。 https://n8n.io/pricing/
n8n docker の安全なアップデート(更新)方法
n8nは活発に開発が続けられており、頻繁に新しい機能の追加やバグ修正が行われます。
n8n docker 環境を最新の状態に保つことは、セキュリティと機能の両面で重要です。
docker-compose を使っていれば、アップデート作業は非常に安全かつ簡単に行えます。
- 【重要】アップデート前のバックアップ手順
- Dockerイメージの最新版を取得 (pull)
- コンテナの再起動(docker-compose up -d)
【重要】アップデート前のバックアップ手順
n8n docker のアップデートは非常に安定していますが、万が一の事態に備え、アップデート作業前には必ずデータのバックアップを取得することを強く推奨します。
データ永続化のために volumes を設定している場合、バックアップ対象は docker-compose.yml で指定したボリューム(このガイドの例では n8n_data と postgres_data)です。
まず、念のためn8nコンテナを停止します。
docker compose down
次に、Dockerが管理しているボリュームの物理的な場所を探し、その内容(_data フォルダなど)を丸ごと別の場所にコピーします。
ボリュームの場所は docker volume inspect n8n_data や docker volume inspect postgres_data といったコマンドで確認できます。
または、より簡単な方法として、一時的に別のコンテナ(例:Ubuntuイメージなど)を起動し、そのコンテナにバックアップ対象のボリュームをマウントし、tar コマンドなどでアーカイブ(zipファイルのようなもの)を作成してホストPCにコピーする方法もあります。
どのような方法であれ、最低でも n8n_data (ワークフローと暗号化キーを含む)と postgres_data (実行履歴や資格情報を含む)の2つのボリュームデータを安全な場所にコピーしておけば、万が一アップデートに失敗しても復元できます。
こちらはn8nのセルフホスト環境における公式アップデートガイドです。 合わせてご覧ください。 https://docs.n8n.io/hosting/installation/updating/
Dockerイメージの最新版を取得 (pull)
データのバックアップが完了したら、n8nの新しいバージョンのDockerイメージを取得します。
docker-compose.yml があるフォルダで、以下のコマンドを実行します。
docker compose pull
このコマンドは docker-compose.yml ファイル内に記述されている services(この例では n8n と db)の image を確認し、latest タグ(または指定されたバージョンタグ)の最新版がローカルになければ、Docker Hub(イメージの保管場所)からダウンロードします。
すでに最新版を持っている場合は、「Image is up to date」といったメッセージが表示されます。
n8nio/n8n:latest のイメージが新しくダウンロードされたことを確認してください。
(postgres:16 のようにバージョンを固定しているイメージは、変更がなければダウンロードされません)
この pull コマンドは、まだ既存のコンテナを停止したり再起動したりはしません。
あくまで新しいイメージをローカルに持ってくるだけの、安全な操作です。
コンテナの再起動(docker-compose up -d)
最新のDockerイメージを pull で取得したら、いよいよn8nコンテナを新しいイメージで再起動(=アップデート)します。
実行するコマンドは、コンテナを最初に起動した時と同じです。
docker compose up -d
このコマンドは、以下の動作を賢く実行します。
docker-compose.ymlの定義と、現在起動中のコンテナを比較します。n8nサービスにおいて、ローカルにあるイメージ(先ほどpullした新しいイメージ)が、現在起動中のコンテナが使用しているイメージ(古いイメージ)よりも新しいことを検出します。- 古い
n8nコンテナを自動的に停止(stop)し、削除(remove)します。 - 新しい
n8nイメージを使って、新しいコンテナを作成(create)し、起動(start)します。
この際、volumes でマウントしている n8n_data と postgres_data はそのまま新しいコンテナに引き継がれます。
そのため、古いコンテナが削除されてもデータは失われません。
db サービス(PostgreSQL)に関しては、イメージに変更がないため、停止や再作成は行われず、起動したままとなります。
これが docker-compose によるアップデートの強力な点です。
起動後、http://localhost:5678 にアクセスし、n8nが正常に動作すること、そして右下のバージョン番号などが新しくなっていることを確認してください。
知っておくと便利なn8n dockerの追加設定
基本的な起動とアップデートができるようになったら、n8n docker をより快適に使うための追加設定も知っておくと便利です。
特にタイムゾーンとデータ保存場所は、多くの人が設定する項目です。
- タイムゾーン(TZ)を日本時間に設定する方法
- データ保存場所(volumes)の確認と変更
タイムゾーン(TZ)を日本時間に設定する方法
n8nのDockerコンテナは、デフォルトではUTC(協定世界時)のタイムゾーンで動作します。
しかし、日本でn8nを使用する場合、「Cron」ノード(スケジュール実行)や、ワークフロー内で日付や時刻を扱う際に、タイムゾーンがUTCのままだと不便です。
(例えば、毎朝9時に実行したいのに、UTCの午前9時=日本時間の午後6時に実行されてしまうなど)
これを解決するには、docker-compose.yml の n8n サービスの environment(環境変数)セクションに、タイムゾーンを指定する変数を追加します。
docker-compose.yml の n8n サービスに、TZ=Asia/Tokyo の行を追加します。
YAML
services:
n8n:
(他の設定...)
environment:
(他の環境変数...)
- TZ=Asia/Tokyo
(他の設定...)
このガイドの最初にある docker-compose.yml の例には、すでに TZ=Asia/Tokyo の設定が含まれていますが、より確実にスケジュール実行(Cronノードなど)の時刻を制御するために、GENERIC_TIMEZONE もあわせて設定することを推奨します。
docker-compose.yml を変更した後は、docker compose up -d コマンドを再度実行することで、設定が反映された新しいコンテナが起動します(古いコンテナは自動的に削除されます)。
これにより、n8nのワークフロー内で実行される時刻関連の処理が、日本標準時(JST)に基づいて行われるようになります。
こちらはコンテナのタイムゾーン設定について解説したn8n公式ドキュメントです。 合わせてご覧ください。 https://docs.n8n.io/hosting/configuration/configuration-examples/time-zone/
データ保存場所(volumes)の確認と変更
このガイドの docker-compose.yml では、volumes: セクションで n8n_data: と postgres_data: という二つの「名前付きボリューム」を定義しました。
これにより、データはDockerが管理する特定の領域に保存されますが、その物理的なパスはホストPCからは少し分かりにくい場所(例:WindowsのWSL内など)になります。
もし、バックアップなどの管理上、「ホストPCの特定のフォルダ(例: C:\n8n\data)」にデータを直接保存したい場合、volumes の設定を「バインドマウント」に変更することができます。
docker-compose.yml の n8n サービスと volumes: セクションを以下のように変更します。
(変更前)
YAML
services:
n8n:
(省略)
volumes:
- n8n_data:/home/node/.n8n
(省略)
volumes:
n8n_data:
postgres_data:
(変更後:バインドマウント)
YAML
services:
n8n:
(省略)
volumes:
- ./n8n_data:/home/node/.n8n
(省略)
volumes:
# n8n_data: (名前付きボリュームの定義を削除)
postgres_data:
./n8n_data という記述(相対パス)は、「docker-compose.yml があるのと同じフォルダ内の n8n_data フォルダ」を意味します。
C:/n8n/data:/home/node/.n8n のように絶対パスで指定することも可能です。
この設定で docker compose up -d を実行すると、docker-compose.yml と同じ場所に n8n_data フォルダが作成され、その中にn8nのワークフローや設定ファイルが(ホストPCから見える形で)保存されていきます。
ただし、バインドマウントはホストOSのファイルシステム権限の問題(特にLinux)が発生しやすい場合があるため、Dockerに慣れていないうちは、デフォルトの名前付きボリュームを使用するのが最もトラブルが少ない方法です。
n8n docker導入時のトラブルシューティング
n8n docker の導入や運用時には、いくつかの典型的な問題が発生することがあります。
ここでは、よくある問題とその解決策を紹介します。
- コンテナが正常に起動しない場合の確認点
- Webhookでのファイル(バイナリデータ)がうまく扱えない時は
- アップデート後にデータが消えた?(データ永続化の確認)
コンテナが正常に起動しない場合の確認点
docker compose up -d を実行した後、docker compose ps で状態を確認した際に、n8n や db コンテナが Exit や Restarting になっている場合、起動に失敗しています。
まず確認すべきは「ログ」です。
docker compose logs n8n (n8nコンテナのログ)
docker compose logs db (dbコンテナのログ)
これらのコマンドでエラーメッセージを確認します。
よくある原因としては、docker-compose.yml の記述ミス(インデントのズレなど)、ports: - "5678:5678" で指定したポート番号(5678)がホストPC上の他のプログラムによって既に使用されている、などがあります。
また、db コンテナが起動する前に n8n コンテナが起動してしまい、データベース接続に失敗して終了することもあります(depends_on で制御していますが、タイミング次第で発生し得ます)。
その場合は、docker compose restart n8n でn8nコンテナだけを再起動すると、今度は db が起動しているため接続に成功することがあります。
設定変更やポートの競合を解消した後、docker compose down で一度クリーンアップしてから、再度 docker compose up -d を試してください。
Webhookでのファイル(バイナリデータ)がうまく扱えない時は
Webhookノードを使って外部からファイル(画像やPDFなどのバイナリデータ)を受け取るワークフローを組んだ際、ファイルサイズが数MB程度でもメモリ不足のエラー(OOM Killerでコンテナが落ちるなど)が発生することがあります。
これは、n8nがデフォルトではバイナリデータをメモリ(RAM)上で処理しようとするためです。
この動作を変更し、バイナリデータをメモリではなく一時ファイル(ファイルシステム)に書き出すように設定することで、メモリ消費量を大幅に抑えることができます。
docker-compose.yml の n8n サービスの environment に、以下の変数を追加します。
N8N_DEFAULT_BINARY_DATA_MODE=filesystem
(例)
YAML
services:
n8n:
(他の設定...)
environment:
(他の環境変数...)
- TZ=Asia/Tokyo
- GENERIC_TIMEZONE=Asia/Tokyo
(他の設定...)設定変更後は docker compose up -d を実行してコンテナを再作成してください。
これにより、大きなバイナリデータを含むWebhookリクエストも、より安定して処理できるようになります。
大量のデータを扱う場合は、あわせて N8N_PAYLOAD_SIZE_MAX 環境変数で処理可能なペイロードサイズの上限を引き上げることも検討してください。
アップデート後にデータが消えた?(データ永続化の確認)
n8n docker のアップデート(pull と up -d)を実行した後、ブラウザでアクセスしたら、過去に作成したワークフローや資格情報がすべて消えており、初期設定のオーナーアカウント作成画面に戻ってしまった、というケースがあります。
これは、n8nのデータが正しく「永続化」されていない場合に発生します。
原因のほとんどは、docker-compose.yml の volumes の設定ミスです。
n8nのデータ(ワークフロー、設定、暗号化キーなど)は、コンテナ内の /home/node/.n8n というフォルダに保存されます。
volumes の設定で、このコンテナ内のパスを、ホスト側のボリューム(例: n8n_data)またはフォルダ(例: ./n8n_data)に正しくマウントする必要があります。
(正) volumes: - n8n_data:/home/node/.n8n
(誤) volumes: - n8n_data:/root/.n8n (パスが違う)
(誤) volumes: - /home/node/.n8n (マウント元が指定されていない)
もしアップデート前にこの設定が間違っており、データがコンテナ内にしか保存されていなかった場合、docker compose up -d によるコンテナの再作成(古いコンテナの削除と新しいコンテナの作成)の際に、古いコンテナと共にデータも失われてしまいます。
このガイドの通り、最初から volumes: - n8n_data:/home/node/.n8n と設定していれば、このような問題は発生しません。
万が一データが消えてしまった場合は、アップデート前に取得したバックアップからデータをリストア(復元)する必要があります。
【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない
「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。
これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。
- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。
- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方
では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
プロンプトの質を高めたい方のために、生成AIプロンプト研修のおすすめを比較した記事はこちらです。 合わせてご覧ください。
使い方①:最強の「壁打ち相手」にする
自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」
これにより、一人では気づかなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「無知な生徒」として教える
自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」
AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」
AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。