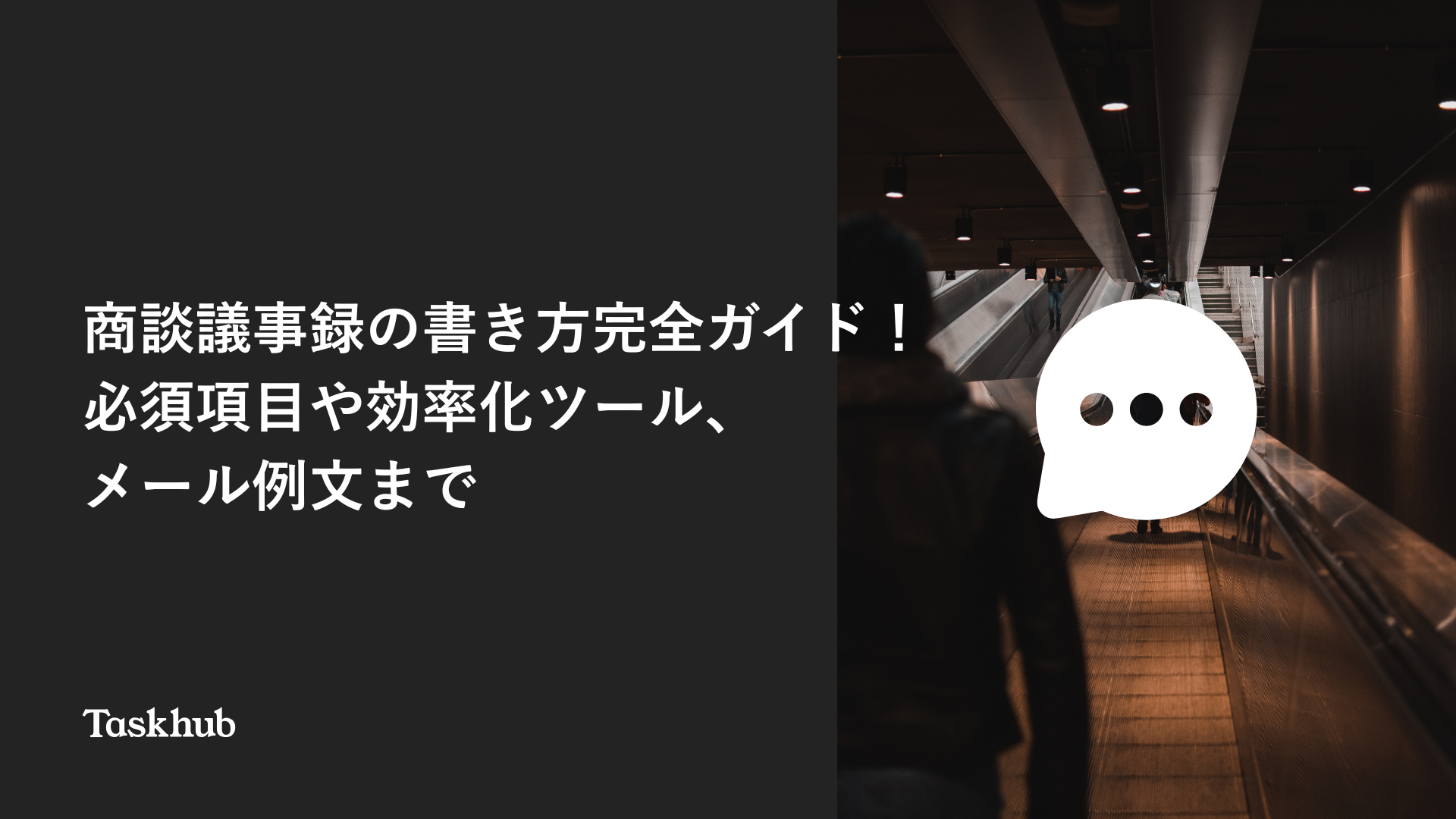「商談の議事録を任されたけれど、何を書けばいいのか分からない」
「毎回、上司に修正されてばかりで時間がかかってしまう…。」
こういった悩みを持っている若手営業マンや新入社員の方も多いのではないでしょうか?
実際、営業担当者が本来の「販売活動」に充てられている時間は全体のわずか28%に過ぎないというデータもあり、事務作業の効率化は喫緊の課題です。 https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/images/form/pdf/pdf/state-of-sales-report-salesforce.pdf
議事録は単なるメモではなく、プロジェクトを円滑に進め、トラブルを未然に防ぐための重要なビジネス文書です。書き方のコツさえ掴めば、作成時間を大幅に短縮できるだけでなく、顧客や社内からの信頼獲得にも繋がります。
本記事では、商談議事録の具体的な書き方や必須項目、そのまま使えるテンプレート、そして最新のAIツールを活用した効率化テクニックについて解説しました。
数多くの企業の営業DXを支援している弊社が実践しているノウハウを余すことなくご紹介します。
営業DXの全体像について詳しく知りたい方は、こちらのDX導入の完全ガイドも合わせてご覧ください。
日々の業務効率を劇的に改善するヒントになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ商談議事録を作るのか?その目的と重要性
議事録作成を「面倒な作業」と捉えてしまうと、どうしても質が下がりがちです。
しかし、議事録にはビジネスを成功させるための明確な目的が3つ存在します。
これらを理解することで、何を書くべきかの判断軸ができ、作成スピードと質が同時に向上します。
それでは、議事録作成の核心となる3つの目的について解説します。
言った言わないのトラブル防止と合意形成
商談において最も避けなければならないのは、後になってから「言った、言わない」のトラブルが発生することです。特に金額や納期、機能要件などの重要な条件について、口頭だけで合意してしまうのは非常に危険です。
人間の記憶は曖昧なものであり、時間の経過とともに都合よく書き換えられてしまうことも珍しくありません。
そのため、決定事項を文書として残し、双方で確認し合うプロセスが不可欠となります。
議事録は、商談内容を客観的な事実として記録した証拠資料としての役割を果たします。
商談直後に議事録を共有し、相手に内容を確認してもらうことで、その時点での「合意形成」が完了します。
もし認識に齟齬があれば、この段階で修正することができるため、後々の大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
PMI(プロジェクトマネジメント協会)の報告によると、非効果的なコミュニケーションはプロジェクト予算の損失リスクを大幅に高めるとされており、議事録による正確な記録はコスト管理の観点からも極めて重要です。 https://www.pmi.org/learning/library/communication-11189
自分と自社を守るためにも、議事録は強力な武器となるのです。
社内関係者への正確な情報共有とネクストアクションの明確化
商談には、必ずしも決裁者やプロジェクトに関わる全てのメンバーが同席できるわけではありません。上司や技術担当、法務担当など、商談の場にいなかった関係者に対して、正確に情報を共有することも議事録の重要な役割です。
単に「良い雰囲気でした」といった定性的な報告ではなく、具体的に何が決まり、どのような課題が残っているのかを伝える必要があります。
正確な情報共有がなされることで、上司は適切な判断を下すことができ、チームメンバーは自分の役割を即座に理解できます。
また、商談後の「ネクストアクション」を明確にすることも欠かせません。
誰が、いつまでに、何をすべきかが不明確なままだと、案件は停滞してしまいます。
議事録によってタスクと期限を可視化することで、チーム全体の動きを加速させ、案件を成約へと近づけることができるのです。
議事録は、チームで仕事を進めるためのバトンと言えるでしょう。
顧客との信頼関係構築と認識のすり合わせ
質の高い議事録を素早く送ることは、顧客からの信頼獲得に直結します。「仕事が早い」「こちらの話をしっかり聞いて理解してくれている」という印象を与えることができるからです。
逆に、議事録が遅かったり、内容が的外れだったりすると、「この担当者に任せて大丈夫だろうか」と不安を抱かせてしまいます。
議事録は、営業担当者の能力や誠実さをアピールするプレゼンテーションの一部でもあります。
また、議事録を送付することは、顧客と認識をすり合わせるためのコミュニケーションツールとしても機能します。
文字に起こされた内容を確認することで、顧客自身も頭の中が整理され、潜在的な要望や懸念点に気づくきっかけになることもあります。
丁寧な議事録を通じて、「あなたとなら安心して仕事ができる」というパートナーシップを築くことこそが、長期的なビジネスの成功には不可欠です。
議事録作成を事務作業ではなく、顧客満足度を高めるサービスの一環と捉えましょう。
そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。
抜け漏れ厳禁!商談議事録に必ず盛り込むべき5つの必須項目
良い議事録には、必ず押さえておくべき共通の項目があります。
これらが抜けていると、後から読み返したときに状況が分からなくなってしまいます。
逆に言えば、これらの項目さえ網羅されていれば、体裁が多少崩れていても十分に機能する議事録となります。
ここでは、商談議事録に必ず盛り込むべき5つの必須項目について詳しく見ていきます。
1.基本情報(日時・場所・参加者)
まず最初に記載すべきなのは、商談の基本となる事実情報です。いつ、どこで、誰と誰が話したのかという情報は、アーカイブとして管理する上で検索性を高めるためにも重要です。
日時は「2025年○月○日(月) 14:00〜15:00」のように、曜日や終了時刻まで正確に記載します。
場所については、自社の会議室なのか、相手先の訪問なのか、あるいはZoomやTeamsなどのオンライン形式なのかを明記しましょう。
参加者については、自社と相手先を分けて記載します。
相手先の参加者は、役職や氏名の漢字に間違いがないよう、頂いた名刺やメールの署名欄と照らし合わせて慎重に確認してください。
敬称は「様」で統一するのが一般的ですが、社内向けに展開するメモであれば「殿」や敬称略のルールがある場合もあります。
欠席者がいる場合で、その共有が必要な際は「欠席:○○様」と添えておくと、誰に情報が伝わっていないかが明確になります。
この基本情報があるだけで、読み手は一瞬で「どの会議の記録か」を認識できます。
2.決定事項(合意した内容)
議事録の中で最も重要度が高いのが、この「決定事項」です。商談の中で双方が合意した内容、確定した条件などを箇条書きで明確に記載します。
例えば、「プランAにて契約を進めること」「導入時期は来年の4月とすること」「定例会を毎週火曜日に実施すること」などが該当します。
ここが曖昧だと、後で言った言わないの水掛け論になるリスクが最も高い部分です。
ポイントは、決定した事実だけを簡潔に書くことです。
「〜という方向で調整する」といった曖昧な表現は避け、「〜と決定」と言い切れるものをここに記載します。
もし条件付きの合意であれば、「○○の機能実装を前提として、プランAで合意」のように、条件もセットで記録します。
忙しい役職者は、この決定事項の欄だけを見て判断を下すことも多いため、一目で結論が分かるように目立たせて記載することが大切です。
3.未決事項・持ち帰り課題(保留点)
商談の場ですべてが決まるわけではありません。その場では判断できず、持ち帰りとなった項目や、継続して検討が必要な事項を「未決事項」として記録します。
例えば、「システム連携の詳細な仕様については技術担当に確認後に回答」「見積もりの再提示が必要」といった内容です。
ここで重要なのは、何が保留になっているのかを明確にすることです。
未決事項が不明確だと、ボールがどこにあるのか分からなくなり、案件が宙に浮いてしまう原因になります。
「保留」と書くだけでなく、なぜ決まらなかったのかという理由も簡単に添えておくと、後から振り返った時に状況を思い出しやすくなります。
また、次回の商談で必ず議論すべき議題(アジェンダ)の候補にもなるため、漏らさず記録しておくことで、次回の商談準備もスムーズになります。
未決事項を管理することは、プロジェクトを前進させるための原動力となります。
4.議論の経緯(なぜその決定に至ったか)
決定事項に至るまでのプロセスや背景を記録するのが「議論の経緯」です。単に結果だけを知らされても、会議に参加していなかった人は「なぜその結論になったのか」が理解できず、納得感が薄れてしまうことがあります。
例えば、プランAに決まった理由として、「プランBは予算オーバーであり、プランCは納期に間に合わないため」といった比較検討の過程を記載します。
また、顧客から出た強い要望や、逆に懸念として挙げられたポイントなどもここに含めます。
詳細な発言録にする必要はありませんが、重要な意思決定の分岐点となった発言やロジックは要約して残しておくべきです。
これにより、後日「やっぱりプランBの方がいいのではないか?」という蒸し返しが起きた際にも、「あの時はこういう理由でAを選んだ」と論理的に説明することができます。
コンテキスト(文脈)を共有することは、チーム全体の認識レベルを合わせるために非常に有効です。
5.今後の予定とToDo(誰が・いつまでに・何をするか)
最後に、商談の結果を受けて具体的にどのようなアクションを取るのかを記載します。いわゆる「ToDoリスト」や「ネクストアクション」と呼ばれる部分です。
ここでは「誰が(Who)」「いつまでに(When)」「何をする(What)」の3要素をセットで書くことが絶対条件です。
「見積もりを作成する」だけでは不十分で、「鈴木が、11月20日までに、修正見積書を作成してメールで送付する」と具体的に書きます。
自社のタスクだけでなく、相手にお願いしているタスク(例:要件定義書の確認、契約書の捺印など)も忘れずに記載しましょう。
期限を明確に切ることで、双方に程よい緊張感が生まれ、タスクの放置を防ぐことができます。
次回の打ち合わせ日程が決まっている場合は、それもここに記載します。
この項目が埋まっていない議事録は、仕事が完結していないのと同じです。
必ずアクションプランを明確にして商談を締めくくりましょう。
【コピペでOK】状況別・商談議事録のテンプレートとフォーマット
議事録を一から作成するのは時間がかかります。
あらかじめフォーマットを用意しておき、商談中はそこに情報を埋めていく形式にすれば、抜け漏れを防ぎつつ作成スピードを劇的に向上させることができます。
ここでは、そのままコピー&ペーストして使える3つのパターンのテンプレートを用意しました。
状況に合わせて使い分けてください。
基本の商談議事録フォーマット
最も汎用性が高く、初回の商談からクロージング、定例会議まで幅広く使える標準的なフォーマットです。
基本的にはこの型を持っておけば困ることはありません。
【商談議事録】
日時:202○年○月○日(○) 00:00〜00:00
場所:貴社 会議室A / オンライン(Zoom)
参加者:
貴社:○○様、○○様
自社:○○、○○
■決定事項
・
・
■ToDo(ネクストアクション)
【自社】
・(担当名):(内容) ※期限:○月○日
・(担当名):(内容) ※期限:○月○日
【貴社】
・(担当名):(内容) ※期限:○月○日
■未決事項・持ち帰り課題
・
・
■議論の概要・経緯
- ○○について - (内容要約) - (内容要約)
- ○○について - (内容要約)
■次回予定 日時:○月○日(○) 00:00〜 内容:○○についての合意
課題解決・提案型の詳細フォーマット
ヒアリングや提案など、込み入った話をする際に適したフォーマットです。
顧客の課題とそれに対する解決策の議論を中心に記録します。
【商談議事録(提案・検討会)】
日時・場所・参加者:(基本フォーマット同様)
■本日のゴール
・自社新プランのご提案と導入可否の判断
■決定事項
・
■顧客課題(現状と悩み)
・
・
■提案内容と反応
・提案内容:○○プランによる業務効率化
・顧客反応:コスト面で懸念あり、機能面は高評価
■質疑応答(Q&A)
Q:○○機能は既存システムと連携可能か?
A:API連携により可能。別途仕様書を提出する。
Q:
A:
■今後の進め方・ToDo ・ ・
確認・顔合わせ等の簡易フォーマット
名刺交換や簡単な挨拶、あるいは進捗確認だけの短い打ち合わせに適したシンプルなフォーマットです。
要点だけをスピーディーに共有することに特化しています。
【お打ち合わせメモ】
日時・場所・参加者:(基本フォーマット同様)
■確認事項
・プロジェクト進捗は予定通り
・来月のキャンペーン内容は確定済み
■共有事項
・弊社の夏季休業期間について伝達済み
■次回アクション ・定例会にて詳細数値を報告(担当:○○)
「分かりやすい」と評価される商談議事録の書き方・コツ
同じテンプレートを使っていても、書き手によって分かりやすさには雲泥の差が出ます。
「この人の議事録は読みやすい」と評価されるためには、文章の構成や表現にちょっとした工夫が必要です。
ここでは、読み手の負担を減らし、内容がスッと頭に入ってくるような書き方のコツを4つ紹介します。
今日からすぐに実践できるテクニックばかりです。
5W1Hを意識して結論から簡潔に書く
ビジネス文書の鉄則ですが、結論から書く「PREP法」や「ピラミッド構造」を意識しましょう。
「〜という理由があり、〜という経緯で議論が進み、結果として〜になった」という書き方は、最後まで読まないと結論が分からず、読み手にストレスを与えます。
まず「結果として〜に決定した」と書き、その後に「理由は〜だからである」と続けるのが正解です。
また、文章を書く際は5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)の要素が抜けていないか常にチェックしてください。
特に「誰が(Who)」と「何を(What)」は曖昧になりがちです。
主語を明確にし、一文を短く区切ることで、誤解の余地がないクリアな文章になります。
箇条書きを多用するのも、情報を構造化して伝えるための有効な手段です。
事実(発言)と解釈(感想)を明確に分けて記載する
初心者がやりがちなミスの一つが、事実と自分の感想を混同して書いてしまうことです。
例えば、「先方は前向きだった」という記述は、書き手の主観的な解釈に過ぎません。
議事録に求められるのは客観的な事実です。
「先方は『予算内で収まるならすぐにでも導入したい』と発言した」と書けば、それは事実の記録になります。
その上で、「発言のトーンから、成約の確度は高いと感じられる」といった所感を書きたい場合は、備考欄や所感欄を設けて事実とは分けて記載しましょう。
事実と解釈が混ざると、読み手はどこまでが本当に合意された内容なのか判断できなくなります。
情報の純度を保つために、この区別は厳密に行うようにしてください。
専門用語は社内用語か一般的かを判断して噛み砕く
社内で当たり前に使っている略語や専門用語が、顧客にも通じるとは限りません。議事録は顧客とも共有するものであるため、相手が理解できる言葉を選ぶ配慮が必要です。
例えば、「ASAPで対応します」と書くより、「至急対応します」と書いた方が親切ですし、「FIXしました」より「確定しました」の方が誤解がありません。
もし専門用語を使う必要がある場合は、括弧書きで補足を入れましょう。
また、社内展開用の議事録であっても、他部署の人が読む可能性があります。
特定の部署でしか通じないスラングは避け、誰が読んでも同じ意味に取れる標準的なビジネス用語を使うのがマナーです。
言葉の壁を取り除くことで、情報の流通がスムーズになります。
決定事項とToDoを目立たせて記載する
忙しいビジネスパーソンは、議事録を一言一句丁寧に読む時間がない場合がほとんどです。多くの人は、自分に関係のある箇所や、結論部分だけを斜め読みします。
Webユーザビリティの権威であるNielsen Norman Groupの研究でも、ユーザーの79%はテキストを一字一句読まずにスキャン(流し読み)していることが明らかになっており、ビジネス文書においても「拾い読み」を前提とした構成が求められます。 https://www.nngroup.com/
そのため、最も重要な「決定事項」と「ToDo」は、パッと見ただけで目に飛び込んでくるように視覚的に工夫しましょう。
これらを議事録の冒頭に配置したり、記号(【】や■)を使って見出しを強調したりするのが効果的です。
長い文章の中に決定事項を埋没させてはいけません。
「ここだけ読めば会議の成果が分かる」というブロックを作っておくことが、読み手への最大の配慮となります。
読みやすい議事録は、それだけで仕事ができる証拠となります。
商談議事録をメールで送る際のマナーとタイミング
議事録は作成して終わりではありません。
関係者に確実に届け、内容を確認してもらうまでが仕事です。
メールで送付する際にも、相手への配慮や暗黙のビジネスルールが存在します。
ここでは、議事録メールを送る際の適切なタイミングと、開封率を高めるためのメール作成のポイントについて解説します。
原則として商談後24時間以内(翌日午前中まで)に送る
議事録送付の鉄則は「スピード」です。人間の記憶は1日経つだけでその大部分が失われてしまいます。記憶が鮮明なうちに送ることで、相手も内容の確認がしやすく、認識のズレをその場で修正できます。
理想は商談が終わった当日中、遅くとも翌日の午前中まで(24時間以内)には送付しましょう。
これが3日も4日も遅れてしまうと、仕事が遅いというレッテルを貼られるだけでなく、プロジェクト自体のスピード感も損なわれます。
もし、完璧な議事録を作るのに時間がかかりそうであれば、70%の完成度でも良いのでまずは「取り急ぎのメモ」として共有し、詳細は後送するという方法もあります。
とにかくボールを早く投げ返すことが、信頼関係の維持には不可欠です。
メール本文に要約を記載し、添付ファイルを開かなくても内容が伝わるようにする
議事録をWordやPDFファイルで添付する場合でも、メール本文に何も書かずに「添付ファイルをご確認ください」とだけ送るのは不親切です。
スマートフォンでメールを確認する人も多いため、添付ファイルを開くという一手間は意外とハードルが高いものです。
メールの本文に、決定事項とToDoの要約を箇条書きで記載しておきましょう。
そうすれば、相手はメールを開いた瞬間に会議の要点を把握できます。
「詳細な経緯については添付のファイルに記載しております」と誘導すれば、詳細を知りたい人だけがファイルを開けば済みます。
相手の時間を使わせない工夫が、デキるビジネスマンのメール術です。
そのまま使える!議事録送付時のメール例文
ここでは、社外のお客様に議事録を送る際の標準的なメール例文をご紹介します。
これをベースに、状況に合わせてアレンジして使用してください。
件名:【議事録】○○プロジェクトに関するお打ち合わせの件(株式会社○○ 名前)
○○株式会社
○○部 ○○様
いつも大変お世話になっております。
株式会社○○の(自分の名前)でございます。
本日はご多忙の折、お打ち合わせのお時間をいただき誠にありがとうございました。
本日の商談内容を議事録としてまとめましたので、送付いたします。
ご確認いただき、もし認識に相違がございましたら、
お手数ですがご指摘いただけますと幸いです。
=====【本日の要点まとめ】=====
■決定事項
・○○プランにて契約手続きを進める
・導入開始日は○月○日とする
■ネクストアクション
・弊社:お見積書の修正版を送付(明日正午まで)
・貴社:契約書の内容確認およびご捺印(来週末まで)
====================
詳細につきましては、添付のPDFファイルをご確認ください。
引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
署名
議事録作成が劇的に楽になる!効率化ツールと活用術
手動ですべてを記録し、清書するのは大きな労力がかかります。
現在は便利なデジタルツールが多数登場しており、これらを活用しない手はありません。
ここでは、議事録作成の時間を半分以下に短縮するための具体的なツールと活用術を紹介します。
生成AIの具体的な導入方法や活用ガイドについて、法人向けの解説記事をご用意しています。ぜひご覧ください。
テクノロジーを味方につけて、本質的な業務に集中できる環境を整えましょう。
Googleドキュメント等のクラウドツールで同時編集・共有する
Wordなどのローカルファイルをメールでやり取りするのは、バージョン管理が煩雑になりがちです。GoogleドキュメントやNotionなどのクラウドツールを使えば、URLを共有するだけで常に最新の状態を全員が見ることができます。
また、商談中に画面共有しながらその場で議事録を書き込み、「この内容で合っていますか?」と確認しながら進めるライブ・議事録作成もおすすめです。
その場で合意が取れるため、持ち帰って清書し、確認メールを送るという工程を丸ごとカットできます。
社内のメンバーと共同編集もできるため、一人が発言を記録し、もう一人がToDoを整理するといった連携も可能です。
クラウドツールの導入は、議事録作成の効率化への第一歩です。
AI自動文字起こしツールを活用して記録の手間を省く
近年、AIによる音声認識技術は飛躍的に向上しています。ZoomやTeamsの文字起こし機能や、専用のAI議事録ツールを使えば、会議の発言をほぼ自動でテキスト化してくれます。
特に最新のAIモデル(GPT-5など)の技術を応用したツールでは、単なる文字起こしだけでなく、文脈を理解した要約や、決定事項の自動抽出まで行ってくれるものも登場しています。
例えば、複雑な議論が行われた場合でも、AIが「即時応答」と「深い推論」を自動で切り替えて処理することで、非常に精度の高い議事録ドラフトを瞬時に作成できるようになっています。
これにより、人間はAIが作った下書きを微修正するだけで済み、ゼロから書く手間から解放されます。
AI会議アシスタントを提供するOtter.aiの調査では、こうしたツールを使用することで、専門職の62%が週に4時間以上を節約できたと回答しており、導入効果は明白です。 https://otter.ai/blog/the-leading-ai-meeting-assistant-otter-ai-unveils-game-changing-productivity-boost-62-of-professionals-say-that-ai-saves-them-over-an-entire-month-of-work-each-year
ただし、機密情報の取り扱いには注意が必要です。
法人向けのセキュリティが担保されたプランを利用するなど、リスク管理をした上で活用しましょう。
ChatGPTを使った会議の議事録作成方法について、具体的なプロンプトや活用事例をこちらの記事で詳しく解説しています。
ZoomやTeamsの録画・録音機能を補助的に使う
オンライン商談の場合は、ボタン一つで録画が可能です。これにより、メモを取り損ねた箇所があっても、後からその部分だけを聞き直して正確に記載することができます。
ただし、録画データがあるからといって、メモを全く取らなくて良いわけではありません。
1時間の会議をまた1時間かけて見直すのは非効率極まりないからです。
あくまで録画は「保険」として使い、会議中は重要なポイントのメモに集中しましょう。
また、録画を見直す際は、再生速度を1.5倍〜2倍速にすることで時間を節約できます。
対面商談の場合は、スマホのボイスレコーダーアプリなども有効ですが、必ず相手の許可を取ってから録音するようにしましょう。
商談議事録に関するよくある質問
最後に、議事録作成に関して新入社員や若手の方からよく寄せられる質問に回答します。
ちょっとした疑問を解消して、自信を持って議事録作成に取り組んでください。
商談中にメモを取るのが追いつかない場合はどうすればいいですか?
無理に全ての会話を書き留めようとせず、重要なキーワードや数字、決定事項だけに絞ってメモを取りましょう。接続詞や丁寧語などは無視して、箇条書きで事実だけを羅列するのがコツです。
また、商談の最後に「本日の決定事項は○○と○○で間違いありませんか?」と口頭で復唱して確認する時間を設けるのも有効です。
その場で確認が取れれば、メモが不完全でも正しい議事録を作成できます。
どうしても不安な場合は、先輩社員に同席してもらい、最初はサポートをお願いするのも良いでしょう。
相手が話した内容を一字一句記録する必要はありますか?
一字一句記録する必要はありません。むしろ、話し言葉をそのまま文字にすると非常に読みづらい文章になってしまいます。
求められているのは、発言の意図や要点をまとめた「要約」です。
ただし、クレーム対応や法的な争いが予想される場面など、特定の状況下では発言のニュアンスを含めた詳細な記録が必要になる場合もあります。
基本的には、読み手が短時間で理解できるように情報を整理・編集することが議事録作成者の腕の見せ所です。
録音をする際は相手に許可を取るべきですか?
はい、録音をする際は必ず相手に許可を取りましょう。無断で録音することは、マナー違反であるだけでなく、場合によっては信頼関係を大きく損なう原因になります。
「議事録を正確に作成するために、録音させていただいてもよろしいでしょうか?」と正直に伝えれば、断られることはほとんどありません。
この一言があるだけで、相手に対する誠意が伝わります。
社内会議であっても、録音する旨を一言断るのがビジネスマナーです。
なお、法的な観点では、相手の同意を得ない「秘密録音」であっても、著しく反社会的な手段でない限り、民事訴訟における証拠能力は認められる傾向にありますが、信頼関係維持のためには事前の承諾が不可欠です。 https://www.emg-total-law-office.jp/post/
あなたの記憶は1時間で半分消える?心理学が証明する「直後の議事録」が最強な理由
商談が終わった直後、「内容は覚えているから、あとでまとめて書こう」と後回しにしていませんか?実はその判断が、ビジネスにおける致命的なミスを招く可能性があります。ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスの研究によれば、人間の脳は情報をインプットした瞬間から忘却が始まり、驚くべきスピードで記憶を失っていくことが分かっています。
具体的には、学習や経験から20分後には42%を忘れ、1時間後にはなんと56%もの記憶が失われるとされています。この「エビングハウスの忘却曲線」は心理学の基礎的な研究として知られており、人間の記憶がいかに早く減衰するかを客観的に示しています。 https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve
つまり、商談が終わって会社に戻る頃には、会話の半分以上が頭の中から消え去っているか、曖昧な状態になっているのです。この「空白の56%」を自分の都合の良い解釈で埋めてしまうことが、「言った・言わない」のトラブルや、顧客との認識ズレを引き起こす最大の原因です。
記憶の鮮度が落ちる前に記録を残すことは、単なる事務作業ではなく、ビジネスのリスク管理そのものです。人間の脳の限界を科学的に理解し、商談直後の5分を議事録作成に投資できるかどうかが、信頼される営業マンとそうでない人を分ける大きな分岐点となるでしょう。
引用元:
ヘルマン・エビングハウスは、無意味な音節を用いた記憶実験を行い、時間の経過とともにどれだけ記憶が保持されるかを曲線で示しました。これを「エビングハウスの忘却曲線」と呼び、人間の記憶の減衰速度を示した心理学の基礎的な研究として広く知られています。(Hermann Ebbinghaus, “Über das Gedächtnis”, 1885年)
まとめ
営業活動において、商談の質を高めることと同様に、その内容を正確に残す議事録の作成は極めて重要です。
しかし、多忙な営業現場では「移動時間に追われて作成する暇がない」「要約や清書に時間がかかりすぎる」といった理由で、議事録作成が後回しにされがちです。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
今回の記事で解説したような商談議事録の作成はもちろん、録音データからの自動文字起こし、要点の抽出、さらにはネクストアクションのリスト化まで、目的に合った「アプリ」を選ぶだけで、AIが瞬時に業務を代行してくれます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、顧客情報や商談内容といった機密データも万全のセキュリティ下で扱えるため、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIに指示を出すのが難しそう」という企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに議事録作成時間を大幅に短縮できる設計なので、浮いた時間を本来の提案活動や顧客とのコミュニケーションに充てられる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社の営業DXを一気に加速させましょう。