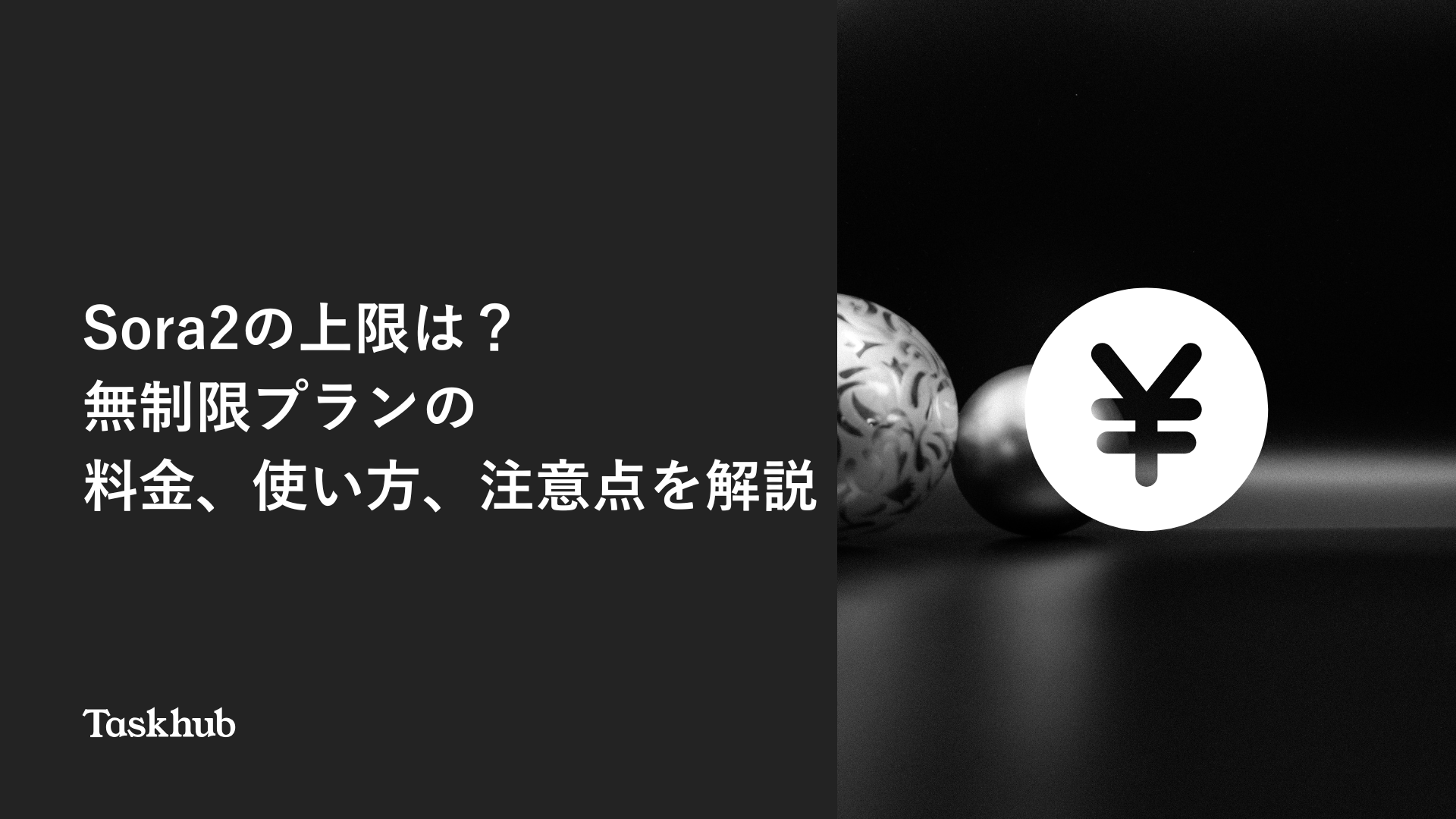「Sora2で動画を作りたいけど、上限が気になって思い切り使えない…」
「Sora2の無制限プランについて詳しく知りたい。」
「Sora 1からSora2になって、何がどう変わったの?」
こういった疑問や悩みを持っている方も多いのではないでしょうか?
待望の一般公開(段階的)が開始されたOpenAIの動画生成AI「Sora2」(Sora最新モデル)は、その圧倒的なクオリティで世界中を驚かせています。 しかし、その一方で利用上限や利用開始の方法がどのようになっているのか、情報が錯綜している状況です。
本記事では、Sora2の最新の利用上限、料金体系、そしてSora2の能力を最大限に引き出す使い方や注意点について、網羅的に解説します。
AI活用コンサルティングを専門とする弊社が、Sora2の公式情報を徹底的に分析し、ビジネスやクリエイティブ活動にすぐ活かせる情報だけを厳選しました。
こちらは生成AIの企業活用について、メリットから導入の注意点まで網羅的に解説した記事です。 合わせてご覧ください。
ぜひ最後までご覧いただき、あなたの動画制作に役立ててください。
動画生成AI「Sora2」とは?
まずは、動画生成AI「Sora2」の基本的な概要と、従来モデルからどう進化したのかを確認していきましょう。
Sora2は、OpenAIが開発したテキストから動画を生成するAIモデルの最新版です(公式には「Sora」と呼ばれますが、本記事では区別のためSora2と呼びます)。 初期の限定プレビュー版(Sora 1)の性能を飛躍的に向上させ、よりリアルで、より長く、より指示に忠実な動画生成を実現しました。
Sora2の基本機能と特徴
Sora2の最大の特徴は、テキストプロンプト(指示文)を入力するだけで、非常に高品質で物理法則に準拠した動画を生成できる点にあります。
単なる映像の断片ではなく、一貫したストーリー性を持つシーンや、複雑なカメラワーク(ドリー、ズーム、パンなど)を反映した映像を作り出すことができます。
また、動画から動画を生成する「Video-to-Video」機能も強化され、既存の映像を全く異なるスタイルや内容に変換することも可能です。
こちらはOpenAIによるSora2の公式システムカード(機能、制限、安全性の詳細)です。 合わせてご覧ください。
Sora 2は、OpenAI が提供する最先端の新しい動画・音声生成モデルです。Sora を基盤とするこのモデルは、物理演算の精度向上、よりリアルな描写、音声の同期、操作性の向上、スタイル適用範囲の拡張など、従来の動画モデルでは実現が難しかった機能を備えています。ユーザーの指示への忠実度も高いため、想像力に富んでいながら、現実世界の変化に基づいた動画を作成できます。Sora 2では、ストーリーテリングやクリエイティブな表現を可能にするツールキットを拡張しているほか、一歩進んだモデルとして物理世界の複雑さをより正確にシミュレートできます。Sora 2は、sora.com と新しいスタンドアロン型 iOS Sora アプリでご利用いただけます。今後、API でも利用可能になる予定です。
引用元:https://openai.com/index/sora-2-system-card/
従来モデル(Sora 1)からの進化点
Sora2は、Sora 1と比較して主に以下の点で大幅に進化しています。
1. 生成品質の飛躍的向上:
Sora 1で時折見られた、物理的な不自然さ(物が不自然に曲がる、人物の手足が崩れるなど)が大幅に改善されました。
光の反射、水の流れ、髪の毛の揺れなどが、実写と見分けがつかないレベルで再現されます。
2.生成時間の安定化と品質向上:
初期モデル(Sora 1)で示された最大60秒の動画生成が、Sora2ではより安定し、高品質になりました。
3. プロンプトへの忠実度の向上:
Sora 1では無視されがちだった細かい指示(特定の服装、背景のディテールなど)も、Sora2では高い精度で反映されるようになりました。
なぜSora2の「利用上限」が注目されている?
Sora2の「利用上限」がこれほど注目される理由は、その圧倒的な性能の裏返しとして、莫大な計算コスト(コンピュートリソース)が必要だからです。
高品質な動画を1本生成するためには、高性能なGPUを長時間占有する必要があります。
そのため、OpenAIはサービスの安定供給とコストのバランスを取るため、ユーザーごとに利用上限やクレジット制度を設けざるを得ません。
特にクリエイターや企業からは、「試行錯誤のためにもっと多く生成したい」「上限を気にせず使いたい」という声が強く、料金プランと利用上限のバランスがSora2活用の最大の鍵となっています。
Sora2の「上限」は?最新の利用制限まとめ
Sora2の利用上限は、Sora 1の完全招待制だった頃から緩和されつつありますが、利用はアクセス権やプラン(例:ChatGPT Plusなど)に基づいて管理されています。 ここでは、Sora2の上限に関する最新の状況をまとめます。
現在の生成回数や時間の上限(公式情報)
Sora2の利用上限は、提供形態によって異なります。
例えば、ChatGPT Plusユーザー向けに提供されるSoraは、ChatGPTの利用上限(例:GPT-4oのメッセージ制限など)に準拠する形で制限が設けられる可能性があります。
「上限なし(無制限)」は本当?
2025年10月現在、一般ユーザー向けの「上限なし(無制限)プラン」は提供されていません。
Sora2の利用は、ChatGPT Plusのサブスクリプションなど、既存のサービス枠内での提供が中心となっており、利用回数には一定の制限が設けられています。 将来的により柔軟なプランが発表される可能性はありますが、現状では「無制限」での利用はできません。
利用枠(クレジット)の現在の状況
Sora2の利用は、アクセス権が付与されたアカウントごとに管理されています。
例えばChatGPT Plusを通じて利用する場合、追加料金なしでSoraの機能が解放されますが、サーバーの負荷状況に応じて、一度に生成できる回数や時間帯に制限がかかる可能性があります。
Sora2の料金プランとアクセス方法
2025年10月現在、Sora2専用の独立した料金プラン(Free, Standard, Proなど)は正式に発表されていません。 アクセス方法は、主に以下の形態で段階的に提供されています。
- ChatGPT Plus ユーザーへの提供: 月額20ドル(約3,000円)のChatGPT Plusサブスクリプションに登録しているユーザーに対し、Soraの機能が順次解放されています。追加料金なしでSoraの機能が利用可能になります。
- Soraアプリ(iOS)経由: 米国、カナダなど一部の国で先行してiOSアプリ「Sora by OpenAI」がリリースされています。アプリの利用は招待制となっており、招待枠を得ることで利用可能になります。
こちらはiOS版「Sora by OpenAI」の公式App Storeページです。 合わせてご覧ください。 https://apps.apple.com/us/app/sora-by-openai/id6744034028 - Enterpriseプラン: 法人向けのEnterpriseプランでは、カスタマイズされたアクセス権が提供される可能性がありますが、詳細は個別問い合わせとなります。
「上限なし(無制限)」で使えるプランは?
前述の通り、2025年10月現在、一般ユーザー向けの「上限なし(無制限)プラン」は提供されていません。
ChatGPT Plusユーザーも、サーバーの混雑状況やOpenAIのポリシーに基づき、利用回数には一定の制限が適用されます。 コストを気にせず試行錯誤ができる環境は限定的ですが、今後のプラン拡充が期待されます。
Sora2の始め方と登録手順
Sora2は、Sora 1時代の完全招待制から緩和されましたが、誰でもすぐに利用開始できるわけではなく、段階的な提供となっています。PC(ブラウザ)版とスマホアプリ版(iOS先行)が提供されています。 PC(ブラウザ版)での始め方 PCでの利用は、主にChatGPT Plusユーザー向けに提供されます。
PC(ブラウザ版)での始め方
PCでの利用が、プロンプトの入力や生成結果の確認がしやすく、メインの利用方法となります。
- ChatGPT Plusに登録: OpenAIの公式サイトから、ChatGPT Plus(有料プラン)に登録します。
- アクセス権の待機: Sora2(Sora)へのアクセス権は、Plusユーザーに対して段階的に付与されています。
- 利用開始: アカウントにSoraの機能が解放されると、ChatGPTのインターフェース内や専用のWebページから動画生成が利用可能になります。
スマホアプリ(iOS/Android)での始め方
スマホアプリ版は、外出先でのアイデアのスケッチや、生成結果の簡易チェックに便利です。
- アプリのダウンロード: App Storeで「Sora by OpenAI」と検索し、公式アプリをダウンロードします。(※2025年10月現在、Android版は提供されていません)
- ログイン: PC版で作成したアカウント、または新規でアカウントを作成してログインします。
- 同期: PC版とアカウントは自動で同期され、生成した動画やクレジット残高は共通で管理されます。
OpenAI公式ヘルプセンターによる「Soraアプリの始め方」の詳細ガイドです。 合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/12456897-getting-started-with-the-sora-app
招待コードは現在も必要?
いいえ、Sora2の一般公開に伴い、Sora 1の時代に必要だった招待コード(ウェイティングリストへの登録)は完全に不要となりました。
現在(2025年10月時点)は、誰でもSora2公式サイトから即座に登録し、利用を開始することができます。
Sora2の新機能と上限緩和で可能になったこと
Sora2では、従来モデルからの品質向上に加え、待望の新機能が搭載されました。
また、ChatGPT Plusユーザーへの機能解放など、一般ユーザーへのアクセスが拡大されたことが、クリエイティブの幅を大きく広げています。
新機能①:音声・音楽の自動生成
Sora2の目玉機能の一つが、動画の内容と雰囲気に合わせた音声・BGM・効果音を自動で生成する機能です。
プロンプトで「波の音」「カフェの雑踏」「壮大なオーケストラのBGM」といった指示を加えるだけで、映像にマッチしたサウンドが自動的に付与されます。
従来は、Soraで生成した無音の動画に、別途音声素材を探して編集する必要がありましたが、この機能によりSora2単体で音付きの動画を完結できるようになりました。
新機能②:カメオ機能(人物の固定)
Sora2の「カメオ機能」は、特定の人物の顔や服装、特徴を記憶させ、異なるシーンや動画でも一貫して同じキャラクターとして登場させることができる機能です。
Sora 1では、同じプロンプトを使ってもシーンが変わると人物の顔が変わってしまう問題がありました。
カメオ機能により、特定のキャラクター(例:「赤いジャケットを着た短髪の女性」)を主人公とした連続性のあるストーリー動画の制作が格段に容易になりました。
こちらはSora2の「カメオ機能」について、日本語で詳しく解説した技術記事です。 合わせてご覧ください。 https://ascii.jp/elem/000/004/326/4326237/3/
アクセス拡大で高品質な動画が作りやすくなった
Sora2へのアクセス機会が(限定的ではあるものの)増えたことは、多くのクリエイターにとって朗報です。 AIによる動画生成は、意図した通りの結果を得るために、何度もプロンプトを修正・再生成する「試行錯誤」が不可欠です。
これまでは利用自体が困難でしたが、利用制限の範囲内であっても、Sora2の高度な物理シミュレーションの調整、カメラワークの微調整、カメオ機能の精度向上などに時間を費やすことが可能になり、作品全体のクオリティを追求しやすくなりました。
Sora2で生成された動画の参考例
Sora2は、その汎用性の高さから、すでに様々なジャンルの動画生成に活用されています。
ここでは、Sora2の能力を示す代表的な参考例を紹介します。
実例①:実写風の風景・ドキュメンタリー
Sora2が最も得意とする分野の一つです。
「雨上がりの東京の路地裏、ネオンが水たまりに反射している様子」「サバンナを歩く象の家族、夕日が逆光になっているドローン映像」といったプロンプトで、実写と見分けがつかないほどのリアルな映像が生成されます。
自然風景や都市景観など、ドキュメンタリータッチの映像素材として非常に強力です。
実例②:アニメ・イラスト風の動画
Sora 1では難易度が高かった、非実写(アニメ、クレイアニメ、ピクセルアートなど)のスタイルも、Sora2では大幅に品質が向上しました。
「日本の90年代アニメスタイルで、教室で会話する2人の学生」「クレイアニメーションで、パン生地がこねられてオーブンで焼かれる様子」など、特定の画風を指定した動画生成が可能です。
実例③:物理演算を使ったアクションシーン
Sora2は、単なる映像の模倣ではなく、動画の世界の物理法則を理解(シミュレート)しています。
そのため、「車がコーナーをドリフトする様子、タイヤスモークと火花が散る」「水中で気泡がゆっくりと上昇していく様子」など、物理的に正確なアクションシーンや特殊効果の生成に優れています。
実例④:商品紹介・広告動画
ビジネス利用として、商品紹介動画の制作が活発です。
「白いミニマルな背景で、新しいデザインのスニーカーがゆっくりと回転する」「モデルが新製品の化粧水を使い、肌が潤う様子のクローズアップ」など、高品質な広告素材を低コストで生成できます。
カメオ機能と組み合わせることで、特定の商品を使ったライフスタイルシーンなども簡単に作成可能です。
Sora2のビジネス活用アイデア
Sora2の上限緩和と機能強化により、特にビジネスシーンでの活用が急速に進んでいます。
ここでは、具体的な活用アイデアを3つ紹介します。
SNS投稿・ショート動画の量産に
TikTokやInstagramリール、YouTubeショートなどのショート動画プラットフォームは、コンテンツの「量」と「質」の両方が求められます。
Sora2を活用すれば、一つのテーマで複数のバリエーションの動画を(利用制限の範囲内で)効率的に生成できます。例えば、製品の異なる使用シーン、異なるターゲット層に向けたメッセージなど、A/Bテスト用の動画素材を効率的に作成可能です。
プレゼン資料用のデモ動画作成に
企画書やプレゼンテーション資料において、テキストや静止画だけでは伝わりにくいサービスのイメージや、製品の利用シーンを動画化するのにSora2は最適です。
「未来のスマートシティのコンセプト動画」「新しいアプリの操作デモ風の映像」などをSora2で具体的に視覚化することにより、企画の説得力を大幅に高めることができます。
教育・研修コンテンツのビジュアル化に
社内研修や顧客向けのチュートリアル動画など、教育コンテンツの制作にもSora2は役立ちます。
複雑な機械の操作手順、抽象的な経営理論、歴史的な出来事の再現など、実写では撮影が困難または高コストな内容も、Sora2を使えば低コストでビジュアル化できます。
これにより、学習者の理解度を深める効果が期待できます。
Sora2を使う上での注意点
Sora2は非常に強力なツールですが、その能力を最大限に引き出し、同時にトラブルを避けるためには、いくつかの注意点があります。
高品質な動画を生成するプロンプトのコツ
Sora2の品質はプロンプト(指示文)の質に大きく左右されます。
こちらは、生成AIのプロンプト作成スキルを磨くための研修サービスについて徹底比較した記事です。 合わせてご覧ください。
詳細な描写:
単に「犬が公園を走る」ではなく、「ゴールデンレトリバーが、晴れた日の緑豊かな公園で、楽しそうに赤いフリスビーを追いかけている。スローモーション。」のように、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確に記述します。
カメラワークの指定:
「ドローン空撮」「主人公の目線(POV)」「下からのあおり(ローアングル)」「ゆっくりとズームアウト」など、具体的なカメラワークを指定することで、映像のクオリティが格段に上がります。
こちらはOpenAI公式(Cookbook)が提供する、Sora2の高品質なプロンプト作成ガイドです。 合わせてご覧ください。 https://cookbook.openai.com/examples/sora/sora2_prompting_guide
著作権・肖像権(カメオ機能利用時)の扱い
Sora2で生成した動画の著作権は、基本的に生成者(ユーザー)に帰属するとされています(プランの利用規約に従う必要があります)。
ただし、カメオ機能を使用する際に、実在の人物(俳優や著名人)の写真や名前を許可なく使用することは、肖像権やパブリシティ権の侵害にあたる可能性が非常に高いです。
カメオ機能は、あくまでオリジナルのキャラクターを生成・固定するために使用してください。
こちらは生成AIを企業利用する際のリスクと、その対策や注意点について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
禁止されているコンテンツとポリシー違反
OpenAIは、Sora2の利用において厳格なコンテンツポリシーを定めています。
以下のようなコンテンツの生成は禁止されており、違反するとアカウント停止の対象となる可能性があります。
- 極端な暴力や残虐な表現
- 性的なコンテンツ(ヌード、性行為など)
- ヘイトスピーチ、差別的な表現
- 実在の人物のディープフェイク(特に欺瞞的な目的のもの)
OpenAIが定める、画像および動画生成に関する公式のコンテンツポリシー全文はこちらです。 合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/creating-images-and-videos-in-line-with-our-policies/
生成動画の商用利用は可能か?
ChatGPT PlusやEnterpriseプランなど、有料のアクセス権を通じて生成された動画は、原則として商用利用が可能とされています(OpenAIの最新の利用規約に従う必要があります)。 広告、SNSマーケティング、商品動画、Webサイトの背景動画など、幅広いビジネス用途で活用できます。
Sora2の「上限」に関するよくある質問
最後に、Sora2の利用上限に関して、ユーザーから多く寄せられる質問とその回答をまとめます。
Sora2の利用上限は今後変更される可能性はありますか?
はい、可能性は非常に高いです。
OpenAIは、AIモデルの効率化とハードウェアの増強を継続的に行っています。
将来的には、サーバーの処理能力が向上し、より多くのユーザーが低コストで利用できるようになることが予想されます。
利用制限や料金体系は、需要と供給のバランスを見ながら今後も随時見直される(緩和される)可能性が高いでしょう。
日本からでも無制限プランは契約できますか?
はい、Proプラン(無制限のRelaxモード含む)はグローバルで提供されており、日本からも問題なく契約可能です。
支払いも日本円でのクレジットカード決済に対応しています。
公式サイトから登録する際に、居住国として日本を選択し、通常通り手続きを進めれば利用できます。
一度に生成できる動画の長さ(時間)の上限はどれくらいですか?
現在(2025年10月時点)のSora2では、一度のプロンプトで生成できる動画の長さ(時間)の上限は、最大で60秒(1分)とされています。 これはSora 1(初期モデル)で示された上限が維持されつつ、生成される動画の品質や一貫性が大幅に向上しています。
組織におけるAI活用:思考停止を防ぎ、真の生産性向上を実現する方法
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、多くの企業でDX推進や業務改善の切り札として期待されています。しかし、「AIに任せれば、頭を使わなくて済む」という安易な考え方は、組織全体の思考力低下を招くリスクもはらんでいます。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究が示すように、AIへの過度な依存は脳の活動を低下させ、深く考える力や記憶力、アイデア創出力の衰退につながる可能性があります。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
では、企業はどのようにAIを導入し、従業員の思考力を維持・向上させながら、最大限のメリットを享受できるのでしょうか。その鍵は、AIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として活用することにあります。東京大学などのトップ研究機関で実践されているように、AIを効果的な「壁打ち相手」や「教師役」、あるいは「アイデアの触媒」として利用することで、従業員はより深く思考し、創造性を高めることができます。
AIを「組織の脳力強化ツール」に変える具体策
AIを単なる効率化ツールで終わらせず、組織全体の知的生産性を高めるためには、以下のような具体的な活用法が考えられます。
1. 課題解決のための「最強の壁打ち相手」としてAIを活用
新しいプロジェクトの企画や、複雑な問題の解決に取り組む際、AIをあえて「鋭い指摘をするコンサルタント」として設定し、自社の意見や企画に対する弱点やリスクを洗い出させます。
プロンプト例:「(自社の企画や課題)について、優秀なコンサルタントの視点から、最も致命的な弱点や想定されるリスクを3つ挙げてください。」これにより、多角的な視点を取り入れ、より堅牢な計画を立案する能力を鍛えることができます。
2. 知識定着と伝達力向上のための「無知な生徒」役としてAIを活用
従業員が特定のテーマについて深く理解しているかを確認するため、AIを「専門知識のない生徒」として設定し、そのテーマについて説明させます。AIからの質問に答える過程で、自身の理解度を再確認し、曖昧な点を明確にすることができます。
プロンプト例:「今から『(特定の業務プロセスや業界トレンド)』について説明します。あなたは新入社員だと思って、少しでも分かりにくい点があれば質問してください。」これは、社内でのナレッジ共有や新人教育の効率化にも繋がります。
3. イノベーションを促進する「アイデア触媒」としてAIを活用
ブレインストーミングの初期段階で、AIに「面白いアイデアを出して」と丸投げするのではなく、自社の持つアイデアの“種”(キーワードやコンセプト)をAIに与え、それらを組み合わせた斬新な切り口や視点を提案させます。
プロンプト例:「『(新製品のテーマ)』についてアイデアを求めています。キーワードは『環境配慮』『カスタマイズ性』『体験型』です。これらの要素を組み合わせて、これまでにない製品企画の切り口を5つ提案してください。」AIが提案する意外な組み合わせからインスピレーションを得て、最終的なイノベーションに繋がるアイデアを創出する力を養います。
まとめ
企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。