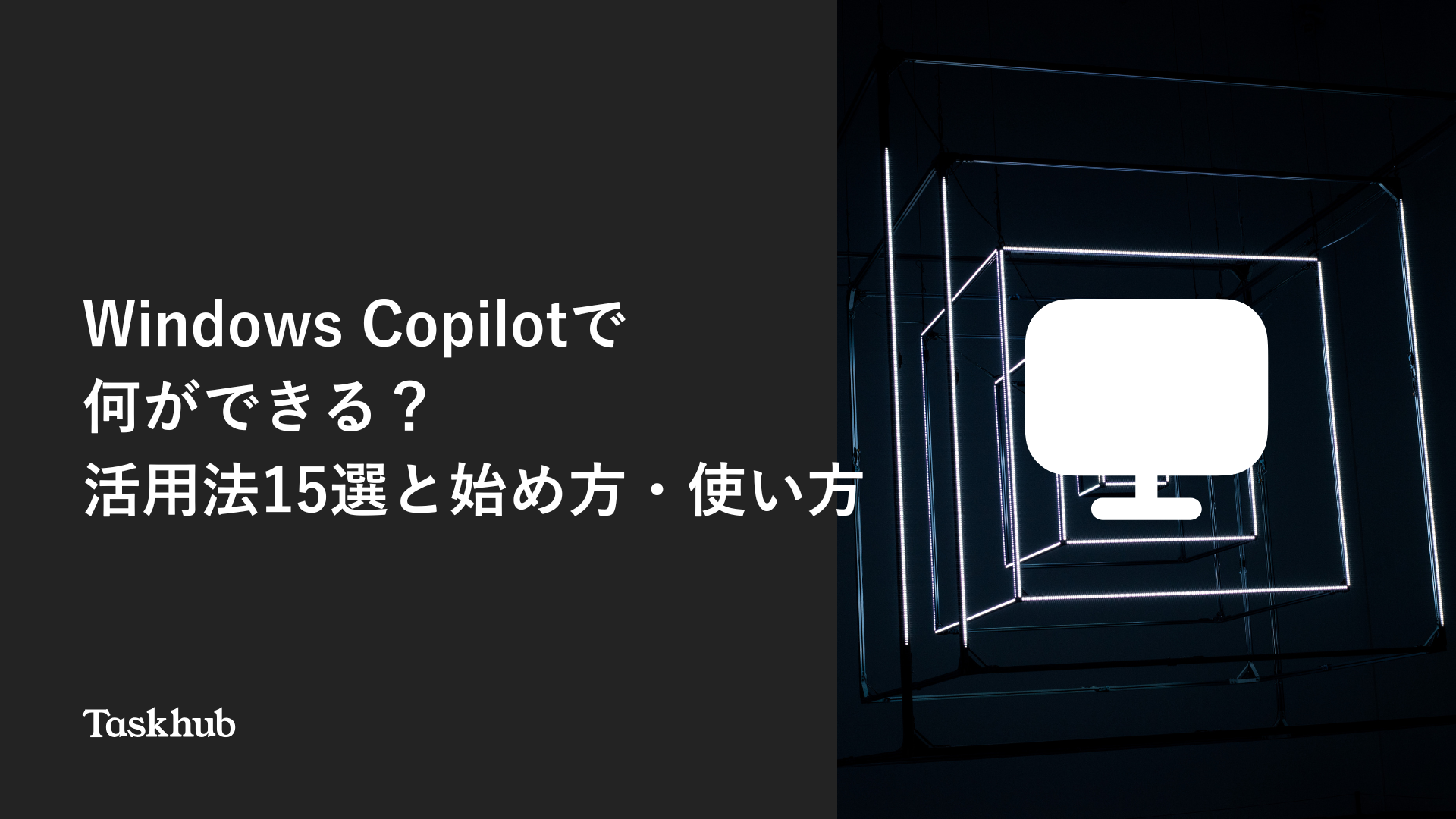「Windows Copilotって最近よく聞くけど、具体的に何ができるの?」
「PCにアイコンは出てるけど、どう使えばいいか分からない…。」
こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
Windows Copilotは、Windows 11に搭載されたAIアシスタント機能です。PC操作の自動化から、質問応答、文章作成、画像生成まで、さまざまなタスクをサポートしてくれます。
本記事では、Windows Copilotでできることや具体的な活用法15選、有料版との違い、基本的な使い方や表示されない場合の対処法まで、網羅的に解説します。
PC作業の効率を劇的に上げたい方は、きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
Windows Copilotとは?何ができるようになるのか
ここでは、Windows Copilotの基本的な概要と、無料版・有料版の違いについて解説します。
Windows Copilot(またはCopilot in Windows)は、OpenAIのGPT-5世代など最新AIモデルを搭載した、Windows標準のAIアシスタントです。
こちらはGPT-5について、リリース日、機能、料金、GPT-4との違いを解説した記事です。 合わせてご覧ください。
チャット形式で指示(プロンプト)を入力するだけで、PC操作、情報検索、コンテンツ作成など、これまで手動で行っていた多くの作業を自動化・効率化できます。
OSと統合されているため、単なるチャットボットを超えたサポートが可能です。
それでは、具体的な機能とプランの違いを見ていきましょう。
Windows Copilotの基本機能と特徴
Windows Copilot(現在はOS上では「Copilot in Windows」、または単に「Copilot」と呼ばれることもあります)は、Windows 11のタスクバーに統合されており、ショートカットキー(Windowsキー + Cキー)やアイコンクリックで簡単に起動できます。
主な特徴は、OSの操作をAIに任せられる点です。
例えば、「ダークモードにして」「集中モードをオンにして」といった指示で、設定画面を開くことなくPCの設定を変更できます。
また、Web検索エンジン「Bing」と連携しているため、常に最新の情報を反映した回答が得られるのも強みです。 質問応答、文章の要約・翻訳、アイデア出しはもちろん、Microsoft自社開発のMAI-Image-1やOpenAIのDALL-Eなどをベースにした画像生成機能(Image Creator)や、画像の内容を認識する機能(Copilot Vision)も無料で利用できます。
これらの機能がOSレベルで提供されるため、複数のアプリケーションを横断するような作業もスムーズに行えるようになります。
Microsoft Copilotの個人向け機能に関する公式の概要については、こちらのページで詳しく紹介されています。 合わせてご覧ください。 https://www.microsoft.com/en/microsoft-copilot/for-individuals
無料版と有料版(Copilot Pro / Microsoft 365 Copilot)の違いは?
Windows 11に標準搭載されている「Copilot」は、基本的に無料で利用できます。
これには、前述のPC操作、Web検索、質問応答、画像生成などの機能が含まれており、個人ユーザーの日常的な作業効率化には十分な性能を持っています。
一方、有料版として個人向けの「Copilot Pro」と、主に企業向けの「Microsoft 365 Copilot」が存在します。これらは月額(または年額)のサブスクリプション料金が必要です。 有料版の最大の違いは、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、TeamsといったMicrosoft 365アプリ(旧Officeアプリ)との深い連携です。
例えば、「Wordで企画書を書いて」「Excelでこのデータを分析してグラフ化して」「Teams会議の議事録を要約して」といった、各アプリ内での高度なAIサポートが受けられます。
日常的な利用であれば無料版、個人でもOfficeアプリ連携や最新モデル(GPT-5など)の優先アクセスを求める場合は「Copilot Pro」、企業としてOfficeアプリやTeamsで高度なAIサポートを求める場合は「Microsoft 365 Copilot」、と棲み分けがされています。
Windows Copilotでできること一覧!便利な活用法15選
Windows Copilotで何ができるか、具体的なイメージが湧かない方もいるかもしれません。
ここでは、Windows Copilotの便利な活用法を15個ピックアップして紹介します。
無料版でも利用できる機能がほとんどですので、ぜひ試してみてください。
活用法①:PCの設定を変更する (例: ダークモードにする)
Copilotの大きな特徴が、Windows OSの設定変更です。
従来は設定アプリを開き、目的の項目を探して操作する必要がありましたが、Copilotならチャットで指示するだけです。
例えば、「ダークモードにして」「音量を50にして」「Wi-Fiをオンにして」「Bluetoothデバイスを接続して」といった指示を出すと、Copilotが該当する設定項目を提示したり、直接変更を実行したりします。
設定画面のどこにあるか分からない機能でも、自然な言葉で指示できるため、PC操作に不慣れな人にも優しい機能です。
また、「集中モードを30分間オンにする」といったタイマー設定も可能で、作業効率化に直結します。
わざわざマウスでカチカチと操作していた手間が省け、思考を中断させずにPC環境を整えられます。
活用法②:アプリを起動する (例: Wordを開く)
PC内のアプリケーションを起動する際もCopilotが役立ちます。
スタートメニューやデスクトップからアイコンを探す代わりに、「Wordを開いて」「電卓を起動して」「ペイントを立ち上げて」と指示するだけです。
複数のアプリを同時に使う作業でも、「メモ帳とブラウザを開いて」といった指示で、効率的に作業環境を整えられます。
特に、普段あまり使わないアプリや、どこに保存したか忘れがちなツールを起動する際に便利です。
ただし、すべてのサードパーティ製アプリに対応しているわけではありませんが、主要なWindows標準アプリやMicrosoft製のアプリは高精度で起動できます。
日常的な「アプリを起動する」という小さな手間を削減できるだけでも、PC作業のストレス軽減に繋がります。
活用法③:知りたいことを質問して回答を得る
Copilotは、高性能な検索エンジンの側面も持っています。
Bing検索と連携しているため、一般的な知識から専門的な情報、最新のニュースまで、あらゆる質問に回答できます。
「今日の東京の天気は?」「〇〇社の最新の株価は?」「AIの仕組みを分かりやすく教えて」といった質問を投げかけると、Web上の情報を検索・要約して分かりやすい形で提示してくれます。
従来の検索エンジンと異なり、複数のWebサイトを自分で見比べる必要がなく、知りたい答えをピンポイントで得られるのがメリットです。
回答には情報源(ソース)のリンクも表示されるため、より詳しい情報を確認したい場合や、情報の正確性を担保したい場合(ファクトチェック)にも便利です。
調べ物にかかる時間を大幅に短縮できる、Copilotの基本的な活用法です。
活用法④:文章の作成・翻訳・要約を依頼する
Copilotは、OpenAIの高度な言語モデルを搭載しているため、文章関連のタスクが非常に得意です。
「顧客向けの丁寧な謝罪メールを作成して」「新しいプロジェクトのアイデアを5つ提案して」「このブログ記事のタイトル案を10個出して」といった指示で、高品質な文章を瞬時に生成します。
文章を一から考える手間が省けるだけでなく、自分では思いつかないような表現や構成案を得ることもできます。
また、翻訳機能も強力です。
「以下の英語の文章を日本語に翻訳して」「この日本語のレポートを自然な英語にして」といった指示で、高精度な翻訳が可能です。
さらに、長い文章やWebページの内容を短くまとめる「要約」も得意です。
こちらはCopilotで要約を作成する方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
「このニュース記事の要点を3つにまとめて」と依頼すれば、重要なポイントだけを抽出してくれます。
活用法⑤:Web上の最新情報を検索する
Copilotは、Bing検索エンジンと統合されているため、リアルタイムの情報を取得できます。
多くのAIチャットボットが持つ「訓練データが古いために最新情報に弱い」という弱点を克服しています。
「今週末のおすすめイベントは?」「最新のスマートフォンモデルの比較をして」「〇〇(スポーツ選手)の昨日の試合結果は?」など、”今”知りたい情報について正確に回答できます。
レストランの予約状況や、商品の在庫情報(対応サイトのみ)など、動的な情報にもアクセス可能です。
この機能により、Copilotは単なる知識データベースではなく、現実世界と連動した「最新情報に強いアシスタント」として機能します。
調べ物の手間を省き、常に新しい情報に基づいた意思決定をサポートしてくれます。
活用法⑥:画像の内容を読み取ってもらう(Copilot Vision)
Copilotには「Copilot Vision」と呼ばれる画像認識機能が搭載されています。
チャット欄に画像をドラッグ&ドロップするか、クリップボードから貼り付けることで、その画像の内容について質問したり、説明させたりできます。
例えば、観光地の写真を見せて「この建物は何ですか?」「ここはどこですか?」と質問すると、場所や建物の名前を教えてくれます。
グラフや図表の画像を読み込ませて「このグラフから何が分かるか説明して」と指示すれば、データを分析し、傾向を読み取ってくれます。
他にも、商品の写真から製品名を特定したり、料理の写真からレシピを推測させたりすることも可能です。
文字だけでは説明しづらい内容を、画像を使ってAIに伝えることができる強力な機能です。
視覚的な情報を扱う作業が多い場合に非常に役立ちます。
活用法⑦:指示した通りの画像を生成する(Image Creator)
Copilotは、文章から画像を生成するAI「Image Creator」も統合しています。これにはMicrosoftが自社開発した「MAI-Image-1」やOpenAIの最新モデルが利用されています。
「青い空を飛ぶ赤いドラゴンの絵を描いて」「近未来的な都市の風景画像を生成して」「ブログ記事のアイキャッチ画像を作成して」といったように、テキストでイメージを伝えるだけで、オリジナルの画像を生成できます。
生成したい画像のスタイル(例:「水彩画風で」「サイバーパンク調で」「写真のようにリアルに」)を指定することも可能です。
プレゼン資料のスライド、SNSの投稿、Webサイトの挿絵など、ビジュアルコンテンツが必要なあらゆる場面で役立ちます。
従来はデザインスキルや高価なソフトが必要だった画像作成が、誰でも簡単に行えるようになりました。
アイデアを視覚化したい時に、非常に便利な機能です。
活用法⑧:音声で指示や対話をする
キーボード入力だけでなく、音声による指示や対話も可能です。
Copilotのチャットウィンドウにあるマイクアイコンをクリックすることで、PCに接続されたマイクを通じてAIと会話できます。
手が離せない作業中や、タイピングが面倒な時に便利です。
「明日の天気を教えて」「〇〇について調べて」と話しかけるだけで、Copilotが音声またはテキストで回答します。
複雑なプロンプトを考えるのが苦手な人でも、普段誰かに話しかけるような感覚でAIを活用できます。
また、読み上げ機能を使えば、生成された回答を音声で聞くことも可能です。
PCの画面を見続けるのが疲れた時や、他の作業をしながら情報をインプットしたい時に役立ちます。
より自然で直感的なAIとのコミュニケーションを実現する機能です。
活用法⑨:開いているWebページや記事を要約する
Copilotは、Microsoft Edgeブラウザと連携することで、現在開いているWebページやPDFの内容を認識できます。
EdgeブラウザのサイドバーからCopilotを起動し、「このページを要約して」「この記事の重要なポイントを教えて」と指示するだけです。
長いニュース記事、詳細なレポート、複雑な技術文書などを読む時間を大幅に節約できます。
Copilotが自動で全文を読み込み、要点を簡潔にまとめてくれるため、情報収集の効率が飛躍的に向上します。
また、単なる要約だけでなく、「この記事の内容に基づいて反論を考えて」「この記事の筆者の主張は何?」といった、内容の深い理解を助ける質問も可能です。
Webリサーチや学習の強力なサポートツールとして機能します。
活用法⑩:スクリーンショットから文字を認識する
Windowsのスクリーンショット機能(切り取り&スケッチなど)とCopilotを連携させることができます。
画面の一部をスクリーンショットで撮影し、その画像をCopilotに読み込ませることで、画像内のテキストを認識(OCR)させることが可能です。
例えば、WebサイトやPDFでコピーが禁止されているテキスト、画像内に埋め込まれた文字、エラーメッセージのスクリーンショットなどをCopilotに読み込ませます。
そして、「この画像からテキストを抽出して」「このエラーメッセージの意味を教えて」と指示します。
Copilotは画像内の文字を正確に読み取り、テキストデータとして出力したり、内容について解説したりできます。
手動で文字起こしをする手間が省けるため、データ入力やトラブルシューティングの際に非常に便利です。
活用法⑪:長い文章を作成・編集する(Notebook機能)
Copilotには「Notebook(ノートブック)」と呼ばれる、より長い文章の作成や編集に特化したインターフェースが用意されています。
通常のチャット画面は一問一答形式で素早いやり取りに向いていますが、Notebookは広々とした編集エリアが特徴です。
左側に指示(プロンプト)を入力し、右側にAIが生成した結果が表示されます。
生成された文章をその場で編集し、さらに追加の指示を出して内容をブラッシュアップしていく、といった使い方ができます。
ブログ記事の下書き、レポートの作成、プログラミングコードの記述など、ある程度の分量が必要なコンテンツ作成に最適です。
チャット形式では流れがちな長い指示や、何度も修正を重ねるような作業も、Notebookを使えばストレスなく行えます。
活用法⑫:プラグインで機能を追加・拡張する
Copilotは「プラグイン」や「Copilot Studio」で作成されたカスタムAI(エージェント)に対応しており、外部サービスと連携して機能を拡張できます。 これにより、Copilotが標準では持っていない特定の機能を利用できるようになります。
例えば、レストラン予約サイトのプラグインを有効にすれば、「今夜渋谷で2名で予約できるイタリアンを探して」といった指示で、空席情報を検索し、予約手続きまでサポートしてくれるようになります(対応サービスのみ)。
他にも、旅行予約サイト、Eコマースサイト、特定の業務ツールなど、さまざまなプラグインやカスタムAI(GPTs)が提供されています。
設定メニューから利用したいプラグインをオンにするだけで、Copilotの活躍の場がさらに広がります。
自分のよく使うサービスと連携させることで、Copilotをよりパーソナライズされたアシスタントに育てることが可能です。
活用法⑬:チャットで日常会話や相談をする
Copilotは、業務効率化だけでなく、日常的な会話相手や相談相手としても利用できます。
「今日は疲れたよ」「何か面白いジョークを言って」「今日の夕食の献立を一緒に考えて」といった、雑談や軽い相談にも応じてくれます。
AIは感情的にならず、常に客観的で論理的な(あるいは共感的な)回答を返してくれるため、ちょっとした話し相手が欲しい時や、壁打ち相手が欲しい時に便利です。
「会話のスタイル」を選択する機能(例:「創造的に」「バランスよく」「厳密に」)もあり、目的に応じてAIの性格を切り替えることもできます。
人間関係のストレスなく、気軽にアイデアを整理したり、気晴らしをしたりできるのも、AIアシスタントならではの活用法と言えるでしょう。
活用法⑭:仕事や趣味のアイデアを出してもらう
新しい企画やプロジェクト、趣味の活動などでアイデアに行き詰まった時、Copilotは強力なブレインストーミングのパートナーになります。
「新しいYouTubeチャンネルの企画案を10個出して」「子供向けの週末イベントのアイデアを考えて」「新しい小説のあらすじを提案して」といった指示を出すと、AIが多様な視点からアイデアを生成してくれます。
自分一人では思いつかないような突飛なアイデアや、既存の要素を組み合わせた新しい切り口など、思考の幅を広げるきっかけを与えてくれます。
生成されたアイデアをベースに、さらに「そのアイデアをもっと具体的にして」「別のターゲット層向けの案も出して」と深掘りしていくことも可能です。
創造的な作業の第一歩として、Copilotを活用するのは非常に有効です。
活用法⑮:スマホアプリで外出先でも使う
Copilotの機能は、PCだけでなく、スマートフォンアプリ(iOS/Android)でも利用できます。
「Microsoft Copilot」アプリをインストールすれば、Windows版とほぼ同等の機能を外出先でも手軽に利用可能です。
PCで作成した文章の続きをスマホで編集したり、外出先で気になったことをスマホのCopilotで質問したり、撮影した写真をその場でCopilot Visionで解析させたりできます。
Microsoftアカウントでサインインしていれば、PCとスマホでチャット履歴が同期されるため、デバイスをまたいでシームレスに作業を続けることができます。
PCの前にいない時でも、高性能なAIアシスタントを常に携帯できるのは大きなメリットです。
日常生活のあらゆる場面でAIのサポートを受けられるようになります。
【有料版】Copilot Pro / Microsoft 365 Copilotでできること (Office連携)
Windows 11標準のCopilotでも多くのことができますが、個人向けの「Copilot Pro」(Microsoft 365 Personal/Family契約者が対象)や、ビジネス向けの「Microsoft 365 Copilot」では、Officeアプリとの連携が真価を発揮します。
Microsoft 365 CopilotがWordやExcelなどの各アプリで何ができるか、その詳細なサービス概要については、こちらの公式ドキュメントで解説されています。 合わせてご覧ください。
Microsoft 365 Copilot は、作業タスクに役立つ AI を活用したツールです。
ユーザーは Copilot にプロンプトを入力し、Copilot は AI によって生成された情報で応答します。 応答はリアルタイムであり、ユーザーがアクセス許可を持つインターネット ベースのコンテンツや作業コンテンツを含めることができます。
ユーザーは、作業タスクに関連するコンテンツを取得し、使用している Microsoft 365 アプリのコンテキストで取得します。
たとえば、Operations Manager を使用していて、人事部と連携してジョブの説明を更新しているとします。 Copilot プロンプト セッションでは、Copilot にジョブの説明を作成し、説明に含める必要がある修飾を追加するように依頼できます。 同じプロンプト セッションで、生成されたジョブの説明を展開して、レベル 1、レベル 2、レベル 3 などの異なるレベルを作成することもできます。
エージェントを作成して使用して、organizationのデータ ソースを使用して Copilot エクスペリエンスをカスタマイズすることもできます。 たとえば、倉庫マネージャーであり、出荷の状態を把握する必要があります。 Copilot配送業者に「出荷1234の状態は何ですか?」Copilot はデータ ソースを使用して情報を取得し、状態で応答できます
引用元: https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-overview
ここでは、Microsoft 365 CopilotがOfficeアプリ(Microsoft 365アプリ)と連携することで何ができるようになるのか、その主な機能を紹介します。
これらの機能は、個人の生産性だけでなく、チーム全体の業務効率を根本から変える可能性を秘めています。
それでは、各アプリでの具体的な活用例を見ていきましょう。
Outlook:メール作成や要約
Microsoft 365 Copilotは、Outlookでのメール業務を劇的に効率化します。
「〇〇さんへのプロジェクト進捗確認メールを、丁寧な文面で作成して」と指示するだけで、適切なメール文案を即座に生成します。
過去のやり取りやカレンダーの予定を踏まえた内容を提案することも可能です。
また、受信トレイに溜まった大量の未読メールを要約する機能も強力です。
「過去1週間の重要なメールを要約して」と指示すれば、優先度の高いメールだけをピックアップし、内容を簡潔にまとめてくれます。
長いメールスレッド(やり取り)の要点を把握するのにも役立ち、メール処理にかかる時間を大幅に削減できます。
Word:文章作成、要約、編集
WordにおけるCopilotは、強力なライティングアシスタントとして機能します。
「〇〇に関する企画書のドラフトを作成して」と指示するだけで、指定したテーマに基づいた構成案と本文を自動で生成します。
既存のドキュメントを読み込ませて、「この文章を要約して」「もっとプロフェッショナルなトーンに書き換えて」「表形式にまとめて」といった編集作業も可能です。
白紙の状態から文章を書き起こす負担を軽減し、推敲やブラッシュアップといった、より創造的な作業に集中できるようになります。
また、社内の他のドキュメント(PowerPointやExcelのデータなど)を参照しながら文章を作成することもでき、資料作成の精度とスピードが向上します。
Excel:データ分析、グラフ作成
ExcelでのCopilot活用は、データ分析のハードルを大きく下げます。
これまで関数やピボットテーブルの知識が必要だった作業も、自然な言葉で指示するだけです。
「この売上データから、製品別の傾向を分析して」「どの地域が最も成長しているか教えて」「月次の売上推移をグラフにして」といった指示で、Copilotがデータを解析し、インサイト(洞察)を提示したり、適切なグラフを自動で作成したりします。
複雑なデータセットを前にしても、何から手をつければよいか分からないといった状況を回避できます。
データに基づいた迅速な意思決定をサポートし、専門家でなくても高度なデータ分析が可能になります。
PowerPoint:スライド作成、構成案作成
PowerPointでのCopilotは、プレゼンテーション資料作成の強力なサポーターです。
「〇〇についてのプレゼン資料を5枚のスライドで作成して」とテーマを伝えるだけで、タイトル、目次、各スライドの内容、さらには適切な画像やデザインまで含めたドラフトを自動生成します。
また、既存のWord文書やメモ書きを読み込ませて、「この内容をプレゼン資料に変換して」と指示することも可能です。
スライドの構成案を考える手間、一枚一枚デザインを整える手間が大幅に削減されます。
「このスライドにスピーカーノート(発表者用のメモ)を追加して」「アニメーションを追加して」といった、細かな調整も指示できます。
資料作成の時間を短縮し、発表内容を練り込む時間や練習により多くの時間を割けるようになります。
Teams:会議の要約、議事録作成
Microsoft TeamsにおけるCopilotは、会議の生産性を飛躍的に高めます。
会議中にCopilotを起動しておくと、リアルタイムで会話を文字起こしし、誰が何を話したかを記録します。
会議終了後には、「この会議の要点をまとめて」「決定事項(ToDoリスト)を一覧にして」と指示するだけで、AIが自動で議事録を生成します。
こちらはChatGPTで会議の議事録を作成する方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
会議に途中参加した場合でも、「ここまでの議論を要約して」と聞けば、すぐに状況をキャッチアップできます。
また、会議中に「〇〇さんの意見について、どう思いますか?」といった形で、特定の論点についてAIに意見を求めることも可能です。
議事録作成の手間をなくし、議論そのものに集中できる環境を整えてくれます。
Windows Copilotの始め方と基本的な使い方
Windows Copilotをまだ使ったことがない方のために、ここからは基本的な始め方と使い方を解説します。
利用開始までのステップは非常に簡単です。
Windows 11が最新の状態であれば、特別なインストール作業は不要ですぐに使い始められます。
Windows 11でCopilotを利用可能にする方法
Copilot in Windowsは、Windows 11のバージョン「23H2」以降で標準機能として提供されています(最新の24H2や25H2ではさらに機能が強化されています)。
もしタスクバーにCopilotのアイコンが表示されていない場合、まずはWindows Updateを確認してください。
「設定」アプリを開き、「Windows Update」を選択します。
「更新プログラムのチェック」をクリックし、利用可能なすべての更新プログラム(オプションの更新プログラムを含む)をインストールしてください。
PCを再起動後、OSが最新バージョンになれば、Copilotが利用可能になるはずです。
ただし、組織(会社や学校)のPCでは、管理ポリシーによってCopilotが無効化されている場合があります。
その場合は、システム管理者に確認が必要です。
タスクバーからCopilotを起動する
Copilotが有効になると、通常はタスクバーの右端(通知領域の近く)に、青緑色の渦巻きのようなCopilotアイコンが表示されます。
このアイコンをクリックするだけで、画面の右側にCopilotのサイドバーが表示され、チャットを開始できます。
また、キーボードショートカット「Windowsキー + Cキー」でも、Copilotを素早く起動・非表示に切り替えることができます。
頻繁に利用する場合は、このショートカットキーを覚えておくと便利です。
もしアイコンが表示されていない場合は、タスクバーの何もないところを右クリックし、「タスクバーの設定」から「Copilot in Windows」のスイッチがオンになっているか確認してください。
プロンプト(指示)を入力して使う
Copilotのサイドバーが表示されたら、下部にあるチャットボックスに、AIにしてほしいこと(プロンプト)をテキストで入力します。
例えば、「東京の明日の天気を教えて」「集中できるBGMを流して(Spotifyなど連携アプリが必要な場合あり)」「この文章を校正して」といった具合です。
入力して送信すると、Copilotが指示を解釈し、回答を生成します。
回答が気に入らない場合や、もっと深掘りしたい場合は、続けてチャットで追加の指示を出します。
「もっと簡潔にまとめて」「別の視点から教えて」など、対話を重ねることで、求めている回答に近づけていくことができます。
また、マイクアイコンをクリックすれば音声入力も可能です。
まずは簡単な質問やPC操作から試してみて、AIとの対話に慣れていくのがおすすめです。
Windows 11でCopilotを使い始めるための具体的な手順や画面操作については、こちらのMicrosoft公式サポートページでも図解されています。 合わせてご覧ください。 https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/windows-%E3%81%A7%E3%81%AE-copilot-%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81-1159c61f-86c3-4755-bf83-7fbff7e0982d
Windows Copilotが表示されない?原因と対処法
Windows 11を最新にしたはずなのに、Copilotのアイコンが表示されない、起動できないというケースがあります。
考えられる主な原因はいくつかあります。
ここでは、Copilotが表示されない場合の代表的な原因と、それぞれの対処法について解説します。
簡単な設定変更で解決することが多いので、諦めずに確認してみてください。
原因①:Windows 11のバージョンが古い (23H2以降が必要)
最も多い原因は、Windows 11のバージョンが古いことです。
CopilotがOSに統合されたのは、バージョン「23H2」からです(安定利用には23H2以降が推奨されます)。
まずは「設定」→「システム」→「バージョン情報」を開き、「Windowsの仕様」欄にある「バージョン」を確認してください。
ここが「22H2」以前になっている場合は、Windows Updateを実行する必要があります。
「設定」→「Windows Update」で、「更新プログラムのチェック」を行い、バージョン24H2や25H2といった、利用可能な最新バージョンへの機能更新プログラムをインストールしてください。
インストールには時間がかかる場合があり、数回の再起動が必要なこともあります。
原因②:タスクバーのCopilot表示がオフになっている
Windowsのバージョンは最新なのにアイコンが出ない場合、タスクバーの設定がオフになっている可能性があります。
Copilotのアイコンは、表示・非表示を切り替えることができます。
タスクバーの何もない部分を右クリックし、「タスクバーの設定」を選択します。
開いた設定画面の上部にある「タスクバー項目」の中に、「Copilot in Windows」(または単に「Copilot」)というスイッチがあります。
このスイッチが「オフ」になっていたら、「オン」に切り替えてください。
これでタスクバーにCopilotアイコンが表示されるはずです。
単純な設定ミスであることが多いので、まずはここを確認してみましょう。
原因③:Microsoftアカウントでサインインしていない
Windows Copilotの機能は、Microsoftアカウントと連携して動作します。
もしPCにローカルアカウントでサインインしている場合、Copilotが利用できない、または機能が制限されることがあります。
Copilotを最大限に活用するためには、MicrosoftアカウントでWindowsにサインインすることが推奨されます。
「設定」→「アカウント」→「ユーザーの情報」で、現在ローカルアカウントになっていないか確認してください。
もしローカルアカウントの場合は、「Microsoftアカウントでのサインインに切り替える」といったオプションから、お持ちのMicrosoftアカウントでサインインし直してください。
アカウントを連携させることで、Copilotの全機能や、デバイス間での履歴同期などが利用できるようになります。
Windows Copilotを有効化・無効化する方法
Windows Copilotは便利な機能ですが、人によっては「使わないから非表示にしたい」「間違って起動するのが邪魔」と感じることもあるかもしれません。
ここでは、Copilotを意図的に有効化(表示)する手順と、逆に無効化(非表示)にする手順を解説します。
自分の使い方に合わせて設定を変更してください。
設定からCopilotを有効化する手順
Copilotを有効化(タスクバーにアイコンを表示)する最も簡単な方法は、タスクバー設定の変更です。
前述の「表示されない場合の対処法」と同じ手順になります。
- タスクバーの何もない領域を右クリックします。
- 表示されたメニューから「タスクバーの設定」を選択します。
- 設定画面が開いたら、「タスクバー項目」のセクションを探します。
- 「Copilot in Windows」(または「Copilot」)の項目を見つけ、その横にあるスイッチを「オン」にします。
これでタスクバーにCopilotアイコンが表示され、クリックまたはショートカットキー(Windows + C)で起動できるようになります。
Windows Updateなどで最新版になっていれば、基本的にはこの操作で有効化が完了します。
Copilotを無効化する手順
Copilotを無効化(タスクバーから非表示に)したい場合も、有効化と逆の手順を踏むだけです。
- タスクバーの何もない領域を右クリックします。
- 「タスクバーの設定」を選択します。
- 「タスクバー項目」のセクションにある「Copilot in Windows」(または「Copilot」)のスイッチを「オフ」にします。
これでタスクバーからCopilotアイコンが消え、視界に入らなくなります。
ただし、この方法ではショートカットキー(Windows + C)を押すとCopilotが起動してしまう場合があります。
もしショートカットキーも含めて完全に無効化したい場合は、より高度な設定(グループポリシーエディターやレジストリの編集)が必要になりますが、PCの動作に影響を与える可能性があるため、初心者の方には推奨されません。
まずはタスクバーから非表示にする方法で十分でしょう。
Windows Copilotを上手に使いこなすコツ
Copilotは非常に高性能なAIですが、その能力を最大限に引き出すには、使い方(指示の出し方)に少しコツが必要です。
ここでは、Copilotからより正確で、期待通りの回答を得るための「プロンプト(指示文)」のコツをいくつか紹介します。
これらのポイントを押さえることで、Copilotはあなたの意図をより深く理解し、優れたアシスタントとして機能します。
こちらは生成AIのプロンプト研修について、選び方や料金、活用事例を解説した記事です。 合わせてご覧ください。
指示は具体的に、明確に伝える
AIは、指示が曖昧だと一般的な回答しか返せません。
Copilotを上手く使う最大のコツは、「具体的に」「明確に」指示を出すことです。
例えば、「旅行プランを考えて」と指示するだけでは、AIはどこへ、いつ、何人で行くのか分かりません。
「週末に夫婦2人で、東京から日帰りで行ける温泉地のプランを3つ提案して。予算は1人2万円以内で、電車での移動を前提にして」のように、目的、条件、制約などを具体的に伝えることが重要です。
「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識してプロンプトを作成すると、AIが文脈を理解しやすくなり、回答の精度が格段に向上します。
役割や背景、文脈を共有する
Copilotに特定の「役割」を与えることも非常に有効なテクニックです。
回答者に専門性を持たせることで、その視点に基づいた回答が期待できます。
例えば、「あなたはプロの編集者です。以下の文章を校正し、より読者の心に響く表現に修正してください」と指示します。
あるいは、「あなたは経験豊富なマーケターです。新製品のターゲット層についてアドバイスをください」といった形です。
また、指示を出す「背景」や「文脈」を共有することも重要です。
「顧客からクレームが入った。状況は以下の通り。あなたはカスタマーサポートの責任者として、謝罪メールの文案を作成して」のように、置かれた状況を説明することで、AIはより現実に即した適切な回答を生成できます。
回答例や参考情報を提供する
どのような回答が欲しいのか、具体的な「例」を示すことで、AIは出力の形式やレベル感を合わせやすくなります。
例えば、文章の要約を依頼する際に、「以下の形式で要約してください:【問題点】…【解決策】…【結論】…」とフォーマットを指定します。
あるいは、ブログ記事のタイトル案を依頼する際に、「例:『初心者必見!〇〇の使い方』のような、ターゲットが明確なタイトルを10個考えて」と例示します。
また、特定の情報に基づいて回答してほしい場合は、その情報を先に提供します。
WebページのURLを貼り付けて「このページの内容に基づいて記事を書いて」と指示したり、データを貼り付けて「このデータを分析して」と依頼したりすることで、AIは提供された情報(参照情報)を元にタスクを実行します。
回答が不十分な場合は追加で指示する
一度の指示で完璧な回答が得られるとは限りません。
Copilotの回答が期待通りでなかった場合、そこで諦めずに「追加で指示する」ことが重要です。
AIとの対話は、人間と同じようにキャッチボールを重ねることで精度が上がっていきます。
「ありがとう。でも、もっと簡潔にしてほしい」「そのアイデアは面白いけど、予算が合わない。別の案を出して」「なぜその結論に至ったのか、理由を説明して」といった形で、フィードバックを与え、修正を依頼します。
この「対話を続ける」意識を持つことで、Copilotを自分の意図通りに導き、最終的に質の高いアウトプットを得ることができます。
AIを「育てる」ような感覚で使いこなすのがコツです。
Windows Copilot利用時の注意点とリスク
Windows Copilotは非常に便利なツールですが、利用にあたってはいくつかの注意点とリスクを理解しておく必要があります。
AI技術は発展途上であり、万能ではありません。
これらの点を認識した上で活用することで、トラブルを未然に防ぎ、安全にAIの恩恵を受けることができます。
回答に誤情報が含まれる可能性を理解する
CopilotはWeb上の膨大な情報を学習していますが、その情報がすべて正確とは限りません。
また、AIが情報を組み合わせて回答を生成する過程で、事実とは異なる内容(ハルシネーション)を生み出してしまう可能性がゼロではありません。
こちらはChatGPTでハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。
特に、専門的な知識、医療、法律、金融に関する情報や、最新の時事問題などについては、Copilotの回答を鵜呑みにしないことが重要です。
Copilotは情報収集の「アシスタント」であり、最終的な判断は人間が行う必要があります。
回答には情報源(ソース)のリンクが表示されることが多いので、重要な判断に使う場合は、必ず元の情報源を確認し、ファクトチェック(事実確認)を行う習慣をつけましょう。
機密情報や個人情報は入力しない
Copilotとのチャット内容は、原則としてMicrosoftによって収集され、サービス改善やAIの学習のために利用される可能性があります(設定による)。
そのため、会社の内部情報、顧客データ、開発中の製品情報といった「機密情報」を入力するのは避けるべきです。
また、自分や他人の氏名、住所、電話番号、クレジットカード番号といった「個人情報」も絶対に入力してはいけません。
AIがこれらの情報を学習し、意図せず他者への回答に利用してしまうリスクがゼロではないからです。
特に企業で利用する場合は、会社のセキュリティポリシーを確認し、データの取り扱いルールを遵守する必要があります。
法人向けのMicrosoft 365 Copilotでは、データが学習に使われないよう保護されるプランが提供されています。
Microsoft 365 Copilotにおけるデータ、プライバシー、およびセキュリティの取り扱いに関する公式の技術文書は、こちらで公開されています。 合わせてご覧ください。
Microsoft 365 Copilot は独自の組織データをどのように使用しますか?
Microsoft 365 Copilot は、LLM を組織データに接続することで価値を提供します。 Microsoft 365 Copilot は、Microsoft Graph を通じてコンテンツとコンテキストにアクセスします。 ユーザー ドキュメント、メール、予定表、チャット、会議、連絡先など、組織データに固定された応答を生成できます。 Microsoft 365 Copilot は、ユーザーが現在参加している会議、ユーザーがトピックで行ったメール交換、ユーザーが先週行ったチャット会話など、ユーザーの作業コンテキストとこのコンテンツを組み合わせます。 Microsoft 365 Copilot は、このコンテンツとコンテキストの組み合わせを使用して、正確で関連性の高い、コンテキストに応じた応答を提供します。
重要
Microsoft Graph 経由でアクセスされるプロンプト、応答、データは、Microsoft 365 Copilot で使用されるものを含め、基礎 LLM のトレーニングには使用されません。
引用元:https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy
Office連携は有料版 (Microsoft 365) が必要
Windows 11に標準搭載されている無料版のCopilotと、WordやExcel、Teamsなどで使える有料版の「Copilot Pro」や「Microsoft 365 Copilot」は別物であると理解しておく必要があります。
無料版のCopilotに「Wordで企画書を書いて」と指示しても、PC内のWordアプリを直接操作してドキュメントを作成することはできません(アプリを起動する、一般的な企画書の書き方をアドバイスする、などは可能です)。
OfficOfficeアプリとの深い連携機能を利用するには、個人であれば「Copilot Pro」(別途M365 Personal/Familyが必要)、法人であれば「Microsoft 365 Copilot」といった有料サブスクリプションに別途加入する必要があります。eアプリとの深い連携機能を利用するには、Microsoft 365のビジネス向け(または今後提供される個人向け)のCopilotサブスクリプションに別途加入する必要があります。
「Copilotで何でもできる」と誤解せず、無料版でできることと、有料版でできることの境界線を正しく認識しておくことが大切です。
プロンプトインジェクションやデータ漏洩など、Copilotを導入する際に考慮すべき具体的なセキュリティリスクについては、こちらの専門的な分析記事で詳しく解説されています。 合わせてご覧ください。 https://www.metomic.io/resource-centre/what-are-the-security-risks-of-microsoft-co-pilot
ブラウザ版Copilot (Edge, Chrome) との違いは?
Copilotには、Windows 11のOSに統合された「Windows Copilot(Copilot in Windows)」の他に、Webブラウザ上で動作する「ブラウザ版Copilot」も存在します。
これらは似ていますが、できることや使い勝手に違いがあります。
ここでは、Windows統合版とブラウザ版の違い、そして各ブラウザでの利用方法について解説します。
Windows統合版とブラウザ版の主な違い
最大の違いは、「PCの操作ができるかどうか」です。
Windows統合版(タスクバーから起動するもの)は、OSと深く連携しているため、「ダークモードにして」「Wi-Fiをオンにして」といったPCの設定変更や、「Wordを開いて」といったアプリの起動が可能です。
一方、ブラウザ版Copilot(EdgeやChromeなどのブラウザでCopilotのWebサイトにアクセスして使うもの)は、あくまでWebサービスとして動作するため、PCのOS設定を直接変更することはできません。
主な機能は、Web検索、質問応答、文章作成、画像生成といった、Web上で完結するものが中心となります。
ただし、AIモデルの性能や、Web検索の精度、文章作成能力といった基本的なAI機能に大きな差はありません。
Microsoft Edgeでの利用方法
Microsoft Edgeブラウザには、Copilotが標準でサイドバーに統合されています。
Edgeを開き、ウィンドウの右上にあるCopilotアイコンをクリックすると、Windows統合版と同じようなサイドバーが表示されます。
EdgeのCopilotは、現在開いているWebページの内容を認識できるのが大きな特徴です。
「このページを要約して」「この記事について質問したい」といった使い方ができ、Webリサーチと相性が抜群です。
また、Edgeブラウザを使えば、Windows 10のPCでもCopilotの機能を利用することができます(OS操作はできませんが、検索や文章作成は可能です)。
Windows 11ユーザーであっても、PC操作が不要でWebリサーチがメインの場合は、Edgeのサイドバーを使う方が便利な場面もあります。
Google Chromeなど他のブラウザでの利用方法
Copilotは、Google ChromeやFirefoxなど、Microsoft Edge以外のブラウザでも利用可能です。
これらのブラウザで、Copilotの公式Webサイト(copilot.microsoft.com など)にアクセスし、Microsoftアカウントでサインインするだけです。
使い勝手はEdgeのサイドバーとは異なり、通常のWebページとして表示されます。
基本的なチャット機能、画像生成、Notebook機能などはすべて利用可能です。
普段使いのブラウザを変えることなくCopilotのAI機能を使いたい場合に便利です。
ただし、Edgeのように「開いているページを要約する」といったブラウザ連携機能は、拡張機能などを利用しない限り、標準では対応していません。
どの環境で使うのが自分にとって最も効率的か、試してみるのが良いでしょう。
Windows Copilotに関するよくある質問
最後に、Windows Copilotに関して多くの人が抱く疑問や、よくある質問について回答します。
利用開始前に知っておきたい料金体系や、特定の機能の使い方など、基本的なポイントをまとめました。
CopilotはWindows 10でも使えますか?
Windows 10のOSに統合された形(タスクバーから起動し、PC設定を変更する機能)でのCopilotは、Windows 11専用です。 ただし、Windows 10ユーザーであっても、CopilotのAI機能自体は利用可能です。
OSのアップデートにより、Windows 10でも「Microsoft Copilot」アプリが提供されており、起動して利用できます。
また、Microsoft Edgeブラウザのサイドバーや、CopilotのWebサイトからも同様に利用可能です。 Windows 11のようなPC設定変更はできませんが、AIアシスタントとしての主要な機能はWindows 10でも体験できます。
Copilotは無料で利用できますか?
はい、Windows 11に標準搭載されている「Copilot in Windows」や、ブラウザ版のCopilot(copilot.microsoft.com)は、基本的に無料で利用できます。
これには、OpenAIの最新モデル(GPT-4や、混雑時以外はGPT-5世代のモデルなど)を利用した高度なチャット応答、Web検索、画像生成(Image Creator)、画像認識(Copilot Vision)などの機能が含まれています。
ただし、無料版では1日に利用できる回数や、画像生成の速度などに一部制限が設けられている場合があります(混雑時など)。
一方で、Word、Excel、PowerPointなどのOfficeアプリと深く連携する機能や、最新AIモデルへの優先アクセス権などは、個人向けの「Copilot Pro」や法人向けの「Microsoft 365 Copilot」といった有料サブスクリプションが必要になります。 無料版でも多くの機能を使えますが、Office連携や最新モデルへの優先アクセスが必要な場合は、個人でも「Copilot Pro」などの有料版を選択することになります。
Copilot Vision(画像読み取り)はどう使いますか?
Copilot Visionは、画像の内容をAIに認識させ、それについて質問できる機能です。
使い方は簡単です。
Copilotのチャット入力欄にある「画像の追加」アイコン(クリップボードや紙のアイコンなど)をクリックし、PC内にある画像ファイルを選択します。
または、Web上の画像やスクリーンショットをクリップボードにコピー(Ctrl+C)し、チャット欄に直接貼り付け(Ctrl+V)することもできます。
画像をアップロードした後、「この画像に写っているのは何?」「このグラフを説明して」「この写真の場所はどこ?」といった質問を入力して送信します。
Copilotが画像を分析し、内容に基づいた回答を返してくれます。
Image Creator(画像生成)の使い方は?
Image Creatorは、テキストの指示(プロンプト)からAIに画像を生成させる機能です。
これもCopilotのチャット画面から直接利用できます。
「〇〇の画像を生成して」「〇〇を描いて」といった形で、生成したい画像の内容を具体的にテキストで指示します。
例えば、「雪山の上を飛ぶ、カラフルな鳥のイラストを描いて、水彩画風で」のように、被写体、背景、スタイル(画風)などを細かく指定すると、イメージに近い画像が生成されやすくなります。
Copilotが指示を解釈し、いくつかの画像候補を生成して提示してくれます。
無料版でも利用できますが、高速に生成できる回数には「ブースト」と呼ばれるクレジット制が導入されています(有料版ではこのブースト回数が多く提供されます)。
スマホでも使えますか?
はい、Copilotはスマートフォン(iOSおよびAndroid)でも利用可能です。
Apple App StoreまたはGoogle Play ストアから、「Microsoft Copilot」という名前の公式アプリを無料でダウンロードできます。
スマホアプリ版でも、PCのブラウザ版とほぼ同等の機能が利用できます。
高性能なAIモデルによるチャット、Web検索、Image Creatorによる画像生成などが可能です。
また、スマホのカメラで撮影した写真や、保存されている画像を直接Copilot Visionで分析させることもでき、外出先での利用に便利です。
Microsoftアカウントでサインインすれば、PCとスマホでチャット履歴が同期されるため、デバイスを切り替えてもシームレスに作業を続けられます。
Copilotのスマートフォンアプリ(iOS版)の機能詳細やダウンロードについては、こちらで確認できます。 合わせてご覧ください。 https://apps.apple.com/us/app/microsoft-copilot/id6738511300?mt=12
あなたの脳はサボってる?AIで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い
Copilotや生成AIを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。AIを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法も実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら解説します。
【警告】AIはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない
「AIに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、AIを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。
これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。
- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。
- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。
- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。
便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。
引用元:
MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)
【実践】AIを「脳のジム」に変える賢い使い方
では、「賢くなる人」はAIをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。
使い方①:最強の「壁打ち相手」にする
自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、AIをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。
魔法のプロンプト例:
「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。
使い方②:あえて「無知な生徒」として教える
自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。AIを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。
魔法のプロンプト例:
「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。
使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする
ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。
魔法のプロンプト例:
「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。