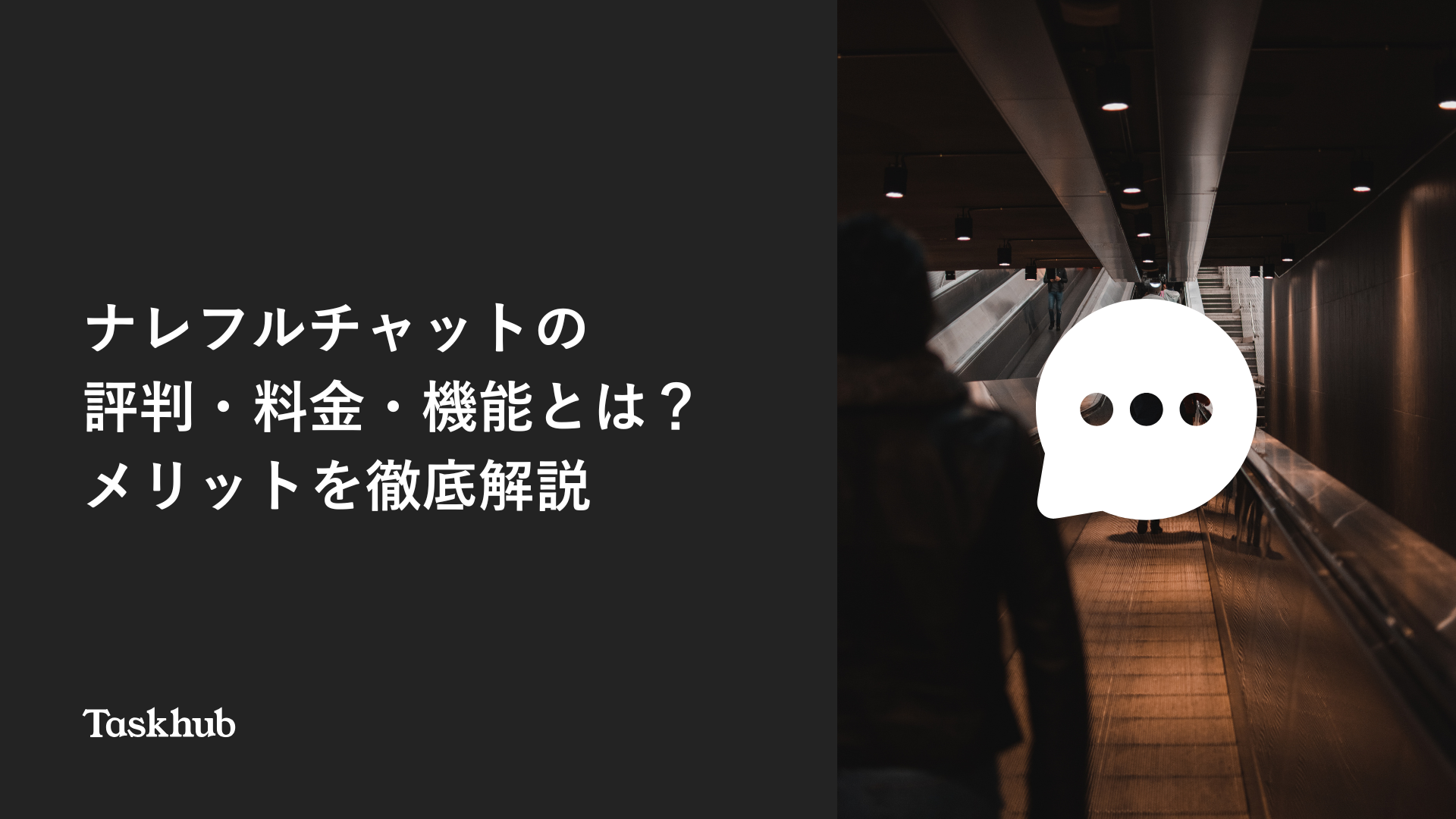「会社でChatGPTを使いたいけど、情報漏洩が怖くて許可できない」
「AIを導入してみたものの、一部の人しか使っておらず、活用が進まない」
「社員が個人でAIを使っている(シャドーIT)のを、どうにかして統制したい」
法人で生成AIの活用を検討する際、こういった悩みを抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。
法人でChatGPTを導入する際の料金やセキュリティ、他のサービスとの比較については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。
本記事では、特許取得済みの独自機能と高いセキュリティを両立させた法人向けChatGPTサービス「ナレフルチャット」について、その評判、料金、具体的な機能を徹底的に解説します。
上場企業をはじめとした多くの導入実績があり、AI初心者から上級者まで、組織全体の業務効率化を実現するヒントが詰まっています。
ぜひ最後までご覧ください。
ナレフルチャットとは?特許取得済みの法人向けChatGPTサービス
ナレフルチャットは、株式会社ナレッジフローが提供する、法人利用に特化した対話型生成AIチャットサービスです。
単にChatGPTを安全に使えるだけでなく、AI活用を組織全体に浸透させ、企業の知識(ナレッジ)として蓄積していくための独自の仕組みを持っています。
ここでは、ナレフルチャットの基本的な情報と、サービスが解決する課題について解説します。
ナレフルチャットの基本情報(表)
| 項目 | 内容 |
| サービス名 | ナレフルチャット |
| 運営会社 | 株式会社ナレッジフロー |
| 概要 | 法人向けセキュアAIチャットサービス |
| 主な機能 | マルチAIモデル対応、プロンプト自動生成、タイムライン機能、RAG(社内ナレッジ検索)、議事録作成、画像生成 |
| 料金体系 | 企業単位の月額定額制(ユーザー数無制限) |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | あり(公式サイトから申込可能) |
AI導入時の課題(セキュリティ・属人化・ナレッジ活用)を解決
多くの企業が生成AIを導入する際に直面する「3つの壁」があります。
McKinseyの2024年グローバル調査によると、65%の組織が生成AIを使用しており、実験フェーズから実導入フェーズへ移行しています。 合わせてご覧ください。 https://www.akooda.co/blog/state-of-generative-ai-adoption
1つ目は「セキュリティ」です。従業員が個人アカウントでChatGPTなどを利用(シャドーIT)すると、入力した機密情報がAIの学習に使われ、情報漏洩につながるリスクがあります。
生成AIを企業で利用する際のリスクや具体的な対策については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。
2つ目は「活用の属人化」です。AIを使いこなせる社員とそうでない社員の間にスキル格差が生まれ、便利なプロンプト(指示文)も個人の中で留まってしまい、組織全体の生産性向上につながりません。
3つ目は「社内ナレッジの活用」です。社内マニュアルや過去の資料など、蓄積された貴重な情報が点在し、必要な時にAIで活用できないという課題です。
ナレフルチャットは、これらの課題を解決するために設計されています。
サービス全体の概要と特徴
ナレフルチャットは、企業のセキュリティポリシーに対応したクローズドな環境で、ChatGPTをはじめとする最新AIモデルを利用できるプラットフォームです。
最大の特徴は、AI初心者でも簡単に高品質な回答を得られる特許技術「プロンプト自動生成・改善機能」と、優れた活用ノウハウを組織全体で共有できる「タイムライン機能」を搭載している点です。
これにより、シャドーITを防ぎながら、AIの利用を全社的に促進し、個々のスキルに依存しない安定した活用レベルを実現します。
また、社内ドキュメントを読み込ませて専用AIチャットボットを作成できるRAG機能も備え、組織の資産であるナレッジを有効活用できます。
ナレフルチャットの料金プラン
ナレフルチャットは、利用人数に関わらず企業単位で契約できる、わかりやすい料金体系を採用しています。
全社員にアカウントを付与しても追加コストが発生しないため、コストを気にせず全社的なAI活用を推進できるのが大きな魅力です。
ここでは、主要なプランとトライアルについて解説します。
企業単位のシンプルな料金体系(プロ・ビジネス・エンタープライズ)
ナレフルチャットの料金プランは、主に3つ提供されています。
プロプランは、月額40,000円(税抜)から利用可能で、利用人数は無制限です。月間1000クレジットが含まれており、最新AIモデルの利用や基本的な機能(プロンプト自動生成、タイムラインなど)をすべて利用できます。
ビジネスプランは、プロプランの全機能に加え、SSO(シングルサインオン)連携やIPアドレス制限など、中規模以上の企業に求められる高度なセキュリティ設定が可能になるプランです。
エンタープライズプランは、さらに高度なセキュリティ要件に応えるため、占有インフラ(シングルテナント)での提供や、個別のカスタマイズに対応する最上位プランです。
自社の規模やセキュリティ要件に合わせて、最適なプランを選択できます。
無料トライアル・デモの申し込み方法
ナレフルチャットでは、導入を検討している企業向けに、無料トライアルやデモを提供しています。
公式サイトの申し込みフォームから、会社名や担当者情報などを入力するだけで、簡単に申請できます。
実際の操作感や、自社の業務でどれだけ活用できそうか、導入前にしっかりと確認することが可能です。
特に、特許技術であるプロンプト自動生成機能や、RAG(社内ナレッジ検索)機能の使い勝手を試してみることをお勧めします。
オプション:生成AIリスキリング研修
ナレフルチャットは、ツールの提供だけでなく、導入後の活用支援にも力を入れています。
導入時のオンボーディング支援や、活用を促進するためのセミナーが提供されています。 また、オプションとして、全社員のAIリテラシーを向上させるための「生成AIリスキリング研修」も正式に提供されています。
社員のプロンプトスキル向上に役立つ生成AIプロンプト研修のおすすめを、こちらの記事で比較解説しています。 合わせてご覧ください。
AI活用を全社に浸透させるためには、ツールの導入と同時に社員教育も重要になるため、具体的なサポート内容については、資料請求や問い合わせの際に確認するとよいでしょう。
ナレフルチャットの主な機能と特徴
ナレフルチャットには、単にAIとチャットできるだけでなく、企業のAI活用を根本から支える独自の機能が多数搭載されています。
特許技術を含むユニークな機能から、業務効率化に直結する便利な機能まで、その特徴を紹介します。
特許技術①:初心者でも簡単な「プロンプト自動生成・改善」
ナレフルチャットの核となる機能の一つが、特許を取得した「プロンプト自動生成・改善機能」です。
AIから精度の高い回答を引き出すには、優れたプロンプト(指示文)が不可欠ですが、初心者がこれを使いこなすのは困難です。
この機能を使えば、利用者の意図をAIが理解し、最適なプロンプトを自動で生成・改善してくれます。
これにより、AIの利用スキルに差がある社員でも、誰でも簡単に高品質な回答を得ることができ、活用のハードルを大幅に下げます。
特許技術②:組織のノウハウを蓄積「タイムライン機能」
もう一つの特許技術が「タイムライン機能」です。
これは、チームメンバーが作成し、高い評価を得た優れたプロンプトやAIの回答を、組織全体で共有・評価できる仕組みです。
便利な使い方が個人のチャット履歴に埋もれることなく、タイムライン上に「ナレッジ」として蓄積されていきます。
他の社員はそのプロンプトを再利用したり、参考にしたりすることで、組織全体のAI活用レベルが底上げされます。
社内情報をAIが回答「社内ナレッジ検索(RAG機能)」
ナレフルチャットは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)機能を搭載しています。
こちらは、RAGが社内情報のようなドメイン固有の知識検索において、LLMの「ハルシネーション(幻覚)」を軽減し、「事実の正確性」を向上させる効果を実証した学術論文です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/html/2403.10446v1
これにより、社内規定、業務マニュアル、過去の議事録など、企業固有のドキュメント(PDF, Wordファイルなど)をアップロードするだけで、それらの情報を基に回答する「自社専用チャットボット」を簡単に作成できます。
SharePointなどのクラウドストレージと連携することも可能です。
「経費精算の方法は?」「A社との前回の取引内容は?」といった社内からの問い合わせ対応をAIに任せることができ、業務の大幅な効率化につながります。
GPT-4oやClaude 3など最新AIモデルを使い分け可能
ナレフルチャットでは、OpenAI社の最新モデル「GPT-5」や「GPT-4o」、Anthropic社の「Claude 3」ファミリー、Google社の「Gemini」など、複数の高性能AIモデルを一つのプラットフォームで利用できます。
近年のAIトレンドとして、「ワンサイズ・フィット・オール(万能型)AIの時代は終わった」と指摘されており、戦略的なモデル選択がビジネス成果に直結します。 合わせてご覧ください。 https://itecsonline.com/post/claude-4-vs-gpt-4-vs-gemini-pricing-features-performance
2025年8月にリリースされたGPT-5は、質問の難易度に応じて思考時間を自動で切り替える能力を持ち、コーディングやデータ分析などで高い精度を発揮します。
業務内容や目的に応じて、文章作成が得意なモデル、分析が得意なモデル、といったように最適なAIを使い分けることが可能です。
こちらは、スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)発行の「AI Index Report 2025」で、GPT-4oやClaude 3.5 Sonnetなど最新モデルの性能が客観的に比較されています。 合わせてご覧ください。 https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai-index-report-2025_chapter2_final.pdf
テキストから画像を生成「画像生成機能」
文章作成だけでなく、画像生成AIも標準で利用可能です。
「青空を飛ぶ猫のイラスト」や「近未来的なオフィスのデザイン案」など、テキストで指示するだけで、プレゼン資料やWebサイト、広告バナーなどに使える画像を簡単に作成できます。
これにより、デザイン業務の効率化や、アイデア出しの幅を広げることができます。
専門的なデザインスキルがない社員でも、ビジュアルコンテンツを手軽に用意できるのは大きな強みです。
会議の「議事録自動作成機能」
会議の音声データや動画ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で文字起こしを行い、議事録を作成する機能も搭載されています。
単なる文字起こしに留まらず、発言者の特定や、決定事項・TODOリストの要約まで行ってくれるため、議事録作成にかかる工数を劇的に削減できます。
会議が多い部署や、議事録作成に時間を取られている企業にとって、非常に価値のある機能です。
いつでもどこでも使える「スマートフォンアプリ」
ナレフルチャットは、PCのブラウザだけでなく、スマートフォンからの利用にも最適化されています。
専用のスマートフォンアプリ(iOS版)も提供されており、RAG機能で作成した社内ナレッジボットは専用のURL(RAGリンク)を通じてスマートフォンから簡単にアクセスできます。
これにより、外出先の営業担当者が移動中に社内情報を確認したり、現場のスタッフがその場でマニュアルを参照したりするなど、時間や場所を選ばない柔軟な働き方をサポートします。
導入・管理をサポートする「管理者向け機能」
企業全体での利用を前提としているため、管理者向けの機能も充実しています。
SSO(シングルサインオン)によるセキュアなログイン管理や、特定のIPアドレスからのみアクセスを許可する「IPアクセス制限」など、企業のセキュリティポリシーに合わせた運用が可能です。
また、ユーザーごとの権限管理や、利用状況を把握するためのアクセスログのダウンロード機能も備わっており、安全かつ統制の取れたAI活用を実現します。
実際の操作画面とサービス紹介動画
ナレフルチャットの公式サイトや導入事例ページでは、実際の操作画面のスクリーンショットや、サービスの概要を紹介する動画が公開されています。
プロンプト自動生成機能がどのように動作するのか、タイムライン機能でどのようにナレッジが共有されるのかなど、具体的な利用イメージを掴むことができます。
無料トライアルを申し込む前に、これらの情報を確認し、自社の使い方と合っているかをイメージしてみるのが良いでしょう。
ナレフルチャットのセキュリティ対策は万全か?
法人利用において、最も重要視されるのがセキュリティです。ナレフルチャットは、情報漏洩リスクを徹底的に排除するための強固なセキュリティ体制を構築しています。
企業の機密情報を守りながら、安全にAIのメリットを享受するための仕組みを見ていきましょう。
クローズドな環境でAI利用時の情報漏洩を防止
ナレフルチャットは、企業ごとに独立したクローズド(閉じた)な利用環境を提供します。
従業員が入力したデータやチャット履歴が、OpenAI社などのAIモデルの学習に利用されることは一切ありません。
これにより、機密情報や顧客情報を扱う業務でも、情報漏洩のリスクを心配することなく、安心して生成AIを活用できます。
個人アカウントの利用(シャドーIT)を禁止し、ナレフルチャットに一本化することで、企業としてAI利用のガバナンスを確立できます。
ISMS(ISO27001)認証取得の高いセキュリティ水準
ナレフルチャットを運営する株式会社ナレッジフローは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISMS(ISO27001)」および、国内の個人情報保護体制の認証である「プライバシーマーク」を取得しています。
これは、情報の機密性、完全性、可用性を維持・改善するための厳格な体制が整備されていることの証です。
さらに、第三者機関(GMOサイバーセキュリティ byイエラエ)によるWebアプリケーション脆弱性診断で最高評価の「A評価」を獲得しており、技術的な安全性も高く評価されています。
ナレフルチャットの評判・口コミと導入事例
ナレフルチャットは、IT商社から広告代理店、建設業、介護福祉分野まで、業種を問わず多くの企業に導入されています。
実際に導入した企業からは、コストパフォーマンスの高さや、AI活用の浸透において高い評価を得ています。
ここでは、具体的な評判や導入事例を紹介します。
導入企業から寄せられた実際の声(口コミ)
ナレフルチャットの導入企業からは、「利用者数制限なしのクレジット制課金がすばらしい」といった声が寄せられています。
一般的なAIサービスがユーザーIDごとに課金されるのに対し、ナレフルチャットは企業単位の定額制です。
これにより、「一部の人しか使わないかもしれない」という導入時の懸念を払拭し、スモールスタートで全社員にAI活用の機会を提供できる点が評価されています。
コストを気にせず全社展開できる料金体系が、導入の決め手の一つとなっているようです。
【事例】業務効率化の成果(株式会社トーコン、株式会社ハイパーなど)
具体的な導入事例として、IT商社の株式会社ハイパーでは、導入後わずか5ヶ月で社員の約8割がAIを活用するまでに普及しました。
結果として、従来は2週間かかっていた作業が2時間で完了するなど、劇的な業務効率化を実現しています。
また、広告・マーケティング支援を行う株式会社トーコンでは、顧客情報の収集や広告分析といった業務にナレフルチャットを活用。
業務効率化はもちろんのこと、プロンプト共有機能を通じて社内全体のAIリテラシー向上にも寄与していると報告されています。
【事例】部門別の具体的な活用方法
導入企業の活用方法は部門によって多岐にわたります。
営業部門では、顧客への提案資料のたたき台作成、メール文面の作成、競合他社の情報収集などに活用されています。
人事・採用部門では、求人票の作成、応募者へのスカウトメール文面の作成、社内規定に関する問い合わせ対応(RAG機能)などで活用が進んでいます。
マーケティング部門では、広告コピーのアイデア出し、ブログ記事の構成案作成、SNS投稿文の作成、データ分析のサポートなど、クリエイティブな業務から分析業務まで幅広く利用されています。
ナレフルチャットを導入するメリット
これまでの機能や事例を踏まえ、企業がナレフルチャットを導入する具体的なメリットを5つのポイントに整理します。
セキュリティの担保からコストパフォーマンスまで、企業が抱える課題を解決する強力な利点があります。
1. 高いセキュリティでAIを安全に利用できる
最大のメリットは、ISMS認証取得の信頼できるセキュリティ環境下でAIを利用できる点です。
入力データがAIの学習に利用されることがないため、情報漏洩のリスクを回避できます。
SSOやIP制限にも対応しており、企業の厳格なセキュリティポリシーにも準拠できます。
シャドーIT問題を解決し、全社で統一された安全なAI利用環境を構築できることは、コンプライアンスの観点からも非常に重要です。
2. AI初心者でも簡単に高品質な回答を引き出せる
特許技術である「プロンプト自動生成・改善機能」により、AI活用が特定のスキルを持つ社員に依存する「属人化」を防ぎます。
AIを使ったことがない社員や、プロンプト作成が苦手な社員でも、簡単な指示を出すだけでAIが意図を汲み取り、最適なプロンプトを提示してくれます。
これにより、全社員がAIの恩恵を平等に受けることができ、組織全体の生産性向上に直結します。
3. 優れたナレッジを組織全体で共有・活用できる
もう一つの特許技術「タイムライン機能」は、AIの活用ノウハウを「個人のスキル」から「組織の資産」へと変える強力な仕組みです。
優れたプロンプトや活用事例がタイムラインで共有され、評価されることで、社員同士が学び合い、AIの活用レベルが自然と向上していきます。
さらに、RAG機能によって社内ドキュメントをAIに読み込ませることで、埋もれていた過去の知識やノウハウを誰もが簡単に引き出せるようになります。
4. 複数の最新AIモデルを最適な業務で使い分けられる
GPT-5、GPT-4o、Claude 3、Geminiなど、世界最高水準のAIモデルを自由に切り替えて使用できる点も大きなメリットです。
例えば、複雑な論理的思考やコーディングにはGPT-5を、自然で人間らしい文章作成にはClaude 3を、といったように、業務の目的に合わせて最適なAIを選択できます。
常に最新のAI技術を利用できるため、ビジネスの競争力を維持・強化することにもつながります。
5. シンプルな料金体系でコストパフォーマンスが高い
料金体系が「企業単位の月額定額制(ユーザー数無制限)」である点は、特に全社導入を目指す企業にとって強力なメリットです。
一般的なID課金制の場合、全社員に配布すると膨大なコストがかかりますが、ナレフルチャットならコストを固定化したまま、利用人数を気にせず展開できます。
「まずは全社員に触れてもらう」というAI活用の第一歩を、非常に高いコストパフォーマンスで実現できます。
ナレフルチャットと他社サービスとの違い
法人向けAIチャットサービスは多数存在しますが、ナレフルチャットは他社と明確な差別化が図られています。
その独自性は、特許技術に裏打ちされた「AI活用の浸透」への強いこだわりにあります。
特許技術(プロンプト自動生成・タイムライン)による独自性
多くの競合サービスが「安全なAI利用環境(セキュリティ)」の提供を主な価値とする中で、ナレフルチャットは「いかにAIを全社に普及させ、使いこなしてもらうか」という点にフォーカスしています。
AI初心者でも使いこなせる「プロンプト自動生成・改善機能」と、ノウハウを組織で蓄積する「タイムライン機能」。
これら2つの特許技術が、他社にはない強力な独自性となっています。
単にAIを使える箱を用意するだけでなく、組織のAIリテラシーそのものを引き上げる仕組みが組み込まれているのが最大の違いです。
手厚い導入・運用サポート体制
ナレフルチャットは、ツールの提供に留まらず、導入後の活用定着までをサポートする体制を整えていると考えられます。
導入事例からも、単にツールを導入して終わりではなく、担当者と伴走しながら社内浸透を進めている様子がうかがえます。
法人向けサービスにおいて、導入後のサポートや活用のための教育(リスキリング)は非常に重要です。
具体的なサポート内容については、導入前の相談段階で確認することをお勧めしますが、組織のAI活用を本気で推進したい企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。
ナレフルチャットはどんな企業におすすめ?
ナレフルチャットは、特定の課題や目的を持つ企業にとって、非常に効果的なソリューションとなります。
自社が以下のいずれかに当てはまる場合、導入を具体的に検討する価値があります。
AI導入のセキュリティに不安がある企業
「AIを使いたいが、情報漏洩が怖い」「シャドーITが蔓延していて統制が取れない」といった、セキュリティに最優先で課題を感じている企業に最適です。
ISMS認証取得のセキュアなクローズド環境で、入力データの二次利用を完全に防ぎます。
まずは安全なAI利用の基盤を確立したい、というニーズに完璧に応えます。
AI活用を全社に浸透させたい企業
「一部のITリテラシーの高い社員しかAIを使っていない」「全社的にAI活用レベルを底上げしたい」と考える企業に強くおすすめします。
プロンプト自動生成機能がAI利用のハードルを下げ、タイムライン機能がノウハウ共有を促進します。
さらに、ユーザー数無制限の料金体系が、コストの壁を取り払い、全社員へのアカウント配布を後押しします。
社内の情報共有やナレッジ活用を活性化したい企業
「社内マニュアルが整備されておらず、問い合わせ対応に工数がかかっている」「過去の貴重な資料が活用されていない」といったナレッジマネジメントに課題を持つ企業にも有効です。
RAG機能を活用して、社内情報を学習させた「自社専用AIボット」を構築できます。
これにより、社員が必要な情報にいつでも即座にアクセスできるようになり、組織全体の知識レベルと業務効率が向上します。
ナレフルチャットの導入ステップ
ナレフルチャットの導入は、一般的なSaaSと同様、シンプルで迅速なプロセスで進められます。
お問い合わせから実際の運用開始まで、基本的な流れを解説します。
ステップ1:お問い合わせ・資料請求
まずは公式サイトの専用フォームから、お問い合わせやサービスに関する詳細な資料を請求します。
この段階で、自社の課題や導入の目的、利用予定人数(規模感)などを伝えておくと、その後のやり取りがスムーズです。
料金プランの詳細や、セキュリティに関するより詳しい資料も入手できます。
ステップ2:無料トライアルまたはデモの実施
資料で基本情報を確認した後、無料トライアルやオンラインでのデモを申し込みます。
無料トライアルでは、実際の操作環境を一定期間試用し、プロンプト自動生成機能やRAG機能などの使い勝手を自社の業務で試すことができます。
デモでは、担当者から直接、機能説明や他社事例の紹介を受けながら、具体的な活用イメージをすり合わせます。
ステップ3:ご契約・導入支援
トライアルやデモを経て、機能、料金、サポート体制に納得できたら、正式に契約を結びます。
契約プラン(プロ、ビジネス、エンタープライズ)を決定し、利用開始に向けた準備を進めます。
この際、SSO連携やIP制限などのセキュリティ設定、初期のユーザー登録など、導入支援チームのサポートを受けながら環境を構築していきます。
ステップ4:運用開始とアフターサポート
環境構築が完了したら、いよいよ全社への展開と運用開始です。
導入初期は、社内説明会の開催や、活用マニュアルの配布などを行い、社員への周知と利用促進を図ります。
運用開始後も、ナレフルチャットのサポートデスクが、活用方法に関する質問や技術的な問題に対応してくれます。
定期的な活用状況のレビューや、新機能の紹介など、継続的なアフターサポートが期待できます。
ナレフルチャットに関するよくある質問(FAQ)
最後に、ナレフルチャットの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
疑問点を解消し、導入の判断材料としてください。
Q. 無料トライアルはありますか?
はい、あります。
ナレフルチャットの公式サイトから、無料トライアルやデモを申し込むことができます。
導入前に実際の機能や操作感を試し、自社の業務に適合するかを評価することが可能です。
Q. 利用人数に制限はありますか?
いいえ、利用人数に制限はありません。
ナレフルチャットの料金プランは、企業単位の月額定額制を基本としています。
そのため、契約したプランのクレジット上限内であれば、全社員が追加料金なしで利用できます。
Q. どのようなAIモデルが使えますか?
OpenAI社のGPT-5やGPT-4o、Anthropic社のClaude 3、Google社のGemini、Grok、Perplexityなど、複数の最新かつ高性能なAIモデルに対応しています。
業務の目的に応じて、最適なモデルを使い分けることができます。
Q. セキュリティ面は大丈夫ですか?
はい、万全の対策が施されています。
入力データがAIの学習に利用されることは一切ないクローズドな環境です。
運営会社はISMS(ISO27001)認証を取得しており、SSO連携やIPアクセス制限など、企業のセキュリティ要件に応じた設定も可能です。
Q. 導入にはどのくらい時間がかかりますか?
契約プランや企業のセキュリティ設定(SSO連携の有無など)によって異なりますが、標準的なプランであれば、契約後、最短で即日〜数営業日で利用を開始できる可能性があります。
詳細なスケジュールについては、お問い合わせ時に確認してください。
ナレフルチャットの運営会社概要
ナレフルチャットは、システム開発とAIサービスを手がける日本の企業によって運営されています。
運営会社情報(CLINKS株式会社)
| 会社名 | CLINKS株式会社 (CLINKS Co., Ltd.) |
| 設立日 | 2002年12月19日 |
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F |
| 事業内容 | システムソリューションサービス事業、法人向けAIサービスの開発・提供など |
| 認証 | ISMS (ISO/IEC 27001)、プライバシーマークなど |
| 公式サイト | https://www.clinks.jp/ |
資料ダウンロードはこちら
ナレフルチャットのより詳細な機能、料金プラン、導入事例についてまとめた資料は、公式サイトからダウンロードできます。https://www.knowleful.ai/
AIの安全な導入と全社的な活用推進に課題を感じている方は、ぜひ一度資料をご覧になってはいかがでしょうか。
AI導入で「成果が出る企業」と「宝の持ち腐れになる企業」の決定的な違い
多くの企業が「生成AIを導入すれば業務が効率化する」と期待を寄せています。しかし、その使い方やツールの選び方を間違えると、AIは「宝の持ち腐れ」になってしまうかもしれません。総務省の調査でも、AI導入の課題として「AIを使いこなせる人材の不足」や「コスト」が挙げられており、全社的な活用がいかに難しいかを物語っています。この記事では、「成果が出る企業」と「失敗する企業」の分かれ道を、具体的なポイントと共に解説します。
【警告】そのAI導入、「2つの壁」で失敗していませんか?
「セキュリティが怖くて、結局AIの利用を禁止してしまった」
「一部の詳しい社員しか使っておらず、全社的な効果が見えない」
これらは、AI導入でよくある失敗パターンです。多くの企業が直面する「2つの壁」が存在します。
- セキュリティの壁: 従業員が個人アカウントでAIを利用(シャドーIT)し、機密情報が漏洩するリスクです。これを恐れるあまり、利用を一律禁止にしてしまい、効率化の機会を失います。
- スキル格差の壁: AIは「プロンプト(指示文)」の質で成果が大きく変わります。AIを使いこなせる社員とそうでない社員の間にスキル格差が生まれ、活用が「属人化」してしまいます。結果、組織全体の生産性向上にはつながりません。
便利なツールを導入したはずが、これらの壁に阻まれ、コストだけがかかり、誰も使わない状態に陥るのです。
引用元:
総務省「令和5年版 情報通信白書」では、日本企業のAI導入における課題として、「AIを使いこなせる人材が不足している」(45.1%)、「導入・運用コストが高い」(44.8%)といった点が上位に挙げられています。
(出典:総務省「令和5年版 情報通信白書」第2部 第5節)
【実践】AIを「全社の武器」に変える企業の共通点
では、「成果が出る企業」は何が違うのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「一部の人の特殊スキル」ではなく、「全社員が安全に使えるインフラ」として整備しています。
そのための鍵は、セキュリティと使いやすさを両立させた「法人向けプラットフォーム」を選択することです。
ポイント①:セキュリティの担保
まず大前提として、入力した情報がAIの学習に使われない、クローズドな環境を選ぶことが不可欠です。SSO(シングルサインオン)やIPアドレス制限などで、企業のセキュリティポリシーに対応できるかも重要な選定基準です。
ポイント②:「属人化」を防ぐ仕組み
AIスキルに自信がない人でも、簡単に高品質な回答を得られる仕組みが重要です。例えば、優れたプロンプトを自動で生成してくれたり、他の人が使った良いプロンプトを社内で共有(ナレッジ化)できたりする機能です。
ポイント③:社内ナレッジの活用
AIが社外の一般情報しか回答できないようでは、業務利用に限界があります。社内マニュアルや過去の議事録といった「社内ナレッジ」をAIに読み込ませ、自社専用の回答ができるようにすることで、AIの価値は飛躍的に高まります。
まとめ
企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。
しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」「セキュリティが不安」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。
Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。
たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。
しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。
さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。
導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。
まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。
Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。